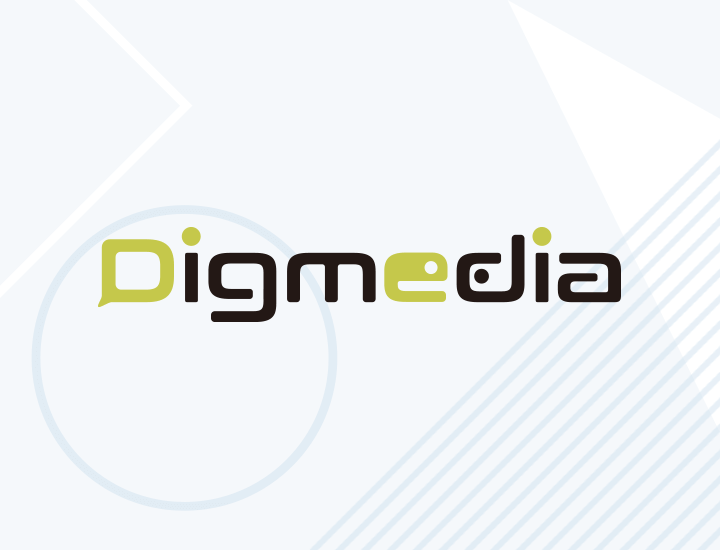就活の準備で大切とされている「就活の軸」。
一体どうやって見つければ良いのか、わからないですよね。
この記事では自分なりの軸の見つけ方をご紹介。
効率的にアピールする方法もお伝えします。
就活の軸とは
就活を進めていく中で「就活の軸」はよく耳にする言葉です。
面接で「就活の軸は何ですか?」と聞かれるケースも、多くありますよね。
「就活の軸」は志望動機とも密接に関係しているため、とても重要です。
一貫性のない志望動機では説得力がなく、信用できません。
自分の中で軸が定まっていないのは、ゴールがないまま走り続けるようなものです。
活動の中で悩むことがあっても、ゴールがなければどの道を選べば良いのかわかりません。
時間をロスしてしまったり、間違った道を選んで後悔したりする可能性があります。
この記事では、就活の軸の意味から、軸の見つけ方まで徹底的に解説します。
効果的なアピール方法もご紹介しますので、最後まで読んでみてくださいね。
明確になった自分なりの軸をもとに、就活をスムーズに進めていきましょう。
就活の軸の意味とは?
そもそも「就活の軸」の意味を正しく理解していますか? 就活の軸とは、就活をするうえで「絶対に譲ることができないこと」を指します。
就職して何がしたいのかを一言で表したものです。
たとえば、
などが就活の軸になります。
ただし、どの企業にも当てはまるような軸では不十分です。
「商品開発に携わりたい」という軸があったら、
というように、軸を深掘りしていきましょう。
①自分の軸に基づき、②応募先企業じゃないといけない理由を、「○○という点で御社が良い」と、言語化できるようにしておきましょう。
就活の軸を決めるメリットは?
就活の軸を決めることが大切だとお伝えしてきました。
次に、就活の軸を決めるメリットを見ていきましょう。
メリットとして挙げられるのは、次の3つです。
効率の良い就活ができる
就活の軸を決めておくことで、志望する企業を絞り込むことができます。
どの企業に応募するべきかをいちいち悩む必要がないので、効率的に就活を進めることが可能です。
入社後のミスマッチが防げる
就活の軸を理解するためには、本当にやりたいことや自分の強みを知るための自己分析が必要です。
軸が定まったということはやりたいことも明確になっているため、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
面接で一貫性をもって回答できる
就活の軸は、どのような内容でもブレることがないものです。
志望動機をはじめ、面接等での質問に対しても、一貫性をもって答えることができます。
企業が面接で就活の軸を質問する理由は?
就活の軸を見つけることは、就活生のみなさんにとってもメリットが多くあることを紹介しました。
一方で、面接やエントリーシートで「就活の軸」を質問する企業にも、理由があります。
企業が面接で就活の軸を質問する理由としては、以下の2つが大きいです。
志望動機が希薄な学生をふるい落とす
企業は、毎日多くの就活生を相手にしています。
その中でどの人材を選ぶべきかの判断基準として、就活の軸を聞いているのです。
自分なりの仕事選びの基準=就活の軸が、明確になっているかを確認して、志望動機が希薄な学生をふるい落としています。
入社後すぐの離職を避ける
企業の一番の心配事は、入社後すぐに退職してしまうことです。
費用をかけて採用したのに、仕事を覚える間もなく辞められてしまっては困りますよね。
そこで、就活の軸を聞き、企業の求める人材と就活生の軸がズレていないかを確認しています。
ミスマッチを防ぎ、早期離職を避けるためです。
自分なりの就活の軸を決める方法は?
ここまで、就活の軸を決める重要性と、企業が軸を質問する理由をお伝えしてきました。
次に、自分なりの就活の軸を決める方法をお伝えします。
就活の軸を決めるための流れは、次の4ステップです。
1つひとつは難しくないので、着実に進めていきましょう。
やりたい仕事や気になる仕事をリストアップする
はじめに、やりたい仕事や気になる仕事を書き出します。
最初は「向いているか、向いていないか」を考える必要はありません。
純粋に「自分がやりたい」と考えている仕事をリストアップしていきましょう。
やりたい仕事は長く続けられることが多いです。
熱意をもって仕事に向かえるよう、自分の興味に忠実になりましょう。
やりたくない仕事をリストアップする
やりたい仕事を書き出したら、今度は反対に「やりたくない仕事」を書き出していきましょう。
やりたくない仕事をリストアップすることで、自分の応募するべき企業が明確になってきます。
やりたい仕事が見つからない場合にも、「やりたくない仕事」のリストアップは有効です。
「やりたくない仕事」以外の仕事は、好きでも嫌いでもない仕事ということ。
実際にやってみたら、合っているかもしれません。
仕事に対して求める条件を設定する
自分の目指す業界や職種が絞れてきたら、次に仕事に求める条件を考えていきます。
仕事に求める条件は人それぞれ違うので、自分が重要だと思う条件を書き出していきましょう。
書き出した条件に合う仕事はどのようなものがあるのか、どの企業であれば実現できるのかを考えます。
もし条件に合う企業が見つからない場合には、条件に優先順位をつけるのも有効です。
優先度の低い条件を外していき、一番多くの条件を満たしている企業へ応募してみましょう。
自分の能力を知り、どんな仕事なら活かせるかを考える
仕事を長く続けるためには、自分の能力を理解することが大切です。
自分の持っているスキルや人柄が、やりたい仕事に合っているとは限りません。
向いていない仕事に応募しても、なかなか採用されませんし、入社後も合わずに退職になる可能性があるのです。
企業や業界によって、求められている人材は異なります。
A社では求められていなくても、B社では喉から手が出るほど欲しい人材かもしれません。
自分の能力を理解し、どの業界・どの職種なら力が発揮できるのか考えてみましょう。
就活の軸の効果的なアピール方法は?
自分の就活の軸が見えてきたら、応募書類や面接を通して企業にアピールしていきます。
この章では、効果的にアピールする方法をご紹介しましょう。
・仕事を通じてやりたいことを能動的にアピールする 企業の面接等で就活の軸を聞かれたときに、「御社の商品やサービスが好き」と消費者目線の回答をする就活生がいます。
しかし消費者目線の回答は避けましょう。
“会社ありき”の受動的な印象を与えてしまい、評価としてはマイナスです。
社会人は自分から積極的に仕事をすることが求められます。
そこで「仕事を通してやりたいこと」を軸に、アピールをすることがポイントです。
以上のポイントのように、仕事を通して実現したいことを伝えましょう。
能動的に仕事に向かっている印象を与えることができ、好印象になります。
誰でも、どんな企業でも当てはまる答えは避ける
就活の軸をアピールする際、誰でも言えることや、どのような企業でも当てはまる答えは避けましょう。
よくあるダメな回答は「社会貢献ができる」や「成長できる」です。
この回答は、誰でもどの企業でも使えてしまいますよね。
どこでも使える回答は、自分の軸を掘り下げていない印象や、志望度が低い印象を与えます。
それでは内定の獲得は難しくなりますので、応募先に合ったアピール内容を考えましょう。
軸を答えるだけでなく理由もアピールする
「就活の軸は何ですか?」という質問に対して、「○○です」と軸だけを答えるのはもったいないです。
軸を答えるだけでなく「どうしてその軸なのか」も伝えるようにしましょう。
企業はこの質問を通して、就活生の価値観も知りたいと思っています。
「その軸を選んだ理由」をプラスアルファで伝えるようにしましょう。
その際、実際に経験したことをもとにして伝えると、よりリアリティーがあり、説得力のあるアピールになります。
軸を決める際に掘り下げておくと良いですね。
軸と志望動機をシンクロさせてアピールする
最後に、志望動機と就活の軸はシンクロさせてアピールすることが有効です。
例えば、海外進出していない企業の面接で、「世界中の人を笑顔にしたい」という軸を伝えたらどうでしょうか?採用担当者は「なぜわが社に応募したのだろう?」と疑問を持ち、志望度が低いと判断するでしょう。
このように、応募する企業に合わない軸や志望動機は逆効果になります。
志望企業の特徴に合うように、軸と志望動機をシンクロさせましょう。
就活の軸は変えてもいいの?
就活生の多くが悩むのが、「一度決めた就活の軸を変更しても良いのか」です。
インターンや会社説明会など就職活動を進めていくと、決めた就活の軸がブレることがあります。
このような場合には、軸を考え直してみましょう。
再度考え直すことで、自分なりの就活の軸の精度が高まり、やりがいを感じる企業や仕事をより見つけやすくなるからです。
一度決めた就活の軸は、どんどん変えていきましょう。
ただし、頻繁に変えると、応募する企業に悩むことになります。
考え直す時は、きちんと掘り下げ、その時にできる最大の検討をしましょう。
就活の軸を明確にして選考に臨もう
就活の軸が明確になると、活動自体に一貫性が出ます。
応募先を選ぶときの基準がはっきりしているので、悩む必要がありません。
軸がしっかりしていると、志望動機にも説得力が出るため、就活に成功しやすくなります。
自分なりの就活の軸を決めるためには、情報収集が大切。
どのような職種や企業があるのかを知らなければ、選択肢に入れることができないからです。
まずはLINEで簡単に情報収集できる「digmedia」がオススメ! 就活の軸についての情報以外にも、就活を進めていくうえで役に立つ情報を配信しています。
ぜひ、チェックしてみてください。
おすすめの記事 自己分析の目的って?目的を理解することで就活を前に進める 【就活】自己分析のやり方5選!自分に合った企業に内定する方法