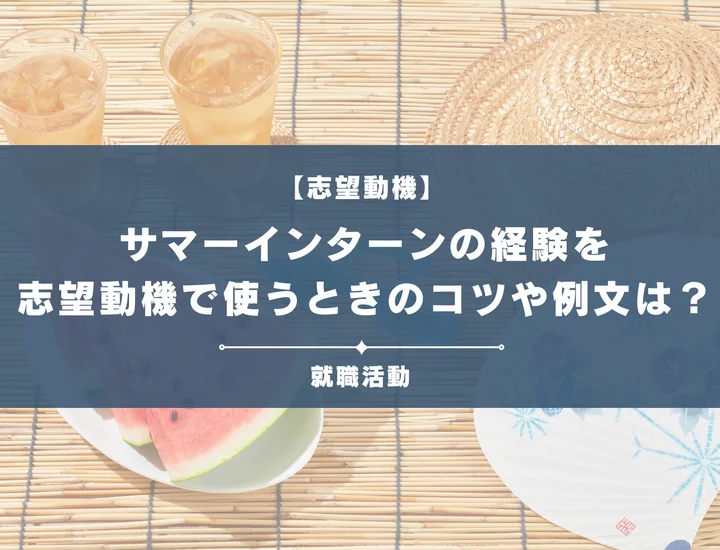HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
「なぜ同業他社ではなく、うちなの?」と聞かれて明確な答えが出せない学生は多くいるのではないでしょうか?
この質問は面接において頻出のテーマでもあります。
この質問に良い答えが返せるかどうかで選考結果の合否に関わる場面もあるでしょう。
本記事では「なぜ同業他社ではなくウチなの?」という質問に答える方法について紹介します。
目次[目次を全て表示する]
【他社との違い】「なんでうちなの?」と質問してくる意図
企業が「なぜ同業他社ではなくウチなの?」という質問をするには主に3つの意図があります。
面接官や人事からの質問には全て意図があるため、この意図の部分を理解しておけば、的外れな回答をすることもなくなり、説得力と一貫性のある回答ができるようになります。
志望する動機を確かめるため
入社後に自社でやりたいことや、何に惹かれて自社を志望するのかを確認するために質問されています。
業界の中でも企業の得意とする部分や魅力はさまざまであるため、その中でも「自社」にはどんなところに惹かれて他社ではなくうちを志望したのか聞かれています。
そのため、他社も行っているサービスや特徴をこの回答として取り上げると、「それうちじゃなくても良くない?」という印象を与えてしまうため注意しましょう。
志望度を測るため
「なぜうちなの?」と聞かれるのは、シンプルに志望度を測るためという意図もあります。
企業は自社で活躍してくれる人材を求めていますが、入社意欲を感じられない学生は採用を避けます。
そういった学生は採用しても辞退したり、入社しても早期で離職してしまう可能性があるからです。
志望度の高い就活生ほど、企業分析をして、選考対策として模擬面接を積み、うまく答えられるよう準備しているでしょう。
ガクチカや自己PRよりはメジャーではない質問ではないため、この質問に説得力を持った回答ができれば「志望度が高いから企業分析を深くしてくれて、選考対策にも時間をかけてくれたのかな」という印象を与えることができます。
業界・企業分析ができているか確かめるため
企業が「なぜ弊社なのか?」と質問する理由の一つは、応募者が業界や企業についてどれほど深く理解しているかを確認するためです。
もし業界や企業に関する分析が不十分であれば、準備不足で信頼を欠く人物として見なされる可能性があります。
また、具体性のない回答は、応募者の意欲や方向性が曖昧だと判断されかねません。
したがって、事前の徹底した情報収集と、それを基にした志望理由の構築が重要となります。
【他社との違い】他社との比較がよく聞かれる業界
「なんでうちなの?」という質問は、業界や企業の特性によって意図が異なります。
以下では、IT・テクノロジー業界、コンサルティング業界、広告・マーケティング業界、金融業界における背景や理由を具体的に解説します。
IT・テクノロジー業界
技術の進化が著しいIT・テクノロジー業界では、応募者が各企業の独自性をどれだけ把握しているかが重要です。
例えば、AIに特化する企業とクラウド技術に強みを持つ企業では、求められるスキルや方向性が異なります。
応募者がこうした背景を理解し、志望企業の強みを具体的に述べることで、情報収集力や業界への関心度をアピールできます。
さらに、単に企業の強みを理解するだけでなく、最新の技術革新がどのように事業に活かされているかを調べ、志望動機に反映することが求められます。
コンサルティング業界
コンサルティング業界では、企業ごとのサービス内容や専門分野が大きく異なります。
そのため、応募者が他社との違いを具体的に理解しているかを確認する質問がよく行われます。
たとえば、戦略コンサルティングを強みとする企業と、デジタル分野での支援を得意とする企業では、提供する価値が異なります。
また、この業界では、応募者自身のキャリアビジョンがその企業の事業内容と一致しているかも重視されます。
広告・マーケティング業界
広告・マーケティング業界では、企業ごとの得意分野やアプローチが異なります。
応募者がそれを十分に理解し、なぜその企業を選んだのかを具体的に説明する能力が求められます。
例えば、デジタル分野を得意とする企業と、伝統的なテレビ広告に強みを持つ企業では、事業戦略が異なります。
こうした違いを正確に理解し、自分の価値観や目指す方向性と結びつけて伝えることが重要です。
金融業界
競争が激しい金融業界では、企業ごとのサービスや強みが明確に異なります。
例えば、個人向けの資産運用を得意とする企業と、法人向けの融資に特化した企業では、アプローチが大きく異なります。
応募者がこうした違いを正確に理解し、その上でなぜその企業を選んだのかを説明できるかが重要です。
また、この業界では、規模や取引先、サービス内容が企業ごとに異なるため、それに応じた研究が欠かせません。
【他社との違い差別化する方法】
差別化の方法としては下記の5つが考えることができます。
他社との違いを理解する上で企業分析は必須です。
その企業分析の中でも他社との違いが見えやすい部分が、業績やMVVになります。
以下の5点は最低限として徹底的に企業のことを理解していきましょう。
業務内容や業績を調べる
企業の業務内容や業績を調べることは、就活準備の基本です。
しかし、差別化を意識する場合、表面的な理解では不十分です。
具体的な業務内容や近年の業績データを詳細に確認し、それが業界内でどのような位置づけなのかを調べる必要があります。
例えば、ある企業が特定の製品やサービスで大きな市場シェアを持つ場合、その要因を理解することが重要です。
深い知識を得ることで、他社ではなくその企業を選ぶ理由を具体的に述べられるようになります。
企業理念や特徴を調べる
業務内容や業績に加えて、企業理念やその企業特有の特徴を理解することが差別化の鍵となります。
企業理念には、その会社が大切にする価値観や方向性が明確に示されています。
これを調べ、共感する部分を自分の志望理由に織り込むことで、説得力を高めることができます。
また、企業独自の文化や取り組みを把握することで、他の企業との差別化がしやすくなります。
企業独自の強みを調べる
企業独自の強みを特定し、それを志望理由に取り入れることは、差別化の最も効果的な方法です。
強みとは、他社にはない製品、サービス、技術、あるいは企業文化などを指します。
例えば、特定の分野での技術力や、他社にない独自のビジネスモデルなどが挙げられます。
これを調べる際には、公式サイトだけでなく、業界ニュースや企業の実績発表も参考にすると良いでしょう。
業界分析を行う
企業分析だけでなく、業界全体を分析することも重要です。
業界のトレンドや課題、競合他社の動向を把握することで、企業の立ち位置が見えてきます。
これにより、その企業がどのような役割を果たしているかを理解できます。
例えば、業界全体がデジタル化に向かう中で、特定の企業が先進的な技術を採用している場合、それが志望理由に活用できるでしょう。
これにより、他社との比較も具体性を持って行うことが可能です。
企業の特徴と自分の強みの適合性について調べる
企業の特徴と自分の強みがどのように適合しているかを考えることは、差別化をする上で欠かせません。
単に企業の強みを述べるだけではなく、自分の経験やスキルがどのようにその企業で活かせるかを具体的に示す必要があります。
例えば、企業が求める「挑戦する姿勢」に対し、自分の過去の挑戦経験を結びつけると効果的です。
これにより、他の応募者との差別化を図りつつ、自分がその企業で活躍できる根拠を明確に示すことができます。
【他社との違い】例文
ここからは、参考にできる例文をいくつかご紹介します。
それぞれ異なる視点から企業の特徴を捉えたものですので、ぜひ自身の志望動機作成に活用してください。
例文1
私は、御社は他社と比べて製品の完成度において群を抜いていると感じております。
特に、開発プロセスの透明性や品質管理の徹底が特徴的で、信頼性の高さに魅力を覚えました。
こうした強みを持つ企業で、自分の経験を活かして貢献できる点に意義を感じています。
また、独自の技術力を軸にした取り組みが評価されていることから、自分もその一翼を担いたいと考え、応募に至りました。
例文2
御社は他社と比較して顧客対応の丁寧さが非常に優れていると確信しています。
特に、お客様一人一人に寄り添う姿勢が徹底されており、長期的な信頼を築いている点に共感しました。
また、私はこれまでの活動で人と信頼関係を築く力を大切にしてきましたので、その強みを活かせる場だと感じています。
責任を持ったサービス提供が評価される環境で自分の成長を目指したいと思っています。
まとめ
いかがでしょうか。
この記事で「なぜ同業他社ではなくウチなの?」という質問に応えるために必要な要素がご理解いただけたら幸いです。
本記事で述べた3つの要素を満たすためには説明会やインターンシップに参加することももちろんですがOB訪問をおすすめします。
「人」という要素で同業他社との区別をするためには複数人の社員に自分の足を使って話を聞きに行く必要があります。
「社風」を知るためにも現場の社員の声を聴くことは必要です。
今回の記事を参考に、面接に向けた準備を進めていきましょう。