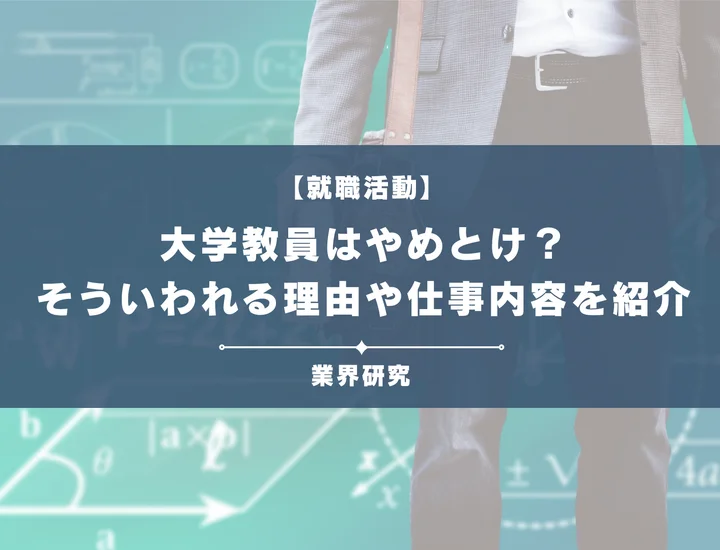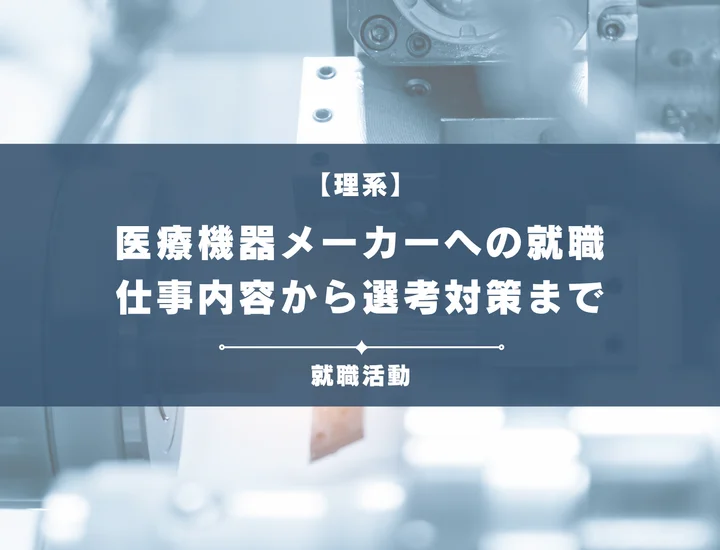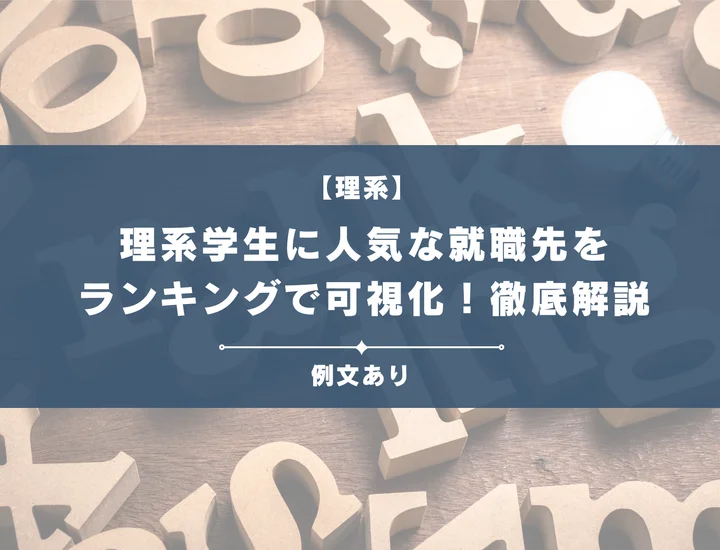HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
大学や大学院を卒業したあとの進路は、一般企業に就職するだけではないのをご存じでしょうか。
資格を取り士業に進むという選択肢もありますし、もう一度進学する人や試験を受けて公務員になる人もいます。
そして、大学教員という進路も存在します。
生涯を通して学びの場に携われる大学教員は、大学院生を中心に人気が高い進路ですが、狭き門としても知られているのです。
大学教員の現状について、さまざまな視点から説明していきます。
【大学教員】やめとけと言われる理由
大学教員は専門性を追求できる魅力的な職業ですが、なぜ「やめとけ」と言われるのでしょうか。
その背景にある、雇用の不安定さや業務負担の重さなど、知っておくべき厳しい現実を解説します。
熾烈なポスト争いと不安定な雇用
博士号を取得すれば大学教員になれるというのは、もはや過去の話です。
現代は博士課程修了者が増加する一方で、少子化の影響を受けて大学の常勤ポストは減少の一途をたどっています。
そのため、一つの公募には国内外から多数の優秀な研究者が応募し、極めて熾烈な競争が繰り広げられます。
運良く採用されたとしても、その多くは任期が3年から5年程度の特任助教やポスドクといった不安定な身分です。
任期満了後には再び職を探す必要があり、安定した生活設計を描くことは困難です。
この終わりの見えないポスト争いと雇用の不安定さが、やめとけと言われる最大の理由の一つです。
研究以外の膨大な業務負担
大学教員の仕事は、世間のイメージとは裏腹に、研究だけに没頭できるわけではありません。
むしろ、研究以外の業務に忙殺されるのが日常です。
担当する授業の準備やレポートの採点、学生の論文指導や進路相談といった教育活動は、非常に多くの時間を要します。
さらに、所属する学部や学科の会議、全学的な委員会、入試やオープンキャンパスの運営といった学内業務も、断ることができない重要な仕事です。
これらに加えて研究費獲得のための申請書作成もあり、純粋な研究時間は深夜や休日に確保せざるを得ない教員が少なくないのです。
費やした時間と労力に見合わない待遇
博士号取得までには、長い年月と多大な学費を投資する必要があります。
しかし、苦労の末に若手教員として得られる給与は、同年代の民間企業勤務者と比較して決して高い水準とは言えません。
特に、キャリアのスタートとなる助教や、コマ給で働く非常勤講師の待遇は厳しいものがあります。
また、裁量労働制の名のもとに、際限のない長時間労働が常態化しがちですが、残業代は支給されません。
費やしてきた時間と労力、そして専門性の高さに対して、報酬や労働環境が見合っていないと感じることが、この仕事を続ける上での大きな障壁となっています。
【大学教員】大学教員とは
大学教員とは、研究を行うとともに、自分の研究分野に関する講義を行う大学職員の総称です。
大学教員にはさまざまな肩書きがあり、年収や業務内容に影響します。
上のポストから学長、教授、准教授、講師、助教、助手に分類され、それぞれに定員があるのが特徴です。
そのため、順調にキャリアを築いていっても定員に空きがなく、学部の増設などが行われない限り昇進できないという側面もあります。
肩書きは、大学内の活動実績や経験、スキルに応じて付与されるのが一般的であり、教授になるためには厳しい条件を満たす必要があります。
講師は教授または准教授に準ずる職務でありますが、大学外の人がゲストとして講義のみを行う場合が多く、著名人が副業として、講師の名を受けて大学で授業をするなど本業が別にあるケースも多いのです。
理想と現実のギャップ
大学教員と聞くと、自分の好きな研究に没頭できる自由な職業というイメージを持つかもしれません。
しかし、その現実は大きく異なります。
教育者として授業準備や学生指導、論文添削に多くの時間を割くのはもちろん、大学の一員として会議や委員会、入試業務といった運営実務もこなす必要があります。
純粋に研究だけに集中できる時間は想像以上に限られており、研究以外の業務に忙殺される日々に悩む教員は少なくありません。
この理想と現実のギャップこそが、大学教員はやめとけと言われる大きな理由の一つなのです。
【大学教員】大学教員の仕事内容とは
大学教員と言えば、学生に対して講義を行っているイメージが強いと思いますが、業務内容はそれだけではありません。
専門分野の研究活動をしながら、大学の運営にまで携わっているのです。
大学教員は研究に対する活動をしながら、学生へ学びの場を提供し、学校運営にも携わるというまったく異なる3つの側面を持っていることをまず頭に入れておきましょう。
より詳しく大学教員の仕事内容について、それぞれを掘り下げて解説していきます。
講義
主な仕事の一つに、大学での講義があります。
大学では、あらゆる専門的な分野を学ぶために多くの講義が開かれており、大学教員は平均して週3日ほど講義を受け持っていると言われています。
講義はただ教壇に立つだけではなく、スライドや資料の作成などの準備も含まれるのです。
近年ではオンライン講義が浸透しているために、その機材を用意する必要もあります。
さらに、テスト作成、採点、学期末には成績をつけるなどの業務も行わなければなりません。
また、ゼミや研究室を受け持っているのなら実験などの活動もあります。
さらに、卒業論文の作成の際の添削や批評、コメントなども業務に含まれます。
その際、レポート課題など文章を多く読まなければならないので、研究との両立が大変になると言われているのです。
研究
教育と並行して、自分の専門分野の研究も行います。
研究内容は、文献調査、実験、フィールドワーク、国内外の学会参加や発表、論文の作成と学術雑誌への投稿、専門書の執筆などが挙げられます。
論文は海外に発表するために、日本語と英語の両方で作成しなければならないケースも多く、かなりの時間を要するのです。
また前述した研究活動だけでなく、助手やアルバイトの雇用と管理や、研究費を多くもらうための申請などの資金面の工面や、学会への出席や研究のための海外出張など、本業に関わる多くのことをやらなければなりません。
学生への高度な教育水準を保ちながら、自分の研究を続け、定期的に多言語で論文を発表するための時間の工面に悩む教員が多いようです。
大学の運営
所属している大学の運営にも携わることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
学部や学科内のクラス編成などのカリキュラム計画をはじめとし、学生向けガイダンスや説明会・試験の企画運営、非常勤および専任教員人事の採用の際の求人と審査、学内のイベントの企画運営、学内委員会などの組織運営、入試問題などが挙げられます。
当然、それらの組織の編成や活動に伴う年間予算の管理と執行も業務に含まれます。
時期によっては、この運営活動の会議や書類作成に追われ、研究活動に時間を割けないこともあるでしょう。
大学教員は勉学に携わることをするだけではなく、大学運営の業務を遂行するための事務系作業とコミュニケーションスキルが必要になるのです。
書類作成業務
大学教員の仕事内容で、特に負担が大きいのが書類作成業務です。
代表的なものに、研究費を獲得するための科学研究費補助金、通称科研費の申請書類があります。
これは自身の研究計画を詳細に記述するもので、採択されるか否かが研究活動を大きく左右するため、作成には膨大な時間と労力を要します。
その他にも、学内での報告書や予算申請書、学生の成績評価や推薦状の作成など、教育・研究以外の事務的な作業が常に発生します。
こうした書類業務の多さが、本来注力すべき研究や教育の時間を圧迫する一因となっています。
【大学教員】大学教員の平均年収
このように、3つの異なる業務のバランスを取ることが難しい多忙な大学教員ですが、どれほどの収入が得られるのでしょうか。
私立大学か国立大学かによって平均年収は異なり、一般的に国立、公立、私立の順に高いと言われています。
また、助手や助教と教授の間ではかなりの開きがあるのも事実で、助手は平均年収が400円台後半、助教では500万円台半ばほどです。
講師になると600万円台、准教授となると700万円台と上がっていきます。
そして、教授の平均年収は1000万程となっており、日本の平均年収の2倍にもなるのです。
しかし、教授の平均年齢は60歳近く、長い下積み時代を経てほんの一握りの人しかなれないポストであるため、単純に額面以外の苦労もあるのは事実です。
定年がないために長く働けることはメリットではありますが、年功序列で順調に昇給できるわけではないことを理解しておきましょう。
助教・准教授・教授でどう変わるか
大学教員のキャリアは、主に助教、准教授、教授という職位で構成され、それぞれ役割と待遇が大きく異なります。
助教は研究室の主宰者である教授のもとで研究や教育の補助業務を担うことが多く、自身の研究時間を確保するのが難しい立場です。
准教授になると、自身の裁量で研究を進められるようになりますが、同時に大学運営に関する責任も増えてきます。
そして教授は、研究室のトップとして予算管理や学生の指導、学内の重要な意思決定まで、全ての責任を負う立場となります。
職位が上がるにつれて給与は安定しますが、その分、研究以外の重圧も増していくのです。
非常勤講師の実態
大学教員の中でも特に厳しい立場に置かれているのが非常勤講師です。
多くは1コマ単位の契約で、給与は授業準備の時間を含めると時給換算でかなり低くなることも珍しくありません。
また、交通費は支給されても研究費や社会保険の補助がない場合がほとんどです。
契約は1年ごとの更新が基本であり、来年度の仕事が保証されないという不安定な身分でもあります。
そのため、複数の大学を掛け持ちして生計を立てる講師も少なくありません。
常勤職へのステップと考える人もいますが、実際にはなかなか抜け出せない厳しい現実があるのです。
【大学教員】大学教員の働き方
さまざまな業務がある大学教員ですが、限られた時間でどのように働いているのでしょうか。
大学教員には、講義や研究室、ゼミなどの決まった授業も存在しますが、それ以外の決まった働き方・時間的な制約はありません。
しかし、先ほども述べたように、生徒の課題確認やテスト作成などの教育に付随する業務や、論文執筆の際に国内外の資料や論文に目を通すなど必要な作業が非常に多くあります。
新しい論文は常に出され続けるため、仕事がなくなるということはありません。
時間的制約は少なく働き方も自由ですが、定時や目標がないためにやるべきことを自分で設定し、時間配分やスケジュール管理も兼ねながら、3つの業務をバランス良く進めていかなかければなりません。
プライベートと仕事を完全に分けることが難しいのは、ワークライフバランスを重視する人間にとってストレスになる可能性があります。
裁量労働制が基本
大学教員の働き方は、多くの場合、裁量労働制が適用されます。
これは、働く時間を自分で自由に決められるというメリットがあります。
しかし、その裏返しとして、労働時間と成果の管理が自己責任に委ねられることを意味します。
明確な定時という概念がないため、研究や授業準備が終わらなければ、深夜や休日も働くのが当たり前になりがちです。
どれだけ長時間働いても残業代は発生せず、仕事とプライベートの境界線が曖昧になります。
この自由な働き方が、結果としてサービス残業の温床となり、心身を疲弊させる原因にもなり得るのです。
学会や共同研究の時間も
大学教員の研究活動は、大学内だけで完結するものではありません。
自身の研究成果を発表し、最新の知見を得るための学会参加は不可欠な活動です。
学会は土日を挟んで開催されることが多く、プライベートの時間を犠牲にする必要があります。
また、他の研究者と協力して研究を進める共同研究も重要です。
これには、他大学や研究機関への出張も伴います。
これらは研究者としてのキャリアを築く上で欠かせない要素ですが、同時に時間的、体力的な負担も大きいのが実情です。
休日が休養ではなく、研究活動の延長線上にある働き方になりがちです。
【大学教員】将来性
大学教員の将来性は、正直なところ良いとは言えないでしょう。
少子高齢化は、大学の経営にも深刻な影響を与えています。
有名大学に人気が集中しているために、経営が赤字の大学も多く存在し、オープンキャンパスや体験入学などのイベント開催をするも学生の確保が難しくなっています。
そして、大学の規模が縮小すれば、必要な教員のポストも少なくなっていくのです。
現在大学院の修士課程を終えたのにも関わらず、助教や助手になれず非常勤講師として30代まで過ごしている者も決して少なくはありません。
そして、年収が高いからと将来が保証されているわけではありません。
教育に力を抜き指導がマンネリ化すれば、実践的な活動を行う講師たちに人気が集まり淘汰されていきます。
アカデミックポストの現状
現在の日本において、大学教員の常勤職、いわゆるアカデミックポストは非常に限られています。
特に18歳人口の減少に伴い、多くの大学が定員割れに悩んでおり、経営状況は厳しさを増しています。
その結果、新たな常勤ポストの設置には慎重にならざるを得ず、一つの公募に対して博士号を持つ多数の優秀な研究者が応募する、熾烈な競争が繰り広げられています。
博士課程を修了しても、すぐに安定した職に就ける保証はどこにもありません。
このポスト不足の深刻さが、大学教員を目指す上での最も大きな壁の一つと言えるでしょう。
任期付きポストの増加とキャリア形成の多様化
近年、大学の人件費抑制策として、任期が定められたポストが増加しています。
特任助教やポスドクといった立場で、契約期間は3年から5年程度が一般的です。
任期付き教員は、常に次の職を探しながら研究や教育に取り組む必要があり、腰を据えた長期的な研究計画を立てにくいという課題があります。
任期満了後に常勤職を得られる保証はなく、任期を繰り返しながらキャリアを繋ぐ不安定な状況に置かれる研究者も少なくありません。
そのため、アカデミアに残るだけでなく、民間企業の研究職など、多様なキャリアパスを視野に入れる必要性が高まっています。
【大学教員】大学教員になるためには
厳しい現実を知ったとしても、一般企業に就職せず研究に携わりたい、教育者の立場に立ちたいという思いを持つ学生は多いでしょう。
「好き」を仕事にすることには厳しい側面がありますが、仕事が楽しければ人生における8割の時間が楽しくなるというのも事実です。
大学教員になるためには、必要なステップがあります。
一般的に認知されている2つの方法について、説明していきます。
教員を目指す方は、今後の進路を判断するために理解しておきましょう。
修士・博士課程を取るのが一般的
大学教員になるためには大学院に進学し、修士課程・博士課程を修了してから、修士号、博士号を取得して大学に採用してもらうのが一般的です。
標準修業年限は修士課程2年、博士前期課程は3年となっており、在籍時に論文を提出し合格しなければなりません。
博士課程を修了するためには、2つを合わせた少なくとも5年の年月が必要になるため、卒業時には27歳を超えています。
しかし先述した通り、専任教員のポストにはなかなか空きが出ないため、スムーズに就職できる例はほんのわずかです。
また、教授に助手として雇ってもらう、もしくは他大学からスカウトされる、大学や研究機関でポストドクターなどとして働くなどのケースも見受けられます。
講師は学士でなる人もいる
学士とは、大学の4年間の課程を修了すれば与えられる学位です。
講師になるためには、2つのうちのどちらかの能力が必要と言われています。
一つめは、教授や准教授の資格に該当していること、もう一つは専攻分野について大学で教育を提供できる能力を認められていることです。
そのため、講師の形態は助教と准教授の間のポジションである大学の専任講師で、もう一つは新聞記者や起業家のような人たちが自分たちの分野について講義を持つ、ゲストの講師に二分化されています。
前者の場合は、修士・博士課程を修了し正式に大学に雇用される必要がありますが、ゲスト講師の場合は講義に必要な能力があると認められれば必要な資格はありません。
そのため、各分野のスペシャリストが非常勤として呼ばれているケースも多いのです。
公募に申し込む
大学ごとや学部ごとに、公募が行われている場合もあります。
この場合、ビジネスマンから大学教員へのキャリアチェンジが可能になります。
しかし、誰でも簡単に公募に応募すればなれるわけではありません。
明言されていませんが、少なくとも大学院の修士課程を修了していなければ応募は厳しい状況です。
そして、自分の現職や学生時代に研究したもので得意の分野を見つけ、学会へ入会し論文を書き、ある程度の評価を得て初めて公募するスタートラインに立てると言えます。
現職の業務と並行しながらの研究活動や執筆活動、そして公募に応募するのはかなりタイトなスケジュールになりますが、一定の評価が得られれば教員として新しいキャリアを始められる可能性は高くなります。
【大学教員】教授になるには運が必要
大学教員を目指すものの多くは、キャリアの目標を教授に設定しているでしょう。
しかし、教授は必ずなれるというものではありません。
現在は教授になるどころか、博士課程を卒業しても助手になれず、非常勤やポスドクとして30代を超えても働いている人が多いのです。
教授になるためには、実力だけではなく運が必要です。
大学教員は常に定足数を満たしており、定年がないため、当てもなく誰かが止めることで空きが出るのを待たなければなりません。
さらに、自分の研究分野の欠員が出る確率は非常に稀であり、多くの時間がかかることを覚悟する必要があります。
教授になれず生涯を終えてしまう人がいる反面、若く有名大学の出身でなくても、研究分野に空きが出てすぐに教授になれてしまう場合もあります。
大学教員は、実力だけでは渡り歩けない世界なのです。
研究業績は最低条件
大学教員の公募に応募する上で、質の高い学術論文を権威ある学術雑誌に発表している、いわゆる研究業績は、選考のスタートラインに立つための最低条件です。
業績がなければ、書類選考を通過することすらできません。
しかし、業績が十分にあれば必ず採用されるというわけではないのが、この世界の厳しいところです。
多くの応募者が同等レベルの優れた業績を持っているため、最終的には教育経験や大学運営への貢献意欲、さらには専門分野のマッチング度や面接での人柄といった、業績以外の多角的な要素で判断されることになります。
公募の仕組み
大学教員の採用は、原則として公募、つまり誰でも応募できるオープンな形式で行われます。
しかし、その内実では必ずしも完全に公平な競争とは限りません。
公募情報が出る前から、内部昇格や特定の研究室出身者など、ある程度採用候補者が決まっている、いわゆる出来レースと呼ばれるケースも存在します。
もちろん、全ての公募がそうではありませんが、採用には研究室の教授の推薦や学会での人脈が有利に働くことも事実です。
業績だけでなく、指導教員との関係や学界での評判といった、見えにくい要素が結果を左右することもあるのが実情です。
【大学教員】向いている人は
大学教員という教育者と研究者への道は、狭く厳しいものです。
どんなに優秀でも、ポストが空くまで待たなければならず、どれだけ待てば教員になれるという保証もありません。
また教育者と言っても、大学や専門分野によってカラーや活動がガラリと変わるために、中学や高校の教師とはかなり異なる立場となります。
安定性もなく非常に多忙ですが、生涯好きなことの研究に費やせるという大学教員に適性があるのは、どのような人なのでしょうか。
向いている人の特徴を2つに分けてみました。
学問への情熱がある人
大学教員に向いている人の絶対条件は、学問への情熱です。
教員になることがそもそも難しく、そこからさらに教授になるためには多くの困難があります。
まじめにコツコツと研究に勤しんでいても、正当に評価されないこともあるでしょう。
仮に大学教授になってからも、研究でつまずく、成果が出ない、予算が降りないなどうまくいかないことの連続です。
目立ちたい、給料を得たい、成果が欲しいという欲求だけでは、決して渡りきることはできません。
それでも研究を続けられる、学問への情熱があるかどうかが教育者として生涯をまっとうできるか否かの条件なのです。
もっと学びたい、知りたいという情熱の火を燃やし続けられる人は、教員としての適性があると言えるでしょう。
同じ作業を繰り返せる人
講義や大学運営は、毎年同じ単調な作業を繰り返し行わなければなりません。
それは研究活動においても言えることで、納得する結果が得られるまで同じことを繰り返し行い続ける必要があります。
とにかく何事にも粘り強さを持って、コツコツ取り組まなければならないのが大学教員です。
そのため、単調な作業にストレスを感じる、同じ作業を繰り返して飽きが来て辞めてしまうという人は向かないでしょう。
逆に、単調な作業の中にも楽しみを見つけながら、繰り返して行える人は素質があると言えます。
ルーティーンに窮屈さを感じるのであれば、講義で学生の質疑応答の時間やグループワークを設けてみるなどの工夫をすると、単純作業から少し脱却できるかもしれません。
次世代の育成に喜びとやりがいを感じられる
これまでの厳しい側面とは対照的に、大学教員には他では得難い大きなやりがいもあります。
その一つが、次世代を担う学生の育成に直接関われることです。
自分の専門知識を伝え、学生たちの知的好奇心に火がつく瞬間を目の当たりにできるのは、教育者としての大きな喜びです。
ゼミや研究室での指導を通して、学生が専門的な思考力を身につけ、社会へと羽ばたいていく姿を見届けることができます。
自分の研究だけでなく、人の成長に貢献することに強いやりがいと使命感を感じられる人にとっては、かけがえのない魅力的な仕事と言えるでしょう。
自律的に計画を立て、粘り強く物事を進められる
大学教員の仕事は、誰かから具体的な指示を受けて動くものではありません。
自身の研究テーマを設定し、長期的な視点で研究計画を立て、実行していく強い自律性が求められます。
研究活動は、論文が不採択になったり、実験がうまくいかなかったりと、すぐに成果が出ないことの連続です。
そうした困難に直面しても、諦めずに粘り強く探求を続けられる精神的な強さも不可欠です。
自分で自分を律し、モチベーションを維持しながら、着実に物事を前に進める力がある人にとって、この仕事は大きな裁量と達成感を与えてくれるでしょう。
【大学教員】よくある質問
ここまで大学教員の厳しい実態や求められる資質について解説しました。
しかし、実際の働き方や就職のプロセスには、まだ多くの疑問があるかもしれません。
ここでは、大学教員を目指す学生から特によく寄せられる質問をピックアップし、具体的にお答えします。
より深く知るための一助となれば幸いです。
大学の先生は夏休みは春休みも休めるのか
学生と同じように長期休暇があると思われがちですが、実態は大きく異なります。
大学教員にとって夏休みや春休みは、授業がない期間というだけで、休暇ではありません。
むしろ、普段の授業期間中には十分に時間を取れない研究活動に集中するための、最も重要な書き入れ時です。
この期間を利用して論文を執筆したり、学会発表の準備を進めたり、来学期の授業のシラバスを作成したりと、やるべきことは山積みです。
まとまった休みが取れるわけではなく、研究者としての活動が本番を迎える時期と考えるのが実態に近いでしょう。
研究室に泊まり込むようなことはあるのか
研究室への泊まり込みは、分野や研究室の文化によります。
特に、長時間にわたる観察や操作が必要な生物系の実験や、締め切り直前の論文執筆、学会発表の準備に追われる時期には、泊まり込みで作業する教員や学生もいます。
しかし、近年はワークライフバランスへの意識の高まりから、昔ほど常態化しているわけではありません。
個人の裁量に任されている部分が大きく、効率的に時間を管理して日中に作業を終える人もいます。
とはいえ、成果を出すためには時間を問わず研究に没頭せざるを得ない状況が、依然として存在することも事実です。
研究業績はどのくらいあれば就職できるのか
就職に必要な研究業績について、論文が何本あれば安泰、という明確な基準はありません。
これは、応募するポストの専門分野や大学のレベル、応募者の数によって、求められる水準が大きく変動するためです。
重要なのは論文の数よりも、掲載された学術雑誌の権威性や、その研究の独創性といった質です。
一つの目安として、競争の激しい分野では、筆頭著者として国際的に評価の高い学術雑誌に論文を複数本掲載していることが、書類選考を通過するための最低ラインとなることが多いでしょう。
まずは自身の分野の慣習を調べることが重要です。
まとめ
大学教員になるための道は、決して安易なものではないことを伝えてきました。
先述したように、博士課程を修了しても就けるポストがないオーバードクター時代となっており、研究者が食べていくのは難しい時世になっています。
ポストを増やすためには学部や大学を増設するしかないのですが、少子化のためにそれも難しいのが現状です。
それでも生涯研究を続けたい、やりがいを重視したいという方は、まずは大学院に進学して修士課程を取ることを目指していきましょう。