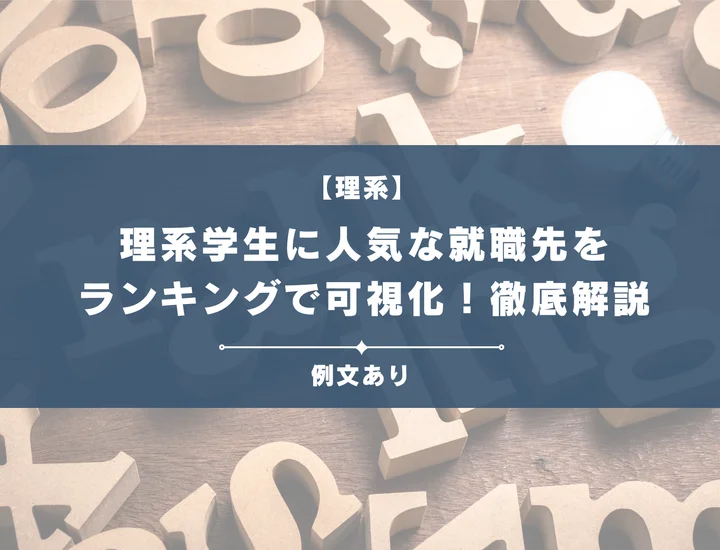HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
本記事では理系に人気の企業や職種をランキング形式で紹介しつつ、理系ならではの就活の進め方やポイントについて解説します。
理系の就活生必見の内容なので、是非最後まで読んでみてください。
【理系版就職ランキング】理系に人気の業界ランキング
理系学生にとって、専門知識を活かせるかどうかは就職先選びの大きな基準です。
研究や実験で培った技術力や思考力をどの業界で発揮できるかを見極めることが、納得のいくキャリアに繋がります。
以下に、理系学生の人気業界を紹介します。
理系の人気業界ランキングを見るためには無料アカウントの作成が必要です。
無料登録すると、就活生向けの理系の人気業界ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
- 人気業界ランキング
- 人気職種ランキング
- 人気企業ランキング
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ自分の就職偏差値と企業ランクをチェックしましょう!
1位:ITサービス・通信
2位:電機・電子部品・半導体
3位:自動車・自動車部品
4位:食品・飲料
5位:化学・医薬品・化粧品・生活用品
6位:機械
7位:エネルギー
8位:商社
9位:コンサルティング
10位:鉄鋼・非鉄・金属製品
11位:建設・設備・道路
12位:航空・海運・鉄道・陸運・倉庫
13位:銀行・生保・損保・証券・信販・カード・リース
14位:ゴム・ガラス・セメント・紙・印刷・インキ
1位:ITサービス・通信
IT業界はデジタル技術の発展とともに急速に拡大しており、理系人材へのニーズが非常に高い分野です。
AIやクラウド、IoTなどの先端分野で活躍できる機会が多く、プログラミングや数学、情報処理のスキルが直接仕事に結びつきます。
また、スタートアップやベンチャー企業も多く存在し、自由な働き方やリモートワークなど柔軟な労働環境を求める学生にも人気があります。
業務を通して新しい仕組みやサービスを社会に提供できる点に大きなやりがいを感じる人が多く、専門性と創造性を活かしたい理系学生にとって非常に魅力的な業界です。
2位:電機・電子部品・半導体
電機や半導体業界は、日本の高度なものづくり技術を象徴する分野であり、世界中でその製品や技術力が高く評価されています。
パソコンやスマートフォン、電気自動車、医療機器など、あらゆる分野に不可欠な電子部品を開発・製造するこの業界では、物理、電気電子、情報、材料工学といった幅広い理系分野の知識が活かされます。
製品の小型化・高性能化が求められる中で、ナノレベルでの精密な制御技術や半導体プロセス開発といった高度な技術が要求されるため、常に学び続ける姿勢が必要です。
また、多くの企業が研究開発投資に力を入れており、大学での研究経験がそのまま活かせる職場環境も整っています。
日本国内だけでなく、台湾や韓国、アメリカなど海外企業との競争も激しいため、グローバルな視点で活躍できる機会が豊富です。
3位:自動車・自動車部品
自動車業界は、近年かつてないほどの技術変革期に突入しています。
特に、電動化(EV)、自動運転、コネクテッドカーといった領域では、機械、電気電子、情報、材料といった複数の工学分野が融合し、次世代のモビリティを支える開発が進んでいます。
理系学生にとっては、自らの専攻分野を活かせる場面が多く、かつ異分野の知識も必要とされるため、技術者としての成長を実感しやすい業界です。
また、日系自動車メーカーの多くはグローバル展開をしており、海外との共同開発や現地拠点とのやり取りも日常的に行われます。
そのため、語学力や異文化理解力も求められる場面が増えており、世界で活躍したいと考える学生には非常に魅力的な環境です。
一方で、安全性や法規制の厳しい領域でもあるため、設計・開発における責任感と緻密さも重要です。
4位:食品・飲料
食品業界は、人々の健康や生活に密接に関わる領域であり、理系学生から根強い人気を集めています。
とくに化学や生物学、農学、応用生物学などの専攻出身者が多く、食品の新製品開発、品質改良、成分分析、衛生管理など、理系ならではの知識と技術が幅広く活かされる業界です。
製品開発の現場では、味や食感の評価、保存性、栄養価のバランスなど、さまざまな要素を科学的に検証しながら、安全かつ魅力的な商品を生み出すことが求められます。
また、製造現場では生産ラインの効率化や衛生管理、生産設備の保守・改善など、工学的な視点も必要とされるため、機械系や電気系の学生にも活躍の場があります。
近年は健康志向や環境意識の高まりにより、プラントベース食品やサステナブルな包装材の開発など、新たな研究テーマも増えています。
5位:化学・医薬品・化粧品・生活用品
化学や医薬品、化粧品、日用品を扱う業界では、研究から製品化、量産化までのプロセスにおいて理系の知識が欠かせません。
特に化学系、薬学系、生物系出身の学生にとっては、学んできた知識がそのまま現場で求められるため、専門性を活かしやすい業界です。
新素材の開発、新薬の研究、安全性試験、品質保証など、多岐にわたる職種が存在し、それぞれに高い専門性と継続的な学習が必要です。
製品の用途も幅広く、医療、衛生、美容、生活と多様な領域に貢献できるため、社会的意義を感じながら働ける点も大きな魅力となっています。
また、長期的な視点で研究に取り組む風土が根付いており、基礎研究と応用研究の両方に携われる環境も整っています。
さらに、最近ではSDGsや環境配慮型製品のニーズが高まっており、生分解性材料や低刺激処方などの研究開発も注目されています。
6位:機械
機械業界は、自動車、航空機、ロボット、産業用装置、工作機械、精密機器など、あらゆる分野のものづくりを支える重要な産業です。
設計、生産技術、制御、試作評価、解析といった多くの工程で機械系の知識が必要とされており、大学で学んだ内容を実務に活かしやすい点が大きな魅力です。
加えて、電気・情報系の知識と連携しながら設計を行うことも多く、メカトロニクスやシステム工学といった複合領域の技術にも触れる機会があります。
製品をゼロから形にしていく工程に関わることができるため、設計者としての達成感や開発者としての誇りを強く感じやすい業界です。
また、機械産業はBtoB企業が多く、表には出にくいものの、産業全体を支える基盤として高い技術力と安定性を兼ね備えています。
7位:エネルギー
エネルギー業界は、電気、ガス、石油、再生可能エネルギーといった社会基盤を支える分野であり、理系学生の中でも技術志向が高い層から根強い人気を集めています。
特に近年は、再生可能エネルギーの研究やスマートグリッド、水素技術、蓄電池の高性能化など、新たなエネルギー技術の開発が進められています。
電気電子、機械、化学、材料、土木など幅広い理系分野が関与しており、自分の専門性を活かせる場が豊富にあります。
また、プラントの設計や運用、保守など大規模な設備に関わる仕事が多く、スケールの大きなプロジェクトに携われる点もこの業界の醍醐味です。
一方で、環境への配慮や安全性の確保が非常に重視されるため、慎重かつ確実な判断力と、社会的責任感が求められます。
8位:商社
商社は、製品や資源の流通を担う業界として知られていますが、理系学生にとってもチャンスのある分野です。
特にプラント、機械、エネルギー、化学品、医療機器など、専門性の高い商材を扱う部署では、理系の知識を活かして技術的な打ち合わせやプロジェクト推進を担うケースがあります。
営業職であっても、単なる物売りではなく、顧客の課題に対して技術的な視点からソリューションを提供することが求められるため、技術者的な役割を果たすことも少なくありません。
また、商社はグローバルに展開している企業が多く、若手のうちから海外拠点や取引先との連携業務に携わるチャンスがあります。
プロジェクトの立ち上げやマネジメント、契約交渉などダイナミックな仕事に挑戦できるため、自分の専門性を軸にしながら、より広いフィールドで活躍したい学生にとって魅力的です。
9位:コンサルティング
コンサルティング業界は、企業や自治体の課題に対して、分析と提案を通じて解決策を導く役割を担っています。
理系出身者は、論理的思考力やデータ解析力、問題解決能力を評価される場面が多く、特にIT系や製造業向けのコンサルティング領域での需要が高まっています。
具体的には、業務プロセスの改善支援、システム導入、技術戦略の立案、新規事業開発の支援など、技術に関する深い理解と構造的な考察が求められます。
また、多様な業界のクライアントと関わる機会が多いため、短期間で幅広い知識と経験を積める点が、向上心の強い理系学生にとって魅力です。
加えて、数字や根拠に基づく提案を行う場面が多いため、研究で培ったデータ処理能力やプレゼンテーション能力も評価されます。
10位:鉄鋼・非鉄・金属製品
鉄鋼や非鉄金属業界は、自動車、建設、機械、インフラなどあらゆる産業の基盤となる素材を提供する、社会を下支えする重要な分野です。
製鉄所や製造工場では、高温・高圧下での複雑なプロセスが行われており、化学工学、材料工学、物理学、機械工学などの幅広い理系知識が求められます。
材料の開発、製造プロセスの最適化、品質保証、構造評価など、多くの場面で理系学生が活躍できる環境があります。
また、近年は軽量化素材の開発や環境負荷の低減、省エネルギー化といった分野でも技術革新が進んでおり、社会的な意義も感じやすい業界です。
さらに、鉄鋼・非鉄製品は最終製品に直接名前が出ないBtoB産業でありながら、その技術レベルと信頼性が日本のものづくりを支えているといっても過言ではありません。
11位:建設・設備・道路
建設業界は、ビル、橋、ダム、道路、トンネルなど、社会インフラを形にするダイナミックな業界です。
理系の中でも土木、建築、環境系の学生にとって、学んできた知識がそのまま実務に活かせる業界として高い人気があります。
施工管理、構造設計、設備設計、環境計画、安全管理、メンテナンス計画など、多様な職種が存在し、大規模プロジェクトにチームで取り組む機会が多いのが特徴です。
実際に目に見える形として成果が残る仕事であるため、仕事のやりがいを視覚的に実感できるという点でも魅力を感じる学生が多くいます。
また、災害復旧や都市の再開発、防災インフラの整備など、社会的意義の高い案件も増えており、地域や人々の暮らしを支える使命感が原動力となることもあります。
12位:航空・海運・鉄道・陸運・倉庫
航空、海運、鉄道、陸運、倉庫といった物流・交通インフラ業界は、モノや人の移動を支える社会の基盤です。
理系学生にとっては、運行システムの最適化、車両や航空機・船舶の設計整備、制御システムの開発、倉庫オペレーションの効率化といった分野での活躍が期待されています。
情報系の学生であれば、輸送ルートの最適化アルゴリズムや予約・発券システムの開発、セキュリティ対策など、システムエンジニアとしての役割もあります。
一方、機械、電気、土木、建築系の学生は、インフラ整備や構造物の保守、車両や設備の開発・検査といった技術的な業務で強みを発揮できます。
また、物流業界では自動倉庫、AGV(無人搬送車)、IoTによる在庫管理などのデジタル化が急速に進んでおり、DXを担う若手技術者の存在が重視されています。
13位:銀行・生保・損保・証券・信販・カード・リース
金融業界はこれまで文系の就職先という印象が強かったものの、近年は理系人材の活躍の場が急速に拡大しています。
特にデータサイエンス、AI、統計解析、金融工学、リスク管理といった分野では、数理的な能力やプログラミングスキルが強く求められています。
情報系や数学系の学生は、アルゴリズム開発や金融商品の価格モデル構築、取引データの解析などに携わることができ、非常に高度な専門性を発揮できます。
また、保険やリース、信販といった分野でも、業務効率化に向けたシステム開発やAI導入、ビッグデータを活用した商品開発が進んでおり、理系の視点が重宝されています。
金融業界の魅力は、論理性や分析力を駆使しながらダイナミックなお金の流れを扱える点にあり、数字に強く、思考力に自信のある学生には相性が良い分野です。
14位:ゴム・ガラス・セメント・紙・印刷・インキ
この業界群は一見地味に見えるかもしれませんが、実は日常生活を支える多くの素材を提供している、縁の下の力持ち的存在です。
扱う製品が生活用品、建築資材、産業資材など多岐にわたるため、化学、材料工学、プロセス工学の知識を活かす場面が非常に豊富です。
製品の特徴としては、熱や圧力、化学反応を用いた製造プロセスが多く、その中で生産性の向上や品質管理、安全対策を担うエンジニアの存在は欠かせません。
また、環境問題への対応として、リサイクル性や持続可能性を考慮した新素材の研究開発が進められており、サステナブルな社会づくりに貢献するチャンスがあります。
近年では、紙や印刷においてデジタル技術との融合が進んでおり、ITや機械系の知識を活かして新たなソリューションを提案する動きも活発です。
【理系版就職ランキング】理系に人気の職種ランキング
理系学生が就職活動で職種を選ぶ際には、自分の専門知識やスキルをどのように活かせるかを意識することが重要です。
一言に理系職種といっても、研究、開発、設計、運用、営業、コンサルティングなどその種類は多岐にわたり、求められる能力や役割も大きく異なります。
ここでは、理系出身者から特に人気の高い5つの職種について、その特徴ややりがい、適性などを詳しく解説していきます。
1位:研究開発
2位:生産技術・品質管理
3位:システムエンジニア(SE)
4位:コンサルタント
5位:技術営業
1位:研究開発
研究開発職は、企業や公的機関などにおいて、新しい製品や技術を生み出すための根幹を担う仕事です。
基礎研究を通じて新たな知見を発見し、それを応用して実用的な技術や製品として形にしていく役割があります。
理論的な探究心と同時に、実験・検証を重ねて社会に貢献できる成果を目指す姿勢が求められます。
新素材の開発、医薬品の創出、エネルギーの効率化、AIの新アルゴリズム研究など、分野は極めて多様です。
また、大学や大学院での研究経験がそのまま活かせる数少ない職種であり、自らの専門性を深めたいと考える理系学生にとって、非常に魅力的な選択肢です。
2位:生産技術・品質管理
生産技術は、製品を効率よく安定して生み出すための製造プロセスを設計し、改善していく技術職です。
工場での生産ラインの設計や設備導入、レイアウト改善、コスト削減といった幅広いテーマに取り組みます。
製品の品質を左右する工程設計にも関わるため、高い精度と論理的な検証力が求められます。
一方、品質管理は製品が一定の基準を満たしているかを確認し、不良の原因を突き止め、再発防止策を講じる仕事です。
品質トラブルを未然に防ぐ役割であり、企業の信頼を守る重要なポジションといえます。
3位:システムエンジニア(SE)
システムエンジニアは、顧客のニーズに基づいて情報システムを企画・設計し、開発から運用・保守までを一貫して支援する職種です。
プログラマがコードを書く立場であるのに対し、SEは全体の構造を考え、スケジュールや工程の管理も行うプロジェクト推進の立場に立つことが多くなります。
業務内容は多岐にわたり、業務系システム、金融系システム、Webサービス、スマートフォンアプリ、製造業の組み込みソフトウェアなど、あらゆる業界で活躍の場があります。
論理的思考力、対話力、マネジメント力などが求められる場面が多く、技術だけでなくビジネス理解やコミュニケーション力も問われます。
開発プロジェクトを成功に導くために、仕様書の作成やテスト計画の立案なども重要な業務であり、全体を俯瞰する視野が必要です。
4位:コンサルタント
コンサルタントは、企業や組織の抱える課題を明らかにし、課題解決に向けた戦略を立案・提案し、実行支援までを行う職種です。
理系出身者は、論理的な分析力や問題解決スキルを活かして、特にIT戦略や製造業の業務改善、データ解析分野で重宝されます。
企業の現場に入り込み、ヒアリングやデータ分析を行い、クライアントとともに最適な施策を考え抜く過程では、高い思考力と対人スキルの両方が必要とされます。
短期間で複数の業界に関わることができるため、多様な経験を積みたいと考える学生にとって魅力的な環境です。
また、経営や事業戦略に携われる機会も多く、技術とビジネスを横断的に捉えたい人にとってはやりがいの大きな職種といえます。
5位:技術営業
技術営業は、製品や技術を単に売るのではなく、顧客の技術的な課題やニーズを理解し、最適な解決策を提案する職種です。
製品の仕組みや機能、導入のメリットを専門的な知識に基づいて説明し、営業活動と技術的支援を両立させる役割を担います。
そのため、機械、電気、化学、情報など、自社製品に関連する理系の知識が不可欠です。
また、顧客との信頼関係構築や課題ヒアリングの中で、コミュニケーション力や提案力も強く求められます。
製品の開発担当者と顧客の間に立ち、仕様調整や納入スケジュールの管理など、社内外の橋渡し役としても活躍する場面が多いです。
営業でありながら専門性を発揮できる数少ない職種の一つです。
【理系版就職ランキング】理系に人気の企業ランキング
理系学生が企業選びをする際には、専門知識が活かせるか、研究や技術に対する姿勢が合っているか、そして将来のキャリアの広がりがあるかを重視する傾向があります。
ものづくりやIT、エネルギー、食品、商社といったさまざまな業界の中から、理系出身者に支持される企業には共通して「技術に対する信頼」と「社会への影響力」があります。
ここでは、特に理系学生から高く評価されている企業をランキング形式で紹介し、それぞれの魅力と特徴を具体的に解説していきます。
1位:NTTデータ
2位:ソニーグループ
3位:トヨタ自動車
4位:Sky
5位:伊藤忠商事
6位:味の素
7位:日立製作所
8位:パナソニック
9位:三菱商事
10位:サントリーグループ
1位:NTTデータ
NTTデータは、日本を代表するシステムインテグレーターとして、官公庁、金融、製造、通信など幅広い分野でITソリューションを提供しています。
理系出身者は、システム設計やプログラミングだけでなく、データサイエンスやAI技術を活用したプロジェクトにも携わることができます。
また、セキュリティ対策やインフラ構築といった社会インフラを支える業務も多く、公共性と安定性の高い技術開発に挑戦できる点が大きな魅力です。
チームで進める大規模プロジェクトが多く、コミュニケーション力や課題解決力も求められますが、その分、自分の関わったシステムが社会に影響を与えている実感を持ちやすいです。
IT分野での最先端技術を学びながらキャリアを積みたい理系学生にとって、非常に人気の高い企業です。
2位:ソニーグループ
ソニーは、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融と多岐にわたる事業を展開しており、技術とクリエイティビティを融合させた製品やサービスで世界中のユーザーに支持されています。
理系の学生にとっては、半導体やセンサー、ロボット、AIなどの最先端分野に関わる研究開発職に加え、製品設計や材料開発、生産技術職としても活躍の場があります。
また、PlayStationや医療機器といった分野でもハードウェアとソフトウェアの融合を進めており、情報系や電気電子系の知識が求められています。
技術に対する深い探究心とともに、ユーザー体験や社会課題への貢献を意識した開発が重視されており、創造性を発揮したい学生にとって理想的な環境です。
新しい価値を世界に届けることを目指す人にふさわしい、挑戦的な舞台が広がっています。
3位:トヨタ自動車
トヨタは世界有数の自動車メーカーとして、グローバルにモビリティの未来を牽引しています。
理系出身者が活躍するフィールドは非常に広く、電気自動車や燃料電池車、自動運転技術などの最先端技術の研究開発、車両やエンジン設計、電子制御システム開発など多岐にわたります。
また、軽量で強度の高い素材の開発や、生産工程の自動化・スマートファクトリー化における生産技術、さらには製品の信頼性を守る品質保証業務でも理系の力が活かされています。
機械、電気電子、情報、材料といった工学分野の知識を総動員して取り組む場面が多く、チームで連携して課題に挑む姿勢が重視されます。
世界規模のプロジェクトで自分の技術を発揮したい人、社会インフラを支える製品づくりに誇りを持ちたい人にとって、非常にやりがいのある企業です。
4位:Sky
Skyは業務系や医療機関向けのシステム、自動車向けの組み込みソフトウェアなど、幅広い分野でソフトウェア開発を行っているIT企業です。
理系学生にとっては、ソフトウェアエンジニアとしてプログラミングや要件定義、設計などに携わる機会が多くあります。
また、品質評価やテスト業務も重要であり、論理的な思考力や根気強さが問われる分野です。
若手でも裁量を持って活躍できる環境が整っており、入社後すぐに開発の中核を担うプロジェクトに参加できることもあります。
教育制度も充実しており、文系出身者も多く活躍しているため、実務で学びながら技術を高めたいと考える人にも適しています。
5位:伊藤忠商事
伊藤忠商事は、エネルギー、食料、機械、化学品、繊維など多様な事業を展開する総合商社であり、理系人材の活躍の幅も広がっています。
技術系のバックグラウンドを持つ社員は、商材の選定や技術評価、プロジェクトの立ち上げにおいて重要な役割を果たしています。
事業開発や投資判断においては、製品や技術の理解が成功の鍵となる場面が多く、専門性をビジネスに転換する力が求められます。
再生可能エネルギー、水資源、スマートシティなどの新領域にも力を入れており、環境やインフラ系の専攻を活かしたい学生にも適しています。
グローバル展開が進んでいるため、海外の企業や顧客との折衝もあり、語学力や国際感覚が活かされる点も魅力です。
6位:味の素
味の素は、食品分野だけでなくアミノ酸やバイオテクノロジーなど、多岐にわたる事業を展開するグローバル企業です。
理系出身者は、調味料や冷凍食品の開発、栄養研究、機能性素材の開発、品質保証や工場の生産技術業務など、さまざまな領域で活躍しています。
食品科学や応用生物学、農学、化学といった分野で学んだ知識をそのまま実務に活かせるため、専攻との親和性が高い点が大きな魅力です。
また、味や栄養だけでなく、安全性や環境配慮も重視されており、社会的意義のある仕事に取り組みたい学生にも人気があります。
グローバル展開を行っているため、海外工場や国際共同研究に関わるチャンスも多く、技術力と語学力を活かしてキャリアを築くことができます。
「食」を通じて人々の健康と幸福に貢献したいという思いを持つ学生にとって、非常にやりがいのある企業です。
7位:日立製作所
日立製作所は、情報技術(IT)と運用技術(OT)を融合させ、社会インフラに貢献する事業をグローバルに展開している企業です。
理系出身者が活躍する領域は非常に広く、電力や交通、水道などの社会インフラを支える制御システムの開発から、AIやクラウドを用いたデジタルソリューションの設計、パワー半導体や医療機器といった製品開発まで多岐にわたります。
電気電子、機械、情報、材料系など幅広い専攻がマッチし、複数の分野が連携して課題解決にあたるプロジェクトが多いのも特徴です。
社会全体の課題に対して、最先端の技術を用いた包括的なソリューションを提供することが求められるため、システム思考と協働力が強く求められます。
国内外の大規模インフラプロジェクトに携われるため、自分の仕事が社会に与える影響を実感できる環境です。
8位:パナソニック
パナソニックは、家電製品から住宅設備、車載機器、BtoBソリューションに至るまで多角的な事業を展開する大手メーカーです。
理系学生にとっては、製品の開発設計、材料開発、バッテリー技術、センサーやAIの研究、ソフトウェア開発、スマートファクトリーの推進など、多くの技術領域で活躍の場があります。
とくに、電気電子、情報、機械、材料、化学系の専攻が活かされる職種が豊富で、製品の性能や安全性を高める技術革新に挑戦できます。
また、グローバルでの事業展開が活発であり、海外拠点との連携や現地ニーズに対応した製品開発を担うこともあります。
暮らしや社会の質を高めるという使命感のもと、技術を通じて人々の生活を豊かにしたいという想いを持つ理系学生にとって、やりがいのある職場です。
9位:三菱商事
三菱商事は、日本を代表する総合商社として、エネルギー、金属、インフラ、化学品、機械、食品など多彩な分野にビジネスを展開しています。
理系学生は、資源開発や発電事業、インフラプロジェクトの企画・運営、製品の技術的評価、投資判断など、専門知識をビジネスに落とし込む役割で活躍します。
また、デジタル変革(DX)の推進にも注力しており、情報系出身者がシステム導入やデータ活用の分野で貢献できる機会も増えています。
世界中のパートナーと協業しながらプロジェクトを進める機会が多く、英語力や異文化理解も重要なスキルとなります。
ビジネススケールの大きさに加えて、社会課題の解決を技術と経営の両面から実現できる環境は、理系学生にとって大きな魅力となっています。
10位:サントリーグループ
サントリーは、飲料、酒類、健康食品などを手がける食品業界のリーディングカンパニーです。
理系出身者は、風味や成分の研究、新しい製造プロセスの開発、品質保証、安全性評価、工場の生産性向上、設備設計など多岐にわたる分野で活躍しています。
食品科学、化学、生物学、農学、醸造学などの専攻が直接活かされる業務が多く、大学での実験経験を実務に応用しやすい点が特長です。
また、環境保全活動にも力を入れており、水源保護や容器リサイクル技術の研究開発といったテーマにも関わることができます。
製品を通じて人々の生活や健康、環境に貢献したいという志を持つ学生にとって、企業理念との親和性が高い職場です。
ブランド力のある商品を科学的に支えたいという思いを持つ理系学生にとって、魅力的な選択肢の一つです。
11位〜100位
11 富士フイルム
12 三井物産
13 富士通
14 野村総合研究所
15 三菱UFJ銀行
16 丸紅
17 日本電気(NEC)
18 住友商事
19 アクセンチュア
20 任天堂
21 三菱重工業
22 東海旅客鉄道
23 三菱電機
24 中外製薬
25 ホンダ
26 キヤノン
27 KDDI
28 東日本旅客鉄道
29 NTTドコモ
30 キリンホールディングス
31 旭化成グループ
32 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
33 デンソー
34 第一三共
35 日本アイ・ビー・エム
36 ロッテ
37 三井住友銀行
38 クボタ
39 花王
40 みずほフィナンシャルグループ
41 東京エレクトロングループ
42 大林組
43 伊藤忠テクノソリューションズ
44 野村グループ
45 キーエンス
46 カゴメ
47 SCSK
48 AGC
49 竹中工務店
50 大成建設
51 NTT東日本
52 鹿島建設
53 NECソリューションイノベータ
54 村田製作所
55 アステラス製薬
56 日清食品グループ
57 グリコグループ
58 豊田自動織機
59 セキスイハイムグループ
60 西日本旅客鉄道
61 全日本空輸(ANA)
62 コーセー
63 清水建設
64 ソニーミュージックグループ
65 ニトリ
66 日本航空(JAL)
67 三井不動産
68 山崎製パン
69 日清医療食品
70 デロイトトーマツコンサルティング
71 三井化学
72 関西電力
73 資生堂
74 三菱地所
75 楽天グループ
76 バンダイナムコエンターテインメント
77 アサヒビール
78 アビームコンサルティング
79 PwCコンサルティング
80 川崎重工業
81 京セラ
82 森永乳業
83 メイテック
84 島津製作所
85 日産自動車
86 三菱ケミカル
87 日鉄ソリューションズ
88 大和ハウス工業
89 東北電力/東北電力ネットワーク
90 NTTコムウェア
91 日立システムズ
92 東芝
93 日清製粉グループ
94 アイシン
95 バンダイ
96 アマゾンジャパン
97 住友化学
98 日本製鉄
99 電通グループ
100 双日
【理系版就職ランキング】理系就職の給料と待遇のリアル
就職先を考えるうえで、給料や待遇といった観点は重要です。
ここでは大学学部卒と大学院卒の給料の差や、業界別の年収・待遇について解説します。
学部卒と大学院卒の初任給相場
一般的に大学院を修了した学生の初任給は、学部を卒業した学生よりも高く設定されています。
これは大学院での専門的な研究経験や高度な知識が、企業から高く評価されるためです。
学部卒の初任給相場:21万円〜23万円
大学院卒の初任給相場:23万円〜25万円
この金額はあくまで目安であり、企業規模や業界、職種によって大きく異なります。
また、近年はジョブ型採用の広がりによって専門性が高い分野では初任給が大幅に上回るケースも増えています。
自身の専門性を活かせる企業や職種を選ぶことで、より高い待遇を目指せるでしょう。
業界別・職種別の平均年収
理系に人気の業界・職種の中でも、給料水準は大きく異なります。
就職後のキャリアパスを考える上で、業界全体の年収水準を把握しておくことが重要です。
まず、IT・情報通信業界では、システムエンジニアやデータサイエンティストは高い年収が期待できます。
例えば、プロジェクトマネージャーの平均年収は691万円、ITコンサルタントは900万円から1,000万円程度と、専門性やスキルが直接年収に反映される傾向にあります。
次に、医薬品・医療機器業界は、専門性の高さから高い年収水準を誇ります。
MR(医薬情報担当者)の平均年収は約700万円、薬事関連職は600万円から1,000万円程度とされており、安定した高収入が見込めます。
さらに、高い論理的思考力や問題解決能力が求められるコンサルティング業界では、理系出身者がトップクラスの給与を得ることも可能です。
特に戦略系コンサルタントは、平均年収1,000万円を軽く超えるケースも珍しくなく、成果次第ではさらなる高年収が期待できます。
最後に、製造業(メーカー)は、企業規模が大きく安定しているため、長期的に安定した年収を見込めます。
メーカー全体の平均年収は約465万円ですが、大手企業では1,000万円を超える企業も多数存在します。技術職や研究職は、専門性を深めることで年収アップも期待できます。
福利厚生や研究設備の重要性
就職先を選ぶ上で、年収だけでなく福利厚生や研究環境も非常に重要な要素です。
特に理系職種は、研究・開発の質が企業の成長に直結するため、以下の点をチェックしておきましょう。
まず、福利厚生です。
住宅手当や社員寮の有無、有給休暇の消化率、育児・介護休業制度の充実度は、長期的に安心して働けるかどうかのバロメーターになります。
これらが充実している企業は、社員の働きやすさを重視している証拠です。
次に、研究環境です。
最新の研究設備が導入されているか、研究予算は十分に確保されているか、そして学会発表や論文執筆を奨励しているかなどを確認しましょう。
企業によっては、大学や研究機関との共同研究に積極的に取り組んでいるところもあり、自分の専門性をさらに高めるチャンスに恵まれることもあります。
最後に、キャリアパスです。
研究職からマネジメント職への移行、専門性を高めるための研修制度など、将来のキャリアプランが描けるかどうかも重要です。
これらの要素を総合的に考慮することで、自分に合った最適な企業を見つけることができます。
【理系版就職ランキング】理系の就職活動の進め方
就職活動を進めるうえで、理系学生ならではの強みや特性をどう活かすかが重要です。
専門知識や研究経験をうまく整理し、企業側に伝える力が求められます。
また、理系の就活では、技術や職種に関する理解に加え、業界の動向にも敏感になることが必要です。
ここでは、自己分析から面接対策まで、理系就活生が意識すべきポイントを順を追って解説します。
自己分析とキャリアプランの明確化
理系の就職活動では、まず自分の専門性と適性を把握することが出発点です。
自分が取り組んできた研究内容や習得したスキル(実験手法、プログラミング、シミュレーションなど)を洗い出し、それを通じて得た能力を具体的に整理します。
論理的思考、探究心、地道に課題に取り組む力など、自分ならではの特徴を言語化することが大切です。
さらに、どんな職種や技術領域に興味があり、将来どのような姿を目指すのかを考えることで、就活の軸が明確になります。
キャリアプランを描くことで、企業選びや自己PRの説得力も大きく高まります。
業界・企業研究の徹底
理系学生の企業選びでは、技術内容や職種との相性を見極めることが重要です。
企業の技術情報や研究開発の方向性、特許の取得状況などを調べることで、自分の専門とどのように関連するかを確認できます。
また、研究開発職、生産技術、ITエンジニアなど、理系人材が活躍できる職種の具体的な役割や業務内容も把握しておきましょう。
加えて、AI、IoT、再生可能エネルギーなど、広い視点で社会全体の技術動向を掴むことも必要です。
企業の将来性や技術的な魅力を理解し、自分の価値をどう活かせるかを言語化する準備を整えましょう。
OB・OG訪問とインターンシップの活用
企業の実態を知る手段として、OB・OG訪問は非常に有効です。
大学の先輩から、業務の進め方や企業文化、研究のどのような部分が役立っているかを直接聞くことで、イメージが具体化します。
また、インターンシップに参加することで、実際の業務内容を体験し、職場の雰囲気や求められるスキルを肌で感じることができます。
特に理系では、技術職や研究職向けの長期・テーマ型インターンに参加することで、成果を企業にアピールしやすくなります。
エントリーシートと筆記試験対策
理系のエントリーシートでは、研究テーマの要点を簡潔に伝える力が必要です。
専門用語を避けつつ、目的、課題、アプローチ、結果を明確にし、そこから得た学びやスキルを論理的に整理して記述しましょう。
また、SPIや玉手箱などの適性検査は、多くの企業で選考に用いられているため、早い段階から準備を進めることが重要です。
問題集を用いて解答スピードや正確さを磨き、対策を怠らないようにしましょう。
面接対策と実践
面接では、自分の研究内容をわかりやすく伝えることが鍵になります。
その際、研究の背景や目的、使用した手法、得られた結果、そこから得た学びなどを、専門外の面接官にも伝わるように構成することが求められます。
また、逆質問の場面では、企業の技術戦略や今後の展望に関する具体的な問いを用意し、興味と意欲を示しましょう。
大学のキャリアセンターなどを活用して模擬面接を実施し、客観的なフィードバックを受けることで、本番への備えを強化できます。
伝えたい内容を整理し、論理的かつ明快に伝える練習を繰り返すことが成功への近道です。
推薦応募と自由応募も検討しよう
理系学生には、学校推薦という選択肢が用意されていることが多く、内定の獲得率も高い傾向があります。
しかし、推薦は辞退が難しく、慎重に志望先を選ぶ必要があります。
一方で、自由応募では自ら複数の企業に挑戦できる自由度があり、自分の適性を幅広く試すことが可能です。
推薦と自由応募は、それぞれの特徴を理解し、自分の戦略に合った活用方法を見極めることが大切です。
【理系版就職ランキング】就職先を選ぶ上での重要ポイント
理系の就職活動では、自分の専攻やスキルをどれだけ活かせるかに加えて、働く環境や将来の展望も重要な判断材料になります。
企業によって重視する技術領域や文化は大きく異なり、自分に合わない企業を選んでしまうと早期離職やミスマッチの原因にもなります。
ここでは、理系学生が企業選びをする際に押さえておくべき5つの重要な観点を具体的に解説していきます。
ポイント1:専門性を活かせるか
理系学生にとって、大学や大学院で培った専門知識やスキルを入社後にどう活かせるかは企業選びの重要な軸になります。
研究内容と関係の深い分野であれば、業務理解が早く、自信を持って仕事に取り組むことができるため、早期に成果を上げやすい環境が整います。
また、企業が求めるスキルと自分が持っているスキルが合致しているかを見極めることで、入社後のミスマッチを減らすことにもつながります。
企業説明会や職種紹介ページなどを通じて、自分の専門分野がどのように業務に活かされているのかを具体的に確認しましょう。
ポイント2:ワークライフバランスを確認
理系の仕事は専門性が高く、プロジェクトによっては長時間労働になる場合もあります。
だからこそ、仕事と私生活のバランスをどの程度取れるかをあらかじめ確認しておくことが大切です。
企業によっては、残業時間が慢性的に長かったり、有給が取りづらかったりすることもあるため、実態に近い情報を集めるようにしましょう。
口コミサイトや四季報、会社説明会、OBOG訪問などを通じて、制度と運用のギャップを確認することが効果的です。
ポイント3:企業文化・社風との相性
理系の仕事はチームで進めることが多く、職場の人間関係やコミュニケーションスタイルが働きやすさに直結します。
企業ごとに組織風土は異なり、年功序列が強い会社もあれば、成果主義でフラットな環境を重視する企業もあります。
自分が働きやすいと感じる雰囲気と、企業が大切にしている価値観が一致しているかを見極めることが重要です。
特に、指示待ちではなく主体的に動ける人材を求めている企業では、積極性や柔軟性が評価されやすく、向いているタイプも変わってきます。
ポイント4:将来性・成長性のある業界であるか
いくら現在の業績や評判が良くても、将来にわたって安定的に成長できるかどうかは別の話です。
理系の技術は時代によって求められる分野が大きく変わるため、企業が変化に対応できる柔軟性や革新性を持っているかを見極める視点が求められます。
新技術への投資状況や研究開発体制、SDGsへの取り組みなどを通じて、社会課題への意識の高さや中長期的な事業展望を把握しましょう。
特に、AI、再生可能エネルギー、医療、ロボティクス、食品・健康といった分野は今後の成長が見込まれており、理系学生にとって注目すべき業界です。
ポイント5:研究制度・キャリアパスが充実しているか
理系職は技術の進化に追いつくためにも、常に学び続ける姿勢が求められます。
そのため、自分のスキルや知識を高められる教育制度が整っているか、明確なキャリアステップが提示されているかを確認しておくことが重要です。
OJTだけでなく、専門分野別の研修、語学トレーニング、資格取得支援、海外研修など、このような機会が多い企業では成長しやすい環境が整っています。
また、技術職からマネジメント職への転換や、専門性を極めるスペシャリスト制度など、複数のキャリアパスがある企業は自分の志向に合わせて将来を選べる点でも魅力です。
【理系版就職ランキング】大学院進学という選択肢
理系学生にとって、大学卒業後の進路をどう選ぶかは、人生における大きな分岐点となります。
学部卒で就職するか、それとも大学院に進学して専門性を高めるかで、その後のキャリアの選択肢や成長の方向性は大きく変わってきます。
どちらにも明確なメリットとデメリットがあり、自分の価値観や将来像に照らして慎重に判断する必要があります。
ここでは、大学院進学の利点と課題、そして学部卒との就職活動の違いについて詳しく解説していきます。
大学院進学のメリット
大学院では、学部時代よりもさらに専門分野に深く踏み込み、自身の研究テーマに集中的に取り組むことができます。
これにより、企業の研究開発職など高度な専門性を必要とする職種への道が開かれやすくなり、技術者としての自信と実力が身につきます。
また、院卒者は初任給やキャリアスタートの位置が学部卒より高めに設定されることも多く、昇進スピードにも差が出るケースがあります。
研究を通して、課題設定から仮説構築、実験と分析、考察と発表という一連のプロセスを繰り返すことで、論理的思考や問題解決能力が大きく鍛えられます。
さらに、国内外の学会に参加したり、論文を発表する中で、将来のキャリアに活かせる研究者ネットワークが広がる点も、大学院ならではの強みです。
大学院進学のデメリット
一方で、大学院進学には注意すべきデメリットも存在します。
まず、修士課程で2年、博士課程であれば5年近く、社会に出る時期が遅れることになります。
同年代の学部卒と比べて経済的な自立が後ろ倒しになり、収入格差やライフプランに影響が出る可能性もあります。
また、大学院生活では学費に加えて生活費も自己負担となるため、奨学金やアルバイトで補う必要があり、経済的な負担は無視できません。
さらに、研究活動そのものも順調に進むとは限らず、実験結果が出ない、論文が通らないといった壁に直面することもあります。
精神的に追い詰められる場面もあるため、粘り強く取り組む姿勢と、自ら課題を乗り越える力が求められます。
大学院卒と学部卒の就職活動の違い
大学院卒と学部卒では、企業が求める人物像に明確な違いがあります。
院卒者に対しては、より実務に近い専門知識の習得や、自律的に研究を進めてきた経験を評価する傾向が強く、入社後も即戦力としての働きが期待されます。
一方、学部卒はポテンシャル採用の意味合いが強く、基礎知識と将来の成長性に重きを置かれることが多いです。
入社後の研修やOJTで丁寧に育てる前提のため、主体性や人柄、柔軟性が評価の軸になります。
選考時期に関しては、現在では学部・院の差は以前ほど見られませんが、専門職では院卒向けの早期選考や推薦枠が用意されている場合があります。
どちらが良いというわけではなく、自分の強みや価値観に合った選択をすることが何より大切です。
【理系版就職ランキング】理系学生がアピールできる強みとは
理系学生が就職活動において強みをアピールする際には、大学や大学院で培ってきたスキルや姿勢を、実体験に基づいて明確に伝えることが大切です。
研究や実験、専門科目の履修など、日々の学びの中には企業が高く評価する力が多く含まれています。
ここでは、理系出身者が持つ代表的な強みと、それを効果的に伝えるためのポイントを具体的に紹介していきます。
論理的思考力と問題解決能力
理系の学習や研究では、物事の因果関係を捉え、筋道を立てて思考する能力が自然と鍛えられます。
また、実験や解析の過程で予期せぬ問題に直面したときに、その原因を突き止め、試行錯誤を重ねながら解決に導く力も培われます。
これらの力は、企業における業務改善やトラブル対応、設計開発などあらゆる場面で求められます。
アピールの際には、自分が実際にどのような課題に直面し、どのような考え方や手順で問題を解決したかを順を追って説明しましょう。
論理の流れが明確に伝われば、再現性のある実務能力として高く評価される可能性が高まります。
探究心・知的好奇心
理系学生の多くは、現象やデータの背景にある本質を深く理解したいという知的好奇心を持っています。
研究や授業の中で得た知識に対して疑問を抱き、自ら調べたり、追加の実験を行ったりといった自主的な行動ができる人材は、企業にとって非常に魅力的です。
この探究心は、単に情報を受け取るだけでなく、問いを立てて学びを深める姿勢として評価され、研究開発や技術職の現場で高く求められる資質でもあります。
自己PRでは、「なぜそうなるのかを深く掘り下げた経験」「自身でテーマを設定して行動に移した事例」を用いて、具体的に示しましょう。
主体的に知識を広げていく力があることを伝えることがポイントです。
仮説思考とデータ分析能力
理系の研究では、仮説を立て、検証に必要なデータを収集し、客観的な分析をもとに考察を行うというサイクルが基本となっています。
この経験から、事実と仮説を分けて考える力や、数値をもとに論理的な結論を導き出す能力が自然と養われます。
企業においても、売上分析、品質改善、業務効率化などあらゆる業務でこの力が活かされる場面が多く存在します。
アピールする際は、どのような仮説を立て、どのようなデータを扱い、どんな分析手法を用いたかを整理して話すと説得力が増します。
結果として得られた気づきや意外な展開があれば、それも加えることで応用力の高さを印象づけることができます。
粘り強さ
研究活動では、失敗や行き詰まりがつきものであり、思い通りに進まない状況に直面することも少なくありません。
その中で粘り強く試行錯誤を続け、原因を突き止め、成果に結びつけていく経験は、理系ならではの価値ある強みです。
粘り強さは、トラブル発生時に冷静に対応できることや、長期的なプロジェクトでも諦めずに取り組む姿勢として企業から高く評価されます。
自己PRでは、失敗から何を学び、どのように行動を変えたかということや、どれだけの時間や工夫を重ねて乗り越えたかということを丁寧に描写することが重要です。
困難を乗り越えた経験は、仕事における信頼性や責任感の強さを裏付けるエピソードとなります。
【理系版就職ランキング】就職関連でよくある質問
理系学生の就職活動には、文系とは異なる疑問や不安がつきものです。
ここでは、理系就活生が抱えやすい質問をまとめ、就職活動を成功に導くためのヒントを解説します。
文系就職は可能?
結論から言うと、理系学生が文系職種に就くことは十分に可能です。
理系で培った「論理的思考力」「課題解決能力」「データ分析能力」は、業界や職種を問わず非常に高く評価されるスキルだからです。
具体的には、複雑な問題を構造的に捉え、解決策を導き出す能力が活かせるコンサルタント、数学や統計学の知識が直接的に役立つ金融業界、データを基にした分析や戦略立案で強みを発揮できるマーケティング職などが挙げられます。
面接では、なぜ文系職種を希望するのかを明確に説明し、理系での経験がどのように活かせるかを論理的にアピールすることが重要です。
単に「文系職に興味がある」だけでなく、「研究で培った分析能力を活かして、企業のマーケティング戦略を立案したい」といったように、具体的な将来像を提示することで、採用担当者に納得感を与えられます。
研究が忙しくて就活できないときは?
研究が忙しくて就活が進まないというのは、多くの理系学生が抱える共通の悩みです。しかし、研究と就活の両立は十分に可能です。
まず、スケジュールの早期管理が鍵となります。
就活の本格的なスタート時期から逆算して、面接対策や企業研究の時間を確保しておきましょう。
次に、研究室の先生や先輩に相談することも有効です。
過去の先輩たちの経験を聞いたり、先生に就活の時期を考慮してもらうよう相談してみましょう。
また、推薦制度の活用は多忙な理系学生にとって大きなメリットです。
教授推薦や学校推薦は、選考プロセスが短縮されることが多いため、効率的に就活を進められます。
さらに、最近ではWeb面接やWebテストなど、オンライン選考の活用も増えています。
移動時間を削減できるため、時間を有効に使って選考に臨むことができます。
これらの方法を組み合わせることで、研究と就活の両立を目指しましょう。
ホワイト企業の見分け方
「ホワイト企業」の定義は人それぞれですが、理系学生が特に重視すべきポイントは以下の通りです。
まず、有給取得率や平均残業時間です。
これらは企業の働きやすさを示す重要な指標であり、企業の公式サイトや就職情報サイトで確認できます。また、離職率の低さも重要なポイントです。
定着率が高い企業は、社員が働きやすい環境である可能性が高いと言えます。
次に、企業の文化や実態を知るためには、口コミサイトやOB・OG訪問が最も信頼できる情報源となります。
実際に働いている社員の生の声を聞くことで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
最後に、理系学生ならではの視点として、研究開発投資の状況も確認しましょう。
研究開発への投資額が大きい企業は、将来性が高く、理系人材を大切にしていると考えられます。
これらの要素を総合的にチェックすることで、自分にとっての「ホワイト企業」を見つけることができるでしょう。
【理系版就職ランキング】まとめ
理系学生が持つスキルや特性は、どの業界でも重宝される普遍的な強みです。
この記事を参考に、理系ならではの価値を、自信を持って発信していきましょう。