
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
大学3年生必見!! 「学業で力を入れたこと」特化の無料作成ツールを配布中
『学業で力を入れたこと』が書けずに悩んでいましたが、AIが強みを診断してくれたおかげで、自信を持ってESを提出できました。第一志望から内定をいただけました!
4つの質問に答えるだけで自己PRとガクチカの文章が完成!業界に合わせた内容で、面接でも高評価をいただきました。就活に必須のツールです。
学業やアルバイト、大学で忙しく、ESを書く時間が取れない!
「学業で力を入れたこと」は就職活動で重要ですが、何を書けばいいのか悩むことが多いですよね。
そこでおすすめしたいのが、「『学業で力を入れたこと』ES・履歴書で差がつくツール!」です。このツールを使えば、4つの質問に答えるだけででAIが自動的にあなただけの文章を作成してくれます。アイデア不足や時間のない就活生にはぴったりです!(web完結)
このツールを活用して、あなたの過去経験をしっかり伝える文章を手軽に作成しましょう。
4つの質問であなただけの文章を作成!
今すぐ作成(無料)
学業で力を入れたこと(ゼミ)
私が学生時代に最も力を入れたことは、〇〇ゼミでのグループ研究において、先行研究では解明されていなかった現象を明らかにし、研究成果を学会で発表、奨励賞を受賞したことです。〇〇ゼミでは、各自が設定した研究テーマに基づき、主体的に研究活動を進めることが求められました。私は、以前から関心のあった〇〇について、先行研究の不足を痛感しており、この機会にそのメカニズムを解明したいと考えました。しかし、研究を進める上で、十分なデータや情報が得られず、仮説の構築すら難しい状況に直面しました。そこで、私はまず、関連分野の論文を徹底的に調査し、知識の基盤を構築することに注力しました。毎日3時間以上、過去の論文や最新の研究動向を分析し、不足している情報を補うことに努めました。さらに、研究の進捗状況や課題について、週に一度、〇〇教授に壁打ちを依頼し、専門的なアドバイスや新たな視点を取り入れることで、研究の方向性を修正しました。その結果、独創的な視点と論理的な考察が評価され、学会発表において奨励賞を受賞することができました。この経験を通して、困難な状況でも諦めずに課題解決に取り組む姿勢、そして、論理的思考力と分析能力の重要性を学びました。これらの経験を活かし、変化の激しいIT業界において、常に新しい知識を吸収し、論理的な思考力で課題を解決できるエンジニアとして貢献したいと考えています。
大学3年生必見!! 「学業で力を入れたこと」特化の無料作成ツールを配布中
『学業で力を入れたこと』が書けずに悩んでいましたが、AIが強みを診断してくれたおかげで、自信を持ってESを提出できました。第一志望から内定をいただけました!
4つの質問に答えるだけで自己PRとガクチカの文章が完成!業界に合わせた内容で、面接でも高評価をいただきました。就活に必須のツールです。
学業やアルバイト、大学で忙しく、ESを書く時間が取れない!
「学業で力を入れたこと」は就職活動で重要ですが、何を書けばいいのか悩むことが多いですよね。
そこでおすすめしたいのが、「『学業で力を入れたこと』ES・履歴書で差がつくツール!」です。このツールを使えば、4つの質問に答えるだけででAIが自動的にあなただけの文章を作成してくれます。アイデア不足や時間のない就活生にはぴったりです!(web完結)
このツールを活用して、あなたの過去経験をしっかり伝える文章を手軽に作成しましょう。
4つの質問であなただけの文章を作成!
今すぐ作成(無料)
学業で力を入れたこと(ゼミ)
私が学生時代に最も力を入れたことは、〇〇ゼミでのグループ研究において、先行研究では解明されていなかった現象を明らかにし、研究成果を学会で発表、奨励賞を受賞したことです。〇〇ゼミでは、各自が設定した研究テーマに基づき、主体的に研究活動を進めることが求められました。私は、以前から関心のあった〇〇について、先行研究の不足を痛感しており、この機会にそのメカニズムを解明したいと考えました。しかし、研究を進める上で、十分なデータや情報が得られず、仮説の構築すら難しい状況に直面しました。そこで、私はまず、関連分野の論文を徹底的に調査し、知識の基盤を構築することに注力しました。毎日3時間以上、過去の論文や最新の研究動向を分析し、不足している情報を補うことに努めました。さらに、研究の進捗状況や課題について、週に一度、〇〇教授に壁打ちを依頼し、専門的なアドバイスや新たな視点を取り入れることで、研究の方向性を修正しました。その結果、独創的な視点と論理的な考察が評価され、学会発表において奨励賞を受賞することができました。この経験を通して、困難な状況でも諦めずに課題解決に取り組む姿勢、そして、論理的思考力と分析能力の重要性を学びました。これらの経験を活かし、変化の激しいIT業界において、常に新しい知識を吸収し、論理的な思考力で課題を解決できるエンジニアとして貢献したいと考えています。
目次[目次を全て表示する]
そもそも学業で力を入れたこととは
学業で力を入れたこととは、就職活動のエントリーシートや面接において頻繁に問われる質問項目です。
これは学生時代に力を入れたこと、いわゆるガクチカの中でも、特に勉強面、例えば授業やゼミ、研究などに焦点を当てたものを指します。
企業は成績の良し悪しそのものよりも、あなたが課題に対してどのように考え、行動したかというプロセスを知りたいと考えています。
学業への取り組み方を通じて、あなたの物事に対する姿勢や思考力を見極めようとしています。
学業で力を入れたこととガクチカの違い
ガクチカとは、学生時代に力を入れたことの略称であり、学業、アルバイト、サークル活動など、学生生活における幅広い経験全体を指す言葉です。
一方で、学業で力を入れたこととは、そのガクチカの中でも特に勉強面に限定したテーマを指します。
もし企業側から学業について教えてくださいと明確に指定された場合は、学業に関するエピソードを選ぶ必要があります。
つまり、学業はガクチカという大きな枠組みの中に含まれる、一つの専門カテゴリであると理解してください。
採用担当者が学業で力を入れたことを聞く4つの理由
採用担当者が学業で力を入れたことを質問するには、明確な意図が存在します。
単に成績やGPAの高さを知りたいだけではありません。
むしろ、その取り組み方やプロセスを通じて、学生の潜在的な能力や人柄を評価しようとしています。
この質問の裏には、入社後に活躍できる人材かを見極めるための重要な視点が隠されています。
ここでは、企業がこの質問をする4つの主な理由について、具体的に解説していきます。
①人柄や価値観が自社と合うか確認
企業は、あなたがどのような学問に興味を持ち、なぜそれに力を入れたのかという動機を知りたがっています。
その選択の背景には、あなたの根本的な価値観や人柄が強く反映されるためです。
例えば、地道な研究を好むのか、チームでの議論を好むのかといった特性は、仕事への向き合い方にも通じます。
採用担当者は、その学生が持つ価値観や人柄が、自社の社風やチームの雰囲気と合っているかどうか、いわゆるカルチャーフィットを判断しています。
②目標達成までの思考プロセスを評価
GPAの高さや優秀な成績といった結果そのものよりも、企業が重視するのはそこに至るまでの過程です。
設定した目標に対し、どのような課題があり、それをどう分析したのか。
そして、その課題を乗り越えるために、どんな計画を立てて行動したのか。
この一連の思考プロセスや課題解決能力は、仕事においてもそのまま活きる能力です。
企業は、入社後も主体的に考え、困難な業務を遂行できる人材かどうかを、このプロセスから評価しています。
③培ってきた専門性のレベルを測る
特に理系の職種や専門職を募集する場合、大学で学んだ知識が業務に直結することが多々あります。
そのため、採用担当者は学生がどの程度の専門性や基礎知識を身につけているのか、そのレベルを測ろうとします。
文系の場合でも、例えば法学や経済学といった特定の分野を深く探究した経験は、論理的思考力や情報収集能力の高さを示す証拠となります。
学生が大学時代に何をインプットしてきたのか、その質と深さを確認しています。
④分かりやすく伝える能力があるか見極める
どんなに高度な研究や深い学びを得ていても、その内容を専門外の人に分かりやすく説明できなければ、ビジネスの現場では活かせません。
採用担当者は、多くの場合あなたの専門分野の素人です。
学生が自分の取り組んだ学業の内容を、専門用語に頼らず、相手の知識レベルに合わせて簡潔に説明できるかどうかを見ています。
この論理的な伝達能力は、社内での報告や顧客への提案など、あらゆる仕事で必要とされる基本的なスキルです。
採用担当者が学業で力を入れたことで評価する4つの基準
企業が学業で力を入れたことを聞く理由を理解したら、次に知るべきは具体的な評価基準です。
採用担当者はあなたの回答から、自社で活躍できる素養があるかを見極めようとします。
この評価基準は、主に4つの視点で構成されています。
単に事実を話すのではなく、これらの基準を満たしているかを意識して回答を準備することが、選考を通過するために非常に重要となります。
①自社の価値観や人柄とマッチしているかどうか
採用担当者は、あなたがなぜその学業に取り組んだのかという動機や背景に注目します。
その選択の裏には、あなたの興味の方向性や大切にしている価値観が表れるからです。
例えば、チームでの協力を重視する学生か、個人での探究を好む学生かといった人柄は、企業の社風と合うかどうかを判断する重要な材料となります。
この適合性、いわゆるカルチャーフィットは、入社後の定着や活躍に直結するため厳しく評価されます。
②主体的に工夫して行動できるかどうか
高い成績や結果そのものよりも、その成果を出すために「あなたが」どう考え、行動したかが評価されます。
授業や研究は受け身になりがちですが、その中で自ら目標を設定したり、困難な課題に対して独自の工夫を凝らしたりした経験が求められます。
採用担当者は、指示待ちではなく、自ら考えて行動できる主体性や課題解決能力を持っているか。
その再現性をエピソードから判断しています。
③学んだことを分かりやすく説明できるかどうか
どんなに高度な専門知識や深い学びを得ていても、それを知らない相手に分かりやすく伝えられなければ、仕事では活かせません。
採用担当者は、あなたが自分の研究や学んだ内容を、専門外の相手にも理解できるように、論理立てて簡潔に説明できるかを評価します。
この伝達能力は、社内外でのコミュニケーションの基礎となるため、非常に重要な評価基準の一つです。
④入社後に活躍できる人材かどうか
最終的に、企業はこれら全ての基準を通じて、あなたが自社に入社した後、継続的に成果を出し、活躍できる人材かどうかを判断しています。
学業での課題の乗り越え方や物事への取り組み姿勢は、入社後に未知の業務や困難に直面した際の対応力を予測させます。
あなたのエピソードから、将来の伸びしろや貢献意欲、いわゆるポテンシャルを感じられるかどうかが、採用の可否を決める大きな基準となります。
学業で力を入れたことを書く前の3ステップ
エントリーシートをいきなり書き始めようとすると、内容が薄くなったり、伝えるべき点がぼやけたりしがちです。
説得力のある回答を作成するには、まず自分の経験を深く掘り下げ、アピールできる材料を整理する準備段階が不可欠です。
この作業を丁寧に行うことで、あなただけのエピソードが明確になります。
ここでは、具体的な経験を洗い出すための3つのステップを紹介します。
Step1. 何を頑張ったか洗い出す
最初のステップは、大学生活で学業に関連する経験を全て書き出すことです。
記憶だけに頼らず、成績表やシラバスを手元に用意すると効果的です。
授業、ゼミ、研究、資格取得など、少しでも印象に残っていることを大小問わずリストアップします。
この段階では、これがアピール材料になるかどうかを判断する必要はありません。
まずは質より量を意識して、候補をすべて洗い出すことに集中してください。
Step2. なぜ頑張ったかを明確にする
Step1で洗い出した経験の候補に対して、次はなぜそれに力を入れたのかという動機を深掘りします。
例えば、なぜそのゼミを選んだのか、なぜ苦手科目の克服を目指したのか、その背景にある理由を自問自答してください。
この動機こそが、あなたの主体性や価値観、人柄を伝える上で最も重要な核となります。
企業はこの部分から、あなたの物事に対する姿勢を読み取ろうとします。
Step3. どう頑張ったかを具体化する
動機が明確になったら、次はその目標や課題に対して、あなたが具体的にどう行動したのかを思い出します。
企業が最も知りたいのは、このプロセスです。
どんな困難があり、それを乗り越えるためにどのような工夫や努力をしたのかを書き出します。
この際、できるだけ数字を用いて客観的に表現することが重要です。
例えば、毎日3時間勉強した、参考書を5冊解いた、GPAが1.0向上した、といった具体的な指標を探してください。
学業で力を入れたことが本当にない場合の対処法
GPAが高くない、あるいは勉強よりもサークルやアルバイトに打ち込んできたため、学業でアピールできることが何もないと悩む学生は少なくありません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
企業はあなたの成績証明書を見たいのではなく、あなたの思考のプロセスや物事への取り組み姿勢を知りたいのです。
一見平凡に思える学生生活の中にも、アピールにつながる要素は必ず隠れています。
ここでは、視点を変えて自分だけのエピソードを見つけ出すための、具体的な5つの対処法を紹介します。
見つけ方①:学業は成績だけではない
多くの学生が陥りがちなのが、学業を成績やGPAの数値だけで判断してしまうことです。
しかし、企業が評価するのは結果そのものよりも、そこに至るまでのプロセスです。
例えば、目標単位取得のために計画を立てて実行した計画性や、図書館に毎日通い続けた継続力、グループワークで議論をまとめた調整力なども、立派な学業への取り組み姿勢です。
まずは、学業イコール成績という思い込みを捨てることが、エピソード発見の第一歩となります。
見つけ方②:苦労した授業を思い出す
優秀な成績を収めた経験よりも、むしろ単位取得に苦労した経験の方が、あなたの強みをアピールできる場合があります。
例えば、苦手意識があった科目や、再履修の末に単位を取った授業を思い出してください。
重要なのは、その困難な状況、つまり課題に対して、あなたがどのように考え、行動したかです。
友人に教えを請うた、教授に粘り強く質問した、独自の勉強法を編み出したなど、課題を乗り越えたプロセスは、課題解決能力の強力な証明となります。
見つけ方③:地道な継続をアピールする
授業に休まず出席した、予習復習を欠かさなかったなど、一見当たり前に思える行動も、継続していれば立派なアピールポイントになります。
特に、アルバイトやサークル活動と両立させながら、学業をおろそかにしなかった事実は、自己管理能力や真面目さ、継続力を示すものです。
多くの学生が疎かにしがちなことを地道に続けた経験は、入社後に仕事へ真摯に取り組む姿勢を連想させ、企業からも高く評価されます。
見つけ方④:唯一熱中できた分野を探す
大学の成績全体で見れば平凡でも、特定の分野や科目に対してだけ、強く興味を持って取り組んだ経験はないでしょうか。
それは専門科目である必要はなく、一般教養の授業でも構いません。
なぜその分野に熱中できたのか、興味を持ってどのように探究したのかを深掘りします。
例えば、関連する書籍を何冊も読んだ、自主的に現地へ足を運んだなど、その行動力はあなたの探究心や好奇心の強さを示すエピソードになります。
見つけ方⑤:授業以外の学習経験を洗い出す
企業が知りたい学びの姿勢は、必ずしも大学の授業内に限定されません。
もし授業でのエピソードが見つからなくても、授業外での学習経験を洗い出してみましょう。
例えば、資格取得のために計画的に勉強した経験、TOEICのスコアアップ、プログラミングの独学、オンライン講座の修了なども、立派な学業の取り組みです。
その際は、なぜ大学の勉強とは別にそれ学ぼうと思ったのか、その主体的な動機も合わせて説明することが重要です。
今から取り組める学業で力を入れたことのテーマ5選
これまでの経験を振り返っても、どうしてもアピールできるエピソードが見つからないと焦る学生もいるかもしれません。
特に就職活動まで時間がある1、2年生や、時間に余裕が生まれた3年生であれば、今から意識的に学業に取り組むことで、それをガクチカとして語ることも可能です。
重要なのは、結果よりもそのプロセスです。
ここでは、今からでも間に合う、ガクチカとしてアピールしやすい具体的なテーマを5つ紹介します。
最も成果が分かりやすく、計画性もアピールできるテーマが資格取得です。
例えば、簿記やITパスポート、FP技能士、TOEICのスコアアップなど、1か月から3か月程度の短期間で結果が出せる目標を設定します。
重要なのは、なぜその資格を選んだのかという動機と、合格や目標スコア達成のために、どのような学習計画を立てて実行したかというプロセスです。
その過程で工夫した点や努力した点を具体的に説明できるように記録しておきましょう。
大学の授業では学べない、より実務的なスキルを学ぶ姿勢は、企業から高く評価されます。
プログラミングやデータ分析、Webデザイン、デジタルマーケティングなど、多くのオンライン学習サービスが存在します。
自分が興味のある分野や、志望する業界で役立ちそうな講座を一つ選び、最後まで修了することを目標にします。
なぜそのスキルを学ぼうと思ったのかという主体的な動機と、学んだことを活かして簡単な制作物などを作ってみると、より説得力が増します。
低コストで始められ、自身の探究心や継続力をアピールできる方法です。
自分の専門分野や、興味のある特定のテーマ、例えばAIやマーケティングなどを一つ決めます。
そして、その分野に関連する書籍を10冊読む、といった具体的な目標を立てます。
ただ読むだけでなく、1冊ごとに内容を要約し、自分の考えや考察をノートにまとめる習慣をつけると、インプットした知識を論理的に整理する能力も同時にアピールできます。
最も身近なテーマであり、自身の成長ストーリーを語りやすい方法です。
これまでの成績が平凡であったとしても、例えば今履修している特定の科目でA評価、すなわち優を目指すと決めます。
なぜその科目を選んだのか、そして目標達成のためにどのような行動を起こしたのかが重要です。
予習復習の徹底、教授への質問、プラスアルファのレポート提出など、具体的な工夫を言語化できるように意識して取り組みましょう。
多くの大学では、キャリアセンターや各学部が主催する、通常の授業とは別の特別講座やセミナーが開催されています。
例えば、ビジネススキル講座や業界研究セミナー、リーダーシッププログラムなどです。
これらに主体的に参加することも、学びへの意欲を示す行動となります。
単に参加したという事実だけでなく、その講座で何を学び、それをどのように自分なりに解釈し、今後の学生生活やキャリアに活かそうと考えたのかを説明できるように準備しておきましょう。
学業で力を入れたことのテーマ一覧
学業で力を入れたことのテーマは、必ずしも学会発表のような華々しい実績である必要はありません。
企業は学生がどのような課題に対し、どう取り組んだかというプロセスを重視しています。
そのため、授業への取り組みやゼミ活動、資格取得など、学びに関する経験はすべてがテーマになり得ます。
ここでは、学生の属性別に、アピールしやすい定番のテーマを一覧にして紹介します。
文系(学部生)向け
文系の学部生の場合、理系のような実験スキルよりも、情報収集能力や論理的思考力、課題特定能力などが評価される傾向にあります。
日々の授業やゼミ活動、卒業論文の執筆過程において、どのように物事を考え、議論を深めていったのかをアピールすることが重要です。
ここでは、文系の学生がエピソードとして使いやすい具体的なテーマ例を紹介します。
ゼミ活動は、文系学生にとってアピールの宝庫です。
チームでの研究発表やディベートの経験は、協調性や論理的思考力を示す良い材料となります。
例えば、意見が対立した際にどのように議論を調整したか、リーダーとしてどのような役割を果たしたか、あるいは難解な文献をどう分かりやすく要約して発表したかなど、具体的なプロセスを深掘りしてみましょう。
卒業論文は、大学4年間の学びの集大成です。
テーマ設定の動機から、膨大な先行研究や文献の調査、フィールドワークやアンケートの実施、そして教授との粘り強い議論まで、すべてのプロセスがエピソードになります。
特に、研究が行き詰まった際にどのように課題を乗り越え、論文を完成させたかという計画性や実行力は、高く評価されるポイントです。
必修科目やゼミの活動以外でも、特定の専門分野に強く惹かれ、自主的に探究した経験も立派なテーマです。
例えば、法学部の学生が特定の判例について深く研究した、経済学部の学生が独自にデータを分析した、といった経験です。
なぜその分野に興味を持ったのかという動機と、どのように知識を深めていったのかという主体的な行動をアピールできます。
グローバル化が進む現代において、語学学習への取り組みは多くの企業で評価されます。
TOEICのスコアを目標設定して達成した経験や、毎日オンライン英会話を継続した経験などが挙げられます。
重要なのは結果としてのスコアだけでなく、目標達成のためにどのような学習計画を立て、どう継続したかというプロセスです。
なぜ語学力が必要だと考えたのか、その目的意識も明確にしましょう。
留学経験は、語学力向上だけでなく、主体性や環境適応能力を示す絶好のテーマです。
単に楽しかった思い出を語るのではなく、文化や価値観の違いに直面し、それをどのように理解し乗り越えたのかという具体的なエピソードが求められます。
見知らぬ土地で自ら課題を見つけ、主体的に行動した経験は、入社後の活躍を期待させる材料となります。
入学当初は成績が振るわなかった学生が、明確な目標を持ってGPAを大幅に向上させた経験は、課題解決能力のアピールになります。
なぜ成績を上げようと決意したのかという動機、そして従来の勉強法をどう見直し、具体的にどのような行動に変えたのかというプロセスが重要です。
結果としての数値だけでなく、目標達成に向けた姿勢の変化を具体的に伝えましょう。
理系(学部生)向け
理系の学部生には、文系学生に求められる論理的思考力に加え、実験や研究活動を通じた粘り強さ、仮説検証能力、そして正確性などが期待されます。
机上の学習だけでなく、実際に手を動かして課題に取り組んだ経験が重視されます。
研究室での日常的な活動や、チームでの製作物など、理系ならではのプロセスを具体的に伝えることが効果的です。
研究活動において、実験が計画通りに進むことは稀です。
多くの場合、失敗と試行錯誤の繰り返しとなります。
企業が知りたいのは、まさにその部分です。
なぜ実験が失敗したのか原因を分析し、新たな仮説を立て、再度検証するという一連のプロセスは、論理的思考力と粘り強さの証明となります。
何十回も条件を変えて挑戦し、最終的にデータを取得した経験は、強力なアピール材料です。
卒業研究では、実験やシミュレーションによって得られた膨大な量のデータを扱うことになります。
そのデータ群から何が言えるのか、どのような法則性や傾向が隠されているのかを論理的に考察した経験は、分析能力のアピールにつながります。
単にグラフを作成したという事実だけでなく、データと向き合い、自分なりの解釈を導き出すためにどのような思考を巡らせたのかを具体的に説明しましょう。
工学部の学生などによく見られる、チームで一つのものを作り上げた経験も、学業における優れたテーマです。
例えば、プログラミングのチーム開発や、設計コンテストへの参加などが挙げられます。
個人としての技術的な貢献に加え、チーム内での役割、意見が対立した際の調整、スケジュール管理など、目標達成に向けて協働したプロセスは、協調性や実行力を示すエピソードとなります。
大学の実験や演習では、時には答えのない、あるいは非常に難解な課題が出されることがあります。
その未知の課題に対し、どのように情報を収集し、計画を立て、実行に移したのかというプロセスは、問題解決能力をアピールする上で有効です。
教授や先輩の助けを借りることも含め、周囲を巻き込みながら課題をクリアした経験は、仕事における積極的な姿勢として評価されます。
大学の授業で学ぶ知識は基礎であり、最先端の技術は日々更新されています。
そのため、授業とは別に、自分の専門分野に関連する最新の技術論文や専門書を自主的に読み、知識をインプットし続けた経験は、高い学習意欲や探究心を示すものとして評価されます。
なぜその知識が必要だと考えたのかという動機と、継続的に学んだ事実を具体的に伝えましょう。
大学院生(修士・博士)向け
大学院生には、学部生よりも深い専門性と研究への主体性が求められます。
単に知識をインプットするだけでなく、自ら課題を設定し、研究を通じて新たな知見を生み出すことが期待されます。
そのため、企業は研究の「成果」そのものよりも、その研究を遂行する過程で発揮された「思考力」や「粘り強さ」を高く評価します。
学部生との違いを意識し、研究の深さとそのプロセスを明確に伝えることが重要です。
学会発表は、自分の研究成果を外部の専門家に向けて発信し、評価を受ける貴重な機会です。
企業は、その準備プロセスや当日の対応を評価します。
研究内容を限られた時間で分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力や、専門家からの鋭い質問や批判に対して論理的に応答した経験は、高い専門性と説明能力、そして精神的な強さを示す強力なエピソードとなります。
修士論文や博士論文の執筆は、大学院での研究活動の集大成です。
このプロセスは、単なる文章作成ではなく、膨大な情報を整理し、論理的な一貫性を持たせて再構築する高度な知的作業です。
テーマ設定から始まり、先行研究の調査、データの分析、そして考察まで、一つの論文を書き上げたという事実は、論理的思考力、分析能力、そして最後までやり遂げる遂行能力の証明となります。
学会誌への論文投稿は、自分の研究が客観的な評価基準を満たしていることを示す強力な証拠となります。
論文が受理されるまでには、専門家による厳格な査読(ピアレビュー)を経る必要があります。
この過程で、批判的なフィードバックを受けて何度も修正を重ねた経験は、自身の研究を客観視する能力と、目標達成に向けた粘り強さ、打たれ強さを示します。
研究活動の核となるのが、仮説検証のプロセスです。
研究テーマに行き詰まった際、ゼロベースで問題点を見直し、新たな仮説を立て、それを証明するために実験や調査の方法を設計・実行した経験は、まさに仕事における課題解決のプロセスそのものです。
この試行錯誤の経験は、入社後に直面するであろう未知の課題に対する問題解決能力をアピールする材料となります。
研究室に所属する大学院生は、後輩の学部生に対して研究の進め方や実験方法を指導する機会も多いでしょう。
これは、自身の研究を進めるのとは異なるスキルが求められます。
相手の理解度に合わせて複雑な内容を分かりやすく説明する伝達能力や、後輩のモチベーションを管理しながらチーム全体の成果向上に貢献した経験は、リーダーシップやマネジメントの素養として高く評価されます。
【ES/履歴書編】学業で力を入れたことの7段階構成
エントリーシートや履歴書で学業について記述する際は、伝えるべき情報を整理し、論理的な順序で構成することが重要です。
読み手である採用担当者に、あなたの経験と強みが正確に伝わるよう、分かりやすい流れを意識する必要があります。
ここでは、あなたの取り組みを効果的に伝えるための基本となる、7段階の構成について解説します。
この型に沿って内容を整理することで、説得力のある文章を作成できます。
作成後はこちらで紹介しているような添削ツールを使って添削することで精度や選考通過率が高まります。
1. 結論「何に力を入れたか」
まず最初に、あなたが学生時代に何に力を入れたのかを簡潔に述べます。
例えば、ゼミの研究活動です、あるいは特定の専門科目の習得です、といった形です。
この結論を冒頭に示すことで、採用担当者は文章全体のテーマを即座に把握できます。
話の要点を先に提示することは、ビジネスにおける基本的なコミュニケーション手法でもあり、論理的な思考力を示すことにもつながります。
2. 動機「なぜ取り組んだか」
次に、あなたがなぜその活動に力を入れようと思ったのか、その動機や背景を説明します。
例えば、純粋な知的好奇心から、あるいは将来の目標に必要だと考えたから、といった理由です。
この動機部分には、あなたの価値観や物事に対する主体性が表れます。
どのような考えを持って行動を開始したのかを明確にすることで、エピソードに深みとあなたらしさが加わります。
3. 課題「どんな困難や目標があったか」
動機を述べたら、その活動に取り組む上で直面した具体的な困難や、自身で設定した目標について記述します。
例えば、実験が思うように進まなかった、あるいはGPAを2.5から3.5に上げるという目標を立てた、などです。
この課題設定を明確にすることで、次の行動への説得力が生まれます。
どのような状況下で行動したのかを具体的に示す、重要なステップです。
4. 行動「課題や目標に対して何をしたか」
設定した課題や目標に対し、あなたが具体的にどのような工夫や努力をしたのかを記述します。
ここは、あなたの主体性や思考プロセスをアピールする最も重要な部分です。
例えば、失敗の原因を分析するために教授に毎週質問に行った、あるいは勉強方法を根本から見直し、友人と勉強会を企画した、などです。
事実を淡々と述べるのではなく、あなた独自の取り組みを明確にしましょう。
5. 結果「行動の結果どうなったか」
あなたの行動が、どのような結果につながったのかを客観的に示します。
可能な限り、数字や具体的な事実を用いて表現することが望ましいです。
例えば、実験が成功し学会発表につながった、あるいは目標としていたGPA3.5を達成できた、などです。
この結果は、あなたの行動が正しかったことの証明となります。
もし大きな成果でなくても、行動によって起きた変化を誠実に記述しましょう。
6. 学び「経験から何を学んだか」
一連の経験を通じて、あなたが何を得たのか、どのようなスキルが身についたのかを言語化します。
例えば、粘り強く仮説検証を繰り返す重要性を学んだ、あるいは計画的に物事を進める力を習得した、などです。
この学びの部分は、あなたの成長の証であり、再現性のある能力を示すことにつながります。
結果だけでなく、経験を内省し、自身の糧としている姿勢をアピールします。
7. 展望「入社後にどう活かすのか」
最後に、その経験から得た学びやスキルを、入社後にどのように活かしていきたいかを述べます。
学んだことを、志望する企業の業務に結びつけて具体的に説明することが重要です。
例えば、研究で培った課題解決能力を、貴社の製品開発において活かしたい、といった形です。
これにより、採用担当者はあなたが自社で活躍する姿を具体的にイメージでき、採用するメリットを感じることができます。
【面接編】1分で伝える学業で力を入れたことの構成(PREP法)
面接で学業について回答する際は、1分程度で簡潔にまとめるよう指示されることがよくあります。
1分間は文字数にすると約300字であり、エントリーシートの文章をそのまま読み上げると時間超過になる可能性が高いです。
面接は対話の場であるため、詳細をすべて話すのではなく、相手に要点を分かりやすく伝えることが重要です。
このような場面では、PREP法と呼ばれる構成が非常に有効です。
これは、結論、理由、具体例、結論の順で話す手法で、短時間で論理的に伝えることができます。
Point(結論)何に力を入れたか
まず最初に、エントリーシートと同様に結論から述べます。
私が学業で力を入れたことは、〇〇です、と簡潔かつ明確に断言してください。
面接官は、あなたが何について話そうとしているのかを即座に理解したいと考えています。
ここで時間をかけると、話の全体像が掴みにくくなります。
スピーチの目安としては、最初の10秒程度でこの結論を伝え終えるのが理想です。
Reason(動機)なぜそれを選んだか
次に、なぜそれに力を入れようと思ったのか、その理由や動機を端的に説明します。
例えば、〇〇という課題を感じたからです、あるいは〇〇という分野に強い興味を持ったからです、といった形です。
この部分は、あなたの価値観や主体性を示す重要なポイントとなります。
しかし、ここでは詳細に語りすぎず、次の具体例につながるキッカケとして、10秒程度で簡潔にまとめることを意識してください。
Example(エピソード)どう乗り越えたか
話の中核となるのが、この具体例、すなわちエピソードです。
エントリーシートで記述した、課題、行動、結果の部分を、30秒程度の短いストーリーとして要約します。
例えば、〇〇という困難がありましたが、私は〇〇と工夫して取り組み、その結果〇〇となりました、という流れです。
あなたの人柄や能力が最も伝わる部分であるため、練習を重ねて、最も伝えたいプロセスを凝縮して話せるように準備しましょう。
Point(貢献)入社後どう活かすか
最後の締めくくりとして、再び結論に戻ります。
この経験から得た学びを、入社後にどう活かせるのかを具体的に述べてください。
この経験で得た〇〇という力を、貴社(御社)の〇〇という業務で活かしたいと考えております、といった形で、未来への貢献意欲を示します。
この最後のPointが、あなたの熱意と将来性を伝える重要なメッセージとなります。
全体のバランスを考え、10秒程度で力強く締めくくりましょう。
NEW!!『あなたのガクチカ』に対する深掘り質問生成ツール【完全無料】
ガクチカの深掘り対策を徹底して行いたい就活生必見!
この度、DigmediaからAIの最新ツールとして、「AIガクチカ深掘り質問ツール」をリリースいたしました。
「あなたのガクチカ」に特化した面接での想定質問を最低でも15個以上生成できます。
完全無料で利用できるため、ぜひ、ガクチカの対策に活用してみてください!
学業で力を入れたことを差別化する5つのポイント
多くの就活生が「学業で力を入れたこと」をアピールするため、平凡な内容では採用担当者の印象に残りません。
あなたの経験をより魅力的に伝え、他の候補者と差をつけるためには、伝え方に工夫が必要です。
ここでは、あなたのエピソードを際立たせ、評価を高めるための「加点」テクニックを5つ紹介します。
これらのポイントを意識するだけで、あなたの回答はより具体的に、より説得力のあるものへと変わります。
①取り組んだ目的や動機を明確にする
なぜその学業を選び、力を入れたのかという目的意識や動機は、あなたの価値観や人柄を伝える上で非常に重要です。
単に単位を取るためといった受け身の理由ではなく、知的好奇心から、あるいは将来の目標に必要だと考えたから、といった主体的な動機を明確にしましょう。
この目的意識こそが、あなただけのエピソードの土台となり、行動全体に説得力を持たせる源泉となります。
②数字と感情を盛り込む
エピソードにリアリティを持たせるために、客観的な事実である数字と、主観的な感情を盛り込むことが効果的です。
例えば、GPAが1.0向上した、という数字に加え、なぜそこまで頑張れたのか、その時の悔しさや達成感といった感情を添えます。
数字は努力の客観的な証拠となり、感情はあなたの人間的な魅力を伝えます。
この二つが組み合わさることで、エピソードはより深く印象に残ります。
③アピールしたい要点を一つに絞る
400字程度の限られた文字数で、継続力も課題解決力もアピールしようとすると、結局どちらの印象も薄れてしまいます。
そのエピソードを通じて、あなたが最も伝えたい強み、例えば粘り強さなのか、分析力なのか、要点を一つに絞りましょう。
一つの強みに焦点を当て、それに関連するプロセスを深く掘り下げることで、採用担当者にあなたの核となる能力を明確に印象づけることができます。
④学びを企業の求める人物像につなげる
企業は、あなたの経験が自社でどう活かせるかを知りたがっています。
経験から得た学びを、応募先企業が求める人物像や具体的な業務内容に意図的に結びつけることが重要です。
例えば、研究で培った分析力を、貴社のデータ分析業務で活かせます、といった形です。
この視点を持つことで、あなたの経験が単なる学生時代の思い出ではなく、入社後に貢献できるスキルの証明となります。
⑤主体性が伝わる動詞を選ぶ
文章の印象は、末尾の動詞によって大きく左右されます。
例えば、ゼミに参加しました、ではなく、ゼミを自ら企画しました、あるいは議論に積極的に貢献しました、といった言葉を選ぶだけで、あなたの主体性や積極性が格段に伝わります。
受け身な表現を避け、あなたがどのように考え、動いたのかが伝わる能動的な動詞を選ぶことで、行動力のある人材として高く評価されます。
【例文25選】学業で力を入れたこと(文系・理系・テーマ別)
ここでは、学業で力を入れたことの具体的な例文を25個紹介します。
文系、理系、大学院生といった属性別、またゼミ活動や成績向上、資格取得といったテーマ別に幅広く分類しました。
あなたの経験や状況に最も近い例文を探し、どのような構成で、どういった言葉で表現すれば効果的に伝わるのか、そのエッセンスをぜひ参考にしてください。
これらの例文はあくまで一例です。
丸写しするのではなく、あなた自身の言葉で表現を磨き上げるための土台として活用しましょう。
文系(学部生)の例文(8選)
文系学部生がアピールしやすい、8つのテーマ別例文を紹介します。
ゼミ活動や卒業論文、語学学習など、文系学生ならではの論理的思考力や探究心を示せる内容となっています。
ESの構成に沿って作成していますので、あなたの経験を当てはめて作成する参考にしてください。
私が学業で力を入れたことは、所属する国際政治ゼミでのグループ研究です。
動機は、チームでの議論を通じて多角的な視点を養いたいと考えたからです。
当初、私たちのチームは先行研究の分析段階で意見が対立し、議論が停滞するという課題がありました。
そこで私は調整役として、各意見の共通点と相違点を整理し、全員が納得できる新たな研究の方向性を提案しました。
結果としてチームは結束し、学内発表会で最優秀賞を受賞できました。
この経験から、傾聴力と合意形成の重要性を学びました。
この強みを、貴社の営業職として顧客との関係構築に活かします。
卒業論文の執筆に最も力を入れました。
〇〇(テーマ名)について研究しましたが、その動機は現代社会の課題解決に貢献したいと考えたからです。
しかし、先行研究が非常に少なく、一次情報が不足しているという課題に直面しました。
そこで私は、従来の文献調査に加え、専門家10名へのインタビューを独自に企画・実行しました。
結果、実態に基づいた独自の考察を加えた論文を完成させ、教授から高い評価を得ました。
この経験から、主体的に課題を設定し、粘り強く解決策を実行する探究力を学びました。
この力を貴社の調査部門で活かしたいです。
TOEICのスコアアップに注力しました。
将来グローバルに活躍したいという動機から、入学時に500点だったスコアを800点以上に引き上げる目標を立てました。
課題はリスニング力の不足だと分析し、従来の勉強法を見直しました。
毎日1時間のシャドーイングと週末の模試を1年間継続する計画を立て、実行しました。
結果、スコアを810点まで伸ばすことができました。
この経験から、目標から逆算し、計画的に努力を継続する力を学びました。
この継続力を、貴社の海外事業部で発揮したいと考えています。
2年次にGPAを1.5向上させた経験です。
1年次はサークル活動に傾倒し、GPAが2.0と低迷しました。
このままでは専門知識が身につかないという危機感を抱いたのが動機です。
課題は学習効率の悪さにあると分析し、予習中心の学習スタイルへ切り替えました。さらに、授業中は最前列で質問することを徹底し、不明点を解消するよう努めました。
結果、2年次のGPAは3.5となり、成績優秀者として表彰されました。
課題を分析し、行動を改善する実行力を学びました。
この実行力を貴社の業務でも活かします。
1年間の交換留学経験です。
現地の学生と対等に議論し、多様な価値観を吸収したいという動機で挑戦しました。
しかし、当初は議論の速さについていけず発言できないという困難に直面しました。
そこで私は、毎日授業の録音を聞き返し、関連論文を3本読むことを自らに課しました。また、現地の友人に発表練習を手伝ってもらうなど、主体的に行動しました。
結果、最終学期には議論の中心となれるようになり、最高評価を得ました。
主体的に環境に適応し、臆せず行動する力を学びました。
この適応力を貴社の新規開拓営業で活かします。
簿記2級の取得です。
経済学部で学んだ知識を実務レベルで理解したいと考え、挑戦しました。
学習当初、特に工業簿記の理解が追いつかないという課題がありました。
そこで私は、半年の学習計画を立て、毎日2時間の勉強時間を確保しました。特に工業簿KIは参考書を3周解き、不明点は教授に質問に行くことで完全に理解しました。
結果、一度の受験で合格できました。
計画的に努力を継続する力を学びました。
この力を、貴社の経理部門で正確な業務遂行に活かしたいです。
必修科目であったマーケティングのグループワークに力を入れました。
チームでの成果を最大化したいという思いで臨みました。
しかし、私たちのチームは議論が拡散し、結論が出ないことが課題でした。
そこで私は書記兼調整役を自ら引き受け、まず議論のゴールと時間配分を明確にしました。議論中は各自の意見を可視化し、論点のズレを修正しました。
結果、チームの議論は効率化し、最終発表ではA評価を得られました。
傾聴力と調整力を学びました。
この力は、貴社のプロジェクト推進において活かせると考えます。
所属する法学部で、〇〇法(専門分野)の探究に力を入れました。
動機は、授業で扱った判例の結論に疑問を持ち、深く知りたいと考えたからです。
課題は、学部生レベルの知識では本質的な理解が難しいことでした。
そこで私は、自主的に関連する国内外の論文を15本読み込み、複数の教授のオフィスアワーを訪ねて議論を交わしました。
結果、その考察をまとめたレポートが教授に評価され、ゼミでの発表機会を得ました。
知的好奇心に基づき主体的に探究する姿勢を学びました。
この探究心を貴社の企画業務で活かします。
理系(学部生)の例文(7選)
理系学部生の強みである、論理的思考力や粘り強さを示せる7つのテーマ別例文を紹介します。
研究室での実験やグループ製作など、理系学生ならではの経験をESの構成に沿って記述しています。
あなたの経験を当てはめて作成する参考にしてください。
研究室での実験に最も力を入れました。
新しい材料の合成を試みましたが、動機は誰も成功していない課題に挑戦したいと考えたからです。
しかし、当初は理論通りに合成が進まず、失敗を繰り返す日々が続きました。
課題は反応条件の最適化にあると考え、温度、圧力、触媒の3つの変数を設定し、50回以上の試行錯誤を行いました。
結果、微量ながらも目的の材料を合成することに成功しました。
この経験から、粘り強く仮説検証を繰り返す重要性を学びました。
この姿勢を貴社の研究開発職で活かします。
卒業研究に力を入れました。
〇〇(テーマ名)に関する研究で、動機は指導教授から最も難易度が高いと聞いていたためです。
研究当初、実験データに一貫性がなく、再現性が取れないという困難に直面しました。
そこで私は、全ての実験手順をゼロから見直し、装置の微細な誤差が原因であると突き止めました。
装置の調整と手順の厳格化を行った結果、安定したデータを取得でき、学会での発表につなげられました。
課題の原因を特定し、地道に解決する力を学びました。
工学部でのグループ製作課題に力を入れました。
動機は、個人のスキルを結集させて一つの製品を作り上げるプロセスを学びたかったからです。
4人チームで自動走行ロボットを製作しましたが、途中でメンバー間の進捗に差が出てしまい、計画が遅延しました。
私はリーダーとして、各々の得意分野を再確認し、タスクを再配分しました。また、週に一度の進捗会議を設け、情報共有を徹底しました。
結果、期限内にロボットを完成させ、コンテストで入賞できました。
チームの力を最大化する調整力を学びました。
プログラミングの自主学習に力を入れました。
情報工学科に所属していますが、授業の知識だけでは実務で通用しないと考えたのが動機です。
当初は、一つのエラーを解決するのに半日かかるなど、効率の悪さが課題でした。
そこで私は、毎日3時間の学習時間を確保し、オンライン講座を活用して基礎を徹底的に固めました。さらに、学んだ知識で簡単な在庫管理アプリを開発し、知人の店で試してもらいました。
結果、実践的なスキルが身につきました。
主体的に学び、実践する力を学びました。
この力を貴社のSEとして活かします。
所属する研究室でのデータ解析作業に力を入れました。
動機は、膨大なデータから意味のある知見を引き出す能力を身につけたかったからです。
当初は、教授から渡された過去の実験データを分析しても、既知の結論しか導き出せないことが課題でした。
そこで私は、統計学の専門書を3冊読破し、新たな分析手法である〇〇(手法名)を独学で導入しました。
結果、従来は見過ごされていた新たな相関関係を発見し、教授から高く評価されました。
知識を主体的に学び、実行に移す力を学びました。
3年次の専門科目の成績向上に力を入れました。
動機は、1、2年次に基礎科目の理解が曖昧なまま進級してしまい、専門分野の学習についていけないという危機感を覚えたからです。
課題は基礎知識の欠如にあると考え、専門科目の学習と並行して、1年次の教科書を全て復習する計画を立てました。
不明点は友人に聞くだけでなく、教授のオフィスアワーを活用して徹底的に解消しました。
結果、3年次の専門科目は全てA評価を得られました。
課題を特定し、愚直に努力する力を学びました。
専門分野の最先端知識のインプットに力を入れました。
動機は、大学の教科書で学ぶ知識が既に古くなっている分野であり、常に最新情報を追う必要があると考えたからです。
課題は、英語論文への苦手意識でした。
そこで私は、毎日1本、海外の最新論文を読むことを自らに課し、重要な単語や表現をノートにまとめ続けました。
結果、半年前は3時間かかっていた論文読解が1時間で可能になり、研究にも活かすことができました。
主体的に学び続ける姿勢を学びました。
この姿勢を貴社の技術開発でも貫きます。
大学院生の例文(5選)
大学院生には、学部生よりも深い専門性と、研究を主体的に遂行した能力が求められます。
ここでは、学会発表や論文投稿など、大学院生ならではの高度な経験をアピールする例文を5つ紹介します。
研究プロセスにおける思考力や課題解決能力を、ESの構成に沿って具体的に記述しています。
学業で力を入れたことは、国際学会での研究発表です。
動機は、自分の研究成果を海外の専門家に評価してもらい、議論を通じて内容を深めたいと考えたからです。
課題は、専門外の聴衆にも研究の新規性と意義を分かりやすく伝えることでした。
そこで私は、専門用語の使用を最小限に留め、研究背景や社会的重要性を丁寧に説明する資料構成を心掛けました。また、想定問答を50個作成し、発表練習を徹底しました。
結果、多くの質問者から研究の意義が伝わったと評価されました。
この経験から、複雑な内容を簡潔に伝える力を学びました。
学術論文の投稿に最も力を入れました。
自身の研究成果の新規性を客観的に証明したいという思いから挑戦しました。
しかし、投稿した論文は査読者から厳しい指摘を受け、一度は掲載不可(リジェクト)となりました。
課題は論理の飛躍とデータ不足にあると分析し、半年間かけて追加実験を行い、論理構成をゼロから見直しました。
結果、修正論文は別の学会誌に受理(アクセプト)されました。
この経験から、批判を糧にして粘り強く成果を改善する力を学びました。
この精神力で、貴社の困難な業務にも貢献します。
研究における仮説検証プロセスに力を入れました。
私の研究テーマは従来の手法では解明されておらず、新たなアプローチが必要でした。
当初立てた仮説が実験で何度も否定され、研究は半年間行き詰まりました。
そこで私は、前提を疑い、関連分野の論文を50本読み直すことで、全く新しい仮説を構築しました。実験系も自ら設計し直した結果、仮説を実証するデータを取得できました。
この経験から、固定観念にとらわれず、ゼロベースで思考する力を学びました。
この思考力を貴社の課題解決に活かします。
研究室での後輩(学部生)指導に力を入れました。
動機は、私自身が学部生時代に指導で苦労した経験から、チーム全体の研究効率を上げたいと考えたからです。
当初、後輩は実験ミスが多く、モチベーションの低下が見られました。
私は一方的に教えるのではなく、週1回のミーティングを設定し、後輩の理解度や悩みを聞き出すことから始めました。その上で、実験マニュアルを一緒に見直し、改善しました。
結果、後輩が主体的に研究に取り組むようになり、チームの研究が加速しました。
傾聴を通じて相手の成長を支援する力を学びました。
自身の研究技術を社会課題の解決に結びつける試みに力を入れました。
〇〇(社会課題)の現状を知り、私の研究がその解決に役立つのではないかと考えたのが動機です。
課題は、研究室レベルの技術であり、実用化にはコストや安定性の面で多くの壁があることでした。
そこで私は、実用化を想定した低コスト化と安定性の向上を新たな目標に設定し、追加実験を行いました。
結果、実用化には至りませんでしたが、新たな可能性を示すデータを取得できました。
専門性を社会のニーズと結びつけて考える視点を学びました。
その他共通の例文(5選)
学部や専攻を問わず、多くの学生が参考にできる共通のテーマ別例文を5つ紹介します。
例えば、実習経験や独学でのスキル習得、あるいはGPA(成績)に関する取り組みなどです。
これらはすべて、あなたの学習姿勢や課題解決能力をアピールする立派なエピソードとなります。
ESの構成に沿って記述していますので、あなた自身の経験に置き換えて作成する際の参考にしてください。
学業で力を入れたことは、3週間の教育(または看護)実習です。
動機は、大学で学んだ理論を現場で実践し、自身の適性を見極めたいと考えたからです。
実習当初は、知識を一方的に伝えることに終始してしまい、生徒(または患者)との信頼関係が築けないという課題がありました。
そこで私は、担当教員(または指導者)に毎日フィードバックを求め、相手の立場に立ったコミュニケーションを徹底的に心掛けました。
結果、実習最終日には、生徒(または患者)から感謝の言葉をもらうことができました。
この経験から、傾聴と状況に応じた柔軟な対応力を学びました。
この力を貴社(または貴院)の業務でも活かします。
データ分析スキルの独学に力を入れました。
動機は、所属する経済学部での学びを、より実証的に深めたいと考えたからです。
当初の課題は、統計学の知識が皆無で、何から学べば良いか分からなかったことでした。
そこで私は、まず統計検定3級の取得を目標に設定し、オンライン講座で基礎を徹底的に学びました。
さらに、学んだ知識を活かし、大学の課題レポートで積極的にデータ分析を取り入れました。
結果、統計検定に合格し、レポートもA評価を得られました。
主体的に目標を設定し、計画的に学ぶ力を習得しました。
GPAを2年次から3年次にかけて1.0向上させた経験です。
動機は、1年次にサークル活動に没頭し、GPAが1.8と低迷したことに強い危機感を覚えたからです。
課題は、非効率な学習習慣にあると分析しました。
そこで私は、サークル活動と両立させるため、通学時間に予習を終える、授業後は必ず図書館で2時間復習するなど、時間管理を徹底しました。
結果、3年次のGPAは2.8となり、学業と課外活動の両立を実現できました。
課題を分析し、行動を改善する実行力を学びました。
この実行力を貴社の業務でも活かします。
全ての授業で最前列に座り、質問をすることを徹底しました。
動機は、大学の学費を払ってくれている両親のためにも、知識を最大限吸収したいと考えたからです。
当初は、人前で質問することにためらいがあり、勇気が出ませんでした。
そこで私は、授業前に予習を徹底し、疑問点を3つ用意しておくという準備を自らに課しました。
結果、授業の理解が深まっただけでなく、教授からも熱心だと評価され、良い関係を築けました。
この経験から、主体的に行動する積極性を学びました。
この積極性を貴社の営業職でも発揮したいです。
4年間を通じてGPA3.5以上を維持したことです。
動機は、学業を学生の本分と考え、全ての科目において高いレベルで知識を習得したいと入学時に決意したからです。
課題は、学年が上がるにつれて専門性が高まり、学習負荷が増大したことでした。
そこで私は、各科目のシラバスを分析し、四半期ごとに詳細な学習計画を立て直しました。
また、友人との勉強会を主催し、知識のアウトプットを徹底することで理解を深めました。
結果、GPA3.6を維持し卒業できました。
目標に対し、計画的に継続努力する力を学びました。
学業で力を入れたことでの注意点とNG例文
学業で力を入れたことのエピソードが良くても、伝え方一つで評価は大きく下がってしまいます。
多くの就活生が陥りやすい、注意すべき書き方が存在します。
ここでは、評価を下げる代表的な5つの注意点について、具体的なNG例文と、それをどのように改善すればよいかをセットで解説します。
これらのポイントを避けるだけで、あなたのエントリーシートは格段に読みやすくなります。
①結果や成績だけを報告する
企業が知りたいのは、GPAや資格取得といった結果そのものではありません。
その結果を出すために、あなたがどのように考え、どのような工夫や努力をしたのか、そのプロセスこそを評価しています。
単に事実や成果だけを報告しても、あなたの人柄や課題解決能力は伝わりません。
取り組みの背景や行動を具体的に記述することが不可欠です。
私が学業で力を入れたことは、成績の向上です。
入学当初はGPAが2.0でしたが、3年次にはGPA3.8まで上げることができました。
この経験で、努力すれば結果が出ることを学びました。
この例文では、GPAが向上したという事実しか分かりません。
なぜ成績を上げようと思ったのかという動機や、具体的にどのような勉強法を実践したのかという行動が抜け落ちています。
GPA2.0という課題に対し、どのように学習計画を見直し、実行したのか、そのプロセスを詳細に記述することで、あなたの主体性や課題解決能力をアピールできます。
②専門用語を多用しすぎる
特に理系学生や大学院生に多く見られる注意点です。
自身の研究内容を熱心に伝えようとするあまり、専門用語を多用してしまうケースです。
しかし、採用担当者はあなたの専門分野の素人であることがほとんどです。
どれほど高度な研究であっても、その内容が相手に伝わらなければ評価につながりません。
自己満足な説明になっていないか、常に意識する必要があります。
私は〇〇(専門分野)の研究室で、△△(専門的な手法)を用いた××(専門用語)の最適化に取り組みました。
従来の××では不可能だった△△を実現し、学会でも評価されました。
これでは、採用担当者はあなたが何をしたのか全くイメージできません。
専門用語は、その分野を知らない中学生にも分かるような言葉に置き換える工夫が必要です。
例えば、その研究が社会のどのような課題を解決できるのか、どのような点で新しいのか、その本質的な意義を平易な言葉で説明するだけで、あなたの伝達能力は高く評価されます。
③動機が受け身である
取り組みの動機が受け身であると、あなたの主体性や意欲が伝わりません。
例えば、必修科目だったから、あるいは友人に誘われたから、といった理由は、あなたが自ら考えて行動したことを示せません。
企業は、指示されたことだけをこなす人材ではなく、自ら課題を見つけて行動できる人材を求めています。
動機は、あなたの価値観を示す重要な要素です。
私が力を入れたのは、必修科目であった〇〇(授業名)のグループワークです。
単位取得が難しいと聞いていたため、メンバーと協力して必死に取り組み、なんとかA評価を得ることができました。
単位取得が目的では、やらされ感が拭えません。
必修科目であったという事実は変えられなくても、その中で自分なりにどのような目的意識を持ったのかを記述すべきです。
例えば、必修科目の中でも特に〇〇という点に興味を持ち、チームの成果を最大化するためにリーダーに立候補した、など、主体的な姿勢に焦点を当てて書き直しましょう。
④学びが抽象的すぎる
エピソードの締めくくりとして、学んだことを記述することは重要です。
しかし、その学びが抽象的すぎると、あなたの成長が具体的に伝わりません。
代表的な例が、コミュニケーション能力を学んだ、という表現です。
これだけでは、あなたが具体的に何ができるようになったのか、その能力がどう仕事に活きるのか、採用担当者は判断できません。
ゼミ活動での議論を通じて、私は協調性を学びました。
この経験を活かして、貴社でもチームワークを大切にして貢献したいです。
協調性という言葉が何を指すのか不明瞭です。
例えば、意見の異なるメンバー間の調整役を果たした経験から、対立する意見を整理し、合意点を導き出す調整力を学んだ、というように具体化する必要があります。
抽象的な言葉を避け、どのような場面で、誰に対して発揮できる能力なのかを明確にすることで、あなたの強みとして説得力を持ちます。
⑤嘘や過度な誇張を書く
自分を良く見せたいという気持ちから、経験を過度に誇張したり、嘘のエピソードを創作したりすることは、絶対にしてはいけません。
採用担当者は、何百人もの学生を見ているプロです。
エントリーシートの段階では通過できたとしても、面接での深掘り質問によって、話の辻褄が合わなくなり、必ず見抜かれます。
信頼を失えば、評価は最低となり、取り返しがつきません。
私は独学でプログラミングを学び、AIを用いた画期的な株価予測システムを開発しました。
その結果、ゼミの仲間全員が投資で大きな利益を上げることに成功しました。
このような非現実的な成果は、すぐに疑いの対象となります。
面接で、システムの具体的な仕組みや、利益に関する詳細な質問をされれば、答えることはできないでしょう。
0を100に見せる必要はありません。
平凡な経験であっても、1を10に見せる工夫、つまり、その経験から何を考え、どう行動したのかというプロセスを深掘りする方が、よほど高い評価につながります。
学業で力を入れたことに関するよくある質問
ここでは、学業で力を入れたことにまつわる、就活生が抱きがちな細かい疑問や不安について回答します。
GPAが低い場合や、文字数指定への対応など、具体的なケースを想定した対処法を知っておくことで、自信を持ってエントリーシートや面接に臨むことができます。
GPAが低い(1点台・2点台)のですが、正直に書くべきですか?
はい、正直に伝えるべきです。 多くの企業は成績証明書の提出を求めるため、GPAについて嘘をつくことはできません。 重要なのは、低いという事実を認めた上で、その理由や背景を説明できるかです。 例えば、他の課外活動に注力していた、あるいは途中から挽回するためにどのような努力をしたか、というV字回復のエピソードを語るなどです。 低いことを隠すよりも、その状況から何を学び、どう行動を改善したかを伝える方が建設的です。
勉強以外(サークル・バイト)を頑張ったのですが、どう答えるべきですか?
企業から学業で力を入れたことと明確に指定された場合、サークルやアルバイトの話をメインにするのは、質問の意図から外れてしまいます。 まずは、勉強以外の活動に注力した事実を認めつつも、その中で学業に関して少しでも工夫した点、例えば単位取得のために計画的に時間管理をした、といったエピソードを探しましょう。 もし学業でのアピールが難しい場合は、正直に学業以外に注力した理由を述べ、学業においても最低限の責任は果たしたと説明する方法もあります。
文字数(200字・400字・600字)ごとの書き分け方は?
基本は記事で紹介した7段階の構成を用います。 400字が標準的な構成を全て盛り込める長さです。 200字の場合は、動機や展望を簡潔にし、結論、課題、行動、結果という最も重要なプロセスに絞って記述します。 600字の場合は、7段階の構成を全て含めた上で、特に動機となった価値観や、課題の深刻さ、そして行動の具体的な工夫を詳細に描写します。 文字数が増えるほど、エピソードの背景やあなたの思考プロセスを厚くするイメージです。
複数のエピソードがある場合、どれを選ぶべきですか?
エピソードを選ぶ基準は二つあります。 一つ目は、あなたの強み、例えば課題解決能力や継続力などが最も明確に表れているエピソードを選ぶことです。 二つ目は、応募先企業の求める人物像に、あなたの学びが最も合致するエピソードを選ぶことです。 例えば、協調性を重視する企業には、個人研究よりゼミのグループワークを選ぶ方が効果的です。 成績の高さやテーマの派手さではなく、プロセスを最も具体的に語れるものを選んでください。
「学業」と「学業以外」の両方を聞かれたらどうしますか?
これは、あなたの多面性やバランス感覚を知りたいという企業の意図があります。 この場合、必ずそれぞれ別のエピソードを用意してください。 例えば、学業ではゼミの研究で培った論理性や探究心をアピールし、学業以外ではサークル活動で発揮したリーダーシップや協調性をアピールするなど、異なる側面を見せることが理想です。 両方を聞かれることを想定し、学生生活全体を振り返ってバランス良くエピソードを準備しておくことが重要です。
学業で力を入れたことのまとめ
学業で力を入れたことは、あなたの成績証明書を見たいのではなく、あなたが物事にどう向き合うかという姿勢、すなわちプロセスを知るための質問です。
企業は、あなたが課題に直面した際に、それをどう分析し、どう考え、どのような工夫をして行動したのかを知りたいと考えています。
平凡な経験だと感じていても、この記事で紹介した見つけ方や構成に沿って深掘りすれば、あなただけの具体的なエピソードが必ず見つかります。
大切なのは、あなた独自の思考と行動を、自信を持って伝えることです。



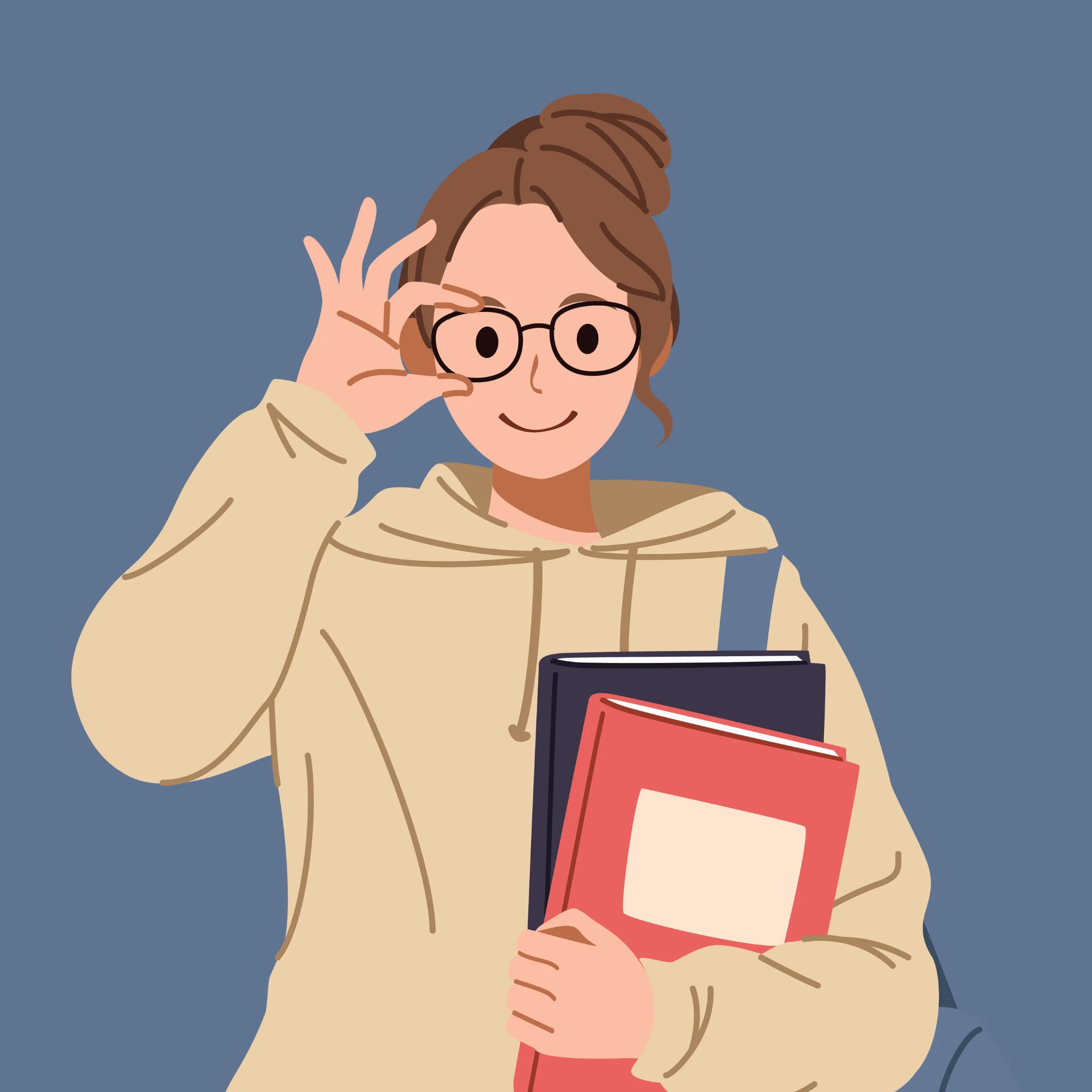

_720x550.webp)
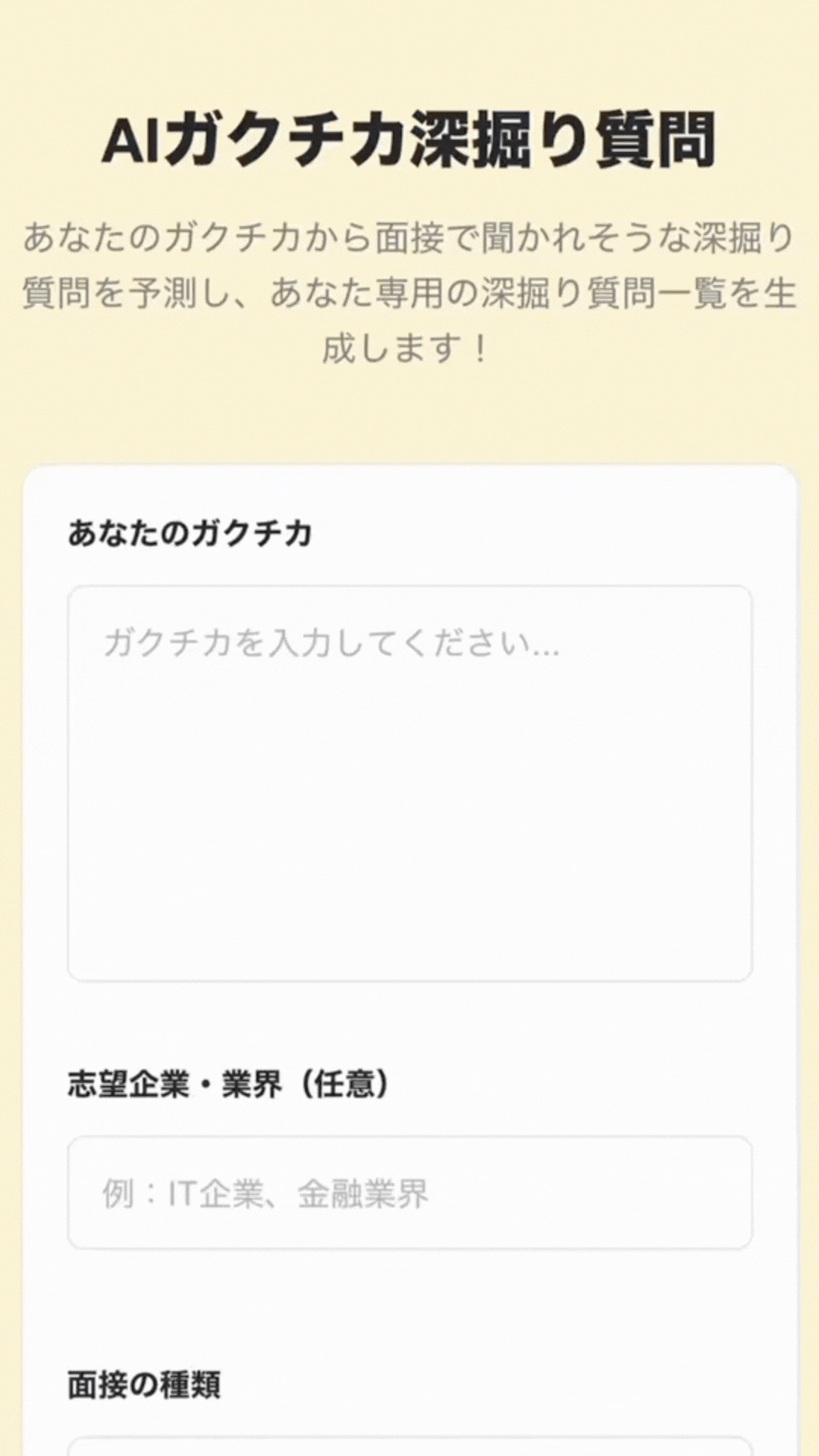
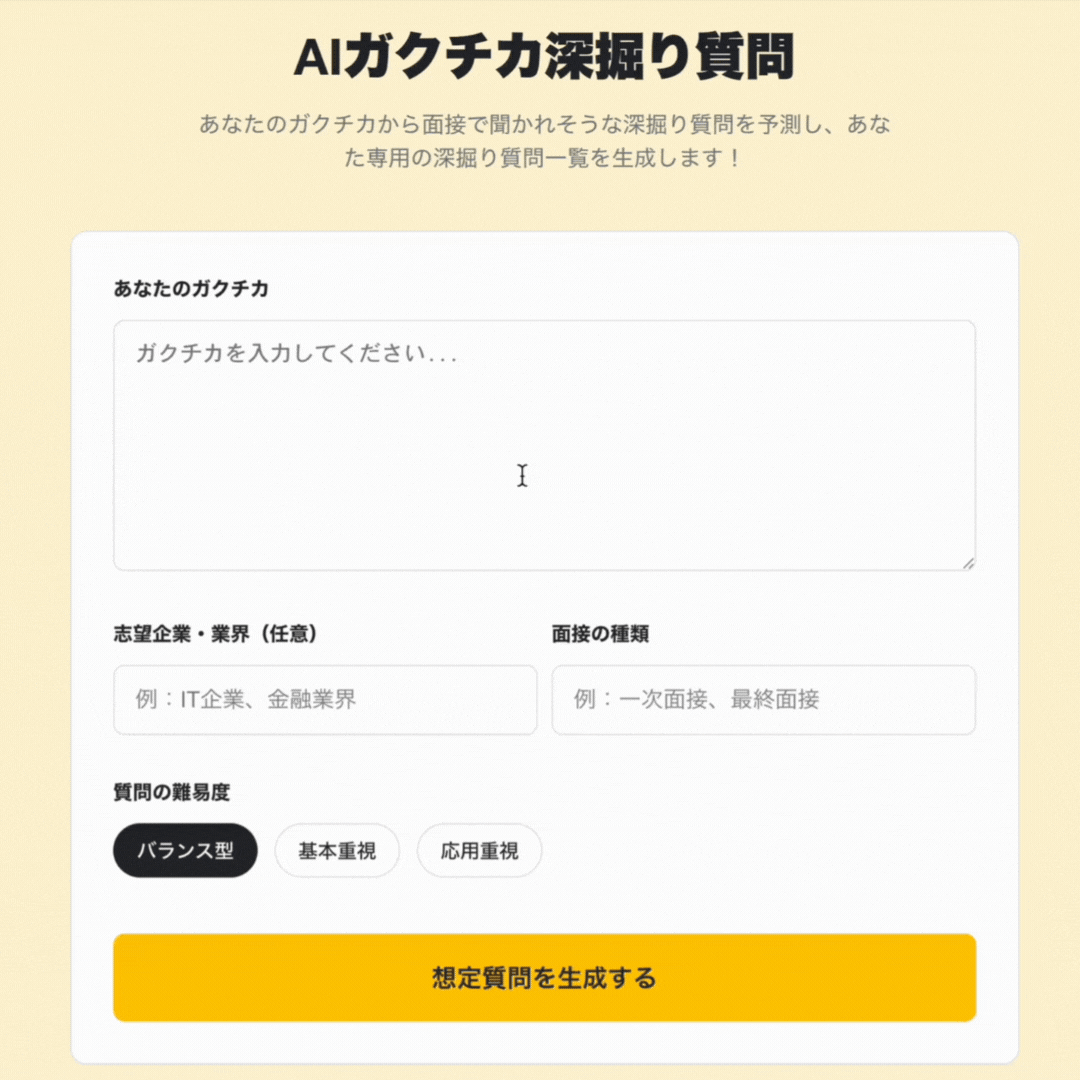







_720x550.webp)

_720x550.webp)






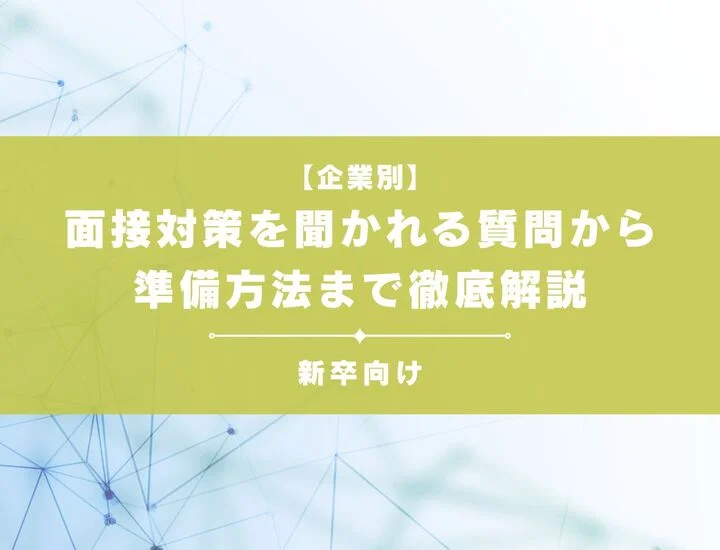





伊東美奈
(Digmedia監修者/キャリアアドバイザー)
伊東美奈
(Digmedia監修者)
そもそも自己分析が浅いと選考通過率は低い
このような準備ステップ、つまり自己分析が不十分だと、エントリーシートの内容は誰でも書けるような平凡なものになってしまいます。
自分の強みや行動特性を深く理解していない回答は、採用担当者の印象に残りません。
なぜ自分がその行動を取ったのかを明確に説明できないため、説得力に欠けてしまいます。
選考通過率を高めるためには、こうした地道な自己分析の作業が不可欠です。