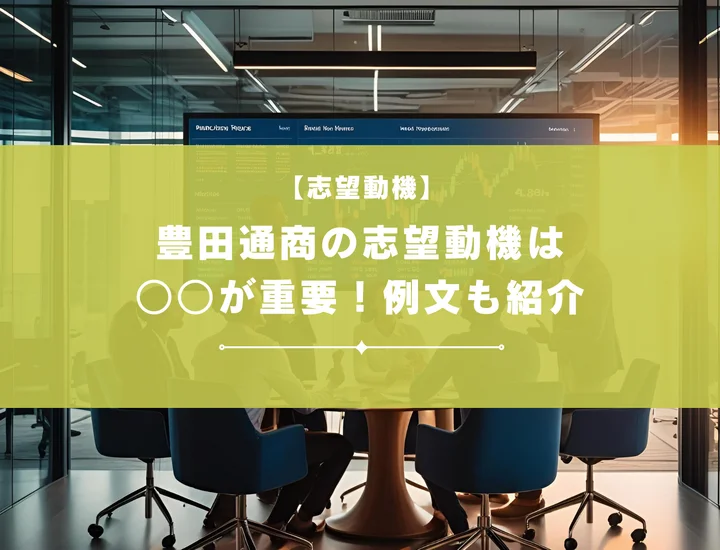HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
シンクタンクは、社会や経済が直面する複雑な課題を解き明かし、未来への羅針盤を示す「知の拠点」として、知的好奇心旺盛な新卒就活生から絶大な人気を誇ります。
その仕事は、国の政策や大企業の経営戦略に影響を与えるなど、極めて社会的インパクトが大きいものです。
その分、選考は最難関。
数多の優秀なライバルに差をつけ、内定を勝ち取るためには、論理的で、熱意にあふれ、かつ自分ならではの視点が盛り込まれた、説得力のある志望動機が不可欠です。
本記事では、シンクタンクの選考を突破するための志望動機の作り方を、基礎から応用まで徹底的に解説します。
【シンクタンク志望動機】シンクタンクってなに?
シンクタンクは、直訳すれば「頭脳集団」。
その名の通り、経済学、社会学、工学、国際関係論など、多様な分野の専門家(研究員)が集結し、社会や経済が抱える様々な課題について調査・分析を行い、その解決策や未来への提言を中立的な立場から社会に発信する研究機関です。
主な業務内容
シンクタンクの根幹をなす業務は、官公庁や地方自治体、国内外の民間企業など、幅広いクライアントからの依頼に基づき、専門的な調査・分析(リサーチ)を行うことです。
例えば、「再生可能エネルギーの導入促進に向けた政策シミュレーション」や「特定地域の人口減少に対する経済的影響の分析」といったテーマについて、膨大な文献調査、統計データの解析、専門家へのヒアリングなどを通じて、客観的なエビデンスを積み上げます。
そして、その結果を基に、現状の問題構造を明らかにし、将来の予測や政策の選択肢などを詳細なレポートにまとめ、提言します。
近年では、この高度なリサーチ能力を活かし、民間企業の経営戦略立案や新規事業開発を支援するコンサルティング業務も増加しており、リサーチとコンサルティングの両輪で社会の知的基盤を支えています。
コンサルとの違い
シンクタンクとコンサルティングファームは、「クライアントの課題を解決する」という点で共通していますが、その主眼とする領域やアプローチに違いがあります。
一般的な戦略コンサルが「民間企業の個別の経営課題」、例えば「売上を3年で2倍にするにはどうすればよいか」といったテーマに焦点を当て、クライアントの収益向上に直接的にコミットするのに対し、シンクタンクは「日本全体の労働生産性を向上させるにはどうすべきか」といった、より「社会全体が抱えるマクロな課題」の解決や政策提言を主眼とすることが多いです。
そのため、特定の企業の利益だけでなく、社会全体の利益を考慮した、より中立的・客観的な立場からの分析が求められ、公共性の高いテーマを扱うという大きな特徴があります。
【シンクタンク志望動機】就活生から人気が高い理由とは
極めて高い知性が求められるにもかかわらず、シンクタンクが優秀な就活生を惹きつけてやまないのには、明確な理由があります。
ここでは、その抗いがたい魅力の源泉を3つの側面から深掘りします。
業務の難易度が高い
シンクタンクが日常的に取り組むのは、年金制度改革、国際的なサプライチェーンの再編、最先端技術の社会実装といった、唯一の正解が存在しない複雑で難解なテーマばかりです。
前例のない課題に対して、膨大な情報の中から本質を見抜き、論理という糸で緻密なストーリーを紡ぎ上げていくプロセスは、知的好奇心をこの上なく刺激します。
常に最先端の知識をインプットし、自身の思考力を極限まで高めることが日常的に求められる環境は、知的な挑戦を通じて自己成長を実感したい学生にとって、最高の舞台と言えるでしょう。
昨日まで分からなかったことが分かるようになる、その連続がここにはあります。
サービス規模が大きい
シンクタンクの仕事は、単一の企業の利益を追求するだけに留まりません。
その提言は、国や業界全体の未来の方向性を左右するような、非常にスケールの大きなテーマを扱います。
自身が関わった調査レポートが、新たな法律の制定や、国家レベルの成長戦略の策定、あるいは業界全体の構造を変えるようなイノベーションのきっかけになることも少なくありません。
自分の仕事が、数多くの人々の生活や社会のあり方そのものに、ポジティブな影響を与えるという手触り感は、他の仕事では決して得られない、大きなやりがいと誇りになります。
社会貢献という言葉を、実感を持って体現したい学生にとって、これ以上ないほど魅力的なフィールドです。
専門性がある
シンクタンクでは、研究員一人ひとりが特定の分野におけるプロフェッショナルとして、深くキャリアを歩んでいきます。
経済、金融、IT、医療、環境、エネルギーなど、自身の強い興味や関心がある領域を徹底的に掘り下げ、その分野の第一人者として社会に認知されることを目指せます。
大学や大学院での研究テーマをさらに発展させ、社会実装に繋げたい、あるいは特定の社会課題をライフワークとして解決に取り組みたい、という明確な目標を持つ学生にとって、その専門性を日々高めながら社会に価値を提供できる環境は、理想的なキャリアパスと言えるでしょう。
【シンクタンク志望動機】求める人物像とは
知の殿堂とも言えるシンクタンクで活躍するためには、一体どのような資質が求められるのでしょうか。
企業が特に重視する4つの人物像について、具体的に解説します。
課題解決能力
シンクタンクの仕事の根幹は、混沌として見える事象を構造的に分解し、問題の真因、すなわち課題の本質を見抜くことにあります。
そのためには、物事を客観的なデータや事実に基づいて冷静に分析する力、そして、前提を疑い、筋道を立てて思考を組み立てる論理的思考力(ロジカルシンキング)が不可欠です。
仮説を立て、情報を収集し、検証を繰り返し、より精度の高い結論を導き出すという、一連の科学的なアプローチを、どんな困難な状況でも粘り強く遂行できる能力が、全ての基本となります。
困難も楽しめる柔軟性
シンクタンクが挑む社会課題には、教科書に載っているような唯一絶対の正解は存在しません。
先行研究や信頼できるデータが乏しい未開の領域で、五里霧中の中、手探りで進まなければならない場面も日常茶飯事です。
こうした先の見えない状況でも、悲観的になるのではなく、むしろ「まだ誰も答えを知らない」という状況を知的な探求の絶好の機会として前向きに楽しめるような、精神的なタフネスと柔軟性が重要です。
行き詰った時に、全く異なる角度から光を当てるような、思考のしなやかさが求められます。
プレゼンテーション能力
どれだけ優れた分析や深い考察を行っても、その価値がクライアントや社会に正しく、そして力強く伝わらなければ、それは自己満足に過ぎません。
自身の分析結果や政策提言を、その分野の専門家ではないクライアントや一般の人々にも分かりやすく、かつ説得力をもって伝える高度なプレゼンテーション能力が求められます。
複雑な内容を平易な言葉で表現する力、聞き手の心を動かすストーリーを構築する力、そして自信に満ちた堂々とした姿勢など、総合的なコミュニケーション能力が厳しく問われます。
専門知識を身に着けるための向上心
社会情勢や経済、そして科学技術は、凄まじいスピードで日々変化し続けています。
そのため、シンクタンクの研究員は、一度身につけた知識に安住することは許されません。
常に自身の専門分野の最新動向を追い続けるのはもちろんのこと、関連する幅広い分野に対してもアンテナを高く張り、貪欲に知識を吸収し続ける知的な向上心が不可欠です。
新しいことを学ぶこと自体に喜びを感じ、自身の知の領域を広げていくことに情熱を燃やせる人材が、シンクタンクでは高く評価されます。
【シンクタンク志望動機】書く前に抑えておこう!3つのポイント
多くの学生を魅了する、説得力のある志望動機は、十分な準備と深い思考から生まれます。
いきなり書き始めるのではなく、まずは自己分析と企業研究を徹底的に行い、考えを整理することから始めましょう。
役割と業務内容を正確に理解する
「シンクタンク」と一括りにせず、それぞれの企業が持つ個性や特徴を正確に理解することが、全てのスタートラインです。
政府系の調査に強いのか、金融機関系の緻密な分析に強みを持つのか、ITコンサルティングの側面が強いのか。
また、リサーチ業務とコンサルティング業務の比率はどの程度か。
各社のウェブサイトや中期経営計画、そして実際に発表されているレポートを最低でも数本は読み込み、事業内容や得意分野、論調の違いを深く理解することで、志望動機に解像度の高い具体性が生まれ、説得力が格段に増します。
知的好奇心と社会貢献を両立してアピール
「知的な仕事がしたい」「難しい課題に挑戦したい」という知的好奇心のアピールは、シンクタンクを志望する上で非常に重要です。
しかし、それだけでは「ただの勉強好き」で終わってしまいかねません。
シンクタンクは、その知見を社会に還元し、より良い未来を創ることを使命とする組織です。
「なぜ自分はその分野に強い知的好奇心を抱くのか」、そして「その知見を活かして、最終的に社会をどのように良くしていきたいのか」という社会貢献への強い意欲をセットで語ることが不可欠です。
自分の個人的な興味と、社会が抱える課題を結びつけて考える視点を持ちましょう。
文字数制限にこだわろう
エントリーシートや面接では、限られた文字数や時間の中で、自身の考えを論理的に、かつ簡潔に分かりやすく伝える能力が厳しく見られています。
これは、シンクタンクの研究員として、クライアントにレポートを提出したり、プレゼンテーションを行ったりする際に求められる基本的なスキルそのものです。
だらだらと長く書くのではなく、一文一文を丁寧に磨き上げ、贅肉をそぎ落とした洗練された文章を目指しましょう。
文字数制限は、あなたを縛る窮屈な制約ではなく、あなたの論理的思考力と要約能力を示すための絶好の機会だと捉えることが重要です。
【シンクタンク志望動機】基本的な構成とは
内容が固まったら、最も伝わりやすい構成で文章を組み立てましょう。
ビジネスシーンでも広く用いられる、論理的で説得力のある文章を作成するための基本的な構成例「PREP法」を紹介します。
結論
まず最初に、「私が貴社を志望する理由は、〇〇という社会課題を、△△という独自のアプローチで解決し、人々の暮らしを豊かにしたいからです」というように、志望動機の結論、つまりあなたが最も伝えたいメッセージを、具体的かつ魅力的なキャッチコピーとして簡潔に述べます。
話のゴールを最初に示すことで、採用担当者はその後の話の展開を予測しやすくなり、内容の理解度が格段に向上します。
あなたならではの視点で、他の学生とは一線を画す、力強い結論を提示しましょう。
根拠
次に、結論で述べた内容を裏付ける、説得力のある具体的な根拠を説明します。
なぜそのように考えるようになったのか、きっかけとなった自身の経験や問題意識を、パーソナルなエピソードとして生き生きと語ります。
「大学のゼミで〇〇を研究する中で、統計データだけでは見えてこない△△という社会課題の根深さを知り、その構造的な解決に貢献したいと強く思うようになりました」というように、あなた自身の原体験に基づいた根拠は、志望動機に誰にも真似できないリアリティと熱量を与えます。
将来のビジョン
最後に、入社後にその企業で何を成し遂げたいのか、そしてどのように成長していきたいのか、将来のビジョンを具体的に語って締めくくります。
「まずは貴社の〇〇という分野の豊富な知見と分析手法を徹底的に吸収し、将来的には△△という新たな領域の政策提言をリードすることで、日本の国際競争力向上に貢献したいです」というように、入社後の活躍イメージを明確に示すことで、あなたのポテンシャルと企業への貢献意欲を強く印象付けることができます。
【シンクタンク志望動機】例文3選
ここでは、具体的な志望動機の例文を3つのパターンで紹介します。
これらはあくまで骨子であり、一例です。
あなた自身の言葉と経験で肉付けし、オリジナルの志望動機を作成するための参考にしてください。
例文①
例文
私が貴社を志望する理由は、データに基づいた客観的な分析を通じて、日本の持続可能な社会保障制度の設計に貢献したいと強く願っているからです。
大学のゼミで計量経済学を専攻し、少子高齢化が公的年金や医療保険の財政に与える影響を分析する中で、世代間の公平性を担保する政策の立案がいかに重要であるかを痛感しました。
数あるシンクタンクの中でも、長年にわたり社会保障分野で質の高い実証研究を積み重ね、政府に対しても数多くの影響力ある政策提言を続けてこられた貴社の実績に、研究者として大きな魅力を感じています。
本インターンシップで貴社の高度な分析アプローチを学び、将来的には国民一人ひとりが生涯にわたって安心して暮らせる社会の実現に貢献したいです。
例文②
例文
貴社を志望する理由は、最先端のデジタル技術に関する深い知見を活かし、深刻な人手不足に悩む日本の中小企業の国際競争力強化に貢献したいと考えているためです。
私は、自身のプログラミングスキルを活かして、製造業のDXを支援する長期インターンに参加し、単なるツールの導入だけでなく、現場の業務プロセスや組織文化の変革こそが成功の鍵であることを学びました。
貴社が技術的な観点だけでなく、経営戦略や人材育成のレベルから企業のDXを包括的に支援されている点に強く共感しています。
貴社のプロフェッショナルな方々と共に働き、一社一社の変革を粘り強く支援する手法を学びたいです。
例文③
例文
私が貴社のインターンシップに参加したい最大の理由は、カーボンニュートラルの実現という地球規模の課題に対し、エネルギー政策の専門家として貢献したいからです。
学生時代に環境経済学を学んだ経験から、環境保護という理想論だけでなく、経済合理性を伴った実現可能な政策でなければ、社会実装は進まないという厳しい現実を知りました。
エネルギー分野において、技術的・経済的な両側面から実現可能性の高い具体的な提言を数多く行っており、産業界からも厚い信頼を得ている貴社でこそ、自身の問題意識を社会に役立つ形にできると確信しています。
貴社で専門性を高め、日本のクリーンなエネルギー転換を加速させる一助となりたいです。
【シンクタンク志望動機】これだけは気を付けるべき注意点
良かれと思って書いた志望動機が、意図せず評価を下げてしまうことがあります。
ここでは、多くの学生が陥りがちな、避けるべき3つの注意点を解説します。
「なんとなく知的にみえる」など浅い動機を避ける
「知的な仕事に憧れている」「社会に大きな影響を与えたい」といった、漠然としたイメージだけで語るのは絶対に避けましょう。
採用担当者は、学生がシンクタンクの仕事をどれだけ具体的に、そして生々しく理解しているかを見ています。
なぜ知的な仕事がしたいのか、なぜ社会に影響を与えたいのか、その背景にあるあなた自身の経験や問題意識を、具体的なエピソードを交えて語らなくては、全く響きません。
「貴社のレポートで〇〇という分析手法が使われていたが、これは△△という観点からも分析できるのではないか」といったレベルまで踏み込むことで、初めて本気度が伝わります。
どこの企業にも共通することは言わない
「貴社の高い専門性に惹かれました」「社会貢献性の高さに魅力を感じます」といった内容は、極論すればどのシンクタンクにも当てはまってしまうため、志望度が低いと判断されかねません。
重要なのは、「なぜ他のシンクタンクではなく、その企業でなければならないのか」という問いに、明確に答えることです。
その企業が持つ歴史的背景や、得意とするリサーチ分野、所属する研究員の専門性、企業文化など、他社にはない独自性に触れ、そこでしか実現できない自分の夢や目標を情熱的に語ることで、初めて「この学生は本気だ」と思わせることができます。
企業研究は怠らない
シンクタンクの選考において、企業研究の深さは、他のどの業界よりも合否を大きく左右します。
企業の公式ウェブサイトや採用パンフレットを見るのは最低限の準備です。
その企業が近年発表した主要な調査レポートや、所属する研究員が出版した書籍、メディアへの寄稿記事などには、必ず目を通しておきましょう。
そこで語られている内容について、自分なりの意見や疑問を持つことができれば、面接での「逆質問」の質も高まり、議論も深まります。
企業研究にかけた時間は、そのままあなたの本気度の表れとして、確実に評価されるでしょう。
まとめ
シンクタンクの仕事は、自身の知的好奇心を満たしながら、同時に社会貢献への強い意志を両立できる、非常にやりがいの大きな、そして崇高な仕事です。
その分、求められる知性のレベルは極めて高く、生半可な気持ちでは到底、内定を勝ち取ることはできません。
本記事で解説した内容を羅針盤とし、徹底的な自己分析と企業研究を行い、あなただけの言葉で、より良い未来を創りたいという熱い想いを伝えてください。