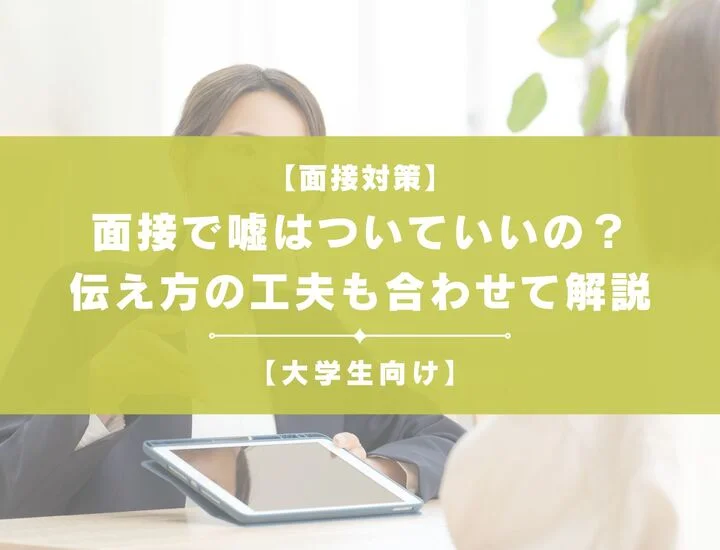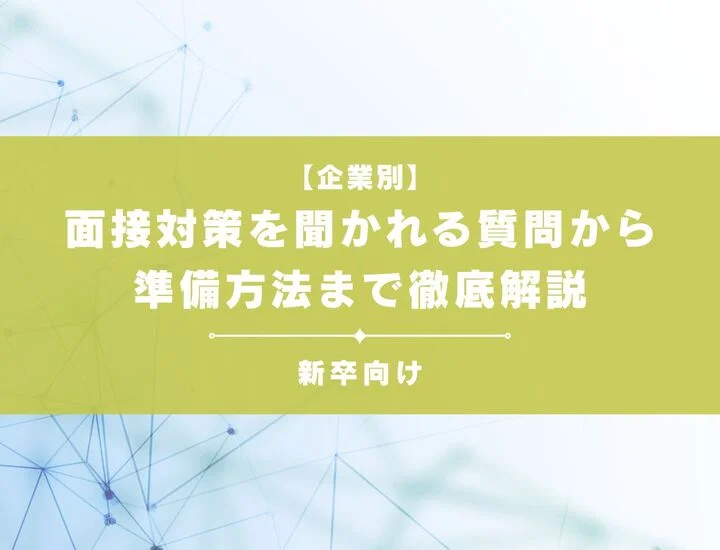HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
面接での嘘は基本的にしてはいけない
就活における面接では、基本的に嘘をつくべきではありません。
面接は、学生と企業がお互いを理解し、相性を見極めるための大切な場です。
ここで嘘をついてしまうと、その後の信頼関係を築くことが非常に困難になります。
自分を良く見せたいという気持ちは誰にでもありますが、偽りの自分を評価されても、入社後に苦しむのは自分自身です。
正直さと誠実さは、どんなスキルよりも重要な評価ポイントだと心得ておきましょう。
面接で嘘をつくとバレるのか?
結論から言うと、面接でついた嘘は高い確率でバレると考えてください。
面接担当者は、毎年何百人もの学生と対話しているプロです。
学生の話し方や表情、話の整合性などから、些細な違和感も見抜く力を持っています。
特に、準備してきた答えをただ話すだけでなく、会話の流れの中で行われる深掘り質問に対して、嘘を突き通すのは至難の業です。
少しでも疑念を持たれると、その後の評価に大きく影響してしまいます。
深ぼられた際に疑われる
面接官は、あなたの経験や考えをより深く理解するために、様々な角度から質問を重ねてきます。
これを深掘り質問と呼びます。
例えば、あなたがアピールした経験について、その時の具体的な状況や、あなたの役割、困難をどう乗り越えたかなどを次々と聞かれるでしょう。
もし話の内容が嘘であれば、具体的なエピソードを語ることができず、答えに詰まったり、話に矛盾が生じたりします。
その瞬間に面接官は疑いを持ち、あなたの発言全体の信憑性が失われてしまいます。
準備不足と評価されるだけでなく、不誠実な人物という印象を与えかねません。
面接で嘘をつくリスク
面接で嘘をつく行為には、想像以上に大きなリスクが伴います。
その場をうまく乗り切れたとしても、後々自分の首を絞めることになりかねません。
バレた時の代償は、単に不合格になるだけにとどまらず、内定の取り消しや、入社後のキャリアにまで影響を及ぼす可能性があります。
軽い気持ちでついた一つの嘘が、あなたの就活全体、ひいては社会人としてのスタートを台無しにしてしまう危険性を理解しておく必要があります。
面接中バレると不合格になる
面接中に嘘がバレた場合、その時点で不合格になる可能性は極めて高いです。
なぜなら、面接官はあなたの能力や経験だけでなく、人柄や誠実さといった人間性も厳しく評価しているからです。
嘘をつくという行為は、この最も重要な信頼性を自ら損なう行為に他なりません。
どれだけ素晴らしいスキルや実績を語っていたとしても、それが偽りであると分かれば、全ての評価が覆ってしまいます。
企業は、共に働く仲間として信頼できる人物を求めていることを忘れてはいけません。
入社後、面接で話した嘘がバレると内定取り消しもあり得る
もし面接の嘘がバレずに内定を得て、入社できたとしても安心はできません。
入社後に、例えば資格の証明書提出を求められたり、業務を任された際に面接で話していたスキルが全くなかったりして嘘が発覚するケースがあります。
これは経歴詐称にあたり、就業規則違反として、最悪の場合、内定取り消しや懲戒解雇といった非常に重い処分につながる可能性があります。
社会人としてのキャリアの第一歩で、このような大きなつまずきを経験することは、将来にわたって深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
嘘をつき続けることは難しい
仮に面接を乗り切り、入社後も嘘がバレなかったとしても、あなた自身が精神的に追い詰められることになります。
いつか嘘がバレるのではないかという不安を常に抱えながら働き続けるのは、非常につらいことです。
周りの同僚や上司と信頼関係を築く上でも、偽りの自分を演じ続けることは大きな障害となります。
本来の業務に集中できず、パフォーマンスが低下することも考えられます。
自分らしさを押し殺し、嘘で固めたキャリアを歩むことは、長い目で見て決して幸せな道とは言えません。
面接での嘘がバレる振る舞い方
面接官は、話の内容だけでなく、あなたの振る舞いからも多くの情報を読み取っています。
自分ではうまく隠しているつもりでも、無意識の行動から嘘がバレてしまうことは少なくありません。
特に、想定外の質問をされた時や、話を深掘りされた時に、焦りから不自然な振る舞いが出やすくなります。
どのような行動が疑念を招くのかを知っておくことで、自分自身の面接対策にも活かすことができるでしょう。
話がかみ合っていない
面接官の質問の意図を正確に理解せず、あらかじめ準備してきた嘘の答えを無理やり話そうとすると、会話がかみ合わなくなります。
例えば、困難を乗り越えた経験について聞かれているのに、実績のすごさばかりをアピールするなど、会話のキャッチボールが成立していない状態です。
これは、自分の話したいことしか考えていない、あるいは何かを隠しているのではないかという疑念を抱かせます。
面接はプレゼンの場であると同時に、コミュニケーション能力を評価される場でもあることを意識し、まずは質問を正しく聞く姿勢が重要です。
実績と中身が一致していない
例えば、サークルのリーダーとして素晴らしい実績を残したとアピールしたとします。
しかし、その実績を達成するまでの具体的なプロセスや、チームの中でどのような役割を果たしたのか、どんな困難があったのかといった中身の部分を深掘りされた時に、具体的に答えられないと、その実績自体の信憑性が疑われます。
数字や結果だけが立派でも、それに伴うストーリーが語れなければ、それは他人の経験を借りてきただけの薄っぺらいアピールだと見なされてしまいます。
実績と中身の一致が、話の説得力を生むのです。
曖昧な表現を使っている
自信がないことや、嘘をごまかそうとする心理は、言葉の端々に表れます。
多かったと思います、たぶん貢献できたはずです、というような曖昧な表現を多用すると、面接官はあなたが事実を語っていないのではないかと感じ取ります。
本当に経験したことであれば、自分の言葉で具体的かつ自信を持って説明できるはずです。
曖昧な答え方は、準備不足を露呈するだけでなく、何か隠し事をしているという不信感を招く原因となります。
自分の言葉で明確に話す練習が不可欠です。
面接担当者はどこで嘘を見抜いている?
多くの学生は、話す内容さえしっかりしていれば嘘は見抜かれないと考えがちですが、それは大きな間違いです。
面接担当者は、長年の経験から、言語情報だけでなく、非言語情報も含めた様々な要素を総合的に観察し、候補者の本質を見極めようとしています。
あなたが思っている以上に、多くのサインから嘘の可能性を察知しているのです。
そのポイントを知ることで、より誠実なコミュニケーションの重要性が理解できるでしょう。
表情や声のトーン、態度から
人は嘘をつくとき、無意識に普段とは違う振る舞いをするものです。
例えば、視線が不自然に泳いだり、急に早口になったり、声のトーンが上ずったりすることがあります。
また、やたらと身振り手振りが大きくなる、貧乏ゆすりをするなど、落ち着きのない態度も、何かを隠しているサインと受け取られることがあります。
話している内容と、表情や態度といった非言語的な情報が一致していないと、面接官はそこに違和感を覚え、あなたの話の信憑性に疑いを持ちます。
深掘りされたときに矛盾点が出たら
嘘を見抜く上で、深掘り質問は非常に有効な手段です。
一つの嘘をつくと、その嘘を正当化するために、別の嘘を重ねなければならなくなります。
面接官は、あなたの回答に対して、なぜそうしたのか、具体的には何をしたのか、その結果どうなったのか、といった質問を繰り返します。
作り話の場合、細部まで一貫性のあるストーリーを即座に組み立てることは極めて困難です。
話しているうちに、以前の発言との間に矛盾が生じ、そこから嘘が発覚するケースは非常に多いのです。
エントリーシートや過去のやり取りから
面接官は、あなたのことをその場で初めて知るわけではありません。
事前に提出されたエントリーシートや履歴書を熟読し、過去の面接での発言内容も記録しています。
面接での発言が、これらの書類の内容と食い違っていたり、以前の面接で話していたことと矛盾していたりすれば、当然ながら嘘を疑われます。
特に、複数の面接官が入れ替わりで面接する場合、情報の引き継ぎは行われています。
その場しのぎの嘘は、後で必ず自分に返ってくることを覚えておきましょう。
面接では絶対に避けたい嘘
自分を少しでも良く見せたいという気持ちから、つい話を盛ってしまいたくなることはあるかもしれません。
しかし、嘘には許される範囲を完全に超えてしまう、絶対に避けるべき領域が存在します。
特に、客観的な事実や経歴に関する嘘は、発覚した際のリスクが非常に高く、取り返しのつかない事態を招きます。
ここでは、就活の面接において、決してついてはいけない嘘の具体例を挙げ、その危険性について解説します。
資格や点数
TOEICのスコアを少し上乗せして伝えたり、持っていない資格を取得済みだと言ったりする嘘は、絶対にしてはいけません。
これらの資格や点数は、多くの場合、入社手続きの際に証明書の提出を求められます。
その段階で嘘が発覚すれば、経歴詐称とみなされ、内定取り消しになる可能性が非常に高いです。
客観的な証拠によって簡単にバレる嘘をつくことは、あまりにもリスクが高すぎます。
自分の実力と正直に向き合うことが、信頼を得るための第一歩です。
経験
リーダー経験がないのにリーダーだったと偽ったり、参加しただけのプロジェクトを自分が主導したかのように話したりすることも、避けるべき嘘です。
入社後、同様の役割を期待された際に、全く能力が伴わなければ、すぐに嘘はバレてしまいます。
周囲からの信頼を失うだけでなく、あなた自身が非常に気まずい思いをし、会社に居づらくなるでしょう。
経験の有無よりも、その経験から何を学び、今後どう活かしていきたいかを自分の言葉で語ることの方が、よほど重要です。
能力
プログラミングができます、英語が堪能ですなど、持っていない能力をあるように見せる嘘も非常に危険です。
企業は、あなたのその能力を期待して採用を決めます。
入社後、そのスキルを前提とした業務を任された時に、全く対応できなければ、業務に支障をきたすだけでなく、会社全体の計画を狂わせることにもなりかねません。
これは単なる見栄ではなく、会社に対する重大な裏切り行為とみなされる可能性があります。
できないことは正直に伝え、学ぶ意欲を示す方が賢明です。
面接では嘘をつかなくても良い方法を考える
自分にアピールできるような華々しい経験がないからと、嘘をつくことを考えてしまう学生もいるかもしれません。
しかし、面接官は全ての学生にスーパーマンのような経験を求めているわけではありません。
大切なのは、等身大の自分を理解し、その中でいかにして自分の魅力やポテンシャルを伝えるかです。
嘘で自分を大きく見せるのではなく、伝え方を工夫することで、ありのままのあなたを評価してもらう方法を一緒に考えていきましょう。
取り組んでいることをアピールする
現時点でスキルや経験が不足していると感じるなら、それを補うために今、何に取り組んでいるかをアピールしましょう。
例えば、語学力が足りないなら、現在オンライン英会話で勉強中です、と具体的な行動を伝えるのです。
これは、目標達成に向けた課題発見能力と、それに対する行動力を示すことにつながります。
完成された人材ではなくても、自ら学び、成長しようとする意欲的な姿勢は、将来性を感じさせ、面接官に非常にポジティブな評価を与えます。
熱意をアピールする
スキルや経験と同じくらい、あるいはそれ以上に企業が重視するのが、入社への熱意です。
なぜ他の会社ではなく、この会社でなければならないのか。
入社してどのような仕事に挑戦し、どう貢献していきたいのか。
こうした強い想いは、多少のスキル不足を補って余りあるほどの強力なアピールになります。
企業のことを徹底的に調べ、自分のビジョンと結びつけて語ることで、あなたの本気度が伝わります。
熱意は嘘をつくことができません。
あなたの正直な気持ちこそが、最強の武器になるのです。
面接でも許容される嘘とは?
これまで面接での嘘は基本的にNGだとお伝えしてきましたが、学生がよく悩むのが、どこまでが許容範囲なのかという境界線です。
事実を完全にねじ曲げる悪質な嘘と、自分を魅力的に見せるための表現の工夫は、全くの別物です。
ここでは、面接官も理解を示してくれる可能性のある、いわばグレーゾーンの伝え方について解説します。
ただし、これも事実に基づいていることが大前提となることを忘れないでください。
ちょっと盛り気味な話
これは、事実を0から1にする嘘ではなく、1の事実を1.2くらいに見せる表現の工夫です。
例えば、アルバイトで売上向上に貢献したという事実がある場合、ただ貢献しましたと言うのではなく、私の提案がきっかけで、チーム全体の売上が前月比10%アップしました、というように、自分の役割を少し強調して話すことです。
もちろん、この数字に全く根拠がなければ嘘になりますが、事実をベースに、よりポジティブでインパクトのある言葉を選ぶことは、アピールの一環として許容されやすいでしょう。
ちょっと脚色した話
これは、話のストーリーをより魅力的にするための演出、つまり伝え方の工夫です。
同じ経験を話すにしても、単に事実を時系列で羅列するだけでは、面接官の印象に残りません。
例えば、困難を乗り越えた経験を話す際に、当時の苦労や自分の感情、そしてそれを乗り越えた時の達成感などを交えて、物語のように語ることで、聞き手はあなたの話に引き込まれます。
これは、事実を偽っているわけではなく、聞き手の共感を得るために表現を工夫しているだけであり、むしろコミュニケーション能力の高さとして評価されることもあります。
嘘と盛る・伝え方を工夫するの違い
就活生が最も混乱するのが、許されない嘘と、許容される盛る話、そして推奨される伝え方の工夫、この3つの違いです。
この境界線を自分の中で明確に持っておくことは、自信を持って面接に臨むために非常に重要です。
事実に基づいているかどうか、そして深掘りされた際に一貫性を持って答えられるかどうかが、これらを見分ける大きなポイントになります。
それぞれの違いを正しく理解し、効果的な自己アピールにつなげましょう。
事実をねじ曲げるのは盛る、構成を工夫するのは伝え方
まず、事実をねじ曲げる、つまり0を1にしたり、1を10に見せたりするのは、許されない嘘です。
一方で、1の事実を1.2程度に大きく見せるのが盛る行為です。
これは、表現をポジティブにすることで、グレーゾーンと言えるでしょう。
そして、最も推奨されるのが、伝え方の工夫です。
これは、1の事実を、より魅力的に、相手に伝わりやすいように話の構成や言葉選びを考えることです。
事実に基づいているという点で、盛ることや嘘とは一線を画します。
自己PRの基本は、この伝え方を磨くことにあります。
盛った話は深掘り弱く、工夫された話は一貫性がある
話を盛る場合、事実の裏付けが弱いため、面接官からなぜそうなったのか、具体的に何をしたのかと深掘りされると、途端に答えに窮し、矛盾が生じやすくなります。
ごまかしていることが見抜かれ、かえって評価を下げてしまうリスクがあります。
一方、伝え方を工夫した話は、あくまで事実に基づいています。
そのため、どんな角度から深掘り質問をされても、具体的なエピソードを交えながら、一貫性を持って自信を持って答えることができます。
この一貫性こそが、あなたの話に信頼性を与えるのです。
伝え方を磨くと誇張しなくても魅力は伝わる
最終的に目指すべきは、話を盛ることで自分を大きく見せるのではなく、伝え方を磨くことで、等身大の自分の魅力を最大限に引き出すことです。
そのためには、徹底した自己分析を通じて、自分の経験の中に隠された価値を再発見する準備が不可欠です。
一つの経験でも、見る角度を変えれば、様々な強みや学びを見出すことができます。
その価値を、相手に分かりやすく、魅力的なストーリーとして語る。
この伝え方のスキルこそが、誇張に頼らなくても面接官の心を動かす、本質的なアピール力につながるのです。
おわりに
面接での嘘について、そのリスクから許容範囲、そして嘘に頼らないアピール方法まで解説してきました。
結論として、面接で嘘をつくことは百害あって一利なしです。
面接は、あなたを偽る場所ではなく、ありのままのあなたと企業との相性を見極める場です。
誠実な姿勢で自分自身と向き合い、しっかりと準備をすれば、あなたの魅力は必ず伝わります。
この記事が、あなたの就活に対する不安を少しでも和らげ、自信を持って面接に臨むための一助となれば幸いです。