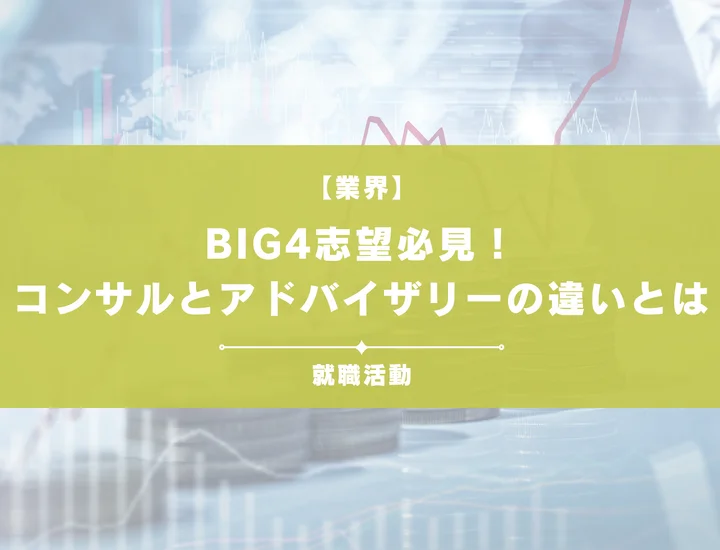HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
【コンサルとアドバイザリーの違い】はじめに
コンサルティングとアドバイザリーは、どちらも企業の課題解決を担う専門職であり、職種としてどちらも「コンサルタント」になりますが、仕事の進め方や求められる力には大きな違いがあります。
この記事ではそれぞれの違いを詳細に解説するので、自分に合った方向性をじっくり見極めてみてください。
【コンサルとアドバイザリーの違い】基本的な違い
コンサルティングとアドバイザリーはどちらも企業の課題を解決する専門職ですが、仕事の進め方や役割には明確な違いがあります。
どちらも似た響きを持つため、就職活動中の学生や転職を考える社会人にとっては混同しやすい分野です。
ここではプロジェクト期間や成果物、顧客との関係性、求められるスキル、チーム構成、監査法人との距離感などを切り口に、両者の違いをわかりやすく解説します。
プロジェクト期間と成果物の違い
コンサルティングは経営全体に深く関わり、数か月から数年に及ぶ長期的なプロジェクトを進めることが多くあります。
経営戦略の策定から実行支援までを伴走するため、成果物は単なる調査報告ではなく、企業がすぐに実行できる変革計画や運用マニュアルの形で提供されます。
一方でアドバイザリーはM&Aや財務調査など特定分野に絞った案件が中心で、期間も数週間から数か月と比較的短めです。
成果物は専門的な助言や詳細な調査分析レポートが中心で、経営判断に必要な情報を精度高く提供することに重点があります。
このようにコンサルティングは企業全体の成長を支える長期戦、アドバイザリーは特定課題を素早く解決する短期戦という違いがあります。
顧客との関係性と関わり方の違い
コンサルティングは顧客企業の内部に深く入り込み、経営陣や現場メンバーと一体となって課題を解決していく立場です。
実行段階でもチームの一員として業務改善や新しい仕組みの定着を支援するため、顧客との密接な連携や現場でのリーダーシップが求められます。
これに対してアドバイザリーは外部の専門家として助言を提供する役割が中心です。
顧客はアドバイザリーが提示する分析結果や提案をもとに、自社で意思決定や実行を行います。
現場に入り込むよりも客観的な立場を維持し、専門知識に基づいた判断材料を提供する点が特徴です。
求められるスキルの違い
コンサルティングでは業界や案件を問わず幅広い課題に対応するため、汎用的な問題解決力が重視されます。
論理的思考、仮説構築、プレゼンテーション、チームマネジメントなど、多様な場面に対応できるスキルが必要です。
一方アドバイザリーは財務、M&A、リスク管理など特定分野に深く関わるため、専門知識が評価されます。
公認会計士や弁護士など資格があると有利で、法務や会計の知識を武器に精緻な分析や助言を行う力が重要です。
この違いから、コンサルは幅広さ、アドバイザリーは専門性を軸にスキルを磨くことが求められます。
チーム構成の違い
コンサルティングではアナリスト、コンサルタント、マネージャーなど職位に応じた階層型のチームが組まれます。
若手からベテランまで幅広い背景を持つメンバーが集まり、案件を通じて多様な知見を共有しながら成長する環境があります。
アドバイザリーは特定分野に特化した専門家チームで構成されることが多く、各メンバーが自分の専門領域で深い知識を発揮します。
このため、コンサルは幅広い人材との協働で総合力を磨く場、アドバイザリーは専門知識を深めてプロとしての精度を高める場という違いがあります。
監査法人との距離感と業務内容の違い
アドバイザリーは監査法人に近い位置で業務を行うことが多く、財務や会計の正確性が重要視されます。
内部統制や財務報告に関わる業務も多く、精密なデータ分析や法規遵守が欠かせません。
一方コンサルティングは経営戦略や事業成長を目的とした支援が中心で、企業価値を高めるための施策を積極的に提案します。
監査法人寄りのアドバイザリーは正確性と専門性、経営寄りのコンサルティングは変革力と実行力を軸に活動する点が大きな違いです。
この距離感の差が、日々の業務内容や職場の雰囲気にも表れます。
【コンサルとアドバイザリーの違い】業務内容から見るコンサルティング
コンサルは企業の経営課題を整理し、解決へ導く専門的な仕事です。
単に助言するだけでなく、実行まで支援して企業を変革する役割を担います。
ここではコンサルティングの基本的な目的、具体的な業務の流れ、分野ごとの特徴をわかりやすく解説します。
経営課題の解決と変革支援
コンサルティングの最大の使命は、顧客企業が抱える経営課題を根本から見極め、成長や変革を実現することです。
成長戦略の立案や新規事業の立ち上げ、業務プロセスの改善、組織再編など、経営全体に深く関わるテーマを扱います。
課題は利益の低下、競合他社との競争、組織の非効率化など多岐にわたります。
コンサルタントは現状を徹底的に分析し、経営層と議論を重ねながら将来の方向性を提案します。
提案後も計画が現場で実行され、成果が出るまで継続的に支援する点が特徴です。
単なる調査報告ではなく、企業が自ら成長できる体制づくりまで関与することで、長期的な企業価値向上に貢献します。
プロジェクトの種類と具体的な業務フロー
コンサルティング業務は課題の特定から実行支援まで一連の流れがあります。
まず企業の現状を分析し、真の課題を発見します。
次に課題を解決するための仮説を立て、必要な情報を集めて検証を進めます。
分析結果をもとに、企業が実際に動かせる具体的な解決策を提案します。
提案が決定した後は、計画が確実に実行されるよう顧客と一緒に進捗を確認しながら支援します。
この過程ではデータ分析力、論理的思考力、コミュニケーション力が求められます。
単なる提言にとどまらず、現場に入り込んで変革を実現するため、短期間で成果を出す責任も伴います。
プロジェクトの種類と専門性
コンサルティングは取り組む領域によって複数の分野に分かれます。
戦略コンサルティングは企業の将来を決める経営戦略や新規事業戦略を扱い、トップマネジメントと直接議論する機会が多い分野です。
総合コンサルティングは戦略、人事、業務改善、IT導入など幅広い課題を横断的に扱い、総合力が求められます。
ITコンサルティングはシステム導入やデジタル化を支援し、技術面から企業の変革を後押しします。
組織や人事を専門とする分野では、人材制度の設計や組織再編を通じて働き方の改善を目指します。
これらの分野はそれぞれ必要とされる知識や経験が異なりますが、いずれも論理的思考力を基盤に顧客の成長を支援する点に共通性があります。
コンサルティングの種類は多岐にわたる
コンサルティング業界には戦略、人事、ITなどの主要分野以外にも、企業の特定課題に深く対応する多様な専門領域があります。
代表的なものに財務や会計に特化した財務コンサルティングがあります。
これは企業の資金計画やコスト削減、M&Aにおける財務戦略立案など、数字を軸に経営を改善する分野です。
公認会計士や税理士などの知識を活かし、財務諸表の分析や資金調達の支援を通して企業の経営基盤を強化します。
また、特定の業界に絞った業界専門コンサルティングも増えています。
さらに近年では環境・エネルギー分野やヘルスケア、デジタル化支援など新しいテーマに特化したコンサルティングも拡大しています。
自分が興味を持つ分野や得意分野を見極め、専門性を高めることで、コンサルタントとして独自の価値を発揮できる環境が広がっています。
【コンサルとアドバイザリーの違い】業務内容から見るアドバイザリー
アドバイザリーは企業が直面する特定分野の課題に対して、専門知識を生かして最適な助言を行う職種です。
ここではアドバイザリーの役割、代表的な案件、監査法人系アドバイザリーの特徴、そして多様化する専門分野について詳しく見ていきます。
特定領域の専門家としての助言
アドバイザリーの基本的な役割は、財務・会計・法務・リスク管理など特定分野の専門家として顧客を支援することです。
企業が買収や資金調達を進める際、判断の根拠となるデータやシミュレーションを示し、経営陣が自信を持って決断できる環境を整えます。
コンサルティングのように経営に深く入り込んで実行を主導するのではなく、外部の専門家として客観的かつ中立的な視点から提言する姿勢が重視されます。
そのため会計士や弁護士、システムエンジニアなど、専門資格や実務経験を活かして活躍する人材が多く、知識の幅と正確性が直接評価につながります。
顧客の経営判断に影響を与える責任が大きいため、最新の法規制や業界動向を常に学び続ける姿勢も欠かせません。
案件の種類と具体的な業務内容
アドバイザリーが扱う案件は多岐にわたります。
M&Aアドバイザリーでは、買収対象企業の財務デューデリジェンス、事業シナジー分析、価格交渉のための資料作成などを通じて、取引の安全性と適正価格を評価します。
財務アドバイザリーでは、資金調達計画や投資戦略に関する分析を行い、金融機関との交渉を支援します。
リスクアドバイザリーでは、サイバー攻撃や法令違反、自然災害など企業活動に潜む多様なリスクを洗い出し、対策を提案します。
案件ごとに数週間から数か月で結論を出す必要があり、短期間で膨大なデータを整理する力が問われます。
複雑な法務や会計の知識を理解した上で、経営層が理解しやすい形にまとめるスキルも重要です。
監査法人系アドバイザリーの特徴
BIG4など監査法人系アドバイザリーは、会計監査で培った財務・会計の知見を最大の強みにしています。
監査業務で培った緻密な分析力を活かし、企業の財務健全性や内部統制の評価、資金調達に伴うリスク検証などを実施します。
法務や税務とも密接に連携するため、国際会計基準や税制改正への対応力も求められます。
監査法人系ならではのネットワークを活用して国内外の規制情報を収集し、グローバルな取引にも迅速に対応できる点が大きな魅力です。
若手のうちから上場企業の大型案件に携われるチャンスが多く、専門知識を実務を通して高められる環境が整っています。
アドバイザリーの種類は多岐にわたる
アドバイザリーの分野は財務や会計だけにとどまりません。
サイバーセキュリティではシステムの脆弱性診断や攻撃対策を提案し、気候変動関連ではカーボンニュートラル達成に向けたリスク評価や投資戦略を助言します。
事業再生では経営不振企業の資金繰り改善や組織再編を支援し、フォレンジックでは不正会計や情報漏えいの調査を実施します。
近年はAIやビッグデータを活用したリスク予測や不正検知など、新しい技術を取り入れたサービスも拡大しており、理系出身者が活躍する場も増えています。
自分の興味や専門分野に合った領域を選ぶことで、専門家としての価値を高めつつ、社会課題の解決に直接貢献するやりがいを感じられます。
【コンサルとアドバイザリーの違い】BIG4におけるコンサルとアドバイザリーとは
BIG4は世界的に展開する総合コンサルティンググループであり、コンサルティング部門とアドバイザリー部門を中心に多様なサービスを提供しています。
両部門は役割が異なるものの、企業の成長や課題解決を支援するという目的は共通しています。
しかし近年はサービス領域が広がり、両者が協力してプロジェクトを進めるケースも増えており、境界は次第に曖昧になりつつあります。
各ファームでの組織構造
BIG4ではコンサルティング部門とアドバイザリー部門が基本的に独立して存在します。
ただし名称や役割はファームごとに異なり、Deloitteはデロイトトーマツコンサルティングとデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー、PwCはPwCコンサルティングとPwCアドバイザリーなど、同じBIG4でも組織体制は多様です。
さらに、デジタル変革やESG関連など新しいサービスが増えることで、両部門がまたがる案件も珍しくなくなっています。
志望するファームを選ぶ際には、最新の組織図や採用ページを確認し、どの部門がどの領域を扱うのかを理解しておくことが重要です。
組織は定期的に改編されるため、入社後に新しい部門が立ち上がる可能性もあります。
部門間の連携と役割分担
顧客の課題が複雑化する中で、コンサルとアドバイザリーが連携して成果を出すプロジェクトが増えています。
例えばM&A案件では、アドバイザリーが財務デューデリジェンスや企業価値評価を担当し、買収後の統合戦略や業務設計はコンサルティングが担うといった役割分担が一般的です。
他にも、リスクマネジメント案件ではアドバイザリーが法務や会計面から助言し、コンサルがITシステムや業務改革を計画するなど、両者の知見を組み合わせることで複雑な問題を総合的に解決します。
この連携によって、顧客企業は戦略立案から実行まで一貫したサポートを受けられるのが大きな強みです。
組織再編や異動の可能性
BIG4は市場の変化に合わせて頻繁に組織再編を行っています。
EYはすでにコンサルとアドバイザリーを統合した体制を採用し、Deloitteも統合の動きを進めています。
こうした動きは、両部門の境界が徐々に曖昧になり、顧客ニーズに応じた柔軟な体制が求められていることを示しています。
また、多くのファームでは社内公募制度や異動制度が整備されており、コンサルティングからアドバイザリー、あるいはその逆へのキャリアチェンジが可能です。
入社後に自分の志向に合わせて専門領域を変えられる点は、BIG4で働く大きな魅力の一つです。
BIG4以外にもアドバイザリーはある
アドバイザリー業務を提供する企業はBIG4だけではありません。
独立系のM&Aブティックファームは特定分野に特化した少数精鋭の体制で、高度な専門性とスピードを強みとしています。
またメガバンクや証券会社では、資金調達やM&A支援を中心に金融面からアドバイザリーサービスを提供しています。
さらに大手IT企業やSIerも事業コンサルティングやシステム導入に関するアドバイザリーを展開しており、技術と金融を組み合わせた案件に携わる機会もあります。
自分のキャリア志向や得意分野に応じて、BIG4に限らず幅広い選択肢から進路を検討することが可能です。
【コンサルとアドバイザリーの違い】選考難易度は違う?
コンサルティング部門とアドバイザリー部門は、同じBIG4の中でも選考フローや重視されるポイントが異なります。
どちらも高い人気を誇りますが、コンサルは論理的思考力や発想力を幅広く試され、アドバイザリーは専門知識や特定領域への興味が強く求められます。
そのため単純にどちらが易しいとは言えず、自分の強みや志向に合った準備が欠かせません。
以下では部門ごとの選考対策と注意点を詳しく見ていきます。
コンサルティング部門の選考対策
コンサルティング部門で最も重視されるのはケース面接です。
企業から提示された経営課題に対して、限られた時間で現状分析、課題抽出、解決策の提案までを論理的に構築する力が求められます。
日頃からニュース記事や身近なビジネス事例を読み、背景要因や解決策を自分なりに整理する習慣をつけることが有効です。
また、ディスカッション型の面接も多いため、考えを端的に伝える発言力や、相手の意見を受け止めつつ議論を深める柔軟性も必要です。
ケース面接対策本やオンライン講座を活用して実際の形式に慣れ、模擬面接を繰り返すことで本番でも落ち着いて対応できるようになります。
論理的思考だけでなく、短時間で結論を導き出すスピード感も評価の対象となります。
アドバイザリー部門の選考対策
アドバイザリー部門でもケース面接が行われる場合がありますが、特に重視されるのは応募者がその専門領域にどれだけ関心を持ち、学んできたかです。
財務、M&A、リスク管理などの分野では、大学での研究内容、インターン経験、資格取得への取り組みなど、具体的な学習や挑戦を示すことが有効です。
例えば会計や統計を学んだ経験、研究でデータ分析を行った実績など、専門性に結びつくエピソードを整理しておくと説得力が増します。
また、業界ニュースやM&Aの事例を日々チェックし、自分なりの見解を持っておくことも大切です。
単なる興味だけでなく、専門分野に対する継続的な学習姿勢が評価されるため、早めに準備を始めて知識を積み重ねることが合格への近道となります。
併願は可能なのか
多くのBIG4ではコンサルティング部門とアドバイザリー部門を併願することが可能です。
複数部門を受けることで、自分の適性や志向に合った選択肢を見つけやすくなり、企業理解も深まります。
ただし、それぞれの部門で求められる人物像や選考内容が異なるため、志望動機や面接準備を部門ごとに分けて練る必要があります。
併願する場合は、自分がどちらにより強い興味を持っているかを明確にした上で、それぞれの面接で一貫したキャリアプランを語れるよう整理しておくことが重要です。
選考難易度
一般的に総合コンサルティング部門は就活生からの人気が非常に高く、倍率も厳しい傾向にあります。
一方でアドバイザリー部門は専門性の高さから応募者がやや少ない場合がありますが、単純に内定が取りやすいわけではありません。
アドバイザリーは財務やリスク管理など特定領域に関する知識や熱意が重視されるため、関連分野への学習や実務経験が不足していると評価を得にくいのが実情です。
コンサルは幅広い課題に対応する思考力を、アドバイザリーは深い専門性を求めるという違いがあり、どちらも入念な準備が合格には不可欠です。
自分がどちらに適性があるかを見極め、早期から情報収集と対策を進めることが成功への第一歩となります。
【コンサルとアドバイザリーの違い】あなたの適性はどっち?
コンサルティングとアドバイザリーは、どちらも企業の課題解決を支援する仕事ですが、求められる資質や働き方には大きな違いがあります。
自分の興味やキャリア志向に合わせて選ぶことで、入社後に力を発揮しやすくなります。
ここでは課題解決への姿勢、仕事の期間、面接でアピールすべき強みという三つの視点から、自分に合った方向性を考えるヒントをまとめます。
課題解決と専門性で考える
コンサルタントに向いているのは、曖昧な課題に対してゼロから解決策を生み出すことにやりがいを感じる人です。
業界やテーマに縛られず、幅広い知識を吸収しながら多様な課題に挑戦したい人には最適な環境です。
また、経営者や役員と直接議論しながら提案を形にするため、自ら仮説を立てて試行錯誤を繰り返すことを楽しめる人が活躍します。
一方、アドバイザリーは特定の分野を深く掘り下げ、その道の専門家としてクライアントを支援する役割が中心です。
会計、財務、リスク管理、サイバーセキュリティなど、明確な専門性を磨きたい人に向いています。
自分が幅広い知識で課題を切り開きたいのか、あるいは特定分野で専門性を高めたいのかを考えることが選択の第一歩です。
長期的か短期的かで考える
コンサルの業務は企業の成長や改革を長期的に支援する特徴があります。
戦略立案から実行まで、半年から数年にわたるプロジェクトを担当し、企業の変革を伴走するスタイルです。
一つの案件に深く入り込み、成果が出るまで粘り強く取り組む力や、チームを率いて長期的に信頼関係を築く姿勢が求められます。
逆にアドバイザリーは、M&Aや財務調査など短期間で結果を出す案件が多く、数週間から数か月単位で次のプロジェクトへ移ることが一般的です。
短いスパンで多くの案件を経験できるため、専門性を積み重ねながら多様な現場を渡り歩きたい人に向いています。
同じ会社でも役割によって案件のスピード感が異なるため、長く一社に深く関わりたいのか、短期集中で多くの案件を経験したいのかが適性を分ける重要なポイントとなります。
面接でアピールするべき強み
コンサル志望の場合は、困難な課題を論理的に整理し、周囲を巻き込みながら解決した経験を具体的に示すことが効果的です。
学生時代の研究やチーム活動などで培ったリーダーシップや調整力をエピソードとともに語ると説得力が増します。
特に、課題を発見し、自ら仮説を立てて実行に移した経験を具体的な数字や成果を交えて説明すると、即戦力としての印象が強まります。
一方アドバイザリー志望では、専攻分野での学び、資格取得への意欲、特定業界への深い関心を具体的に伝えることが重要です。
専門性に関連する学習や実績を、数字や成果を交えて説明することで、採用側に将来の成長ポテンシャルを印象づけることができます。
また、専門知識に加えて継続して学び続ける姿勢を示すと、入社後の成長意欲が伝わりやすくなります。
【コンサルとアドバイザリーの違い】まとめ
コンサルは多様な業界やテーマに携わりながら総合力を磨きたい人、アドバイザリーは専門知識を武器に特定分野で価値を発揮したい人に向いています。
どちらも高い成長環境とやりがいを持つため、早めの情報収集と自己分析が選考突破の鍵となります。
この記事を参考に、自分にとって最適な進路を具体的に描いてみましょう。