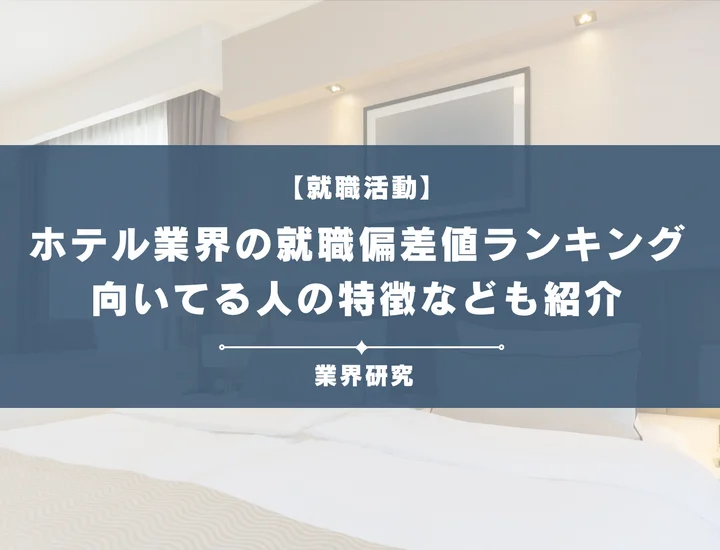HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
今回は、私たちの生活に最も身近な「食品業界」について、その就職偏差値から仕事のリアルまで、徹底的に深掘りしていきます。
「食べることが好き」を仕事にしたいと考えている人、必見です。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職活動を進める中で、「就職偏差値」という言葉を耳にしたことがある人も多いでしょう。
これは、受験における偏差値のように、企業の入社難易度や人気度、待遇などを総合的に評価し、数値化した指標のことを指します。
主にインターネット上の掲示板や就活情報サイトなどで作成・共有されており、企業の相対的な立ち位置を知るための一つの目安として参考にされています。
ただし、この偏差値は公的なデータではなく、作成者や年度によって基準が異なるため、あくまで「参考値」として捉えることが重要です。
偏差値の高さ=自分にとっての良い会社とは限らないため、数字に振り回されすぎず、自分の軸と照らし合わせながら企業研究を進めるための材料の一つとして活用しましょう。
食品業界の就職偏差値ランキング
それでは、具体的に食品業界の就職偏差値ランキングの傾向を見ていきましょう。
食品業界は、生活必需品を扱うという特性から、景気変動の影響を受けにくく、非常に安定した業界として就活生から根強い人気を集めています。
特に、強力なブランド力を持つ大手総合食品メーカーや、特定の分野で高いシェアを誇る企業は、入社難易度が非常に高くなる傾向にあります。
ここでは、一般的な傾向として、ランクごとの企業群の特徴を解説していきます。
【食品業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】日本コカ・コーラ
偏差値70は全業界でも最難関レベルです。
日本コカ・コーラは外資系企業の日本法人であり、圧倒的なブランド力とマーケティング戦略が特徴です。
採用人数は非常に少なく、超少数精鋭の採用となります。
入社には高学歴に加え、卓越した語学力(特に英語)、戦略的思考力、そして学生時代の圧倒的な成果が求められます。
インターンシップ経由での選考も重要であり、早期からの準備と高度なビジネススキルが不可欠です。
【食品業界】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】味の素 サントリー サントリー食品インターナショナル ネスレ日本
【68】明治 アサヒグループ キリン サントリーフーズ アンハイザー・ブッシュ・インベブ日本
【67】日清製粉 日清食品 サッポロビール 江崎グリコ ヤクルト本社 キッコーマン 日本ハム
【66】カゴメ ロッテ 森永製菓 森永乳業 カルビー 味の素食品 モンデリーズ日本 ハイネケン・キリン 日本ケロッグ ダノン日本
国内トップクラスの知名度と人気を誇る大手メーカーがひしめくランクです。
飲料、食品、調味料など、日常生活に欠かせない強力なブランドを持つ企業群です。
国内外で事業を展開しており、入社難易度は非常に高いです。
高い基礎学力や筆記試験のクリアはもちろん、OB/OG訪問やインターンシップ参加を通じた深い企業研究が求められます。
面接では、論理的思考力と「なぜ他社ではなく自社なのか」を明確に伝える強固な志望動機が合否を分けます。
【食品業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】三菱食品 雪印メグミルク ニップン ニッスイ マルハニチロ DM三井製糖 日清オイリオ 不二製油 Jオイルミルズ 伊藤ハム ハウス食品グループ本社 日本食品化工 BRサーティワン ハーゲンダッツジャパン
【64】三井食品 伊藤忠食品 味の素冷凍食品 味の素AGF プリマハム ニチレイ 東洋水産 カンロ キユーピー ミツカン 日本ペプシコーラ販売 ベースフード レッドブルジャパン
【63】伊藤園 山崎製パン エバラ食品工業 日東富士製粉 日本甜菜製糖 ウェルネオシュガー キッコーマンソイフーズ かどや製油 ユーグレナ コカ・コーラボトラーズジャパン モンスタービバレッジ日本 ネスレネスプレッソ 日本デルモンテ グリコチャネルクリエイト
【62】フジパングループ本社 ダイドードリンコ オリオンビール サトウ食品 ヱスビー食品 不二家 湖池屋 おやつカンパニー 六甲バター ユーハ味覚糖 塩水港精糖 ブルボン フジ日本精糖 亀田製菓 中村屋 ブルドックソース キユーピータマゴ キユーピー醸造 森下仁丹
【61】UCC上島珈琲 ポッカサッポロフード&ビバレッジ 日本サンガリアベバレッジカンパニー キーコーヒー アヲハタ ケンコーマヨネーズ 名糖産業 ユタカフーズ 永谷園 モロゾフ 宝酒造 養命酒製造 北海道コカ・コーラボトリング みちのくコカ・コーラボトリング
Bランクに次ぐ、業界を代表する大手・中堅上位企業が中心です。
製粉、製油、冷凍食品、製パンといったBtoBでの高いシェアを持つ企業や、食品卸、特定分野で強みを持つBtoC企業などが含まれます。
福利厚生や事業の安定性から、Bランク同様に就職活動生からの人気は非常に高いです。
徹底した業界研究・企業研究を行い、自分の強みや経験がその企業のどの部門でどう活かせるかを具体的にアピールする必要があります。
SPIや玉手箱などの筆記試験対策も、高得点を目指して万全に行うことが重要です。
【食品業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】敷島製パン スジャータめいらく 柿安本店 霧島酒造 オカムラ食品工業 はごろもフーズ ライフドリンクカンパニー 焼津水産化学工業 仙波糖化工業 ミヨシ油脂 岡山和気ヤクルト工場 ハウスウェルネスフーズ シャトレーゼ ゴディバジャパン
【59】明治チューインガム オハヨー乳業 ヤマザキビスケット ヤマサ醬油 一正蒲鉾 紀文食品 石井食品 滝沢ハム 福留ハム 佐藤食品工業 旭松食品 篠崎屋 石垣食品 日本食研製造 日清シスコ 沖縄コカ・コーラボトリング
【58】富士山の銘水 丸美屋食品工業 えひめ飲料 和歌山ノーキョー食品工業 トモヱ乳業 オタフクソース モランボンプロダクツ ホテイフーズコーポレーション エスエスケイフーズ サンデリカ イオンベーカリー フルタ製菓 全農・キユーピー・エツグステーシヨン
【57】青木フルーツ 銀座千疋屋 寿がきや食品 大東カカオ 四国乳業 日本果実工業 さんれいフーズ ロイヤルデリカ 富士食品工業 マルトモ フルッタフルッタ ユニカフェ ヤヨイサンフーズ マリンフード 東ハト
【56】ハラダ製茶 宮崎県農協果汁 宮島醬油 フンドーキン醤油 伊藤製パン ドンク リョーユーパン 小川珈琲クリエイツ 沖縄ハム総合食品 ゴールドパック たまご&カンパニー ニップンドーナツ
地域に根ざした有力企業や、お菓子・調味料など特定のカテゴリーで確固たる地位を築いている中堅企業が多く含まれます。
BtoCで消費者に広く認知されている企業も多く、安定した経営基盤を持つ優良企業が揃っています。
Cランク以上の企業群と比べると、「なぜその地域で働きたいのか」「なぜその特定分野に興味があるのか」といった、より具体的な志望動機や熱意が重視される傾向にあります。
面接では人柄や社風とのマッチングも見られるため、自己分析を深め、自分の言葉で誠実に伝える練習が効果的です。
【食品業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】日本栄養給食協会 ゴンチャロフ製菓 メリーチョコレートカムパニー 信州ビバレッジ サラダコスモ ジェイエイビバレッジ佐賀 フレッシュワン マルハマ食品 たけや製パン ポテトフーズ 御菓子御殿 日東コーン・アルム アトリオン製菓
特定の地域や分野、OEM(相手先ブランド製造)などで堅実な経営を続けている企業群です。
洋菓子メーカーや地元の飲料メーカーなど、地域社会や特定の顧客層に密着した事業展開が特徴です。
偏差値としては標準的なレベルですが、食品業界自体が根強い人気を持つため、油断は禁物です。
入社には、「食」への純粋な関心や、真面目にコツコツと業務に取り組む姿勢、入社後にどう貢献したいかを丁寧に伝えることが求められます。
筆記試験の基礎を確実に固め、面接では基本的なビジネスマナーを守り、明るくハキハキと受け答えすることが重要になります。
【食品業界】とは
食品業界とは、文字通り「食」に関連する製品やサービスを提供する産業全体を指します。
私たちは毎日食事をしますが、その食材の生産から加工、流通、販売に至るまで、非常に多くの企業や人が関わっています。
人々の生命を維持し、豊かな食文化を支えるという、社会にとって不可欠な役割を担っているのが食品業界です。
景気動向によって需要が大きく変動しにくい「ディフェンシブ産業」とも呼ばれ、その安定性が大きな魅力とされています。
基本的な仕組み
食品業界の仕組みは、製品が消費者に届くまでの流れ、すなわち「サプライチェーン」で理解するのが分かりやすいでしょう。
大きく分けると、「川上(原料調達)」「川中(製造・加工)」「川下(卸売・小売)」の3つで構成されています。
まず「川上」では、農家や漁師、畜産家などが農作物や水産物、畜産物を生産します。
次に「川中」の食品メーカーが、これらの原材料を仕入れ、加工食品や飲料、調味料などを製造します。
この「川中」が、就活生の皆さんが一般的にイメージする食品業界の中心です。
そして「川下」では、食品卸売業者がメーカーから商品を仕入れて在庫管理や物流を担い、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店などの小売業・外食産業に商品を届け、最終的に私たち消費者の手元に届くのです。
主な役割と業務内容
食品業界の最も重要な役割は、「安全・安心」な食品を「安定的」に供給することです。
人々の健康に直結するため、衛生管理や品質管理には他の業界以上に厳しい基準が求められます。
また、時代のニーズに合わせて新しい味や食感、健康機能を持つ商品を開発し、豊かな食文化を創造する役割も担っています。
主な業務内容としては、新しい商品を生み出す「商品開発・研究開発」、製品を効率よく安全に製造する「生産・品質管理」、製造した商品をスーパーや飲食店に提案・販売する「営業」、そして商品の魅力を消費者に伝えブランドを育てる「マーケティング・広報」など、多岐にわたります。
食品業界の現状と今後の動向
食品業界は安定している一方で、今まさに大きな変革期を迎えています。
国内では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「健康志向」や「簡便調理」(手軽に調理できる商品)、「中食(なかしょく)」(持ち帰り惣菜など)のニーズが急速に高まっています。
企業はこうした国内市場の変化に対応した新商品の開発を迫られています。
また、国内市場の縮小を見据え、成長著しい海外市場へ積極的に進出する「グローバル化」も加速しています。
さらに、世界的な課題である「フードロス(食品廃棄)問題」や「SDGs(持続可能な開発目標)」への取り組みも、企業の社会的責任として強く求められており、パッケージ素材の見直しや代替タンパク(大豆ミートなど)の開発が活発化しています。
【食品業界】特徴
食品業界は、私たちの生活に密着しているがゆえの安定性が最大の特徴です。
しかし、その安定性を支えているのは、実に多様な職種のプロフェッショナルたちです。
総合食品メーカーを例にとっても、その内部は様々な機能を持つ部門が連携して成り立っています。
「食品メーカー=商品開発」というイメージだけでは、この業界の全体像は見えてきません。
営業、マーケティング、生産、研究、物流、管理部門など、それぞれの専門家がバトンをつなぐことで、初めて一つの商品が私たちの食卓に届きます。
自分がどの分野で強みを発揮できるかを考えるためにも、代表的な職種について理解を深めておきましょう。
商品開発・研究開発
食品業界の花形とも言われる職種です。
研究開発(R&D)は、主に理系(農学、化学、生物学、栄養学など)の専門知識を活かし、新しい素材の機能性研究や、味・香り・食感を生み出すための基礎技術の開発を行います。
一方、商品開発(商品企画)は、研究部門が開発した技術や市場のトレンド、消費者のニーズを基に、「どのような新商品を、いくらで、どう売るか」という具体的なコンセプトを立案し、試作を繰り返しながら製品化を目指します。
文系出身者でも、マーケティングの視点から商品企画に携わるチャンスは多くあります。
消費者の心を掴む新しい「美味しい」を生み出す、やりがいの大きな仕事です。
生産・品質管理
生み出された商品を、安全かつ効率的に大量生産するための仕組みを管理するのが、生産管理と品質管理の役割です。
生産管理は、工場の稼働計画の立案、原材料の調達、製造ラインの効率化などを担当し、コストを抑えながら安定的に製品を供給する責任を負います。
品質管理は、製造工程全体を監視し、菌の検査や異物混入のチェック、定められた規格(HACCPなど)が遵守されているかを確認します。
食品の安全は、企業の信頼そのものです。
人々の健康を守る「最後の砦」として、非常に高い倫理観と責任感が求められる、食品メーカーの根幹を支える重要な仕事です。
多くの場合、勤務地は工場(地方都市など)となります。
営業・マーケティング
作った商品を消費者に届けるための最終的な「橋渡し」を担うのが、営業とマーケティングです。
営業は、主にスーパー、コンビニ、卸売業者、飲食店といった法人(BtoB)に対して自社商品を提案し、店頭に置いてもらうための交渉を行います。
単に商品を売るだけでなく、「どうすれば売れるか」という売り場作りの提案(棚割りの提案など)も重要な業務です。
マーケティングは、主に一般消費者(BtoC)に向け、テレビCM、SNSキャンペーン、パッケージデザインなどを通じて商品の魅力を伝え、ブランド価値を高める戦略を練ります。
市場のトレンドを敏感に察知し、消費者の購買意欲を刺激するためのあらゆる施策を実行する、クリエイティブな側面と分析的な側面を併せ持つ職種です。
【食品業界】向いている人
食品業界は、その安定性や身近さから多くの就活生に人気ですが、活躍するためには特有の適性が求められます。
単に「食べることが好き」というだけでは務まらない、「食」を仕事にするプロフェッショナルとしての覚悟も必要です。
もちろん、「好き」という情熱は大きな原動力になりますが、それ以上に、食を「支える側」としての視点を持っているかが重要です。
ここでは、食品業界で特に輝ける人の特徴をいくつか挙げてみましょう。
自分自身に当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。
食への強い関心と探究心がある人
「食べることが好き」を一歩進めて、「食」そのものに対する強い好奇心や探究心を持っている人です。
例えば、「なぜこの商品はヒットしているのか?」「この味はどうやって作られているのか?」「最近の健康トレンドの背景には何があるのか?」といったことを、日常生活の中で自然と考えてしまう人は向いています。
この探究心が、商品開発のアイデアや、営業先での説得力のある提案につながります。
トレンドに敏感で、常に新しい情報をインプットし続けることができる人は、変化の早い消費者のニーズにも対応していけるでしょう。
安全と品質への責任感が強い人
食品業界で働く上で、最も欠かせない資質がこれです。
食品は、人の健康、時には生命に直結するものです。
一つの小さなミスが、大規模な健康被害や企業の信頼失墜につながる可能性があります。
そのため、どんなに地味な作業であっても、定められたルールや手順を厳格に守ることができる誠実さと責任感が求められます。
特に生産・品質管理部門はもちろん、営業や企画部門であっても、「安全・安心」を最優先する企業文化が根付いています。
「自分が人々の食卓を守っている」という強い使命感を持てる人は、この業界で長く活躍できるはずです。
安定志向と変化への対応力を併せ持つ人
食品業界は景気変動に強い安定(ディフェンシブ)産業ですが、一方で消費者の嗜好やライフスタイルの変化は非常に激しいという側面も持っています。
「安定」は業界の特性であり、個々の企業が安泰であるという意味ではありません。
したがって、業界の安定性に魅力を感じつつも、その中で起こる「変化」に柔軟に対応できるバランス感覚が重要です。
健康志向、SDGsへの対応、海外展開など、次々と生まれる新しい課題やトレンドを前向きに捉え、自ら学び、行動を変えていける人材が求められています。
伝統を守りつつ、革新にも挑戦できる人が理想です。
【食品業界】向いていない人
逆に、食品業界に足を踏み入れると「思っていたのと違った…」とミスマッチを感じやすい人の特徴もあります。
これは能力の優劣ではなく、単に「相性」の問題です。
入社後のギャップを最小限に抑えるためにも、自分の特性と照らし合わせて正直に自己分析してみることが大切です。
食品業界の華やかなイメージ(新商品の発表会やテレビCMなど)は、仕事全体のほんの一部に過ぎません。
その裏にある地道な努力や厳格なルールを受け入れられるかどうかが、一つの分かれ道になるかもしれません。
衛生管理や細かいルールが苦手な人
食品業界、特に製造現場(工場)では、極めて厳格な衛生管理基準が定められています。
例えば、専用の作業着への着替え、複数回の手洗い・消毒、エアシャワー、私物の持ち込み禁止など、人によっては「面倒くさい」と感じるような細かいルールが日常です。
これらのルールは、食の安全を守るために絶対に欠かせないものです。
もしあなたが、こうした細かい決まり事を守ることや、地道な確認作業を繰り返すルーティンワークが根本的に苦手だと感じるなら、特に生産・品質管理の分野ではストレスを感じやすいかもしれません。
トレンドに無関心な人
食品業界は、消費者の嗜好という「トレンド」に大きく左右される業界です。
次々と新しい商品が発売され、その裏では数え切れない商品が店頭から消えていきます。
業界自体は安定していても、企業間の競争は非常に激しいのです。
そのため、世の中で今何が流行っているのか、消費者が何を求めているのかに常に関心を持ち、情報をキャッチアップし続ける姿勢が求められます。
「食には興味があるけれど、世の中の流行には疎い」という人は、特にマーケティングや商品企画、営業といった職種では、アイデアの枯渇やズレた提案につながってしまう可能性があります。
「食べることが好き」という消費者目線しかない人
これは多くの就活生が陥りがちな落とし穴です。
「食べることが好き」は素晴らしい志望動機の一つですが、それだけでは不十分です。
「消費者」として美味しいものを楽しむことと、「提供者」として安全な商品を安定供給することは、全く異なります。
仕事となれば、自分の好みとは関係ない商品を扱うことも、泥臭い営業活動も、夜間の工場対応も発生します。
華やかな商品企画のイメージだけで入社すると、「こんなはずではなかった」と感じるかもしれません。
「食」を裏方として支えることへの覚悟があるかどうか、自問自答してみる必要があります。
【食品業界】内定をもらうためのポイント
食品業界は、その安定性やBtoCビジネスの身近さから、文系・理系問わず就活生に非常に人気が高い業界です。
強力なブランドを持つ大手企業ともなれば、採用倍率は数十倍、数百倍にも達します。
この激戦を勝ち抜くためには、他の就活生との差別化を図るための戦略的な準備が不可欠です。
単に「食品が好きだから」という思いだけでなく、「なぜ食品業界でなければならないのか」「なぜその企業で、自分は何がしたいのか」を、具体的な経験に基づいて論理的に語れるように準備することが、内定への鍵となります。
なぜ「食品」なのかを徹底的に深掘りする(志望動機)
食品業界の面接で最も重要視されるのが志望動機です。
「食を通じて人々を笑顔にしたい」といった抽象的なフレーズだけでは、採用担当者の心には響きません。
なぜなら、多くの学生が同じようなことを言うからです。
「なぜ、数ある業界の中で食品を選んだのか?」「なぜ、同業他社(例えばA社ではなくB社)を志望するのか?」この2点を徹底的に深掘りしてください。
そのためには、各社の企業理念、主力商品の強み、海外展開の戦略、SDGsへの取り組みなどを細かく比較・分析することが不可欠です。
「その会社でしか成し遂げられないこと」と「自分のやりたいこと」が重なるポイントを見つけ出し、自分の言葉で語れるようにしましょう。
「食」に関連する経験をアピールする(自己PR)
食品業界を志望する上で、「食」に関連する経験は非常に強力なアピール材料となります。
例えば、飲食店やスーパーでのアルバイト経験は、消費者の生の声やトレンドを肌で感じたエピソードとして活用できます。
大学で栄養学や農学、食品化学などを専攻している理系の学生は、その専門知識が研究開発や品質管理でどう活かせるかを具体的に示しましょう。
また、食品ロス削減のボランティア活動や、趣味の料理・お菓子作りから学んだことなども、食への関心の高さを裏付けるエピソードになります。
重要なのは、その経験を通じて何を学び、入社後にどう貢献できるかを明確に結びつけることです。
インターンシップやOB・OG訪問でリアルな情報を得る
食品業界、特にBtoB(業務用食品)が中心の企業や、工場が主な勤務地となる生産管理・品質管理職は、学生が日常で接する機会が少なく、仕事内容を具体的にイメージしにくいものです。
パンフレットやWebサイトだけでは分からない「生の情報」に触れるために、インターンシップやOB・OG訪問を積極的に活用しましょう。
インターンシップでは、実際の業務の一部を体験できるだけでなく、職場の雰囲気や社員の方々の人柄を知ることができます。
OB・OG訪問では、仕事のやりがいだけでなく、大変なことや泥臭い部分(例:工場の実態、営業のノルマなど)も正直に質問してみましょう。
そこで得たリアルな情報が、志望動機に深みと説得力を持たせてくれます。
【食品業界】よくある質問
食品業界は身近なようで、いざ就職先として考えると、意外と知らないことも多いものです。
ここでは、就活生の皆さんからよく寄せられる、食品業界に関する素朴な疑問や不安にお答えしていきます。
「安定しているって本当?」「文系でも活躍できる?」といった、気になるポイントをクリアにして、企業研究に役立ててください。
リアルな実情を知ることで、入社後のミスマッチを防ぎ、自分に本当に合った企業を見つけるヒントになるはずです。
食品業界はやっぱり安定していますか?
はい、他の業界と比較して「安定している」と言えます。
食品は人々が生きていく上で欠かせない「生活必需品」であるため、景気の良し悪しに関わらず、需要が極端に落ち込むことが少ないからです。
こうした産業を「ディフェンシブ産業」と呼びます。
ただし、「業界が安定していること」と「個々の企業が安泰であること」はイコールではありません。
消費者のニーズの変化は激しく、企業間の競争は非常にシビアです。
ヒット商品を生み出し続けられない企業や、時代の変化に対応できない企業は、安定している業界の中でも淘汰されていく可能性があることは理解しておく必要があります。
文系でも商品開発に携われますか?
「商品開発」をどのように定義するかによりますが、チャンスは十分にあります。
商品の「中身」である味や機能性を研究する「研究開発(R&D)」部門は、農学、化学、栄養学などの専門知識が求められるため、理系出身者が中心となることが多いです。
しかし、「どのような商品を市場に出すか」というコンセプトを立案し、パッケージデザインやプロモーション戦略を考える「商品企画」や「マーケティング」の部門では、文系出身者が数多く活躍しています。
消費者のニーズを的確に捉え、魅力的なストーリーを構築する能力は、文系学生が学んできたこととも親和性が高いと言えるでしょう。
転勤や工場勤務は多いですか?
これは企業や職種によって大きく異なりますが、大手総合食品メーカーの場合、全国転勤や工場勤務の可能性は高いと考えておくべきです。
「生産・品質管理」職を希望する場合、勤務地は製品を製造する「工場」が基本となります。
工場は、物流の利便性や広大な敷地を確保するため、地方都市や郊外に立地しているケースがほとんどです。
「営業」職の場合も、全国各地に支社・支店があるため、数年単位での全国転勤(ジョブローテーション)が一般的です。
一方、本社機能である「マーケティング」「商品企画」「管理部門」などは、都市部(東京や大阪など)に集中している傾向があります。
まとめ
今回は、食品業界の就職偏差値から、その仕組み、職種、そして内定獲得のポイントまでを詳しく解説してきました。
食品業界は、私たちの「当たり前の食生活」を最前線で支える、非常にやりがいのある仕事です。
人々の健康や日々の喜びに直結するという責任感と誇りを感じられるのが、この業界の最大の魅力でしょう。
就職偏差値ランキングは、あくまで業界の全体像を掴むための一つの指標に過ぎません。
大切なのは、偏差値の高さに一喜一憂することなく、その企業が持つ独自の強みや理念に共感できるか、そして自分がその中で何を成し遂げたいかを真剣に考えることです。
この記事を参考に、皆さんが「心から働きたい」と思える企業に出会えることを願っています。

_720x550.webp)