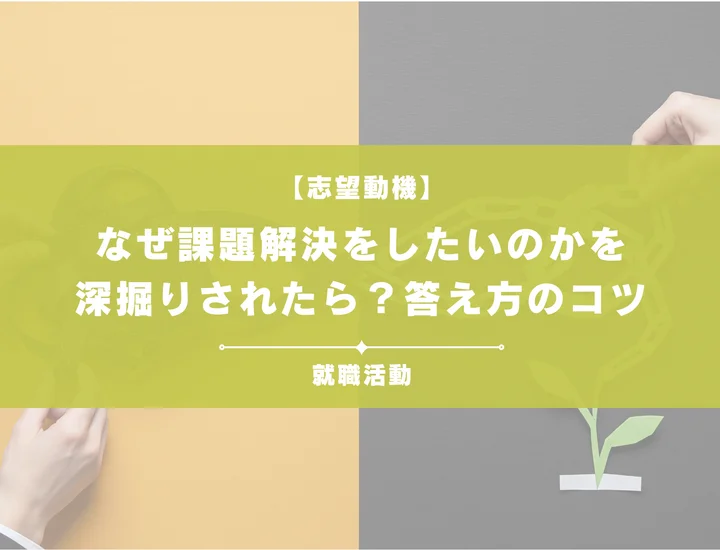HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
就活では課題解決という言葉をよく聞きます。
しかし、その言葉を使うだけでは自分らしさは伝わりません。
大切なのは、なぜその思いを持ったのかを自分の経験から説明できることです。
この記事では、課題解決への思いを自分の言葉で語るための考え方を紹介します。
企業が見るポイントを理解し、自信を持って話せるように準備しましょう。
【なぜ課題解決をしたいのか】面接官は「なぜ?」を問い詰める
就活では、課題解決という言葉を使う学生が非常に多いです。
しかし、その言葉を使うだけでは他の学生と同じに見られてしまいます。
大切なのは、なぜ自分が課題解決に価値を感じるのか、その理由を深く言語化することです。
面接官は、あなたがどのような考えを持ち、どの経験からその思いに至ったのかを知りたいと考えています。
ここでは、面接官がなぜを掘り下げる理由と、課題解決を語る際に意識すべき点を解説します。
「なぜ?」の先を見ている
面接官は、なぜを繰り返すことであなたの価値観を確認します。
どんな経験が自分の行動や選択の根っこにあるのかを知るためです。
課題解決と口にする学生は多いですが、全員が同じ思いを持っているわけではありません。
だからこそ、なぜそう思うのかを具体的に掘り下げる過程が重要になります。
例えば、誰かが困っていた場面で自分が動いた経験や、仕組みを整えることで周囲が助かった場面など、実体験が鍵になります。
その体験を語れるほど、言葉に重みが生まれます。
企業は、自分の価値観を理解し、それを行動に移せる人を求めています。
なぜ課題解決にこだわるのかを語れる学生は、自分の軸を持っていると評価されます。
「課題解決」は就活で多用される
課題解決という言葉は便利ですが、非常に多くの学生が使うため差別化が難しい言葉です。
表面的に使ってしまうと、誰にでも当てはまる志望理由になってしまいます。
そのため、具体的な経験や気づきが欠かせません。
例えば、団体活動で情報共有の仕組みを整えた経験や、働く人の負担を減らすための工夫を行った経験など、実例を話すことで説得力が増します。
さらに、その経験から何を感じ、どう価値観が形作られたのかまで話せると強いです。
面接官は、単に課題解決という言葉を使うのではなく、実際に行動した経験と、その背景にある思いを見ています。
【なぜ課題解決をしたいのか】言語化できない4つの理由
就活で課題解決を軸に語ろうとすると、言葉が浮かばず悩む学生は多いです。
ここでは、なぜ言語化が難しくなるのか、その原因を4つの視点から整理します。
自分の気持ちを深掘りするヒントとして活用してください。
漠然としすぎている
課題解決という言葉はよく使われますが、その中身が曖昧なままだと気持ちが上手く形になりません。
社会の課題、人の課題という言い方では、範囲が広すぎて焦点がぼけてしまいます。
大切なのは、場面と相手と理想の状態を具体的に思い出すことです。
例えば学校で困っている友人を助けた場面、部活で情報が整理されていなかったせいで混乱が起こった場面など、日常にある小さな出来事が手がかりになります。
その経験を思い出し、誰がどんな状況で、どう変わってほしいと感じたのかを言葉にすると、自分だけの軸が見えてきます。
企業に評価されそうだから
課題解決や社会に役立ちたいという言葉は、就活でよく見かけます。
評価されそうだという理由だけで選んでしまうと、自分の気持ちとのつながりが弱くなります。
その結果、話すときにも薄さが出てしまい、面接官に見抜かれることがあります。
本当の動機は、自分が自然に動いてしまう場面や、つい気になってしまうことの中にあります。
評価されるためではなく、自分が昔から大切にしてきた癖や考え方から言葉を探すことで、心からの志望理由に変わります。
原体験と繋げられない
課題解決の理由を語るときに原体験が大切と言われますが、特別な出来事である必要はありません。
大きな成功や感動だけが原体験ではないのです。
自分の気持ちが動いた瞬間を拾うことが大切です。
例えば、無駄が多い作業に違和感を覚えて効率化を考えた経験、困っている人を見て放っておけず手を差し伸べた経験など、日常の小さな行動がヒントになります。
その瞬間の気持ちを丁寧にたどることで、自分の価値観が見えてきます。
本音が言えない
きれいな動機を話そうとすると、気持ちが固まってしまい言葉が出なくなります。
しかし、採用担当者が知りたいのは飾られた言葉ではありません。
あなたの素直な感覚にこそ、本当の動機が隠れています。
放っておけない、無駄が嫌だ、もっと良くできると感じたなどの小さな気持ちが、課題解決を望む理由になります。
真面目である必要はありません。
自分の性格や癖の延長線にある思いこそ、説得力のある動機になります。
本音を言葉にすることで、自分の軸がより強くなります。
【なぜ課題解決をしたいのか】「課題」の解像度を上げる3つの視点
課題解決を志望理由にする学生は多いですが、その言葉の中身がぼんやりしていると相手には伝わりません。
大切なのは「課題」という言葉を自分なりに細かく分けて考えることです。
誰が、どんな場面で、どのように困っていて、どうなってほしいのか。
その視点を持つことで、自分だけの具体的な動機に変わり、説得力が生まれます。
ここでは、その解像度を高める3つの見方を紹介します。
誰の「課題」を解決したいか?
課題を解決したいという思いを言葉にするとき、多くの人が誰を助けたいのかを深く考えずに使ってしまいます。
しかし、目指す相手が違えば課題の内容や関わり方も変わります。
社会全体を良くしたいのか。
組織を良くしたいのか。
身近な一人の生活を良くしたいのか。
その違いを理解することで、自分の思いに芯が生まれます。
ここでは、誰のための課題を解決したいのかを3つの視点で整理します。
社会の課題
社会の課題を解決したいと考える場合、対象は個人や特定の企業ではなく、社会全体の問題に向き合うことになります。
例えば、環境の変化や少子高齢化、教育や医療への格差、地域による不平等など、規模が大きく長い時間をかけて取り組む必要があるテーマが多く見られます。
この視点に興味を持つ人は、世の中をより良くしたいという気持ちが強く、広い視野で物事をとらえられる傾向があります。
ただし、範囲が広い分、自分の経験や行動と結びつけにくい場合があります。
重要なのは、なぜその問題に心が動いたのかを自分の言葉で説明できることです。
大きな課題に向き合う姿勢は立派ですが、自分の原点がなければ説得力は生まれません。
組織の課題
組織の課題を解決したいという考え方は、企業や学校、サークルなど、集団の中で起こる問題に目を向ける姿勢です。
例えば、業務が非効率で時間がかかっている、情報共有がうまくいかず混乱が生まれる、人間関係がうまくいかず離れる人が出るといった状況があります。
この視点を持つ人は、仕組みを整えたり、流れを改善したりすることにやりがいを感じやすいです。
実際に、アルバイトや部活動で役割を整理したり、情報をまとめる仕組みをつくったりした経験は、この視点につながります。
組織は人が集まって動く場所なので、人を理解しながら環境を良くしていく姿勢も必要になります。
個人の課題
個人の課題に焦点を当てる場合、一人一人が日常で感じる小さな不便や困りごとに目を向けます。
例えば、買い物で迷わない仕組みがほしい、子育てをしながら働く人を助けたい、忙しい人が時間を節約できるようにしたいといった具体的な思いです。
このような視点を持つ人は、身近な問題に敏感で、相手の気持ちに寄り添う力があります。
成果が見えやすく、感謝の言葉や笑顔に直接触れる機会も多くなるでしょう。
身近な悩みや不便さを放っておけず、自然と手を動かして助けようとした経験は、個人を起点とした課題意識につながります。
どんな「性質」の課題に惹かれるか?
課題を解決したいという思いにも、実はさまざまな方向性があります。
まだ気づかれていない問題に挑みたいのか。
分かっている課題を少しずつ良くしたいのか。
すでに価値のあるものを広げたいのか。
自分がどの瞬間に気持ちが動くのかを振り返ることで、課題に対する向き合い方が見えてきます。
まだ誰も見つけていない課題の解決
まだ誰も問題と感じていないことに気づき、解決策を生み出すことに心が動くタイプです。
世の中の人が当たり前だと思っていることや、不便さを感じながらも仕方ないと受け止めている場面に目を向けます。
この姿勢は、常識を疑い、自分なりに考える力が大きな武器になります。
新しい形や仕組みをつくるには時間がかかることもありますが、自分の発想で道を切り開けたとき、大きな達成感があります。
また、周囲が気づかなかったことに気づくため、観察力や探究心も重要です。
正解がない状況でも粘り強く試し続けられる人に向いています。
既にある課題の解決
すでに問題として認識されていることに対し、改善を進めることに喜びを感じるタイプです。
今ある仕組みややり方に目を向け、より良くする方法を探します。
小さな工夫や整理によって、日々の仕事や生活が楽になる場面を見つけることができます。
現状を否定するのではなく、出来ている部分を活かしつつ、足りない部分を補う姿勢が求められます。
観察しながら原因を考え、試し、効果を確かめるという流れを丁寧に行うことが大切です。
少しずつ状況が良くなっていく過程を楽しめる人に向いています。
良いものをさらに拡大
すでに良いとされているものを多くの人に届けたり、もっと便利にしたりすることに魅力を感じるタイプです。
広く使われている仕組みやサービスを見て、もっと多くの場面で使えるのではないかと考えます。
基本はしっかり整っているため、何を伸ばすべきかを見極める目が求められます。
また、結果が数字や反応として分かりやすく出るため、その変化を楽しめる人に向いています。
例えば、利用者がより使いやすくなる工夫を考えたり、知ってもらうための方法を考えたりします。
良いものをきちんと届けることで、より多くの人の生活を良くする流れを作ることができます。
何があなたを「解決」に突き動かすか?
課題を解決したいという気持ちの背景には、必ず心が動いた瞬間があります。
その動きは人によって違い、正しさを守りたい思いだったり、困っている人を助けたい気持ちだったり、自分が感じた不便を何とかしたいという気持ちだったりします。
自分がどんな感情に強く反応するのかを理解することで、課題解決に向かう動機がより深くなり、言葉に説得力が生まれます。
ここでは、その感情の種類と特徴を整理します。
「許せない!」(怒り・正義感)
不公平な状況や理不尽な扱いを目の当たりにしたとき、強い違和感を抱き、胸が熱くなる人がいます。
自分だけでなく、周りの人が不利益を受けている場面に出会うと、見過ごせず、なんとか変えたいと感じる気持ちが湧き上がります。
このような感情は、物事の本質を見極め、間違っているものに立ち向かう力になります。
時には周囲から反対されたり、理解されなかったりすることもありますが、自分の内側にある正しさを信じて進むことで、流れを変えることができます。
また、問題の根本を見つけ、仕組みから変えていくような取り組みに向いている傾向があります。
「助けたい!」(共感・優しさ)
誰かが困っている姿を見ると、胸が締めつけられるように感じる人がいます。
相手の気持ちを想像し、その立場に寄り添いながら、少しでも楽にしてあげたいと感じる気持ちが強く働きます。
この動機は、人との関わりの中で力を発揮し、相手の喜びが自分の喜びにつながります。
単に問題を解決するだけではなく、相手にとって安心できる関係や環境を整えることにも価値を見いだします。
小さな変化でも相手が笑顔になることで、自分の行動が意味を持つことを実感できます。
また、相手の言葉だけでなく、表情や声のトーンから気持ちを読み取り、真意に寄り添う力があります。
「不便だ!」(当事者意識・不満)
日常の中で、使いにくいものや無駄が多い仕組みに接したとき、強い不満を覚える人がいます。
その不満は単なる愚痴ではなく、改善の手がかりになります。
自分が困った経験や、身近な人が苦しんでいる場面を見たときに、もっと良くできるはずだという思いが自然と湧き上がります。
この動機は、ユーザーの立場に立った視点を持っており、細かい使い勝手や流れの改善に向いています。
また、実際に使った経験を元に考えるため、具体的な改善点を見つける力があります。
課題を大げさに捉えるのではなく、日常の中に埋もれている小さな問題に気づけることが特徴です。
【なぜ課題解決をしたいのか】“なぜ”を掘り下げる自己分析
課題を解決したいという気持ちには、必ず自分の中に理由があります。
しかし、その理由が言語化できていないと、面接でうまく説明できず、強い志望動機として伝わりません。
大切なのは、かっこいい言葉を並べることではなく、自分の経験と気持ちを丁寧に見つめ直すことです。
ここでは、なぜその思いを持ったのかを深く掘り下げるための方法を紹介します。
「原体験」をもとに考える
課題を解決したい理由を強くするためには、自分が過去にどんな出来事で心を動かされたのかを見つけることが重要です。
面接では立派な表現より、その言葉の裏側にある経験と気持ちが求められます。
例えば、学校やサークルで不便さを感じた経験、家族や友人の困りごとを見て胸が痛んだ経験、自分自身が悔しい思いをして改善したいと感じた経験など、どんな些細なものでも構いません。
その出来事を振り返り、なぜ自分はその場面で行動したくなったのかを考えることで、自分の価値観が浮かび上がってきます。
大きなドラマのような話でなくても、自分の中で意味があれば十分です。
「感情が動いた瞬間」を書き出す
自分の原動力を知るためには、過去の出来事の中で、心が大きく動いた瞬間に注目します。
驚いた時、悔しかった時、誰かに感謝された時、面倒なことを効率的にできて嬉しかった時など、感情が揺れた場面には大切なヒントがあります。
この時、「なぜ自分はその場面でそう感じたのか?」まで考えることが大切です。
怒りを感じたなら、何が理不尽だと感じたのか。
悲しさや共感が湧いたなら、誰の気持ちに寄り添ったのか。
そうした感情の積み重ねこそが、自分らしい価値観につながります。
「小さな成功体験」を深掘り
感情が動いた瞬間の中でも、自分の行動によって変化が起きた経験は特に重要です。
大きな成果である必要はありません。
友人のサークル運営を効率化した、アルバイト先で動線を改善して働きやすくした、授業や委員会の中で工夫をして周囲が助かったなど、小さな取り組みで十分です。
まず状況を整理し、何が問題だったのかを明確にします。
次に、自分が何を目指して動いたのかを思い出します。
そして、どんな工夫や行動をしたのかを書き出し、最後にその結果どう変わったかを整理しましょう。
【なぜ課題解決をしたいのか】「自分の言葉」に変えるには?
課題解決を志望動機として語るとき、最も大切なのは、ありきたりな言い回しではなく、あなた自身の言葉で説明できることです。
表面的なフレーズは、一見立派でもすぐに薄く見えてしまいます。
自分が経験してきたことや大切にしている価値観を丁寧に振り返り、社会で起きている課題と結びつけていくことで、初めて言葉に深みが生まれます。
ここでは、自分の思いを確かな言葉に変えるための考え方を紹介します。
社会課題と原体験を結びつける
社会の課題を解決したいと思う気持ちを自分の言葉で語るためには、まず社会全体の出来事と自分の経験をつなげて考えることが大切です。
例えば、教育格差や地域の高齢化といった社会問題は、直接関係がないように見えても、生活の中で似たような困りごとを見た場面があるかもしれません。
自分が身近で感じた不公平さ、助けたいと思った瞬間、便利になれば良いと考えた経験を思い出し、その気づきを社会の課題と重ね合わせます。
すると、ただニュースで知っただけではなく、自分の心が動いた理由が言葉になります。
大きな出来事でなくても、日常の小さな気づきが十分なきっかけになります。
自分の強みに焦点を当てる
課題解決を語るときに欠かせないのは、ただ思いを述べるだけでなく、自分の強みを通じてどのように関わりたいのかを明確にすることです。
これまでの成功体験や努力して身につけた力を振り返り、自分がどんな場面で力を発揮できたのかを考えます。
例えば、人の話を丁寧に聞き気持ちを汲むことが得意なら、困っている人の声を拾い上げることで課題を見つける役割ができます。
思いと能力が結びつくことで、自分だからできる課題解決の姿がはっきりし、面接でも伝わりやすくなります。
【なぜ課題解決をしたいのか】企業選び・職種選びに活かす
課題解決を軸に就職活動を進めるとき、大切なのは「どの企業でも良い」という姿勢ではなく、自分の思いに合った場所を選ぶことです。
同じ課題でも、業界によって視点や取り組み方は大きく変わります。
さらに、企業の中でも職種ごとに役割や関わり方が異なります。
自分が向き合いたい課題と、どんな方法で解決したいのかを重ね合わせることで、自分に合う道が見えてきます。
何を解決するかを企業で見る
課題解決を軸に企業を選ぶときは、まず自分が向き合いたい対象を意識することが大切です。
世の中全体に広がる問題に向き合いたいなら、教育格差や地方の衰退といった大きな課題に向き合う団体や企業があります。
教育の領域では、学校だけでなく、学びを支える民間サービスや地域で活動する団体も選択肢になります。
企業の内部にある問題に取り組みたいなら、業務を改善したり、仕組みを整えたりする会社が向きます。
自分の思いに最も近い取り組み方をしている企業を探すことで、納得できる進路が見えてきます。
どう解決するかを職種で見る
課題を解決するための道を考えるとき、企業選びだけでなく、職種ごとの役割にも目を向ける必要があります。
同じ課題に向き合っていても、関わり方や求められる力は職種によって大きく変わります。
相手の声を聞き、最初の一歩をつくる仕事が向いているなら、対話を軸にする職が合います。
状況を丁寧に分析し、道筋を立てて進めていく力があるなら、課題の本質を見抜く仕事が向くでしょう。
また、解決のために仕組みや道具を作りたい人は、技術を使って形にしていく役割が合います。
自分がどの段階でやりがいを感じるのかを考えることで、働き方が具体的に見えてきます。
OB/OG訪問でリアルを知る
OBやOGの方に会い、実際の話を聞くことは、机の上での情報収集では得られない学びにつながります。
企業のホームページや説明会では、事業内容や制度など、全体像を広く知ることができます。
しかし、日々の仕事でどんな時間を過ごし、どんなことに喜びや難しさを感じているのかは、なかなか見えてきません。
そこで役に立つのが、現場で働く人から直接話を伺う機会です。
働く人がどんな視点で物事を考え、どんな場面でやりがいを感じ、どんな困難に向き合っているのかを知ることで、仕事のリアルさが増します。
【なぜ課題解決をしたいのか】ES・面接での伝え方
課題解決への思いを持っていても、その魅力を相手に伝えるには工夫が必要です。
面接官は、あなたの言葉が本当に自分の経験から生まれたものか、そして企業の仕事と結びついているかを見ています。
ここでは、エントリーシートや面接で課題解決への思いを伝える際に意識したいポイントを解説します。
。
結論ファーストで話す
面接や書類では、はじめに結論を伝えることが大切です。
結論が最初にあると、相手は話の方向性をつかみやすくなります。
例えば、自分がどんな課題に関心を持ち、なぜそれを解決したいのかという軸を端的に述べます。
そのうえで、背景や理由を補足していく流れを取ることで、相手はあなたの話を整理しながら聞くことができます。
話が長くなると、本当に伝えたい思いが埋もれてしまう場合があります。
最初に伝えたいことを明確にしたうえで、理由や経験を加えていくと、印象がより強く残ります。
具体的な話をする
自分の思いを伝えるときには、具体的な経験を軸にすることが重要です。
どのような状況で、どんな課題に直面し、どう感じて、どのように行動したかを丁寧に振り返ります。
その経験から何を学び、なぜ課題解決という軸が自分に根づいたのかを示すことで、言葉に厚みが生まれます。
また、行動を支えた強みや工夫した点にも触れると、単なる感想ではなく「価値ある経験」として伝わります。
抽象的な表現だけでは伝わりにくいため、実際に起きた出来事や自分の動きを中心に話を組み立てましょう。
企業への思い
課題解決という軸があるだけでは、どの会社でもいいように見えてしまいます。
そこで重要になるのが、なぜその企業で実現したいのかという視点です。
企業の事業内容や強み、取り組みを調べ、自分の経験や思いと重ね合わせます。
その会社だからこそ実現できる価値や、自分がどのように貢献したいのかを具体的に語ることで、強い志望度が伝わります。
自分の軸と企業の取り組みを結びつけ、一本のストーリーとして語れると、面接官の納得感が高まります。
まとめ
課題解決という言葉は重みがあります。
だからこそ、自分の経験や感情を丁寧に振り返り、理由を言葉にすることが大切です。
この記事を参考に、自分が動きたくなる瞬間を思い出し、自分の軸をつくりましょう。