
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
「どんな試験があるんだろう?」 「試験の対策をしておかないといけないのは分かっているけど、何を対策すればいいのか分からない」 「検査の何が合否の判断に使われているのか興味がある」 試験があると分かっていると、悩み、考えなくてはならないことが多いでしょう。
この記事では、性格検査について説明しています。また、どのような回答が検査に不適切なのかも解説しています。さらに対策のポイントの紹介や、いくつかの種類がある性格検査についても、それぞれの特色をご紹介しています。
本記事を読むことで性格検査を行う目的から、その内容の例題、企業が検査の結果のどこを重点的に見ているのかが分かるでしょう。
▼▼▼ この記事の要約動画はこちら ▼▼▼
目次[目次を全て表示する]
【性格検査の対策】性格検査とは?
性格検査(=personality test)とは、パーソナリティを把握するための心理検査であり、選考の際に取り入れられている適性検査の一種です。
性格検査は多くの企業が新卒採用に用いており、候補者は自社の仕事に向いているか、パーソナリティの部分はどうかを把握するために実施しています。
しかしながら「性格検査に良し悪しや正解なんてない」「能力検査とは違って性格検査は重要じゃないから対策しなくていい」などのように、性格検査の対策を行っている学生は多くないのが現実です。
性格検査の対策を行わないことでWebテストの難易度がトップレベルの外資系企業に通過したにもかかわらず、同じテスト結果を同業界の日系企業の選考に利用して落ちてしまった、ということもあります。
落ちた要因は、日系企業と外資系企業で求められる性格が異なるからです。
日系企業では協調性や人当たりの良さが重視されます。“飲みニケーション”という言葉があるように、チームでコミュニケーションを取りながら協力して成果を出していく文化や傾向があります。
一方、外資系企業は成果主義と個人主義の傾向が強いです。実力に見合った評価がされる環境が用意されているので、個人の能力に自信を持ち、今後も圧倒的な実績を残していこうとする人が多いとされています。
つまり、企業の特色や社風によって求められる人物像が異なるため「A社は合格だったけど、同業界のB社は不合格だった」ということが起こりうるのです。
能力検査との違い
採用する時の判断基準となる適性検査のひとつに、能力検査というものがあります。これは、今までに得た知識の応用力や、相手に対しての理解力、何か問題が生じた際の判断力などを見極める検査です。
性格検査は能力検査とは異なり、自社の仕事に対して前向きに取り組めるかどうか、また仲間とコミュニケーションを取りながら、仕事をすすめていけるかどうかなどを見極める検査です。
ちなみに、性格検査と能力検査の2つは、さまざまある適性検査の中でも主流であり、多くの企業が併せて活用しています。
【性格検査の対策】性格検査を行う目的
性格検査を行うには、主に4つの目的があります。
- 候補者を絞り込む
- スクリーニング
- 面接の材料にする
- 面接では確認できなかったことを知る
候補者を絞り込む
自社で活躍している社員と性格や傾向が似ているかを判断し、企業との相性を測る目的で行います。
例えば、社内で活躍している(社員A)がいるとして、人事は(社員A)のようなポテンシャルを持つ新卒を一名採用したいと考えています。そこで性格検査の結果を参考に、新卒の候補者の中から(社員A)に近い性格や傾向、能力を持った学生を洗い出していきます。
選考を進めていく中で、同じような能力値を持つ候補者が二名見つかりましたが、採用枠は一名のみ。
そこで判断する基準となるのが、自社の社風や特色にマッチした性格であるかです。
企業の社風や特色にマッチしているかどうかは性格検査の結果で判断される場合が多くあるため、万が一“この企業に入りたいがために回答を誤魔化す”といったことを行うと、入社後のミスマッチに繋がってしまう恐れがあります。
就活においてミスマッチを起こさないためにも、性格検査は誤魔化さず正直に回答することが大切です。
スクリーニング
知名度のある大手企業や就活生からの人気が高いメガベンチャーなどの場合、応募者が非常に多く選考を効率的に進めるためのスクリーニングは重要な工程です。
Webテストでは「ビッグ・ファイブ理論」に基づき、企業独自の判断でスクリーニングをかけていきます。
ビッグ・ファイブ理論とは“人の性格は5つの要素の組み合わせからなる”ことを説明した理論で、日本で行われている性格検査の多くはこの理論を元に設計されています。
(参照:ビッグ・ファイブ理論)
- 開放性 ー 知的好奇心
- 誠実性 ー 自己統制力やまじめさ
- 外向性 ー 社交性や活動性
- 協調性 ー 利他性や協調性
- 神経症傾向 ー ストレス耐性
「適性検査を用いてスクリーニングをかける」ということは、すなわち企業側は「判断基準となる検査結果を持っている」ということ。そのため、Webテストを受験する際は社風や特色など企業分析を十分に行っておくことがポイントになります。
ビッグファイブ性格診断に関しては下記の記事で詳しく紹介しています。
面接の材料にする
性格検査を含むWebテストの選考を通過すると、次は面接が始まります。適性検査の結果を確認しながら、面接は進められることが多いです。
面接では、ESと併せてその人の性格に一貫性があるかみられます。矛盾点があると嘘をついている可能性があるとして、印象が悪くなってしまいます。
自己分析を通じて、自分の人間性を理解した上で、それぞれが矛盾しないように答えることが大切です。
面接では確認できなかったことを知る
時間の限られている面接だけでは、応募者の持っている能力や性格を完全に把握することはできません。
面接では知ることのできなかった特徴の確認に、性格検査の結果を参考にすることがあります。
この目的で行われる検査は、1次面接以降に行われるケースが多いです。面接の内容と無理に合わせることはせずに、正直に回答しましょう。
【性格検査の対策】性格検査で落ちることはあるのか?
まず結論として、性格検査で落とされることもあります。
性格検査では社風に合っている人材か、求める人材とマッチしている人材かを確認しているのが性格検査です。
また、性格検査の結果は多くの場合、面接官など企業の採用担当者に渡されます。
つまり、性格検査の段階で落とされることはなくとも、面接の結果に大きく影響すると考えられています。
こうした事情を鑑みると、性格検査の対策は抜かりなく行うべきです。
性格検査の結果だけが大きく合否を左右するわけではないかもしれませんが、就活は「総合点」で判断されます。
「性格検査をもっとやっておけば、合格できたのかな...」と後悔しないよう、しっかりと対策しましょう。
【性格検査の対策】 性格検査で落ちやすい人の特徴
ここからは性格検査で落ちやすい人の特徴について詳しく解説していきます。
下記の5点に心当たりのある人は、これから受ける性格検査ではしっかり対策をして臨みましょう。
回答に矛盾がある
webテストでは時折、同じ内容の質問を何度も言い回しを変えて行うことがあります。
回答に矛盾が無いかを確認しているのです。
「ライスケール」という、学生が嘘の回答をしていないかを確認するための検査に引っかかってしまう可能性もあるので、一貫した回答を心がけましょう。
回答でマイナスイメージを与えている
回答でマイナスイメージを与えないようにすることも非常に重要です。
もちろん、真摯に回答することは大切です。
しかし「我慢強い方である」という質問に対して「当てはまらない」と回答するなど、正直すぎて悪い印象を与えるのも良くありません。
曖昧な回答が多い
就活生の価値観や性格を確認するにあたって、重要な質問に対して曖昧な回答をしてしまうと、人柄が伝わりません。
何より、自己分析ができていない人材であるとみなされる可能性も高まってしまいます。
就活において、自己分析は真っ先に行うべきものです。
自己分析ができていないということは「就活に対して頑張っていない、やる気のない人材」と思われる可能性があります。
よって、さまざまな点から考えて、曖昧な回答は避けるべきであると言えます。
回答の結果が求める人物像と合わない
性格検査では、就活生が求める人物像と合っているかを確認しています。
例えば、チャレンジ精神豊富な人材を求めている企業を受ける場合を例に出します。
ここで「新しいことに興味がある」という設問に対して「当てはまらない」と回答してしまうと、マイナス評価となってしまいます。
未回答を残している
性格検査は全問回答が前提です。
そこで未回答を残してしまうと、モチベーションが低い人材であるとみなされてしまう可能性があります。
自分のことを伝える機会を蔑ろにしていると思われてしまうので、必ず全ての設問に回答するようにしましょう。
【性格検査の対策】 性格検査でみられる4つの評価ポイント
ここからは性格検査で見られる4つの評価ポイントについて詳しく紹介していきます。
それぞれのポイントを踏まえた上で回答することで、企業に与える印象は大きく変わってきます。
1:行動特性
行動特性は、就活生個人が持つ行動の原理やその背景となる考え方を指すものです。
いろいろな行動を通して状況を分析することでわかるものです。
性格検査において行動特性を測る項目には下記のようなものが挙げられます。
- 社会的内向性(社交的か田舎)
- 内省性(思慮深さ)
- 持続性(忍耐強さ)
- 身体的活動性(身体を動かすことは好きか)
- 慎重性(計画的に物事を進められるか)
上記に関連していると考えられる設問では、行動特性について問われていると考えれば良いでしょう。
2:意欲
意欲は文字通り、目標や憧れを達成するために積極的に取り組む姿勢、行動しようとする意志のことを指します。
この設問の場合、「必ずこの選択肢を選ばなければならない」というわけではありません。
しかし、選択肢の中で「仕事において積極的である」ことがアピールできる選択肢を選んでおきたいところです。
性格検査で「意欲を測る項目」には下記のようなものが挙げられます。
- 向上欲求(成長する意欲)
- 挑戦欲求(目標にチャレンジする意欲)
- 自律欲求(自分の意志で取り組む意欲)
- 探究欲求(さまざまなことを探求する意欲)
- 啓発欲求(周囲に良い影響を与える意欲)
- 承認欲求(他者に認められようとする意欲)
3:情緒
情緒はさまざまな喜怒哀楽などの感情や心の動きを表すものです。
自分の感情のコントロールの仕方などを判断されることが多く、ストレスへの対処法などがその代表例です。
- 楽観的か、悲観的か
- 自分の意見を持っているタイプか、周りに合わせるタイプか
などを見られることが多いと言えます。
性格検査において情緒を測る項目には下記のようなものが挙げられます。
- 敏感性(物事に敏感か)
- 自責性(責任感があるか)
- 気分性(気分によって行動が変わるか)
- 独自性(独特な考え方を持っているか)
- 自信性(自分に自信を持っているか)
- 高揚性(気分が変化しやすいか)
4:ライスケール
ライスケールは先ほども少し触れましたが、学生の回答に嘘が混ざっていないかを判断するものです。
性格検査には豊富な質問の項目があります。
その中には「就活生が嘘をついていないか」を見極めるための質問もあるのです。
この質問において何問該当してしまったかによって、どのくらい正直、かつ誠実に回答する人材なのかを確認しています。
引っかかるほど不合格が近づいてしまうので、注意しましょう。
ライスケールの質問例には下記のようなものがあります。
- 生まれてから今まで一回も失敗したことがない
- 自分はこれまでの人生で嘘をついたことがない
- 嫌いな人間は一人もいない
- これまで人に一切の迷惑をかけずに生きてきた
【性格検査の対策】性格検査を実施しているwebテスト
ここからは性格検査を実施しているwebテストについて詳しく紹介していきます。
下記の7点は就活でよく遭遇するwebテストなので、確認しておきましょう。
SPI
SPIの性格検査は3部構成になっており、問題数は合計で約300問です。
解答時間は約30分ですが、時間切れになることは滅多にないので落ち着いて取り組みましょう。
第一部と第三部では考え方や行動に関する文章がAとBに表示されます。
- 「Aに近い」
- 「どちらかというとAに近い」
- 「どちらかというとBに近い」
- 「Bに近い」
の4択で答えていくのが回答方式となっています。
一方、第二部では考え方や行動に関する文章が1つ表示されます。
- 「当てはまる」
- 「どちらかというと当てはまる」
- 「どちらかというと当てはまらない」
- 「当てはまらない」
の4択で回答します。
SPIは数あるwebテストの中でも、最も多く出題されるものの一つです。
SPIの対策ができていない人は就活で成功できないと言われるほど頻出のwebテストなので、しっかりと対策してから臨むようにしましょう。
SPIについての詳しい解説は以下の記事をぜひ参考にしてみてください。
玉手箱
多くの企業が実施しているwebテストの一つに、玉手箱が挙げられます。
玉手箱ではパーソナリティと価値観の2つの性格検査が実施されます。
ただし、ほとんどの場合は「パーソナリティ」だけを聞いてくるので、後者は簡単に対策しておくだけでも良いでしょう。
玉手箱4つの文章を1問として、合計で68問出題されます。
制限時間は約20分と短いですが、「大慌てで回答しなければ終わらない」わけではないので、落ち着いて一つひとつ回答しましょう。
4つの文章の中で「最も当てはまるもの」「最も当てはまらないもの」を回答していく回答方式です。
TAL
SPIや玉手箱ほどではありませんが、多くの企業が導入しているwebテストにTALが挙げられます。
こちらも、就活にあたってはしっかりと対策しておきたいテストです。
TALの性格検査は文章形式と図形形式の2種類をこなしていくのが特徴です。
文章形式では、日常でありうる状況の設問に対して7つの選択肢から1・2つ解答します。
計36問を15分で回答していきますが、時間には比較的余裕があります。
図形形式では、「入社後に活躍している自分」などのお題が課され、お題に沿って線が引かれた画像の上に図形を配置していくので、図形問題が苦手な人はしっかり対策しておきましょう。
図形形式は全1問を5分で回答します。
TALの注意点
TALでは選んではいけない選択肢が存在します。
これを選んでしまうと、企業の採用担当者にマイナスなイメージを与えてしまう可能性が高いです。
あらかじめ、念頭に置いた上で問題に臨むようにしましょう。
有名な2つとしては
- あなたが手に持っても良いと思う卵を次の選択肢から2つ選びなさい。」
- 「自動販売機が壊れてお釣りが出ない時、あなたならどうする?」
というものが挙げられます。
前者に関しては「模型の卵」「輪切りにしたゆで卵」は避けた方がいいと言われています。
また、後者は「自動販売機を蹴飛ばす」「自動販売機の会社に電話して文句を言う」は避けるべきとされています。
YG性格検査
YG性格検査は筆記で行われるテストなので、厳密に言うとwebテストではありませんが、対策しておきたいところです。
性格に関する問題120問を「はい」「いいえ」「どちらでもない」で答えるのが回答形式となっています。
この検査では
- 「行動特性」
- 「情緒の安定性」
- 「人間関係」
- 「仕事への取り組み」
- 「リーダー資質」
- 「知覚特性」
などが測定されています。
これらを念頭に置いた上で、しっかりと対策を行いましょう。
TG-WEB
TG-WEBの性格検査は種類が多く、企業が数種類を組み合わせて出題するのが特徴です。
計数・言語・英語・性格テストの4分野があり、いずれも難易度が高いので、何も対策しないとまともに回答できないことでしょう。
内田クレペリン検査
クレペリン検査は筆記テストです。
クレペリン検査では横一列に数字が並んでおり、隣り合う2つの数字を足して回答していきます。
「1・5・7・3・9・5」と並んでいた時の回答は「6・2・0・2・4」で、繰り上がった場合は1の位のみを答えます。
15分間を2セット行うため、非常に集中して作業することが求められます。
よって、集中力に自信が無い人はしっかり対策してから臨みましょう。
GAB
GABの性格検査は全部で68問あります。
問題に対して「当てはまる(当てはまらない)」「自分に近い(遠い)」というように回答していくタイプの問題です。
パーソナリティ(性格)やバイタリティ(活力や体力)、チームワークなどを測るためのテストです。
【性格検査の対策】性格検査で出される問題の例
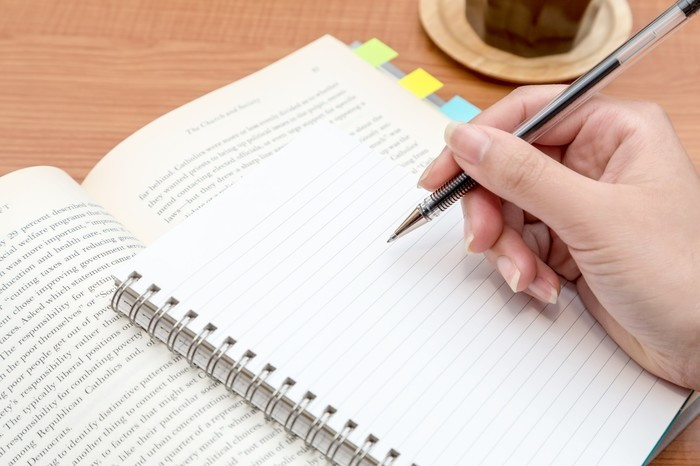
ここでは、具体的な質問例と回答例の一部をご紹介します。
企業はどのような性格の持ち主を好むのか、また、回答にはどのような形式があるのかを知っておきたい方は、ぜひチェックしてみてください。
質問の種類
①職種について コンサルティング業界など、「矛盾がなく道筋を立てて説明できるスキルが必要な職種」に合うかどうか見極める場合。
ex)質問.「物事を深く考えすぎる傾向がある」⇒回答.「あてはまる」がいい ・考えることや論理立てるのが苦手な人は非適性とされやすい
②企業の特色について 外資系企業など、「個々の実力が直接成果につながるなど、結果を重視する企業」に合うかどうかを見極める場合。
ex)質問.「思いやりがないのはよくない」or「不合理であるのはよくない」⇒回答.「不合理であるのはよくない」がいい ・合理性が求められるため、協調性を重視する人は向いていないとされやすい
③社会的モラルについて 「道徳観や倫理観を持っているかどうか」を見極める場合。
ex)質問.「嘘をよくつく方だ」⇒回答.「いいえ」がいい ・嘘をつくことは信用に欠けると判断される
④バランスがとれた考え方について 「柔軟に物事を捉えられるかどうか」を見極める場合。
ex)質問.「落ち込みやすい方だ」⇒回答.「どちらかといえばあてはまる」もしくは、「どちらかといえばあてはまらない」がいい ・「あてはまる」は、失敗した時に落ち込みすぎる印象を与えやすく、一方「あてはまらない」は、楽観的で責任感がないという印象を与えやすい
このように、企業によって求める回答が異なる場合があり、考え方に偏りのない人物を好む傾向にあります。
回答の種類
- 2択「はい」or「いいえ」/「Aに近い」or「Bに近い」
- 4択「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」「どちらかといえばあてはまらない」「あてはまらない」(「どちらともいえない」が入る場合もある)
回答の形式は、それぞれの企業の判断基準によってさまざまです。
【性格検査の対策】性格検査での企業の判断例
企業ごとに合否のために重視する結果は異なります。求める職種や現在の人材の性格のバランスを見て採用しているケースも少なくありません。
どういった判断で不採用を決めてしまうのか、その一例を見てみましょう。
仕事や人に対する姿勢
仕事や人に対する姿勢が企業の基準に見合わない場合は、落とされる場合があります。
特に批判的な姿勢が仕事や他人に対してみられる場合には、周囲への影響を考えて選考から落とされてしまうでしょう。
壁にぶつかったときの姿勢
企業ごとに重視する解決策が異なる場合があります。
積極的にまずは行動する姿勢をみせることを評価する企業や、一度立ち止まり具体的な解決策を思案する思考力を評価する企業もあります。
コミュニケーションの取り方の傾向
自分の考えを押し付けてしまう傾向や、何事も結論をまず出そうとするなど、企業によってはあまり評価されないコミュニケーションの取り方があります。
企業への適応、協調性の重視を求める企業は多いです。
【性格検査の対策】性格検査の対策〜基礎編〜
ここまで豊富にある性格検査について、それぞれ詳しく紹介してきました。
ここからは性格検査の対策において基本となるものを紹介していきます。
下記の対策はESの作成にも役立てられるものなので、しっかり取り組みましょう。
自分の性格を知る
まずは自分の性格について知ることが大切です。
自分の性格を知ることで、性格検査と面接で一貫性を保つことができます。
性格検査のおすすめは3つあります。
1つ目は「クリフトストレングス」です。
有料ではありますが自分の特性がはっきり分かり、強みも見つかるため自己PRにも使えます。
2つ目は「LINEで自己分析」です。
残念ながら、ネット上にあるほとんどの自己分析ツールは問題数が少なく、正確性に欠けてしまいます。
しかし、「LINEで自己分析」であれば90問あるので精密に性格を判断できます。
50万人のデータを元に自己分析を手伝ってくれるので、非常に正確性が高いのです。
また、LINE上で行うため空き時間にもすぐでき、回答の練習にもなるというのも魅力的なポイントです。
豊富な業界、職種に対応しているので、誰でも就活に役立てられる幅広さも魅力と言えます。
3つ目は16personalitiesです。
最近流行っており、SNSのプロフィールに書く人も多いほど注目を集めているので、知っている人も多いのではないでしょうか。
16personalitiesであればイラスト付きで自分がどんな人であるかを当ててもらえるので、視覚的にも楽しいというのが魅力です。
企業研究で求める人物像を把握
自己分析の後は、企業研究で求める人物像を把握することが非常に大切であると言えます。
求める人物像を把握するために見るべきポイントは3つあります。
1つ目は公式サイトなどに記載されている「採用メッセージ」です。
どのような人物を求めているか明確にしている企業もあるため、必ずチェックしておきましょう。
2つ目にチェックしておきたいのは、「社員のインタビュー」です。
インタビューを受けている社員は企業にとって模範的な社員であると言えます。
「どこに出しても恥ずかしくない人材」だからそのインタビューに採用されているのです。
そのため、社員の性格や行動がそのまま求める人物像として反映されていることが多いです。
3つ目は「中期経営計画」です。
中期経営計画は企業の未来を描いているのでそのため、どのような人物を育てていきたいかが書かれていることが多いと言えます。
このほかにも説明会やOB訪問の機会などがあれば、活躍している社員の特徴を聞けると良いでしょう。
アピールしたい人物像を紙に書き出す
自己分析で自分の性格、企業研究で求める人物像を知った後は、アピールしたい人物像を紙に書き出すようにしましょう。
もちろん紙ではなくPCのメモやWordなどでも良いです。
性格検査をする中では、似たような質問がいくつか出題されます。
進めていく中で、自分がどう回答したのか思い出せなくなってしまうことが多々ある。
そこで、アピールしたい性格や人物像を書き出して見直しながら進めることで、一貫性のある回答がしやすくなります。
回答がバラバラだとマイナスイメージになるので、一貫した回答が重要なのです。
また、紙の場合は面接の際にも見直せるので、もし電子媒体にメモした場合は印刷して常に持ち歩くようにしましょう。
設問をよく読む
性格検査の問題の中には「〜である」「〜でない」というように肯定と否定の語尾が混ざっているものもあります。
この問題に引っかかってしまうと逆に回答してしまい、意図せず矛盾が生まれてしまいます。
せっかくしっかり対策をしていても、こうした「凡ミス」でマイナスイメージを与えてしまう就活生は意外と多いです。
受験生の時代、国語のひっかけ問題の対策をしていた人も多いでしょう。
その時のことを思い出して、不用意なミスで減点されないよう注意が必要です。
素早く問題に回答する
素早く問題に回答するのも、性格検査を受ける上で重要です。
性格検査で時間切れになることは滅多にありませんが、念のため素早く回答することを心がけ、だらだら回答しないようにしましょう。
素早く回答するコツとしては「1問にかけられる時間を確認しておく」「設問の速読」の2つがあります。
それぞれ、練習の段階から念頭に置いて取り組みましょう。
回答が明らかな問題に注意する
性格検査の中には、回答によって明らかにマイナスイメージを植え付けてしまう問題もあります。
そういった問題には、企業が求めているような、理想的な回答をすると無難でしょう。
「正直に答えることが良い」は基本的な考えですが、このような問題は多少嘘が入ってしまっても仕方ありません。
例:我慢強い方である・周りの意見を尊重する
【性格検査の対策】性格検査の対策〜実践編〜
ここからは性格検査の実践的な対策方法について詳しく紹介していきます。
ここまで紹介してきた対策が終わったら、早速取り組んでみましょう。
模擬検査を受けてみる
本番の性格検査では自分の性格について知ることはできません。
しかし、模擬検査では回答のスピードなどを意識しながら練習でき、その上、自身の性格まで判断できるので、しっかりと取り組んでおきたいところです。
おすすめのツールとしては「LINEで自己分析」が挙げられます。
スマホだけで取り組むことができるので、スキマ時間や移動中にも利用できます。
また、問題数が豊富なのも「LINEで自己分析」の特徴です。
なんと全部で90問も用意されているので、本番さながらに練習することができます。
「LINEで自己分析」を活用して対策し、余裕を持って本番の性格検査に取り組めるようにしましょう。
志望度が低い企業の検査を受ける
志望度が低い、もしくはそもそも志望していない企業の性格検査を受けるというのも、性格検査の対策としては非常におすすめです。
実際に問題を解く空気感を知ることができますし、場数を踏んでおくことで本番も緊張せずに済むでしょう。
おすすめは志望する企業と同じ業界の、別の企業の性格検査です。
出題傾向が似ていますし、重視されるポイントもほとんど同じなので、実践的な対策になります。
求める人物像に当てはまる回答をしていき、そのテストに通過することができれば、自信を持って本命で回答できるようになるでしょう。
【性格検査の対策】業界別求める人物像を理解して対策!
ここまでは性格検査の対策について徹底的に解説してきました。
ここからはいよいよ、業界別にどのような人物像が求められるか解説していきます。
自分の志望業界の人物像を頭に入れ、寄せて回答することで、適性があると見なされやすいでしょう。
しかし、説明する特徴はあくまでも一般論であるため、企業ごとに変えていくことは必須です。
下記の業界を志望している人は、ぜひ参考にしてみてください。
商社
まずは商社を志望する人に向けた、性格検査の対策方法を詳しく紹介していきます。
求められるスキルが多岐に渡り、それぞれの水準も高いので、しっかりとした対策が求められる業界であると言えるでしょう。
商社は国際的な取引が多いので、異なる文化やビジネス慣習に対応できる適応力が求められます。
また、商談や契約の際の交渉力も必須であると言えるでしょう。
また、商社は複数のプロジェクトやクライアントを同時に扱うことが一般的であり、マルチタスクに対応する能力も求められます。
そして何より、常に状況が変化する業界なので、状況の変化に柔軟に対応できることが必要とされています。
また、他業種や国と提携してプロジェクトを進めることもあるため、多種多様な価値観の人と働くにあたり、リーダーシップも求められることが多いです。
この際、より円滑に他国のメンバーとコミュニケーション取るための語学力があればなお良いです。
金融
金融業界も多くのスキルが高い水準で求められる業界なので、しっかりとした対策をしなければ性格検査にも合格できない可能性があります。
金融業界では、何よりもまずリスクを最小限に抑えながら適切な投資判断をする能力が求められます。
よって、データ分析や市場動向の把握が必要と言えるでしょう。
常に情報を仕入れ、それを分析する能力があることをアピールしていきたいところです。
また、金融機関は信頼性が重要であり、顧客との信頼関係を築くスキルが求められます。
よって、常に顧客に寄り添い、適切なアドバイスができることが重要と言えるでしょう。 傾聴力やコミュニケーション力もアピールしたいところです。
SIer(IT業界)
SIer、つまりIT業界にもさまざまなスキルが必要とされます。
まずなんといっても、ITプロジェクトには技術的な理解、そして納期・予算の管理が不可欠です。
そして、クライアントとの円滑なコミュニケーションが非常に重要と言えます。
クライアントと良好な関係を築くことでより日程の相談などもしやすくなるでしょう。
また、何よりもクライアントのニーズを理解し、適切にフィードバックできるスキルが求められます。
クライアントが求めるものを作り上げるには、技術だけでなく、ニーズをしっかり把握することも必要不可欠です。
出版
出版業界にもさまざまなスキルが必要とされています。
まずなんといっても編集力が必要であると言えるでしょう。
出版業界では作家の作品を上手く編集し、ヒット作品を生むことが求められるからです。
また、市場を分析する分析力や、マーケティングにおける創造性も必要とされています。
作品がより多くの人に知られ、より多くの人の手に渡るためには、それを宣伝する能力も必要です。
社会のニーズを把握し、的確に宣伝できる人こそ、必要とされているでしょう。
広告
広告業界は創造性、コミュニケーション能力、折衝力を駆使して、独創的かつ効果的な広告キャンペーンを立案し実行する業界です。
広告などのキャンペーンを通してクライアントの商品やサービスの魅力を消費者に伝え、購買意欲を刺激することが求められます。
つまり、市場の動向を理解し、クライアントのニーズに合ったクリエイティブな提案をする能力が不可欠です。
クライアントとの信頼関係を築き、効果的な広告戦略を実現するためには、優れたコミュニケーションと交渉技術も必要です。
コンサル
コンサルティング業界ではクライアントのビジネスや組織が直面する複雑な課題を深く理解し、データ駆動の分析を行って具体的かつ実行可能な解決策を提案する必要があります。
クライアントとの強固な信頼関係の構築が不可欠であり、コミュニケーション能力と表現力が求められます。
また、複雑な情報をわかりやすく整理し、効果的に伝える必要もあるので、分析力も必須です。
また、コンサルの仕事は一言でいうならば「問題解決」です。
クライアントの問題を的確に解決するため、問題解決能力も備え付けておきましょう。
食品
食品業界は消費者の健康と直結する分野であり、消費者の嗜好・市場のトレンドを分析力を活用して分析し、それに基づいて新しい製品を開発する能力が求められます。
競争が激しい市場であり、差別化を図り、顧客の注意を引きつけるためには、創造性と革新的な製品開発が不可欠です。
また、食品の安全への意識と品質は最優先事項であり、厳格な衛生管理と品質保証が必要とされます。
製造過程における安全への意識、法規制の遵守、消費者への正確な情報提供など、高い責任感と誠実性が求められる業界です。
化学メーカー
化学メーカーは化学製品の設計、製造、販売を行う業界で、イノベーションと安全性が極めて重要な要素です。
新しい材料、化学物質、製品、または製造プロセスの開発を通じて、さまざまな産業や日常生活に貢献する製品を生み出すことが求められます。
また、化学物質の取り扱いには潜在的な危険が伴うため、製造から廃棄に至るまでの各ステージで厳格な安全基準を遵守することも重要です。
航空
航空業界では特に協力して作業に取り組むためのチームワークが求められます。
また、航空業界では安全性が最優先事項とされているので、安全管理の観念も非常に重要視している企業が多いです。
航空業界は常に人の命を乗せて業務を行うので、他の業界と比べても責任重大であり、安全管理も徹底されているのです。
そして何より、顧客ファーストの考えが根付いている業界でもあります。
常にお客様のことを優先し、安全を管理しつつ、チームワークを持って業務に取り組める人こそ、航空業界に向いていると言えるでしょう。
エネルギー
エネルギー業界にはプロジェクトマネジメントのスキルが必須です。
特に大規模のエネルギープロジェクトの計画や運営においては、プロジェクトマネジメントのスキルが大いに発揮されます。
そして大規模なグループをまとめることが多いので、リーダーシップも併せて必要とされることが多いです。
【性格検査の対策】おすすめの無料性格検査
採用の面接や試験では、緊張する方がほとんどではないでしょうか。ましてや、希望する企業ではなおさらでしょう。
ここでは、無料で性格検査ができるおすすめのサイトを4つご紹介します。あらかじめ検査を体験しておきたい方は、ぜひチェックしてみてください。
適性検査対策 WEBテスト
就職試験によく出る問題の対策として活用されている、全国一斉に行うWEB模擬テストです。多くの企業が実際の一次選考などに利用しています。
採点結果は分野ごとに点数が分かれているため、自分はどの分野が苦手なのかが一目でわかります。苦手分野を把握できるため、実力アップへつながるでしょう。
お試し!Webテスト
主なWebテストでもある、SPI、玉手箱、Web‐CABなどの再現問題を体験できます。実際のWebテスト形式とは異なる場合もあるため、あくまで心構えをしておくための参考として、利用しましょう。
LINEで自己分析
「LINEで自己分析」は本記事で何度も紹介していますが、非常におすすめの性格検査ツールです。
問題数が豊富で、90問も出題され、精密に性格を判断できます。
また、スマホで簡単に回答できるのも魅力です。
移動時間などのスキマ時間に取り組むことができ、そして性格検査の練習にもなります。
忙しい就活生にとって、性格検査は「全ての時間を注ぎ込んで取り組むもの」ではありません。
ESの作成や面接の対策に時間を割くためにも、「LINEで自己分析」を活用して、効率良く性格検査の対策を進めていきましょう。
キミスカ適性検査
キミスカのサイト内にある自己分析診断ツールです。自分の強みや価値観の傾向、職務適性やビジネス戦闘力などがわかります。
数分で診断できるようになっているため、手軽に試したい時におすすめです。
Future Finder
生まれ持った基本的な性格と、ビジネス面に限定した上で活かされる性格を分析できます。
検査結果は、特性やモチベーションなど、カテゴリごとに数字で表されます。わかりやすい性格検査になっているため、客観的に自分を知ることができるでしょう。
【性格検査の対策】性格検査のポイントは「正直に答えること」

性格検査は正直に答えることが重要です。
先述にもある通り、性格検査はミスマッチを防ぐ目的としても実施されています。「〇〇業界に魅力を感じているけれど、自分の性格的には別の業界の方が活躍できるのではないだろうか」などのように、自己分析をしっかりと行いながら検査を受けるようにするといいでしょう。
【性格検査の対策】性格検査は万全の対策をとって臨もう
選考する手段として、ほとんどの企業が性格検査を活用しているため、この検査は避けて通れないといえるでしょう。
本番に備えて自分を分析したり、模試を受けたりして、自分の持ち味をアピールできるよう万全の対策を講じてから臨みましょう。











