
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
理系の卒論を書くとき、一番重要なのはテーマの選定です。
新規性も求められるため、ここが厳しいと感じる方も多いでしょう。
ただ新規性はゼロから考える必要はなく、過去の研究結果なども参考になります。
もし自分1人で考えつかない場合は、教授や先輩のアドバイスも参考にしましょう。
今回は理系の卒論テーマを決める方法や、おすすめのテーマ例などをご紹介します。
テーマ次第で卒論の難易度も変わるため、テーマ選びは慎重に行ってください。
【研究テーマの決め方】研究テーマの決め方は2種類ある
1.自由に決めることができる
2.大枠が決められている
まず初めに、研究テーマの決め方は2種類あります。
研究室に所属していないひとは研究テーマが与えられていないので自由に決められることが多いです。
研究室に所属している人は、研究室のテーマなどによって大枠が決められていることがあります。
①自由に決めることができる
主に研究室に所属していない人が該当者にあたります。
研究テーマが決まってないことで違う研究室の内容の卒論を書いても良いですし、興味
を持っていたことについて記載しても良いでしょう。
②大枠が決められている
主に研究室に所属している人が該当者にあたります。
自身の研究テーマの応用を卒論の内容を書いても良いでしょう。
【研究テーマの決め方】テーマ決めの流れ
理系の卒論では、まずテーマを決めることから始めましょう。
テーマを決めるには、まず興味のある論文を読んでみる、教員にアドバイスをもらうなどがあります。
さらにはアドバイスに沿った論文を読んでみる、仮説から新規性のあるテーマを探す、教員に相談してみるなどが参考になるかもしれません。
なかには理系自体の研究テーマが思いつかない場合や、研究室関連のテーマが思い浮かばないこともあるでしょう。
テーマ次第で卒論の難易度も決まるため、まずはテーマ決めの流れを把握することが大切です。
自己分析をする
まずテーマについて具体的なことが決まっておらず、まったく前に進まない人は自己分析をしましょう。
研究室によっては教授や先輩からテーマを決めてくれることもありますが、そうでないこともあるからです。
テーマを決める際には、これまで自分が何に興味をもって、どんな選択をしてきたのかを考える必要があります。
自分のこれまでを客観的に振り返ることで、意欲をもって取り組みやすい事柄がはっきりするでしょう。
卒論は先輩や教授がアドバイスしてくれることもありますが、最終的に自分で完成させなくてはいけません。
このため自分が興味をもっていて、主体的にいろいろなことを調べたいと思えるほうが良いでしょう。
またある程度長期間そのテーマに向き合うため、おもしろいと思えなければきびしいかもしれません。
研究室で自分の興味のある論文を読む
卒論のテーマを探すならまず、研究室で自分が興味のある論文を読んでみるのがおすすめです。
テーマ決めだけでなく、研究室で過去に先輩が書いた論文は自分が書くうえでも参考になります。
実際に書かれた論文を読めば、同じ研究内容でも違った見方をできるようになるでしょう。
また研究室の論文を読んでおけば、教員や先輩から助言をもらいやすくなるのもメリットです。
論文を参考にするときには、できるだけ自分の考えているテーマと似た分野の論文を読むのがポイントです。
似たテーマであれば、教員や先輩も自分の予備知識から助言してくれるでしょう。
またテーマから多少ずれていても、できれば30冊以上は読んでおくのがおすすめです。
まずは論文を読み慣れることから始め、書くうえでの参考にしてみましょう。
教員にアドバイスをもらう
もしテーマ探しに行きづまったときには、教員におすすめの研究テーマを聞くのもよいでしょう。
ある程度範囲をしぼってもらえれば、自分でも決めやすくなります。
テーマも早く決まりやすいので、人に聞いてみるのも1つの方法です。
教員は生徒の研究内容や、興味のある分野を把握しているので、いわば論文のプロです。
生徒にどこまで助言してくれるかは個人差もありますが、質問すればテーマも決まりやすいでしょう。
教員にテーマについて相談をするなら、今旬な研究テーマ、教員がやろうとしているテーマ・研究で追加したいことなどを、聞くのがおすすめです。
そのうえで教えてもらったテーマに関連する論文があれば、PDFファイルなどをもらいましょう。
もらった論文はぜひ読んでおき、テーマ選定の参考にしてみてください。
アドバイスに沿った論文を読む
論文について教員にアドバイスをもらったら、つぎに一番近いテーマの論文を読みましょう。
PDFファイルをもらったらそのまま読めますし、「Google Scholar」で検索すれば近いテーマの論文もすぐに見つかります。
内容が似ているものは参考にしやすいので、できればすべてダウンロードして読みつくすのもポイントです。
もし探している最中に参考になりそう、面白そうと感じたら論文名をメモするのもおすすめです。
専攻分野で興味のある論文は、実際に卒論で使えるテーマだといえます。
読んでいるうちに「この論文はここの検証が足りないな」などの、箇所が出てくるかもしれません。
その部分を自分の卒論のテーマにする方法もあります。
すでに行われている研究を知っておけば、新規性も出しやすくテーマを決める参考にもなるでしょう。
論文を参考に仮説を立てたうえで新規性のあるテーマを考える
論文をある程度読んだら、つぎは自分で仮説を立て、そのなかに新規性があるかを考えつつテーマを決めましょう。
先行研究が終わればあとはその論文に、新規性やストーリー・ゴール(目標)を追加できるかを検証します。
論文では必須となる新規性やストーリーですが、これにゴールが加わるだけでも卒論は書きやすくなります。
特に重要なのは新規性で、誰も取り組んでいない研究内容を考えることが大切です。
ストーリーでは、新規性によって生まれるメリットなどを考えましょう。
そしてゴールではどういった実験をして、どういった結果が生まれるのか仮説を立てましょう。
なかには「新規性は見つかったけれど、ストーリーが思い浮かばない」などのケースもあります。
そういったときにも定期的に教員や先輩にアドバイスをもらえば、1人で悩むことも少なくなるでしょう。
教員と相談する
論文のテーマが決まったら、自分が決めたテーマでやっていけるのかなど、教員に相談しましょう。
チェック内容は研究所によっても違いますが、最後はテーマの確認をしてもらうのがおすすめです。
テーマの最終チェックでは、たとえば新規性やストーリーがしっかりしているか、実験内容は現実的かなどがあります。
そして特許に該当するような内容か、研究にはどういった機材が必要なのかなどを確認してもらいます。
新規性やストーリーがしっかりとしていれば、教員も理解しやすく、適切なアドバイスを受けられるでしょう。
教員に相談すれば欠点なども見つかりやすくなり、テーマの変更などで時間を取られることもなくなります。
もし教員が「いまいちなテーマ」と感じているようであれば、どこが悪いのかも質問しましょう。
研究テーマは理系就活においても重要
理系の学生にとって、研究テーマは就職活動において自分の専門性や能力を示す重要な要素です。
単なる履修内容や学部名よりも、どのような課題に取り組み、どのような力を身につけたかを伝えることで、企業側に具体的なイメージを持ってもらうことができます。
研究内容の整理と表現を工夫することで、選考時のアピール力が大きく向上します。
専門知識・能力のアピール
研究テーマは、学生がどの分野に関心を持ち、どれだけの知識や技術を習得しているかを伝える指標となります。
特に実験方法や解析手法、使用機器、対象データの扱い方などを明確にすることで、理系学生ならではの専門性を効果的に伝えることが可能です。
テーマに独自性がある場合や、困難な課題に粘り強く取り組んだ経験がある場合は、それ自体が強みとして評価される要素になります。
企業は即戦力としての素養を見ているため、どのような実務に通じる力を持っているかを意識して伝えることが大切です。
論理的思考力・問題解決能力の証明
研究は課題の発見から始まり、仮説の構築、実験や検証、データの解析、結果の考察という段階を経て進んでいきます。
このプロセスを通じて身につく論理的な思考力や問題解決への姿勢は、多くの企業が重視する能力です。
自ら問いを立て、それを根拠に基づいて検証し、結果から新たな知見を導き出す一連の取り組みは、職場での課題対応や開発業務に直結するものです。
この力は業界や職種を問わず活かすことができるため、研究活動で得た経験を自身の成長として具体的に語れることが大切です。
入社後の業務への接続性
自身の研究テーマが企業の技術や事業領域と近い内容であれば、その経験は入社後の早期活躍にもつながる要素となります。
研究を通じて得た知識や技術が企業での開発、分析、生産などの実務に応用できる場合、採用担当者にとって非常に魅力的な要素になります。
企業の研究内容や事業分野を把握した上で、自分の研究とどのような接点があるかを明確に伝えることができれば、志望理由や自己PRの説得力が一段と高まります。
研究と業務の接続性を示すことは、入社後の貢献可能性を伝える重要な材料となります。
研究テーマ選定の準備
理系学生にとって研究テーマの選定は、大学生活後半の学びを左右する大きな分岐点です。
このテーマは卒業研究の成果だけでなく、就職活動や将来の進路選択にも大きな影響を及ぼします。
そのため、テーマを選ぶ際は感覚的に決めるのではなく、入念な準備と情報収集が不可欠です。
ここでは、研究テーマを選定する際に押さえておきたい重要な準備のポイントを解説します。
自己分析(興味関心・得意分野・将来の展望)
研究テーマの選定において、まず取り組むべきは自己分析です。
自分がどのような分野に関心を持ち、どのような問いに対して探究心を持てるのかを明確にしましょう。
それに加えて、これまでの学びの中で得意としてきた知識やスキル、身につけた経験を整理することで、テーマ選びの方向性が見えてきます。
将来的に進みたい業界や職種を視野に入れながら、自分のキャリアに結びつく分野を意識することも重要です。
この段階でじっくりと自分と向き合うことで、研究に取り組む意欲や継続力が高まり、成果につながりやすくなります。
興味・能力・将来の展望を軸に研究テーマを選ぶことで、一貫したキャリア設計が可能になります。
指導教員の専門分野・研究テーマの確認
研究テーマをスムーズに進めていくためには、指導教員の専門性や研究環境を十分に理解しておくことが欠かせません。
教員が現在取り組んでいる研究内容やこれまでの実績、学内外の研究ネットワークなどを確認し、それらと自分の興味がどこで交差するかを検討することが重要です。
教員の持つ研究リソースや設備を活用できるテーマを選ぶことで、実験や調査を円滑に進められるだけでなく、指導を受けやすい環境を整えることにもつながります。
また、指導教員との相性もテーマ選びに影響するため、ゼミや研究室の雰囲気を事前に把握しておくことも有効です。
環境と内容の両面から慎重に判断することが、充実した研究生活の第一歩となります。
研究テーマ選定の具体的なステップ
研究テーマの選定は、卒業研究だけでなく、その後の進路や就職活動にも大きな影響を与える重要なプロセスです。
自分の関心と専門性、そして研究の実現可能性を丁寧に見極めながら進めることが、納得のいくテーマ決定につながります。
ここでは、研究テーマを選ぶための具体的なステップを段階ごとに整理して紹介します。
興味のある分野の深堀り
自己分析によって見えてきた興味のある分野を、さらに掘り下げる段階です。
学術論文や専門書、新聞記事、学会発表などを通じて、現在どのような研究が行われているのか、どのような課題が残されているのかを把握します。
複数の分野に関心がある場合は、それぞれの分野で同様の調査を行い、研究対象としての面白さや課題の明確さを比較することが有効です。
この段階で得た情報は、後の研究計画やテーマ設定の質を大きく左右します。
興味を具体的な研究対象に結びつけるための重要な準備段階となります。
既存の研究テーマの調査と分析
深堀りした分野の中で、既に行われている研究テーマを調査し、どのような知見が蓄積されているかを分析します。
この過程では、どの分野が成熟しているのか、どの視点が未解決であるのかを見極めることが重要です。
また、同じテーマでも異なる手法や視点からのアプローチが存在するため、それらを比較検討し、自分の研究の立ち位置を明確にしていきます。
既存の研究内容を丁寧に整理することで、独自性や実現性のあるテーマへとつなげやすくなります。
このステップを通じて、自分が新たに加えられる価値や観点を探ることができます。
研究課題の発見・設定
既存の研究の分析や自分の関心をもとに、取り組むべき研究課題を明確に設定する段階です。
研究課題は曖昧ではなく、具体性と学術的意義を両立させたものである必要があります。
また、卒業研究として実行可能な範囲に収めることも現実的な判断として重要です。
テーマの背景や課題意識を言語化できるようにしておくと、その後の研究設計やプレゼンテーションにも活用しやすくなります。
しっかりと整理された研究課題は、指導教員や外部の人に対しても理解されやすく、フィードバックを得る際にも有効です。
テーマの具体化(目的・内容・方法論)
設定した研究課題に対して、どのような目的を持ち、どのような内容を扱い、どのような手法で研究を進めるのかを具体的に明文化する段階です。
目的が曖昧だと研究が迷走する可能性があるため、解明したい現象や得たい成果を明確にします。
さらに、文献調査、フィールド調査、実験、シミュレーションなどの中から、最も適切な方法論を選定します。
この段階では、研究計画書の骨組みを作成する意識で取り組むと良いです。
研究の設計が具体的になることで、全体像が見えやすくなり、実行への見通しも立てやすくなります。
実現可能性の検証(期間・設備・予算・倫理)
テーマを具体化した後は、それが現実的に実行可能かどうかを多角的に検証することが必要です。
研究期間内に完了できるスケジュールか、使用する実験機器やソフトウェアが研究室にそろっているか、費用負担が過大でないかを確認します。
また、扱う対象や手法によっては倫理的配慮が必要になる場合もあるため、事前に確認しておくべきです。
研究の途中で大きな障害が発生しないようにするためには、この段階でのリスク管理が欠かせません。
実現性が明らかになっているテーマは、安心して継続的に取り組むことができます。
指導教員との綿密な相談と方向性の確認
テーマの内容と実現可能性を整理したら、最終的に指導教員と相談し、方向性の確認を行います。
教員の専門的な視点からアドバイスを受けることで、自分では見落としていた課題や改善点に気づくことができます。
また、テーマに関して許可が下りるかどうか、研究室内でのリソースの配分が可能かといった実務的な確認も必要です。
一方的に決めるのではなく、フィードバックを受けながら内容を修正していく姿勢が求められます。
このプロセスを丁寧に行うことで、納得度の高い研究テーマにたどり着くことができます。
研究テーマ設定後の展開
研究テーマが決まった後の取り組みは、就職活動でも高く評価される重要な経験になります。
単に研究を進めるだけではなく、計画的に活動し、成果を外部に発信する力まで求められます。
この段階で得られる知識や姿勢は、将来の社会人生活にも直結する貴重な成長機会です。
ここでは、研究テーマ設定後に行うべき具体的な展開について解説します。
研究計画書の作成
研究テーマを決定した後は、そのテーマに沿った研究計画書の作成を行います。
研究の目的、取り組む内容、使用する方法、スケジュール、必要な設備や予算などを明確に記述し、今後の活動を効率よく進める土台とします。
計画書を作ることで、自分の研究の方向性や達成目標を客観的に見直すことができ、実現可能性の検証にも役立ちます。
また、研究を進める過程で計画の見直しが必要になることもありますが、あらかじめ骨組みがあることで柔軟な対応がしやすくなります。
丁寧に作成された計画書は、指導教員との意思疎通にも重要な役割を果たします。
研究活動の実施
計画書に基づいて、実際の研究活動を主体的に進めていく段階です。
実験、観察、データ収集、文献調査など、テーマに応じた手法を用いながら、仮説の検証と結果の蓄積を行っていきます。
この過程では、専門知識の深化とともに、トラブルへの対応力や粘り強く継続する姿勢も培われます。
計画通りにいかない場面も多くありますが、その都度原因を分析し、改善策を講じることが、実践的な課題解決力の養成にもつながります。
研究の中で得られた経験は、自己PRや面接でも活用できる貴重な素材になります。
研究成果の発表・論文作成
研究が一定の成果を上げた段階で、学内外での発表や論文執筆を行います。
卒業論文としてまとめるだけでなく、学会発表やポスターセッションなどに参加することで、研究成果を広く発信する機会が得られます。
この経験は、専門性だけでなくプレゼンテーション能力や論理的表現力の証明にもなります。
また、他者からの質問やフィードバックを受けることで、研究をさらに洗練させることができます。
自分の取り組みを外部に伝えるという姿勢は、企業でも評価される重要な力となります。
研究テーマ選定における失敗例と対策
研究テーマの選定は、卒業研究やその後の就職活動に大きな影響を与える重要なプロセスです。
しかし、慎重に進めなければ、テーマ設定の段階でつまずき、研究の進行やキャリア設計に支障が出る可能性があります。
ここでは、研究テーマ選定における失敗例と、その対策について具体的に解説します。
興味本位だけのテーマ設定
研究テーマを選ぶ際、自分の興味を大切にすることは重要ですが、それだけに偏ってしまうとリスクを伴います。
実現可能性や学術的意義、将来のキャリアとの関連性を無視したテーマは、研究の進行が滞ったり、成果が就職活動に結びつかない事態になりかねません。
特に、自分の関心が強くても、必要な知識や技術、指導体制が整っていない場合は、研究が孤立しやすくなります。
対策としては、興味を持った段階で一度立ち止まり、指導教員と相談することが効果的です。
実現困難なテーマ選択
意欲的な姿勢から、規模が大きすぎるテーマや高度な設備を要する研究を選んでしまうケースがあります。
しかし、研究期間や環境には制約があり、それらを超えたテーマは思うように進まず、挫折やモチベーション低下の原因になります。
研究には柔軟な修正力が求められますが、そもそも設計段階で現実的な範囲に収めておくことが重要です。
テーマ設定時には、必要な実験機器、使用可能な施設、費用、作業時間の見積もりなど、実行条件を明確に確認しましょう。
また、過去にその研究室で扱われたテーマの傾向を参考にすることで、無理のない計画が立てやすくなります。
指導教員とのコミュニケーション不足
研究活動において、指導教員との連携は欠かせません。
相談や報告を怠ると、研究の方向性がずれたり、問題発生時の対応が遅れたりする可能性があります。
特にテーマの初期段階では、研究の進め方に不安を感じることも多いため、適切なアドバイスを受けながら進めることが望まれます。
また、研究室ごとに運営スタイルや評価基準が異なるため、方針を共有することもトラブル回避につながります。
定期的に進捗を報告し、疑問や課題があれば積極的に相談する習慣を身につけましょう。
【研究テーマの決め方】卒論に適したテーマとは?
卒論のテーマは、どこの研究所に入るかで内容もほぼ決まります。
そのため具体的なテーマを、研究室の教員に相談することも多いでしょう。
卒論に適したテーマ選びには、新規性がある内容か、自分が興味をもてる内容かが大切です。
テーマを選ぶときには自分から提案もできますが、教員や先輩の論文を踏襲することがほとんどです。
また卒論のテーマ選びでは、研究所に伝わる既存テーマと新規テーマがあり、メリットなどで選ぶのもよいでしょう。
ただテーマ選びに迷ったときには、既存テーマを参考にするほうが卒論を書きやすくなります。
新規性がある内容
理系の卒論では、すでに研究されたテーマを利用しても、卒論としては認められません。
そのため内容に新規性があるかどうかは重要です。
卒論のテーマ選びで迷ったときには、教員や先輩の論文を参考にすることもあるでしょう。
ただ先輩と同じテーマを選べば、それは既出のテーマであり新規性がないと思われてしまいます。
卒論で重要視されるのは、新規性はもちろんですが独創性も求められます。
先輩や教員の論文はあくまで参考程度に留め、それに新しい要素を加えるか、もしくはまったく新しいテーマを考えるようにしましょう。
また新規性=ゼロから考えるものとは限りません。
そのため手軽に新規性を出したいなら「この実験では、ここが足りないかも」など、先輩のテーマを参考にするのもおすすめです。
自分が興味のある内容
教員におすすめされたテーマといっても、自分が興味のあるテーマでなければ実験も進まないでしょう。
そのため、まずは自分が興味のあるテーマを探すべきです。
もし自分が興味をもてるテーマを探すなら、学会に参加してみるのもおすすめです。
学会ではさまざまな研究発表が行われているので、自分の興味がある分野も見つかりやすいでしょう。
また学会に参加すれば、分野ごとの研究動向・仮説をどうやって立てるのか、研究手法なども参考になります。
教員や先輩の意見を聞くことも大切ですが、興味のある分野についての勉強がおろそかになる可能性も高くなります。
そのため先輩や教員などの意見は、参考程度に留めましょう。
あくまで自分の卒論であることを忘れないようにしてください。
研究力をつけるのに役立ちそうな内容
自分の興味のある論文や現在行っている研究を卒論のテーマとして研究するのはもちろん大丈夫です。
しかし、今まで手をつけていなかったテーマや難しいと思っていた研究テーマをあえて選択してみるのもいいでしょう。
新たな研究を行う過程で自身が気づかなかった面白い発見もあるでしょう。
正直楽できるテーマもあり
実際、正直楽ができるテーマを選択するのも良いでしょう。
大学4年生のほとんどの人が来年から就職する中、卒論に時間を取られすぎて思い出を作ることが出来なかった!なんて場合もあります。
自分がやり易い研究テーマで素早く終わらせて、大学生活最後の思い出を作っておきましょう。
【研究テーマの決め方】理系の卒論の書き方
ここで、典型的な理系の学生が卒論を書き上げるまでの流れをざっと確認しましょう。
卒論の書き方を知っておくと、どんなテーマを選べば良いかも、ある程度見えてくることがあります。
特に大学院に進む場合は同じテーマを継続して取り組むこともあるため、卒論の出来は重要です。
一方、学部卒で就職したいと考えていて、卒論をそれほど重視していない人もいるかもしれません。
そのような人でも研究と就活を両立するために、卒論の書き方を知っておいて損はしないでしょう。
研究テーマを決める
研究室に配属されると、まずはこれまでに説明したやり方で、取り組む研究テーマを決めます。
理系の場合、分野に関してはどの研究室に入るかで、ある程度絞られることになるでしょう。
教授が取り組んでいる研究の一部を与えられたり、卒業する先輩のテーマを引き継いだりすることも多いからです。
一方で研究室をあげて取り組んでいる研究があるわけではなく、卒論のテーマが自由な場合もあります。
この場合でも教授からサポートしてもらいやすいよう、テーマ決めの時点で相談しておくのが良いでしょう。
また研究室によっては、その学生が大学院に進みたいかによって、テーマの重さを変えている場合もあります。
このため学部卒で就職したい場合は、テーマ決めの時点でその意思を伝えておきましょう。
卒論の目的や背景を明確にする
テーマを決めたら自分の卒論の目的や背景、最終的にどのような結論を導き出したいかを考えましょう。
これは、理系の多くの学問は論理的な仮説と、実験による検証によって成り立っているからです。
このため、なぜそのような実験を行う必要があるのか、合理的な目的や背景が求められます。
目的を設定するには、これまでそのテーマがどのように研究されてきたのかを勉強することも必要でしょう。
また、卒論は1年程度の短い期間で1つの仮説を立てて、それを実証しなくてはいけません。
このためゴールから逆算して、それに合わせた実験を計画して進めるほうが効率的でしょう。
これらの背景や目的は就活でアピールする際にも重要なポイントになるため、しっかり考えておく必要があります。
実験の準備をする
目的や背景が決まったら、次に実験機材や材料を整えるなどの準備を行いましょう。
まずは自分が導き出したい結論を出すために、どういった裏付けや実験が必要か考えることから始まります。
分野によっては実験の取り組み方や手順が決まっていることもあるため、先行研究の勉強も必要です。
また必要な実験機材や、プログラムなどのソフトウェアがある場合には、教授や先輩に相談しても良いでしょう。
なかには最初の実験だけでは不十分で、再度実験が必要になる場合もあります。
このようなことは、実際に実験に取り組んでみてからはじめて気づけることも少なくありません。
このため、スケジュールには十分余裕をもって、何かあってもやり直しができるように準備を進めましょう。
実験を行い結果について考察する
実験を行いデータがそろったらそれを確認し、想定通りの結果が得られているのかをじっくり考察します。
考察をする中で、好ましい結果が得られなかったときは、次に必要な計画を立てなくてはいけません。
分野やテーマにもよりますが、特殊な機材が必要だったり時間のかかったりする実験の場合は、慎重な計画が必要です。
また実験結果によっては仮説を立て直すなど、研究の方向修正を行う必要もあります。
この判断は卒論自体の出来にも大きく関わってくるため、教授などにアドバイスを求めても良いでしょう。
これらの実験と考察を何度も繰り返して、卒論の完成度を上げてゆくことになります。
考察を記載するときには、先行研究と比べてどのような優位性があるのかも述べましょう。
【研究テーマの決め方】卒論で身に付く力とは?
・文章力
・論理的思考力
・問題解決力
一例にすぎませんが以上が卒論で身につけることのできる能力です。
文章力
卒業論文は少なくとも2万字以上の文字を書く必要があります。
普段は文章を書くのが苦手な人でもある程度卒論を書き進めていくと
文章を書くことに慣れてきてうまくなるでしょう。
論理的思考力
卒論は構成を1から自分で考える必要があります。
研究テーマから実験方法、仮説や結果どの順序で書くのが1番伝わり易いかなど汲み取って作成をします。
そのため、結論から順序立てて書く卒論は論理的思考能力の準備となるでしょう。
課題解決力
自身で課題を発見し、研究を行うことでその課題に関する既存手法を分析し、課題にあった新しい提案を自分で創造できるようになることができます。
このような問題を自身で発見し解決していける課題解決力は社会に出ても役に立つことでしょう。
【研究テーマの決め方】研究テーマの例
理系の卒論テーマを決めるなら、文系とは違った視点で攻めるのもおすすめです。
理系ならではの卒論テーマには、たとえば高性能ビックデータ解析アルゴリズムの研究、ヒューマノイドロボティクスの研究などがあります。
またWebサービス連携による、ソフトウェア構築技法の研究などがあります。
卒論のテーマは、研究室やゼミのレベルによっても内容は異なるでしょう。
ただ大学4年生へ進級するまでに、せめてテーマだけでも決まっていないと書き上げるのは難しいでしょう。
まずはテーマを決めるのが大切なので、以下の例もぜひ参考にしてみてください。
高性能ビックデータ解析アルゴリズムの研究
卒論のテーマなら、ビックデータを正しく分析、もしくは解析するためのアルゴリズム開発に関する研究もおすすめです。
そもそもビッグデータとは、従来のデータベース管理システムでは難しかった大量のデータ群を指します。
形式や種類も、さまざまなものがあります。
インターネットが普及したことで、SNSを利用する人も増えました。
同時に膨大なデータの解析や、処理に関する研究が必須となりました。
もし卒論でテーマにするなら、ビッグデータの解析アルゴリズムの研究は、まさに旬であるともいえます。
理系ならではのテーマでもあり、情報やデータ量にも事欠かないでしょう。
新規性も出しやすいテーマなので、テーマ選びに迷ったときにはぜひ検討してみてください。
ヒューマノイドロボティクスに関する研究
ヒューマノイドロボットの制御には、実験と考察がつきものです。
そのためこちらも理系の卒論テーマには、うってつけといえます。
ただロボットと一口に言っても、芸術・学術・産業などの分野によって、定義は異なるものです。
現実世界で有名なヒューマノイドロボットは、たとえばTelevox(家電製品を遠隔操作)や、エリック(立ったり座ったりなどの動作が可能)などがあります。
例えば学天則(表情を七変化させる)などが有名です。
ヒューマノイドロボットは、走れる・踊れる・歩けるなど、パフォーマーとして活用されています。
しかし現在ではより、実用化する動きが生まれています。
人間にとって重労働といわれる作業を、ロボットが代わりにできるようになれば、よりヒューマノイドロボットが必要とされるシーンも多くなるでしょう。
卒論でも旬の分野なので、研究しがいのあるテーマといえます。
Webサービス連携によるソフトウェア構築技法の研究
卒論テーマを決めるなら、IT系のWebサービスの連携とアプリケーション開発技法を研究してみるのもおすすめです。
データの連携が必要となった背景には、ビジネス環境の変化・グローバル化などがあります。
企業の統廃合・合併・業務提携などで、以前は別々に保持していたシステム間の処理を凍結する必要も出てきたからです。
また昨今ではWebアプリケーションを、短時間で構築する技法が必要とされている背景もあります。
そのためアプリケーションは頻繁に機能変更する必要に迫られ、開発や保守の技法は必要不可欠といえるでしょう。
卒論のテーマを決めるなら、これらの課題をクリアする研究も旬といえます。
ぜひIT系のテーマで新規性を出し、研究結果を卒論にまとめてみましょう。
まとめ
今回は理系の卒論テーマを決めるまでの流れや、卒論に適したテーマなどをご紹介していきました。
理系に限らず、卒論を書き始めるにはまずテーマが必要です。
自分で1から探してもよいでしょう。
しかし内容を濃くしたい、もしくは自分では決められないなどの場合は、教員や先輩からのアドバイスも参考にしてみましょう。
理系ならではのテーマも多くあるので、まず卒論に新規性があるかが重要です。
ぜひテーマの決め方を参考にして、中身の濃い卒論を書いてみてください。

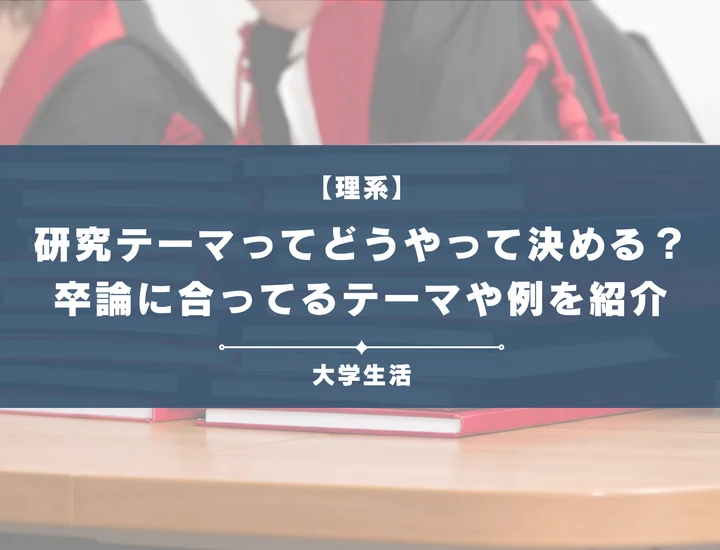


_720x550.webp)





