
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
「そもそも研究概要書って何?」 「企業が研究概要書の提出を求めることがあるのはなぜ?」 「研究概要書はどんなことに気を付けて書いたら良いの?」 このように、就職・転職活動中の方や、現在進路に悩んでいる学生の皆さんには、様々な疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では、研究概要書に関する基礎的な知識に加え、研究概要書が必要となる7つの理由と、書き方の手順についてご紹介しています。
この記事を読むことで、研究概要書の大まかな組み立て方や構成の仕方、注意したい点について把握できます。また、研究概要書を作成した後にすると良いことなどにも触れていますので、既に研究概要書の作成が済んでいる方にとっても参考になるでしょう。
研究概要書を作成しようと考えている方は、是非この記事をチェックしてみてはいかがでしょうか。
就活で必要となることがある研究概要とは?
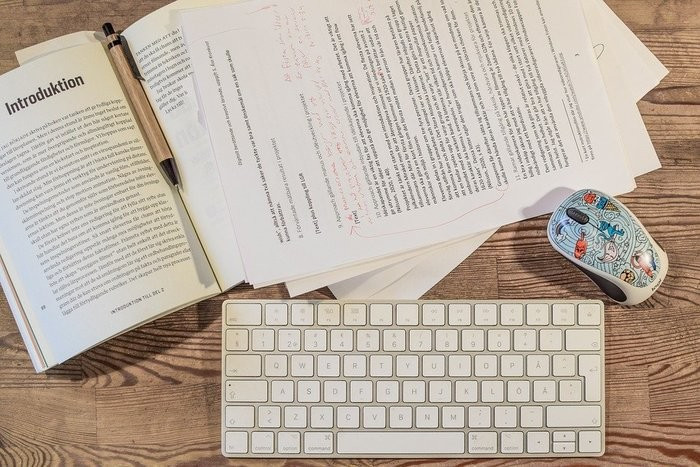
就職活動における研究概要とは、大学や大学院で自らが取り組んできた研究の目的、方法、成果、考察などを簡潔にまとめた資料です。
特に理系の学生に提出を求められることが多く、企業側はこの概要を通じて、応募者がどのようなテーマに関心を持ち、どのような過程を経て成果を出したかを確認しています。
研究の専門性そのものよりも、「情報を整理して伝える力」や「課題を分析・解決する能力」「論理的思考力」「主体的な取り組み姿勢」などが見られています。
そのため、専門用語を並べるだけではなく、専門外の人でも理解できるようにわかりやすく記述することが重要です。
自分がどのような工夫や試行錯誤を経て結果にたどり着いたのか、どのように課題を乗り越えたのかを丁寧にまとめることで、自分の強みや成長をアピールできます。
研究概要に書ける研究内容が思いつかない
研究内容を書くとなった場合どのようなことを書けばよいのかわからない学生さんもいるはずです。
研究が始まっていない方や研究がまだ進んでいない方にとって研究概論を書くのは非常に難しいものになります。
以下の記事では研究内容にどのような内容を書けばいいのかわからない学生向けに研究内容を書くためのポイントを紹介しています。
是非参考にしてみてください。
企業が研究概要の提出を求める7つの理由

では、企業はなぜ研究概要書の提出を求めることがあるのでしょうか。
ここでは、企業が研究概要書の提出を求める理由について7つご紹介しましょう。研究概要書の提出の意図を把握したい方は、是非参考にしてみて下さい。
論理的思考力を確認するため
課題解決能力を判断するため
大学で取り組んだことを知るため
研究によって得た成果を見るため
独自の発想力や工夫ができるか知るため
読みやすく伝わりやすい文章を書けるか見るため
面接で使うため
1:論理的思考力を確認するため
研究活動は、目的の設定から仮説の構築、計画の立案、実験や調査の実施、データ解析、そして結論に至るまで、一貫した論理的プロセスに基づいて進められます。
企業は研究概要を通して、こうした一連の流れを応募者がどれだけ筋道を立てて説明できるかを確認しています。
論理的思考力とは、単に結論を述べるのではなく、根拠となるデータや先行研究を適切に引用し、矛盾なく道筋を示す力です。
もし、途中に曖昧な記述や説明の飛躍があれば、論理的思考が弱いと見なされる可能性もあります。
研究概要では、複雑な内容を他人が読んでも理解できるよう、明確な構成と一貫した説明が求められます。
この能力は、実際の仕事でも企画や課題解決に活かされるため、企業にとって重要な判断材料となるのです。
2:課題解決能力を判断するため
研究では、未解決の問題や前例のないテーマに挑むことが多くなります。
そのため、問題を正確に把握し、原因を分析し、解決方法を導き出す力が求められます。
企業が研究概要を通じて確認したいのは、応募者がどのような課題を認識し、それに対してどんなアプローチで解決を試みたのかという点です。
例えば、実験が思うように進まなかったときにどのように工夫したのか、仮説が誤っていた場合にどのように軌道修正をしたのか、そうした対応の具体性が評価されます。
単に成果を出すだけでなく、困難に対してどのように向き合い、継続的に改善を図ったかという姿勢が見られます。
このような実体験に基づいた課題解決力は、社会人になった後の業務遂行に直結する力とみなされ、非常に重視されます。
3:大学で取り組んだことを知るため
研究概要は、応募者が大学または大学院でどのようなテーマに取り組み、何を学び、どのような姿勢で研究を進めてきたのかを伝える材料となります。
企業は、研究テーマの内容そのものよりも、「なぜそのテーマを選んだのか」「その研究にどれだけ主体的に関わったのか」を重視する傾向があります。
学生時代にどのような問題意識を持ち、課題にどのようなアプローチをしたかという点から、その人の興味関心の方向性や自主性、成長意欲を読み取ろうとしています。
また、研究を通して得た知識やスキルが、実務にどう活かせるかを評価するための手がかりとしても用いられます。
したがって、テーマの専門性だけでなく、取り組む姿勢や成長の軌跡を簡潔かつ丁寧に伝えることが重要です。
4:研究によって得た成果を見るため
研究概要は、研究活動の「結果」を具体的に示す場でもあります。
企業は、応募者がどのようなアウトプットを出したのか、そしてその成果を得るまでにどれだけの工夫や努力があったのかを重視します。
成果とは、論文の執筆や学会発表、特許の出願、プロトタイプの作成、あるいは新規技術の発見など、多様な形があります。
重要なのは、結果の有無以上に、成果に至るまでの過程で何を工夫し、どのように乗り越えてきたのかということです。
企業は、困難な状況下でも粘り強く取り組み、最終的に結果を形にする力を持つ人材を高く評価します。
また、得られた成果が社会や産業にどのように貢献する可能性を持っているかという視点も重要です。
5:独自の発想力や工夫ができるか知るため
研究では、既存の手法をなぞるだけではなく、自ら工夫し、新たな発想を生み出す力が求められます。
企業は研究概要から、応募者がどのような視点で研究に取り組み、どれだけ創造的なアプローチをしてきたかを読み取ろうとします。
例えば、実験条件を工夫したり、独自の解析手法を取り入れたりといった取り組みは、応募者の柔軟な思考力や創意工夫の姿勢を示すものです。
また、課題に対して他とは異なる視点から解決策を模索した経験は、企業にとってイノベーションを生み出す素養のある人材であると受け取られます。
研究概要では、オリジナリティのある工夫があれば積極的に盛り込み、それが研究全体にどう貢献したのかを論理的に説明することが大切です。
6:読みやすく伝わりやすい文章を書けるか見るため
研究概要は、専門的な内容をわかりやすく伝えるための文章力や構成力が試される資料でもあります。
企業は、内容の正確さだけでなく、「第三者にどれだけ明確に、簡潔に伝えられているか」を重要視しています。
専門用語を多用せず、背景や目的を丁寧に説明し、論理的に内容を展開できているかが評価の対象となります。
また、図表や箇条書きなどを使って視覚的にもわかりやすい資料になっているか、全体の構成が整理されているかも見られています。
研究者としての説明力は、将来的に社内外の関係者とのやりとりや、報告書・プレゼン資料作成に直結するビジネススキルでもあります。
そのため、文章での表現力や説明スキルを備えているかどうかを確認するために、研究概要が活用されるのです。
7:面接で使うため
研究概要は、エントリー時に提出した後、面接でも頻繁に取り上げられる重要な資料です。
面接官は事前に研究概要に目を通し、関心を持ったポイントや疑問点を深掘りする形で質問を行います。
応募者は、書面で伝えた内容をもとに、自分の研究について明確に、かつ論理的に説明できる力が求められます。
「どのような仮説を立てたのか」「なぜその方法を選んだのか」「結果からどのような考察をしたか」など、細かい点まで聞かれることもあります。
そのため、研究概要に書いた内容を自身でもしっかり理解し、関連する質問にも冷静かつ的確に答えられる準備が必要です。
面接を通じて、論理性、プレゼン力、研究への熱意などを総合的に判断されるため、研究概要は面接の質を左右する大きな要素となります。
研究概要書の基本的な形式

ここでは、研究概要書の基本的な形式についてご紹介していきます。
企業によっては、形式に指定があり、自分の思ったような形式にできないこともあります。よく指定される形式を把握しておくことによって、構成に悩むことも減るでしょう。
是非、参考にしてみて下さい。
文章のみの形式
一般的な選考に使われるエントリーシートのように、文章だけで構成するように指定されることもあります。
使用するソフトや文字数についても、各企業から指定されることが多いです。
PowerPointを使った形式
PowerPointを使って、研究概要書をまとめるよう指示されることもあります。
まとめる内容自体は、文章のみの時と変わりませんが、グラフや表、イラストなどを入れることができるため、視覚的に訴えかけやすくなるのが特徴です。
書式の指定がない自由形式
その他、企業によって様々な指定があることもあるでしょう。
数百字程度で短くまとめるよう指示されることもあれば、数千字を使ってまとめることもあります。文字数や形式に違いがあっても、相手に伝わりやすいように配慮して構成するのがポイントです。
研究概要書の書き方7つの手順

ここでは、研究概要書の書き方の手順をご紹介していきます。
書き方の手順を把握しておくことで、構成のしやすさがグンとアップするでしょう。是非、参考にしてみてはいかがでしょうか。
目的を明確にする
研究概要は、あなたの研究活動を就職活動において効果的に伝えるための重要な資料です。
単に研究内容を羅列するのではなく、その研究を通じて得た知識・スキル・考え方を企業にどう伝えるかを意識する必要があります。
採用担当者は研究テーマ自体よりも、それを通じてどのような能力を身につけたのか、企業で活かせる資質を持っているかを重視しています。
そのため、「誰に」「何を」「どのように」伝えたいのかを明確にすることが、研究概要作成の第一歩となります。
自分の研究を通してどのような価値を企業に提供できるかを意識しながら、書き始めることが大切です。
構成要素を整理する
良い研究概要を書くためには、まずどのような情報を盛り込むべきかを明確に整理することが重要です。
研究概要の基本構成には、以下のような項目が含まれます。
①研究タイトル:研究の内容を端的に表すもの。
②研究背景・目的:なぜその研究に取り組んだのか、どんな課題意識を持っていたのか。
③研究内容・方法:使用した材料、装置、手法、実験の流れなどを簡潔に記載。
④研究成果・考察:どのような結果が得られ、それがどんな意義を持つのか。
⑤今後の課題・展望:現時点での限界と今後の方向性。
⑥アピールポイント:研究を通じて得たスキル、工夫した点、社会への応用など。
このように構成を整理することで、読み手にわかりやすい研究概要になります。
情報を整理・分析する
構成を把握したら、次は自分の研究に関する情報を集めて、どの部分を研究概要に載せるかを検討します。
研究ノートや実験記録、発表資料などの過去の記録は、研究の流れや重要な結果を再確認するために有効です。
また、学会発表やゼミでのスライドも視覚的な整理に役立ちます。
加えて、指導教員との議論も重要な情報源です。
研究の意義や立ち位置、自身の取り組みがどのような価値を持つかを整理する際には、専門的な視点からアドバイスをもらうとよいでしょう。
こうした情報を収集・分析し、必要な要素を選別することで、研究概要に説得力と深みを持たせることができます。
アウトラインを作成する
研究概要の情報が整理できたら、すぐに文章を書き始めるのではなく、まずアウトラインを作成することが推奨されます。
アウトラインは、各章の骨組みを先に考えることで、全体の流れを論理的に整理するための手段です。
一般的には「はじめに」「背景と目的」「研究内容・方法」「成果と考察」「今後の展望」「結び」の順に構成します。
それぞれのパートにどの情報を盛り込むかをあらかじめ決めておけば、執筆中に迷うことなくスムーズに進められます。
また、構成を可視化することで、読み手の理解を助ける論理展開になっているかの確認にも役立ちます。
読みやすく整理された研究概要にするためにも、アウトライン作成は欠かせないプロセスです。
文章を作成する
アウトラインに基づいて文章を書き進める段階では、「簡潔さ」「分かりやすさ」「論理性」が求められます。
専門用語を多用せず、学部卒や非専門の採用担当者でも理解できるよう、かみ砕いた表現を意識しましょう。
また、各項目間が自然につながるように構成し、読者が迷わないように段落や見出しを活用するのも有効です。
事実と自分の考察を明確に区別し、主観的になりすぎないよう注意してください。
図や表を使って視覚的に補足することも有効ですが、使いすぎると逆効果になるためバランスが大切です。
企業から文字数や形式の指定がある場合には必ず遵守し、それに合わせて内容を調整する必要があります。
推敲・添削を行う
文章が完成したら、それで終わりではありません。
必ず何度か読み返して、内容の精査と表現の修正を行いましょう。
誤字脱字や表記の揺れ、文法のミスなどは信頼性を損ねる原因となります。
また、読み手が疑問を感じる部分や、説明が足りない箇所がないかをチェックすることも重要です。
可能であれば、第三者に読んでもらい、客観的な視点でフィードバックを受けるとよいでしょう。
指導教員やキャリアセンター、就活経験のある先輩に見てもらうのもおすすめです。
内容のブラッシュアップを通じて、より完成度の高い研究概要へと仕上げていきましょう。
最終確認と提出
推敲を終えたら、提出前の最終確認を丁寧に行いましょう。
文章内容だけでなく、提出形式に誤りがないかも確認することが重要です。
ファイル名、形式(PDF、Wordなど)、文字数やフォントサイズなど、企業や学校から指定された条件を再確認し、逸脱がないようにします。
また、メールやエントリーフォームを使って提出する場合には、送信先、件名、本文の内容も適切に整えておく必要があります。
締切までに余裕を持って提出し、不備がないように最後まで責任を持って対応しましょう。
研究概要は、自分の研究成果だけでなく、ビジネスにおける基本的な対応力も見られるポイントです。
研究概要書の作成でおさえておきたい10のポイント

研究概要書をまとめる時には、一枚のポスターを作るような感覚で行うと良いと言われています。
できるだけ一連の流れが分かりやすく、研究から何を学んだのかまでが伝わる内容に仕上げることがポイントでしょう。
ここでは、研究概要書の作成をする上でおさえておきたいポイントについて、詳しくご紹介していきます。是非、参考にしてみてはいかがでしょうか。
- 文字数制限や指定形式を守る
- 初心者にもわかりやすいように専門用語を避ける
- 簡潔にまとめる
- グラフや図を用いる
- 見やすいフォントを用いる
- 強調したい部分は太字にする
- 結果だけでなく学んだことや企業でどう活かせるかを書く
- 使用する色を統一する
- 「です・ます調」か「だ・である調」のどちらかに揃える
- 面接で質問されることを想定して書く
1:文字数制限や指定形式を守る
多くの企業では、研究概要書の文字数に制限を設けています。この文字数制限には、従うようにしましょう。指定された文字数を守ることは、時間を守るのと同じくらい重要なマナーです。
最初に構成した文章だと、字数を超えてしまう場合には、不要な文章や言い回しを削除していきましょう。反対に、文字数が足りない場合には、1つひとつの項目を深堀し、具体的に書いていくと良いでしょう。
文字数制限を超えてしまっても、少なすぎても、悪い印象を与えかねないため、できる限り指定される文字数に近づけるように意識するのがおすすめです。
2:初心者にもわかりやすいように専門用語を避ける
面接官や採用担当者が、自身の研究テーマに詳しいとは限りません。場合によっては、言葉さえ聞いたことがないという可能性もあるため、専門用語を使うのは避けましょう。
自身では、「専門用語は使っていない」と思っていても、年代が離れている方には理解できない言葉が含まれていることもあります。
時間に余裕がある場合には、年の離れた家族などに一度目を通してもらい、全くの初心者にも理解できる内容になっているかチェックしてもらうと良いでしょう。
3:簡潔にまとめる
「簡潔にまとめる」というイメージが湧かない方は、一枚のポスターをイメージしてみましょう。
ポスターは、表題から研究の背景、結果、考察まで一枚の紙面に簡潔にまとまっていることが多いです。研究概要書も、このポスターのように仕上げると一連の流れが伝わりやすくなります。
4:グラフや図を用いる
企業から、グラフや図の使用に制限が設けられている場合を除き、適度にグラフや表を入れることをおすすめします。
面接官は、何枚もの研究概要書に目を通すため、パッと目に飛び込んできやすい構成になっていることが重要です。グラフや表を入れることによって、見やすい構成になるだけでなく、読み手のことまで意識していることをアピールできます。
5:見やすいフォントを用いる
見やすい研究概要書は、フォントにもこだわる必要があります。
文章が長くなる場合にはゴシック体を、短文の場合にはArialやCalibriがおすすめです。また、数字や英語にはTimes New Romanを使うのが一般的でしょう。どちらもシンプルな字体であることから、論文などで使われることが多く、見やすく構成することができます。
企業からフォントについて指定がある場合には、その指定に従いましょう。
6:強調したい部分は太字にする
研究を通して、自身が学んだことや、入社後に活かせるスキルなどは太字にし、強調するのがおすすめです。適度に強調を入れることで、文章自体にメリハリが出て、読者も読みやすくなります。
重要なのは、「適度に」強調を入れることです。あまり強調を乱用すると、本当に伝えたいのがどの部分なのかが伝わりにくくなってしまいます。
7:結果だけでなく学んだことや企業でどう活かせるかを書く
研究概要書は、研究を通して得た結果を書くだけでは不十分です。結果を書くだけで良ければ、他の学生と内容が重複してしまう可能性が高いためです。
結果はもちろん重要ですが、それ以上に重要視されているのは、「研究から学んだことや、企業で活かせること」です。
例えば、「実験ではAという結果が得られたが、自分の予想と大きくかけ離れているものではありませんでした。次回の実験でも、同じフレームワーク使って、さらにBという条件をプラスすれば、精度の高い結果が出ると考えています。」など、結果を受けて今後どう活かすかを書くのがポイントでしょう。
8:使用する色を統一する
研究概要書では、文字、グラフ・表の全ての色を統一することをおすすめします。
色を何色も使うと、どこが重要な部分なのかが分かりにくくなるだけでなく、ごちゃっとした印象になってしまいがちです。どうしても複数色を使いたい場合には、似たような系統の色を選ぶなどし、統一感を持たせることが重要でしょう。
例えば、文章中の重要な箇所には赤、グラフには青を使うなど、ある程度統一感があると、読み手も読みやすくなります。
9:「です・ます調」か「だ・である調」のどちらかに揃える
文末の表現にも注意しましょう。
文末は「です・ます調」と「だ・である調」のどちらを使っても問題ありませんが、どちらかに統一することが重要です。特に企業からの指定がない場合には、自身が使いやすい方を使いましょう。
文章が最後まで書き上がったら、文末がきちんと統一されているかチェックするようにしましょう。
10:面接で質問されることを想定して書く
研究概要書が書き上がったら、面接で面接官に質問されそうなことを想定しましょう。また、その質問に対する回答まで用意しておくと良いです。
実際の面接をイメージし、回答をある程度用意しておけば当日慌てることも少なくなるでしょう。
また、用意した回答は一度声に出して、読んでみることをおすすめします。練習と本番では緊張感が違い、思ったような表情で話ができないこともあります。面接官がその場にいると考えて、練習をしておきましょう。
研究概要の例文紹介
例文1:触媒開発
私が取り組んだ研究は、自動車排ガス浄化に用いる新規触媒の開発です。
環境負荷やコストの面から課題のある貴金属触媒に代わる材料として、ペロブスカイト型酸化物に注目しました。
具体的にはソルボサーマル法を用いて複数の組成で合成を行い、XRDやSEMで構造を解析し、ガスフロー試験によって活性や耐久性を評価しました。
その結果、特定組成の試料が高い除去性能を示し、硫黄による被毒にも強いという成果が得られました。
特に、思うような性能が出なかった際には、反応条件や前駆体の調整を何度も行い、要因を一つ一つ洗い出す過程で、問題解決への粘り強さと論理的に考える力を養うことができました。
この経験から、課題が発生しても諦めずに多角的に検証し続ける姿勢を身につけることができました。
研究を通じて培った材料合成技術、触媒評価、データ分析、さらに試行錯誤を繰り返す粘り強さは、貴社の製品開発業務でも十分に活かせると考えております。
例文2:画像診断支援システム開発
私は医療分野における画像診断の効率化を目指して、深層学習を用いたMRI画像の自動診断支援システムの研究を行いました。
U-Netをベースにしたセグメンテーションモデルを構築し、データ拡張や転移学習といった手法を導入して、限られた医療画像データでも高い精度が得られるよう工夫しました。
その結果、Dice係数0.91という高い精度を達成し、専門医の診断とほぼ同等のレベルの出力を実現しました。
また、ヒートマップによる可視化機能も取り入れ、医師が診断根拠を確認できる仕組みも設計しました。
研究を通して、深層学習モデルの実装やデータ分析に関する実践力を高めるとともに、試行錯誤を重ねる中で、仮説検証や工夫を積み重ねる重要性を強く実感しました。
さらに、学会発表を通じて第三者にわかりやすく説明する力も身につけることができました。
これらの経験を通じて培ったAI技術への理解や実装力、そして現場ニーズを意識した提案力は、貴社の医療技術開発にも応用できると考えています。
研究概要を書き終えたらするといいこと
研究概要は就職活動の中で重要な提出書類ですが、書き終えたからといって安心してはいけません。
企業はその内容を面接の材料として掘り下げるため、研究概要は提出して終わりではなく、面接に活かすことが大切です。
また、外部の視点からフィードバックをもらい、内容をより実践的なものへと磨き上げることも欠かせません。
ここでは研究概要を仕上げた後に取り組むべき二つのステップについて解説します。
研究概要を元にした面接練習をする
研究概要は面接で必ず取り上げられます。
そのため概要を提出した後は、想定される質問に答えられるように練習することが大切です。
質問の定番は研究の説明を短時間で行うことや、研究から得た学び、直面した課題への取り組み方などです。
ここで重要なのは、専門外の人でも理解できる言葉で話すことです。
専門的な表現をそのまま使うのではなく、平易な表現に置き換える練習を繰り返しましょう。
実際に声に出して練習することで、内容を自然に話せるかどうかを確認できます。
さらに効果的なのは、友人や家族に面接官役をお願いし、わかりにくい部分や説得力の弱い部分を指摘してもらうことです。
外部の視点を取り入れることで、自分では気づけない改善点を発見でき、より説得力のある説明に仕上げることが可能になります。
OB・OG訪問でフィードバックをもらう
研究概要を完成させたら、OB・OG訪問を活用して現場の声を取り入れることも効果的です。
志望先で働く先輩に研究概要を読んでもらうと、自分のアピールが企業の目線からどう受け止められるのかを把握できます。
現場の先輩からは、実務に直結する内容の強調や改善点といった具体的な助言が得られるでしょう。
こうした助言は書類や公式情報からは得られない実践的な学びになります。
また、OB・OG訪問を通じて企業文化や評価されやすい人物像を知ることもできます。
企業ごとに注目されるポイントは異なるため、その違いを理解して研究概要を調整することが重要です。
できれば複数の先輩に確認してもらい、さまざまな意見を集めることで内容を多角的にブラッシュアップできます。
研究概要に関するよくある質問
研究概要は理系学生にとって就活の重要なアピール材料です。
しかし、書き方や内容に悩む人も多く、特に研究が未完成だったり進学予定があったりすると戸惑いがちです。
また、文系学生にとってもゼミや卒業論文をどう表現するかが課題になります。
ここでは研究概要に関して多く寄せられる質問を取り上げ、具体的な解決策を紹介します。
研究内容が浅いのですがどう書けばいいですか
研究成果が十分に出ていなくても問題ありません。
大切なのは結果よりも取り組みの過程です。
なぜその研究に挑んだのかという課題意識を明確にし、その課題を解決するためにどのような仮説を立て、どんな工夫をしたのかを丁寧に記すことが求められます。
結果が出なかったとしても、失敗から学んだことや改善の工夫を加えることで、粘り強さや論理的思考力をアピールできます。
例えば先行研究を徹底的に読み込み、新しい手法を試し続けたといった過程を具体的に示せば、努力と成長の姿勢が伝わります。
成果よりも、挑戦と改善を繰り返す姿勢を前面に押し出すことが評価につながります。
大学院に進学予定ですが、研究概要は必要ですか
大学院進学を予定している場合でも、企業によっては研究内容について提示を求められる場合があります。
特に研究職や技術職を志望する場合は必須となることが多いです。
その際は学部での卒業研究の内容を整理して提示するだけでなく、大学院で予定している研究テーマについても触れると良いでしょう。
将来どのような研究を進めたいのか、その研究を通じて社会や企業にどのように貢献したいのかを語ることで、明確なビジョンを示すことができます。
研究内容の完成度に不安があっても、研究への姿勢や専門性を高めたいという意欲をアピールできれば十分に評価対象となります。
文系でも研究概要は必要ですか
文系学部では研究やゼミ活動が必須でない場合も多いため、研究概要を提出する機会は少ないです。
しかし一部の企業では、応募者の学びの姿勢や思考力を確認するために研究概要の提出を求めることがあります。
その際は、ゼミでの学びや発表内容、卒業論文のテーマや結論を整理して書くことが大切です。
さらに、授業の中で取り組んだ課題や個人的に調べたリサーチを盛り込むことで、自らの主体性や知的好奇心を伝えることができます。
研究そのものの専門性ではなく、課題意識を持って取り組んだ姿勢や、自分で情報を集めて整理し発表する力をアピールできれば十分です。
文系学生であっても、論理的思考力や分析力を示す手段として研究概要は有効であり、就活における強力な武器となります。
複数社の選考で同じ研究概要を使ってもいいですか
同じ研究概要を使い回すこと自体は問題ありません。
しかし、そのまま全ての企業に提出するのではなく、志望企業に合わせて内容を微調整することが内定への近道です。
企業ごとに事業内容や求める人物像は異なり、アピールすべきポイントも変わってきます。
IT企業であれば、データ解析力やプログラミング経験を強調すると効果的です。
一方でメーカーなら、自分の研究が製品開発や生産工程の改善に応用できる点を前面に押し出すと良いでしょう。
一から書き直す必要はありませんが、企業研究を踏まえて調整することで、読み手に伝わる説得力が大きく高まります。
その企業だからこそ活かせる強みを意識してアピール内容を変えることが、他の候補者との差別化につながります。
ポイントを押さえてわかりやすく魅力的な研究概要を作成しよう

本記事では、研究概要書に関する基礎知識や、書き方の手順、注意点などについてご紹介しました。
研究概要書は、研究の過程や成果をまとめる書類のことで、企業はその過程だけでなく、学生の考えたことや、その学生が持つスキルもチェックしています。
自身のスキルや、研究の成果をアピールすることはもちろん大切ですが、何よりも意識したいのは、読み手の立場に立って研究概要書を作成することでしょう。是非、本記事を参考にして、研究概要書を作成してみて下さい。



![[理系大学の偏差値ランキング ] 就職率・出身有名人からおすすめの大学を紹介!](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/digmedia/media/2021/07/pixta_55193636_M_720x550.webp)






