
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就活を始める際に、車が好きなあなたは自動車業界の主要企業を一通り受けてみようと考えているのではないでしょうか。
この記事では「自動車業界の概要」「自動車業界の主要企業」「自動車業界の最新の動向」など自動車業界のことを簡単に説明します。
その後、「志望動機を考える3step」「志望動機の構成」「志望動機のクオリティを上げるポイント」を順番に説明し最後に例文を2つ紹介します。
少し長文にはなりますが、最後まで読むことで業界への理解が深まり、志望動機の書き方の参考にもなります。
是非、最後までご覧下さい。
- 自動車業界の動向
- 志望動機の作成方法
- 自動車業界の志望動機のポイント
- 自動車業界の志望動機の例文
- 自動車業界を志望している人
- 志望動機の書き方がわからない人
- 選考を通過する志望動機を作成したい人
目次[目次を全て表示する]
【自動車業界の志望動機】作成する前におさえるポイント
自動車業界を志望する際、単に「車が好き」という理由だけでは説得力に欠けます。
企業はその動機の背景や、入社後のビジョン、スキルとの接続までを総合的に見ています。
以下に、志望動機を作成する前に考えておくべき重要な観点を3つに分けて解説します。
なぜ自動車業界で働きたいのか
志望動機を語るうえで、自動車業界そのものに対する関心の深さは重要な要素です。
まず、自動車との出会いや関心を持った原体験を具体的に振り返りましょう。
「幼い頃から車が好きだった」という一文だけではなく、「親と一緒に整備をしていた経験がものづくりへの関心につながった」など、自分だけのエピソードを軸にすると説得力が増します。
また、自動車業界が担っている社会的役割にも目を向けましょう。
モビリティの提供だけでなく、環境対応、安全性の向上、地方の交通課題解決など、幅広い社会課題に挑んでいる点を理解することが大切です。
加えて、自動運転、EV化、コネクテッドカーなど、今後の技術革新に関心を持ち、それが業界を志望する理由であることを伝えることで、将来を見据えた視点を持っている印象を与えることができます。
なぜその企業で働きたいのか
同じ自動車業界の中でも、企業ごとに理念や強みは異なります。
そのため「どこでもよい」という印象を避けるには、その企業独自の魅力に触れることが欠かせません。
企業の掲げるビジョンや経営理念を調べ、自分の価値観と合致する点を見つけましょう。
たとえば、「人と地球にやさしい車づくり」に共感したのであれば、その背景にある社会貢献や技術開発の姿勢にも触れるとよいです。
また、他社との違いとして、技術力、デザイン力、ブランド戦略、グローバル展開など、強みや独自性に言及すると深みが出ます。
そのうえで、自分が希望する職種がどのようにその企業の事業に関わっているかを調べ、自分の経験やスキルがどのように貢献できるのかを整理して伝えることが重要です。
入社して何をしたいのか
企業側は、応募者が入社後に何を目指しているのか、どのように成長したいのかを知りたいと考えています。
そのため、「成長したい」という言葉だけでなく、具体的な行動計画や目標を持って語ることが求められます。
たとえば「安全性の高い車づくりに携わりたい」といった目標に対して、「大学で学んだ材料力学を活かして、衝突時の衝撃吸収構造の研究に挑戦したい」といった形で、具体的な業務や貢献の方法を提示しましょう。
また、短期目標と長期目標の両方を意識すると、計画性や将来への展望が感じられます。
さらに、技術進化が著しい業界であるからこそ、「新しい知識や技術を学び続けたい」という成長意欲も、企業にとっては非常に魅力的な要素です。
過去の経験と志望企業での目標が一貫しているかを確認し、自己成長と企業への貢献を両立させる志望動機を構築しましょう。
自動車業界について調べる
志望動機を作成する前にやっておいてほしいことの一つ目は「業界研究」です。
業界研究とは自分の志望する業界について研究することです。
自動車業界の仕事内容や動向についてしっかりと研究することが重要になります。
業界研究をしっかりとやることで次の「企業研究」がやりやすくなるので、業界研究は丁寧にやりましょう。
詳しい業界研究のやり方は以下の記事で紹介しているので是非参考にしてみてください。
企業について調べる
志望動機を作成する前にやっておいてほしいことの二つ目は「企業研究」です。
企業研究は自分の志望する企業について研究することです。
志望動機を作成するうえで企業研究は重要な工程になります。
自分が志望する企業でなくてはならない理由を話すためにしっかりと企業研究をやりましょう。
具体的な企業研究のやり方は以下の記事で紹介しているので是非参考にしてみてください。
自己分析
志望動機を作成する前にやっておいてほしいことの三つ目は「自己分析」です。
自己分析は、ガクチカや自己PRを作成するうえでも重要な工程なのでしっかりと行うようにしましょう。
自己分析をすることで自分の強みを活かしてどのように活躍していきたいのかを明確にすることができます。
自己分析のやり方は以下の記事で詳しく紹介しているので是非参考にしてみてください。
【自動車業界の志望動機】魅力的な構成
志望動機は、企業が応募者の価値観や方向性を理解するための重要な判断材料です。
そのためには、自分の思いや経験をわかりやすく整理し、企業との接点を明確に示す必要があります。
特に「結論」「理由」「入社後の展望」「結び」という4つの構成を意識してまとめることで、説得力のある内容になります。
以下に、それぞれのパートの役割と書き方を詳しく解説します。
結論(志望理由の要約)
志望動機の冒頭では、まず「自分は何を実現したいのか」「なぜその企業で働きたいのか」を明確に述べることが重要です。
読んだ瞬間に志望の方向性が伝わることで、面接官や採用担当者の印象に残りやすくなります。
たとえば、「私は〇〇の分野で、貴社の〇〇事業において〇〇を実現したいと考えております」といった簡潔かつ情熱的な表現が効果的です。
この段階では詳細に触れる必要はなく、自分の思いを要約して伝えることに重点を置きましょう。
業界や企業の将来性に関心を持っている姿勢や、自分がどのように貢献したいかを一文で示すことで、読み手の興味を引きます。
理由(結論に至った背景・動機)
結論を支えるためには、具体的な背景や体験を交えて理由を深掘りすることが欠かせません。
まず、自動車やものづくりに関心を持つようになったきっかけなど、原体験に基づくエピソードを述べることで、志望の信憑性が高まります。
次に、その企業に惹かれた理由として、企業理念や社風、技術力などに共感した点を丁寧に説明します。
加えて、自動車業界の現状や将来性を理解していることを示し、志望する職種がその中で果たす役割を理解しているかを伝えると説得力が増します。
単なる憧れではなく、論理的な流れを意識して構成することがポイントです。
入社後の展望(どのように貢献したいか)
企業が重視するのは、応募者が入社後にどのような価値をもたらすかという点です。
そのためには、自分が持つスキルや経験がどのように活かせるかを明確に述べる必要があります。
たとえば、「〇〇の経験で培った〇〇の力を活かして、貴社の〇〇課題に取り組みたい」といった具体的なつなげ方が理想的です。
また、短期的な目標(3年以内に〇〇に取り組む)と長期的な目標(将来的にはプロジェクトをリードする)を併せて語ると、計画性と将来性の両方をアピールできます。
変化の激しい自動車業界においては、継続的な学びや技術吸収への姿勢を示すことも重要なポイントとなります。
さらに、現時点でのスキルだけでなく、将来的に習得したい知識や資格についても触れると、自己成長に前向きな印象を与えることができます。
結び(入社への熱意)
最後は、簡潔に自分の意欲を伝えて締めくくります。
「貴社の一員として、自動車業界の発展に貢献したいと強く感じております」といった前向きな表現が効果的です。
ここでは新たな情報を追加するよりも、それまで述べた内容を踏まえたうえで、入社への強い思いを再確認する役割があります。
丁寧で端的な表現を心がけることで、読み手に誠実さと意欲が伝わり、好印象を残すことができます。
また、「どんな環境でも挑戦し続ける覚悟がある」「変化を恐れず柔軟に対応していきたい」といった姿勢を含めると、ポテンシャルの高さを感じさせることができます。
このパートでは、自分の人柄や志向性がにじみ出るような表現を選ぶことで、より印象深い締めくくりになります。
志望動機作成のポイント
志望動機を書く際には、PREP法(結論・理由・具体例・結論)を意識すると、論理的かつ読みやすい構成になります。
また、企業のホームページやIR情報、業界ニュースを活用した企業研究を怠らず、その情報を自分の言葉で落とし込むことが重要です。
さらに、自分の過去の経験・価値観・スキルと、企業の理念や求める人物像との間に一貫性があるかを常に確認しながら、文章を仕上げていくことが成功への鍵となります。
文章全体のバランスにも注意し、志望理由ばかりが長くならないように調整しましょう。
企業側は、意欲・適性・理解度の3点を総合的に判断しています。
そのため、どの段落にも「自分の強み」と「企業との接点」が見えるように工夫することが大切です。
【自動車業界の志望動機】最新トレンド
自動車業界の志望動機を作成する上では、自動車業界について深く理解しておくことも非常に重要です。
そこで、ここからは自動車業界の最新の動向について詳しく紹介していきます。
さまざまなポイントを踏まえた上で業界理解をすることで、企業の採用担当者に良い印象を与えられる志望動機を作成できるでしょうから、ぜひ確認してみてください。
業界規模
自動車業界の最新の動向を抑える上で、業界の規模についてもしっかりと把握しておくことが非常に重要であると言えます。
自動車業界の業界規模は約60兆円であり、全製造業の20%弱を占めている、非常に規模の大きな業界です。
国内の生産台数は半導体不足などの影響により減少してしまっています。
グローバルで見ると、現状トヨタのシェア率が最も高いと言われてはいますが、中国市場の拡大や世界のEV推進など業界構造自体が変わってしまう可能性もあるため、「必ず、今後も圧倒的なシェアが続き続ける」とはなかなか考えがたいと言えるでしょう。
新たなビジネスの開拓
日本国内の自動車メーカーは今、岐路に立たされているといっても過言ではありません。
その理由は国内の人口減少や若者を中心とした深刻な自動車離れが原因で、自動車関連の市場は次第に縮小していくと予想されているからです。
そのため自動車メーカー各社は自動車販売以外のビジネスの構築が必要になってくるとしています。
実際にMaas(Mobility as a service)という「”地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス”」の提供に注力する自動車メーカーもあります。
水素エネルギー
水素エネルギーは近年においても非常に注目されている、自動車業界において非常に注目されているポイントの一つです。
水素エネルギーは環境に優しい次世代エネルギーとして非常に有用だからです。
水素は地球上に最も多い元素であり、枯渇する心配がありません。
また、CO2の排出などもないので環境に優しいのも大きな特徴です。
ただし、EV同様、製造過程に非常に問題を抱えておりCO2を発生させないブルー水素やグリーン水素などの方法はありますが、まだまだ発展途上なので、「水素エネルギーが覇権を握る時代がすぐに来るか」と聞かれると、そうでもないでしょう。
CASE
現在の自動車業界は『100年に1度の大変革時代』とされ、自動車メーカーからモビリティカンパニーへと、「CASE」という言葉をトレンドワードとしてモデルチェンジが進んでいます。「CASE」とは「Connected」「Automation」「Shared&Service」「Electric」の頭文字を繋げた造語です。
これらは「繋ぐ」「自動化」「共有」「電動化」という今まで自動車とは関係のなかった領域での技術革新のことを言います。
志望動機を書く前にそれぞれに注目し、業界のトレンドを押さえておきましょう。"
この「Connected」は今活発な動きを見せているインターネットとモノを繋ぐ「IoT」の技術を自動車に応用した技術です。
この技術が進歩することで今までにない新しいサービスの提供が可能になっています。
例えば保険会社の損保ジャパン日本興亜が提供している「スマイリングロード」のサービスは通信機能を搭載したドライブレコーダーにより、ドライバーの安全運転を管理するサービスです。
走行距離や急ブレーキの回数などを元にフィードバックしてくれたり、好成績を出せば素敵なプレゼントをゲットできる仕組みになっています。
他にも、車両に乗っていなくてもスムーズな駐車をしてくれる「リモートパーキングシステム」や出入りに手間取る駐車の問題を解決してくれるシステムなどがあり、車両とインターネットが繋がると今まで考えられなかったことが実現可能になります。
自動車業界がいう「自動化」とはまさに「自動運転」です。
一昔前までは「もっと未来の話」とか「映画の中のこと」との認識を持つ人が多かったと思いますが、国内の自動車メーカーはもちろん、海外の自動車メーカーも開発に注力しており、成果が出てきています。
ホンダやメルセデスは自動運転レベル3の市販車をすでに発売しており、日本やドイツでも走行が認められています。
このレベル3は条件付自動運転のレベルで、手を離すハンズオフに加え、進行方向から目を離すアイズオフまでが許される基準となります。
また、アメリカや中国ではセーフティドライバーが同乗する自動運転タクシーのサービスの実証が始まっており、今後も技術革新が進む領域となっています。
「Shared&Service 」は難しい書き方をしていますが、つまりは「カーシェアリング」のことを指します。
自動車メーカー各社は若者の車離れの原因の一つに「高い維持費」を挙げており、その解決のためにも「車を保持しない」=「車に乗らない」ではなく、「車を保持しない」=「カーシェアを使う」の構図を進めていくとしています。
実際、各社が「カーシェア」を推進していることで街中に「カーシェアポイント」が増え、週末はそこに一台も止まっていないという風になりつつあります。
こうしたことからもこの「Shared&Service 」は伸びる領域であると言えます。
「Electric」は「電動化」とされており、それは「電気自動車」のことを指します。
世界中で地球温暖化などの環境問題に取り組む必要があるとされており、自動車メーカーも例外ではありません。
その中でも特に「脱炭素社会」の実現に向けてEUが2035年以降にハイブリット車を含むガソリン車販売を規制する方針を打ち出しました。
その結果、ヨーロッパを中心に多くの自動車メーカーが「電気自動車」の開発に注力することになりました。
この「電気自動車」開発のネックは大きな車両を動かすためのバッテリー問題です。
このバッテリーが「電気自動車」全体のコストの4割を占めており、なかなか実用的な開発が進まない現状です。
そこで自動車メーカー各社は電池のメーカーとの共同開発に取り組み、競争力をつけようとするメーカーも増えてきており、技術革新も近い未来の話になりつつあります。
【自動車業界の志望動機】業種
続いて自動車業界の業種についても詳しく説明していきます。
自動車業界には大きく分けて4種の業種があり、それぞれについてしっかりと確認していきましょうましょ
完成車メーカー
完成者メーカーは、自動車業界において中心の役割を果たす企業とされており、自動車部品メーカーや商社から鉄鋼などの原材料を用いて、最終的な製品である車両を設計開発に組み立てることを主な業務としています。
トヨタや日産、ホンダといった世界的によく知られる企業がこのカテゴリーに含まれており、高品質な車両を市場に提供することで、グローバルな自動車市場において強い影響力を持っています。
完成車メーカーの強みとして、車両の設計や開発における総合的な能力があり、これらの企業は安全性や環境性能、性能、デザインなど消費者のニーズに応えるために、必要なあらゆる面での研究開発に力を入れている点が挙げられます。
新しい駆動技術や自動運転技術など、自動車業界の将来を左右するような先進技術の開発にも積極的に取り組んでいます。
製品の設計から販売アフターサービスに至るまでの一連のプロセスを管理することで、ブランド価値を高め、顧客満足を追求しているのです。
高いブランド力と市場での競争力を確立し、業界におけるリーダーシップを保持している企業と言えるでしょう。
- トヨタ自動車
- 本田技研工業(ホンダ)
- 日産自動車
- マツダ
- スズキ
- SUBARU
自動車部品メーカー
自動車部品メーカーは自動車産業の中で非常に重要な役割を担っており、エンジン部品やトランスミッション、ブレーキシステム、電子機器、内装など自動車を構成するさまざまな部品の製造と開発をしています。
自動車は数千から数万の部品で構成されており、そのほとんどが専門の部品メーカーによって共有されています。
こうした部品メーカーは完成車メーカーと密接に連携し、高品質な部品を提供することで、最終製品である自動車の性能や安全性や快適性を向上させているのです。
多くの自動車部品メーカーは、特定の部品やシステムに特化しており、例えばデンソーはカーエアコン、アイシンはパワートレインなど、それぞれにおいて得意な分野を持っています。
- デンソー
- アイシン精機
- パナソニック
- 豊田自動織機
- 住友電気工業
- ジェイテクト
- トヨタ紡績
- 日本精工
- ボッシュ
自動車ディーラー
自動車ディーラーは消費者と自動車産業の間の重要な橋渡し役として機能しています。
主な業務は新車や中古車の販売だけでなく、車両の定期点検や車検、修理等、アフターサービスも行います。
自動車ディーラーは顧客に対して車両の購入から、その車両の生涯にわたるサポートを提供し、顧客満足を追求しているのです。
正規販売店のディーラーは特定の完成車メーカーと直接契約を結んでおり、メーカーの新車のみを取り扱っています。
メーカーから提供される研修や技術・情報にアクセスでき、メーカーの純正部品を使用しているので、品質と安心感を確保できるのが大きな特徴と言えるでしょう。
一方で、サブディーラーは正規の販売店と異なり、複数のディーラーやオークションなどから仕入れたさまざまなメーカーの車両を販売しています。
これにより、顧客は幅広い選択肢から自分に合った車を選ぶことが可能になり、場合によっては正規販売店よりも低価格で車両を購入することもできるでしょう。
全般的に自動車のディーラーは、顧客が車両を購入する際のアドバイスやサポートを提供するだけでなく、車検や定期的なメンテナンスなど、車両の維持や管理に関わる一連のサービスを提供している業者といえます。
- トヨペット
- Hpnda Cars
- 日産プリンス
【その他】株式会社オートウェーブ、株式会社ネクステージ、VTホールディングス株式会社
自動車関連サービス
自動車関連サービスも、自動車業界において非常に重要な役割を担っている企業のことです。
中古車販売店からカー用品店、ガソリンスタンド、損害、保険会社、レンタカー会社など自動車の購入から日用の使用、メンテナンス、さらには非常時のサポートまで自動車のライフサイクル全般をカバーしているのが大きな特徴です。
中古車販売店は新車に比べて手頃な価格で車を手に入れたい消費者にとって重要な選択肢であり、品質保証や整備済みの車両を提供することで中古車市場の信頼性を高めています。
ガソリンスタンドは自動車の運転に必要な燃料供給のほか、洗車や軽微なメンテナンスサービスを提供し、日常的な車の使用をサポートしています。
損害保険会社は事故や故障など、不測の事態に備える重要な役割を担っており、レンタカー会社は旅行やビジネスなど、一時的に車が必要な際、移動手段を提供し、利便性を高めています。
このように自動車を持つ消費者の生活を豊かにし、安全で快適なドライブライフを支えるために必要不可欠な企業であると言えるでしょう。
【中古車販売】ガリバー、ネクステージ
【カー用品】オートバックス、イエローハット
【ガソリンスタンド】ENEOSホールディングス(ENEOS、出向興産)、コスモエネルギーホールディングス(コスモ石油、太陽石油)
【損害保険】東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン
【自動車業界の志望動機】職種
仕事内容が分かったところで次は「自動車メーカーの職種」について説明していきます。
経理や総務、人事などの職種も当然ありますが、ここでは「開発エンジニア」「マーケティング」「生産技術者」「営業」「事務」といった自動車メーカーの職種として代表的な5つを説明していきます。
- 開発エンジニア
- マーケティング
- 生産技術者
- 営業
- 事務
開発エンジニア
「製造開発」の仕事を担当する「開発エンジニア」をまずは説明していきます。
この「開発エンジニア」は車両や組み立てるための部品の開発に携わるエンジニアのことを指します。
車両の機械設計や電子制御、車体設計などのエンジニアが集まり、車両の設計、開発、評価、テストを繰り返し行い、新しい車両や新技術の開発を行います。
開発エンジニアは世の中にまだ存在していない新車種や新技術の開発を最も身近に行う職種で、非常に魅力的な仕事です。
また、自動車メーカーの強みや技術力の顔となるため、応募してくる学生は非常に多く、就活では人気の職種になります。
【資格】自動車整備士資格、機械設計技術者試験など
- 機械工学・電気工学の基礎知識
- デジタルスキル、プログラミングスキル
- 問題解決力・論理的思考力
マーケティング
この「マーケティング」は仕事内容の「販売」に分類される仕事です。
主な業務内容としては製品の「市場調査」や「マーケティング戦略の立案」「販売促進活動」などを行うことです。
正確に顧客のニーズや世の中のトレンド情報を分析し、現状の自社製品の需要を把握して販売戦略を考える仕事になります。
「販売」するためにはまずこの「市場調査」が欠かせない要素になってくるため、「マーケティング」の仕事は非常に重要な役割を担っています。
「販売促進活動」には広告やプロモーション、イベントの企画・実施なども含まれており、実際に顧客と接する機会も非常に多い仕事です。
広告にはテレビCMなどの実施や、その内容の構成を考える仕事も含まれており、マーケティングの仕事は想像よりも多岐に渡ります。
- 市場調査・データ分析のスキル
- コミュニケーション能力
- クリエイティブな思考力
- プロジェクト管理スキル
生産技術者
「製造」の仕事内容でも軽く触れましたが、良い品質の製品を効率よく製造することを自動車メーカーには求められます。
その難題に挑む職種が「生産技術者」です。
「生産技術者」の仕事内容は主に自動車の製造工程や生産ラインの改善を担当します。
例えば生産ラインの設計や生産プロセスの改善、生産の自動化システムの導入や、生産ラインの省人によるコスト削減などを目指し、日々設計の見直しやテストを行っています。
この繰り返しが自動車メーカーの生産効率の向上や、より良い品質の車両を製造することに繋がっています。
- 設計ツールやプログラミングスキル
- コミュニケーション能力・マネジメント力
- 課題発見・課題解決能力
営業
「営業」は「販売」の業務を担当し、顧客に自社商品を販売します。
主な業務内容としては「自動車の販売促進」や「販売活動」を担当しています。
日本各地だけでなく海外にも拠点を構え、現地の顧客への自社の車両を提案や販売する商談を行います。
顧客は法人、個人を問わず様々なので、それに伴ってニーズも様々です。
「営業」はその顧客のニーズに合わせた提案を行うことで、決して安くない買い物をしてもらうことに繋げます。
無事契約交渉がまとまったら、納期の確認や定期点検などのアフターサービスの説明などを行い、最終の納車までサポートします。
直接顧客と向き合う職種なので、難しい要求や無理難題に直面することもありますが、自社製品が売れる感動を体感できるやりがいのある職種です。
- 車に関する知識
- ヒアリングスキル
- コミュニケーション能力
- トーク力
事務
事務職の業務は学部問わず、人気の職種です。
自動車業界の事務職は、製造や販売、サービスに関連する業務をサポートする役割を担っています。
事務職は、各部門が円滑に業務を進められるよう、細やかなサポートを行うことが求められます。
また、業界特有の知識や規則に対応するため、正確で迅速な処理能力が重要となります。
- 一般的な事務スキル
- 接客スキル
- コミュニケーション能力
- 異文化対応できる語学力
【自動車業界の志望動機】主要企業
自動車メーカーの「仕事内容」と「職種」が理解できたところで、「自動車業界の主要企業」を紹介していきます。
ここでは「トヨタ自動車」「スズキ」「ホンダ」の国内大手3社と「フォルクスワーゲン」の海外企業大手の1社を説明していきます。
「トヨタ自動車」のことを知らない日本人はいないのではないでしょうか。
それほどに世界的に有名で、日本最大手の自動車メーカーです。
愛知県豊田市に本社を置く、「トヨタ自動車」はトヨタグループの中核企業で、ダイハツ工業と日野自動車の親会社であり、SUBARUの筆頭株主です。
国内シェアは3割を超えており、2022年のグループ全体の販売台数は1048万台と、3年連続で世界1位となっています。
車両のラインナップの豊富さやハイブリッド技術、水素エンジンの開発などに強みを持ち、技術的に進んでいる企業です。
主要ブランドは「トヨタ」と「レクサス」で国内外に多くのファンが存在しています。
「スズキ」に関しても多くのテレビCMなどを通して認知を広げている大手自動車メーカーです。
静岡県浜松市に本社を置く、国内販売台数2位の自動車メーカーです。
「スズキ」は自動車だけでなく、バイクなどの二輪車も販売しておりその規模は世界販売台数で8位、国内販売台数は2位です。
軽自動車に力を入れており、1998年から採用しているコーポレートスローガンは「小さなクルマ、大きな未来」としており、ここからも軽自動車への注力が見てとれます。
それだけではなく「スズキ」は登録車販売にも注力しており、全方面から自動車販売に取り組んでいます。
またインドでは海外企業ですがインド国内最大手の企業となっており、今後市場の伸長が見込めます。
「ホンダ」は東京都港区に本社を置く自動車メーカーで正式名称は「本田技研工業」です。
この「ホンダ」、自動二輪車の販売台数、売上高は世界1位、自動車の販売台数は世界7位となっています。
国内での登録車販売では2位、軽自動車販売では3位となっており、「N-box」は軽自動車モデル別販売で首位に立っています。
他にも小型ジェット機の出荷数世界1位、芝刈り機のシェアも世界1位、他には発電機、除雪機、小型耕うん機の国内シェアが1位と自動車だけでなく、様々な分野で大きな影響力を与える大手企業であると言えます。
「フォルクスワーゲン」はドイツのヴォルフスブルクに本社を置く、世界最大手の自動車メーカーです。
「フォルクスワーゲン」のグループには「アウディ」「ポルシェ」「ランボルギーニ」「ベントレー」といったクルマ好きなら誰もが知っている世界的自動車メーカーを抱えており、ヨーロッパでは20年以上に渡りトップシェアを維持しています。
また近年中国に進出し、シェアを伸ばしています。
主力製品は「ビートル」や「パサート」「ポロ」「ゴルフ」などがあり、特に「ゴルフ」は世界的に大ヒットし、ベストセラーとなりました。
販売台数で「トヨタ自動車」と競っており、世界的大手自動車メーカーの一つと言えます。
【自動車業界の志望動機】向いている人
続いて自動車業界に向いている人の特徴についても詳しく紹介していきます。
下記の4点が当てはまる人は、自動車業界で働くに当たってストレスフリーに楽しく業務に取り組むことができるでしょう。
リーダーシップを発揮できる人
リーダーシップを発揮できる人も、自動車業界において活躍できる可能性が高いです。
確かにどの業界にも言えることですが、リーダーシップを持って意欲的に物事を進められる人はさまざまな場面において非常に重宝されます。
特に自動車業界は日本経済を支えている非常に大きな業界であり、「自分が日本の経済を支えるんだ」という強い意思を持って業務に取り組むことができる人は非常に向いていることでしょう。
将来の日本経済に影響を与えるようなプロジェクトを任される可能性もあるので、メンタルの強さや多さなども求められてきます。
リーダーシップを発揮し、日本の経済に貢献するという意思を持って働くことができる人物は、まさに自動車業界にぴったりであると言えるでしょう。
グローバルに活躍したい人
グローバルに活躍したい人も自動車業界で働くことに非常に向いています。
日本の自動車メーカーは現在世界でもトップクラスのシェア、そしてプレゼンスを持っています。
海外に行って「日本と言えば何か?」と聞かれると「寿司」「侍」の次に「車」と言う人もいるほど、「日本=車」というイメージは海外からすると強いのです。
売り上げの海外比率も非常に高く、日本市場を超えて、グローバル市場での競争が非常に重要と言えます。
よって、海外文化に興味を持っている人、人や英語が得意な人、国際交流をしてみたいという方は、非常に自動車業界に向いていると言えるでしょう。
協調性を持って働きたい人
協調性を持って働きたい人も自動車業界にぴったりであるといえます。
自動車は皆さんご存知の通り、さまざまな細かい部品や素材から作られているものです。
さらにそれが消費者にも当たるまではメーカーだけでなく、工場やディーラーなどさまざまな人を介して届けられるのです。
つまり、多くの人の連携や協調が欠かせない業界であると言えますが、消費者に届くまでに関わる人々の種類が数ある業界の中でもトップクラスに多いです。
よって、組織としての働き方ができる人、これまで協調性を持って何か成し遂げてきたことがあるという人には、ぴったりの業界です。
よって、これまで何かしら部活やサークルなどで協調性を持って取り組んだ経験があるならば、積極的に述べることができると良いでしょう。
クルマが好きな人
なんといっても、車が好きな人は自動車業界で働くに当たってぴったりであると言えるでしょう。
むしろ車があまり好きじゃないならば、自動車業界で働くのもストレスが溜まるかもしれません。
ただし、「ただ車が好きなだけ」でなく、将来車に関して、どのように関わっていきたいか、どのようにビジネスにつなげたいか考えられる人に向いているといえます。
しかし、車好きである人でも、どのような仕事を担当するのか、どのような業務が自分に向いているのかをしっかりと分析しておくことが重要です。
ただ車が好きというだけでは、あまりにも志望動機として弱いのでマイナスな印象を与えてしまう可能性もあります。
しっかりと自分が車が好きであるということを活かし、どのように仕事をしていくのか考えていくことが重要なのです。
【自動車業界の志望動機】効率的に作る方法
就活を始める際に、車が好きな人であれば自動車業界の大手企業を一通り受けてみようと思っているのではないでしょうか。
エントリーシートを効率的に作るために、志望動機を使いまわしたいと考えている人も多いでしょう。
そこでは、自動車業界の志望動機を簡単に作れる方法を紹介します。
以下の5つの項目について詳しく解説していくので、最後まで読んでいってください。
- ネタを集めておく
- 企業の求める人物を把握する
- 例文を参考にする
- OB・OG訪問をする
- 構成を意識する
ネタを集めておく
自動車業界の志望動機を効率よく作成するためには、就活が始まる前から自己分析をして志望動機で使えるネタを集めておくことが必要です。
例えば、部活動やサークル、ゼミ、インターン、課外活動での経験や学びなど志望動機でかけそうなことを普段から考えておきましょう。
出来事だけではなく、そこで得た強みからなぜその企業を志望するに至ったのかまで述べられるようにすると良いでしょう。
志望動機のネタを複数パターンを考えておくことで、ある程度使いまわしができます。
自分自身の強みを理解し、アピールに使える強みや経験を集めておけば、どのような質問にも対応しやすくなります。
企業の求める人物像を把握する
次に、企業の求める人物像を把握しておきましょう。
どれだけ素晴らしい経験や強みがあったとしても、企業が求める人物像に合っていなかったり、その企業の働き方や社風に合わないと判断されてしまえば、評価が低くなってしまいます。
質の高い志望動機を書くうえで業界研究は避けられません。
自動車業界の概要や企業の社風を理解することで業界理解が深まり、高評価を得られる志望動機を書くことができます。
逆に企業の求める人物像がわかっていないと、自動車業界であればどこでもいいんだなと思われてしまう可能性があります。
事前に企業の求める人物像を把握し、それに合うように志望動機の考え方や書き方を工夫しましょう。
例文を参考にする
最後は、例文を参考にすることです。
毎回志望動機を1から作成するにはかなり時間がかかってしまいますよね。
そのため、例文を参考にして自分なりの回答を作ることをおすすめします。
しかし、例文をそのまま真似してしまうとありきたりなエントリーシートになり、ほかの学生との差別化ができません。
自分なりの表現や語彙を使って工夫し、オリジナリティを出すようにしましょう。
また、例文にプラスして企業の独自性にも言及しましょう。
志望動機を使いまわしていると思われないためにも、業界研究と企業研究をしたうえで志望動機を書くようにしましょう。
この記事を載せているdigmediaでも例文を紹介しているので参考にしてください。
OB・OG訪問をする
志望動機を効率的につくる方法の一つに、OB・OG訪問を活用することが挙げられます。
実際に企業で働いている方の話を聞くことで、仕事内容や企業の理念について、インターネットでは得られない情報を知ることができます。
また、実際の業務内容や社風を直接感じ取ることができるため、自分の価値観やキャリアビジョンと照らし合わせながら、志望動機を明確にするのに役立ちます。
加えて、OB・OG訪問を通じて得た具体的なエピソードを盛り込むことで、他の応募者との差別化を図ることが可能です。
構成を意識する
「志望動機の構成」は大きく分けて「結論」「根拠」「展望」の3つに分類できます。
結論的にはこの「結論」「根拠」の部分が使い回せる部分です。
それでは「結論」「根拠」「展望」の詳しい書き方について順番に説明していきます。
志望動機における「結論」とは「あなたの就活の軸」を中心に考えると良いでしょう。
「自動車業界に入社するのは〇〇という目標を達成するため」「将来自動車業界を〇〇のように変えていきたい」「自動車業界で〇〇を成し遂げたい」などを最初に書くことで、採用担当者としても次の展開を予想しやすく、頭に入ってきやすいです。
この「結論」はダラダラとは書かずに端的に伝えるようにしましょう。
そうすることで、次の根拠や最後の展望を読むまで採用担当者の集中力が持ちます。
「結論」を端的に伝えた次はその「結論」に至った「根拠」を書いていきましょう。
この「根拠」は「あなたの就活の軸」を作った部分で、採用担当者も非常に重視しています。
この「根拠」は、より具体的なエピソードを用意して志望動機に組み込むようにしましょう。
当然ですが選考が進むと面接があり、その面接でもこの「根拠」の部分は深掘りされる可能性が非常に高く、志望動機を書きながらあなたの経験をよく振り返るようにしておくと面接の対策にも繋がります。
「結論」「根拠」と書いてきた志望動機も、この「展望」でそのクオリティは大きく左右されます。
この「展望」は使い回しができない部分で、特に企業研究が重要な部分になります。
「入社後のあなたの展望」ですので、その企業が「強み」としていることや「独自性」などに言及する必要があり、企業ごとに内容を変える必要があります。
「入社後の目標」を伝えるだけではなく、「会社への貢献」をどうしていくかも一緒に書くことで採用担当者に「あなたが入社するイメージ」をさせることが可能で、それは非常に高評価に繋がることが多いので参考にして下さいね。
【自動車業界の志望動機】例文10選
ここまで自動車業界の志望動機を作る上での「構成」と「クオリティを上げるポイント」を説明してきました。
最後はそれらを踏まえた例文を「技術職」「営業職」「事務職」「マーケティング職」「商品開発職」「製造職」の7パターンと車好きをアピールした例文、過去の経験をアピールする例文として「自動車工学の専攻」「プログラミングスキル」「自動車関連のインターンシップ」の3つを用意しました。
是非、あなたの志望動機の参考にして下さい。
技術職の例文
私は交通事故がない豊かな世の中を作りたいと強く思い、貴社を志望いたしました。
その理由として、私は高校生の時に自宅の近くで交通事故に遭いました。
幸い命に別状はありませんでしたが、今でも残る傷跡と深い心の傷はまだ完全には癒えていません。
事故を起こした加害者の方も長期間に渡り私のサポートをして下さったり、車の修理や補償、私の病院代の支払いなどで大変な苦労をされていました。
この経験から交通事故は関わった全員を不幸にすると実感しましたし、このような不幸な思いをする方が1人でも減ったら良いと強く感じました。
私は貴社が安全に対して同業他社よりも高い意識を持ち取り組みをされていることを知りました。
貴社の思いは私と同じ意識であり、私自身も貴社に入社し車両を製品開発の部分から携わりたいと強く思いました。
そして私の成し遂げたいことである交通事故のない豊かな社会を作り出すことにチャレンジしたいと考えています。
営業職の例文
私が貴社の営業職を志望する理由は、国籍や人種を超えて、貴社の自動車で人々の生活を支えたいと思ったからです。
大学3年の夏休みにヨーロッパを回った際、多くの日本の車が活躍している姿を目にし、より多くの人々に日本の素晴らしい車を届けたいと感じました。
私の語学力を活かし、世界中の人々に車を届けることができるのは、グローバルに展開している貴社のような規模が大きく、世界基準で考えている企業であると考え、志望しました。
貴社に入社した暁には英語力を活かし、日本だけでなく、海外の企業や顧客に対しても営業活動を行い、一人でも多くの人に素晴らしい素晴らしい体験をしてほしいと考えています。
就活コンサルタント木下より

「なぜ」をベースに考えられているというのも、営業職の例文を作成する際のポイントです。
具体的な展望が示されており、入社後のイメージが掴みやすいことでしょう。
曖昧な部分を可能な限り減らすことで、企業の採用担当者に良い印象を与えられる可能性が高まるので、しっかりと対策をしていくことが重要であるといえます。
事務職の例文
今現在も比較的田舎の地域に住む私は、幼少期から車での移動が当たり前でした。
スーパーに買い物に行くのも車、本屋さんに行くのも車、何をするにも車がないと成立しない状況です。
それは今も大きくは変わらず、この車での移動が私の豊かな生活を支えていたんだなと実感いたしました。
逆に考えると車で移動する選択肢がなかった場合、私は豊かな暮らしとはほど遠い不便な生活を強いられていたかもしれません。
この事実は私が住む日本だけでなく世界中で起こっていると感じており、貧困の格差が大きい地域ではより、移動の制限を強いられている人々が多くいて、その人々の為に私に何かできないかを考えるようになりました。
そんな時、貴社は比較的低価格で車を販売しており、移動の制限がより強い新興国でのシェアが高いことを知りました。
私は貴社に入社後、国内で経験を積み、最終的には海外で貴社の車を広げることにチャレンジしたいと考えています。
そのことは私の考える移動の制限がない世界を実現する近道だと感じていますし、この世界をもっと世界各地に広げたいと考えております。
上記の例文では、自身の経験を具体的に書いています。
また、そこから感じた問題・課題と「なぜその企業なのか」の理由が強く結びついており、とても説得力の高い志望動機になっています。
高い評価を得られる志望動機を書くためには、自己分析と企業研究の両方が必ず必要です。
企業と自分の価値観ややりたいことがマッチしているということをうまくアピールしましょう。
マーケティング職の例文
私は、市場のニーズを的確に捉えた戦略を構築する仕事に魅力を感じています。
特に、自動車業界は技術革新が進み、顧客の価値観が多様化しているため、マーケティングの重要性が高まっています。
私は大学で経済学を専攻し、消費者行動の分析について学びました。
ゼミでは自動車市場の動向を研究し、購買意欲に影響を与える要因を考察しました。
その中で、ブランドイメージやプロモーションが購買決定に与える影響の大きさを実感しました。
また、インターンシップではデータ分析を活用し、ターゲット層に最適な広告施策を提案する経験を積みました。
貴社のマーケティング職では、消費者の潜在的なニーズを捉え、製品価値を最大化する施策を考えたいです。
持ち前の分析力と創造性を活かし、魅力的な市場戦略を展開できるよう努力します。
就活コンサルタント木下より

マーケティング職は、データ分析と消費者行動の理解が重要です。
この例文では、大学での研究やインターンシップ経験を通じて、マーケティングの基礎を身につけたことを伝えています。
また、自動車業界の変化に対応した戦略を立案できる点を強調しています。
企業の特徴を踏まえつつ、マーケティングの視点からどのように貢献できるかを具体的に述べることが大切です
商品開発職の例文
私は、革新的な技術を取り入れた製品開発に携わりたいと考えています。
自動車業界は、電動化や自動運転技術の進展により、大きな変革期を迎えています。
こうした状況の中で、より安全で快適なクルマを生み出すことに貢献していきたいと思い、商品開発に関心を持ちました。
大学では機械工学を学び、材料の特性や設計技術について深く研究しました。
特に、振動制御に関する研究では、異なる素材の組み合わせによる剛性向上を実験的に検証しました。
また、学内プロジェクトでは、自動車部品の軽量化をテーマに設計を担当し、コスト削減と強度確保の両立を実現しました。
貴社では、これらの経験を活かし、次世代のモビリティを実現する製品開発に取り組みたいです。
より良い技術を形にし、ユーザーの期待を超えるクルマづくりに貢献します。
商品開発職では、技術的な知識と実践経験の両方が求められます。
上記の例文では、大学での研究やプロジェクト経験を具体的に示し、技術的な理解があることを強調しています。
また、自動車業界の変革に興味を持ち、その中で自身がどのように関与したいかを明確に述べると人柄や価値観、貢献意欲についても効果的に伝えることができるでしょう。
製造職の例文
私は、高品質な製品を効率的に生産する技術に魅力を感じています。
自動車は、長期間にわたって安全性が求められる製品であり、製造プロセスの精度が重要です。
私は、品質管理や生産技術の向上に貢献できる技術者になりたいと考え、大学では生産工学を専攻し、効率的な製造工程の設計について学びました。
特に品質管理に関心を持ち、統計的手法を用いた不良品削減について研究しました。
工場見学や実習を通じて、生産ラインの最適化に取り組む現場の努力を目の当たりにし、より深く製造業に関心を持ちました。
インターンでは、製造現場での課題を分析し、工程改善の提案を行いました。
この経験を活かし、貴社の製造部門で生産技術の最適化に貢献したいです。
品質向上とコスト削減を両立し、より良いクルマづくりに携わるのが私の夢です。
就活コンサルタント木下より

製造職では、品質管理や生産技術に関する知識と現場での経験が重要です。
上記は、大学での研究や工場見学、インターン経験を通じて、製造工程の最適化に興味を持ち、それに取り組んできたことを示しています。
また、製造現場での課題解決に貢献できる姿勢を強調し、企業の生産性向上にどう貢献できるかを具体的に述べている点が良いです。
車好きをアピールした例文
私は、幼少期からクルマに強い関心を持ち、自動車業界で働くことを目指してきました。
クルマは単なる移動手段ではなく、運転する楽しさやデザインの美しさを兼ね備えた魅力的な存在です。
大学では工学を学び、特に車両の運動性能に関する研究を行いました。
サークル活動では、自動車競技に参加し、実際の走行データを分析しながらセッティングを調整しました。
また、アルバイトではカー用品店で接客を担当し、顧客のニーズに応じた提案を行いました。
これらの経験を通じて、クルマに関する知識を深めるだけでなく、多くの人にその魅力を伝えることにやりがいを感じました。
貴社では、クルマの楽しさをより多くの人に届ける仕事に携わりたいです。
製品の魅力を最大限に引き出し、ユーザーに喜ばれるクルマづくりに貢献します。
クルマ好きであることを志望動機にする際は、単なる趣味ではなく、業務にどう活かせるかを示すことが重要です。
本例文では、大学での研究、サークル活動、アルバイト経験を通じて、クルマへの興味が実践的な知識やスキルにつながっていることを伝えています。
また、自身の経験をもとに、クルマの魅力を広めることに貢献したいという姿勢を明確に示しています。
車好きをアピールした例文
私が自動車業界を志望する理由は、大学で学んだ自動車工学を通して、ものづくりの面白さと社会貢献性を実感したからです。
特に、ゼミでは電動車両のパワートレイン設計に携わり、モーターの出力効率を高める研究を行ってきました。
実験データをもとに冷却構造の設計を見直した結果、理論上の出力効率を約15%向上させることができ、教授からも高い評価をいただきました。
この経験を通じて、データを用いて構造改善にアプローチする力と、チームでの設計・検証作業の重要性を学びました。
また、課題の抽出から試作・評価まで一貫して行う中で、細部までこだわる姿勢と、粘り強く仮説検証を繰り返す力が養われました。
さらに、CADやシミュレーションツールを用いた設計技術も身につけており、即戦力としての実務対応にも自信があります。
貴社では、より効率的で持続可能なモビリティ社会の実現に向けて、専門知識と実践力を活かし、次世代の車両開発に貢献したいと考えています。
就活コンサルタント木下より

この例文では、専門的な技術と学術的な実績を具体的に示すことで、実践的スキルと車に対する情熱の両面をアピールしています。
学びの成果と今後の展望が自然につながる構成になっており、専門人材としての価値が明確に伝わる内容ですね。
【経験別例文】プログラミングスキル
私の強みはプログラミングを通じて課題を解決する力であり、車に関する情報を扱うシステムへの興味がきっかけです。
大学ではPythonとRを用いて交通データの可視化プロジェクトに取り組み、道路渋滞の発生傾向を分析しました。
約1万件の走行ログからパターンを抽出し、混雑の時間帯や地点ごとの傾向を明らかにすることができました。
この経験を通して、データに基づく判断の大切さと、車に関連する情報技術の活用可能性を実感しました。
また、最近は機械学習による走行予測モデルの構築にも挑戦しており、将来的には安全運転支援や自動運転技術にも貢献したいと考えています。
車の走行履歴からメンテナンス時期を予測するモデルにも関心があり、エンジニア視点だけでなくユーザー目線でも価値を創出したいと感じています。
貴社が進めているコネクテッドカーやソフトウェア開発の領域で、自らのプログラミングスキルと課題発見力を活かして貢献したいです。
プログラミングの技術だけでなく、車への応用にどうつなげているかが明確に描かれた内容です。
抽象的な能力ではなく、具体的なデータ・成果・将来の関心分野が段階的に伝わる構成になっています。
【経験別例文】自動車関連のインターンシップ
私は大学3年の夏、自動車販売会社でのインターンシップに参加し、現場での接客や販売支援業務を経験しました。
お客様のニーズをヒアリングし、ライフスタイルに合った車種を提案する業務を通して、「ただ売るだけでなく、信頼関係の構築が重要である」と実感しました。
とくに印象的だったのは、ご家族連れのお客様に対して、安全性能と燃費性能を丁寧に説明した結果、購入につながったことです。
この経験から、商品知識とコミュニケーション力の両立が必要であることを学びました。
また、販売に関わる裏方業務として、在庫管理や見積作成、営業担当のスケジュール調整などにも携わりました。
現場での業務全体を知ることで、営業職の重要性と多忙さを理解し、自らの仕事への責任感を高めるきっかけになりました。
貴社では、お客様のニーズを正確に捉え、安心感と納得感のある提案ができる営業担当者として信頼される存在を目指して努力してまいります。
現場での体験を通して学んだ具体的なスキルと気づきを、今後の仕事観につなげた構成です。
販売・接客だけでなく、裏方業務にも触れており、実務理解の深さと責任感がしっかり伝わる例文になっています。
【自動車業界の志望動機】作成時の注意点とNG例文
自動車業界の志望動機を作成する際には何に注意して書いたらいいのでしょうか。
注意すべきことを頭に入れてから志望動機を作成することで、企業から高評価を受けることができます。
ここでは以下の注意点について詳しく解説していきます。
-
待遇・条件に触れている
-
具体性がない
-
受け身すぎる
-
顧客目線
待遇・条件に触れている
NG例文
私は、福利厚生が充実しており、働きやすい環境が整っている貴社に魅力を感じ、志望いたしました。
特に、年間休日や住宅手当、育成制度がしっかりしている点に安心感を持っています。
安定した環境の中で、長期的にキャリアを築きたいと考えております。
また、大手企業である貴社であれば将来の収入面でも安心できると感じています。
今後は、そうした環境の中で、社会人としてのスキルを少しずつ学びながら成長していきたいと考えています。
まず1つ目は、待遇・条件に触れていることです。
志望動機を書く際に、企業の待遇や給与、労働環境などについて触れるのはやめておきましょう。
そればかり書いてしまうと、会社の志望度や労働意欲を疑われてしまうかもしれません。
仕事の内容よりも給与や待遇の良いところを求めて転職してしまうかもしれないという印象を与えてしまう可能性があります。
企業は長く働いてくれる人材を求めているので、給与や待遇などについて書かれた志望動機では評価が低くなってしまいます。
そう思われることを避けるために、基本的にこれらには触れないようにしましょう。
働き方ややりたいことに結び付けてポジティブな書き方をするのであれば、必ずしもNGではありません。
具体性がない
NG例文
私は、自動車を通じて多くの人々の生活を支える貴社の取り組みに共感し、志望いたしました。
これまで社会を支えてきた企業の一員として、自分も誰かのためになるような仕事がしたく、そのためにも、貴社で経験を積み、自動車の魅力をより多くの人に伝えていきたいと考えています。
製品の素晴らしさを広め、多くの人に貢献できるよう努力し、今後も社会に必要とされる存在になれるように頑張りたいと思っています。
2つ目は、具体性がないことです。
具体性がない志望動機の評価は高くなりません。
社会貢献をしたい、御社の製品を広めたいなど具体的ではない志望動機では、企業研究ができておらず志望度が低いのではないかと思われてしまいます。
そのため、志望動機ではなぜそれを目指したのか、なぜやりたいのか、どのような部門のどのような事業に携わりたいかなどをできるだけ具体的に書けるようにすると良いでしょう。
自動車業界の業界研究、企業研究をしっかりして、その企業であなたがどのような働き方をしているかイメージしながら書くようにしてください。
なるべく抽象的な表現を避け、その企業の特色を織り交ぜて書くとより高評価を得ることができます。
受け身すぎる
NG例文
私は、自動車業界で必要とされる技術や知識を学びたいと思い、貴社を志望いたしました。
自動車に関する専門性や業界全体の仕組みについて、まだまだ知らないことが多くあります。
貴社の先進的な取り組みや豊富な実績の中で、そうしたノウハウを吸収し、知識を深めたいと考えています。
入社後は、現場で多くのことを学びながら、自分にできることを少しずつ増やしていきたいです。
まずは教わる姿勢を大切にし、自己成長を実現したいです。
3つ目は、受け身すぎることです。
御社に入社して、営業のノウハウを学びたいです、などといった受け身すぎる志望動機は評価が低いです。
これに加えて、学んだあとにそのスキルを使ってどのような仕事に就きたいか、どのように貢献できるかなどを述べられるとよいです。
あなたにはどんな強みがあり、どんな価値観で、それを企業でどう活かすことができるかをアピールしましょう。
受け身ではなく、自分で貪欲に学んでいく姿勢も大切です。
企業が求める人物像を意識しながら書くようにしてください。
ここまで書けるとクオリティの高い志望動機になります。
顧客目線
NG例文
私は、子どものころから貴社の製品に親しみがあり、今でもその乗り心地やデザインに魅力を感じています。
特に、家族で出かけたときに乗ったSUVは快適で、走行中も安心感がありました。
その経験から、貴社のファンとして、自動車の素晴らしさをもっと多くの人に届けたいと感じるようになりました。
自動車の魅力を伝える側になりたいという思いが強くなり、志望を決意いたしました。 まずは自分が愛用者として貴社の良さを伝えていきたいと思っています。
「御社の商品が好きで志望した」などといった顧客目線の志望動機もあまりよくないです。
入社後は商品を消費するのではなく、研究・開発、企画・マーケティング、経理、営業などといった仕事につき、辛い仕事もこなしていかなくてはなりません。
商品が好きなだけでは、やっていけないのでは?と思われてしまうこともあります。
企業の商品について言及することは悪いことではありませんが、ただ好きというだけではなく、自分が入社してからやりたいことや思いなどもアピールしましょう。
商品を好きで熱意があり、入社してからのイメージもついていれば評価の高い志望動機になります。
【自動車業界の志望動機】志望動機が書けたら...
自動車業界の志望動機の例文はいかがでしたでしょうか。
きっとあなたも書くことにチャレンジしてみようと感じているのではないでしょうか。
その勢いのまま志望動機を書き切ったあなたはそれに満足してしまうかもしれません。
しかし、この志望動機を第三者に確認してもらうことが大切です。
友人や家族に頼める人は添削をしてもらいましょう。
この第三者の確認はあなたが今まで気が付かなかったところや気にかけていなかった言葉遣いなどをしっかり見てもらえますよ。
友人や家族に頼むのは恥ずかしいと思っているあなたには「就活エージェント」がおすすめです。
就活のプロがあなたの志望動機をしっかり添削してくれます。
就活エージェントを活用することで、就職活動で悩んでいることを解決するために相談に乗ってくれたり、ESの文章を添削してくれます。
「就活エージェント」の中でも特におすすめなのは「ジョブコミット」です。
少しでも気になった場合は下記リンクから登録だけでもしてみて下さい。
【自動車業界の志望動機】まとめ
就活が本格化してくると各企業に合わせて志望動機を0から作るのは難しいです。
しかし、志望動機の中でも「あなたの就活の軸」やその根拠であれば使い回しが可能です。
しかし、入社後の「展望」に関しては企業によって強みなどが違いますので企業研究などしっかりして準備する必要があります。
出来上がった志望動機はできれば第三者に一度確認してもらって下さい。
その際おすすめなのは「就活エージェント」に頼る方法です。
是非、参考にあなたの就活を進めて下さいね。








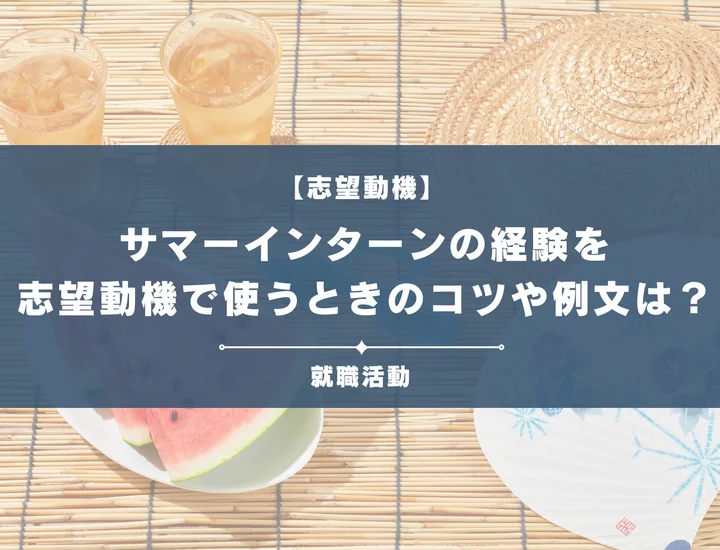







就活コンサルタント木下より
この例文は、具体的な事故にあった経験から自動車業界を志望するという事が書かれており、説得力のある志望動機になっています。
「なぜその業界なのか」「なぜその企業なのか」についての説明がされていることがポイントです。
経験などの具体例を織り交ぜ、その業界や企業を選ぶことになった経緯を自分の言葉で書くことが大切です。
他の企業でもいいのでは?と思われないように、企業研究もしっかりしたうえで志望動機を作成しましょう。