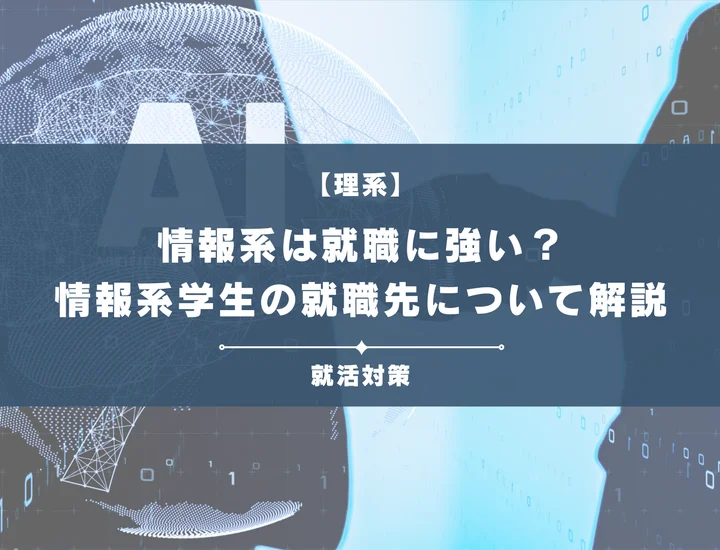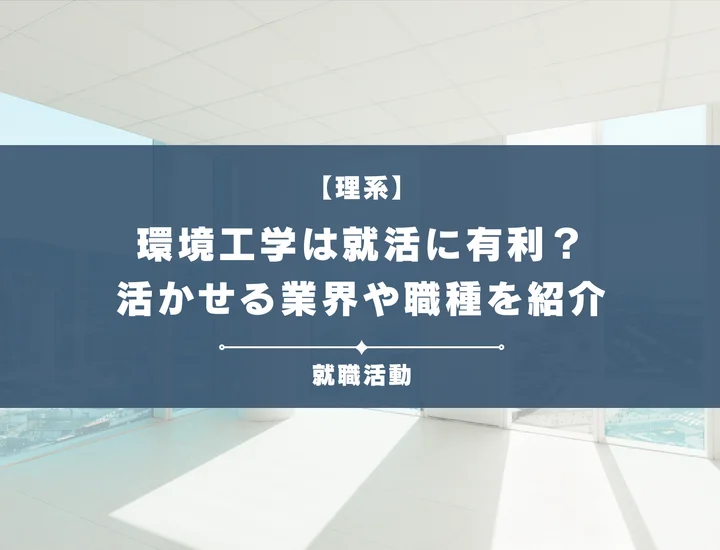HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就職活動を目の前に控えた大学3年生、もしくは修士過程1年生が気になるのが、「就職活動で何社くらいを目安に受ければいいのか」についてではないでしょうか?
正直、学業や研究だけでかなり忙しく、就職活動に時間を割けるか不安もありますよね。
そんなあなたのために、この記事では「理系と文系の就活難易度の違い」「なぜ理系の方がエントリー社数が少ない?」などの話から初めて「理系の学びが活かせる業界」「院進したほうが有利?」「研究と就活の両立方法」などの知りたい情報を順番に説明していきます。
最後にはより具体的な「エントリーする企業の内訳は?」「エントリーの多さで発生するメリット・デメリット」を説明していきますので、参考にしてみて下さい。
目次[目次を全て表示する]
【理系・何社受ける?】理系と文系の就活難易度の違い
まず最初は就職市場のエントリー数の傾向から説明していきます。
きっとあなたも気になっていると思いますが「理系と文系の就活難易度の違い」があるのかについて詳しく見ていきましょう。
まず文系の平均的なエントリー数は約20社です。
これが多いのか少ないのか判断が難しいと思いますので、理系の平均的なエントリー数を言うと約5〜10社と、多くて文系の半分程度となります。
理系の中でも学部で細分化していくと、工学系の方が就活市場でも仕事の数自体が多いため、やや有利になる傾向があり、物理系の方が不利と言われることが多いです。
【理系・何社受ける?】なぜ理系の方がエントリー社数が少ない?
文系よりも理系の就活生の方がエントリー社数が少ない傾向にあることがわかりましたが、「なぜ理系の方がエントリー社数が少ない?」と疑問に思いませんか?
この項目では「理系の学びを活かせる業界が限られているから」「院進を考える人もいるから」「研究との両立が大変だから」「企業から学校あてに推薦がくる場合があるから」の代表的な理由である4つを順番に説明していきます。
きっと理系のあなたであれば、納得の理由になっているはずですよ。
理系の学びを活かせる業界が限られているから
まず最初の理由は「理系の学びを活かせる業界が限られているから」です。
文系は経済学部や経営学部、文学部など、専門性が高すぎず汎用性の高い学業であるため、就職先の幅も広く大学で学んだことを広く浅く活かせる傾向にあります。
しかし理系に関しては、専門性が高い内容を勉強し、研究室では難しい問題や課題に対して時間を割き、突き詰めていくことが多く、その学びの内容を活かせる業界は自然と狭く限られた業界になりがちです。
その上、難しい研究をしてきたからこそ、その知識や技術を活かせる業界に就きたいと思う就活生が多く、そこのことも志望できる業界を狭めている要因の一つと言えます。
院進を考える人もいるから
文系の学生に比べ、理系の学生は「院進を考える人もいるから」就職活動よりも試験勉強やその対策に時間を取られてしまうため、エントリー社数が少なくなる傾向にあります。
院進を考えながら就職活動を行っている場合、院進に失敗した時の保険であったり、人生の経験の内と考え行っている場合もあり、センター試験の記念受験と同じ考え方です。
そのため、あくまで院進を考えている学生は勉強を最優先しているため、自然とエントリー社数が少なくなるということになります。
研究との両立が大変だから
理系の大学生は3年生、4年生となっても毎日のように研究室に通うことが一般的で、就職活動が始まったとしても、「研究との両立が大変だから」エントリー社数を減らす傾向にあります。
それに加え、アルバイトも並行して行っている場合、研究室、アルバイト、就職活動の3つを掛け持ちすることになり、物理的にこなせなくなるため、「もう無理!」となるのは当然です。
その3つを全力で取り組むためには、少ない時間を見つけて行うしかないため、エントリーする業界や企業を広げることは得策ではなく、自分を苦しめる選択です。
事前にしっかり業界・企業研究を行い、エントリー社数を絞ることで、一社一社にしっかりと向き合う時間ができ、対策を取ることができるため効率的です。
企業から学校あてに推薦が来る場合があるから
理系の場合、専門性が高いため特定の学校の研究室に向けて企業から推薦が来ることが少なくないため、そもそも就職活動のエントリーすら必要ない場合もあります。
この推薦は大学の指定校推薦に似た制度で、学内の選考を通過する必要があったり、一度選考を受け内定を獲得した場合、辞退できないなどの制約があります。
しかし、選考の内容が他の一般応募の就活生よりも短縮、簡略化されている場合が多いので、推薦が来ている企業に入社の意志がある場合は活用しない手はないです。
研究室を選ぶ時すでにこの推薦制度を把握している学生も多く、この制度を利用する就活生は自然と学内推薦の対策に集中するため、自然とエントリー社数が減るということです。
【理系・何社受ける?】理系就活生の平均エントリー数は?
理系就活生は文系に比べてエントリーする企業の数が少ない傾向があります。
これは単なる応募意欲の差ではなく、学びの内容や進路の選択肢、研究との両立、推薦制度など複数の要因が関係しています。
理系特有の事情を理解することで、効率的に就職活動を進めるための参考になります。
理系の学びを活かせる業界が限られているから
大学や大学院で学んだ専門的な知識やスキルを発揮できる企業は、業界や分野がある程度限られます。
そのため志望先は、自分の研究分野と密接に関わる企業や部署に集中する傾向があります。
幅広い業界に応募するよりも、関連性や適性を重視して応募するため、自然とエントリー数は少なくなります。
また、専門性が高い企業ほど採用枠が少ないことも多く、応募先は厳選される傾向にあります。
結果として、理系就活生は量より質を重視する応募スタイルになりやすいです。
院進を考える人もいるから
学部卒業後に大学院進学を検討している学生は、就職活動を本格的に行わない場合があります。
進学が第一希望の場合、就職活動は進学先が決まらなかった場合の保険という位置づけになることもあります。
そのため、エントリー企業はごく一部に限られる傾向があります。
就職活動の準備や企業研究に時間を割くよりも、進学試験や研究に集中するケースも多く、結果として応募数が少なくなります。
こうした状況は特に研究職や専門職を志望する学生に見られます。
研究との両立が大変だから
理系の学生は、卒業研究や修士論文の作成などで多忙な時期と就職活動のピークが重なることがあります。
研究は進捗や成果が評価に直結するため、疎かにすることはできません。
そのため、長期にわたる就職活動よりも、限られた時間で応募する企業を厳選するスタイルになります。
特に研究室のスケジュールや教授の指導方針によっては、面接や説明会の日程調整が難しい場合もあります。
結果として、効率的に応募先を絞らざるを得ない状況が生まれます。
企業から学校あてに推薦が来る場合があるから
大学や大学院によっては、企業から直接推薦依頼が届くことがあります。
推薦応募は選考が短縮されることが多く、内定率も高い傾向があります。
このため、推薦を受けた場合は他の企業への応募を控える学生も少なくありません。
推薦制度を利用することで、限られた労力で確実に内定を得る戦略を取る学生が多いのです。
結果として、全体のエントリー数は減るものの、内定獲得率は高くなるという特徴があります。
【理系・何社受ける?】理系就活生がエントリーする会社の選び方
理系就活生がエントリーする企業を選ぶ際には、自分の強みや価値観を明確にした上で、効率よく候補を絞ることが重要です。
専門知識を活かせるか、新しい分野に挑戦できるか、働きやすい環境かなど、基準を定めて探すことでミスマッチを防ぎやすくなります。
ここでは、理系就活生が企業選びを進める際の具体的な視点を解説します。
軸を明確にする
企業を選ぶ前に、自分が働く目的や将来の方向性をはっきりさせることが大切です。
研究で培った専門知識を社会に役立てたいのか、新しい分野でスキルを広げたいのか、それとも働きやすさや安定を重視するのかを考えます。
複数の視点で軸を持つと、企業を比較した際に優先順位がつけやすくなります。
また、軸が明確になると志望動機にも一貫性が出て、選考時の説得力が高まります。
迷った時は、価値観や将来像を紙に書き出して整理すると効果的です。
研究内容と関連性の高い企業から探す
理系就活生の強みは、専門性の高さと研究で得た知識の深さです。
その強みを活かすためには、自分の研究内容に関係する企業を優先的に探す方法が有効です。
研究室と共同研究を行っている企業や、学会で関わった企業は候補になりやすいです。
さらに、教授やキャリアセンターに相談することで、自分の専門に関心を持つ企業を紹介してもらえる場合があります。
こうしたつながりを利用すれば、入社後の業務との親和性が高まり、早期に成果を出せる可能性も高くなります。
逆求人型サイトを活用してみる
研究や授業で忙しく、企業探しの時間を十分に確保できない学生に有効なのが逆求人型サイトです。
自分のプロフィールや研究テーマを登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届きます。
これにより、自分では考えていなかった業界や意外な企業との出会いが生まれることもあります。
効率的に情報収集や企業選定を進められるため、就職活動の幅を広げる手段として有用です。
特に、研究の合間に就活を進めたい人には適した方法と言えます。
【理系・何社受ける?】理系の学びが活かせる業界
ここの項目では、理系の分野を学んだ就活生が向いているかもしれない「理系の学びが活かせる業界」について説明していきます。
イメージできる範囲でいうと、研究をしていることが想像できる製薬業界などが代表的でしょうか。
しかし、理系の学びが活かせる業界は思っているよりも幅広く、IT業界や製造業、エネルギー業界、輸送業会、素材業界、意外なところでいうと金融業界なども含まれます。
ではなぜこれらの業界で理系の学びが活かせるのか気になりますよね。
その詳しい内容が知りたい場合は以下のリンクから飛んで確認してみて下さい。
【理系・何社受ける?】院進したほうが有利?
ここでは先ほども軽く触れましたが理系の学生は院進する人が多い傾向にあり、就活では「院進したほうが有利?」なのか気になりますよね。
結論から言いますと、有利に働くことが多いです。
院進することで、より高い専門的な知識と経験を積むことで、就職活動において学部生時代よりも選択肢の幅が広がることは間違いありません。
しかし、これは研究職などの高い専門性を必要とする企業の場合で、どの職に関しても同じことが言えるとは限りませんので注意が必要です。
それに加え、多くの企業では学部卒よりも院卒の方が初任給が高い傾向にあり、初年度の年収もそれに伴い高くなります。
【理系・何社受ける?】研究と就活の両立方法
理系の学生は勉強や研究室で忙しく、それにアルバイトもしている場合、正直就職活動を行っているような時間はないというのが本音だと思います。
しかし、どうにか時間を作りエントリーシートを作成したり、面接対策を行う必要があります。
ここでは「研究と就活の両立方法」として「隙間時間を活用する」「先輩のアドバイスをもらう」「就活エージェントを活用する」の3つを順番に説明していきます。
時間がないからこそ意識するべきポイントですので、しっかり確認して下さいね。
隙間時間を活用する
まずは「隙間時間を活用する」ことを意識していきましょう。
「そんなこと言われても、もうびっしりスケジュール埋まっているよ」という声が聞こえてきそうですが、本当にそうでしょうか?
朝、大学に向かうために乗る電車の時間、駅から大学までの歩いている時間、研究で結果待ちの時間、大学からバイト先に向かう時間など、あなたは今その時間を何に使っているでしょうか?
もし音楽を聞いている、寝ているのであれば、その時間の一つだけでも自己分析をする時間、面接での受け答えを頭で練習する時間に置き換えてみましょう。
それだけでも意識が就職活動に向くことになり、自然と隙間時間を見つけて取り組むようになるはずです。
先輩のアドバイスをもらう
大学の先輩という存在は非常に貴重な存在で、学業だけでなく就職活動のこと、就職して実際働くということなど、色々な知識を与えてくれる存在です。
そのため、もしあなたが研究室、アルバイト、就職活動の両立に苦しんでいるのであれば「先輩のアドバイスをもらう」ことをおすすめします。
仮に同じ業界を目指していなくても、どのように就職活動を乗り越えたのかを、同じような状況であったはずの先輩に聞くことで、具体的な解決策を教えてくれるかもしれません。
就活エージェントを活用する
もしあなたが先輩に聞くのはちょっと遠慮してしまう、相談するにも友達がまだ就職活動のモードに入っておらず相談できないと悩んでいる場合は、第三者に相談してみましょう。
そこで私がおすすめする方法が「就職エージェントを活用する」という方法です。
この就活エージェントは就職活動のプロで、何社エントリーすればいいのかはもちろん、エントリーシートや面接対策、業界選びまでサポートしてくれます。
第三者なので逆に普段聞きにくいことも聞きやすく、あなたの就職活動が終わるまで隣でサポートしてくれるので心強い存在になること間違いなしです。
少しでも気になった場合は下記にリンクを貼っておきますので、登録だけでもしてみて下さい。
【理系・何社受ける?】エントリーする企業の内訳は?
ここからはより具体的に、理系の就活生が何社にエントリーするのか、その「エントリーする企業の内訳は?」について説明していきます。
理系の就職活動の平均エントリー数は平均して5〜10社というのは、一番最初の項目で説明しましたが、その詳しい内訳は「第一志望群が5社以内、第二志望群が10社以内」を目安にすると安心です。
それに加え、選考の日程は全てコントロールできる訳ではありませんが、できるだけ第二志望群を先にスケジュールしておくとさらに安心です。
その理由は、第二志望群の企業で選考の経験を積んでおくことで、第一志望群の選考で自分の力を発揮しやすくなるためです。
【理理系・何社受ける?】エントリーの多さで発生するメリット・デメリット
最後に就職活動における「エントリーの多さで発生するメリット・デメリット」を両方説明していきます。
当然ですが、エントリーをしないことには就職活動は進みませんし、内定を獲得することはできません。
しかし、多くの企業にエントリーしたからといって、必ず内定がもらえる訳でもなく、エントリー数を限定したからといって、良い準備ができるとも限りません。
ここではどちらの場合も想定してメリット・デメリットを説明していますので、あなたの性格や就活の進め方も含めて、メリットがあるのはどちらなのかを考えてみましょう。
多くエントリーしたときのメリット・デメリット
まずは「多くエントリーしたときのメリット・デメリット」を説明していきます。
メリットとしては、「場数を踏むことで選考に慣れる」「職に就けない可能性を下げる」の2つが挙げられます。
就職活動の最大の難関である面接は、あなたが思っているよりも緊張します。
そのため面接やグループワークを多くこなすことで、その雰囲気に慣れ、あなた本来の力を発揮することができるようになります。
それに加え、就職できない可能性を下げることにも繋がり、この2つが大きなメリットです。
逆にデメリットとしては「学業に影響が出る」「一社一社に掛けられる時間が減る」ことです。
どちらも選考に時間を割くことで生じるデメリットで、両方がダメな方向に向かうことで、負の連鎖を起こし、最悪の場合単位が足りずに留年する可能性もあり危険です。
エントリー社数を限定したときのメリット・デメリット
次に「エントリー社数を限定したときのメリット・デメリット」を説明していきます。
メリットとしては「一社一社に対してしっかり対策ができる」「学業との両立がしやすい」ことです。
ただでさえ時間がない理系の就活生は、しっかり対策をしようとすると自然とエントリー数が限定されていきます。
また、エントリー数を限定することで、研究も疎かにならずきちんと両立することができます。
いいことばかりに聞こえますが、限定することで起こるデメリットもあり、それは「選考慣れできずにいつまでも本来の力を発揮できない」「最悪の場合就職できない」です。
先ほども触れましたが、面接は緊張するので慣れるまで本来の力を発揮できない就活生が多く、これがいつまでも続くと最悪の場合就職できない可能性があります。
そのため、事前の準備を人よりも行う必要があります。
まとめ
理系は文系に比べて専門性が高く、それを活かすためにあらかじめ業界を絞ることで、自然とエントリー数が少なくなる傾向にあります。
しかし、エントリー数は学業との両立、企業からの推薦、院進などの要因もあり、その数だけ見て一概に文系よりも理系の方が就職活動の難易度が低いとは言い切れません。
多くの就活生が悩む就職活動と学業の両立は、隙間時間を見つけることと、先輩や就活エージェントに相談することで少しでも解決することができそうです。
就職できるか不安だからと、むやみにエントリーすることは得策ではなく、間口を広げるのか、限定するのかは、自分の性格と相談して決めてみて下さいね。