
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就活の軸が見つからなくて悩んでいる方へ
就職活動が本格的に始まろうとしている時期に「今ひとつやる気が起きないな〜」と感じている原因はもしかすると就活の軸が定まっていないことにあるのかも知れません。
しかし就活の軸と言われてもいまいちピンときていない就活生は思いの外多く、自分だけかもと悩む心配はありません。
この記事では就活の軸について色々なポイントに焦点をあて、その意味や企業が聞いてくる理由などを説明していきます。
就活の軸のことで悩むのは、この記事を読んでやめることができるはず!
【就活の軸がない】就活の軸とは
まずはそもそも「就活の軸とは」何を意味しているのかを説明していきます。
就活の軸とはあなたが大学を卒業し、企業で働く上で絶対に譲れないことや条件のことを指します。
例えば「絶対に実家から通える範囲で働きたい」「在学中に取得した〇〇の資格を活かしたい」「土日休みは譲れない」などのことを言います。
この就活の軸、つまりはあなたが何がなんでも譲れない条件などをあらかじめ決めておかないことには就職活動は前に進みません。
就活の軸を決めずに就職活動をするということは、暗闇を闇雲に歩き回ることと同じです。
就職活動が本格的に始まる前に就活の軸は決めておいた方が良いと言えるでしょう。
【就活の軸がない】就活の軸を決めるメリット
就活の軸の意味や就職活動における重要性が分かったところで、次はより具体的に「なぜ就活の軸を決めた方が良いのか」の理由に迫っていきたいと思います。
ここでは特に重要な「企業選びに一貫性が出る」「効率良く就活が進められる」「働くイメージが付く」の3つに絞って詳しく説明していきます。
企業選びに一貫性が出る
就活の軸を決めた方が良い理由の1つ目は「企業選びに一貫性が出る」ためです。
就活の軸、つまりあなたが絶対に譲れないことや条件を決めておくことで、受ける企業に一貫性を持たせることができます。
このことは受ける企業に共通点を自然と作ることに繋がり、選考時に「他に受けている企業はありますか?」という質問にも一貫性を持ち答えることができるようになります。
また、就活の軸を「〇〇業界で働きたい」と業界を絞るような条件があると、より業界や企業への志望度が高いことをアピールするための材料にすることもでき便利です。
効率良く就活が進められる
就活の軸を決めた方が良い理由の2つ目は「効率良く就活が進められる」ためです。
就活の軸が定まっていないと、先ほど説明したように暗闇の中を闇雲に歩き回るのと同じ状態になってしまいます。
これを就職活動に置き換え考えると、別に対して志望度が高くない企業の選考を受けに行き、時間を無駄にしてしまう状況と同じです。
就職活動が本格的に始まると、1日に2社の面接に行き、隙間時間にエントリーシートを書き、それが終わるとアルバイトのような過酷な日々を過ごすことになります
そのため、闇雲に歩き回る時間をできるだけ少なくするために、あらかじめ就活の軸を決めておいた方が良いと言えるでしょう。
働くイメージが付く
就活の軸を決めた方が良い理由の3つ目は「働くイメージが付く」ためです。
就活の軸を考える際に全員が必ず行うのが、就職し働くことを現実的に想像することです。
家からの通勤、出勤後の働く内容、退勤後のプライベートの時間など、現実的にイメージすることで自分に必要なことや絶対に避けたい状況を考えることができます。
これはあなた自身がどのように働きたいのか、将来どうなりたいのかなどを考えるきっかけにもなります。
ここまで考えるには何かのきっかけがないと難しいため、就活の軸を考えるという行為自体にメリットがあると言えます。
ミスマッチを防止できる
就活の軸を決めた方が良い理由の4つ目は「ミスマッチを防止できる」ためです。
就活の軸を明確にすることで、自分の価値観や考え方に合った企業を選ぶことができ、ミスマッチを防止することができます。
軸が定まることで、自分の理想と異なる企業に応募する機会が減り、就職後の不満や早期退職のリスクを軽減できます。
また、企業側も就活生の軸を通じて価値観や人柄を判断し、企業理念に合った人材を見つけやすくなります。
結果として、企業と就活生の双方にとって満足度の高い採用が実現し、就職後の活躍も期待できます。
【就活の軸がない】就活の軸を定めないときのデメリット
就活の軸を定めることは、就職活動を成功させるための重要なステップです。
しかし、軸がないまま就活を進めると、いくつかのデメリットが生じる可能性があります。
以下では、軸を定めないことによる具体的なデメリットについて詳しく解説します。
面接官からの印象が良くない
就活の軸がないと、面接官に対してあまり良い印象を与えられない可能性があります。
面接官は、応募者がどれだけ自分自身のキャリアについて深く考えているか、どれだけ企業と自分のビジョンが一致しているかを確認したいと考えています。
しかし、軸が定まっていない場合、面接での質問に対して曖昧な答えをしてしまい、結果的に面接官にマイナスな印象を与えてしまうことがあります。
また、就活の軸がないと、応募先の企業との相性をしっかりとアピールできず、内定をもらえない可能性が高まります。
就活でのモチベーションがなくなる
就活の軸が定まっていないと、就活全体のモチベーションが低下する可能性があります。
軸がない状態では、就活の進め方が曖昧になり、具体的なゴールが見えにくくなるため、就活に対する意欲が低下しがちです。
このような状況に陥ると、自己分析や企業研究に力が入らず、結果として就活の結果にも悪影響が出ることがあります。
また、軸がないことで、複数の企業に応募する際に一貫性のない志望動機を述べることになり、企業側に誠実さや熱意を伝えにくくなります。
【就活の軸がない】企業が就活の軸を聞く理由
就活の軸を考えるだけでメリットがあることが分かったところで、次は逆の立場から「企業が就活の軸を聞く理由」を説明していきます。
ここでは代表的な理由として「どういう働き方を望んでいるのか」「業界・企業に対する志望度の高さを知りたい」の2つに絞り深掘りして説明していきます。
どういう働き方を望んでいるのか
企業が就活の軸を聞く理由の1つ目は「どういう働き方を望んでいるのか」を汲み取るためです。
企業の採用担当者が就職活動で一番重視しているのは、あなたと企業のマッチ度が高いかどうかです。
社風や価値観が合うのか、今いる社員とやっていけるのかどうかと同様に、働き方の思考がマッチしているのかも重要です。
そのため、企業の採用担当者はあなたの望む働き方と自社の働き方を見比べ、本当にあなたが活躍できる環境なのかを判断しています。
ここのマッチ度が低いと、どんなにあなたのスキルや能力が高くてもそれを活かすことができないと判断されてしまうことでしょう。
業界・企業に対する志望度の高さを知りたい
企業が就活の軸を聞く理由の2つ目は「業界・企業に対する志望度の高さを知りたい」からです。
就活生が受ける企業を選ぶ理由としてたまに聞くのが「有名だから」「テレビCMを見たことがあるから」などの安直な理由です。
しかし、当然ですがこの理由では選考を通過することはできないと断言できます。
「業界に将来性を感じたから」「自分のスキルを活かしたいから」「大学で学んできた領域だから」ときちんとした理由があれば志望企業に一貫性を持たせることができます。
この志望企業に一貫性を持たせることは、業界・企業に対する志望度の高さをアピールできる材料になるため意識しておいて損はありません。
自社に合うかどうか
就活の軸は、学生の価値観や働き方の希望が反映されたものです。
企業が就活の軸を尋ねる理由は、その軸が自社の方針や理念と合致しているかを確認し、ミスマッチを防ぐためです。
学生が求める働き方と企業の方向性が異なる場合、モチベーションを維持することが難しく、早期離職のリスクが高まります。
そのため、企業は面接で学生の就活の軸を確認し、自社に長く貢献できる人材かどうかを見極める意図があります。
【就活の軸がない】わからない原因
就活を一生懸命頑張っているにもかかわらず、就活の軸が分からなくなってしまうことは多くの就活生が経験する悩みです。
ここでは、主な原因として
- 「悩みの増加」
- 「選択肢の多さ」
- 「経験不足による自信の低下」
の3つについて詳しく解説します。
就活を頑張る中で悩みが出てくる
就活を進めるうちに、多くの業界や職種についての情報が入ってきます。
これにより、最初は「やりたい」と思っていたことでも、業界や企業に対するデメリットが見えてきて、迷いが生じることがあります。
例えば、最初は志望していた業界でも、働き方や将来性に不安を感じ、志望度が下がることがあるかもしれません。
このような状況では、一度立ち止まり、自分が本当に求めるものが何かを再考することが重要です。
選択肢が多すぎる
多くの業界や職種に興味があると、「本当に自分に合ったものは何か?」と悩むことになります。
就活は将来のキャリアを決定する大きな選択であり、どれか一つに絞るのが難しく感じるのは当然です。
選択肢が多すぎると、すべてに手を出そうとしてしまい、結果的にどれも中途半端になってしまうことがあります。
こうした状況を避けるためには、まずはいくつかの業界を少しずつ試してみる「絞り込み型の自己分析」が効果的です。
経験が少なくて自信が持てない
学業やアルバイトで特筆すべき成果を出していないと感じると、自分に強みや軸がないのではないかと不安に感じることがあります。
特別な経験がなくても、小さな成功や失敗の中で自分が工夫した点や乗り越えた点に目を向けることが大切です。
【就活の軸がない】就活の軸の見つけ方
企業が就活の軸を聞く理由がぼんやりとでも理解できたところで、ここの項目では「就活の軸の見つけ方」について説明していきます。
効率的に就活の軸を決めるための方法として、ここでは「自己分析」「業界・企業研究」「目標の設定」「優先順位の設定」の4つのステップに分けて説明していきます。
自己分析
就活の軸を決めるために必要なこと1つ目は「自己分析」です。
自己分析とはその文字の通り、自分のことを分析することです。
あなた自身の過去の経験や体験を振り返り、その当時の感情やモチベーションの源泉を探ることで価値観や思考回路を紐解くことができます。
就職活動にこの自己分析は必須と言えるため、もう少し深掘りして説明していきますね。
どういうことに興味がある?
自己分析を行う際に意識して欲しいのが「どういうことに興味がある?」と自分に問いかけ考えることです。
「今の自分は何に興味があるのか」「高校生の時の自分は何に興味があったのか」「今、熱中していることは何?」「あの時ハマっていたことは?」といった調子で自分に問いかけていきましょう。
そうすることで、過去のあなたから今のあなたまで、いったい何に興味があったのかが分かります。
それらの興味があったことの共通点を考えることで、「自分は1人で黙々と何かに打ち込むことが好きなんだ」「人と接することが好きなんだ」と発見できるはずです。
どこに強みがある?
自己分析をすることで自分の「どこに強みがある?」という問いに答えることができるようになるはずです。
この自分の強みを何もせず自分自身で把握できている人はそう多くはありません。
しかし、自己分析をしっかりと行うことで、「自分は〇〇に強みがありそう」「人よりも〇〇が優れているな」「〇〇の部分は自信がある」と気付くことができます。
これは入社後に活かしたい自分の特徴を把握するためには必須であり、就活の軸を考える上でもとても大切な要素になります。
また、自己PRや志望動機を組み立てる際にも活かすことができるため、汎用性が高いと言えます。
どんな価値観を持っている?
自己分析をしっかりすることであなた自身「どんな価値観を持っている?」ということが見えてくるようになります。
例えば大勢と過ごす時間よりも1人でのんびりする時間の方が好きだとか、自分のためよりも他人のための方が頑張れるなど。
あなたの今までの経験を振り返ることで、あなたが何を優先してきたのか、何に重きをおいてきたのかが分かるはずです。
そのあなたの価値観は働く上でも曲げることは難しく、それから逸れるようなことがあれば大きなストレスを感じるようになります。
この価値観が企業とマッチしていないと、最悪の場合早期退職に繋がる可能性も否定できません。
業界・企業研究
就活の軸を決めるために必要なこと2つ目は「業界・企業研究」です。
自己分析をすることで、あなたが興味ある業界や企業がある程度絞れてくるはずです。
ある程度絞れたら次にする必要があるのが、その業界全体をまず調べ全体像をざっくりと把握することです。
業界全体の規模感や将来性、業界内の大手企業のことやこれからの課題などを事前に把握しておくことで、企業の特徴がより理解しやすくなります。
そこからあなたが気になった企業を数社ピックアップし深掘りしていきます。
社風や企業の歴史、具体的な事業内容や同業他社との差別化のポイント、求める人物像などをしっかりと把握していきましょう。
目標の設定して逆算する
就活の軸を決めるために必要なこと3つ目は「目標の設定」です。
できればこの目標は短期目標と長期目標の2つを準備しておく方が良いと言えます。
その理由は、目の前にある課題をがむしゃらにこなして到達できる短期目標だけでは将来のビジョンを組み立てるのが難しいためです。
とは言いつつ長期目標だけを設定しても、今すぐにやるべきことが見えなくなってしまいます。
「10年後には部長になってやるぞ!そのためには3年以内に〇〇の中で一番の成績になることを目標にしよう!」と2段階の目標があると、今やるべきことが見えてくるはずです。
もしくは3年間隔で目標を設定していく方法もあり、こちらの方がより目標を更新しやすく、モチベーションの維持に繋がると言えます。
優先順位の設定し考える
就活の軸を決めるために必要なこと4つ目は「優先順位の設定」です。
自己分析や業界・企業研究、目標の設定を通じてあなたが大切に思っていることや、大事にしたい価値観が何個か浮かび上がってきているはずです。
しかし、それらの全てを叶えてくれる企業に出会うことは難しく、優先順位をつける必要があります。
また、エントリーシートや面接で伝えることができる範囲にも限りがあるため、多くても3つまでに絞っておきましょう。
「絶対に〇〇の資格を活かす!」「絶対に実家から近くが良い!」「土日祝休みは譲れない!」といったように、自分の中でベスト3を決めておくことをおすすめします。
行きたい企業から共通点を調べる
就活の軸を決めるためには、まず行きたい企業から共通点を調べることが重要です。
業界研究や企業研究を通じて、興味がある業界や企業の共通点を見つけることができるので、その共通点をもとに、自分の優先事項を考えてみましょう。
例えば、企業の魅力に感じた点を具体的に挙げてみることで、自分が就活するうえで何を大切にしたいのかが見えてきます。
こうすることで、自分の価値観や考え方に合った就活の軸を見つけることができ、より効果的な就職活動が可能になります。
周りに話を聞いてみる
就活の軸が見つからないときは、家族や友人、先輩など、身近な人たちに話を聞くことが有効です。
自分の考えだけでなく、他人の視点を取り入れることで、新たな発見が得られる場合があります。
たとえば、家族に自分の性格や強みについて聞いたり、友人と将来の働き方について話し合ったりすることで、自分では気づかなかった可能性や価値観が浮かび上がることがあります。
また、先輩に実際の仕事や業界の話を聞くことで、具体的な働くイメージを掴む手助けにもなります。
OBなどインタビューを参考にする
企業のホームページやSNSに掲載されている情報を活用して、自分が働いている姿をイメージするのも効果的です。
特に、OBやOGのインタビュー記事は、就活中のエピソードや実際の職場での経験談が詳しく載っているため、非常に参考になります。
こうしたインタビューを通じて、同じ企業や業界で働く人々の価値観や仕事への取り組み方を知ることで、自分に合う職場や業務内容を見つけやすくなります。
【就活の軸がない】就活の軸の主な分類
就活の軸を選ぶことは、理想の職場を見つけるために非常に重要です。
自分にとって何が大切かを明確にすることで、ミスマッチを防ぎ、より満足度の高い就職活動ができます。
以下に、就活の軸を選ぶためのポイントを3つに分類して説明します。
働き方・環境
就活の軸として、まず働き方・環境が挙げられます。
勤務地や働き方(休日・フレックス・残業)を考慮し、自分にとって理想的な環境を見つけましょう。
また、福利厚生や給与、人間関係なども重要な要素です。
ただし、これらの希望を企業に直接伝えるとマイナスイメージを与える可能性があるため、自分の中で優先順位を明確にしておくことが大切です。
これにより、自分が快適に働ける環境を見つけやすくなります。
企業の文化や理念
次に、企業の文化や理念も重要な就活の軸です。
企業の規模(大手・ベンチャー・中堅)や業務の成長速度、ブランド力などを基に選ぶことができます。
また、企業のビジョンや社風に共感できるかどうかも重要なポイントで、企業の理念をもとに選ぶことで、企業側の印象も良くなり、志望動機にもつなげやすくなります。
これにより、ミスマッチを避け、企業との相性を高めることができます。
仕事内容
最後に、仕事内容も就活の軸として重要です。
自分の努力が評価される働き甲斐や、達成感や成長を感じられる仕事を見つけましょう。
また、職種の選択も重要で、興味や経験に基づいてどのような仕事に就きたいかを考えます。
さらに、キャリア展望も考慮し、企業内での昇進の可能性や、独立支援や留学制度などのサポートがあるかを確認することも大切です。
これにより、モチベーションを高め、長期的に充実したキャリアを築くことができます。
【就活の軸がない】簡単にかける文章構成のコツ
就活の軸を文章にする際、明確で分かりやすい構成を意識することが重要です。
特に、エントリーシート(ES)や面接で伝える際は、簡潔かつ論理的にまとめることで、採用担当者にスムーズに理解してもらいやすくなります。
就活の軸を整理する際には、「結論」「根拠とそれに関する経験」「企業との関連性」の順番で書くと、より説得力のある内容になります。
結論
最初に、自分の就活の軸を端的に述べることが重要です。
たとえば、「私の就活の軸は、技術を活用しながら、社会に価値を生み出せる仕事に携わることです。
」と明確に伝えることで、相手は何についての話かをすぐに理解できます。
このように、最初に結論を述べることで、論理的な構成になり、相手に伝わりやすくなります。
また、面接では、面接官が限られた時間の中で話を聞くため、最初に結論を述べることで、話の方向性が明確になり、スムーズに進めることができます。
根拠とそれに関する経験
次に、なぜその軸を持つに至ったのか、根拠となる経験を述べます。
たとえば、「大学での研究活動を通じて、技術が社会の課題解決に貢献できることを実感しました。
」といった形で、自分の経験を交えて説明すると、より説得力が増します。
また、具体的なエピソードを加えることで、就活の軸が単なる理想論ではなく、実体験に基づいたものであることを伝えることができます。
企業との関連性
最後に、自分の就活の軸と企業とのつながりを示すことで、企業にマッチしていることを伝えます。
「貴社は、技術を活かして社会課題の解決に取り組んでおり、私の就活の軸と一致しています。
」のように、企業の事業や理念と関連づけることで、志望動機にもつながる内容になります。
他にも、企業の特徴を具体的に挙げながら、「貴社の〇〇事業では、新しい技術を活用し、社会に新たな価値を提供しており、私の目指す方向性と一致しています。
」と述べると、より企業研究をしていることが伝わります。
【就活の軸がない】就活の軸で避けるべき内容
就活の軸を決めるために必要なことが分かったところで、次は「就活の軸の注意点」を説明していきます。
ここでは「待遇や受け身な姿勢を出す」「理由もなく抽象的な内容」の特に注意が必要なポイントを一緒に確認していきましょう。
待遇や受け身な姿勢を出す
就活の軸の注意点1つ目は「待遇や受け身な姿勢を出す」ことです。
「就活の軸は給与ができるだけ高い企業を受けることです」と正直に答える就活生はいないと思いますが、このように待遇面を就活の軸にするのは避けましょう。
また「福利厚生が他社よりも優れている」「有休消化率が高い」「社員食堂が安い」「社内研修が充実している」などの理由も表には出さないようにしましょう。
正直、給与も福利厚生も有休消化率も社員食堂も働く上ではとても大事な要素です。
そのため、企業を選ぶ基準にすること自体は問題ではありません。
しかし、企業の採用担当者に伝わらないように意識は常にしておきましょう。
理由もなく抽象的な内容
就活の軸の注意点2つ目は「理由もなく抽象的な内容」は避けたいところです。
人気の業界である食品業界でありがちなのが「食べるのが好きだから」というとてつもなく抽象的な就活の軸です。
これではあなたの個性やオリジナリティを全く感じることができないため、アピールには繋がらないと言えます。
過去のあなたの経験を紐付けし、なぜ食べることが好きになったのかを具体的なエピソードと共に説明することで、あなた独自の就活の軸を完成させることができます。
誰にでも当てはまるような内容にならないように注意していきましょう。
どの企業にも当てはまる軸
就活の軸を決める際には、どの企業にも当てはまるような一般的な軸を避けることが重要です。
どれほど納得できる体験談やエピソードをもとにしていても、それがすべての企業に当てはまる軸であると、「他社でもいい」という印象を与えてしまいます。
したがって、自分で定めた軸とその企業がどのように関連しているかを企業分析を通じて調べ、その点を志望動機として伝えることが大事です。
企業ごとに異なる価値観や文化に合わせた軸を設定することで、より効果的なアピールが可能になります。
会社目線の軸を設定する
就活の軸を設定する際、避けるべきは「この製品が好きだから」や「このサービスに共感したから」といった消費者目線の理由です。
これらは企業を選ぶ基準として浅く感じられるため、面接官に十分な企業理解がないと判断される可能性があります。
代わりに、企業の一員としてどのように貢献できるかを考える「従業員目線」の軸を設定することが重要です。
たとえば、「新しい市場を開拓したい」や「グローバルな事業で挑戦したい」といった目標を掲げることで、企業の目標と自分の目標が一致していることを示せます。
これにより、採用担当者に良い印象を与えられ、企業とのマッチ度をアピールすることが可能になります。
【就活の軸がない】就活の軸を答える時のポイント
就活の軸を企業に効果的に伝えるためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
まず、志望度の高さを示すこと、次に、自分の経験や考え方を軸にしっかりとアピールすることで、説得力のあるPRが可能となります。
以下でそれぞれのポイントを詳しく解説します。
志望度の高さを伝える
企業に自分の志望度の高さをしっかりと伝えるためには、就活の軸と企業の特徴や理念との共通点を示すことが重要です。
例えば、企業が持つ事業内容や社風、企業理念をしっかりと理解し、それが自分の軸とどのようにマッチしているかを説明することで、なぜその企業を志望しているのかを具体的に示せます。
企業研究を深く行い、共通点を見つけることで、志望動機がより明確になり、企業側にも熱意が伝わりやすくなります。
説得力を持たせる
就活の軸に説得力を持たせるためには、単なる価値観の説明だけでなく、具体的な体験談を交えることが重要です。
実際にその軸に沿って行動したエピソードや経験を語ることで、自分の性格や行動力を具体的に伝えることができます。
また、面接官に対して自分がどのような人間であるかを理解してもらうためにも、エピソードを使って話を展開することで、より個性が伝わるアピールが可能になります。
企業との共通点をアピール
企業は、自社の理念や目標に共感し、それに沿った価値観を持つ人材を求めています。
そのため、自分の就活の軸が企業の方針や文化とどのように一致しているのかを明確に述べることが重要です。
たとえば、「御社が掲げる『挑戦を重視する姿勢』に共感し、私自身もこれまで新しい環境で挑戦を続けてきました」といったように、共通点を具体的に伝えます。
また、共通点を述べるだけでなく、「なぜその企業でなければならないのか」という理由も加えることで、応募者の志望度の高さがより強く伝わります。
これには企業の特徴や独自性を深く理解していることが前提となるため、事前のリサーチも欠かせません。
就活の軸を決めた経験談を伝える
就活の軸を伝える際には、まず結論を簡潔に述べ、その背景や理由を具体的なエピソードを通じて説明します。
たとえば、「私は、どんな環境でも柔軟に対応し、目標を達成する力を大切にしています」という結論を述べた後に、その考えに至った経験を具体的に示します。
「大学時代、ゼミのプロジェクトで異なる意見がぶつかり合う中、仲間と協力しながら解決策を模索した結果、最終的に高い評価を得ることができました」といった具合に、行動の背景やその結果を述べます。
また、エピソードを述べる際には、どのような価値観や思考がそこにあったのかを説明することで、自分が軸として重視する要素の説得力を高めることができます。
こうした背景を語ることで、単なる言葉ではなく、実体験に基づいた軸であることを示せます。
ほかの回答と一貫性を持たせる
就活の軸を伝える際には、志望動機や自己PRとの整合性を意識することが不可欠です。
たとえば、「チームワークを重視する」という軸を述べた場合、志望動機や自己PRでも、それに関連するエピソードや志向を強調する必要があります。
「これまで個人で成果を出すことを重視してきました」という内容が別の回答で出てくると、一貫性が失われ、面接官に自己分析が不十分だと見なされる可能性があります。
一貫性を保つためには、軸を設定する段階で、他の回答とどのようにリンクするかを考えながら内容を作成することが重要です。
さらに、すべての回答が完成した後には、軸や志望動機、自己PRの間に矛盾がないかを全体的に見直し、必要に応じて調整することがポイントになります。
【就活の軸がない】どの業界でも万人受けする就活の軸例文
どの業界でも万人受けする軸の例文は以下の軸をキーワードにして設定すると良いでしょう。
以下の軸のポイントと例文を参考にしてみてください。
やりがい
やりがいを軸にすることで、仕事への熱意や主体性が感じられ、「長期的に活躍してくれそう」という印象を与えやすいです。
一方で「やりがいを感じたら頑張る=受け身」と捉えられる恐れがあるため、「自らやりがいを見出す力」も併せてアピールすることが必要になってきます。
私は、自分の努力が形となり、成果として実感できる環境で働きたいと考えています。
大学のゼミでは、新規プロジェクトを企画し、運営に携わる機会がありました。
その際、企画立案から進行管理まで担当し、ゼミの仲間と協力しながらプロジェクトを形にしました。
プロジェクトを進める中で、メンバー間の意見が対立する場面もありましたが、議論を重ねながら最適な方向性を模索しました。
また、外部との調整も必要になり、関係者との交渉を進める中で、計画通りに進まないことの難しさを実感しました。
しかし、その都度チームと連携しながら課題を解決し、最終的には成功に導くことができました。
仕事においても、困難を乗り越えながらプロジェクトを推進し、自らの努力が結果として表れる環境で活躍したいと考えています。
社会貢献
社会貢献を軸にするのは、「人の役に立ちたい」「人の生活を支えたい」という価値観を企業に伝えやすく、業界を問わず好意的に受け取られやすいです。
ただしどの企業でも通じやすい軸のため「どのような形で・どんな人に貢献したいのか」といった具体性を持たせる差別化が必要となってきます。
私は、仕事を通じて人々の生活をより良くすることに貢献したいと考えています。
大学時代、地域の子どもたちを対象にした学習支援のボランティアに参加しました。
そこで、学習に苦手意識を持つ子どもたちと向き合い、少しでも自信を持って学べるようサポートしました。
最初は、勉強に対して消極的な子どもが多く、どのように関心を持ってもらうか試行錯誤しました。
一人ひとりの理解度に合わせた指導方法を考えたり、勉強に対するハードルを下げる工夫を取り入れたりする中で、徐々に学ぶ楽しさを感じてもらえるようになりました。
支援を続けるうちに、「勉強が楽しくなった」と話してくれる子が増え、学習意欲の向上を実感しました。
働く中でも、社会に貢献することを意識しながら、自分のスキルを活かせる場面を見つけ、より良い環境を生み出していきたいです。
自己成長
自己成長を軸にすることで、どの業界でも「挑戦する姿勢」と「向上心」を評価されやすくなります。
企業は変化する市場に対応できる柔軟性を持つ人材を求めているため、自己成長を重視する姿勢は、自ら進んでスキルや知識を磨き、変化に適応しようとする意欲を示すことができ、幅広い業界で好印象を与えます。
「私は常に新しい知識やスキルを吸収し、自分自身を向上させていくことに強い興味を持っています。
大学時代、様々な分野の授業を積極的に受講し、幅広い教養を身につけ、特に、プログラミングの授業では、独学で応用技術まで習得し、学内コンテストで優勝するまでに至りました。
この経験から、努力次第で自分の可能性を大きく広げられることを実感しました。
就職活動では、社員の成長を重視し、継続的な学習機会を提供している企業を探しています。
また、新しいプロジェクトや部署異動などを通じて、様々な経験を積むことができる環境も重要だと考えています。
入社後は、与えられた業務をこなすだけでなく、常に改善点を見出し、効率化や品質向上に取り組みたいと思います。」
チームワーク
チームワークを軸にする理由は、どの業界でもプロジェクトの成功において協力が不可欠だからです。
組織で働く上で、他者と円滑に連携し、目標達成に向けて貢献できる能力は評価されます。
業界を問わず、チームで成果を上げる力は重要視され、コミュニケーション能力や協調性の証明にもなります。
「私はチームで協力し合いながら目標を達成することに大きな喜びを感じます。
大学のゼミ活動では、地域活性化プロジェクトに参加し、メンバー間の意見の相違や作業の遅れなど、様々な困難に直面しました。
しかし、お互いの強みを活かし、弱みを補い合うことで、最終的には素晴らしい成果を上げることができました。
そのため、就職活動では、チームワークを重視し、社員同士が積極的にコミュニケーションを取り合える職場環境を自分の就活の軸としています。
例えば、部署を越えた横断的なプロジェクトチームの存在や、社内勉強会の開催など、協働の機会が豊富な企業に魅力を感じます。
入社後は、自分の役割をしっかりと果たすだけでなく、常に周囲への気配りを忘れず、同僚のサポートも積極的に行いたいと考えています。」
顧客志向
顧客志向は、どの業界でも高く評価される軸です。
企業は顧客満足を最優先にしており、顧客のニーズを正確に把握し、適切な提案やサービスを提供する力は、顧客の信頼を得るための基本的なスキルで、顧客との信頼関係を築く力が、多くの業界で成功をもたらします。
「私は、お客様の声に真摯に耳を傾け、その期待に応えることで、社会に貢献できる仕事に就きたいと考えています。
アルバイト先の飲食店では、お客様からの細かな要望や苦情に丁寧に対応することで、リピーター率の向上に貢献しました。
就職活動では、顧客第一主義を掲げ、常にサービスの質の向上に努める企業を探しています。
例えば、定期的な顧客満足度調査の実施や、お客様の声を商品開発に活かすような取り組みを行っている会社に興味があります。
また、社員が顧客と直接対話する機会が多い職場環境も魅力的だと感じています。
入社後は、お客様のニーズを的確に把握し、それに応える製品やサービスの提供に尽力したいと思います。」
【就活の軸がない】就活の軸がそれでも分からない!
これまで就活の軸がない場合の対策や見つけ方を詳しく紹介しましたが、それでも分からない方もいると思います。
そこで、ここまでの方法でも自分の就活の軸を見つけられなかった方のために2つ最後の手段をお伝えするので参考にしてください。
一覧から見つけてみる
一般的な就活の軸を一覧化してまとめた記事があるので、どうしても見つからない人はこの記事を読んでみてください。
ここに書いてある軸を一つ選択し、自分の過去の経験と繋げて文章にすればOKです。
エージェントに相談してみる
自己分析、業界・企業研究、目標や優先順位の設定をやっても「就活の軸がそれでも分からない!」と悩んでいる場合は就活エージェントを活用することをおすすめします。
就活エージェントとは就職活動のプロであり、あなたの良きパートナーになり得る存在です。
就活の軸を考えるだけでなく、エントリーシートの添削や面接対策、受ける企業の選定まで行ってくれます。
1人で悩んでいても前に進めないため、就活エージェントを活用し効率的に就職活動に取り組んでみてはいかがでしょうか。
下記にリンクを貼っておきますので、少しでも気になった人は無料ですので登録だけでもしてみませんか?
まとめ
就活の軸とはあなたが譲れないことや条件のことを指します。
そのため、事前に決めておかないと受ける企業を選ぶ基準がないため、とても大回りをしてしまい、多くの時間を無駄にしてしまいます。
そうならないためにも自己分析、業界・企業研究、目標や優先順位の設定を行い、就職活動が本格的に始まる前に就活の軸を決めておきましょう。
1人で考えても全く思い浮かばない場合は、就活エージェントに頼ってみることをおすすめします。




_720x550.webp)






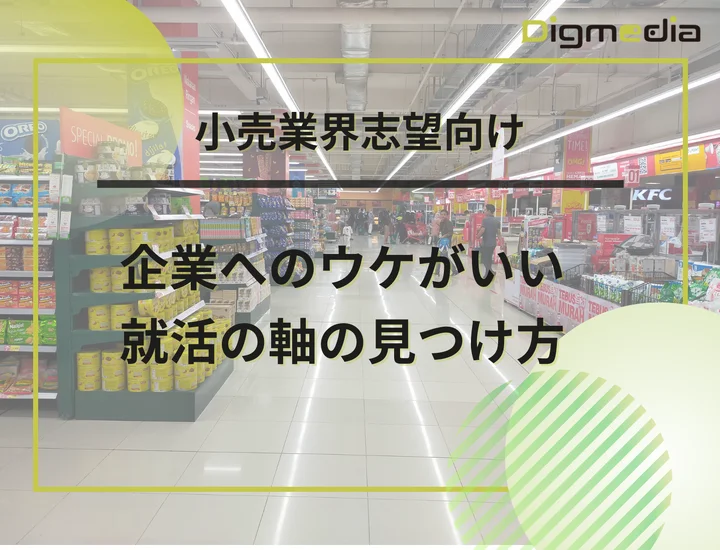

_720x550.webp)





就活コンサルタント木下より
例えば、アルバイトでの接客経験や部活動でのチームワークなど、日常の中での経験から学んだことを深掘りすることで、そこから就活の軸を見つけることができます。