
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
面接でよく聞かれるのが、ゼミや研究室でどんなことをしていたのかという質問です。
頭の中では分かっていても口に出すとややこしい内容になってしまうなど、伝え方が難しい質問の1つだと言えます。
特に理系の研究内容に関しては、専門的な知識がないと理解できない内容が多いため、その伝え方には注意が必要です。
この記事では面接時にゼミや研究の内容について質問される理由から説明し、伝え方や回答するための下準備などを徹底的に解説していきます。
【面接で研究内容】面接で聞かれる研究
まずは「面接で聞かれる研究」の種類について説明していきます。
研究と聞くと「理系の研究」を頭に思い浮かべる人が多いと思いますが、「ゼミ研究」もその内の1つです。
文理問わず研究に関しての質問がされるため、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
ゼミ研究
面接で聞かれる研究には文系も入る「ゼミ研究」も含まれます。
研究と聞くと一見理系だけに関係するものというイメージがあると思います。
しかし、文系も所属するゼミ研究では、専門分野のことについて突き詰めていくため、ゼミ研究も立派な研究の1つと言えます。
経済や経営などに関する知識を活用し、地域復興の一翼を担った、町おこしイベントの集客のお手伝いをしたことなどは研究と言って間違いありません。
そのため、イメージ通りの研究室に入り白衣を着て手袋を着用して行うことだけが研究ではなく、何かを突き詰めて考えた経験こそが研究だと考えましょう。
理系の研究
研究と言われて真っ先にイメージするのはやはり「理系の研究」だと思います。
毎日同じ作業を繰り返してデータを集め、そのデータから次の改善内容を考え実行することを繰り返し行うという単純作業の連続が理系の研究です。
研究の内容は所属するゼミや研究室で全く違うため、あなたらしい個性を出せるという特徴があります。
また、あなたが本当に興味のある分野の研究であれば、楽しみながら取り組むことができているはずです。
普段の研究内容だけでなく、今取り組んでいる卒業研究の内容も就職活動で話すことができるため、温度感のあるエピソードを組み立てやすいという点はメリットだと言えます。
【面接で研究内容】面接で研究を聞かれる理由
面接で聞かれる研究の種類が分かったところで、次は「面接で研究を聞かれる理由」を説明していきます。
ここでは特に企業の採用担当者が知りたいと思っている「研究経験の価値」と「研究内容の重要性」にフォーカスし説明していきます。
質問される理由が分かれば、答えるべき内容が明確になります。
研究経験の価値
面接で研究内容を聞かれる理由の1つ目は「研究経験の価値」を測るためです。
ゼミ研究や研究室での研究をすることで、その分野に関する専門知識が深まることはもちろんのこと、他の能力やスキルの向上も見込めます。
そのため、企業の採用担当者はあなたが研究経験から、あなたがどのような能力やスキルを習得したのかを知りたいと考えています。
例えるなら、地道に粘り強く同じ作業ができる能力を身につけたことや、何か問題が発生してもそれを解決できる能力が伸びたことなどです。
これらの能力は全ての企業から重宝される傾向にあるため、思う存分アピールしていきましょう。
また、企業が求める人物像と照らし合わせることで、研究経験の中で何をアピールすべきかが見えてくるはずです。
研究内容の重要性
面接で研究内容を聞かれる理由の2つ目は「研究内容の重要性」を知りたいからです。
大学であなたが取り組んだ研究内容をどのように業務に活かすことができるのかを企業の採用担当者は知りたいと考えています。
ここが上手く繋がれば、「即戦力として計算できるな」「頼りになりそうだな」というポジティブな印象を与えることができます。
また、研究に取り組んだ経験があることで、それに関連する業務がイメージしやすく、一緒に働いている姿を鮮明に想像させることができます。
これはあなたの持っているポテンシャルを分かりやすく伝えるための一番の方法だと言えます。
ここの内容が上手く伝われば、大きなプラス評価に繋がる可能性がとても高くなると言っても過言ではありません。
コミュニケーション力
研究内容を説明する場面では、就活生のコミュニケーション能力が見られます。
企業は、研究を通じて得た知識や成果をわかりやすく伝える力が、仕事の場での情報共有やチーム内の協力にどの程度役立つかを評価しています。
特に、専門的な内容を非専門家にも理解させる能力は、顧客対応や社内プレゼンテーションなど、業務で求められることが多いスキルです。
そのため、研究の詳細を伝える際は、専門用語を適切に使いつつ、誰にでも伝わる説明を意識することが大切です。
仕事への応用力
企業が研究内容を尋ねる理由の一つに、その研究が業務にどのように応用できるかを見極めることがあります。
研究は単に知識を得るだけでなく、課題解決や新しい価値を創造する手段として活用されます。
例えば、研究のテーマが応募先企業の業務内容や製品開発に関連する場合、その知識や経験がどのように役立つかを説明できれば、採用担当者に好印象を与えることができます。
具体的な応用例や、自分の研究が企業にとってどのような利益をもたらすかを考えておくことが重要です。
プレゼンテーション能力
面接で研究内容を話す際には、プレゼンテーション能力が試されます。
企業は、入社後に必要となる企画提案や報告の場面で、候補者がどれほど的確に情報を伝えられるかを評価しています。
特に、研究の目的や成果をわかりやすく説明し、聞き手の理解を得る能力が重視されます。
また、話の構成や視覚的な補足資料の使い方などもプレゼン力の一部として見られることがあります。
柔軟性のある論理的思考力
研究内容に関する質問を通じて、柔軟性のある論理的思考力が評価されることもあります。
研究では、課題を特定し、解決策を検討し、結果を次のステップにつなげることが求められます。
企業は、こうしたプロセスをどのように進めたかを知ることで、応募者の問題解決能力や新しい状況に対応する柔軟性を確認しています。
特に、失敗や予想外の結果が出た際の対応や、それをどのように次の行動に活かしたかについてのエピソードは、企業側に良い印象を与えるポイントです。
【面接で研究内容】作成の準備
面接で研究のことが聞かれる理由が分かったところで、次は実際に文章を組み立てる際の「作成の下準備」について説明していきます。
ここでは研究経験についての文章を組み立てる前に取り組んで欲しいこととして「自己分析の活用」「研究の具体例」「スキルとの関連付け」の3つを説明していきます。
どの要素も研究についての文章を組み立てるのに必要不可欠ですので、必ず確認するようにして下さいね。
自己分析の活用
研究のことを文章にする際は「自己分析の活用」を念頭に置いて組み立てていきましょう。
研究のことを伝えるのになぜ自己分析の結果が活用できるのかと疑問に思う就活生も多いと思います。
確かに直接的に自己分析で振り返った経験や印象的な出来事は活用できないかもしれません。
しかし、そこで気がついた価値観や大切にしていることなどの情報は活用できます。
ここでポイントとなってくるのが、あなたがなぜその研究に取り組んでいるのかという理由の部分です。
将来人の役に立ちそうだから、多くの人に影響を与えそうだから、世の中がもっと便利になりそうだからなど。
あなたの取り組んでいる研究内容がどのような価値を持っているのかということを、あなた自身の価値観で明確にしていきましょう。
研究の具体例
研究のことを文章にするためには「研究の具体例」をいくつか用意しておく必要があります。
あなたが今まで取り組んできた研究内容を振り返り、その研究結果や成果を深掘りしていきましょう。
ここでポイントとなるのが、具体的に思い出すことです。
そのため、過去の実験結果をもう一度確認したり、論文やレポートの内容も振り返っておきましょう。
もしその中に、あなたの研究結果が実際に役に立った実例があれば大きなプラス評価に繋がる可能性があるため、どんどんアピールしていきましょう。
それに加え、受ける企業の業務内容に直接関係する可能性の高い研究内容があれば積極的にアピールしていきましょう。
スキルとの関連付け
研究のことを文章にする際は「スキルとの関連付け」を忘れないように意識しておきましょう。
スキルの関連付けとは、あなたが一生懸命取り組んだ研究で得たスキルや能力が、受ける企業や職種でどのように活きるのかを説明していくことを指します。
あなたが取り組んだ研究内容を100%活かすことができる企業を探すのは難しいと思います。
しかし、あなたが取り組んだ研究内容から得たスキルや能力を活かすことができる企業を探すことは可能です。
ここで意識して欲しいのが、スキルや能力は決して専門的な知識や取得した資格だけではないということです。
スキルや能力の中には継続力やコミュニケーション能力なども含まれており、それらを活かすことができる職種は数多く存在しています。
読みやすいプレゼン資料を用意する
研究内容を説明する際には、読みやすいプレゼン資料を用意することが大切です。
資料は、面接官に対する配慮や準備の姿勢を示す重要なツールです。
文字数が多すぎず、図表やグラフを適切に活用した資料は、視覚的にもわかりやすく、好印象を与えます。
さらに、資料を簡潔にまとめることで、自分の説明がスムーズになり、プレゼン全体の質が向上します。
準備の段階で、第三者に資料を見せて意見をもらうと、内容の改善点が見つかりやすいです。
こうした丁寧な準備が、面接官への信頼感を高める要因となります。
逆質問を用意しておく
面接では、研究内容の説明だけでなく、逆質問を用意しておくことも重要です。
逆質問は、自分が企業や職種についてどれだけ関心を持っているかを示す絶好の機会です。
質問がない場合、面接官に熱意が感じられない印象を与えてしまうことがあります。
最低でも2つ以上の質問を準備し、内容は企業研究や自身の志望動機と関連付けるようにしましょう。
たとえば、「貴社の研究開発で特に注力している分野は何ですか」といった質問は、研究内容との関連性をアピールできます。
【面接で研究内容】適切な答え方のポイント
研究に関する文章を作成するための下準備の仕方が分かったところで、次は「適切な伝え方のポイント」を説明していきます。
ここでは特にポイントとなる「1.基本はESと同じ内容で答える」「2.研究内容の説明はゆっくり話す」「3.想定される質問の回答を準備しておく」の3つに絞って詳しく説明していきます。
1.基本はESと同じ内容で答える
適切な伝え方のポイント1つ目は「基本はESと同じ内容で答える」ことです。
企業の採用担当者はESの内容を見てあなたに興味を持った結果、面接までたどり着いています。そのため、面接でもまずはESと同じ内容で答えて問題ありません。
書いてある内容をそのまま正確に伝えることを意識しましょう。
面接だからといってESに書いた内容に別のエピソードを足したり、はたまた全く違う内容で話すことは必要ありません。
用意しておくべきことは、深掘り質問された時に正確に答えることができるようにしておくことだけです。
そのためには過去の研究内容をしっかりと振り返っておく必要があると断言できます。
2.研究内容の説明はゆっくり話す
適切な伝え方のポイント2つ目は「研究内容の説明はゆっくり話す」ことです。
就職活動の面接はアルバイトの面接などと違い、とても緊張するものです。
そのため、あなたからすれば普通に話しているつもりでも、いつの間にか早口になってしまっていることが多いです。
理系の研究内容などは複雑な内容かつ、専門的な知識が必要な場合が多いので、早口になってしまうと内容が全く伝わらないという事態に陥ってしまいます。
そうならないためにも、面接ではいつも以上にゆっくり話すという意識を持っておきましょう。
ちょっとゆっくり過ぎるかなと思うくらいで練習しておくと、面接本番でちょうどいいくらいの口調になるはずです。
3.想定される質問の回答を準備しておく
適切な伝え方のポイント3つ目は「想定される質問の回答を準備しておく」ことです。
最初の「基本はESと同じ内容で答える」の項目でも説明しましたが、面接では深掘り質問をされます。
企業の採用担当者はあなたがESに書いた研究の経験に事前に目を通しており、あらかじめ深掘り質問を用意してきています。
この深掘り質問の内容は質問されるまで分からないため、回答を準備しにくいと言えます。
しかし、あなたの過去の研究内容などをしっかりと振り返っておくことで、大体の質問に答えることができるはずです。
また、ESに研究内容を書く際、あえて質問されるようなポイントを作るというのも対策方法の内の1つです。
しっかりと過去の研究内容を振り返り、あらゆる対策を練っておきましょう。
【面接で研究内容】面接前にする対策
面接で研究内容を話す場合、時間ごとに研究内容の話し方を複数用意しておくことで、その状況に応じて柔軟に研究内容を伝えることができます。
例えば一言で伝える場合は、簡潔に「〇〇に関する△△の研究を行っていました。」のように簡潔にまとめる必要があります。
また、10秒程度で伝える場合は、「〇〇という現象において見られる、△△という細菌の増減の原因について研究を行っていました。」のように、一言で伝える場合の内容をもう少し詳しくした伝え方をしましょう。
一言で伝える場合も、10秒で伝える場合も非常に簡潔かつ分かりやすい伝え方を心がけなければならないため、できる限り採用担当者が咄嗟に理解できるような簡単な言葉を用いて説明するようにしましょう。
さらに以下では、30秒、1分、5分かけて伝える例をそれぞれ紹介します。
30秒での答え方
研究内容を30秒程度で答える場合は、おおよそ150字から200字で研究内容を説明する必要があります。
短い時間で説明しなければいけない上、一言だけでは足りないため難しく感じるかもしれませんが、以下の例文を参考に、自分の研究をどのようにまとめるか考えてみましょう。
例文
私は〇〇大学〇〇学部において、〇〇に関する研究を行っていました。
具体的には、〇〇という現象において見られる、△△という細菌の増減の原因について研究を行いました。
この研究では、〇〇と△△の間には〇〇という関係性があることを発見しました。
この研究を通して、分析力と問題解決能力を養うことができました。
また、研究発表会でのプレゼンテーション経験から、人にわかりやすく説明する能力も身につけました。
これらの経験は、貴社に入社後も必ず活かせるものと確信しております。
1分での答え方
続いて、研究内容を1分程度で答える場合の伝え方を紹介します。
1分の場合は、300字から400字程度の内容で説明するといいでしょう。
これまでよりもさらに具体的な研究内容やその過程を話すことができるため、その経験で何を最もアピールしたいか整理したうえで、そのポイントをより詳しく説明できるような伝え方を考えましょう。
例文
私が大学時代に最も力を入れて取り組んだのは、〇〇に関する研究です。
この研究では、〇〇という課題に対し、△△という新しいアプローチを試みました。
具体的な研究プロセスとしては、まず先行研究を徹底的に調査し、課題の核心部分を特定しました。
次に、実験計画を立案し、実際に実験を行いました。
実験データに基づいて分析を重ね、仮説の検証を行いました。
この過程で、計画通りに進まないことや、予想外の結果に直面することもありましたが、その都度チームメンバーと議論を重ね、解決策を探しました。
その結果、当初の予想を大きく上回る成果を得ることができ、学会での発表機会も得られました。
この研究活動を通じて、困難な状況でも諦めずに粘り強く問題解決に取り組む力、多角的な視点から物事を捉え、分析する力を身につけました。
また、チームワークの大切さも学びました。
これらの経験は、社会に出ても必ず役に立つと信じています。
5分での答え方
5分で研究内容を話す場合は、かなり詳しく話すことができます。
研究テーマ、研究過程で直面した課題、それを乗り越えた過程、結果、その経験から得た学びなど、説明する内容が増える分論理的に内容を整理する必要があります。
その中でも採用担当者が主に重視するポイントは、直面した課題をどのように乗り越えたかという過程です。
そのため、そこに比重をおいた伝え方を意識しましょう。
【面接で研究内容】面接で話す文の構成
研究について適切に伝えるためのポイントが分かったところで、次は「面接で話す文の構成」の仕方を説明していきます。
ここでは構成する順番通りに「まずは目的を話す!」「苦労したこと」、そして最後に「学び」を書いていきましょう。
構成方法を変えるだけで、伝わり方は大きく変わりますので、しっかりと確認していきましょう。
結論ファースト
面接官に研究内容を伝える際は、結論から話し始めることが大切です。
結論を先に述べることで、自分が伝えたい要点が明確になり、面接官も話の全体像を理解しやすくなります。
例えば、「私の研究テーマは〇〇です。
その目的は△△を解明することで、成果として□□が得られました」といった形で、要点を冒頭で伝えると良いでしょう。
結論ファーストで話すことにより、プレゼンの流れがスムーズになり、面接官の評価にも良い影響を与えます。
目的を話す
研究の目的を説明することは、自分の価値観や考え方を伝える重要な場面です。
「なぜその研究を行ったのか」という理由を明確に述べることで、研究への熱意や課題意識が伝わります。
たとえば、「私は〇〇という社会課題に興味を持ち、それを解決するために△△の研究を行いました」といった具合に、目的を簡潔かつ具体的に説明します。
目的を話すことで、自分が研究を通じて何を学び、何を得たのかを明確に示せるため、面接官に深い印象を与えることができます。
苦労したこと
結論とその目的の次は、それを研究するために「苦労したこと」を述べていきましょう。
研究に取り組んでいると、実験が上手く進まない、データが思い通りに取れない、想像と違う結果が出たなどの問題に直面するはずです。
そういった苦労した経験を文章中に組み込むことで、問題を乗り越えるだけの精神力や問題解決能力があるというポジティブな印象を与えることができます。
また、苦労した経験を組み込むことで、あなたが研究に真剣に取り組んでいたこともアピールできます。
あらゆる点を考慮しても、この苦労した経験を文章中に盛り込まない手はないと言えるでしょう。
学び
結論とその目的、苦労したことだけでなく、そこから得た「学び」を書くことで、文章のクオリティを飛躍的に向上させることができます。
この学びをアピールすることで、企業の採用担当者はあなたのことを成長してくれる人材だと認識するようになります。
その理由は、仕事をする上で苦労することは多くあり、その苦労の数だけあなたは成長してくれるのではないかと期待させることができるためです。
この学びには、どのようにしてその苦労を乗り越えたのかという部分も含まれています。
そのため「〇〇という苦労があったが、〇〇して乗り越えた結果〇〇を学んだ」という形が基本の形になります。
【面接で研究内容】研究内容をわかりやすく伝えるために
採用担当者はほとんどの場合、研究分野の専門的な知識を持っていません。
そのため、研究内容をはじめて聞く人でも理解しやすいように、専門的な用語を使わずに簡潔にまとめる必要があります。
あくまで採用担当者が重視しているのは、研究過程であるため、研究テーマやその背景知識などについては深堀せず、最低限の説明にとどめましょう。
簡潔にまとめる
研究内容を簡潔にまとめることは、面接で非常に重要です。
面接官はあなたの専門分野のプロではない場合が多いので、高校生や文系の方でも理解できるような説明を心がけましょう。
学会で発表するような詳細なレベルは必要ありません。
まずは、あなたが「何を研究していたのか」「なぜその研究をしたのか」「その研究から何が分かったのか」という、研究の目的、背景、そして最も重要な結果を、短くまとめて話せるように準備してください。
例えば、私の研究は〇〇の現象を解明することでした。
この現象がなぜ起こるのかを突き詰めることで、将来的に△△という課題を解決できる可能性があると考えて研究に取り組みました」といった形で、全体像を分かりやすく提示すると良いでしょう。
【面接で研究内容】参考例文
ここでは、面接で研究内容を話す場合の例文を理系の研究と文系のゼミ研究に分けて紹介します。
研究内容やその経験のどのような点を面接で強調したいかは、個々で全く異なりますが、以下で紹介する例文を参考にすることで、効果的な伝え方の構成や内容の比重を実践的に理解することができます。
理系の研究①
例文
私の大学時代の研究は、現代のインターネット環境における誤情報が入り乱れる状況に対応するため、正しい情報を迅速かつ正確に検知するシステムを構築することでした。
この研究は、膨大なデータの中から真実を見極めるという非常にチャレンジングな課題に取り組むものでした。
研究を進めるにあたり、メンバーと協力して検知プログラムの骨組みを開発しました。
私は、メンバーそれぞれが担当したデータや知識を統合し、全体のプログラムを構築する役割を担いました。
この作業は非常に複雑で、何度も試行錯誤を繰り返す必要があり、強い忍耐力が養われました。
また、メンバーとはデータ分析の手法やプログラムの設計について活発な議論を重ねました。
異なる視点や意見をすり合わせながら、一つの目標に向かって協力し合う中で、コミュニケーション能力の重要性を改めて実感しました。
この研究を通じて、私は複雑な問題を論理的に分析し、解決策を導き出す能力、そしてチームで協働しながら目標達成に貢献する力を身につけました。
これらの経験は、貴社で働く上でも必ず活かせると確信しております。
理系の研究②
例文
私の大学時代の研究は、食物に含まれる特定の成分が、人の健康にどのような影響を与えるかについて深掘りするものでした。
具体的には、〇〇(研究対象の食物や成分名を具体的に入れる)が持つ機能性に着目し、そのメカニズムを分子レベルで解明することを目指していました。
研究では、まず〇〇(実験方法や分析手法を簡潔に入れる)を行い、得られたデータを統計的に解析しました。
この過程では、複雑なデータを正確に読み解き、そこから意味のある知見を導き出す論理的思考力が養われました。
また、実験計画の立案から実行、そして結果の考察まで、計画性と問題解決能力が求められる場面が多々あり、試行錯誤を繰り返しながらも粘り強く取り組むことで、これらのスキルを向上させることができました。
この研究を通じて、私は科学的なアプローチで物事を深く探求する力、そして得られた知見を分かりやすく整理し、伝える力を身につけました。
貴社が取り組まれている〇〇(応募先の企業の事業内容や製品と関連付ける)の分野において、私の研究で培った分析力や探究心が貢献できると確信しております。
文系のゼミ研究
例文
私の大学での専門はマーケティングで、特にゼミでは顧客の購買行動について深く研究してきました。
現代は選択肢が多様化している時代だからこそ、いかにユーザーを引きつけるかという知恵に大きな価値があると感じ、このテーマを選びました。
顧客が購買に至るトリガーは何なのか、そしてそれを効果的に刺激するにはどうすればよいのかを、国内外の様々な事例を通して探求しています。
ゼミで特に力を入れて取り組んだのは、ソーシャルネットワークがユーザーの購買行動に与える影響に関する研究です。
具体的には、DellのようにTwitter(現X)での発信が売上向上に明確に貢献している企業と、積極的に発信しているにもかかわらず成果につながっていない日本企業の間にどんな違いがあるのかを分析しました。
この研究を通じて、単に情報を発信するだけでなく、ターゲット顧客の心に響くコミュニケーションの戦略が重要であることを深く理解しました。
貴社が現在、ネットマーケティングに非常に注力されていると伺い、私のゼミで培ったデータに基づいた顧客購買行動の分析力や、ソーシャルネットワークを活用した効果的なマーケティング戦略の立案といった視点は、貴社で働く上で必ず貢献できると確信しております。
【面接で研究内容】NGな伝え方
ここまで下準備の仕方や伝える際のポイント、構成の仕方を説明してきましたが、それらを台無しにしないためにも「NGな伝え方」を確認していきましょう。
ここでは特に注意が必要なポイントとして「専門用語が多い」「内容が薄い」「話が長すぎる」の3つに絞ってNGな理由を詳しく説明していきます。
専門用語が多い
NGな伝え方の1つ目は「専門用語が多い」ことです。
これは特に理系の研究を伝える際に気をつけたいことです。
理系の研究では普段何気なく使っている言葉が実は専門用語だったということもあります。
そのため、企業の採用担当者が同じ研究をした経験がないと、何のことを言っているのかさっぱり分からないという事態に陥ってしまう可能性があります。
また、企業の採用担当者が文系であった場合はそもそも理系の研究というものが正しくイメージできないため、余計に言葉選びが重要になってきます。
誰にでも分かりやすいような言葉を選び、文章を組み立てていくように意識しておきましょう。
内容が薄い
NGな伝え方の2つ目は「内容が薄い」ことです。
エントリーシートで質問される項目全てに共通することですが、文章の内容が薄いと印象に残らず、選考を進めることはできません。
また、研究内容があまりにも薄過ぎると、「この学生はサボっていたのか?」「在学中に何を学んだんだ?」という不信感に繋がる可能性もあります。
それに加えて意識しておきたいことは、あなたが行った研究の内容自体が薄くなっていないかということです。
文章中にあなたが取り組んだこと、それに取り組んだ理由、困難を乗り越えた経験、学んだことが含まれているかをきちんと確認するようにしましょう。
これらの要素が一つでも抜けていると、内容が薄いと思われてしまうということを覚えておきましょう。
話が長すぎる
NGな伝え方の3つ目は「話が長すぎる」ということです。
就職活動の面接では時間の枠が決まっているため、質問には端的に答える方が好印象を与えることができます。
そのため、研究について質問された際は、ESの内容以上に話す必要はないと言えます。
確かに、あなたが苦労したポイントやこだわった点などについて語りたくなる気持ちも分かります。
しかし、それは友人との会話だけにして、就職活動の面接では質問されたことに素直に答えることを意識しておきましょう。
長く話をした方がコミュニケーション能力をアピールできると思っている就活生も多いと思いますが、それは間違った認識です。
端的に相手が必要としていることを伝えるというのが真のコミュニケーション能力です。
話は短く内容濃くを意識して面接に臨みましょう。
【面接で研究内容】面接でされる質問を想定する
面接で研究内容について質問された際、的確に答えるためには事前準備が重要です。
まずは、研究内容について全く知識がない人、例えば文系の人や家族などに、自分の研究概要を説明してみましょう。
専門用語を避け、できるだけ平易な言葉で伝えることがポイントです。
説明後には、相手に理解できたかどうか、特に研究の意義や価値が伝わったかどうかを尋ねてみましょう。
もし相手が理解できていない部分があれば、それは説明が不十分な箇所です。
相手からの質問や疑問点を聞くことで、自分が説明する上で曖昧にしていた点や、相手が特に興味を持つポイントが見えてきます。
このプロセスを繰り返すことで、自分の説明が誰にでも理解できるように、より簡潔で分かりやすいものにブラッシュアップできます。
また、相手からどのような質問が出やすいのか、質問の傾向を把握することで、面接で想定される質問への対策にもなります。
就活エージェントを利用するのもいい
以上のような練習を面接の専門家相手に実践するとより効果的です。
就活エージェントは、面接や就活における採用担当者側の思考を深く理解したプロが、内定まで親身にアドバイスをくれます。
面接のプロである就活エージェントの担当者に面接練習を依頼することで、より的確なアドバイスを得ることができます。
【面接で研究内容】よくある質問
面接対策として「よくある質問とその答え方」についてあらかじめ準備しておくことをおすすめしています。
面接の感想でよく聞くのが「予想外の質問をされた」というなんとも怖い感想です。
しかし、予想外の質問はされても1、2問程度で、あとはよくある質問だと言えます。
そのため、しっかりと事前準備を行っておけば大抵の質問に答えることができるはずです。
しかし、面接が苦手な就活生も多く、不安を感じていると思います。
ここでは多くの就活生が感じている「深掘りされたら何を話す」のがいいのか「研究内容が薄いと感じる場合」どうすればいいのか「他の応募者との比較」してしまうという悩みを一気に解消していきます。
深掘りされたら何を話す
多くの就活生が感じている不安要素の代表格がこの「深掘りされたら何を話す」のが正解なのかということです。
深掘り質問をされる際は、基本的にはこの記事で説明してきた「苦労したこと」や「そこから学んだこと」に関する質問が多いです。
または、「研究経験をどう活かしていくのか」というキャリアビジョンに関する質問です。
そのため、今まで説明してきたポイントを押さえておけば深掘り質問にしっかりと対応できるはずです。
なぜ深掘りされるか
この「なぜ深掘りされるか」という理由を正しく把握することで、より効率的に面接対策できると言えます。
また、その理由が理解できていると、相手をあらかじめ準備している深掘り質問へ誘導することも可能になり面接を有利に進めることができるようになります。
研究についての発言の信憑性を確認する
もしあなたの研究内容に関する深掘り質問をされた場合、それは「研究についての発言の信憑性を確認する」狙いがあると考えるようにしましょう。
流石にあなたが嘘をついているのではないかと疑っている訳ではないと思いますが、研究の内容がぼやけていると相手に思われている可能性が高いです。
そのため、あなたが行ってきた研究の内容や費やした時間や労力を正しく相手に伝える必要があります。
ここで意識したいのが数字で伝えるということです。
例えば毎日3時間研究室で〇〇の実験をした、データを収集するのに10時間かかったなど、具体的かつ定量的に伝えることで、エピソード全体の信憑性を高めることができます。
活動内容の難易度を確認する
もしあなたの頑張りに関する深掘り質問をされた場合、それはあなたの「活動内容の難易度を確認する」狙いがあると考えましょう。
例えば「研究はどれくらい大変でしたか?」「あなたはその中でどのような役割でしたか?」などの深掘り質問をされた場合などです。
もしかすると、あなたの研究経験の難易度が低いのではないかと思われている可能性があり、思わぬところでネガティブな印象を与えている可能性もあり危険です。
そうならないためにも、研究で苦労した点を具体的に説明したり、チーム内でのあなたの役割を正確に伝える必要があります。
あなたが行った研究内容が簡単ではなかったということを、エピソードを交えながらアピールしていきましょう。
研究内容が薄いと感じる場合
あなた自身が面接で話す「研究内容が薄いと感じる場合」、他の要素で補っていきましょう。
確かに研究の中には地味でインパクトに欠ける研究も多く、他の就活生に比べて内容が薄いと感じる場合もあります。
そんな時に多くの就活生がやりがちなのが、実験の内容に関する嘘をついてしまう、もしくは内容を盛ってしまうということです。
一見問題ないように感じますが、深掘り質問された時に大抵その嘘はバレてしまいますのでおすすめはできません。
実験内容が薄いと感じるようであれば、そこから学んだことや習得したスキルにフォーカスして文章を組み立てていきましょう。
それらをキャリアビジョンに組み込むことで、大きなプラス評価に繋げることも可能です。
他の応募者との比較
もしあなたが「他の応募者との比較」に悩んでいるのであれば、その時間を自己分析の時間にあてることをおすすめします。
多くの就活生が直面するのがこの他者との比較です。
特に集団面接では他の応募者と顔を合わせるということもあり、余計に意識してしまいます。
その結果、自分の順番が回ってきた時に焦ってしまい、上手く回答することができなかったというなんとも残念な結果に終わってしまったという経験はないでしょうか?
そうならないためにも、他の応募者と比較するのではなく、あなたらしさに自信を持って面接に臨みましょう。
あなたはこの世界で唯一無二の存在です。
あなたらしいユニークで個性的なエピソードや考え方を前面に出し、あなた自身を売り込んでいきましょう。
まとめ
面接で聞かれるあなたの研究経験は一旦ESの内容をそのまま伝えましょう。
その際、アピールしたい気持ちが抑えきれず話が長くなってしまうことや、専門用語が増えてしまうことに気をつけましょう。
話す構成は結論→目的→苦労したこと→学びの順番を意識することで、建設的に話ができるという印象を与えることができます。
他の就活生と差別化するためにも、文中にあなたらしいエピソードや視点を盛り込むことを意識しておきましょう。
そのためには事前に研究のことを振り返っておくことと、自己分析に取り組んでおくことが重要になります。
あなたらしい文章を組み立て、自信を持って面接に臨みましょう!



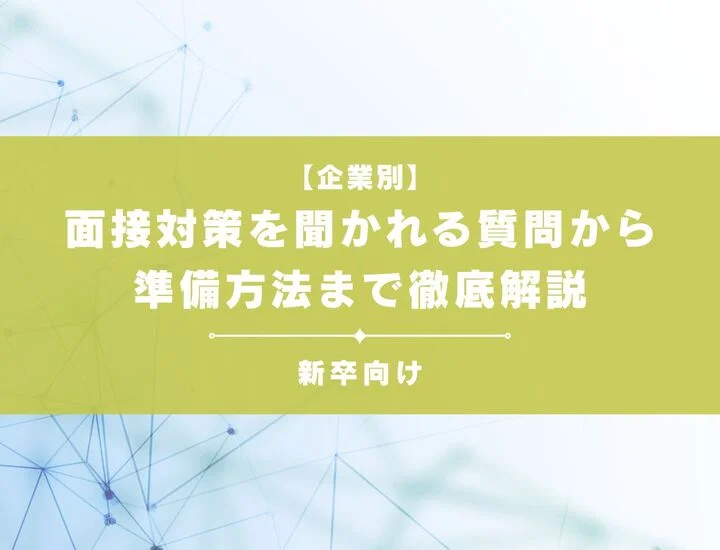
_720x550.webp)






