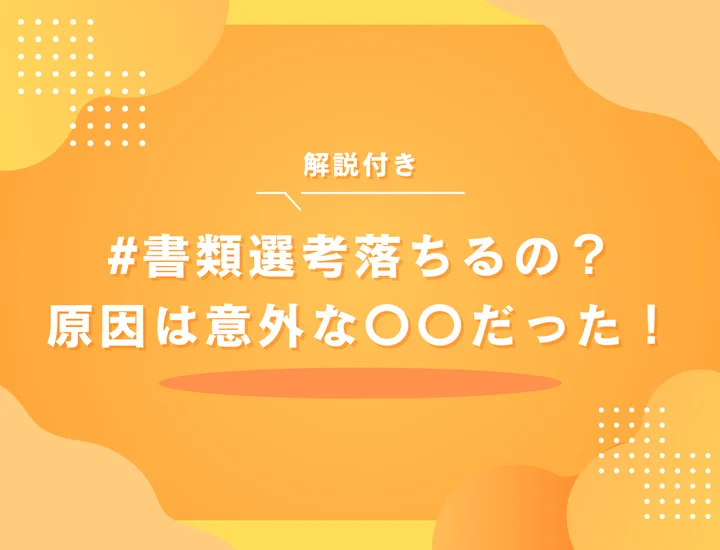HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
【新卒書類選考なんで落ちる?】企業が書類選考をおこなう理由
書類選考で落ちる原因を知るには、まず「なぜ企業が書類選考を行うのか」を理解することが大切です。
ただ単に応募者をふるいにかけるだけでなく、企業ごとに意図や目的があります。
この章では、企業がどのような理由で書類選考を実施しているのかを紐解いていきます。
企業の目線を知ることで、あなたの提出書類にどんな改善が必要なのかも見えてくるでしょう。
面接対象者を選ぶため
企業が書類選考を行う最大の目的は「限られた面接枠の中で、できるだけ自社に合いそうな人と会うため」です。
実際、多くの企業では数百〜数千の応募がある中から、面接可能な人数に絞り込む必要があります。
その際に使われるのが、履歴書やエントリーシート(ES)といった応募書類です。
ここで基本的なマナーや文章力、志望度や人となりが伝わるかどうかがチェックされます。
つまり、企業は最初の書類で「この人に会ってみたい」と思えるかを判断しているのです。
いかに書類の段階で自分の魅力を伝え、企業に「会いたい」と思ってもらえるかが鍵となります。
学生の志望度や「人となり」を見るため
書類選考では、単にスキルや資格だけでなく、あなた自身の「考え方」や「価値観」にも注目されています。
特に新卒採用では、経験よりも「将来性」や「企業との相性」が重視されます。
そのため、自己PRや志望動機の欄では、どのような思いで取り組んできたか、どのような価値観を持っているかが問われているのです。
志望度の高さは、書類の丁寧さや熱量からも読み取られます。
形式的な文章ではなく、「なぜこの企業で働きたいのか」「自分の経験とどうつながるのか」を自分の言葉で伝えることが大切です。
学歴フィルターは一部企業で存在する
残念ながら、すべての企業が完全に「人物重視」というわけではなく、一部の企業では「学歴フィルター」が存在しています。
特に応募数が多く、採用枠が限られている企業では、効率的にふるいをかけるために、大学名や偏差値を目安にする場合もあります。
また、特定の専門知識を求める職種では、専門分野に強い大学の学生を優先的に選考対象とすることもあります。
ただし、すべての企業がそうとは限りません。
学歴に自信がなくても、志望動機や自己PRで自分の価値をしっかり伝えられれば、書類選考を通過することは十分可能です。
【新卒書類選考なんで落ちる?】書類選考で落ちる人の6つの特徴
書類選考に落ち続ける人には、いくつかの共通点があります。
どれだけ熱意があっても、履歴書やエントリーシートの書き方次第ではその気持ちが正しく伝わらず、不合格となることも珍しくありません。
この章では、書類選考に落ちてしまう人が陥りがちな6つの特徴を紹介します。
どれかひとつでも当てはまっていれば、改善することで通過率が大きく上がる可能性があります。
① 書類に不備がある・読みにくい
書類選考において最も基本的でありながら、最も多いミスが「不備」と「読みにくさ」です。
例えば、誤字脱字や記入漏れ、証明写真のサイズ違い、押印忘れなどは、意外と多くの学生が見落としがちなポイントです。
また、字が汚くて読みづらかったり、行間が詰まりすぎていて目が滑るような書類は、それだけで読む気が削がれてしまいます。
丁寧に仕上げたつもりでも、形式が整っていなければ内容がどれだけ良くても落とされることはあります。
「最後に読み手の立場で読み直す」「提出前にチェックリストを活用する」など、基本を徹底することが通過の第一歩です。
② 略語やマナー違反がある
日常で何気なく使っている略語やカジュアルな言葉遣いが、就活の場ではマナー違反になることがあります。
たとえば「バイト」や「インターン」などの略語、「(株)」のような省略表記は、書類では避けるべきとされています。
また、提出期限に遅れたり、指定されたフォーマットに従っていない書類もマナー違反として扱われる可能性があります。
人事担当者は、社会人としての基本的な礼儀を見ています。
「この人はTPOをわきまえられるか」「社会人として信頼できるか」という視点でも書類は見られているということを忘れず、言葉遣いやルールには細心の注意を払いましょう。
③ 自己PRや志望動機に具体性がない
自己PRや志望動機が抽象的なままだと、企業はその学生がどんな人物なのかイメージすることができません。
「コミュニケーションが得意」「リーダーシップがある」といった言葉は誰でも使えるため、それだけでは説得力がありません。
重要なのは、その強みを裏付ける具体的なエピソードがあるかどうかです。
「どんな場面で」「どのような行動をし」「どんな成果や学びがあったのか」を語ることで、信頼性と魅力が一気に高まります。
企業はあなたの「これまで」から「これからの可能性」を判断しようとしています。
④ 企業の求める人物像とズレている
企業はそれぞれに異なる「求める人物像」を明確にしています。
たとえば、「行動力のある人材」を求めている企業に対して「慎重さ」や「計画性」をアピールしても、魅力的には映りません。
これはスキルや性格が悪いという話ではなく、単純にマッチしていないだけです。
企業研究を十分に行い、その企業が何を重視しているのかを把握した上で、自己PRの内容を合わせることが通過のコツです。
適性が合っていないと感じられれば、面接の機会すらもらえない可能性があります。
⑤ 志望度が伝わらない
多くの就活生が見落としがちなポイントが「志望度の高さ」をどのように伝えるかです。
形式的な志望動機や、ありきたりな文章では「本気度」が伝わらず、印象に残りません。
志望度を伝えるには、「なぜ数ある企業の中でその会社を選んだのか」「その企業にしかない魅力は何か」を自分の言葉で書くことが重要です。
企業は「うちに入りたい理由」を具体的に語れる学生に対して、面接で直接話を聞いてみたいと思うものです。
熱意が伝わるかどうかで、合否が大きく分かれることもあります。
⑥ 書類の改善・振り返りをしていない
書類選考に落ちた際に、その原因を分析せず同じ書類を使い回していると、同じミスを繰り返す可能性が高くなります。
「なぜ落ちたのか」「どの部分が弱かったのか」を自分なりに考察し、改善を積み重ねる姿勢が重要です。
通過した書類との違いを比較することで、改善ポイントが明確になります。
「一度作ったら終わり」ではなく、毎回の選考結果をふまえてアップデートし続けることが、書類通過率を高める最大のコツです。
可能であれば第三者にフィードバックをもらいましょう。
【新卒書類選考なんで落ちる?】書類選考の通過率が高い人の特徴とは?
「何十社も落ちている人もいれば、次々に通過していく人もいる」。
この差は、たったひとつの才能によるものではありません。
書類選考に通る学生には共通する“勝ちパターン”があります。
本章では、実際に書類選考を高確率で通過している学生の特徴を3つに分けて紹介します。
「頑張ってるのに通らない……」と悩む人は、自分と何が違うのかを確認して、ぜひ取り入れてみてください。
企業ごとに対策を変えている
書類選考の通過率が高い人の多くは、「企業ごとに合わせた書類の書き分け」をしています。
これは単なる自己紹介の使い回しではなく、志望動機や自己PRを企業ごとの採用方針や理念に沿って調整しているということです。
たとえば、「チャレンジ精神を評価する会社」には挑戦経験を前面に出した自己PR、「チームワークを重視する会社」には協調性を軸にしたエピソードを記載しています。
企業の求める人物像に合わせて、書類の構成や伝える内容を柔軟に変える力があるからこそ、どんな企業にも響く書類を届けられるのです。
これが「通る人」の共通習慣です。
自己分析と企業研究に時間をかけている
通過率の高い人は、書類作成前の「準備」に多くの時間をかけています。
特に、自己分析と企業研究はしっかりと行っており、自分の強みと企業の特性を結びつけて表現する力が高いです。
「なんとなく良さそう」ではなく、「自分がなぜこの企業に惹かれたのか」を言語化できる人は、文章にも説得力があります。
企業が「この学生は本当にうちで働きたいと思っているんだな」と感じるのは、下調べをした上での具体的な志望理由や、共感の言葉があるときです。
土台がしっかりしている人の書類は、どんな担当者にも響くのです。
第三者視点で改善を繰り返している
通過率が高い学生は、自分の書類に対して「他人の目」を必ず入れています。
自分では完璧に仕上げたつもりでも、読み手にどう映るかは別です。
そうした“ズレ”をなくすために、信頼できる先輩やキャリアセンター、社会人メンターなど第三者に見てもらい、フィードバックをもとに修正を重ねています。
自己完結せず、他人の意見を取り入れてブラッシュアップしていく姿勢が、質の高い書類を生み出す鍵です。
「通る書類は一発で完成するものではない」。それが通過率の高い人たちの共通認識です。
【新卒書類選考なんで落ちる?】書類選考の通過率を上げる7つの対策
書類選考に落ちる理由は様々ですが、対策をすることで確実に通過率は上がります。
ここでは、実際に通過率を改善した学生が取り組んでいた「7つの具体的な対策法」を紹介します。
すぐに取り入れられるものも多いため、今の自分の書類と照らし合わせながら確認していきましょう。
① PREP法で読みやすく伝える
PREP法とは、結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→再結論(Point)の順で構成する文章術です。
この型を使うことで、論理的かつ伝わりやすい文章を作ることができます。
結論が最初にくることで、採用担当者が内容を瞬時に把握できるため、書類をじっくり読んでもらえる確率も上がります。
また、具体例を入れることで内容に信頼性が生まれ、説得力も高まります。
読みやすさと理解のしやすさは、通過率に直結する重要なポイントです。
② 応募企業ごとに書類を作り分ける
「どの会社にも同じ自己PR・志望動機で出している」――これでは選考突破は難しいです。
企業によって求めている人物像は異なるため、それに合わせて書類の内容も調整する必要があります。
企業のビジョンや事業内容と、自分の価値観や経験を接続させることで、「だからこの会社を選んだんだ」と伝えることができます。
企業ごとの「オリジナル感」が、書類選考通過においては大きな武器になります。
③ 初頭効果・親近効果を活かした構成
人は「最初」と「最後」に触れた情報の印象が強く残る傾向があります。
この心理効果を活用するために、自己PRや志望動機では書き出しと締めの一文に工夫をしましょう。
最初に強みや意欲を端的に示すことで、第一印象をグッと引きつけることができます。
また最後には「入社後どう貢献したいか」など、未来をイメージさせる内容で締めくくることで、好印象を残しやすくなります。
構成の工夫一つで、全体の印象が大きく変わります。
④ 自己PRには具体的なエピソードを盛り込む
自己PRにおいて「私は〇〇な性格です」だけでは説得力がありません。
その強みが発揮された場面や、周囲に与えた影響までを語ることで、評価される自己PRになります。
例えば「行動力がある」と言うなら、「どのような目的で、どんな行動をとり、どんな結果になったのか」まで記載しましょう。
エピソードの有無で、あなたの印象は大きく変わります。
⑤ 応募締切はできるだけ早く提出する
提出が遅れると、それだけで評価を下げてしまうケースもあります。
特に人気企業では、応募が早いほど選考への意欲が高いと見なされる場合があります。
早めの提出は、スケジュール管理や計画性のアピールにもつながります。
また、締切ギリギリではミスやトラブルが起きやすいため、余裕を持って準備することが大切です。
⑥ 第三者による書類添削を活用する
自分では完璧と思っていても、第三者が見ると意外なミスや曖昧さがあるものです。
信頼できる先輩やキャリア支援の担当者、または社会人メンターに見てもらうことで、客観的かつ具体的なフィードバックが得られます。
自分では気づけない視点を得ることで、内容の精度と説得力が格段に高まります。
書類選考で落ちた経験があるなら、一度は他人の目を通すことをおすすめします。
⑦ 書類にあなたの価値観が表れているか
優れた書類には「その人らしさ」がにじみ出ています。
自分がどんな価値観を持ち、どんな姿勢で行動してきたのか。
表面的な実績だけでなく、そこにある思考や信念が読み取れる書類は、企業側に強く響きます。
数値や実績よりも、何を大切にして行動してきたのかが見える内容を意識しましょう。
それが、面接で「会ってみたい」と思わせる最大の武器になります。
【新卒書類選考なんで落ちる?】書類選考に落ち続けるときの改善ステップ
「何通出しても通過しない」と感じている場合は、立ち止まって改善するタイミングです。
就活は「数打てば当たる」だけではうまくいきません。
落ちた理由を丁寧に分析し、対策を講じることで、次の応募書類の精度は確実に上がります。
ここでは、書類が通らない時に行うべき「3つの改善ステップ」を紹介します。
このプロセスを実践すれば、無駄打ちを減らし、着実に突破力を高めることができます。
過去の書類を比較して共通点を見つけよう
書類選考に何度も落ちてしまう人にまずやってほしいのが、過去に提出した書類の比較です。
通過した書類と落ちた書類を見比べることで、書き方や構成、内容にどんな違いがあるのかが見えてきます。
たとえば、落ちた書類は抽象的な表現ばかりで、エピソードに具体性がない可能性があります。
逆に通過した書類には明確な実績や行動が記されているかもしれません。
自分がどんな文言を繰り返し使っているか、テンプレート化しすぎていないかにも注目しましょう。
文章のトーン、企業ごとのカスタマイズ度、表現の鮮度などもポイントです。
見比べて分析することで、どのような書き方が評価されやすいのかが自然と浮き彫りになります。
まずは現状を「見える化」し、失敗パターンを把握することから改善は始まります。
通過した書類をベースに改善する
一度でも書類選考を通過した経験があるなら、それは貴重な財産です。
そこに含まれているのは「評価された要素」です。
その書類の構成、エピソードの流れ、言い回しなどをじっくり分析し、他企業に提出する際のベースにしましょう。
通過実績のあるフォーマットを基にして、企業の特徴にあわせて調整することで、説得力を維持しながら個別対応が可能になります。
ただし、企業ごとの違いを無視して丸ごと使いまわすのは危険です。
例えば、求める人物像や業界ごとのキーワードが変われば、それに応じて自己PRや志望動機の「軸」も見直すべきです。
共通点を活かしつつ、企業ごとに「なぜこの会社か」が伝わるように仕上げていくのがコツです。
うまくいった書類から学ぶ姿勢が、通過率アップの第一歩となります。
サービスでプロに見てもらう
何度も落ちてしまっている場合、自分だけで改善するのは限界があります。
そこで効果的なのが、就活支援サービスや現役社会人に書類を見てもらうことです。
特にMatcherなどのサービスでは、志望企業で働いている人に直接添削を依頼できるため、非常にリアルなフィードバックを受け取ることが可能です。
自分では「良い書類」と思っていても、企業側から見ると伝わらないポイントが多く含まれていることは珍しくありません。
客観的な視点でチェックしてもらうことで、自分では気づけなかった改善点を見つけ出せるのです。
さらに、社会人の視点から「もっとこう書いた方が伝わる」といったアドバイスをもらえば、完成度は一段と高まります。
プロや経験者の力を借りることは、就活において非常に賢い選択肢です。
【新卒書類選考なんで落ちる?】自己PRと志望動機が上手く書けないときの対処法
「自己PRや志望動機がうまく書けない」と悩む就活生は非常に多いです。
伝えたい気持ちはあっても、どこからどう書き始めればいいのかわからず、手が止まってしまうこともあるでしょう。
しかし、コツさえつかめば誰でも質の高い文章を仕上げることが可能です。
このセクションでは、書き出しの工夫や具体的な書き方のテクニック、そして例文との正しい向き合い方を詳しく解説します。
書類選考で「伝わる」文章に仕上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
書き出しで悩んだら「PREP法+エピソード」がおすすめ
自己PRや志望動機の書き出しで悩む就活生は多いです。
最初の一文は、採用担当者に強い印象を与える重要なポイントです。
そこでおすすめなのが「PREP法+エピソード」の活用です。PREP法とは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(再主張)の流れで構成する文章技術です。
特に自己PRでは、まず自分の強みを結論として明示し、その根拠を説明し、具体的な体験談で裏付け、最後にもう一度アピールするという形にします。
PREPに沿って、かつオリジナルのエピソードを入れることで、文章に説得力と個性が出ます。
一文一文を短く区切ることで読みやすくなり、書き出しの段階から相手に「会ってみたい」と思わせる自己PRが完成します。
志望動機が浮かばない時は「なぜこの業界・企業なのか」から掘り下げる
志望動機が思い浮かばない時、多くの人が「何を書いたらいいかわからない」と手が止まってしまいます。
そんな時は「なぜこの業界なのか」「なぜこの企業なのか」から逆算して掘り下げましょう。
まずは、あなたがその業界に興味を持ったきっかけや、共感した理念、魅力を感じた社員の声などを言語化していきます。
さらに、数ある企業の中でその会社を選ぶ理由を明確にしましょう。
企業研究を通じて得た情報をもとに、自分との接点を探すことが深掘りのカギになります。
「なんとなく」ではなく「だからこの会社に入りたい」が言える状態を目指しましょう。
志望動機に芯が通っていれば、書類選考はもちろん、面接でも説得力が増します。
例文を参考にしても「丸パクリ」はNG
就活サイトやSNSにはたくさんの自己PR・志望動機の例文が掲載されています。
参考にすることは悪いことではありませんが、注意したいのは「そのまま使う=丸パクリ」です。
企業の採用担当者は何百枚というESを読んでおり、よくあるテンプレ文や見覚えのあるフレーズはすぐに見抜かれます。
例文を使う場合は、自分の経験や価値観に置き換え、自分だけの表現に言い換えることが大前提です。
例文の構成や言い回しの参考にしつつ、「あなたらしさ」を加えましょう。
特に具体的なエピソードは自分の体験でなければ意味がありません。
「この文章はこの人にしか書けない」と思わせることが通過率を上げる鍵になります。
【新卒書類選考なんで落ちる?】まとめ|落ちる原因は必ず改善できる
この記事では「書類選考なんで落ちる?」という疑問をテーマに、落ちる確率や原因、そして通過率を上げるための対策を詳しく解説してきました。
書類選考に通らない原因は、「内容が伝わりにくい」「企業のニーズとマッチしていない」「志望度が伝わらない」など、対策可能な要素がほとんどです。
書き方のテクニックとしてはPREP法を活用したり、企業ごとに書類を作り分けたり、具体的なエピソードや自分の価値観をしっかり盛り込むことが大切です。
また、第三者に添削してもらうことも非常に効果的です。
書類選考で落ちてしまうのは決して「才能がないから」ではありません。落ちた理由を分析し、正しい方向で改善すれば、誰でも通過率を上げていくことができます。
就職活動は自分を見つめ直す絶好の機会でもあります。焦らず、一歩ずつ、自分らしい書類を仕上げていきましょう。