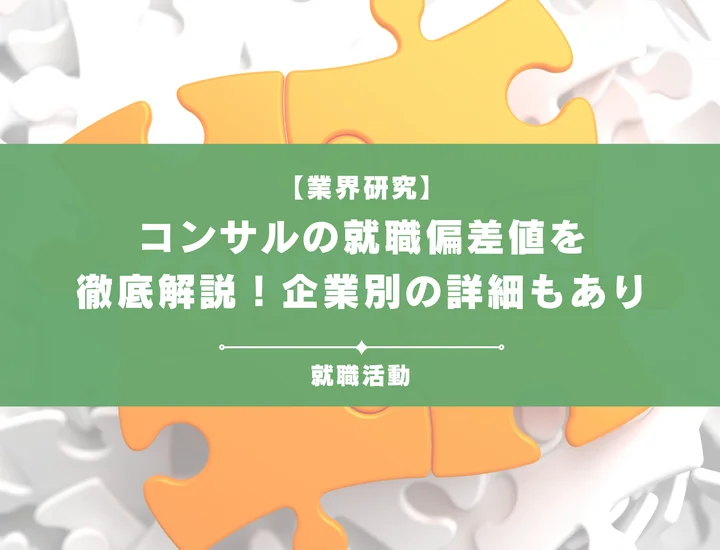HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
はじめに
コンサルティング業界は、高い専門性と問題解決能力を武器に企業の成長を支援する、非常に魅力的な業界です。
その一方で、選考難易度の高さでも知られており、多くの就活生が憧れと共に厳しい挑戦を覚悟しています。
この記事では、コンサルティング業界の全体像から、その特徴、求められる人物像、そして内定を勝ち取るための具体的なポイントまでを網羅的に解説します。
業界への深い理解は、他の就活生と差をつけるための第一歩です。
ぜひ本記事を参考に、コンサルティング業界への挑戦を成功させてください。
コンサルティングの就職偏差値ランキング
コンサルティング業界を目指す上で、多くの学生がコンサルティング就職偏差値のランキングを参考にします。
一般的に、マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン コンサルティング グループ、ベイン・アンド・カンパニーといった外資系戦略ファームは最上位に位置付けられ、極めて高い能力が求められます。
偏差値の高さだけに目を奪われず、自分に合った最高の環境を見つけることが就職活動成功の鍵となります。
【コンサルティング業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】マッキンゼー・アンド・カンパニー
Aランクに位置するコンサルティングファームは、世界的に名を知られるトップ企業が揃っています。
求められる能力は極めて高く、戦略的思考力や英語力、リーダーシップ、そして高いプレッシャーの中でも成果を出せる実行力が求められます。
選考対策としてはケース面接の徹底的な練習が必須であり、外資系志望者の中でも特に優秀な学生が集まる傾向があります。
【コンサルティング業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の企業を見るためには無料アカウントの作成が必要です。
無料登録すると、27卒向けのコンサルティング業界の就職偏差値ランキング全公開(Bランク〜Eランク)
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ自分の就職偏差値と企業ランクをチェックしましょう!
【69】ボストン・コンサルティング・グループ A.T.カーニー フーリハンローキー
【68】PwCストラテジー& ベイン・アンド・カンパニー アリックスパートナーズ ローランドベルガー アーサー・ディー・リトル M&Aキャピタルパートナーズ
【67】アクセンチュア(戦略) オリバー・ワイマン モニターデロイト EYパルテノン ブーズ・アレン・ハミルトン(日本法人はPwCストラテジー&に統合)
【66】コーポレイトディレクション ドリームインキュベータ 経営共創基盤IGPI P&Eディレクションズ デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー KPMGフィナンシャルアドバイザリーサービス PwCアドバイザリー ストライク
Bランクの企業も外資系や日系大手の戦略ファームが多く、高い就職偏差値を誇ります。
論理的思考力に加えて、チームでの協働力や柔軟性が求められる場面が増えています。
ケース面接やインターンを通じて実践的な理解を深めておくことが選考突破の鍵となります。
【コンサルティング業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】三菱総合研究所(研究員・コンサルティング) 野村総合研究所(戦略) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 日本オラクル(コンサルティング) コーンフェリー・ジャパン YCPジャパン
【64】マース・アンド・コー マーサージャパン ウイリス・タワーズワトソン エーオンヒューイットジャパン L.E.K.コンサルティング フロンティア・マネジメント
【63】アクセンチュア(非戦略) PwCコンサルティング デロイトトーマツコンサルティング KPMGコンサルティング EYストラテジー・アンド・コンサルティング ベイカレント(戦略) クニエ ジェンパクトコンサルティング
【62】電通総研 大和総研 IBMコンサルティング ガートナージャパン ライズコンサルティング 日本経営システム NTTデータ経営研究所 シグマクシス ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ グラックス・アンド・アソシエイツ
【61】アバナード みずほリサーチ&テクノロジーズ グローバルヘルスコンサルティング KPMGヘルスケアジャパン ケンブリッジテクノロジーパートナーズ クレイア・コンサルティング サイモン・クチャー&パートナーズ M&A総合研究所
Cランクでは、日系大手や外資準大手、シンクタンク系の企業が多く見られます。
戦略以外にも人事、IT、財務など専門性に特化した領域での活躍が期待されます。
自己分析と職種理解を組み合わせて志望動機を練り込むことが重要です。
【コンサルティング業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】アビームコンサルティング 日本総合研究所 三菱総研DCS ベイカレントコンサルティング(非戦略) 船井総研M&A 名南M&A インテージ(コンサルティング) リクルートマネジメントソリューションズ 電通コンサルティング
【59】山田ビジネスコンサルティング 三井住友トラスト基礎研究所 日立コンサルティング 富士通総研 博報堂コンサルティング フューチャーアーキテクト IQVIAソリューションズジャパン 価値総合研究所
【58】りそな総合研究所 オンデック ウルシステムズ ディルバート ブリッジコンサルティンググループ スカイライト・コンサルティング リフィニティブ・ジャパン
【57】船井総合研究所 タナベコンサルティング ビジネスブレイン太田昭和 名南経営コンサルティング 新経営サービス ストラテジーテック・コンサルティング AGSコンサルティング パクテラ・コンサルティング・ジャパン
【56】NX総合研究所 日本能率協会コンサルティング リンクアンドモチベーション ビジネスコーチ レイヤーズコンサルティング みらいコンサルティング プラスアルファ・コンサルティング オリエンタルコンサルティングタンツ NBCコンサルティングタンツ ロングブラックパートナーズ
Dランクの企業は中堅コンサルティングファームやシンクタンク系が中心です。
特定分野において専門性を発揮している企業が多く、安定志向の学生に人気があります。
OB訪問や説明会での情報収集が志望動機や自己PRに直結するため、地道な準備が大切です。
【コンサルティング業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】三菱総合研究所(研究員・コンサルティング) 野村総合研究所(戦略) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 日本オラクル(コンサルティング) コーンフェリー・ジャパン YCPジャパン
【64】マース・アンド・コー マーサージャパン ウイリス・タワーズワトソン エーオンヒューイットジャパン L.E.K.コンサルティング フロンティア・マネジメント
【63】アクセンチュア(非戦略) PwCコンサルティング デロイトトーマツコンサルティング KPMGコンサルティング EYストラテジー・アンド・コンサルティング ベイカレント(戦略) クニエ ジェンパクトコンサルティング
【62】電通総研 大和総研 IBMコンサルティング ガートナージャパン ライズコンサルティング 日本経営システム NTTデータ経営研究所 シグマクシス ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ グラックス・アンド・アソシエイツ
【61】アバナード みずほリサーチ&テクノロジーズ グローバルヘルスコンサルティング KPMGヘルスケアジャパン ケンブリッジテクノロジーパートナーズ クレイア・コンサルティング サイモン・クチャー&パートナーズ M&A総合研究所
Cランクでは、日系大手や外資準大手、シンクタンク系の企業が多く見られます。
戦略以外にも人事、IT、財務など専門性に特化した領域での活躍が期待されます。
自己分析と職種理解を組み合わせて志望動機を練り込むことが重要です。
【コンサルティング業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】アビームコンサルティング 日本総合研究所 三菱総研DCS ベイカレントコンサルティング(非戦略) 船井総研M&A 名南M&A インテージ(コンサルティング) リクルートマネジメントソリューションズ 電通コンサルティング
【59】山田ビジネスコンサルティング 三井住友トラスト基礎研究所 日立コンサルティング 富士通総研 博報堂コンサルティング フューチャーアーキテクト IQVIAソリューションズジャパン 価値総合研究所
【58】りそな総合研究所 オンデック ウルシステムズ ディルバート ブリッジコンサルティンググループ スカイライト・コンサルティング リフィニティブ・ジャパン
【57】船井総合研究所 タナベコンサルティング ビジネスブレイン太田昭和 名南経営コンサルティング 新経営サービス ストラテジーテック・コンサルティング AGSコンサルティング パクテラ・コンサルティング・ジャパン
【56】NX総合研究所 日本能率協会コンサルティング リンクアンドモチベーション ビジネスコーチ レイヤーズコンサルティング みらいコンサルティング プラスアルファ・コンサルティング オリエンタルコンサルティングタンツ NBCコンサルティングタンツ ロングブラックパートナーズ
Dランクの企業は中堅コンサルティングファームやシンクタンク系が中心です。
特定分野において専門性を発揮している企業が多く、安定志向の学生に人気があります。
OB訪問や説明会での情報収集が志望動機や自己PRに直結するため、地道な準備が大切です。
【コンサルティング業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】船井総研ロジ アウンコンサルティング ノースサンド AKKODiSコンサルティング ビジネスコンサルタント ビジョン・コンサルティング 東京コンサルティングファーム バーチャレクスコンサルティング ブレインワークス 創造経営センター 北浜グローバル経営 たすきコンサルティング アットストリームコンサルティング テクノ経営総合研究所 吉岡経営センター
Eランクには中小規模のコンサルティング会社が多く含まれます。
個別案件の支援や地域密着型の経営支援など、独自のスタンスを持つ企業も少なくありません。
中堅大学からの採用も活発であり、人物重視の選考が行われやすい点が特徴です。
【コンサルティング】とは
コンサルティング業界とは、企業や公的機関などが抱える経営上の課題を特定し、その解決策を提案・支援することを主な事業とする業界です。
クライアントは、新規事業の立案、業務プロセスの改善、M&A戦略の策定、ITシステムの導入など、自社だけでは解決が難しい複雑な問題に直面しています。
コンサルタントは、高度な専門知識と客観的な視点を持つプロフェッショナルとして、これらの課題解決に貢献します。
その専門性の高さから、この業界がどのような構造で成り立っており、コンサルタントが日々どのような業務に取り組んでいるのか、その基本を理解することから始めましょう。
コンサルティング業界の主な種類と分類
コンサルティング業界は、提供するサービスや専門領域によっていくつかの種類に分類されます。
代表的なのは、企業の全社戦略や事業戦略を扱う戦略系コンサルティングです。
経営層が抱える最重要課題に取り組むため、極めて高い論理的思考力が求められます。
次に、戦略の実行から業務改善、IT導入まで幅広く支援する総合系コンサルティングがあります。
BIG4と呼ばれる会計事務所系のファームが多く、多様なキャリアパスが魅力です。
また、IT戦略の立案やシステム導入を専門とするIT系コンサルティング、特定の業界や業務領域(例:人事、財務)に特化した専門特化系コンサルティング、官公庁を主なクライアントとするシンクタンク系など、その領域は多岐にわたります。
自分の興味や強みがどの領域で活かせるのかを考えることが、ファーム選びの第一歩となるでしょう。
各分野で求められるスキルやカルチャーも異なるため、企業研究を深めることが重要です。
コンサルタントの具体的な仕事内容
コンサルタントの仕事は、プロジェクト単位で進められます。
まず、クライアントへのヒアリングや市場調査を通じて、課題の現状を徹底的に分析します。
集めた情報から課題の本質を特定し、解決に向けた仮説を構築します。
この仮説を検証するために、さらなるデータ分析や関係者へのインタビューを重ね、解決策の精度を高めていきます。
そして、導き出した解決策を報告書やプレゼンテーション資料にまとめ、クライアントの経営層に提案します。
提案が承認された後は、その実行を支援するフェーズに移ることも少なくありません。
現場の従業員を巻き込みながら、改革が円滑に進むよう伴走します。
華やかなイメージを持たれがちですが、実際には膨大な資料の読み込みやデータ分析といった地道な作業が多くを占めます。
論理的思考力はもちろん、泥臭い作業をやり抜く実行力も不可欠な仕事です。
コンサルティング業界の市場規模と将来性
コンサルティング業界の市場規模は、世界的に拡大を続けています。
現代のビジネス環境は変化のスピードが速く、企業は常に新しい課題に直面しているからです。
特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、多くの企業にとって喫緊の課題であり、IT戦略や業務改革に強いコンサルタントへの需要を押し上げています。
また、近年ではサステナビリティや脱炭素社会の実現に向けたGX(グリーン・トランスフォーメーション)に関するコンサルティングも急増しています。
このように、社会や経済の大きな変化に対応して新たな需要が生まれるため、コンサルティング業界の将来性は非常に高いと言えます。
景気の動向に左右される側面はあるものの、企業が課題を抱え続ける限り、コンサルタントの役割がなくなることはないでしょう。
安定した成長が見込まれることも、この業界が高い人気を誇る理由の一つです。
【コンサルティング】特徴
コンサルティング業界には、他の業界とは一線を画す独特の文化や働き方が存在します。
それは、個人の成長を極限まで促す一方で、常に高い成果を求められる厳しさも併せ持っています。
こうした特徴を理解することは、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。
実力主義の文化、プロジェクト単位の働き方、そして高年収と激務。
これらの特徴が自分に合っているのか、じっくりと考えてみましょう。
憧れだけで飛び込むのではなく、リアルな姿を理解した上で挑戦することが、後悔のないキャリア選択につながります。
実力主義・成果主義の文化
コンサルティング業界は、年齢や社歴に関係なく、個人の実力や成果(バリュー)が評価される文化が根付いています。
新卒入社の若手であっても、優れた分析力や示唆に富んだ提案ができれば、プロジェクト内で重要な役割を任されます。
逆に、経験年数が長くてもクライアントの期待を超える貢献ができなければ、評価は厳しくなります。
この実力主義は、報酬や昇進にも明確に反映されます。
成果を出し続ければ、同世代のビジネスパーソンと比較して驚くべきスピードで昇進し、高い報酬を得ることが可能です。
若いうちから大きな裁量権を持ち、自分自身の力でキャリアを切り拓いていきたいと考える人にとっては、非常に魅力的な環境と言えるでしょう。
常に自己研鑽を怠らず、プレッシャーの中で成長し続ける意欲のある人材が求められています。
「Up or Out」の厳しい環境
Up or Out(昇進か、さもなくば退職か)という言葉は、コンサルティング業界の厳しさを象徴するものです。
これは、一定の期間内に次の役職に昇進できなければ、会社を去ることを促されるという文化を指します。
全てのファームで厳格に運用されているわけではありませんが、根底には常に成長し続けなければならないという考え方があります。
コンサルタントは、それぞれの役職で求められる役割やスキルレベルが明確に定義されており、それを満たすための成長が常に求められます。
この環境は、人によっては大きなプレッシャーとなるでしょう。
しかし、常に成長を求められるからこそ、他業界では得られないほどの速さでビジネススキルを習得できるという側面もあります。
この厳しい環境を乗り越えた人材は、転職市場においても非常に高く評価される傾向にあります。
プロジェクト単位での働き方
コンサルタントの働き方は、特定の部署に所属し続けるのではなく、プロジェクトごとにチームを組んで業務にあたるのが基本です。
一つのプロジェクトは数ヶ月から1年程度の期間で、終了するとチームは解散し、各メンバーはまた別の新しいプロジェクトにアサインされます。
この働き方の最大の魅力は、短期間で多様な業界やテーマに携われることです。
自動車業界の案件の次は金融業界、マーケティング戦略の次は組織改革といったように、常に新しい知識やスキルを吸収する機会に恵まれています。
知的好奇心が旺盛な人にとっては、飽きることのない刺激的な環境でしょう。
一方で、プロジェクトが変わるたびに新しい人間関係を構築し、異なるチームの進め方に適応していく必要があります。
高い適応能力と柔軟性が求められる働き方と言えます。
高年収だが激務な傾向
コンサルティング業界は、高年収であることでも知られています。
特に外資系の戦略ファームでは、新卒の初任給から高い水準が設定されており、その後の昇進に伴う昇給率も非常に高いです。
これは、優秀な人材を確保するための戦略であると同時に、コンサルタントが生み出す付加価値の高さが反映された結果でもあります。
しかし、その高年収の裏には、激務という側面が存在することも事実です。
クライアントが多額の報酬を支払う以上、その期待を超える成果を出すことが絶対的な使命となります。
そのため、プロジェクトの重要な局面では、深夜までの残業や休日出勤が必要になることも少なくありません。
近年は働き方改革が進み、以前よりは労働時間の管理が厳しくなっていますが、依然としてハードな仕事であることは覚悟しておくべきでしょう。
【コンサルティング】向いてる人の特徴
自分がこの業界に向いているのかを客観的に見極めることは、非常に重要です。
論理的思考力やコミュニケーション能力はもちろんのこと、強いプレッシャーの中で成果を出し続ける精神的な強さも問われます。
これから挙げる人物像に、自分自身がどれだけ当てはまるかを考えてみてください。
単なる憧れだけでなく、自己分析を通じて適性を深く理解することが、厳しい選考を突破し、入社後も活躍し続けるための土台となるでしょう。
知的好奇心と学習意欲が旺盛な人
コンサルタントは、プロジェクトごとに全く異なる業界やテーマを扱うため、常に新しいことを学び続ける必要があります。
例えば、これまで全く知らなかった製造業のサプライチェーンについて、短期間で専門家と対等に議論できるレベルまで知識を深めなければなりません。
そのため、どのような分野に対しても臆することなく、知的好奇心を持って積極的に学んでいける姿勢が不可欠です。
書籍や論文を読むだけでなく、専門家にヒアリングしたり、現場に足を運んだりと、あらゆる手段を尽くして情報を吸収する貪欲さが求められます。
未知の領域に飛び込むことを楽しみ、自分の知識の幅が広がることに喜びを感じられる人は、コンサルタントとしての適性が高いと言えるでしょう。
逆に、特定の分野だけを深掘りしたいという志向の人には、あまり向いていないかもしれません。
論理的思考力と問題解決能力が高い人
論理的思考力(ロジカルシンキング)は、コンサルタントにとって最も重要なスキルです。
クライアントが抱える複雑で曖昧な問題を、構造的に整理し、課題の本質を正確に突き止める能力が全ての基本となります。
例えば、売上不振という現象に対して、なぜそうなっているのかをMECE(モレなく、ダブリなく)の考え方で分解し、真の原因を特定していきます。
そして、その原因を解消するための打ち手を、説得力のある根拠と共に導き出す必要があります。
こうした一連の思考プロセスを、いかなる状況でも冷静かつ迅速に行える力が求められます。
物事を感情や感覚ではなく、客観的な事実とデータに基づいて判断し、道筋を立てて考えることが得意な人は、コンサルタントとして大きな強みを発揮できるでしょう。
この能力は、後述するケース面接で重点的に評価されます。
精神的・肉体的なタフさを備えている人
コンサルタントの仕事は、精神的にも肉体的にも非常にハードです。
クライアントの経営層からは常に高い期待と厳しい要求を突きつけられ、限られた時間の中で最高の結果を出さなければならないというプレッシャーが常にかかります。
プロジェクトが佳境に入れば、長時間労働が続くことも珍しくありません。
このような厳しい環境下でも、常に冷静さを保ち、ポジティブな姿勢で仕事に取り組める精神的な強さが不可欠です。
また、不規則な生活や高い負荷に耐えうるだけの体力も必要になります。
自分で自分のコンディションを管理し、高いパフォーマンスを維持し続ける自己管理能力もタフさの一部と言えるでしょう。
ストレスをうまく発散する方法を知っていたり、困難な状況を成長の機会と捉えられたりする人は、この厳しい環境を乗り越えていける可能性が高いです。
高いコミュニケーション能力で周囲を巻き込める人
コンサルタントは、一人で黙々と分析だけをしていれば良いわけではありません。
むしろ、多様な立場の人々と円滑に意思疎通を図り、信頼関係を築くコミュニケーション能力が極めて重要です。
プロジェクトの初期段階では、クライアントの役員から現場の担当者まで、様々な人から本音や実情を引き出すヒアリング能力が求められます。
そして、分析を経て導き出した提案をプレゼンテーションする際には、相手が納得し、行動に移したいと思えるような説得力のある伝え方が必要です。
さらに、改革を実行する段階では、時に抵抗勢力となる人々とも粘り強く対話し、改革の必要性を理解してもらい、協力を得なければなりません。
このように、人を動かし、周囲を巻き込んでいく力が、最終的な成果を大きく左右するのです。
【コンサルティング】向いてない人の特徴
コンサルティング業界は就職偏差値が非常に高く、多くの学生が憧れる人気のキャリアです。
しかし、その働き方は極めて特殊であり、残念ながら誰にでも向いているわけではありません。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、どのような人がコンサルタントの仕事に苦労しやすいのか、その特徴を理解し、冷静に自己分析してみることが大切です。
自分自身の特性と照らし合わせながら、本当に目指すべき道か考えてみましょう。
論理的に考えるのが苦手
コンサルタントの思考の根幹をなすのは、論理的思考力です。
クライアントが抱える複雑で巨大な問題を解決するためには、感覚や経験則だけに頼ることは許されません。
物事を構造的に分解し、データや事実に基づいて原因を特定し、誰が聞いても納得できる筋道を立てて解決策を構築する能力が不可欠です。
感情や直感を優先してしまい、なぜそう言えるのかを客観的な根拠で説明することが苦手な場合、クライアントを説得することはできません。
日頃から物事のなぜを深く考え、順序立てて説明する習慣がない人は、コンサルタントの基本業務で非常につまずきやすいでしょう。
抽象的なお題を扱うのが苦痛になる
コンサルタントに与えられるお題は、売上を向上させたい、新規事業を考えたいといった、非常に抽象的なものであることがほとんどです。
そこには決まった答えも、具体的な作業手順もありません。
このような曖昧な状況から、自ら課題は何かを定義し、情報を集め、仮説を立てて検証を繰り返すことで、具体的な実行プランに落とし込んでいくのが仕事です。
そのため、明確な指示がないと動けない人や、何をすべきか細かく教えてほしいという受け身の姿勢の人にとっては、常に暗闇の中を手探りで進むような感覚に陥り、大きな精神的苦痛を感じてしまう可能性が高いでしょう。
プレッシャーに弱く、体力に自信がない
コンサルタントの仕事は、極めて高いプレッシャーとの戦いです。
クライアントは高額な報酬を支払い、企業の未来を左右するような重要な課題の解決を託します。
限られた期間内に必ず成果を出さなければならないという責任は、想像以上に重くのしかかります。
また、プロジェクトが佳境に入ると、深夜までの長時間労働が続くことも珍しくありません。
このような厳しい環境で質を維持し続けるには、精神的なタフさと、それを支える最低限の体力が不可欠です。
ストレス耐性が低い人や体力に自信がない人は、心身のバランスを崩してしまうリスクがあります。
【コンサルティング】内定をもらうためのポイント
付け焼き刃ではない、本質的な対策が不可欠です。
特にコンサルティング業界の選考は、地頭の良さと呼ばれる論理的思考力や問題解決能力を試す、特殊な形式のものが多く含まれます。
生半可な準備では、優秀なライバルたちに太刀打ちできません。
ここでは、内定を勝ち取るために最低限押さえておくべき4つの重要なポイントを解説します。
これらの対策を徹底的に行うことが、憧れのファームへの扉を開く鍵となります。
一つひとつの対策に真剣に向き合い、万全の準備で選考に臨みましょう。
ケース面接とフェルミ推定の対策は必須
コンサルティング業界の選考、特に面接において避けて通れないのが、ケース面接とフェルミ推定です。
ケース面接とは、ある企業や業界の課題(例:特定の飲食店の売上を向上させるにはどうすればよいか)を与えられ、その解決策を面接官との対話を通じて導き出す形式の面接です。
一方、フェルミ推定は、一見見当もつかないような数量(例:日本全国にある電柱の数は何本か)を、論理的な思考プロセスを立てて概算するものです。
これらの選考で見られているのは、最終的な答えの正しさだけではありません。
それ以上に、どのように考え、問題を構造化し、仮説を立て、論理的に説明できるかという思考のプロセスそのものが評価されます。
対策本を読み込むだけでなく、友人やキャリアセンターの職員と模擬面接を繰り返し行い、自分の考えを分かりやすく伝える練習を積むことが不可欠です。
「なぜコンサルティングか」「なぜそのファームか」を明確にする
コンサルティング業界の面接では、志望動機の深さが厳しく問われます。
まず、世の中に数ある業界の中で、なぜコンサルタントという仕事を選んだのかを、自身の経験や価値観と結びつけて具体的に語る必要があります。
例えば、学生時代の経験から課題解決にやりがいを感じた、多様な業界に関わることで速いスピードで成長したい、といった動機を掘り下げておくことが重要です。
次に、数あるコンサルティングファームの中で、なぜそのファームを志望するのかを明確に説明できなければなりません。
そのためには、各ファームの得意領域、カルチャー、過去のプロジェクト事例などを徹底的に研究し、他社との違いを自分の言葉で語れるようにしておく必要があります。
企業のウェブサイトだけでなく、OB・OG訪問などを通じて生きた情報を集め、自分のキャリアプランとそのファームでできることを接続させることが説得力を高めます。
長期インターンシップに参加して実務経験を積む
コンサルティング業界の内定獲得において、長期インターンシップへの参加は非常に有効な手段です。
実際に数週間から数ヶ月間、社員と共にプロジェクトに近い業務を経験することで、コンサルタントの仕事に対する解像度を飛躍的に高めることができます。
この経験は、志望動機に圧倒的なリアリティと説得力をもたらすでしょう。
また、インターンシップでのパフォーマンスが評価されれば、本選考で有利になるケースや、そのまま内定に直結するケースも少なくありません。
企業側にとっても、学生の実務能力やカルチャーフィットを見極める絶好の機会となります。
人気ファームのインターンシップは選考倍率が非常に高いですが、挑戦する価値は十分にあります。
大学1、2年生の段階から情報を収集し、早期から選考対策を始めることが、参加への道を拓く鍵となります。
簡潔かつ論理的に話す能力をアピールする
コンサルティング業界の選考では、面接での受け答え全てが評価の対象となります。
特に重視されるのが、簡潔かつ論理的に話す能力です。
これは、日々の業務で忙しい経営層に対して、要点をまとめて分かりやすく報告・提案するコンサルタントの基本動作そのものだからです。
面接官からの質問の意図を正確に汲み取り、まずは結論から話すことを徹底しましょう。
その上で、理由や具体例を構造的に説明する、いわゆるPREP法(Point, Reason, Example, Point)を意識すると良いでしょう。
冗長な話し方や、話の要点が見えない説明は、思考が整理されていないと見なされ、マイナスの評価につながります。
日頃から友人との会話や大学の発表など、あらゆる場面でこの話し方をトレーニングし、自然に実践できるよう準備しておくことが、内定への近道となります。
【コンサルティング】よくある質問
コンサルティング業界は専門性が高く、情報も限られているため、就活生の皆さんからは多くの質問が寄せられます。
特に、求められるスキルや実際の働き方については、リアルな情報を知りたいという声が多いです。
入社後のミスマッチは、自身にとっても企業にとっても不幸な結果を招きます。
そうした事態を避けるためにも、疑問点は選考が本格化する前に解消しておくことが大切です。
ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について、実情を踏まえて回答します。
これらの回答を通じて、コンサルティング業界への理解をさらに深めていきましょう。
英語力はどのくらい必要ですか?
コンサルティング業界、特に外資系ファームでは、英語力の重要性が年々高まっています。
グローバルなプロジェクトが増えており、海外オフィスのメンバーとの連携や、英語の資料を読み解く機会が日常的にあるためです。
ファームやプロジェクトによって求められるレベルは異なりますが、一般的にはビジネスレベルの英語力、特に読み書きの能力は必須と考えておくと良いでしょう。
英語での情報収集やメールのやり取りに支障がないレベルが求められます。
会話力(スピーキング)に関しては、流暢でなくとも、自分の意見を論理的に伝えられる能力があれば、高く評価されます。
入社時点では必須としないファームでも、入社後の昇進の要件になっていたり、語学研修制度が充実していたりする場合が多いです。
英語力に自信があれば、活躍の場は間違いなく広がります。
文系や理系、学歴は選考に関係しますか?
コンサルティング業界の選考において、文系か理系かという出身学部は直接的な有利不利にはつながりません。
実際に、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍しています。
重要なのは、文系・理系といった枠組みではなく、コンサルタントとして必須の論理的思考力や問題解決能力を個人として備えているかどうかです。
学歴に関しては、結果としていわゆるトップクラスの大学出身者が多く在籍しているのが実情です。
これは、地頭の良さを測る一つの指標として企業側が見ている側面や、そうした大学の学生が早期からコンサルティング業界を志望し、入念な対策を行っていることが背景にあると考えられます。
しかし、学歴だけで合否が決まるわけでは決してありません。
選考過程でポテンシャルや論理的思考力を示すことができれば、学歴に関わらず内定を勝ち取ることは十分に可能です。
ワークライフバランスはどのようになっていますか?
ワークライフバランスは、コンサルティング業界を志望する多くの就活生が気にする点です。
かつては、寝る間も惜しんで働くのが当たり前というイメージが強かったですが、近年は業界全体で働き方改革が進んでおり、状況は大きく改善されつつあります。
多くのファームで労働時間の管理が徹底され、不必要な長時間労働を是正する動きが活発化しています。
しかし、クライアントの期待に応えるという仕事の性質上、プロジェクトの納期前などの繁忙期には、依然として激務になることは覚悟しておく必要があります。
一方で、プロジェクトとプロジェクトの間にまとまった休暇(On the beachと呼ばれることもあります)を取得しやすいという特徴もあります。
オンとオフのメリハリをつけ、オフの期間は自己投資やリフレッシュに充てるという働き方が一般的です。
ファームによって制度やカルチャーが異なるため、OB・OG訪問などで実情を確認することをおすすめします。
まとめ
本記事では、コンサルティング業界について、その全体像から内定獲得のポイントまでを詳細に解説しました。
コンサルティング業界は、クライアントの課題解決を通じて社会に大きなインパクトを与えられる、非常にやりがいの大きな仕事です。
重要なのは、業界の華やかなイメージだけでなく、その厳しさや求められる資質を正しく理解し、自分自身の適性を見極めることです。
そして、目標とするファームが決まったら、ケース面接対策をはじめとする徹底的な準備を行うことが不可欠です。
この記事が、皆さんのキャリア選択の一助となり、厳しい選考を乗り越える力となることを心から願っています。