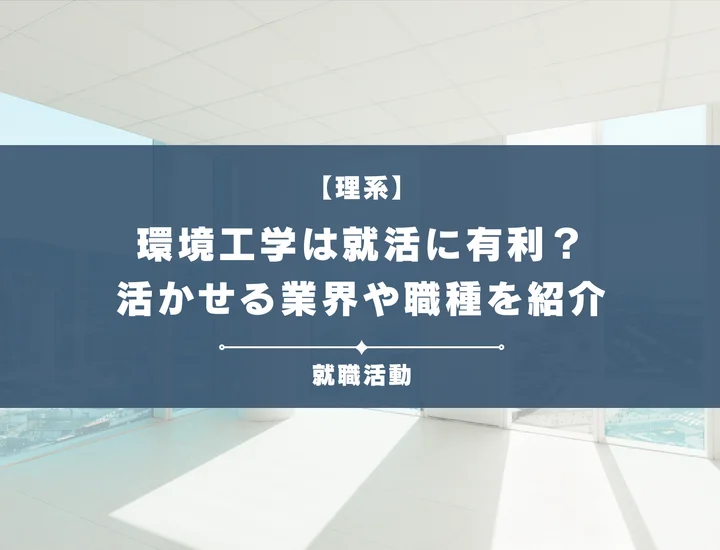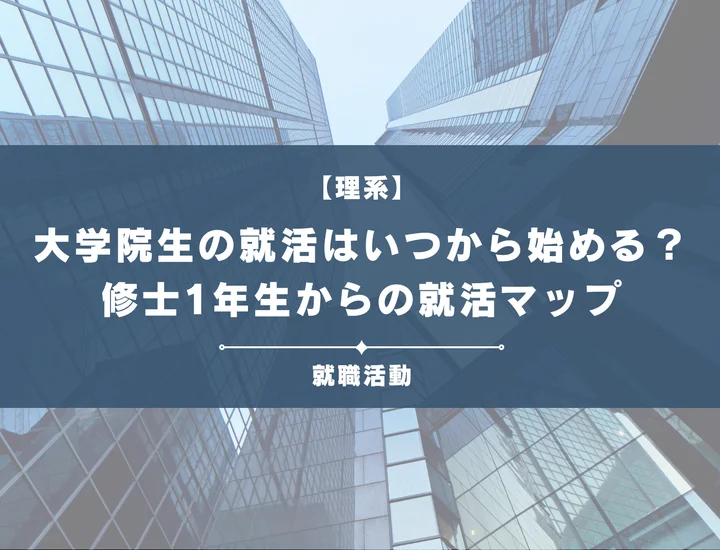HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
環境工学は、持続可能な社会の実現に欠かせない学問分野です。
この記事では、環境工学を活かせる業界や職種、就職活動の進め方や対策のポイントについて、具体的かつわかりやすく解説していきます。
【環境工学・就職】環境工学は就職に有利
環境工学は、地球環境の保全と持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を担う学問です。
近年では、気候変動や環境破壊が深刻化する中で、企業や自治体も環境への対応を経営や政策の中心に据えるようになってきました。
そのような背景のもと、環境に関する知識と技術を持つ人材への期待はますます高まっています。
ここでは、環境工学が就職に有利とされる理由について、具体的な視点から詳しく解説していきます。
高まる環境意識と企業のニーズ
SDGsや脱炭素社会といった言葉が一般的に使われるようになり、多くの企業が環境に配慮した取り組みを経営の中核に据えるようになっています。
温室効果ガスの排出削減、再生可能エネルギーの導入、製品のライフサイクル全体での環境負荷の低減など、あらゆる分野で環境技術の活用が進められています。
このような流れの中で、環境工学を学んできた学生には、社会的課題に対して具体的な技術や知識を用いて貢献できる人材としての期待が寄せられています。
企業の環境部門だけでなく、生産管理、品質保証、技術開発など、さまざまな部署で環境への対応が求められており、活躍の場が広がっています。
また、環境報告書の作成やESG経営の推進といった、経営に関わる領域でも環境工学の視点が重要視されているため、将来的なキャリアの選択肢も多様です。
幅広い専門分野
環境工学は、地球や人の暮らしに関わるあらゆる課題に対応するために、多くの専門領域を横断する学問です。
水処理や廃棄物処理、大気中の有害物質の除去など、生活の基盤を支える技術から、温室効果ガスの排出抑制や再資源化といった地球規模の取り組みまで、幅広い分野が対象となります。
こうした多様な知識を持つことにより、就職先の業界も自然と多岐にわたります。
製造業では生産工程での環境負荷を抑える工夫に、建設業では土壌や水質への影響を考慮した設計に、自治体や官公庁では環境政策の立案や施行に携わることができます。
また、都市計画や交通インフラにおいても、環境の視点は不可欠となっており、計画の初期段階から専門家として関わる機会があります。
【環境工学・就職】環境工学を活かせる業界
環境工学で学んだ知識や技術は、さまざまな業界で求められています。
気候変動や資源問題が深刻化する中で、持続可能な社会の実現に向けた取り組みは多くの企業や行政機関にとって最優先の課題です。
ここでは、環境工学を専攻する学生が活躍しやすい代表的な業界について、その特徴や主な仕事内容を詳しく紹介していきます。
総合建設業(ゼネコン)
総合建設業は、都市や地域のインフラ整備を担う業界であり、環境工学の知識が活かされる場面が数多く存在します。
近年は、環境への影響を最小限に抑えた建築設計や施工が求められるようになっており、省エネルギー性の高い建物や再生可能素材を使った構造物の開発が進められています。
また、過去の工場跡地や埋立地などにおいては、土壌汚染の調査とその対策が欠かせません。
このような現場では、環境リスクを評価し、適切な工法を提案する技術者が必要とされます。
さらに、廃棄物処理施設や下水処理場の設計・建設においても、水質保全や公害防止の観点から環境工学の視点が活かされます。
現場における実践力と環境保全に対する意識の両立が求められる分野です。
プラントエンジニアリング
プラントエンジニアリング業界では、エネルギーや水、廃棄物などの処理を担う大規模施設の設計から運転管理までを行います。
環境工学で学ぶ水処理技術や排ガス対策、廃棄物の焼却や再資源化などの知識は、まさにこの業界で活かされるものです。
具体的には、上下水道施設やごみ焼却施設、バイオマス発電所などの建設に関わる機会が多く、各種設備が環境に与える影響を考慮しながら設計する必要があります。
運用面では、省エネルギー化や安定稼働を意識した管理が求められ、技術力に加えてマネジメント力も重要です。
環境への配慮と大規模プロジェクトに対する工学的な視点を融合させることで、持続可能なインフラ整備に貢献することができます。
メーカー
メーカーにおいては、製品の設計から生産、リサイクルに至るまでの各段階で環境への影響を抑える工夫が求められています。
自動車、電機、化学などの分野では、環境規制の強化や市場のニーズに対応するため、製品そのものの改良や製造プロセスの見直しが常に行われています。
環境工学を学んだ人材は、素材の選定からエネルギー使用量の削減、排出物の削減などにおいて重要な役割を果たします。
また、廃棄された製品の回収や再利用を進めるリサイクル技術の開発にも携わることができます。
近年では、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みも活発化しており、環境対応型のモノづくりに関わる人材の需要は今後も高まっていくと考えられます。
電力・ガス会社
エネルギー分野でも、環境工学の知識を活かして働ける場面は増え続けています。
特に再生可能エネルギーの導入が進められている中で、太陽光、風力、地熱などを安全かつ効率的に運用するための技術が求められています。
また、送配電網の整備や、電力使用量の最適化など、持続可能なエネルギーシステムの構築においても、環境への影響を考慮した判断が必要になります。
ガス会社では、CO2排出量の削減やメタン漏れ対策などの課題に対して、設備面や運用面からの改善が行われています。
これらの仕事では、理論だけでなく実務に直結する視点が重視され、エネルギーと環境の両面を理解している人材が貴重な戦力となります。
コンサルティングファーム
コンサルティング業界では、企業や自治体に対して環境面での課題解決を支援する業務が行われています。
環境アセスメントを通じて開発が自然環境に与える影響を評価したり、環境規制に適合するための対応策を提案したりすることが主な役割です。
また、カーボンフットプリントの計測や温室効果ガスの削減目標の設定、環境報告書の作成など、企業の環境経営を支える取り組みにも関わります。
この分野では、理系的な知識に加えて、クライアントとの調整力や資料作成のスキルも必要になります。
環境に関する幅広い課題をビジネスの現場で解決していくため、実践的な提案力と柔軟な対応力が求められます。
官公庁・地方自治体
官公庁や地方自治体においても、環境工学の専門知識は役に立ちます。
温室効果ガスの削減目標を達成するための政策立案や、廃棄物の適正処理、水質や大気のモニタリングといった行政的な業務は多岐にわたります。
また、公共事業を実施する際には、地域環境への配慮が求められ、その評価や監視を行う立場として環境工学を学んだ人材が活躍します。
加えて、地域住民への啓発活動や、事業者への指導・支援など、対人業務も多く含まれています。
公益性の高い業務であるため、社会全体に貢献しているという実感を持ちやすく、安定したキャリアを築ける選択肢として人気があります。
研究機関
研究機関では、環境問題の解決に向けた新しい技術や理論の開発が行われています。
大学や国立の研究所では、水質改善技術や新しい再生可能エネルギーの開発、大気や土壌の浄化手法など、応用可能な成果が日々生まれています。
基礎研究だけでなく、企業と連携して実用化を目指す研究や、国の政策に反映されるような調査も行われています。
この分野では、専門性の高さに加えて継続的な探究心が必要です。
また、研究成果を論文や学会で発表するなど、情報発信も求められる場面が多くあります。
知識を深めながら、新たな発見を通じて社会課題の解決に挑戦したい人には最適なフィールドです。
【環境工学・就職】環境工学が活かせる具体的な企業例
環境工学は水や空気、エネルギーや廃棄物といった身近な資源や環境問題に直接関わる学問です。
その知識や技術は、社会のさまざまな産業で求められています。
建設、エネルギー、製造業、コンサルティング、そして行政まで、活躍の場は幅広く存在します。
ここでは、環境工学を学んだ人が具体的にどのような企業で力を発揮できるのかを紹介します。
清水建設
清水建設は日本を代表する総合建設会社で、建築や土木だけでなく不動産開発や環境関連事業にも積極的に携わっています。
特に環境分野では、専用の環境技術研究所を設け、省エネや再生可能エネルギー、環境浄化などに関する研究を進めています。
環境工学を学んだ人は、大規模な開発に伴う環境アセスメントの実施や、土壌・地下水汚染の浄化技術開発に携わることができます。
さらに建設現場での廃棄物の適正処理やリサイクル推進、太陽光や風力など再生可能エネルギー施設の建設にも関わる機会があります。
社会インフラと環境保全を両立させるための技術を実践できる場として、大きな魅力があります。
栗田工業
栗田工業は水処理の専門企業として、工業用水や生活排水の処理、再利用を行う装置や薬品を提供しています。
特に半導体製造などで欠かせない超純水システムに強みを持ち、世界的に高いシェアを誇ります。
環境工学を学んだ人は、水質の分析や改善策の提案、排水処理システムの設計・運用などに携わります。
また、省水化やリサイクル技術の開発も重要な役割です。
効率的で環境に優しい薬品や装置の研究開発にも関わることができ、地球規模の水資源問題に貢献するやりがいを実感できます。
ダイキン工業
ダイキン工業は空調機器とフッ素化学を二本柱とする企業で、エアコンや冷媒の開発では世界有数の実績を持ちます。
環境工学の知識は、省エネ性能を高める技術開発や、環境負荷の少ない冷媒の研究で活かせます。
また、室内の空気質を改善するための空気清浄技術や換気システムの開発にも携われます。
さらに、製造工程での排水や廃棄物削減、化学物質の適正管理も重要な役割です。
世界的に気候変動対策が求められる中、ダイキンは持続可能な社会の実現に向けて技術革新を続けています。
海外展開も積極的であり、グローバルな舞台で環境技術を発揮できる環境が整っています。
持続可能な快適環境を世界に提供するダイキンでは、環境工学の力が幅広く求められています。
東京電力ホールディングス
東京電力は日本最大の電力会社で、火力、原子力、水力、再生可能エネルギーなど多様な発電事業を行っています。
環境工学を学んだ人は、火力発電所でのCO2排出削減技術の開発や高効率発電システムの導入に携われます。
また、風力や太陽光など再生可能エネルギー施設の開発や運営、建設に伴う環境影響評価も重要な業務です。
さらに、環境リスクの管理や生物多様性の保全活動も行っており、持続可能なエネルギー供給に貢献できます。
エネルギーインフラを担う企業として社会的責任も大きく、安全性と環境保全の両立が求められます。
海外のエネルギー事業や新技術導入も進んでおり、環境工学の専門性を活かして広範な課題に取り組める場が整っています。
社会基盤を支える電力事業の中で、環境技術を駆使して未来のエネルギーを形にすることができます。
デロイト
デロイトは世界最大級の総合コンサルティングファームであり、監査や税務だけでなく環境分野のコンサルティングにも力を入れています。
環境工学を学んだ人は、企業の脱炭素戦略やサステナビリティ方針の策定を支援する役割を担えます。
また、温室効果ガス排出量の算定や環境報告書の作成支援、環境規制対応のアドバイスも行います。
さらに、カーボンニュートラルや循環型経済といった新しい産業の創出にも携わることができます。
多様な業界のクライアントと関わるため、幅広い視点で環境課題を捉え、解決策を提案できるのが特徴です。
国際的な枠組みや最新の環境基準に対応するプロジェクトも多く、グローバルな活躍を目指す人にとって大きな魅力があります。
企業経営と環境保全の両立を支える立場として、広い視野で環境課題に取り組めるのが特徴です。
環境省
環境省は日本の環境行政を担う中央省庁で、温暖化対策や自然保全、公害対策など幅広い政策を担当しています。
環境工学を学んだ人は、科学的データを基に大気や水質の基準を定めたり、再生可能エネルギー技術の導入を推進したりします。
また、全国規模での環境調査や監視業務を通じて環境問題の実態を把握し、解決策を講じる役割を果たします。
廃棄物処理やリサイクルを促進する制度設計や技術的指導も重要な業務です。
国際会議や多国間協力にも関わる機会があり、グローバルな視点で環境政策をリードする役割も担っています。
市民や産業界と連携し、良い社会を築くための仕組みづくりに直接携われるのも大きな魅力です。
国の政策を通じて持続可能な社会の実現を支える場として、環境工学の専門性を存分に発揮できる職場です。
【環境工学・就職】環境工学を活かせる職種例
環境工学の知識は、社会の持続可能性を支えるさまざまな仕事で必要とされています。
就職活動では、自分の専門性をどのような職種で活かせるのかを知っておくことが重要です。
ここでは、環境工学を学んだ学生が実際に活躍しやすい代表的な職種について、それぞれの仕事内容や求められる能力を詳しく紹介していきます。
研究開発職
研究開発職では、新しい環境技術や素材の開発、既存技術の改良などに取り組みます。
省エネルギー型の機器の開発、CO2を吸収する新素材、再生可能資源を使った製品など、環境負荷の少ない技術や製品を世の中に送り出すための仕事です。
環境工学で得た知識や実験経験を活かし、課題の発見から仮説の設定、実験、検証という流れを自ら組み立てて進めていく力が求められます。
また、文献調査や特許情報の確認、試作品の評価など、多くの情報を扱うことになるため、情報整理力や論理的な思考力も大切です。
製品開発部門や企業の研究所、公的な研究機関など、活躍の場は多岐にわたります。
世の中のニーズに応える技術を生み出すという使命感を持って働ける、やりがいのある職種です。
設計・開発職
設計・開発職は、環境に配慮した施設や製品を具体的な形にしていく仕事です。
上下水道処理施設やごみ焼却場などの設計を担当するケースや、工場の排出ガス対策設備の構築に関わることもあります。
また、製品そのものの環境性能を高めるための設計、使用中のエネルギー効率を改善する工夫など、幅広い分野で環境への配慮が求められています。
環境工学で学ぶ基礎知識をベースに、CADなどの設計ツールやシミュレーションソフトを使いこなす技術が求められる場合もあります。
多くの場合、複数の関係者と連携しながら計画を進めるため、協調性やコミュニケーション力も大切な要素になります。
実際のものづくりを通じて、環境に優しい社会づくりを支える重要な仕事です。
施工管理
施工管理は、環境関連施設の建設現場において、工程や品質、安全、コストの面で全体をコントロールする職種です。
現場では、設計図通りに建設が進むように調整するだけでなく、周辺環境への影響や騒音・振動対策、水質汚濁の防止なども重要な課題となります。
環境工学で得た知識を活かして、建設工程の中でも環境に対する配慮を実践する役割を担います。
また、作業員や協力会社とのやり取りが多いため、現場対応力や的確な判断力が求められます。
建設プロジェクトにはスケジュールの遅れや予算の制約といった難しさもありますが、完成したときの達成感は大きな魅力です。
現場の最前線でモノづくりを支える中で、環境の視点を持ち込むことができる貴重なポジションです。
環境コンサルタント
環境コンサルタントは、企業や自治体の環境に関する課題に対して、調査・分析・提案を行う専門職です。
仕事の一例として、開発計画に対する環境影響評価、温室効果ガスの排出量の算定、持続可能な企業戦略の策定支援などがあります。
環境工学の知識をもとに、科学的な根拠に基づいた提案を行うことで、クライアントの信頼を得る必要があります。
この職種では、調査データの整理やレポートの作成、プレゼンテーションなど、多岐にわたる業務をこなす力が求められます。
また、法規制や制度に関する理解も重要となるため、常に最新の動向に目を向ける姿勢が必要です。
多様な案件に関わることができるため、知的好奇心の強い人や、柔軟な発想で課題解決に取り組める人に向いています。
技術営業職
技術営業職は、環境関連の製品やサービスを顧客に提案し、導入から運用までをサポートする仕事です。
単に製品を販売するのではなく、顧客の課題を技術的に理解し、最適な解決策を一緒に考えていく姿勢が求められます。
環境計測機器、浄水装置、省エネルギーシステムなどを扱うことが多く、専門知識を活かして信頼を築いていくことが重要です。
また、製品の使い方や導入効果について説明する場面もあるため、分かりやすく伝える力が必要になります。
営業であると同時に技術者としての視点も持つため、現場での対応や社内の技術部門との連携も頻繁に行われます。
人と関わることが好きで、技術とビジネスの両面に興味がある人にとっては、非常にやりがいのある職種です。
公務員(環境系)
環境系の公務員は、環境省や地方自治体の職員として、地域や国全体の環境保全に関する政策を企画・実施する仕事です。
大気や水質の監視、公害対策、廃棄物の管理、環境教育の推進など、さまざまな業務を通じて地域社会の安全と快適な生活環境を守ります。
また、企業や市民に対する環境指導や支援業務もあり、知識だけでなく対話力や調整力も求められます。
地域特性に応じた対応が必要となるため、柔軟な発想と現場感覚も重要な要素です。
地道な仕事が多いですが、住民の暮らしに直結する公共性の高い職務であり、大きなやりがいを感じられます。
安定した雇用環境の中で、社会貢献性の高い仕事に就きたいと考える人には、非常に適した進路です。
【環境工学・就職】就職活動の進め方
環境工学を学ぶ学生が、自分の専門性を社会で活かすためには、計画的な就職活動が欠かせません。
やみくもに応募するのではなく、自分の強みや興味、そして働きたい環境を明確にし、それに合った業界や企業をしっかりと調べることが成功の鍵です。
ここでは、就職活動を段階的に整理し、それぞれのステップで意識すべきポイントを具体的に解説していきます。
自己分析・業界研究
就職活動の第一歩は、自己分析から始まります。
自分がどんな価値観を持ち、どんな分野に興味を持っているのかを整理することで、納得のいく進路選びにつながります。
環境工学の中でも、水処理、大気汚染対策、廃棄物処理、エネルギー管理など、自分が特に関心を持っている分野を明確にすることが重要です。
また、自分の得意なことやこれまでに達成した経験を振り返り、それがどんな業務に役立つのかを考えておくと、後の選考でも役立ちます。
業界研究では、どの企業が環境課題にどう向き合っているかを具体的に調べましょう。
企業ホームページや就職情報サイトのほか、OBOG訪問を活用することで、実際の仕事内容や職場の雰囲気を深く理解できます。
自分の志向と企業の特徴が一致するかを確かめることが、ミスマッチを防ぐうえで非常に大切です。
企業説明会・インターンシップ
企業説明会やインターンシップは、企業への理解を深める貴重な機会です。
説明会では、業務内容や組織の特徴、求める人物像について直接話を聞くことができ、企業研究を進めるうえでのヒントが得られます。
また、インターンシップでは、実際の業務を体験できるため、自分がその企業や職種に向いているかを確かめることができます。
短期間のプログラムでは企業の概要を知ることができ、長期間のものでは実務に近い経験が積める場合もあります。
事前に企業の情報を調べておくことで、インターンシップ中により深い学びを得ることができます。
加えて、インターンシップで良い印象を残せば、本選考での評価にプラスになることもあります。
ES作成・Webテスト対策
エントリーシートは、自分を企業に伝えるための大切な書類です。
単に経験や研究内容を並べるのではなく、それらを通じてどのような力を身につけたか、企業でどう活かせるかを明確に書くことが求められます。
研究内容については、専門用語を使いすぎず、誰にでも伝わるように工夫して説明することが大切です。
また、論理的な構成を意識し、読み手が納得できるように仕上げる必要があります。
Webテストについては、SPIや玉手箱など複数の形式が存在し、それぞれに特徴があります。
問題集や模擬試験を通じて慣れておくことで、本番でも落ち着いて対応できます。
特に時間配分や問題の傾向を把握することが重要です。
学業や研究と並行しての準備になるため、早めに取りかかることを意識しましょう。
面接対策
面接では、エントリーシートに書いた内容を深掘りされることが多く、自分の考えや姿勢を直接伝える場でもあります。
自己PRや志望動機に加えて、研究内容についても質問されることがよくあります。
そのため、専門外の人にも分かりやすく話す練習を繰り返し行うことが重要です。
環境問題に対する自分の意見や、その課題に対してどのように貢献したいかという視点も準備しておくと良い印象を与えられます。
また、面接ではコミュニケーションの取り方や表情など、言葉以外の部分も評価されます。
模擬面接を通して、話す内容だけでなく、姿勢や話し方も確認しておくと安心です。
大学のキャリアセンターや友人の協力を得ながら、本番に備えて実践的な対策を積み重ねていくことが大切です。
【環境工学・就職】就職活動を有利に進めるには
環境工学を学ぶ学生が、自分の専門性を活かして就職活動を成功させるためには、単に知識を習得するだけでなく、社会との接点を意識することが大切です。
専門的な能力と、実社会でそれをどう活かすかという視点の両方を持つことで、企業からの評価も高まりやすくなります。
ここでは、就職活動を有利に進めるために実践しておきたい5つのポイントを紹介します。
専門知識をより深める
大学で学ぶ環境工学の内容は、水質管理、大気汚染防止、廃棄物処理、エネルギーの有効利用など、社会課題と直結した分野が多くあります。
そのため、基礎知識をしっかりと理解することはもちろん大切ですが、それだけにとどまらず、それぞれの知識がどのように実社会で活かされているかを考える視点を持つことが重要です。
たとえば、水処理技術を学んでいる場合は、その技術が上下水道の整備や産業排水の改善にどう応用されているかを調べ、実際の課題とのつながりを意識しましょう。
ニュースや実際の事例をもとに、学んだ知識がどのような場面で求められているかを具体的に想像する習慣を持つことで、面接やエントリーシートでも説得力のあるアピールが可能になります。
研究内容をわかりやすく説明する
就職活動では、自分の研究内容について質問されることが多くあります。
その際に重要なのは、相手が専門知識を持っていない場合でも、理解できるように話すことができるかどうかです。
研究の背景や目的、取り組んだ方法、得られた結果を、順序立てて整理し、専門用語をできる限り使わずに説明する練習をしておきましょう。
また、その研究が社会にどのような形で役立つのか、どんな課題を解決しようとしているのかを、自分の言葉で伝えることが求められます。
たとえば、廃棄物処理の効率化に関する研究であれば、環境負荷の軽減やコスト削減といった社会的なメリットにまで言及できると良いです。
資格取得と語学力
環境分野で活躍するうえで、専門資格を取得することは自分の能力を証明する有効な手段となります。
環境計量士や公害防止管理者、技術士補などは、企業からの信頼も高く、即戦力として期待されやすくなります。
在学中に取得を目指すことで、就職活動時にアピール材料として活用できます。
また、環境問題は国際的な協力や取り組みが必要な場面が多いため、英語のスキルも重視されます。
海外とのプロジェクトや資料作成、会議参加などの場面を想定して、日頃から英語に触れる習慣をつけておくとよいでしょう。
TOEICや英検などの資格は、語学力を客観的に示す指標として有効です。
専門性と国際性の両方を備えることで、環境分野における選択肢はさらに広がります。
コミュニケーション能力と協調性
どれだけ専門知識があっても、それを現場で活かすためには周囲との連携が欠かせません。
職場では、他分野の技術者や営業、行政担当者など、異なる立場の人々と協力しながら業務を進める機会が多くあります。
そのため、チームで動く力や、自分の意見を的確に伝える力、相手の考えを理解する姿勢が求められます。
日頃からグループワークやサークル活動、アルバイトなどの中で、人と関わる経験を積み重ねておくと、自然とこの力が育まれます。
また、研究発表やディスカッションの場でも、他人の意見に耳を傾け、必要に応じて建設的な意見交換ができるよう意識しましょう。
そもそもコミュニケーション能力と協調性は、どの企業でも重視される要素であり、選考の中でもしっかりと見られる部分です。
情報収集と多様な視点
環境問題は、法制度や技術の進化、国際情勢によって常に変化しています。
そのため、日頃から新聞やニュースサイト、専門誌などを通じて、最新の情報をキャッチアップしておくことが大切です。
自分の専門領域だけでなく、エネルギー政策、リサイクル技術、カーボンニュートラルといった他分野にも興味を持ち、知識の幅を広げていきましょう。
多様な視点を持つことで、課題に対して柔軟かつ創造的に対応する力が身につきます。
また、企業ごとに取り組んでいる環境施策や技術の方向性を知ることで、志望動機や面接での発言にも説得力が増します。
普段からアンテナを張って情報を収集し、自分の専門性とどうつなげるかを考える姿勢が、周囲と差をつけるポイントになります。
まとめ
環境工学の知識は、社会のあらゆる場面で必要とされる専門性です。
だからこそ、自分の学びをどのように社会とつなげていくかを常に意識し、具体的なビジョンを持って行動しましょう。