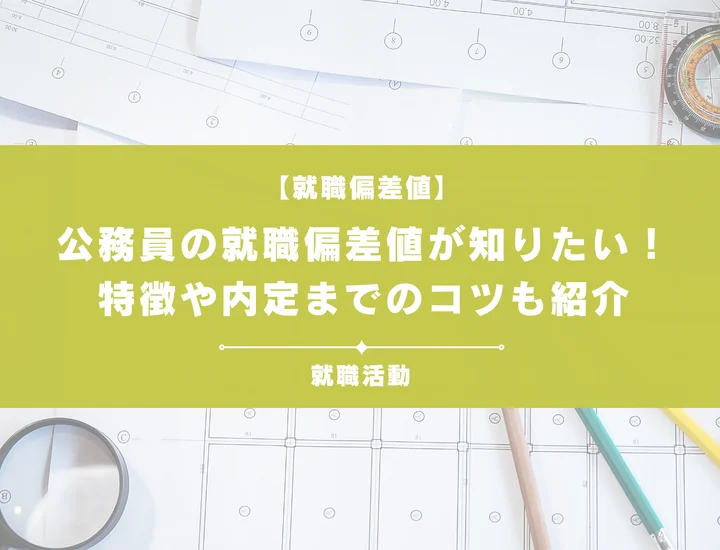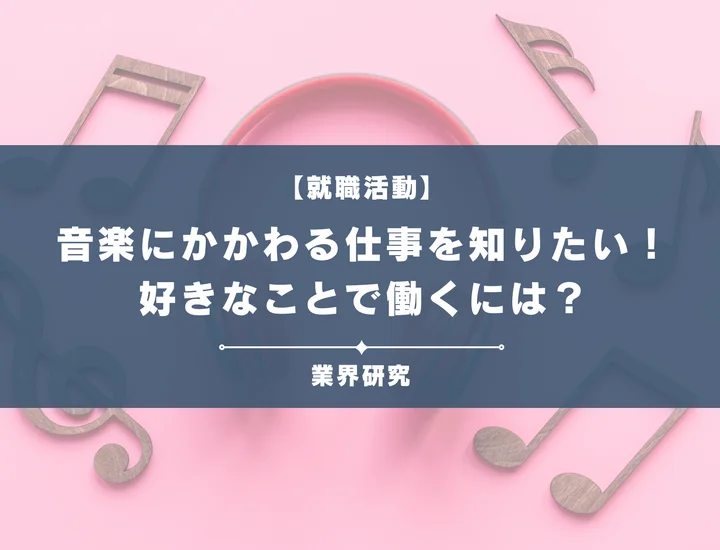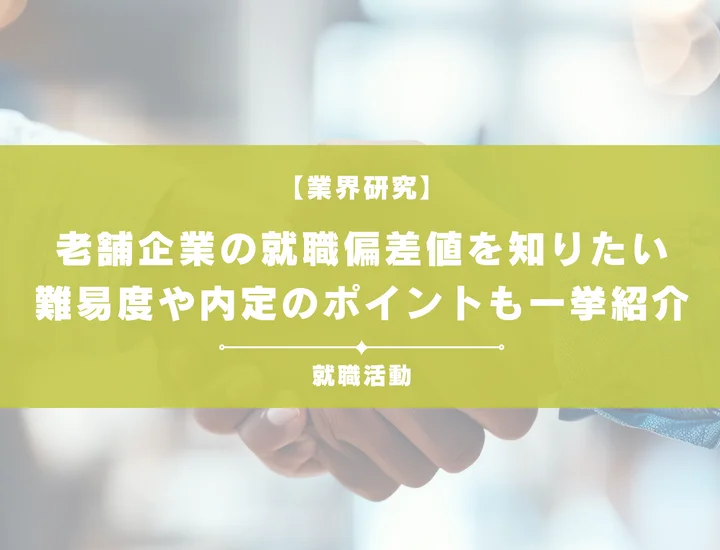HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、主に民間企業を対象として、その企業への入社難易度を分かりやすく示すために作られた指標です。
公的なデータではなく、就職予備校などが企業の人気度や選考倍率、ブランド力といった要素から独自に算出したものです。
数値が高いほど入社が難しいとされ、学生が自身の学力や立ち位置を測り、企業選びを行う上での一つの目安として広く参考にされています。
公務員にもこの考え方が転用され、試験の難易度を示す際に使われることがあります。
公務員の就職偏差値ランキング
ここからはさっそく公務員の就職偏差値をご紹介していきます。
就活生の皆さんが、興味のある省庁や役職はどの就職偏差値ランクなのか確認していきましょう。
【公務員業界】Sランク(就職偏差値75以上)
【75】内閣総理大臣(石破茂)
主に国政トップや特定の政党党首など、選挙と議会運営を通じて選出されるポジションが中心です。
政策立案力と卓越したリーダーシップが必須であり、国会答弁や危機管理を主導できる総合力が求められます。
入るための現実的なルートは、地方議会から国政へ段階的にステップアップし、政策実績と党内基盤を築くことです。
政治活動の継続、選挙戦略、人脈形成、メディア対応の訓練など、長期的かつ総合的な準備が必要です。
【公務員業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【74】副総理 最高裁判所長官 議長(衆議院・参議院)
【73】内閣官房長官 財務大臣 外務大臣 防衛大臣
【72】経済産業大臣 厚生労働大臣 会計検査院長 人事院総裁
【71】その他の国務大臣 国家公安委員会委員長 自民党派閥領袖 野党党首
【70】衆議院議員 参議院議員 副大臣 都道府県知事 地域政党党首 内閣法制局長官 内閣官房副長官 金融庁長官 警察庁長官 会計検査院長 公正取引委員会委員長 国家安全保障局長 国家公務員倫理審査会長
国政の要職や独立行政機関トップ級、主要省庁の長官級などが多い層です。
法律・経済・外交の高度専門性に加え、調整力と危機管理能力が重視されます。
議員系は選挙での当選と党内での実績が不可欠で、官僚系は国家総合職でのトップクラスの成績と多様なポストローテーション経験が有利です。
対策として、政策論文・ディベート訓練、語学力強化、官庁訪問での高評価獲得、実績の可視化が求められます。
【公務員業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ公務員の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】省庁長官 大臣政務官 警視総監 自衛隊(統合幕僚長) 内閣情報通信政策監 宮内庁(侍従長) 原子力規制委員会委員長 外務省(特命全権大使)
【68】財務省(官僚) 外務省(官僚) 裁判官 検察官 自衛隊(将官) 海上保安監 国立大学職員(教授)
【67】経済産業省(官僚) 防衛省(官僚) 総務省(官僚)
【66】内閣府(官僚) 厚生労働省(官僚) 金融庁(官僚) 警察庁(官僚) 教育委員長 国会議員政策担当秘書
高位官僚や法曹、自衛隊将官、警察トップ、特命大使など専門性と統率力を兼ね備えた職が多い層です。
国家総合職の上位通過や司法試験合格、幹部候補としてのキャリア形成が鍵となります。
対策は、専門記述・政策立案演習、ケース面接、英語・第2外国語、国内外留学や出向での実績づくりです。
法曹はロー・司法試験対策、制服組は幹部学校・任官後評価での抜擢が重要です。
【公務員業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】国土交通省(官僚) 農林水産省(官僚) 文部科学省(官僚) 法務省(官僚) 公安調査庁(官僚) 外務省(専門職員) 衆議院事務局職員 参議院事務局職員
【64】環境省(官僚) デジタル庁(官僚) 宮内庁(官僚) 海上保安庁(官僚) 消防庁(官僚) 裁判所事務菅(総合職) 自衛隊(佐官) 国公立学校(校長) 教育委員 警察(警視長) 自衛隊(医官) 航空自衛隊(パイロット)
【63】地方上級職員(東京) 国公立学校(教頭) 皇宮護衛官 国立国会図書館職員(総合職) 議員速記者(廃止) 警視庁(特別捜査官)
【62】地方上級職員(大阪) 復興庁(官僚) 特許審査官 国税専門官 財務専門官 労働基準監督官 防衛省専門職員 防衛大学校(職員) 防衛医科大学校(職員)
【61】地方上級職員(北海道・名古屋・神奈川・福岡) 家庭裁判所調査官 航空管制官 警察(警部) 消防吏(消防司令)
中央省庁の本省・外局や国会機関、専門官職、都市部の地方上級など幅広い専門分野が集まる層です。
国家総合職・一般職や各種専門職試験の対策と、面接・官庁訪問での適性示しが重要です。
論文・数的処理・法律経済の基礎固め、業務研究、OBOG訪問で志望動機の具体性を高めることが効果的です。
語学やITリテラシー、統計・会計などの実務スキルの加点も合否を左右します。
【公務員業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】地方上級職員(政令指定都市) 警察官(警部補) 消防吏(消防司令補) 自衛隊(尉官) 公務員薬剤師 麻薬取締官
【59】地方上級職員(中核市) 国公立学校(教師) 消防吏(消防士長) 法務技官(心理) 食品衛生監視員 海上自衛隊(特殊警備隊) 陸上自衛隊(特殊作戦群・第一空挺団)
【58】地方上級職員(その他の市町村) 海上自衛隊(サブマリーナ) 検察事務官 公務員看護婦
【57】消防吏(消防士長) 警察(巡査部長) 航空自衛隊(曹士) 海上自衛隊(曹士) 警察(巡査長) 法務教官 入国警備官 公務員保健師
【56】陸上自衛隊(曹士) 警察(巡査) 消防吏(消防士) 海上保安士 公務員保育士 学校事務公務員 国公立学校(非常勤講師) 学校用務員 学校給食調理員
地方自治体の中核人材や現場の治安・防災・医療福祉を担う職種が中心です。
教養試験・専門試験に加えて体力試験や適性検査、集団面接の比重が高いのが特徴です。
数的処理・文章理解・時事対策を早期に固め、体力づくりと面接訓練を並行するのが効果的です。
地域課題の理解と住民対応力を示す具体的エピソードの準備が合格を左右します。
【公務員業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】防衛大学校(学生) 海上保安大学校(学生) 航空保安大学校(学生) 海上保安学校(学生) 陸上自衛隊高等工科学校(学生)
各分野の幹部候補生や専門人材を養成する学生採用枠が中心です。
学科試験・面接に加え、身体検査や適性検査の基準を満たすことが必須です。
数学・理科・英語など基礎学力の強化と、志望動機の一貫性、学校独自の課題対策を行います。
早期の体力づくりと人物面の評価を意識した指導歴・部活動等の実績整理が有効です。
【公務員】とは
公務員は国や地方公共団体に勤務し、社会基盤を支える重要な役割を担う職業です。
その安定性から就職先として非常に高い人気を誇ります。
この記事では、公務員の就職偏差値ともいわれる難易度や、その仕事の具体的な特徴、内定を得るためのポイントまで詳しく解説していきます。
就活で人気が高い理由
公務員が就職活動で高い人気を集める最大の理由は、その圧倒的な安定性にあります。
民間企業とは異なり、景気の動向によって経営が大きく左右されることがなく、リストラなどの心配もほとんどありません。
給与や退職金、年金制度も法律や条例で定められており、長期的な人生設計を立てやすい点は大きな魅力です。
また、社会貢献性の高さも人気の要因といえるでしょう。
利益追求を目的とせず、国民や地域住民の生活をより良くするために働くことに、大きなやりがいを感じる人は少なくありません。
さらに、福利厚生が充実しており、育児休業などの制度が利用しやすいことから、ワークライフバランスを重視する学生からも注目されています。
このような魅力から、公務員の人気は常に高く、その難易度を示す一つの指標として就職偏差値という言葉が使われるのです。
国家公務員と地方公務員の違い
公務員は大きく国家公務員と地方公務員の二つに分けられ、その役割や働き方は大きく異なります。
国家公務員は、中央省庁やその出先機関に勤務し、国全体の運営に関わるスケールの大きな仕事を担当します。
国の政策立案や法律の制定、国家プロジェクトの推進など、日本の未来を形作る重要な役割を担います。
勤務地は全国規模となり、数年ごとの転勤があるのが一般的です。
一方、地方公務員は都道府県庁や市町村役場などで働き、その地域の住民に密着した行政サービスを提供します。
教育、福祉、まちづくりといった、人々の暮らしに直結する分野で活躍します。
勤務地は基本的に採用された自治体内となり、地域に根差して長期的に貢献できるのが特徴です。
どちらを目指すかは、どのような規模で、誰のために働きたいかという自身の価値観によって選択することが重要です。
公務員の就職偏差値が意味すること
就職活動において、企業の入社難易度を示す指標として就職偏差値が使われることがあります。
しかし、公務員の場合、採用は学力や人物を測る試験の結果によって公平に決定されるため、民間企業のような明確な偏差値は存在しません。
それでも公務員の就職偏差値という言葉が使われるのは、試験の倍率や合格に必要な学力レベルから、その難易度を便宜的に表現するためです。
例えば、最難関とされる国家公務員総合職や、倍率の高い人気自治体は、就職偏差値が高いと表現されることがあります。
ただし、この指標はあくまで一般的な目安に過ぎません。
大切なのは、偏差値の数字に一喜一憂するのではなく、自分が志望する試験種の倍率や試験内容、求められる能力を正確に把握することです。
参考情報として捉え、自分に合った職種を見極めるための判断材料の一つとしましょう。
【公務員】特徴
公務員の仕事は、その安定したイメージが先行しがちですが、他にも多くの特徴があります。
民間企業とは異なる給与体系やキャリア形成、そして働き方の実態は、就職先を考える上で非常に重要なポイントです。
ここでは、給与やキャリア、働き方といった具体的な側面に焦点を当て、公務員という職業の魅力と実態を深掘りします。
給与や福利厚生の安定性
公務員の最大の魅力の一つは、給与や福利厚生が手厚く安定している点です。
給与は俸給表という法律や条例に基づいた体系で定められており、民間企業のように業績によって大きく変動することがありません。
勤続年数に応じて着実に昇給していくため、将来の収入を見通しやすく、安定した生活設計が可能です。
また、期末手当や勤勉手当といった、民間企業のボーナスにあたる手当もしっかりと支給されます。
さらに、住居手当、通勤手当、扶養手当などの各種手当も充実しています。
休暇制度も整備されており、年次有給休暇の取得が奨励されているほか、夏季休暇や結婚休暇などの特別休暇も用意されています。
こうした経済的な安定と手厚い福利厚生は、安心して長く働き続けるための大きな支えとなるでしょう。
キャリアパスと昇進の仕組み
公務員のキャリアパスは、長期的な視点で人材を育成する仕組みが整っています。
多くの場合、年功序列を基本とした昇進制度が採用されており、勤続年数や経験を重ねることで着実にステップアップしていくことが可能です。
採用後は、新規採用職員研修をはじめ、各階層に応じた様々な研修が用意されており、業務に必要な知識やスキルを継続的に学ぶことができます。
特に、国家公務員や大規模な自治体では、数年ごとに部署を異動するジョブローテーション制度が一般的です。
これにより、多様な業務を経験し、幅広い視野と行政官としての総合的な能力を養うことができます。
特定の分野の専門性を深めるというよりは、様々な経験を通じて組織全体に貢献できるゼネラリストとしての成長が期待されるキャリアパスといえるでしょう。
ワークライフバランスの取りやすさ
公務員は、ワークライフバランスを実現しやすい職業として知られています。
勤務時間は原則として1日7時間45分と定められており、土日祝日は休日となるため、カレンダー通りの生活を送りやすいのが特徴です。
年次有給休暇も比較的取得しやすく、計画的にプライベートの時間を確保することが可能です。
また、育児休業や介護休業といった制度も法律で保障されており、特に近年は男性の育児休業取得も推進されるなど、家庭と仕事の両立を支援する環境が整いつつあります。
ただし、部署や時期によっては繁忙期があり、予算編成期や議会対応の時期などは残業が多くなることも事実です。
また、災害発生時などには緊急で出勤を求められることもあり、国民や住民の安全を守るという責任の重さも理解しておく必要があります。
【公務員】向いている人
安定性や社会貢献性など、多くの魅力を持つ公務員ですが、その働き方は誰にでも向いているわけではありません。
民間企業とは異なる組織文化や仕事の進め方があるため、自身の性格や価値観との相性を見極めることが大切です。
ここでは、公務員という働き方に特に適性がある人の特徴を3つの観点から解説し、自己分析の参考にしていただければと思います。
安定志向で長期的に働きたい人
将来の経済的な見通しを立て、一つの組織で腰を据えて長く働きたいと考えている人にとって、公務員は非常に魅力的な選択肢です。
民間企業のように会社の業績や景気の波に給与が左右されることがなく、解雇のリスクも極めて低いため、安心してキャリアを積み重ねることができます。
年功序列で着実に給与が上がっていく仕組みは、成果主義の厳しい競争環境よりも、安定した環境でじっくりと成長したい人に適しています。
住宅の購入や子育てといった長期的なライフプランを具体的に描き、安定した基盤の上で人生を歩んでいきたいという価値観を持つ人にとって、公務員の雇用環境は大きな安心材料となるでしょう。
刺激よりも堅実さを、短期的な成果よりも長期的な安定を求める人に向いている職業です。
社会や地域に貢献したい人
公務員の仕事の根幹には、営利を目的とせず、社会全体や地域住民のために奉仕するという精神があります。
そのため、自分の仕事を通じて誰かの役に立ちたい、社会をより良くしたいという強い思いを持つ人にとって、これ以上ないやりがいを感じられる職業です。
例えば、道路や公園といったインフラを整備したり、福祉サービスを必要とする人を支援したり、地域の安全を守ったりと、その業務は人々の生活に直結しています。
自分の働きが、目に見える形で社会の基盤を支えているという実感は、大きなモチベーションとなるでしょう。
目先の利益や個人の成果ではなく、公共の利益という大きな目標に向かって、地道に貢献していくことに喜びを感じられる人こそ、公務員としての資質があるといえます。
勉強や準備をコツコツ続けられる人
公務員になるためには、避けては通れないのが公務員試験です。
この試験は、法律、経済、政治、数的処理など非常に幅広い科目から出題されるため、合格には長期間にわたる計画的な学習が不可欠となります。
一夜漬けの知識では到底太刀打ちできず、毎日少しずつでも机に向かい、知識を積み重ねていく地道な努力が求められます。
このような継続的な努力を苦とせず、目標に向かってコツコツと準備を進められる人は、公務員試験を突破できる可能性が高いでしょう。
また、その姿勢は公務員になってからも重要です。
法律や制度は常に変化していくため、新しい知識を学び続ける探求心や、複雑な課題に対して粘り強く取り組む真面目さが求められるからです。
地道な努力を続けられる誠実な人柄は、公務員にとって重要な資質の一つです。
【公務員】内定をもらうためのポイント
憧れの公務員になるためには、計画的な準備と戦略が不可欠です。
特に、長丁場となる公務員試験を乗り越え、面接で自分の適性や熱意を効果的にアピールする力が求められます。
ライバルも多い中で内定を勝ち取るためには、他の受験生と差をつける工夫が必要です。
ここでは、公務員の内定を勝ち取るための具体的なポイントを解説します。
公務員試験対策のスケジュール管理
公務員試験の合否は、いかに計画的に学習を進められたかで決まるといっても過言ではありません。
出題範囲が膨大であるため、試験日から逆算して長期的な学習計画を立てることが最初のステップです。
一般的には、1年以上の準備期間を見込むのが理想的とされています。
まずは、数的処理や憲法、民法、経済原論といった、配点が高く理解に時間がかかる主要科目から着手しましょう。
そして、学習の進捗に合わせて、知識の定着度を測るために定期的に過去問や模擬試験を解くことが重要です。
これにより、自分の苦手分野を客観的に把握し、計画を修正していくことができます。
独学での管理が難しい場合は、予備校や通信講座を活用し、効率的に学習を進めるのも有効な手段です。
徹底したスケジュール管理こそが、合格への一番の近道となります。
面接でアピールすべき強み
近年、筆記試験の成績だけでなく、面接での人物評価を重視する自治体や省庁が増えています。
公務員の面接では、誠実さや真面目さといった基本的な人柄に加えて、組織の一員として貢献できる能力をアピールすることが重要です。
特に、多様な住民や関係者と円滑に業務を進めるためのコミュニケーション能力や協調性は不可欠です。
また、前例のない課題にも対応できるような課題解決能力も高く評価されます。
そして何よりも大切なのは、なぜ民間企業ではなく公務員なのか、そしてなぜこの自治体や省庁で働きたいのかという、一貫性のある明確な志望動機です。
事前にその組織の政策や課題を徹底的に研究し、自身の経験や強みをどう活かせるのかを具体的に語れるように準備しておくことが、他の受験生との差別化につながります。
民間との併願戦略
公務員が第一志望であっても、民間企業と併願することは多くのメリットがあります。
公務員試験は最終的な合否が判明するまでに時間がかかるため、併願は就職先が決まらないというリスクを回避するための有効な手段です。
また、民間企業の選考プロセスに参加することで、自己分析を深めたり、グループディスカッションや面接の場に慣れたりすることができます。
これは、公務員試験の人物試験においても大いに役立つ経験となるでしょう。
ただし、両立させるためには綿密なスケジュール管理が必須です。
民間企業の就職活動に時間を取られすぎて、公務員試験の勉強が疎かになってしまっては本末転倒です。
あくまで公務員試験対策を軸に据え、民間企業の選考は面接の練習の場と捉えるなど、自分の中で明確な優先順位をつけて取り組むことが成功の鍵です。
【公務員】よくある質問
公務員を目指すにあたり、多くの方が様々な疑問や不安を抱えています。
試験の実際の難易度や、自分の学歴や専攻が有利に働くのかどうかなど、気になる点は多いでしょう。
インターネット上には様々な情報が溢れていますが、正確な情報を得ることが重要です。
ここでは、就職活動生から寄せられることの多い質問に分かりやすくお答えします。
公務員試験はどれくらい難しい?
公務員試験の難易度は、一言で表すことはできず、受験する試験の種類によって天と地ほどの差があります。
最難関として知られるのは、将来の幹部候補となる国家公務員総合職で、合格には非常に高い学力が要求されます。
これに次いで、国家公務員一般職や地方上級(都道府県、政令指定都市)などが続きます。
市役所や町村役場などの試験は、これらに比べると難易度はやや下がりますが、人気のある自治体では倍率が数十倍に達することも珍しくなく、決して簡単ではありません。
難易度を測る指標としては、筆記試験のボーダーラインの高さと採用倍率が参考になります。
自分がどのレベルの試験に挑戦するのか、合格にはどれくらいの学習が必要なのかを正確に把握し、戦略を立てることが重要です。
文系・理系で有利不利はある?
公務員試験において、文系と理系のどちらが一方的に有利ということはありません。
一般的にイメージされる行政職(事務職)では、法律や経済、政治学といった科目が多く出題されるため、法学部や経済学部の学生が受験しやすい傾向はあります。
しかし、教養試験では数的処理や自然科学といった理系的な思考力が問われる科目も出題されるため、文系学生が圧倒的に有利というわけではありません。
一方、理系の学生には、土木、建築、化学、農業、情報といった、自身の専門知識を直接活かせる技術職という選択肢が豊富にあります。
これらの技術職は、行政職に比べて採用倍率が低い場合もあり、専門性を活かしたい学生にとっては有利な選択となり得ます。
結論として、自分の専攻や得意分野に合った職種を選べば、文系・理系による有利不利はほとんどないといえるでしょう。
大学院進学後でも受験できる?
大学院を修了してから公務員試験を受験することは全く問題ありません。
多くの公務員試験では、年齢要件の上限が30歳前後(一部の試験ではそれ以上)に設定されているため、大学院修了後でも十分に受験資格があります。
むしろ、大学院での研究活動を通じて培われた高度な専門知識や、論文執筆で養われた論理的思考力、分析能力は、公務員として働く上で大きな強みとなります。
面接試験においても、研究内容について深く掘り下げて質問されることがあり、そこで自身の能力を効果的にアピールできれば、他の受験生との差別化を図ることが可能です。
国家公務員総合職では、院卒者試験という区分が設けられており、学部卒とは別の土俵で選考が行われるため、大学院での学びを直接評価してもらえる機会もあります。
まとめ
公務員は、その安定性や社会貢献性の高さから、就職先として常に高い人気を誇る職業です。
就職偏差値という言葉でその難易度が語られることもありますが、それはあくまで一つの目安に過ぎません。
大切なのは、国家公務員や地方公務員といった職種の違いや、それぞれの試験の難易度を正しく理解し、自分の適性や価値観に合った選択をすることです。
公務員の内定を勝ち取るためには、長期的な視点に立った計画的な試験対策と、面接で自身の強みや熱意を的確に伝える準備が不可欠です。
この記事で解説したポイントを参考に、ぜひご自身のキャリアについて深く考え、後悔のない選択をしてください。