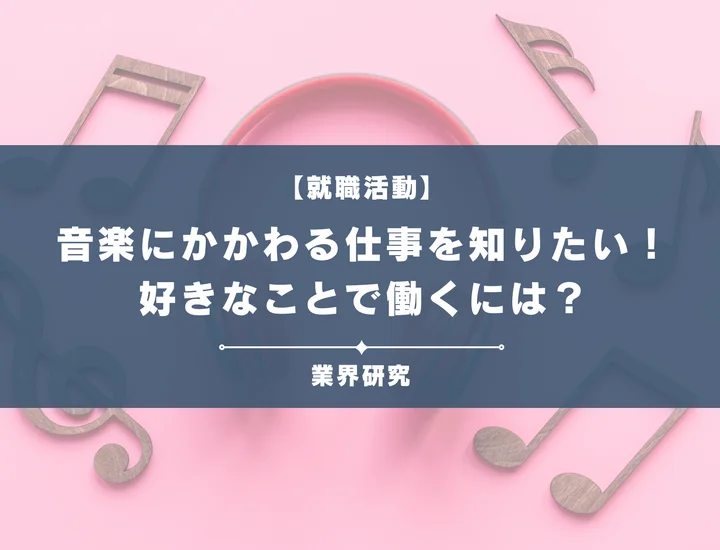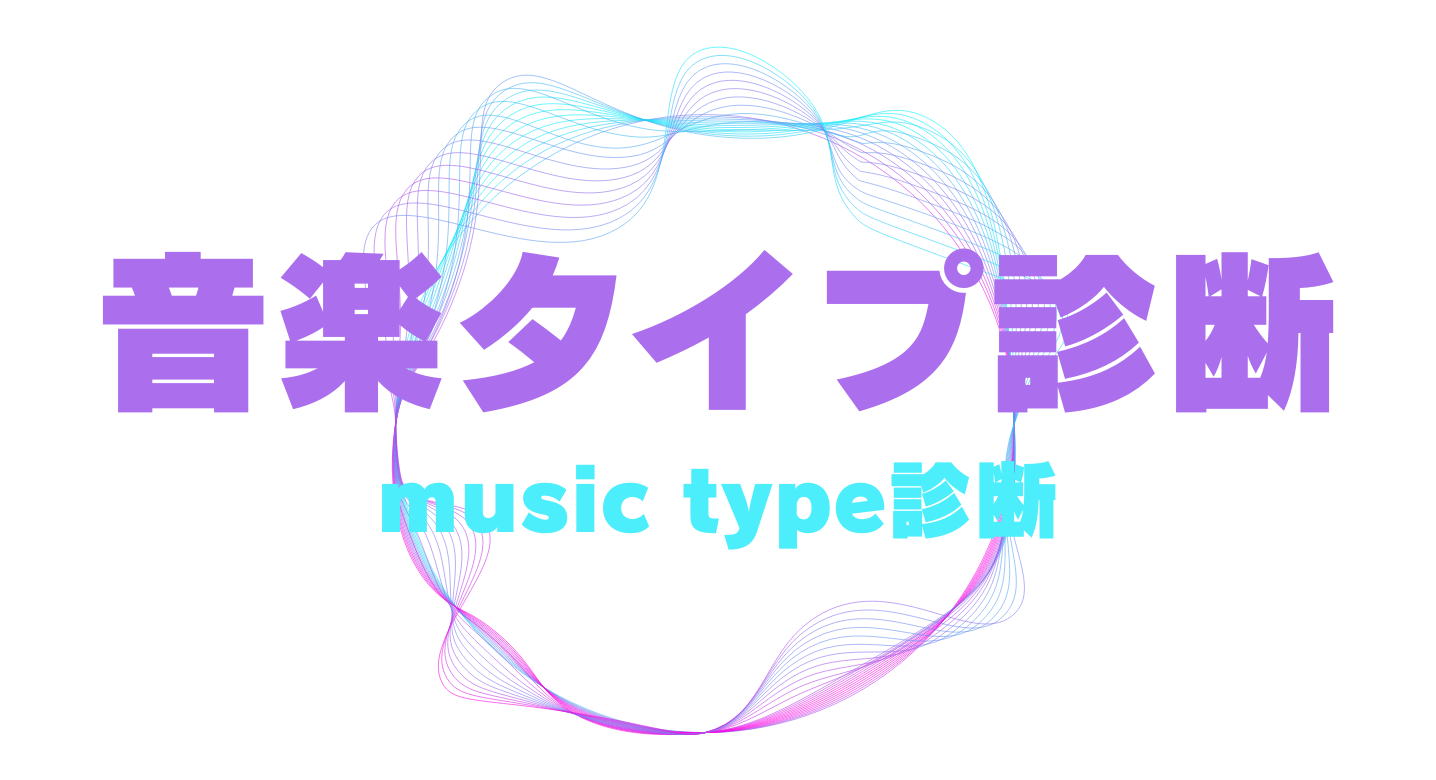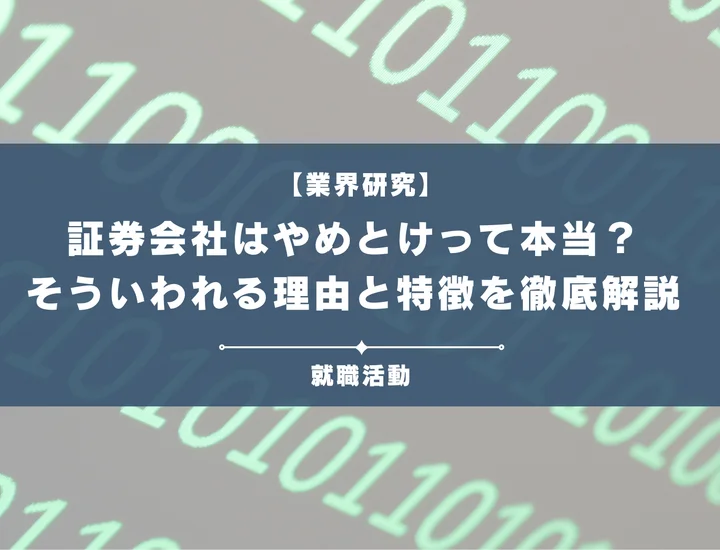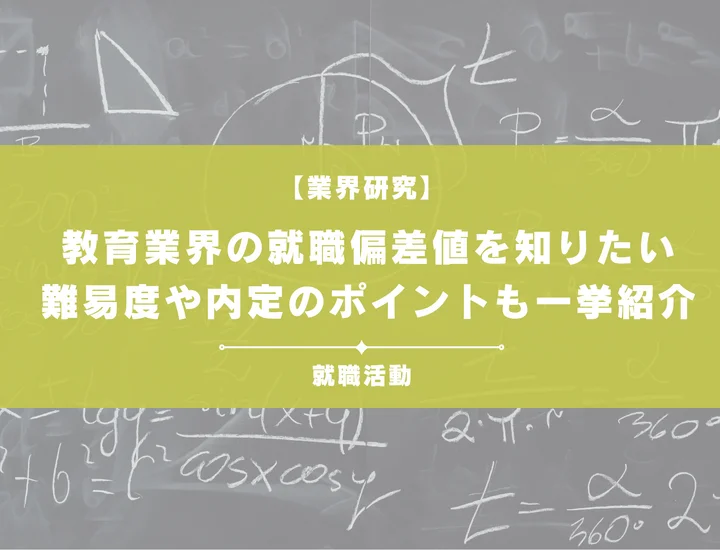HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
NEW!! あなたのタイプがわかる「音楽タイプ診断」
「どんな音楽が自分に合うんだろう?」「自分の性格に合うジャンルは?」そう思って、新しい音楽を探すのにモヤモヤしていませんか?
そんなあなたに、あなたの音楽タイプがわかる「音楽タイプ診断」をご用意しました。
ロック?ポップス?クラシック?
あなたの音楽タイプ・おすすめジャンル・聴き方まで、診断結果でまるっと可視化!
「なんとなく音楽を聴いている」で止まっているなら、今こそ新しい発見のチャンス。
気分転換にも使える、完全無料の診断ツールです。
今すぐ診断して、自分に合う音楽スタイルと、相性の良いジャンル・アーティストを見つけよう!
はじめに
音楽が好きで、それを仕事にしたいと考える人は少なくありません。
音楽にかかわる仕事と聞くと、アーティストやバンドマンなど表舞台で活躍する姿を思い浮かべるかもしれませんが、実際にはその活動を支える多種多様な職業が存在します。
音楽を創り出し、多くの人へ届け、感動を生み出す過程には、数えきれないほどのプロフェッショナルが関わっています。
この記事では、音楽にかかわる仕事の全体像や種類、業界の現状、そして就職を目指すためのポイントまで、幅広く解説していきます。
音楽にかかわる仕事とは?
音楽にかかわる仕事とは、単に演奏したり歌ったりするだけでなく、楽曲の制作からプロモーション、ライブの運営、権利の管理まで、音楽という文化とビジネスを成り立たせる全ての業務を指します。
そこには、クリエイティブな才能が求められる仕事もあれば、ビジネススキルや交渉力が重要になる仕事もあります。
音楽業界は、こうした様々な専門性を持つ人々が協力し合うことで、一つの大きなエコシステムを形成しているのです。
この記事を読み進めることで、あなたが持つスキルや情熱を活かせる仕事がきっと見つかるでしょう。
音楽業界で働くとはどういうことか
音楽業界で働くということは、音楽という文化を創造し、ビジネスとして成立させるプロセスの一端を担うことです。
多くの人が想像する華やかなイメージだけでなく、その裏側には地道な作業や複雑な権利関係、シビアなビジネス戦略が存在します。
例えば、レコード会社、芸能プロダクション、音楽出版社、コンサートプロモーターなど、それぞれが異なる役割を担い、連携しながらアーティストの活動を支えています。
音楽への情熱はもちろん不可欠ですが、同時に社会人としてのコミュニケーション能力や論理的思考力、市場を分析するマーケティングの視点も強く求められます。
音楽を愛する気持ちを、多くの人々に価値として届けるための仕組みを理解し、その中で自分の役割を果たしていく。
それが音楽業界で働くということの本質といえるでしょう。
華やかさと裏方の両面性
音楽にかかわる仕事には、スポットライトを浴びる華やかな側面と、それを陰で支える裏方の側面があります。
多くの人が目にするのは、ステージで輝くアーティストや、ヒットチャートを賑わす楽曲でしょう。
しかし、その成功の裏には、膨大な数の裏方スタッフの存在が欠かせません。
例えば、一つのライブを開催するためには、企画を立てるプロモーター、会場を手配し交渉する制作担当、機材を運びセッティングする技術スタッフ、アーティストの身の回りの世話をするマネージャーなど、様々な役割のプロフェッショナルが動いています。
彼らの地道で緻密な仕事があるからこそ、アーティストは最高のパフォーマンスを発揮でき、観客は心から音楽を楽しむことができるのです。
自分が表に出るのではなく、音楽やアーティストを支えることに喜びを感じられる人にとって、裏方の仕事は大きなやりがいのある世界です。
就活生が知っておきたい業界の現状
現在の音楽業界は、大きな変革期にあります。
かつてはCD販売が収益の柱でしたが、インターネットの普及により、サブスクリプション型のストリーミングサービスが主流となりました。
これにより、音楽の聴かれ方やヒットの生まれ方が大きく変化しています。
SNSでのバイラルヒットや、動画プラットフォームとの連携が重要になり、デジタルマーケティングの知識やデータ分析のスキルがこれまで以上に求められるようになりました。
また、CDの売上が減少した一方で、ライブや音楽フェスの市場は拡大しており、そこで生まれる感動や体験価値が重視されています。
さらに、国内市場だけでなく、海外展開を視野に入れたグローバルな戦略も不可欠です。
就活生は、こうした業界構造の変化を理解し、新しい時代の音楽ビジネスにどう貢献できるかを考える視点を持つことが重要になります。
音楽にかかわる仕事の種類
音楽にかかわる仕事は、その役割によっていくつかのカテゴリーに分類できます。
自分の興味やスキルがどの分野で活かせるのかを知るために、まずは全体像を把握しましょう。
例えば、楽曲そのものを生み出す制作系の仕事、アーティストの活動を導くマネジメント系の仕事、音楽を世の中に広める企画・マーケティング系の仕事、そして音楽を届けるためのプラットフォームを担う仕事や、ライブという感動の場を創り上げる仕事など、その内容は実に多岐にわたります。
ここでは、それぞれの仕事内容について詳しく見ていきます。
制作系の仕事(作曲家・編曲家・レコーディングエンジニアなど)
制作系の仕事は、音楽という作品そのものをゼロから創り上げる、クリエイティブな役割を担います。
代表的な職種には、メロディを生み出す作曲家、楽曲に彩りを加える編曲家、歌詞を紡ぐ作詞家などがいます。
彼らはアーティスト本人である場合もあれば、専門の作家として楽曲提供を行う場合もあります。
また、生演奏や打ち込みで音を創るサウンドクリエイター、アーティストの演奏や歌を録音し、音質を調整するレコーディングエンジニア、そして最終的な音源のクオリティを仕上げるマスタリングエンジニアもこの分野に含まれます。
これらの仕事に就くには、音楽理論の知識や楽器の演奏スキルはもちろん、DAW(音楽制作ソフト)を扱う高度な技術が求められます。
アーティストのイメージや想いを汲み取り、最高の形で音源に落とし込む、音楽制作の根幹を支える重要な仕事です。
マネジメント・プロデュース系の仕事
マネジメント・プロデュース系の仕事は、アーティストの才能を見出し、その活動全体を戦略的にサポートし、成功へと導く役割を担います。
アーティストマネージャーは、最も身近な存在としてスケジュール管理、メディア対応、ライブへの帯同など、公私にわたるサポートを行います。
アーティストが音楽活動に集中できる環境を整える、重要なパートナーです。
A&R(アーティスト・アンド・レパートリー)は、新しい才能の発掘や契約、そしてアーティストに合った楽曲の選定や制作の進行管理を担当します。
ヒットを生み出すための、いわば制作現場の司令塔です。
そして音楽プロデューサーは、楽曲のコンセプト決定から、作家やエンジニアの選定、予算管理まで、音楽制作の全責任を負う総監督的な存在です。
これらの仕事には、アーティストとの信頼関係を築くコミュニケーション能力や、業界内外の関係者と渡り合う交渉力が不可欠です。
企画・マーケティング系の仕事
企画・マーケティング系の仕事は、完成した音楽をいかにして多くの人々に届け、ビジネスとして成功させるかを考える役割を担います。
宣伝プロモーターは、テレビ、ラジオ、雑誌、Webメディアなどに対してアーティストの情報を発信し、露出の機会を創出します。
メディアの担当者との良好な関係構築が重要です。
販促(セールスプロモーション)担当は、CDショップやオンラインストアと連携し、特典の企画や店頭での展開を考え、販売促進活動を行います。
そして近年重要性が増しているのが、デジタルマーケティング担当です。
SNSでのキャンペーン企画、Web広告の運用、ストリーミングサービスの再生回数やリスナーの動向といったデータを分析し、効果的なプロモーション戦略を立案します。
市場のトレンドを敏感に察知する感性と、人々を惹きつける企画力、そしてデータに基づいた論理的な思考力が求められる仕事です。
配信・レーベル・メディア関連の仕事
音楽をリスナーの元へ届けるためのプラットフォームや媒体を運営するのが、この分野の仕事です。
レコード会社(レーベル)のディレクターは、A&Rと近い役割を持ちますが、より宣伝や制作進行管理に重点を置く場合が多いです。
また、音楽出版社では、楽曲の著作権を管理し、カラオケやCMなどで楽曲が使用される際の利用促進や許諾業務を行います。
近年では、音楽配信サービスの役割が非常に大きくなっています。
そこでは、新しい楽曲をユーザーに推薦するプレイリストの編成や、独自のコンテンツ企画、レーベルとの交渉などが行われます。
さらに、音楽雑誌の編集者やライター、ラジオ局のディレクターといった音楽メディアの仕事も、特定のアーティストやジャンルを深く掘り下げて紹介し、音楽文化の発展に貢献する重要な役割を担っています。
ライブ・イベント運営スタッフ
ライブや音楽フェスといった、音楽の感動を直接観客に届ける現場を創り上げるのが、ライブ・イベント運営スタッフの仕事です。
コンサートプロモーター(イベンター)は、ライブの企画立案から、アーティストのブッキング、会場の確保、チケットの販売戦略、プロモーションまで、イベント全体を統括します。
イベント制作会社のスタッフは、プロモーターの依頼を受け、予算管理や関係各所との調整など、より実務的な運営を担います。
当日の現場では、進行全体を管理する舞台監督、会場の音響を担当するPAエンジニア、音楽を光で演出する照明スタッフ、アーティストの楽器を管理するローディー(楽器テック)など、多くの技術専門職が活躍します。
多くのスタッフと円滑に連携するチームワークと、予期せぬトラブルに冷静に対応できる判断力、そして何よりもイベントを成功させるという強い責任感が求められます。
音楽にかかわる仕事の文系・理系別のキャリアパス
音楽にかかわる仕事は、専門的な知識を持つ人だけの世界ではありません。
文系、理系といった学問的背景を問わず、多様な人材が活躍できるフィールドが広がっています。
あなたが大学で培ってきた知識やスキルは、思いがけない形で音楽業界に貢献できる可能性があります。
ここでは、文系出身者、理系出身者それぞれにどのようなキャリアパスが開かれているのか、そして専門教育を受けた人たちとの違いは何かを解説します。
自分の強みをどのように活かせるか、具体的なキャリアを想像してみましょう。
文系出身者に多い職種
文系出身者は、大学で培ったコミュニケーション能力、文章構成力、論理的思考力、社会や文化に対する深い洞察力などを活かせる職種で多く活躍しています。
例えば、アーティストの魅力をメディアやファンに伝える宣伝・広報、新しい才能を発掘し、制作現場をまとめるA&R、アーティストの活動を全面的に支えるマネージャーなどは、高い対人スキルが求められるため文系出身者が多い傾向にあります。
また、法学部で学んだ知識は、楽曲の権利を守る音楽出版社の著作権管理部門で、商学部や経済学部での学びは、市場を分析し戦略を立てるマーケティング部門や、会社の経営を支える経理・財務部門で直接的に活かすことができます。
語学力を活かして、海外アーティストとの交渉や海外展開を担当する道も開かれています。
理系・情報系のスキルが活きる職種
音楽業界はテクノロジーの進化と密接に関わっており、理系・情報系のスキルを持つ人材の重要性がますます高まっています。
音響工学や情報工学の知識は、レコーディングエンジニアやPAエンジニア、マスタリングエンジニアといった音の専門家として直接的に活かせます。
これらの職種では、音の物理的な特性を理解し、最新の機材やソフトウェアを駆使する能力が不可欠です。
また、ストリーミングサービスが主流となった現在、膨大なリスナーの視聴データを分析してヒットの法則を探るデータアナリストや、より良い音楽体験を提供するアプリやWebサービスを開発するITエンジニアの需要も急増しています。
音楽制作ソフトウェアやシンセサイザーを開発する楽器メーカーなども、理系出身者にとって魅力的な職場です。
論理的思考力やデータ分析能力は、新しい音楽ビジネスを創造する上で強力な武器となります。
専門学校や音大出身者との違い
音楽大学や専門学校の出身者は、在学中に音楽理論や楽器演奏、レコーディング技術といった専門的かつ実践的なスキルを体系的に学んでいます。
そのため、特に制作系や技術系の職種において、即戦力として期待されることが多いのが特徴です。
一方、一般大学の出身者は、音楽以外の幅広い教養や、専門分野で培った論理的思考力、課題解決能力などが強みとなります。
音楽業界の企業も、多様な視点を持つ人材を求めており、出身大学だけで有利不利が決まるわけではありません。
大切なのは、自分自身のバックグラウンドを強みとして認識し、それを音楽業界でどのように活かせるのかを具体的に説明できることです。
専門知識は入社後でも学ぶ意欲があれば十分に身につけられます。
音楽への深い愛情を土台に、自分のユニークな視点をアピールすることが重要です。
音楽にかかわる仕事に向いている人の特徴
音楽が好きという気持ちは、この業界を目指す上での大前提ですが、それだけで長く活躍し続けるのは難しいかもしれません。
音楽にかかわる仕事には、共通して求められる資質や姿勢があります。
自分がこの業界で働くことに向いているのかどうか、客観的に見つめ直してみることは、就職活動を進める上で非常に重要です。
ここでは、音楽業界で特に求められる3つの人物像について解説します。
これからの自己分析の参考にしてみてください。
音楽を裏から支えることに喜びを感じられる人
音楽にかかわる仕事の多くは、アーティストのように表舞台に立つのではなく、彼らが輝くための環境を整える裏方の役割です。
自分が手がけた楽曲やイベントが成功し、多くの人々が感動している姿を見ること、そしてアーティストから感謝されることに、何よりも大きな喜びを感じられる人がこの仕事に向いています。
自分の名前が世に出ることよりも、チームの成功や作品のクオリティ向上に貢献することにやりがいを見出せる姿勢が大切です。
例えば、地道な事務作業や関係各所との細かい調整も、全ては最高の音楽を届けるための一部であると理解し、前向きに取り組めるかどうか。
縁の下の力持ちとして、音楽文化を支えることに誇りを持てる人こそ、この業界で必要とされる人材です。
チームで動くのが得意な人
一つの楽曲がリスナーに届くまで、あるいは一つのライブが成功するまでには、非常に多くの人々が関わっています。
作詞家、作曲家、エンジニア、A&R、マネージャー、プロモーター、デザイナー、ライブスタッフなど、異なる専門性を持つプロフェッショナルたちが一つのチームとして動きます。
そのため、自分の役割と責任をしっかりと果たしながら、常に周囲と連携し、情報を共有するチームワークが不可欠です。
自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見にも耳を傾け、全体の目標達成のために最善の方法を一緒に考える姿勢が求められます。
報告・連絡・相談を徹底し、円滑な人間関係を築けるコミュニケーション能力は、音楽業界で働く上で最も重要なスキルの一つといえるでしょう。
忍耐力や柔軟性を持っている人
音楽業界の仕事は、華やかなイメージとは裏腹に、非常に厳しくハードな側面も持っています。
楽曲のリリース前やライブの直前などは、昼夜を問わず作業が続くことも珍しくありません。
また、アーティストの急な要望や機材トラブル、予期せぬスケジュールの変更など、常に不測の事態に対応する柔軟性が求められます。
こうしたプレッシャーのかかる状況でも、冷静さを失わずに最善の解決策を見つけ出し、粘り強く物事を前に進める忍耐力が必要です。
理不尽だと感じることや、地道な下積み期間を経験することもあるかもしれません。
しかし、そうした困難な状況を乗り越え、一つの作品やイベントを成功させた時の達成感は計り知れません。
心身ともにタフで、変化を楽しめるくらいの柔軟性を持った人が、この業界で長く活躍できるでしょう。
音楽にかかわる仕事のメリットとデメリット
憧れの音楽業界で働くことは、多くの魅力がある一方で、厳しい現実も存在します。
就職活動においては、その両面を正しく理解し、自分にとって本当に価値のあるキャリアなのかを見極めることが重要です。
ここでは、音楽にかかわる仕事の代表的なメリットであるやりがいと、デメリットとして挙げられることの多い労働環境や安定性について、具体的に解説していきます。
客観的な視点を持つことで、より現実的で後悔のないキャリア選択ができるはずです。
やりがい・達成感を得られる
音楽にかかわる仕事の最大のメリットは、自分の仕事が音楽という形で世の中に残り、多くの人々に感動や喜びを届けられることです。
自分が関わった楽曲がヒットチャートを駆け上がったり、街中で流れたりした時の喜びは格別です。
また、手塩にかけて準備したライブで、満員の観客が熱狂している光景を目の当たりにした時の達成感は、何物にも代えがたいものがあります。
アーティストの成長を間近で支え、共に夢を追いかけるプロセスそのものに大きなやりがいを感じる人も多いでしょう。
音楽という、人々の心に深く影響を与える文化の創造に貢献しているという実感は、日々の仕事の大きなモチベーションになります。
好きなことを仕事にできるという純粋な喜びも、この仕事ならではの大きな魅力です。
忙しさや労働環境の厳しさ
一方で、デメリットとしてまず挙げられるのが、労働環境の厳しさです。
音楽業界の仕事は、基本的に労働時間が不規則で、長時間労働になりがちです。
特に、楽曲の締切前やライブツアー中、大規模なプロモーション期間中などは、休日返上で働くことも少なくありません。
夜間のレコーディングや早朝からの現場入りなど、生活リズムが不規則になることも覚悟しておく必要があります。
また、業界の慣習として、アシスタントや若手のうちは給与が低い傾向にあり、厳しい下積み期間を経験することも多いのが実情です。
華やかな世界の裏側で、強い精神力と体力が求められることは、入社前に理解しておくべき重要なポイントです。
収入やキャリアの安定性について
収入やキャリアの安定性に関しても、留意すべき点があります。
前述の通り、若手のうちは一般的な企業の同年代と比較して、給与水準が低いケースが見られます。
会社の規模や職種にもよりますが、いきなり高い収入を得るのは難しいかもしれません。
しかし、音楽業界は実力主義の世界でもあります。
ヒット作を生み出したり、重要なポジションで実績を積んだりすることで、年齢に関係なく大きな報酬を得るチャンスがあります。
キャリアの安定性については、業界のトレンドの変化が速いため、常に新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が不可欠です。
一つの会社に長く勤めるというよりは、実績を元にキャリアアップの転職をしたり、最終的には独立して自分の会社を立ち上げたりと、自分の力でキャリアを切り拓いていくという意識を持つことが重要になります。
音楽にかかわる仕事を目指す就活ポイント
音楽業界への就職は、人気が高く競争も激しいため、しっかりとした準備と戦略が必要です。
ただ漠然と音楽が好きというだけでは、数多くのライバルの中から選ばれるのは難しいでしょう。
ここでは、音楽にかかわる仕事を目指す就活生が押さえておくべき重要なポイントを3つに絞って解説します。
効果的な志望動機の作り方から、経験の活かし方、そして内定を勝ち取るための業界研究まで、具体的なアクションプランを示していきます。
志望動機の作り方(「音楽が好き」だけではNG)
採用担当者は、応募者が音楽好きであることは当然のこととして捉えています。
そのため、面接でただ音楽への愛情を語るだけでは、十分なアピールにはなりません。
重要なのは、好きという気持ちをもう一歩掘り下げ、なぜこの業界でなければならないのか、なぜ数ある音楽関連企業の中でその会社を志望するのか、そして入社後に自分の何を活かして貢献できるのかを具体的に伝えることです。
例えば、その企業が手がけた特定のアーティストのプロモーション戦略に感銘を受けたエピソードを交え、自分ならその手法をさらに発展させてこう貢献したい、といったように、情熱を具体的なビジネスプランに結びつけて語ることが求められます。
音楽への愛を、ビジネスへの意欲と貢献の意志として示すことが、効果的な志望動機作成の鍵です。
インターンやアルバイト経験の活かし方
音楽業界でのインターンシップや、ライブスタッフ、レコード店などのアルバイト経験は、就職活動において非常に強力な武器になります。
これらの経験を通じて、業界の仕組みや仕事の厳しさを肌で感じたという事実は、あなたの志望度の高さを証明する何よりの証拠です。
面接では、単に経験したという事実だけでなく、その経験から何を学び、どのような課題を見つけ、それに対してどう考え行動したのかを具体的に話せるように準備しておきましょう。
また、音楽業界と直接関係のないアルバイト経験であっても、例えば接客業で培ったコミュニケーション能力や、チームで目標を達成した経験などは、音楽業界で求められるチームワークや対人スキルとして十分にアピールできます。
どんな経験も、自分の強みと結びつけて語る工夫が大切です。
業界研究・企業研究の進め方
業界研究は、音楽業界が今どのような状況にあり、どこへ向かおうとしているのかという大きな流れを掴むために不可欠です。
音楽関連のニュースサイトや業界誌を定期的にチェックし、ストリーミング市場の動向、新しいテクノロジーの活用事例、ライブビジネスの現状など、最新の情報をインプットしましょう。
その上で、興味のある企業について深く掘り下げる企業研究に移ります。
公式サイトの企業理念や事業内容はもちろん、その企業に所属するアーティストや過去にリリースした作品、最近のプロモーション事例などを徹底的に調べ上げます。
なぜ競合のA社ではなく、このB社で働きたいのかを、具体的な事例を挙げて説明できるレベルまで理解を深めることが目標です。
可能であれば、OB・OG訪問などを活用し、現場で働く社員の生の声を聞くことも極めて有効な手段です。
よくある質問(Q&A形式)
音楽にかかわる仕事を目指すにあたり、多くの就活生が様々な疑問や不安を抱えていることでしょう。
ここでは、特に多く寄せられる質問をQ&A形式で取り上げ、具体的にお答えしていきます。
未経験からの挑戦は可能なのか、音楽の専門知識は必須なのか、そして将来どのようなキャリアを築けるのか。
こうした疑問を解消することで、より明確な目標を持って就職活動に臨むことができるはずです。
あなたの不安を少しでも和らげる手助けになれば幸いです。
未経験でも応募できる?
結論から言うと、多くの職種で未経験者の応募は可能です。
特にレコード会社や芸能プロダクションなどが実施する新卒の総合職採用では、入社時点での専門スキルよりも、ポテンシャルや人柄、そして音楽への情熱が重視される傾向にあります。
入社後の研修制度を通じて、必要な知識やスキルを身につけていくことが前提となっています。
ただし、レコーディングエンジニアやデザイナーといった専門技術職の場合は、学生時代からの経験やスキルが求められることがほとんどです。
未経験から応募する場合は、なぜ音楽業界で働きたいのかという明確なビジョンと、これまでの経験で培った自分の強みを、音楽の仕事にどう活かせるのかを論理的に説明できることが重要になります。
アルバイトなどで少しでも業界に触れておくと、熱意を伝える上で有利に働くでしょう。
音楽が専門じゃなくても大丈夫?
音楽大学や専門学校を卒業していなくても、全く問題ありません。
実際に音楽業界で活躍している人の多くは、一般大学の出身者です。
企業側も、音楽の専門知識を持つ人材だけでなく、ビジネスやマーケティング、法律、ITなど、多様なバックグラウンドを持つ人材を求めています。
重要なのは、専門的な知識の有無よりも、日常的にどれだけ深く、そして幅広く音楽に触れているかです。
特定のジャンルだけでなく、様々な音楽を聴き、その魅力やヒットの背景を自分なりに分析し、自分の言葉で語れることが大切になります。
面接では、好きなアーティストや最近気になった曲について質問されることも多いため、音楽に対する自分自身の視点や愛情をしっかりと伝えられるように準備しておきましょう。
将来のキャリアパスは?
音楽業界でのキャリアパスは非常に多様です。
例えば、レコード会社にA&Rとして入社し、経験を積んでヒット作を連発するプロデューサーになったり、レーベルの責任者になったりする道があります。
また、アーティストマネージャーとしてキャリアをスタートさせ、最終的には芸能プロダクションの経営に携わる役員になる人もいます。
宣伝やマーケティングの担当者としてスキルを磨き、業界内でより大きなプロジェクトを任されるポジションに転職していくケースも少なくありません。
近年では、音楽業界で培ったエンターテインメントビジネスのノウハウを活かして、IT企業や広告代理店など、異業種へ活躍の場を広げる人も増えています。
自分の実績とスキル次第で、様々なキャリアを切り拓いていけるのが、この業界の魅力の一つです。
まとめ
この記事では、音楽にかかわる仕事について、その種類から業界の現状、求められる人物像、そして就職活動のポイントまでを網羅的に解説しました。
音楽業界は、アーティストという光を支える無数の裏方のプロフェッショナルによって成り立っており、文系・理系を問わず、あなたの情熱とスキルを活かせる多様なフィールドが存在します。
その一方で、労働環境の厳しさや実力主義といったシビアな側面も持ち合わせています。
音楽にかかわる仕事を目指すには、好きという気持ちに加えて、業界を深く理解し、自分に何ができるのかを具体的に語るための徹底した準備が不可欠です。
この記事が、あなたの夢への第一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。