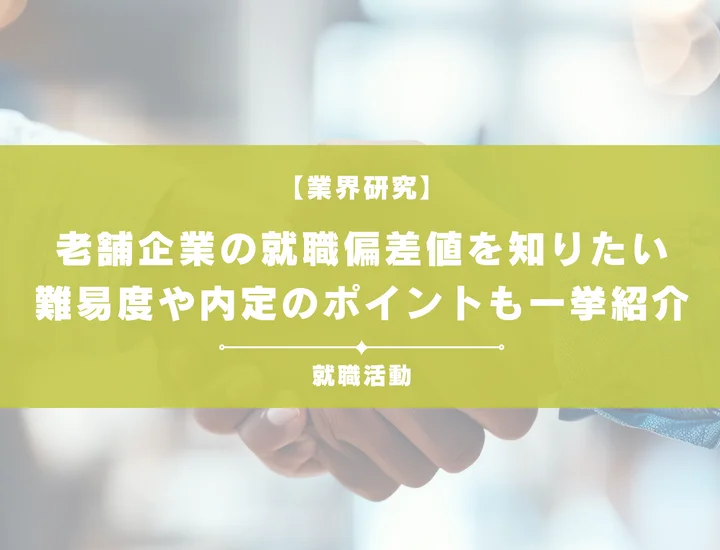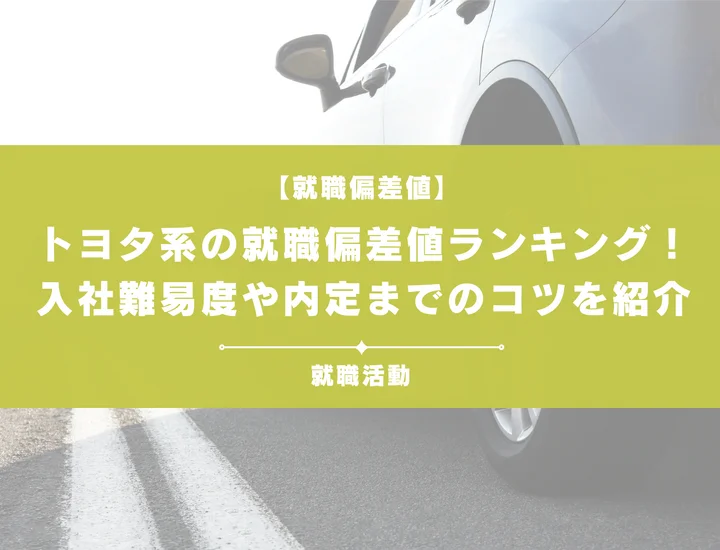HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業の入社難易度を相対的に示すために使われる指標のことです。
これは予備校などが算出する公式なデータではなく、主に就職活動生の間で、企業の人気度、採用倍率、採用実績(学歴)などを基に語られている俗語的なものです。
業界研究や企業選びにおいて、その業界内での立ち位置を知るための一つの目安として参考にすると良いでしょう。
老舗企業の就職偏差値ランキング
ここでは、老舗企業の就職偏差値ランキングを紹介します。
このランキングは、創業100年を超えるような長い歴史を持つ企業群、例えば大手デベロッパー、素材メーカー、食品会社などのうち、特に就活生からの人気が高く、安定性とブランド力を兼ね備えた企業の入社難易度を基に作成されたものです。
ただし、偏差値はあくまで目安の一つです。
このランキングを参考に、各社の歴史や社風を深く研究していきましょう。
【老舗企業】SSランク(就職偏差値78以上)
【80】金剛組(578) 池坊華道会(587)
【79】慶雲館(705) 古まん(717) 善吾楼(718) 五位堂工業(794)
【78】田中伊雅仏具店(885) 中村社寺(970)
SSランクは、創業1000年を超え、中には飛鳥時代から続く企業も含まれる、日本の歴史そのものと言える企業群です。
寺社建設、旅館、華道、仏具など、日本の伝統文化の維持・継承を事業の中核としています。
一般的な新卒一括採用を行っているケースは稀です。
入社には、宮大工などの専門技能の習得や、事業継承に対する極めて強い意志と覚悟が求められる場合が多いです。
【老舗企業】Sランク(就職偏差値75以上)
【77】一文字屋和輔(1000) 伊藤鉄工(1189) まるや八丁味噌(1337)
【76】佐久ホテル(1428) 虎屋(1526) 松井建設(1586) ナベヤ(1560) 住友金属鉱山(1590)
【75】養命酒製造(1602) 竹中工務店(1610) 松坂屋(1611) ヤマサ醤油(1645) キッコーマン(1661) 東急百貨店(1662) ユアサ商事(1666) 岡谷鋼機(1669) 三越(1673) 田辺三菱製薬(1678) 住友林業(1691)
Sランクは、室町時代や江戸時代初期に創業した、数百年単位の歴史を持つ超老舗企業群です。
和菓子(虎屋)、醤油(キッコーマン)、建設(竹中工務店)、鉱山(住友金属鉱山)など、日本の生活や産業に深く根ざした事業を展開しています。
高いブランド力と安定性を誇り、入社難易度は非常に高いです。
選考では、一般的な対策に加え、なぜこれほどの歴史を持つ自社なのか、その伝統と革新の歴史をどう理解しているかを問われます。
【老舗企業】Aランク(就職偏差値70以上)
Aランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Aランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ老舗企業の就職偏差値をチェックしましょう!
【74】銭高組(1705) 小野薬品工業(1717) タキヒヨー(1751) イオン(1758) 武田薬品工業(1781)
【73】清水建設(1804) 鈴与(1801) ミツカン(1804) そごう(1830) 高島屋(1831) 長瀬産業(1832) 鹿島(1840) IHI(1853) 浅草花やしき(1853) 伊藤忠商事(1858) 丸紅(1858) 蝶理(1861) 上組(1867) 伊勢丹(1886)
【72】キリン(1870) 三菱商事(1871) 資生堂(1872) 毎日新聞(1872) みずほFG(1873) 大成建設(1873) コニカミノルタ(1873) 読売新聞(1874) 東芝(1875) 島津製作所(1875) 古河機械金属(1875) サッポロビール(1876) 三井住友FG(1876) 三井物産(1876) 十六銀行(1877) 塩野義製薬(1878) 東京海上日動(1879)
【71】三菱UFJ銀行(1880) 沖電気工業(1881) 日本ペイント(1881) カナデビア(1881) セイコーグループ(1881) 太平洋セメント(1881) 明治安田生命(1881) 日本銀行(1882) 大林組(1982) 三菱重工(1884) 商船三井(1884) DOWA(1884) 南海電鉄(1884)フジクラ(1885) 田中貴金属工業(1885) 東京ガス(1885) 中日新聞(1886) 小林製薬(1886) 日産化学(1887) ヤマハ(1887) 花王(1887) 三菱鉛筆(1887) 帝国ホテル(1887) 三菱倉庫(1887) 損保ジャパン(1887) ENEOS(1888) 朝日生命(1888) 住友重機械工業(1888) カゴメ(1899) アサヒビール(1889) 東海汽船(1889) 任天堂(1889) 日本生命(1889)
【70】クボタ(1890) ライオン(1891) 日本郵船(1893) 名古屋鉄道(1894) 大日本印刷(1894) 博報堂(1895) アンリツ(1895) 松竹(1895) 川崎重工業(1896) 東京建物(1896) グンゼ(1896) 大阪ガス(1897) UBE(1897) 住友ファーマ(1897) 明電舎(1897) NEC(1899) サントリー(1899) 飯野海運(1899) 住友倉庫(1899) 第一三共(1899)
Aランクは、江戸時代後期から明治時代にかけて創業した企業群です。
三菱・三井・住友などの財閥系企業、大手ゼネコン、金融、インフラ、メーカーなど、日本の近代産業を牽引してきた基幹企業がほぼ全て含まれます。
現代の就職活動においても、これらは最難関企業群であり、極めて優秀な学生が競い合います。
入社には、トップクラスの学歴や能力に加え、大組織の一員として長期間貢献し続ける「誠実さ」や「組織適応力」が厳しく見られます。
【老舗企業】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】電通(1901) 今治造船(1901) 大和証券(1902) 品川リフラクトリーズ(1903) バンドー化学(1906) 阪急阪神HD(1907) 日本製鋼所(1907) ダイハツ工業(1907) AGC(1907) 日清紡(1907) 味の素(1909) 凸版印刷(1908) スズキ(1909)
【68】日立製作所(1910) 日産自動車(1910) 出光興産(1911) エーザイ(1911) シャープ(1912) 名村造船所(1911) 吉本興業(1912) ヤンマー(1912) イビデン(1912) ハウス食品(1913) トンボ鉛筆(1913) 住友化学(1913) 安川電機(1915) 小糸製作所(1915) いすゞ自動車(1916) カルピス(1916) SUBARU(1917) ニコン(1917) 横浜ゴム(1917) アイダエンジニアリング(1917) 日本板硝子(1918) パナソニック(1918) シチズン時計(1918) フマキラー(1918) 住友商事(1919) ヤマト運輸(1919) キューピー(1919) 川崎汽船(1919) オリンパス(1919)
【67】マツダ(1920) 小学館(1922) 豊田自動織機(1926) 三菱電機(1921) 中外製薬(1925) 東レ(1926) 野村證券(1925) 日揮(1928) コマツ(1921) 東邦ガス(1922) スタンレー電気(1920) 不二越(1928) 井関農機(1926) 岡三証券(1923) ダイキン(1924)
【66】ブリジストン(1931) 大阪メトロ(1933) 三井化学(1933) 富士フイルム(1934) 日本製鉄(1934) TDK(1935) 富士通(1935) 富士通ゼネラル(1935) 淀川製鋼所(1935) リコー(1936) トヨタ自動車(1937) キヤノン(1937) 三菱地所(1937) ディスコ(1937) 日本IBM(1937)
Bランクは、20世紀初頭(明治末期〜昭和初期)に創業した企業が中心です。
トヨタ、日産、パナソニック、日立といった日本を代表する大手メーカーや、三菱地所などのデベロッパーが含まれます。
Aランク同様、就職難易度は最難関です。
対策としては、筆記試験や複数回の面接を突破する基礎能力に加え、学生時代に高い成果を出した「ガクチカ」が不可欠です。
【老舗企業】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】ローム(1940) 三井不動産(1941) HOYA(1941) INPEX(1941) トーヨーカネツ(1941) エーザイ(1941) 東京メトロ(1941) 村田製作所(1944) 東洋エンジニアリング(1944)
【64】共同通信(1945) TOYOTIRE(1945) ソニー(1946) カシオ計算機(1946) コーセー(1946) シロキ工業(1946) 平和不動産(1947) 本田技研工業(1948) エステー(1948) 千代田化工建設(1948) ワコール(1949) アイシン精機(1949) デンソー(1949) アステラス製薬(1949) 住友不動産(1949) 新電元工業(1949)
【63】関西電力(1951) 中部電力(1951) 日本航空(1951) 電源開発(1952) コメリ(1952) 佐川急便(1953) 浜松ホトニクス(1953) 昭和真空(1953) JRA(1954) アドバンテスト(1954) 大和ハウス工業(1955) テレビ朝日(1957) フジテレビ(1957) 永谷園(1953) 石油資源開発(1955) ベネッセ(1955) 日本原子力発電(1957) セブンアンドアイ(1958) SMC(1959) 森ビル(1959) 京セラ(1959) レーザーテック(1959)
【62】積水ハウス(1960) サンリオ(1960) オリエンタルランド(1960) リクルート(1960) ユニチャーム(1961) すかいらーく(1962) セコム(1962) ファーストリテイリング(1963) アスクル(1963) 東京エレクトロン(1963) オリックス(1964) 未来工業(1965) 野村総合研究所(1965) ニトリ(1967) 王将フードサービス(1967) テレビ東京(1968) オービック(1968) SCSK(1969)
【62】ソフトバンク(1981) ワークマン(1982) 日本オラクル(1982) レイヤーズコンサルティング(1983) WOWOW(1984) 日本たばこ産業(1985) NTT(1985) スクウェア・エニックス(1986) JR東海(1987) JR東日本(1987) JR西日本(1987) エイベックス(1988) 光通信(1988) 東京ドーム(1988) カインズ(1989) ぐるなび(1989) 良品計画(1989)
【61】三菱総合研究所(1970) 森トラスト(1970) アイリスオーヤマ(1971) 日本マクドナルド(1971) ニデック(1973) サイゼリヤ(1973) リゾートトラスト(1973) マイナビ(1973) キーエンス(1974) ローソン(1975) セガサミー(1975) ファナック(1976) ビッグモーター(1976) くら寿司(1977) コーエーテクモ(1978)
【61】NTTドコモ(1991) ヤフー(1996) 楽天(1997) サイバーエージェント(1998) DeNA(1999) DMM(1999) Mixi(1999) ガンホー(1998) カカクコム(1997) ドワンゴ(1997) タマホーム(1998) 日本一ソフトウェア(1993) アビームコンサルティング(1993) オープンハウス(1997) クックパッド(1997) ZOZO(1998) ネクステージ(1998) ベイカレント(1998) NTT西日本(1999) NTT東日本(1999) NTTコミュニケーションズ(1999) 出前館(1999)
Cランクは、戦後の高度経済成長期から1990年代のIT革命期にかけて創業した企業が混在しています。
ソニー、ホンダなどの世界的なメーカーから、リクルート、キーエンス、楽天、サイバーエージェントなど、比較的新しいサービス・IT企業まで、非常に多岐にわたります。
対策としては、メーカー系は技術力や安定性、IT系はベンチャースピリットなど、企業の成り立ちや文化に合わせた自己PRが求められます。
【老舗企業】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】KDDI(2000) LINE(2000) KLab(2000) エムスリー(2000) ドリームインキュベータ(2000) MonotaRO(2000) ルネサスエレクトロニクス(2002) バルミューダ(2003) グリー(2004) M&Aキャピタルパートナーズ(2005) ワイヤレスゲート(2004) 日本郵政(2006) ゆうちょ銀行(2006) かんぽ生命(2006) ブシロード(2007) UQコミュニケーションズ(2007) ビズリーチ(2007) コロプラ(2008)
【59】Cygames(2011) ジモティー(2011) AppBank(2012) スマートニュース(2012) ジャパンディスプレイ(2012) UUUM(2013) メルカリ(2013) Casa(2013) サンバイオ(2013) オーシャンネットワークエクスプレス(2017) ANYCOLOR(2017) PayPay(2018) 楽天モバイル(2018)
Dランクは、2000年代以降に設立された、いわゆる「メガベンチャー」や新興IT企業が中心です。
「老舗企業」という括りとは対極にある、現代の成長企業群です。
これらの企業は変化のスピードが非常に速く、伝統や安定よりも「実力主義」や「イノベーション」を重視します。
対策として、学歴や既存のスキル以上に、自ら考え行動できる「自走力」や、新しいサービスへの好奇心、圧倒的な成長意欲が求められます。
【老舗企業】とは
老舗企業とは、創業から数十年、あるいは100年以上の長い期間にわたって事業を継続している企業を指します。
浮き沈みの激しい経済環境の中で、時代を超えて存続してきた実績は、それ自体が強力なブランドであり、就職活動においても安定志向の学生から根強い人気を集めています。
ここでは、老舗企業の基本的な概念について、3つの側面から詳しく解説していきます。
長年続く伝統ある企業
老舗企業の最も明確な定義は、その長い歴史と伝統です。
創業から50年、100年、中には数百年にわたって事業を営んできた企業も存在します。
これらの企業は、多くの経済危機や社会の変化を乗り越えてきた経験と、そこで培われた独自の技術、ノウハウ、そして企業文化を持っています。
例えば、特定の製法を守り続ける食品メーカーや、地域社会と共に発展してきたインフラ企業、代々受け継がれる技術を誇る素材メーカーなどです。
この長い歴史に裏打ちされた伝統は、一朝一夕では築けない強固な経営基盤の証であり、社員にとっても自社への誇り(プライド)の源泉となっています。
就職偏差値の高さは、こうした歴史的価値への評価も反映されていると言えます。
顧客や取引先との信頼関係が強い
老舗企業が長期間にわたり事業を継続できた最大の理由は、顧客や取引先との間に築かれた強固な信頼関係にあります。
短期的な利益を追求するのではなく、誠実な取引を地道に積み重ね、高品質な製品やサービスを提供し続けることで、あの会社なら間違いないという信用を勝ち得てきました。
この信頼は、目に見えない無形の資産であり、新規参入企業が容易に真似できない参入障壁ともなっています。
例えば、BtoB(企業間取引)が中心の素材メーカーや部品メーカーでは、この取引先との長期的な信頼関係こそがビジネスの根幹です。
こうした企業で働くことは、会社の看板(ブランド)が自分を守ってくれるという安心感につながる一方で、その看板を汚さない誠実な振る舞いが常に求められることも意味します。
地域密着型の企業も多い
老舗企業の中には、特定の地域に深く根ざし、その地域の発展と共に歩んできた企業も数多く存在します。
例えば、地方の有力な百貨店、地元のインフラを支えるガス会社や電力会社、あるいはその土地の銘菓を製造する菓子メーカーなどです。
これらの企業は、地域経済において重要な役割を果たし、地元住民からの信頼も厚いことが特徴です。
グローバルに事業を展開する企業とは異なり、ビジネスの規模は限られるかもしれませんが、その分、地域社会への貢献を肌で感じながら働くことができます。
また、転勤の範囲が限定的であるケースも多く、特定の地域で腰を据えて長く働きたいと考える学生にとって、非常に魅力的な選択肢となります。
こうした地域貢献性の高さも、老舗企業が選ばれる理由の一つです。
【老舗企業】特徴
老舗企業には、その長い歴史の中で培われてきた独特の文化や特徴があります。
これらは、就職偏差値ランキングで上位に来るような人気企業にも共通して見られるものであり、働く環境やキャリア形成にも大きな影響を与えます。
ここでは、老舗企業によく見られる3つの具体的な特徴について解説します。
安定した経営と落ち着いた社風
老舗企業の最大の特徴は、その安定した経営基盤にあります。
幾多の不況や環境変化を乗り越えてきた実績は、リスクに対する耐性が強いことの証です。
短期的な業績変動に一喜一憂せず、長期的な視点に立った堅実な経営が行われていることが多いです。
この経営の安定性は、社風にも反映されます。
流行を追いかけたり、過度な競争を煽ったりするよりも、和を重んじ、落ち着いた雰囲気の中で仕事に取り組む企業が多い傾向にあります。
ガツガツとした雰囲気よりも、協調性を大切にし、じっくりと物事に取り組みたいと考える人にとっては、非常に働きやすい環境と言えるでしょう。
この安心感が、就職偏差値の高さや根強い人気を支えています。
社員教育に力を入れている
老舗企業の多くは、社員を長期的な視点で育成する文化が根付いています。
これは、社員を短期的な労働力としてではなく、会社の伝統や技術を受け継ぐ大切な財産(人財)として捉えているためです。
新入社員研修にじっくりと時間をかけるのはもちろん、入社後もOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて、先輩社員がマンツーマンで丁寧に指導するメンター制度などが充実していることが多いです。
すぐに結果を出すことを急かさず、数年単位で一人前に育て上げようという風土があります。
また、その企業独自の技術や商習慣、あるいは企業理念(社是・社訓)を学ぶ機会も多く設けられており、会社への帰属意識を高めることにもつながっています。
変化に慎重な文化
長い歴史と伝統を持つがゆえに、新しいことへの挑戦や変化に対しては慎重な姿勢をとる文化があることも、老舗企業の特徴の一つです。
これは、過去の成功体験が強固であることや、築き上げてきた信頼やブランドを何よりも大切にするがゆえに、失敗のリスクを極度に恐れる傾向があるためです。
意思決定のプロセスが複雑で、稟議(りんぎ)や会議に時間がかかり、スピード感に欠けると感じることもあるかもしれません。
若手の革新的なアイデアが、すぐには受け入れられにくい側面もあります。
この安定性を重視する文化は、メリットであると同時に、変化の激しい現代においてはデメリット(リスク)ともなり得ると理解しておく必要があります。
【老舗企業】向いている人
老舗企業の持つ安定性や落ち着いた社風は、多くの学生にとって魅力的ですが、その独特な文化がすべての人に合うわけではありません。
高い就職偏差値に惹かれて入社したものの、社風が合わずに苦労するケースもあります。
ここでは、どのような思考性や価値観を持つ人が老舗企業に向いているのか、代表的な3つの特徴について解説します。
安定志向のある人
老舗企業の最大の魅力である経営の安定性や、長期雇用を前提とした文化は、何よりも安定した環境で働きたいと考える人に最適です。
数年で転職を繰り返すキャリアよりも、一つの会社に腰を据え、じっくりとキャリアを築いていきたいという志向性を持つ人は、老舗企業の風土にマッチするでしょう。
給与が短期間で急激に上がることは少ないかもしれませんが、景気の波に左右されにくく、着実に昇給や昇進が見込める安心感があります。
また、福利厚生が充実している企業も多く、住宅や家族に関するサポートも手厚い傾向があります。
こうした安定した基盤の上で、仕事だけでなく、長期的な人生設計(ライフプラン)も考えたい人に向いています。
誠実でコツコツ努力できる人
老舗企業は、顧客や取引先との信頼関係を何よりも重んじます。
そのため、そこで働く社員にも、誠実な人柄と、地道な努力を厭わない姿勢が強く求められます。
派手なパフォーマンスや口先だけの弁舌よりも、与えられた仕事に対して真摯に向き合い、約束を守り、小さな成果をコツコツと積み重ねられる人が評価される傾向にあります。
日々の業務は、一見すると地味なものも多いかもしれませんが、その一つ一つが会社の信用を支えているという責任感を持ち、真面目に取り組める。
そうした堅実さを持った人は、老舗企業において上司や同僚、そして顧客からも厚い信頼を得て、長期的に活躍することができるでしょう。
調和を大切にできる人
老舗企業の多くは、個人の成果を追求するよりも、組織全体の和やチームワークを重んじる文化を持っています。
これは、長い歴史の中で、多くの人々が協力し合って困難を乗り越えてきた経験から培われたものです。
そのため、自分が目立つことよりも、チームや部署全体の目標達成を考え、周囲と歩調を合わせられる協調性が求められます。
自分の意見を主張する際も、一方的に押し通すのではなく、相手の立場や意見を尊重し、組織全体の調和を考えながら調整を図る能力が重要です。
個人の実力で突き進みたいというタイプの人よりも、周囲と協力しながら一つのことを成し遂げるプロセスに喜びを感じる人の方が、老舗企業の文化には馴染みやすいと言えます。
【老舗企業】内定をもらうためのポイント
就職偏差値ランキングで上位に来るような人気の老舗企業は、その安定性から多くの学生が応募し、高い競争率になります。
こうした企業から内定を勝ち取るためには、その歴史と文化を深く理解し、それにふさわしいアピールをすることが不可欠です。
ここでは、老舗企業の選考を突破するために、特に意識すべき3つのポイントを紹介します。
企業の歴史や理念を理解する
老舗企業の選考を受ける上で、その企業の歴史や企業理念(社是・社訓など)を深く理解しておくことは絶対条件です。
なぜその企業が100年以上も存続し得たのか。
創業者がどのような想いで事業を立ち上げ、歴代の経営者がどのような危機を乗り越えてきたのか。
その歴史を学ぶことで、その企業が何を大切にしているのかという核心的な価値観が見えてきます。
面接では、単に製品が好き、安定しているから、といった理由だけでは評価されません。
その企業の理念のどの部分に共感したのか、そしてその歴史や伝統を未来につなげていくために、自分が入社してどう貢献したいのかを、自分の言葉で具体的に語ることが重要です。
この企業研究の深さが、志望度の本気度として伝わります。
誠実な印象を与える
老舗企業は、顧客や取引先からの信頼を第一に考えるため、採用する人材にも誠実さや真面目さを強く求めます。
選考の場では、奇をてらったアピールや、話を大げさに盛ることは逆効果になりかねません。
むしろ、服装や髪型などの身だしなみを清潔に整え、相手の目を見て、ハキハキと、そして何よりも正直に受け答えをすることが重要です。
自分の強みだけでなく、弱みや失敗経験についても、それをどう受け止め、改善しようと努力しているかを誠実に話す姿勢が好印象を与えます。
時間を厳守する、丁寧な言葉遣いを心がけるといった、社会人としての基本的なマナーを徹底することも、あなたの誠実さを示す大切な要素となります。
安定志向ではなく「長期的成長志向」を語る
老舗企業を志望する際、安定しているからという理由をそのまま伝えるのは得策ではありません。
企業側は、安定した環境に安住したい人ではなく、その安定した基盤の上で、会社と共に長く成長し続けてくれる人材を求めているからです。
したがって、アピールすべきは安定志向ではなく、長期的な成長志向です。
例えば、充実した教育制度を活用してじっくりと専門性を高め、10年後、20年後には会社の中心的な人材として貢献したい、といった具合です。
また、伝統を守るだけでなく、その中で新しい価値を生み出したいという、変化を恐れない前向きな姿勢(ただし、あくまでも会社の文化を尊重する前提で)を示すことも有効です。
【老舗企業】よくある質問
老舗企業は、安定性や落ち着いた社風といった魅力がある一方で、古くさい、変化が遅いといったネガティブなイメージを持つ就活生もいるかもしれません。
就職偏差値やランキングだけでなく、実際の働き方やキャリアについて、リアルな情報を知りたいでしょう。
ここでは、特によくある3つの質問について、分かりやすく回答していきます。
老舗企業は変化に弱いですか?
変化に慎重な文化があるのは事実ですが、変化に弱いかどうかは企業によります。
むしろ、100年以上存続してきた企業は、その時代時代で大きな変化(戦争、不況、技術革新など)に対応し、自己変革を遂げてきたからこそ生き残っている、とも言えます。
ただし、その変化のスピードは、ITベンチャーなどと比較するとゆっくりしている傾向はあります。
最近では、老舗企業もデジタル化(DX)の推進や、新しい事業領域への挑戦に積極的に取り組んでいるケースも増えています。
企業研究の際は、その企業が伝統を守る一方で、未来に向けてどのような変革に取り組んでいるか、そのバランスを見極めることが重要です。
若手でも活躍できますか?
若手でも活躍できるチャンスは十分にあります。
ただし、その活躍の仕方は、成果主義の外資系企業などとは異なるかもしれません。
老舗企業では、入社後すぐに大きなプロジェクトを任されるというよりは、まずは基礎的な業務をしっかりと学び、地道な努力を重ねる中で、徐々に信頼を勝ち取っていくプロセスが重視されます。
その誠実な仕事ぶりが評価されれば、若手であっても責任のある仕事を任されるようになります。
また、若手ならではの新しい視点や、デジタルスキルなどは、むしろ歓迎されることも多いです。
組織の和を重んじつつ、自分のできることを着実に実行し、前向きな提案を続ける姿勢が、活躍の鍵となります。
転勤は多いですか?
これは、企業や業種によって大きく異なります。
全国に支店や工場、営業所を持つ大手メーカーや金融機関、インフラ企業などの場合は、数年単位での全国転勤(ジョブローテーション)がキャリアパスに組み込まれていることが一般的です。
これは、様々な地域の特性や業務を経験させ、将来の幹部候補として育成するという目的があります。
一方で、特定の地域に密着した百貨店や、本社機能が集中している企業、あるいはBtoBで拠点が少ない企業などの場合は、転勤が少ない、あるいは全くないケースもあります。
自分が将来的にどのような働き方をしたいのか(全国で活躍したいのか、地元で働きたいのか)を考え、志望する企業の転勤の有無や頻度を、OB・OG訪問や説明会などでしっかりと確認しておくことが大切です。
まとめ
老舗企業の就職偏差値ランキングや、その特徴、内定を獲得するためのポイントについて解説しました。
老舗企業は、その圧倒的な安定性と、人をじっくり育てる文化が大きな魅力ですが、同時に変化に慎重な側面も持ち合わせています。
ランキングやイメージだけで判断せず、その企業の歴史や理念に深く共感できるか、そして自分の価値観やキャリアプランと本当に一致しているかを徹底的に見極めることが、後悔のない就職活動につながります。