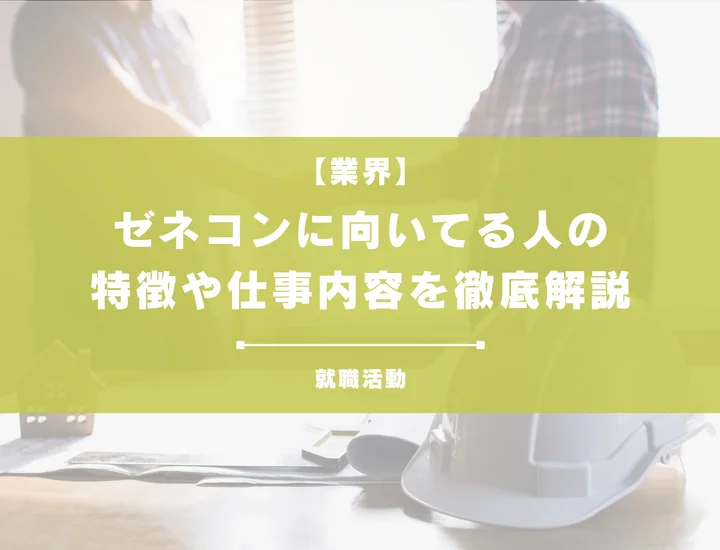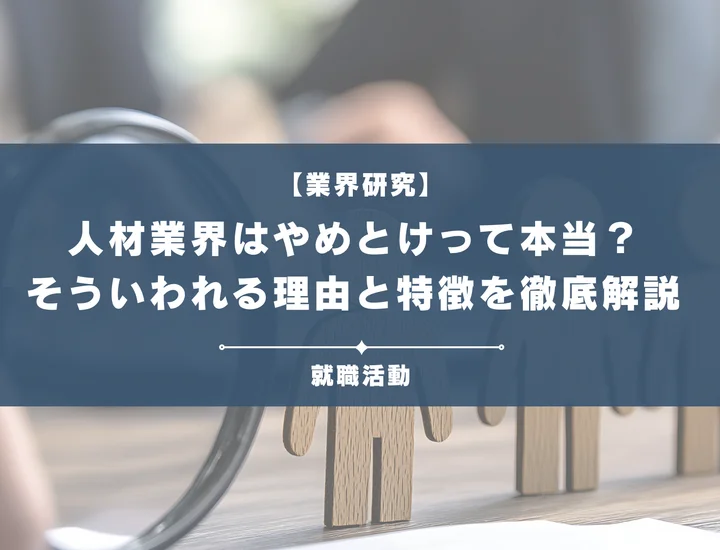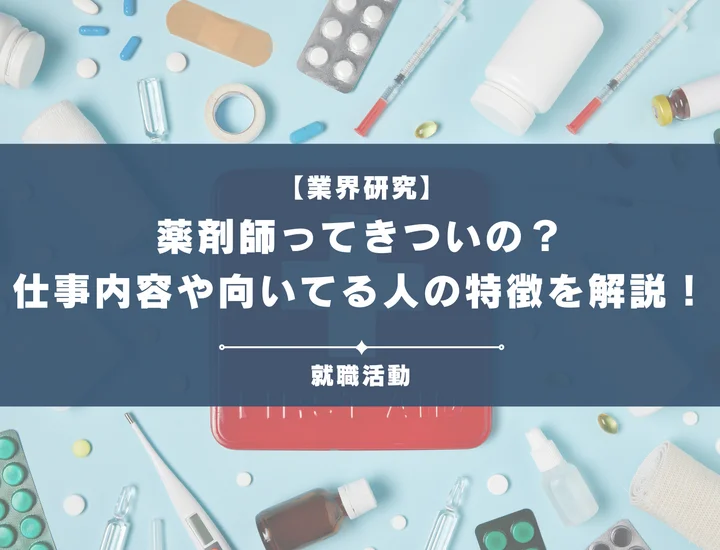HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業の入社難易度を学生からの人気度や選考倍率などから算出した指標です。
明確な定義はなく、あくまでも就職活動における企業選びの一つの目安として活用されるもので、順位は毎年変動します。
製薬業界の就職偏差値ランキング
製薬業界の就職偏差値は、外資系メガファーマや国内大手が上位を占める傾向にあります。
企業の安定性や研究開発力、平均年収の高さなどが、入社難易度を測る上での主な指標となり、学生から高い人気を集めています。
ここからは各ランクごとに紹介していますので、自分の行きたい企業の位置を確認してみましょう。
【製薬業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】ファイザー製薬 グラクソ・スミスクライン日本 ヤンセンファーマ日本 ギリアド・サイエンシズ日本
このランクには、世界的に絶大な影響力を持つ外資系のメガファーマが名を連ねています。
グローバル規模での新薬開発力、圧倒的な売上高、そして業界最高水準の給与体系が特徴です。
入社には、薬学や生命科学分野での高度な専門性に加え、ビジネスレベル以上の語学力が必須とされます。
博士号取得者や海外経験者も多く応募するため、極めてハイレベルな競争を勝ち抜くための卓越した実績や論理的思考力が求められます。
【製薬業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ製薬業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】ノバルティスファーマ日本 バイエル薬品 アムジェン日本
【68】武田薬品工業 中外製薬 第一三共 サノフィ日本 ブリストル・マイヤーズスクイブ日本 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本
【67】アステラス製薬 日本イーライリリー アストラゼネカ日本 メルク・アンド・カンパニー日本 バイオジェン日本
【66】小野薬品工業 塩野義製薬 協和キリン エーザイ アストラゼネカ日本 アボットジャパン ヴィアトリス製薬
Aランクに次ぐ外資系大手と、日本の製薬業界を牽引するトップ内資企業がひしめくランクです。
革新的な新薬を次々と生み出す高い研究開発力と、安定した経営基盤を両立している企業群といえます。
ここでも高い専門性と語学力は前提条件となります。
その上で、各社の企業文化や強みとする研究領域を深く理解し、自身の専門性と将来のビジョンを明確に結びつけてアピールすることが不可欠です。
【製薬業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】大塚製薬 大鵬薬品工業 住友ファーマ 日本ベーリンガーインゲルハイム ユーシービージャパン
【64】大正製薬 参天製薬 ツムラ 田辺三菱製薬 シンバイオ製薬 そーせいグループ ペプチドリーム ノボノルディスクファーマ日本
【63】杏林製薬 持田製薬 帝人ファーマ 旭化成ファーマ MeijiSeikaファルマ JCRファーマ アンジェス サンバイオ モデルナ日本 ロシュ・ダイアグノスティックス日本
【62】ロート製薬 鳥居薬品 科研製薬 生化学工業 キッセイ薬品工業 タカラバイオ 武田テバファーマ
【61】小林製薬 日本新薬 富士製薬工業 興和 沢井製薬 東和薬品 ゼリア新薬工業 あすか製薬 ミズホメディー ラクオリア創薬 オンコリスバイオファーマ
内資系の有力企業や、特定の疾患領域で高いシェアを誇るスペシャリティファーマが中心となるランクです。
また、ペプチドリームやそーせいグループなど、独自の技術で急成長するバイオベンチャーも含まれています。
企業の規模は様々ですが、それぞれが持つ独自の強みや将来性を見極めることが重要になります。
「なぜこの会社でなければならないのか」を、自身の研究内容やキャリアプランと関連付けて具体的に語れる深い企業研究が合格の鍵を握ります。
【製薬業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】佐藤製薬 久光製薬 千寿製薬 カルナバイオサイエンス ペルセウスプロテオミクス ノイルイミューン・バイオテック KMバイオロジクス
【59】扶桑薬品工業 日本ケミファ 日本臓器製薬 ビオフェルミン製薬 わかもと製薬 ステラファーマ 坪田ラボ デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ブライトパス・バイオ
【58】大幸薬品 ニプロファーマ 森下仁丹 室町ケミカル クリングルファーマ レナサイエンス 大正エム・ティー・シー
【57】佐藤薬品工業 中京医薬品 窪田製薬 湧永製薬 日本全薬工業 富士薬品 免疫生物研究所
【56】全星薬品工業 高田製薬 松田薬品工業 長生堂製薬 北日本製薬 帝國製薬 京都薬品工業 救急薬品工業 新新薬品工業 リバテープ製薬 エイワイファーマ
一般用医薬品(OTC)で知名度の高い企業や、後発医薬品(ジェネリック)を扱うメーカー、堅実な経営を続ける中堅の医療用医薬品メーカーなどが含まれます。
地域医療に貢献していたり、特定のニーズに特化した製品で安定した基盤を築いていたりする企業が多いのが特徴です。
専門性に加えて、チームで成果を出す協調性や、誠実な人柄といったポテンシャル面も重視される傾向にあります。
企業の理念に共感し、入社後にどのように貢献していきたいかを熱意をもって伝えることが大切です。
【製薬業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】日医工(上場廃止) 小林化工(医薬製造撤退) テラ(廃業)
このランクに挙げられている企業は、過去に経営上の大きな問題を抱え、事業撤退や上場廃止に至ったケースです。
就職偏差値というよりも、企業の安定性や将来性を見極める重要性を示唆しています。
就職活動においては、企業の人気や知名度だけでなく、IR情報や近年のニュースを精査し、財務状況やコンプライアンス体制に問題がないかを確認する情報収集能力が不可欠です。
自身のキャリアを長期的な視点で考え、安心して働き続けられる企業を選ぶことが何よりも重要となります。
【製薬業界】とは
製薬業界は、病気の治療や予防に使われる医薬品を創り出す、極めて社会貢献性の高い産業です。
人々の生命に直結するため、就職偏差値も高く、安定性と専門性を求める学生から毎年高い人気を集めています。
人々の生命と健康を支える社会貢献性の高い産業
製薬業界の最も大きな魅力は、自社の製品を通じて世界中の人々の命を救い、健康な生活に貢献できる点です。
新薬が開発されれば、これまで治療が困難だった病気に苦しむ患者さんやその家族に希望を届けられます。
このような使命感は、働く上での大きなやりがいとなるでしょう。
また、高齢化社会の進展に伴い、医薬品の重要性はますます高まっています。
社会的な意義と将来性を両立していることが、製薬業界が就職市場で高い評価を受け、就職偏差値ランキングで常に上位に位置する理由の一つです。
「医療用医薬品」と「一般用医薬品」に分類される
製薬業界が扱う医薬品は、大きく二つに分類されます。
一つは、医師の処方箋が必要な医療用医薬品です。
特定の疾患に対して高い効果を持つ専門的な薬であり、企業の売上の大半を占めます。
もう一つは、ドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品、通称OTC医薬品です。
こちらは風邪薬や鎮痛剤など、比較的軽微な症状に対応します。
就職活動においては、志望する企業がどちらの医薬品を主力としているか理解することが重要です。
それにより事業戦略や求められる職種、働き方も変わってくるため、企業研究の第一歩となります。
研究開発から製造、販売・情報提供まで一貫したプロセス
製薬業界の仕事は、新しい薬の候補物質を探す基礎研究から始まります。
次に、薬の有効性や安全性を確認する非臨床試験や臨床試験といった開発段階に進みます。
国からの承認を得て初めて、厳格な品質管理のもとで製造され、医療機関に届けられます。
そして、MRと呼ばれる医薬情報担当者が、医師や薬剤師に薬の適正な情報を提供し、販売活動を行います。
このように、一つの薬を患者さんに届けるまでには、多様な職種の専門家が関わる長いプロセスが存在しており、自身の専門性や興味に合わせて活躍できるフィールドが広がっています。
【製薬業界】特徴
製薬業界は、景気に左右されにくい安定した経営基盤と、特許に守られた高い収益性を持つことが特徴です。
一方で、一つの新薬を生み出すためには莫大な投資と長い年月が必要となる、ハイリスク・ハイリターンなビジネスモデルでもあります。
景気変動の影響を受けにくい安定した経営基盤
医薬品は人々の生命維持に不可欠なものであるため、景気が悪化しても需要が急激に落ち込むことはありません。
いわゆるディフェンシブ産業の代表格であり、安定した経営基盤を持つ企業が多いのが大きな特徴です。
この安定性は、就職偏差値が高い要因の一つであり、長期的なキャリアプランを考えやすい魅力的な環境といえるでしょう。
特に、革新的な新薬を複数持ち、強固な開発パイプラインを持つ大手企業は、盤石な収益構造を誇ります。
安心して研究開発や事業活動に専念できる環境は、働く社員にとっても大きなメリットです。
新薬創出には莫大な研究開発費と時間が必要
一つの新薬が世に出るまでには、一般的に10年以上の歳月と数百億円から数千億円もの莫大な研究開発費が必要とされます。
新薬候補物質の中から、最終的に国の承認を得て製品化に至る確率は、2万分の1から3万分の1ともいわれるほど非常に厳しい世界です。
この成功確率の低さから、研究開発職には高度な専門知識はもちろん、失敗を恐れずに粘り強く挑戦し続ける精神的な強さが求められます。
企業にとっては、研究開発への大規模な先行投資が常に必要となる、ハイリスクな事業構造といえます。
特許によって高い利益率が守られるビジネスモデル
新薬の開発に成功した企業は、特許を出願・取得することで、一定期間その薬を独占的に製造・販売する権利を得ます。
この特許期間中は、競合他社がいないため、高い薬価を維持でき、研究開発費を回収して大きな利益を生み出すことが可能です。
この仕組みが、製薬業界の高い収益性を支える根幹となっています。
しかし、特許が切れると、他のメーカーが同じ有効成分の医薬品、いわゆるジェネリック医薬品を安価で販売できるようになり、売上が大幅に減少するパテントクリフという課題に直面します。
そのため、各社は特許切れを見据え、常に次の新薬を生み出し続ける必要があります。
【製薬業界】向いている人
製薬業界で活躍するには、人々の健康に貢献したいという強い想いが不可欠です。
また、日進月歩の医療分野で常に学び続ける知的好奇心と、人の命に関わるという高い倫理観・責任感を持ち合わせていることが極めて重要になります。
社会や人々への貢献意欲
製薬業界の仕事は、病気と闘う患者さんやそのご家族の未来に直接的に貢献できる、非常に社会的意義の大きい仕事です。
そのため、誰かの役に立ちたい、社会をより良くしたいという強い貢献意欲が、仕事のモチベーションの源泉となります。
特に新薬開発は、困難の連続であり、長い道のりです。
その中で、薬を待つ患者さんの存在を想い、最後までやり遂げようとする使命感が不可欠です。
面接でも、なぜ医療や医薬品の分野で社会貢献したいのか、自身の経験に基づいた具体的な理由を語れることが、志望度の高さを伝える上で重要になります。
常に学び続けることが苦じゃない
医学・薬学の分野は、日々新しい発見や技術革新が生まれる世界です。
昨日までの常識が、今日には覆されることも珍しくありません。
そのため、どの職種であっても、常に最新の論文や医療情報にアンテナを張り、自身の知識をアップデートし続ける学習意欲が求められます。
特に研究開発職やMR職は、専門家である医師や科学者と対等に議論する場面も多く、継続的な学習がなければ務まりません。
知的好奇心が旺盛で、新しい知識を得ることに喜びを感じられる人は、製薬業界で大きく成長し、長く活躍し続けることができるでしょう。
倫理観が高く責任感が強い
製薬業界が扱う医薬品は、人の生命に直接的な影響を与えるものです。
有効性はもちろんのこと、安全性に対しても最大限の配慮が求められ、わずかなミスも許されません。
そのため、社員一人ひとりが、薬事法をはじめとする関連法規を遵守し、高い倫理観を持って業務に取り組む必要があります。
自分の仕事が、多くの人々の命と健康を背負っているという強い責任感を持ち、誠実に物事を進められる人でなければなりません。
真面目で、決められたルールを厳格に守れる実直さは、製薬業界で働く上での重要な資質といえます。
【製薬業界】内定をもらうためのポイント
就職偏差値が高い製薬業界の内定を得るには、徹底した業界・企業研究が不可欠です。
なぜ製薬業界なのかを明確にし、職種ごとに求められるスキルを理解した上で、インターンシップなどを通じて企業との接点を増やすことが重要です。
なぜ製薬業界かが明確
数ある業界の中で、なぜ製薬業界を志望するのかを明確に言語化することが全てのスタート地点です。
多くの学生が挙げる、社会貢献性という理由だけでは不十分です。
自身の過去の経験や価値観と結びつけ、なぜ食品でも医療機器でもなく、医薬品でなければならないのかを具体的に語る必要があります。
例えば、家族が病気をした際に薬の力に助けられた経験や、大学での研究を通じて創薬の可能性に魅了された経験など、あなただけのオリジナルなストーリーが説得力を生みます。
この志望動機の軸が固まることで、その後の企業選びや面接での受け答えにも一貫性が生まれます。
求められてるスキルを理解しアピール
製薬業界は職種ごとに専門性が高く、求められるスキルが明確です。
研究職であれば、自身の研究内容が企業のどの開発領域で活かせるのか、専門性を具体的にアピールする必要があります。
MR職であれば、専門家である医師と信頼関係を築くための高いコミュニケーション能力や論理的思考力が求められます。
自身の学生時代の経験、例えば研究活動や部活動、アルバイトなどで、これらのスキルをどのように培い、発揮してきたのかを具体的なエピソードを交えて伝えることで、入社後の活躍イメージを面接官に持たせることが重要になります。
インターンシップに積極的に参加する
インターンシップは、企業の文化や事業内容を肌で感じられる貴重な機会です。
ウェブサイトや説明会だけでは得られない、社員の方々の雰囲気や仕事への姿勢などを知ることで、企業とのミスマッチを防ぎ、志望動機をより深めることができます。
また、グループワークなどを通じて、社員の方に自分の能力や人柄を直接アピールするチャンスでもあります。
企業によっては、インターンシップ参加者向けの早期選考や、選考の一部免除といった優遇措置を設けている場合もあります。
就職偏差値が高い人気企業の内定を掴むためには、積極的に参加し、他の学生より一歩リードすることが有効な戦略です。
【製薬業界】よくある質問
製職偏差値が高い製薬業界を目指す学生からは、企業の安定性や、文系・学歴フィルターの有無に関する質問が多く寄せられます。
ここでは、それらの疑問に対して、業界の現状を踏まえながら解説していきます。
就職偏差値が高い企業は安定している?
結論から言うと、就職偏差値が高い企業は、研究開発力や収益性が高く、経営基盤が安定している傾向にあります。
偏差値上位にランクインする企業は、革新的な新薬を複数有しており、それが安定した収益源となっています。
しかし、前述の通り、医薬品の特許が切れると売上が激減するパテントクリフのリスクを常に抱えています。
そのため、企業の本当の安定性を見極めるには、現在の売上だけでなく、将来の収益源となる開発パイプラインがどれだけ充実しているかを確認することが非常に重要です。
安定性を重視するなら、目先の偏差値だけでなく、企業の将来性まで見据えた分析が不可欠です。
文系でも大丈夫なのか?
文系学生でも製薬業界で活躍できるフィールドは十分にあります。
代表的な職種はMR職です。
MRは医師や薬剤師と対話し、医薬品の情報を伝える役割を担うため、理系の知識以上に高いコミュニケーション能力や信頼関係構築力が求められます。
入社後の充実した研修制度で専門知識を習得できるため、文系出身のMRは数多く活躍しています。
また、本社部門においても、人事、経理、法務、広報、経営企画など、文系学生の専門性を活かせる職種は多岐にわたります。
理系が中心の業界というイメージはありますが、多様な人材が企業の成長を支えているのが実情です。
学歴は重要視されるのか?
職種によって学歴の重要度は異なります。
特に研究職や開発職といった専門職では、特定の分野での研究実績が問われるため、大学院卒、特に修士了以上が応募条件となる場合がほとんどです。
そのため、結果的に旧帝大や有名私立大学の出身者が多くなる傾向はあります。
一方で、MR職や本社部門のスタッフ職では、専門性よりも個人の資質やポテンシャルが重視されるため、研究職ほど学歴が直接的な評価に結びつくわけではありません。
しかし、就職偏差値が高い人気企業には、多様な大学から優秀な学生が応募するため、学歴に関わらず、論理的思考力や明確な志望動機など、高いレベルでの競争になることは間違いありません。
まとめ
製薬業界は、高い社会貢献性と安定性から、就職偏差値が非常に高い人気の業界です。
内定を勝ち取るためには、業界と企業、そして職種への深い理解が不可欠です。
本記事で解説した業界の特徴や求められる人物像を参考に自己分析を進め、なぜ自分が製薬業界で働きたいのか、そして入社後にどう貢献できるのかを明確に語れるように準備を進めていきましょう。
インターンシップなどを活用し、積極的に情報収集を行うことが、ライバルと差をつける鍵となります。