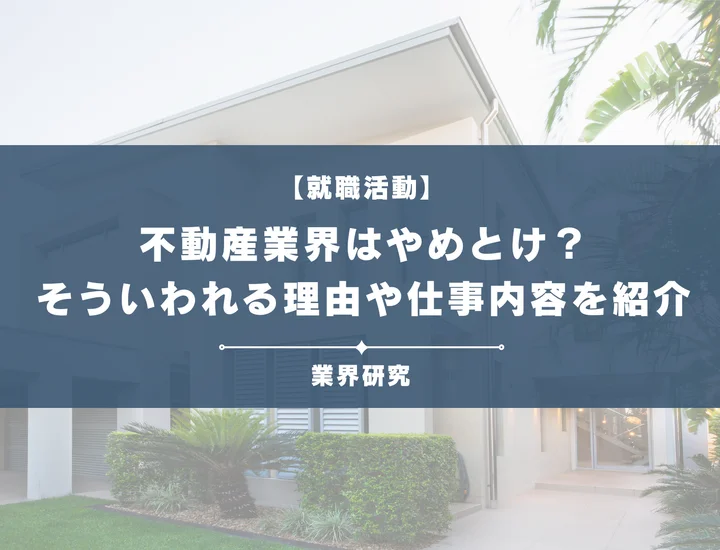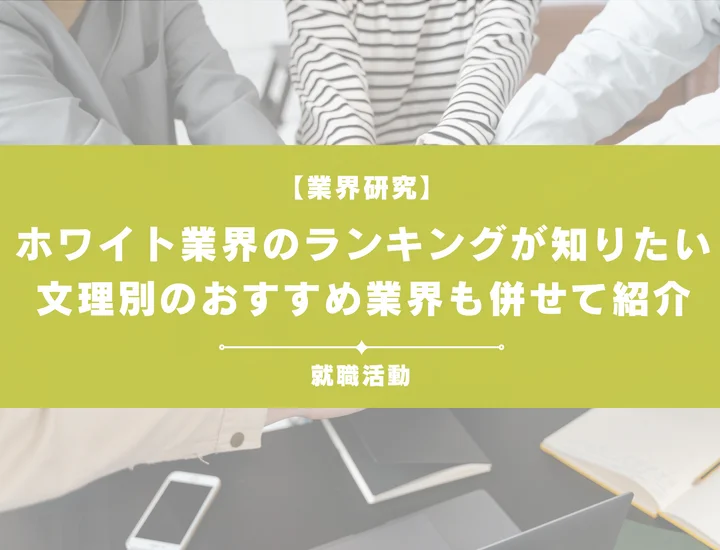HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
就職活動を進める中で、不動産業界に興味を持ちながらも、インターネットや周囲の評判で、不動産業界はやめとけという言葉を目にして不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
確かにこの業界には、厳しい側面があることも事実です。
しかし、そうしたイメージだけで判断し、大きな可能性を秘めた選択肢を閉ざしてしまうのは非常にもったいないことです。
この記事では、なぜ不動産業界はやめとけと言われるのか、その具体的な理由を深掘りするとともに、業界の魅力や将来性、そして自分に合った企業を見つけるための方法まで、就職活動に役立つ情報を網羅的に解説していきます。
この記事を読めば、不動産業界に対する理解が深まり、ご自身のキャリア選択に自信を持てるようになるはずです。
【不動産業界やめとけ】不動産業界とは
不動産業界と一言でいっても、その仕事内容は非常に多岐にわたります。
土地や建物を扱うという共通点はありますが、事業領域は大きく開発、販売、賃貸、管理などに分かれており、それぞれで求められるスキルややりがいも異なります。
街のランドマークを創り出すスケールの大きな仕事から、人々の暮らしに密着し、人生の節目に立ち会う仕事まで、社会に与える影響が大きく、ダイナミックな魅力を持つ業界です。
一方で、市場は経済の動向に左右されやすく、常に変化にさらされています。
就職活動を進める上では、こうした業界の全体像を正しく理解し、自分がどの分野でどのような働き方をしたいのかを明確にすることが重要になります。
様々な仕事内容がある
不動産業界の仕事は、人々の生活や経済活動の基盤となる不動産を多角的に扱う、社会貢献性の高いものです。
主な仕事内容は、土地を仕入れてマンションや商業施設などを建設するデベロッパー事業、完成した建物や中古物件の売買を仲介する販売・仲介事業、アパートやマンションの入居者募集や契約手続きを行う賃貸事業、そして物件の維持管理や入居者対応を担う管理事業の4つに大別されます。
例えば、デベロッパーは地図に残るような大規模な街づくりに携わるやりがいがあり、売買仲介は顧客の人生における最大の買い物に寄り添う責任と喜びがあります。
また、賃貸仲介は多くの人の新生活のスタートを支える仕事であり、管理は建物の資産価値を守り、快適な住環境を提供する専門性の高い仕事です。
このように、不動産業界には多様なキャリアの選択肢があり、それぞれの分野で専門知識を身につけ、プロフェッショナルとして成長していくことが可能です。
自分の興味や適性がどの分野にあるのかを考えることが、業界理解の第一歩となります。
不動産業界の現状
現在の不動産業界は、社会情勢の変化とともに大きな変革期を迎えています。
新築マンションの価格は都心部を中心に高騰を続けており、それに伴って中古物件市場も活性化しています。
一方で、地方では人口減少による空き家問題が深刻化しており、その利活用が大きな課題となっています。
働き方の多様化も業界に影響を与えており、テレワークの普及によってオフィスのあり方が見直されたり、都心から郊外への移住ニーズが高まったりと、新たな需要が生まれています。
また、近年はIT技術を活用した不動産テックと呼ばれるサービスが急速に拡大しており、VRでの内見やAIによる価格査定、電子契約などが普及し始めています。
こうしたデジタル化の波は、従来の業務プロセスを大きく変え、生産性の向上に貢献することが期待されています。
変化が激しい時代だからこそ、新しいビジネスチャンスが生まれており、柔軟な発想と行動力が求められる業界であるといえるでしょう。
【不動産業界やめとけ】やめとけと言われる理由7選
不動産業界はやめとけと言われる背景には、この業界特有の働き方や慣習が関係しています。
例えば、お客様の都合に合わせることが多いため勤務時間が不規則になりがちであったり、成果が給与に直結する厳しさがあったりします。
もちろん、全ての企業が同じというわけではありませんが、就職活動を行う上で、こうしたネガティブなイメージを持たれることが多い理由について事前に理解しておくことは、入社後のミスマッチを防ぐために非常に重要です。
ここでは、やめとけと言われる代表的な7つの理由を挙げ、それぞれの実態について詳しく解説していきます。
これらの情報を踏まえた上で、自分にとって許容できる範囲なのかどうかを冷静に判断しましょう。
クレーム対応がある
不動産業界の仕事、特に賃貸仲介や物件管理の業務において、お客様からのクレーム対応は避けて通れない部分です。
例えば、入居者からは、エアコンが動かない、水漏れがするといった設備の不具合に関する連絡が日常的に入ります。
また、騒音やゴミ出しのルールなど、住民間のトラブルの仲介役を担うことも少なくありません。
家賃の支払いが滞っている入居者に対して、督促の連絡をしなければならないこともあります。
こうした対応は、時に厳しい言葉を受けたり、感情的な相手と対峙したりする必要があるため、精神的な負担が大きいと感じる人もいるでしょう。
しかし、一つ一つの問題に誠実に向き合い、迅速に解決策を提示することで、お客様からの信頼を得ることができます。
困難な状況を乗り越えることで、問題解決能力やコミュニケーションスキルが飛躍的に向上するという側面もあり、自身の成長に繋がる経験と捉えることもできるでしょう。
ノルマがある
不動産業界、特に売買仲介や賃貸仲介といった営業職には、多くの場合、厳しいノルマが設定されています。
個人の売上目標や契約件数が月ごと、四半期ごとに細かく定められており、その達成状況が給与や評価に直接反映される成果主義の世界です。
目標を達成できない月が続くと、上司からのプレッシャーを感じたり、周囲の同僚と自分を比較して焦りを感じたりすることもあるでしょう。
特に、給与体系に歩合給の占める割合が大きい場合、成果が出なければ収入が安定しないという厳しさもあります。
一方で、自分の頑張りが成果として明確に数字に表れ、それが収入に直結する点は大きなモチベーションになります。
年齢や社歴に関わらず、実力次第で高い評価と報酬を得られるため、競争の激しい環境で自分を試したい、成果に見合った対価を得たいと考える人にとっては、非常にやりがいのある環境であるといえます。
土日出勤のケースが多い
不動産業界を目指す上で、勤務体系について理解しておくことは非常に重要です。
多くのお客様は、土日や祝日に休みを取っている社会人や家族連れであるため、物件探しや内見、契約手続きなども自然と休日に集中します。
そのため、不動産会社の営業担当者は、お客様の都合に合わせて土日に出勤するのが一般的です。
その代わりとして、平日の火曜日や水曜日などを定休日としている企業が多く見られます。
友人や家族と週末の予定を合わせにくいことをデメリットに感じる人もいるかもしれません。
しかし、見方を変えれば、平日の空いている時間帯に銀行や役所での手続きを済ませたり、混雑を避けて買い物やレジャーを楽しんだりできるというメリットもあります。
自身のライフプランやプライベートで何を重視するかを考え、このような勤務スタイルが自分に合っているかどうかを慎重に検討することが大切です。
考え方が古いケースがある
不動産業界の一部には、昔ながらの体育会系の気質や、年功序列といった古い考え方が根強く残っている企業も存在します。
例えば、契約が取れるまで帰れないといった雰囲気や、上司の指示は絶対という上下関係の厳しさ、精神論を重視する風潮などが挙げられます。
また、業界全体としてIT化の導入が他の業界に比べて遅れている側面もあり、現在でもFAXでのやり取りや紙ベースでの契約書管理など、アナログな業務プロセスが中心となっている企業も少なくありません。
こうした企業文化は、若い世代にとっては窮屈に感じられたり、非効率的であると捉えられたりすることがあります。
ただし、近年では若手社員の意見を積極的に取り入れたり、DXを推進して業務効率化を図ったりと、時代に合わせて変化しようと努力している企業も増えています。
企業訪問やインターンシップなどを通じて、その会社の実際の雰囲気を感じ取り、自分の価値観と合うかどうかを見極めることが重要です。
平均年収が低い
不動産業界は高収入というイメージがある一方で、業界全体の平均年収を見ると、必ずしも他の業界より高いわけではないというデータがあります。
国税庁が発表している民間給与実態統計調査によると、不動産業・物品賃貸業の平均給与は、全産業の平均と同程度か、やや下回る水準で推移しています。
これは、業界内に様々な職種が存在するためです。
例えば、成果が収入に直結する営業職では、若くして年収1000万円以上を稼ぐ人がいる一方で、会社の業績を支える事務職や管理部門などは、比較的安定した給与体系であることが多いです。
また、企業規模によっても年収水準は大きく異なります。
平均年収という一つのデータだけを見て判断するのではなく、自分が希望する職種や企業の給与体系を個別に確認することが重要です。
特に営業職を希望する場合は、基本給と歩合給の割合や、成果に応じたインセンティブの詳細について、事前にしっかりと調べておく必要があります。
景気の影響を受けやすい
不動産業界は、社会全体の景気動向に業績が大きく左右されるという特徴を持っています。
景気が良い時期には、企業の設備投資が活発になりオフィスの需要が高まったり、個人の所得が増えて住宅の購入意欲が向上したりするため、不動産市場は活況を呈します。
また、住宅ローン金利が低い時期も、購入を後押しする要因となります。
しかし、反対に景気が後退すると、企業は投資を控え、個人も将来への不安から大きな買い物である不動産の購入を見送る傾向が強まります。
そうなると、不動産の価格が下落し、市場全体が停滞してしまう可能性があります。
このように、不動産業界は金融政策や経済情勢といった外部環境の変化を常に受け続ける業界です。
そのため、日頃からニュースや経済の動向にアンテナを張り、変化を予測しながらビジネスを行う必要があります。
安定性を求める人にとってはリスクと感じるかもしれませんが、経済のダイナミズムを肌で感じたい人にとっては刺激的な環境だといえるでしょう。
サービス残業が多い
不動産業界の働き方として、サービス残業が多いというイメージを持つ人も少なくないでしょう。
残念ながら、一部の企業においては、そうした実態が今なお残っているケースがあります。
例えば、日中はお客様への対応や物件の案内に時間を費やし、定時を過ぎてから契約書類の作成や物件情報の入力といった事務作業を行わなければならないことがあります。
また、お客様からの急な連絡に対応するため、勤務時間外でも電話やメールの確認を余儀なくされる場面もあるかもしれません。
こうした状況が常態化し、時間外手当が適切に支払われない、いわゆるサービス残業が発生してしまうのです。
ただし、近年は働き方改革の流れを受けて、勤怠管理を徹底したり、ノー残業デーを設けたりと、労働環境の改善に真摯に取り組む企業も着実に増えています。
企業選びの際には、口コミサイトの情報を参考にしたり、面接の場で残業時間の実態や管理体制について質問したりするなど、実情をしっかりと見極める努力が求められます。
【不動産業界やめとけ】働く魅力
ここまで不動産業界の厳しい側面について解説してきましたが、もちろん、それを上回る多くの魅力があることも事実です。
やめとけという言葉の裏側にある、この業界ならではのやりがいや醍醐味を知ることで、より深く業界を理解することができます。
例えば、自分の努力が成果として明確に評価され、若いうちから高収入を目指せる環境や、学歴に関係なく実力でキャリアを切り拓いていける風土は、成長意欲の高い人にとって大きな魅力となるでしょう。
ここでは、不動産業界で働くことの具体的な魅力を3つの観点からご紹介します。
これらのポジティブな側面にも目を向けることで、不動産業界が自分にとって本当に挑戦する価値のある場所なのかを判断する材料にしてください。
キャリアアップしやすい
不動産業界は、年齢や社歴に関わらず、実力と成果が正当に評価される文化が根付いているため、キャリアアップしやすい環境であるといえます。
多くの企業、特に営業部門では成果主義が採用されており、実績を上げれば、若くしてチームリーダーや管理職といった責任あるポジションを任されるチャンスが豊富にあります。
また、宅地建物取引士、通称宅建士という国家資格の取得がキャリアを大きく後押しします。
宅建士は不動産取引の専門家であることを証明する資格であり、重要事項の説明など独占業務を行えるため、多くの企業で取得が推奨されています。
資格手当を支給する企業も多く、昇進の条件となっている場合もあります。
このように、自身の努力が昇進や昇給といった目に見える形で報われやすく、明確な目標を持って仕事に取り組める点は、成長意欲の高い人にとって大きなやりがいとなるでしょう。
専門知識と実務経験を積むことで、将来的には独立開業という道も拓けます。
高収入が狙える
不動産業界の最大の魅力の一つとして、成果次第で高収入を得られる可能性が高いことが挙げられます。
特に、不動産の売買仲介や投資用物件の販売などを手掛ける営業職では、個人の業績に応じてインセンティブ、つまり歩合給が支払われる給与体系が一般的です。
これは、固定給に加えて、自分が仲介した契約の金額や件数に応じた報酬が上乗せされる仕組みです。
そのため、大きな契約を成立させれば、一度に数百万円のインセンティブを手にすることも夢ではありません。
実際に、20代で年収1000万円を超えるトップ営業も数多く存在します。
学歴や年齢は関係ありません。
お客様との信頼関係を築き、成果を出し続けることができれば、それに見合った報酬を得ることができます。
自分の努力が直接収入に反映されるこの仕組みは、仕事に対する強いモチベーションとなり、常に高い目標を掲げて挑戦し続けたいと考える人にとって、非常に魅力的な環境であるといえるでしょう。
学歴不問が多い
不動産業界は、他の業界と比較して学歴不問の求人が多いことも大きな特徴です。
特に営業職の採用においては、出身大学の名前よりも、コミュニケーション能力や誠実さ、目標達成への意欲といった個人のポテンシャルが重視される傾向にあります。
これは、不動産の売買や賃貸といった仕事が、お客様との信頼関係をいかに築けるかが最も重要であるためです。
学歴に自信がない人でも、人柄や熱意を評価され、誰もが知る大手企業で活躍できるチャンスが十分にあります。
また、多くの企業では、入社後の研修制度が非常に充実しています。
不動産に関する専門知識や法律、営業のノウハウなどを基礎から体系的に学べるため、未経験からでも安心してキャリアをスタートさせることが可能です。
学歴というフィルターにとらわれず、誰もが平等に挑戦できる門戸の広さは、多様な人材が活躍できる不動産業界ならではの魅力といえるでしょう。
【不動産業界やめとけ】ホワイト企業の見つけ方
不動産業界には厳しいイメージがある一方で、社員を大切にし、働きやすい環境を整えている、いわゆるホワイト企業も数多く存在します。
就職活動を成功させる鍵は、こうした企業をいかにして見つけ出すかにかかっています。
インターネット上の評判や表面的な情報だけで判断するのではなく、客観的なデータや多角的な視点から企業を分析することが重要です。
ここでは、不動産業界の中から自分に合ったホワイト企業を見つけるための具体的な方法を3つご紹介します。
これらの方法を実践することで、入社後のミスマッチを防ぎ、心から満足できるキャリアの第一歩を踏み出すことができるでしょう。
離職率の低い企業
企業の働きやすさを客観的に判断するための最も重要な指標の一つが、離職率です。
特に、新卒で入社した社員が3年以内にどれだけ定着しているかを示す「新卒3年後定着率」は、その企業が若手社員を大切に育てているかどうかのバロメーターになります。
離職率が低いということは、それだけ社員の満足度が高く、労働環境や人間関係、福利厚生、キャリアパスなどに大きな不満が少ないことの表れといえます。
企業の採用ホームページや、就職四季報などの就職情報誌には、離職率や平均勤続年数が掲載されている場合がありますので、必ず確認するようにしましょう。
もしデータが公開されていない場合は、OB・OG訪問や面接の際に、差し支えない範囲で質問してみるのも一つの方法です。
離職率の低さは、社員が長期的に安心して働ける環境であることの有力な証拠となります。
口コミを確認する
企業の公式情報だけでは分からない、社内のリアルな雰囲気や実情を知るためには、就職活動者向けの口コミサイトを活用することが非常に有効です。
そこには、実際にその企業で働いていた元社員や、現役で働いている社員からの率直な意見が数多く投稿されています。
例えば、給与や昇進の満足度、残業時間の実態、有給休暇の取得しやすさ、上司や同僚との人間関係、社内のカルチャーなど、説明会では聞けないような具体的な情報を得ることができます。
特に、ポジティブな口コミだけでなく、ネガティブな口コミにもしっかりと目を通すことが重要です。
どのような点に不満を感じる人がいるのかを知ることで、自分にとってそれが許容できる範囲なのかを判断する材料になります。
ただし、口コミはあくまで個人の主観に基づいた情報であるため、一つの意見を鵜呑みにせず、複数のサイトを比較検討しながら、総合的に判断する姿勢が大切です。
ホームページを確認する
企業の公式ホームページは、その会社が社員をどのように考えているかを知るための情報の宝庫です。
事業内容や業績だけでなく、働き方に関するページを注意深く読み解きましょう。
特に確認すべきは、福利厚生制度、研修制度、そしてキャリアパスの3つの項目です。
住宅手当や家族手当、資格取得支援制度などが充実しているか、新入社員研修から階層別研修まで、社員の成長を継続的にサポートする体制が整っているか、そして社員が将来どのようなキャリアを築いていけるのか、具体的なモデルケースが示されているかなどをチェックします。
また、社員紹介のページで、どのような人がどのようなやりがいを持って働いているのかを知ることも、社風を理解する上で非常に参考になります。
生き生きと働く社員の姿が多く紹介されている企業は、社員満足度が高い傾向にあります。
【不動産業界やめとけ】業界の将来性
就職活動において、業界の将来性を見極めることは非常に重要です。
人口減少やテクノロジーの進化など、社会が大きく変化する中で、不動産業界は今後どのように変わっていくのでしょうか。
ネガティブなイメージが先行することもありますが、業界を取り巻く環境を正しく理解すれば、そこに新たなビジネスチャンスや将来性を見出すことができます。
ここでは、不動産業界の未来を予測する上で参考となる3つのトレンドについて解説します。
これらの情報を基に、不動産業界がこれから先も持続的に成長していけるのか、そして自分がその中でどのように活躍していきたいのかを考えてみましょう。
不動産会社の事業所数は増加傾向
意外に思われるかもしれませんが、国土交通省の調査によると、宅地建物取引業者、つまり不動産会社の事業所数は、近年増加傾向にあります。
これは、比較的少ない資本で開業できるため新規参入のハードルが低いことや、他業種の大手企業が不動産事業に参入するケースが増えていることなどが背景にあります。
市場に新たなプレイヤーが増え続けているということは、それだけ不動産業界にビジネスチャンスがあると見なされている証拠であり、業界全体の活気を示していると捉えることができます。
もちろん、競争が激化するという側面もありますが、多様なサービスが生まれることで業界全体が活性化し、消費者にとっては選択肢が増えるというメリットもあります。
このデータは、不動産業界が決して斜陽産業ではなく、むしろ成長と変化の可能性を秘めた分野であることを示唆しています。
規模は減少傾向にある
事業所数が増加している一方で、業界全体の市場規模としては、横ばい、もしくは微減傾向にあるという見方もあります。
これは、従業員数が数名程度の小規模な事業者が増加しており、一社あたりの売上規模が小さくなっていることが一因と考えられます。
不動産業界は、全国規模で事業を展開する大手デベロッパーや仲介会社が市場の大部分を占める一方で、特定の地域に密着してきめ細やかなサービスを提供する無数の小規模な会社によって支えられているという構造を持っています。
就職活動においては、単に企業の規模の大きさだけで判断するのではなく、その企業がどのような強みを持っているのかを見極めることが重要です。
例えば、特定のエリアの不動産情報に精通している、富裕層向けの物件に特化している、リノベーション事業に強みを持っているなど、規模は小さくても独自の価値を提供して成長している企業は数多く存在します。
今後はDXが求められる
伝統的に対面でのやり取りや紙の書類を重視してきた不動産業界ですが、今後はDX、すなわちデジタルトランスフォーメーションの推進が、企業の成長を左右する最も重要な鍵となります。
具体的には、VR(バーチャルリアリティ)技術を用いて遠隔地からでも物件の内部を詳細に確認できるオンライン内見や、膨大なデータからAIが物件の適正価格を算出する価格査定システム、契約手続きをオンラインで完結させる電子契約などが急速に普及していくでしょう。
また、顧客情報を一元管理し、個々のニーズに合わせた最適な提案を行うためのCRM(顧客関係管理)システムの活用も不可欠になります。
これらのデジタル技術を積極的に導入することで、業務の効率化を図り、顧客満足度を向上させることができます。
これからの不動産業界で活躍するためには、ITリテラシーや新しい技術を積極的に学び、活用していく姿勢が強く求められます。
【不動産業界やめとけ】おすすめの対策方法
不動産業界への就職を成功させるためには、やみくもにエントリーするのではなく、戦略的に対策を立てて行動することが不可欠です。
業界特有の事情や、企業ごとの文化の違いを深く理解し、自分に合った企業をいかに見つけ出すかが、入社後のミスマッチを防ぐための鍵となります。
情報収集を制する者が、就職活動を制するといっても過言ではありません。
ここでは、不動産業界を目指す就活生が、納得のいくキャリア選択をするために、ぜひ実践してほしい具体的な対策方法を3つご紹介します。
これらの方法を組み合わせることで、より効率的かつ効果的に就職活動を進めることができるでしょう。
就活エージェントを利用する
自分一人での企業探しや選考対策に不安を感じる場合は、就活エージェントを積極的に利用することをおすすめします。
就活エージェントとは、専任のキャリアアドバイザーが、個別のカウンセリングを通じてあなたの強みや適性、希望をヒアリングし、それに合った企業を紹介してくれるサービスです。
一般には公開されていない非公開求人を紹介してもらえる可能性があるほか、応募書類の添削や模擬面接など、選考を突破するための具体的なサポートを無料で受けることができます。
特に、不動産業界に特化したエージェントであれば、業界の最新動向や各企業の社風といった、より専門的で深い情報を提供してくれます。
第三者の客観的な視点からアドバイスをもらうことで、自分では気づかなかった新たな可能性を発見できるかもしれません。
効率的に、かつ安心して就職活動を進めるための心強いパートナーとなるでしょう。
企業研究を行う
入社後のミスマッチを防ぐために最も重要で、かつ基本的な対策が、徹底した企業研究です。
企業のホームページや採用サイト、会社案内などを読み込むことはもちろんですが、それだけでは不十分です。
有価証券報告書などのIR情報を確認して経営状況を分析したり、業界紙やニュースサイトでその企業の最近の動向をチェックしたりと、多角的な視点から情報を集めましょう。
特に不動産業界は、同じ業界内でも、マンション開発を手掛けるデベロッパー、売買を専門とする仲介会社、物件管理を主軸とする管理会社など、ビジネスモデルによって仕事内容や働き方、求められるスキルが大きく異なります。
それぞれの企業が、どの事業領域に強みを持ち、どのような戦略で成長しようとしているのかを深く理解することが不可欠です。
自分がその企業の一員として、どのように貢献できるのかを具体的に語れるレベルまで研究を深めることが、内定への近道となります。
OB・OG訪問を行う
企業の本当の姿を知るために、OB・OG訪問は非常に有効な手段です。
実際にその企業で働く先輩社員から直接話を聞くことで、ホームページや説明会だけでは決して得られない、リアルな情報を得ることができます。
例えば、仕事の具体的なやりがいや、逆に大変だと感じること、職場の人間関係や雰囲気、残業や休日出勤の実態、評価制度など、気になるけれど面接では聞きにくいような質問も、OB・OG訪問の場であれば尋ねやすいでしょう。
訪問を依頼する際は、大学のキャリアセンターを通じて紹介してもらう方法が一般的ですが、最近ではSNSなどを活用して個人的に連絡を取る学生も増えています。
訪問前には、企業のウェブサイトを読み込んで質問リストを作成しておくなど、事前の準備をしっかりと行い、限られた時間を有意義なものにすることが大切です。
まとめ
不動産業界はやめとけという言葉は、この業界が持つ厳しい側面を捉えたものですが、それは一面的な見方に過ぎません。
ノルマやクレーム対応、不規則な勤務形態など、確かに大変な部分はありますが、それ以上に、成果が正当に評価され高収入を目指せること、社会に大きく貢献できること、学歴に関わらず誰もが挑戦できることなど、多くの魅力とやりがいに満ちた業界でもあります。
大切なのは、ネガティブな評判に惑わされることなく、あなた自身の目で業界の実態を確かめることです。
企業研究を徹底し、OB・OG訪問などを通じて生の声に触れることで、自分に合った企業は必ず見つかります。
この記事で紹介した情報を参考に、不動産業界への理解を深め、自信を持って就職活動に臨んでください。
あなたの挑戦を心から応援しています。