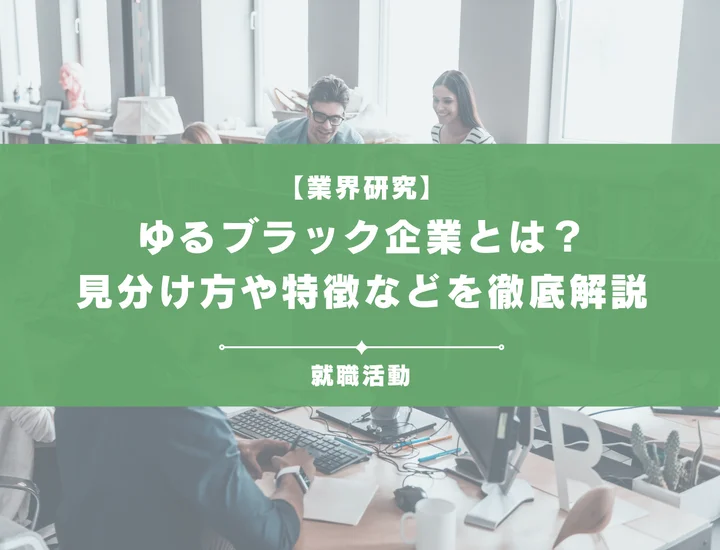HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
就職活動において、多くの学生がブラック企業を避けたいと考えるのは当然です。
しかし近年、その対極にあるような、働きやすいけれど成長が見込めない、ゆるブラック企業という存在が注目されています。
残業やノルマに追われる生活は望まない、でも自分の市場価値が高まらない環境も不安だ、という悩みは多くの就活生が抱えるものでしょう。
この記事では、ゆるブラック企業とは何か、その定義から特徴、見抜き方までを網羅的に解説します。
ご自身のキャリアプランと照らし合わせながら、後悔のない企業選びをするための参考にしてください。
【ゆるブラック企業】とは
ゆるブラック企業という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、具体的にどのような企業を指すのでしょうか。
一見すると、働きやすく魅力的に見えるこの言葉には、長期的なキャリアを考える上で注意すべき側面も含まれています。
ここでは、ゆるブラック企業の定義や、しばしば混同されがちなホワイト企業との違い、そしてなぜ今この言葉が注目を集めているのかについて、その背景から詳しく掘り下げていきます。
自分にとって最適な企業を見極めるための、正しい知識を身につけましょう。
定義
ゆるブラック企業とは、一般的に、残業が少なく休日もしっかり取れて、人間関係のストレスやハラスメントもない、いわゆる働きやすい環境である一方で、仕事のやりがいや自己成長の機会が乏しい企業を指す言葉です。
過酷な労働環境を強いるブラック企業とは真逆の性質を持ちながら、社員の長期的なキャリア形成にとってはマイナスに作用する可能性があるため、ゆるいブラックと表現されます。
具体的には、誰にでもできる単調な業務が多く、専門的なスキルが身につかない、成果を出しても評価や給与に反映されにくい、といった特徴が挙げられます。
プライベートの時間を確保しやすいというメリットがある反面、自身の市場価値を高め、将来の選択肢を広げたいと考える人にとっては、物足りなさを感じる環境と言えるでしょう。
ホワイト企業との違い
ゆるブラック企業とホワイト企業は、どちらも残業が少なく福利厚生が整っているなど、働きやすい環境である点は共通しています。
しかし、両者の間には決定的な違いが存在します。
それは、社員の成長を促す仕組みや文化があるかどうかです。
真のホワイト企業は、働きやすい環境を提供することに加えて、社員一人ひとりのキャリア形成を積極的に支援します。
例えば、挑戦的な仕事を任せる風土があったり、充実した研修制度や資格取得支援制度が整っていたり、成果を正当に評価する人事制度が機能していたりします。
一方で、ゆるブラック企業は、ただ楽なだけで、社員を育てようという意識が低い傾向にあります。
働きやすさという表面的な魅力だけでなく、その企業で働くことを通じて自分がどのように成長できるのか、長期的な視点で見極めることが両者を見分ける上で非常に重要になります。
なぜ注目されてるのか
ゆるブラック企業という言葉が注目されるようになった背景には、社会全体の働き方の変化と、若い世代の価値観の多様化があります。
働き方改革の推進により、多くの企業で長時間労働の是正が進みました。
その結果、残業は少ないものの、業務内容が薄まり、成長機会が失われてしまう企業が生まれてきたのです。
また、Z世代と呼ばれる現代の若者は、仕事一辺倒の生活よりもプライベートの充実を重視する傾向があります。
そのため、定時で帰れて休日も多い環境は、一見すると非常に魅力的に映ります。
しかし、その一方で、終身雇用が当たり前ではなくなった現代において、将来への不安から専門的なスキルを身につけて自分の市場価値を高めたいと考える人も少なくありません。
このワークライフバランスを重視する価値観と、キャリアへの不安という二つの思いの間で揺れ動く就活生が多いことから、ゆるブラック企業という存在が注目を集めているのです。
【ゆるブラック企業】特徴3選
では、ゆるブラック企業には具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
働きやすいというメリットの裏に隠された注意すべき点を知ることで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
ここでは、ゆるブラック企業によく見られる三つの特徴を挙げ、それぞれを詳しく解説していきます。
これらの特徴を理解し、企業研究の際にチェックするべきポイントとして活用してください。
自分が入社後、いきいきと働ける環境かどうかを判断するための重要な指標となるでしょう。
仕事が単調でスキルが身につかない
ゆるブラック企業の最も代表的な特徴は、日々の業務が単調なルーティンワークで占められていることです。
業務が過度にマニュアル化されており、誰がやっても同じ成果を出せるように標準化されているため、個人の創意工夫や思考力が求められる場面がほとんどありません。
例えば、毎日同じデータを入力する作業や、決められた手順通りに書類を作成する業務などがこれにあたります。
こうした仕事は覚えるのが簡単で精神的な負担は少ないかもしれませんが、数年続けても市場価値の高い専門的なスキルや経験を身につけることは困難です。
変化の激しい現代において、社外では通用しないスキルしか持たない人材になってしまうリスクがあります。
その結果、いざ転職を考えた際に、アピールできる実績がなく、キャリアの選択肢が著しく狭まってしまう可能性があるのです。
評価基準があいまい
成果を出しても出さなくても評価が変わらない、というのもゆるブラック企業の典型的な特徴です。
年功序列の風潮が根強く残っており、個人のパフォーマンスよりも勤続年数や年齢が重視される傾向にあります。
明確な評価基準や目標設定制度が存在しない、あるいは形骸化しているため、社員がどれだけ努力して成果を上げても、それが給与や昇進に適切に反映されません。
このような環境では、社員のモチベーションは自然と低下していきます。
頑張っても報われないのであれば、最低限の仕事だけをこなそうと考えるようになるのは当然のことでしょう。
結果として、社内には挑戦や自己成長に対する意欲が低い社員が増え、組織全体が停滞してしまう、いわゆるぬるま湯体質と呼ばれる状態に陥りがちです。
挑戦より安定を重視する社風
ゆるブラック企業には、新しいことへの挑戦を歓迎せず、現状維持を最優先する保守的な社風が見られます。
過去の成功体験に固執し、変化をリスクと捉える傾向が強いため、若手社員が新しいアイデアを提案しても、前例がないことを理由に却下されることが少なくありません。
失敗を極端に恐れる文化が根付いているため、社員は積極的に行動することをためらい、指示されたことだけをこなすようになります。
このような環境では、自ら課題を発見し、解決策を考えて実行するといった、ビジネスパーソンとして重要な能力を養う機会がほとんどありません。
安定しているように見えても、市場の変化に対応できず、企業の将来性が危ぶまれる可能性も秘めています。
自身の成長を望む人にとっては、閉塞感を感じやすい環境と言えるでしょう。
【ゆるブラック企業】多い業界・職種
ゆるブラック企業は、特定の業界や職種に偏って存在する傾向があります。
もちろん、これから挙げる業界や職種のすべての企業がそうだというわけでは決してありませんが、構造的にゆるブラック企業になりやすい要因を抱えているケースがあるのは事実です。
こうした傾向を知っておくことで、企業選びの際に注意すべきポイントがより明確になります。
あくまで一つの参考情報として、ご自身の企業研究に役立ててください。
大切なのは、業界や職種といった大きな括りだけでなく、個々の企業の実態をしっかりと見極めることです。
地方の中小企業
一部の地方に拠点を置く中小企業には、ゆるブラック企業の特徴が見られることがあります。
その背景には、特定の地域に深く根差し、長年にわたって安定した顧客基盤を築いているケースが多いことが挙げられます。
競合他社が少なく、市場環境の変化が緩やかであるため、企業として新たな挑戦をする必要性に迫られにくいのです。
その結果、事業内容や働き方が何十年も変わらず、社内全体が現状維持を好む保守的な雰囲気になりがちです。
また、都市部に比べて人材の流動性が低いため、旧来の年功序列制度が温存されやすく、若手が成長できる機会が限られてしまうこともあります。
もちろん、地方には革新的で成長意欲の高い優良な中小企業も数多く存在するため、企業ごとの文化や方針を個別に見極めることが何よりも重要です。
事務職・ルーティンワーク系
一般事務や経理事務、データ入力といった、いわゆる事務職やルーティンワークが中心となる職種も、ゆるブラック企業的な環境になりやすい傾向があります。
これらの職種は、業務の正確性や効率性が重視されるため、作業手順が細かくマニュアル化されていることが多く、個人の裁量で仕事を進める場面が少ないのが特徴です。
日々の業務が定型化されているため、一度覚えてしまえば楽にこなせるようになる一方で、新しい知識やスキルを習得する機会は限られます。
ただし、同じ事務職であっても、業務改善の提案が奨励されたり、より専門性の高い業務に挑戦させてもらえたりする企業も存在します。
求人票を見る際には、単に事務職と書かれているだけでなく、その仕事を通じてどのようなスキルが身につくのか、キャリアアップの道筋が示されているかを確認することが大切です。
新規事業が少ない安定志向
インフラ業界や、特定の許認可に基づいて事業を行う企業、あるいは成熟した市場で高いシェアを持つメーカーなど、事業基盤が非常に安定している企業群にも、ゆるブラック企業の特徴が見られることがあります。
これらの企業は、安定した収益モデルが確立されているため、リスクを取ってまで新規事業に積極的に投資する必要性が低い場合があります。
その結果、社内の雰囲気は落ち着いていて働きやすいものの、変化や挑戦の機会は少なくなります。
若手社員は既存事業の維持管理に関わる業務が中心となり、事業をゼロから立ち上げるようなダイナミックな経験を積むことは難しいかもしれません。
企業の安定性は大きな魅力ですが、その安定が成長の機会を妨げていないか、新しい取り組みに対する姿勢はどうなのか、といった点を確認することが重要です。
【ゆるブラック企業】入るリスクとは
残業が少なく、精神的なプレッシャーも少ないゆるブラック企業は、一見すると理想的な職場に思えるかもしれません。
しかし、長期的なキャリアという視点で見ると、いくつかの重大なリスクをはらんでいます。
目先の働きやすさだけにとらわれず、5年後、10年後の自分の姿を想像したときに、その環境が本当に自分にとってプラスになるのかを冷静に考える必要があります。
ここでは、ゆるブラック企業に入社することで生じうる三つの具体的なリスクについて解説します。
キャリアの停滞・転職が難しい
ゆるブラック企業で働くことの最大のリスクは、キャリアの停滞です。
日々の業務が単調で、挑戦的な仕事も少ないため、専門的なスキルや知識、そして問題解決能力といったポータブルスキルが身につきません。
その結果、社外の労働市場で通用する人材、つまり市場価値の高い人材になることが難しくなります。
数年間その環境に身を置いた後、いざ転職しようと思っても、職務経歴書に書けるような実績やアピールできるスキルが何もない、という事態に陥りかねません。
特に、年齢を重ねるにつれて、同世代の他の企業で働く人たちとのスキルや経験の差はどんどん開いていきます。
キャリアアップを目指したくても、選択肢が限られてしまい、結果的にその会社に留まらざるを得なくなる可能性が高まるのです。
年収が上がりにくい
年収が上がりにくいことも、ゆるブラック企業が抱える大きなリスクの一つです。
多くのゆるブラック企業では、評価基準があいまいであったり、年功序列制度が根強く残っていたりするため、個人の成果が給与に反映されにくい構造になっています。
どれだけ頑張って成果を出しても、大幅な昇給やインセンティブは期待できず、給与は年齢とともにごく僅かずつしか上がっていかないケースがほとんどです。
また、企業自体が新しい事業に挑戦せず、市場の成長から取り残されている場合、会社の業績が大きく伸びることも期待できません。
その結果、世の中の平均年収が上昇していく中で、自社の給与水準だけが停滞し、相対的に収入が低くなってしまう可能性があります。
若いうちは良くても、将来的に家庭を持つことなどを考えると、経済的な不安につながるかもしれません。
成長意欲が下がる
人間は環境に影響される生き物です。
ゆるブラック企業のぬるま湯のような環境に長期間身を置いていると、かつて持っていたはずの成長意欲や向上心が徐々に失われていくリスクがあります。
周りの同僚も挑戦や変化を好まず、最低限の仕事だけをこなすという姿勢であれば、自分もそれで良いと感じるようになってしまうのです。
新しいことを学んだり、スキルを磨いたりすることへのモチベーションが低下し、仕事に対してやりがいや面白みを感じられなくなってしまいます。
最初は楽で良いと思っていた環境が、いつしか自分を無気力にさせ、自己成長の機会を奪っていくことになりかねません。
仕事を通じて何かを成し遂げたい、専門性を高めたいという気持ちがある人にとっては、この意欲の低下が最も深刻なリスクと言えるかもしれません。
【ゆるブラック企業】見抜き方はあるのか
ゆるブラック企業を就職活動の段階で見抜くことは、決して簡単ではありません。
なぜなら、求人票や企業のウェブサイトでは、働きやすさや安定性といったポジティブな側面が強調されがちだからです。
しかし、いくつかのポイントに注意して情報収集を行えば、その企業がゆるブラック企業である可能性を見極めるヒントを得ることは可能です。
ここでは、就活生が実践できる具体的な見抜き方を三つのアプローチから紹介します。
一つの情報源を鵜呑みにせず、多角的な視点で企業を分析することが重要です。
求人票・説明会でのチェックポイント
まずは、求人票や会社説明会といった公式な情報から得られるヒントに注目しましょう。
求人票の仕事内容の欄が、誰にでもできる、簡単な作業、サポート業務といった抽象的な言葉だけで埋められており、具体的な業務内容や求められるスキルについての記述が乏しい場合は注意が必要です。
また、成長できる環境をアピールしているにもかかわらず、具体的な研修制度やキャリアパスについての説明が曖昧な場合も同様です。
会社説明会では、積極的に質問をすることが有効です。
特に、若手社員の具体的な仕事内容や、これまでに最も成長を実感できた経験、失敗から学んだエピソードなどを尋ねてみましょう。
その回答が具体的で、熱意が感じられるものであれば安心材料になりますが、もし回答が曖昧だったり、当たり障りのない内容に終始したりするようであれば、慎重に判断する必要があります。
社員の口コミや評判
次に有効なのが、就職情報サイトなどに掲載されている、実際にその企業で働く社員や元社員による口コミ情報を参考にすることです。
これらの情報は、企業の公式発表では分からない、社内のリアルな雰囲気や実態を知るための貴重な手がかりとなります。
特に注目すべきは、仕事のやりがい、成長環境、20代の成長環境、人事評価の適正感といった項目です。
これらの評価が著しく低い場合や、仕事が楽で定時に帰れること以外のポジティブな書き込みが少ない場合は、ゆるブラック企業である可能性が考えられます。
ただし、口コミはあくまで個人の主観に基づいた意見であるため、一つの書き込みを鵜呑みにするのは危険です。
複数のサイトで情報を比較検討し、できるだけ多くの意見に目を通して、全体的な傾向を掴むように心がけましょう。
OB・OG訪問
ゆるブラック企業を見抜く上で最も効果的な方法が、OB・OG訪問です。
実際にその企業で働く大学の先輩から、直接、本音の話を聞くことができます。
ウェブサイトや口コミだけでは得られない、生きた情報を手に入れる絶好の機会です。
訪問の際には、日々の仕事の具体的な流れ、仕事のやりがいや大変な点、入社後にどのようなスキルが身についたか、そして今後のキャリアプランなどを遠慮なく質問してみましょう。
特に、入社3年から5年目の若手の先輩に話を聞くと、自身が入社した後の姿を具体的にイメージしやすくなります。
先輩社員がいきいきと自身の仕事について語ってくれるか、明確な目標を持って働いているか、といった点を注意深く観察することで、その企業が若手の成長を後押しする文化を持っているかどうかを肌で感じ取ることができるでしょう。
【ゆるブラック企業】就活時に注意する点
ゆるブラック企業を避けて、自分に合った企業を見つけるためには、企業選びの段階で意識すべきいくつかの重要な注意点があります。
単に情報を集めるだけでなく、その情報を自分自身の価値観と照らし合わせて判断するプロセスが不可欠です。
ここでは、入社後のミスマッチを防ぎ、納得のいくキャリアの第一歩を踏み出すために、就職活動中に特に注意してほしい三つのポイントについて解説します。
これらを実践することで、表面的な情報に惑わされず、企業の本質を見抜く力が養われるはずです。
企業研究は「仕事内容」から
企業選びを行う際、多くの学生は企業の知名度や給与、福利厚生といった待遇面にまず目が行きがちです。
しかし、ゆるブラック企業を避けるという観点では、何よりもまず入社後に自分が担当することになる仕事内容を徹底的に深掘りすることが重要です。
その企業で働くことは、一日の大半をその仕事に費やすことを意味します。
その仕事が単調な作業の繰り返しなのか、それとも日々新しい課題に取り組むものなのか。
どのようなスキルが求められ、経験を積むことでどのような専門性が身につくのか。
具体的な業務内容と、そこから得られる成長の可能性を詳しく調べることで、その企業が自分にとってのゆるブラック企業に該当するかどうかを判断する精度が格段に上がります。
企業のブランドイメージだけでなく、そこで働く自分の姿をリアルに想像することが大切です。
OB訪問やインターンで社風を体感する
企業のウェブサイトや採用パンフレットには、挑戦を歓迎する、風通しの良い社風といった魅力的な言葉が並んでいます。
しかし、それが本当かどうかは、実際に社内の空気に触れてみないと分かりません。
そこで強く推奨されるのが、OB・OG訪問やインターンシップへの参加です。
これらの機会を活用して、社員の方々と直接コミュニケーションをとり、その企業の文化を肌で感じ取ることが極めて重要です。
社員の方々はどのような表情で働いているか、職場には活気があるか、若手社員が積極的に意見を言える雰囲気があるか。
インターンシップに参加すれば、実際の業務を体験しながら、社員同士のやり取りや職場の日常を垣間見ることができます。
こうした現場での体感が、自分とその企業の相性を見極めるための何よりの判断材料となるのです。
就活軸を明確にする
最終的に最も重要なことは、自分自身の就活軸を明確にすることです。
そもそも、どのような企業をゆるブラック企業と感じるかは、人それぞれの価値観やキャリアプランによって異なります。
仕事よりもプライベートを最優先し、安定した環境で着実に働きたいと考える人にとっては、ゆるブラック企業はむしろ理想的な職場かもしれません。
一方で、若いうちから多くの経験を積み、圧倒的に成長したいと考える人にとっては、避けるべき環境となります。
だからこそ、まずは自己分析を徹底的に行い、自分が仕事に何を求めるのか、どのような働き方をしたいのか、将来どのようなキャリアを築きたいのかを具体的に言語化する必要があります。
自分の軸が定まっていれば、企業の情報を収集する際にも、自分にとって重要なポイントは何かを見失うことなく、冷静な判断を下すことができるようになります。
よくある質問
ここまで、ゆるブラック企業の様々な側面について解説してきましたが、就活生の皆さんの中には、まだいくつかの疑問が残っているかもしれません。
ここでは、ゆるブラック企業に関して特によく寄せられる二つの質問を取り上げ、それぞれの問いに対してお答えしていきます。
これらの回答を通じて、ゆるブラック企業に対する理解をさらに深め、ご自身の企業選びにおける判断の一助としてください。
ゆるブラック企業は悪いこと?
ゆるブラック企業は、一概に悪いものだと断定することはできません。
その評価は、個人の価値観やライフプランに大きく左右されるからです。
例えば、仕事はあくまで生活のための手段と割り切り、趣味や家庭、自己投資など、プライベートの時間を何よりも大切にしたいと考える人にとっては、残業がなく定時で帰れるゆるブラック企業は非常に魅力的な選択肢となり得ます。
また、他に明確な目標があり、仕事に大きなエネルギーを割きたくないという人にとっても、精神的・体力的な負担が少ない環境は好都合でしょう。
問題なのは、成長意欲が高い人が、その実態を知らずに入社してしまうことで生じるミスマッチです。
重要なのは、その企業が自分自身の仕事に対する価値観や将来の目標と合致しているかどうかを、入社前に見極めることなのです。
見抜けず入社してしまったら?
もし、ゆるブラック企業だと気づかずに入社してしまった場合でも、すぐに悲観する必要はありません。
まずは、その環境の中で自分にできることを見つけて行動してみましょう。
例えば、業務に関連する資格の勉強を始めたり、社外のセミナーや勉強会に参加してスキルアップを図ったりと、自己投資の時間は十分に確保できるはずです。
また、与えられた業務をただこなすだけでなく、効率化や改善の提案を積極的に行ってみるのも良いでしょう。
それでも状況が変わらず、将来への強い不安が拭えないのであれば、転職を視野に入れることも一つの有効な選択肢です。
特に若いうちであれば、第二新卒としてポテンシャルを評価してくれる企業も多く存在します。
今回の経験を、次の企業選びの軸を明確にするための貴重な学びだったと捉え、前向きに行動することが大切です。
まとめ
この記事では、ゆるブラック企業の定義から特徴、見抜き方、そして就活時に注意すべき点までを詳しく解説しました。
ゆるブラック企業とは、残業が少なく働きやすい一方で、自己成長の機会が乏しく、長期的なキャリア形成にリスクを伴う可能性のある企業のことです。
重要なのは、それが自分にとって良い企業なのか、悪い企業なのかを、自分自身の就活軸に照らし合わせて判断することです。
表面的な働きやすさや企業の知名度だけで判断するのではなく、具体的な仕事内容や社風、成長環境といった本質的な部分に目を向けることが、後悔のない企業選びに繋がります。
求人票の確認はもちろん、口コミサイトの活用、そしてOB・OG訪問やインターンシップを通じて、多角的に情報を収集し、企業のリアルな姿を掴む努力を怠らないでください。
最終的には、自分が仕事に何を求めるのかを明確にし、納得のいくキャリアの第一歩を踏み出しましょう。