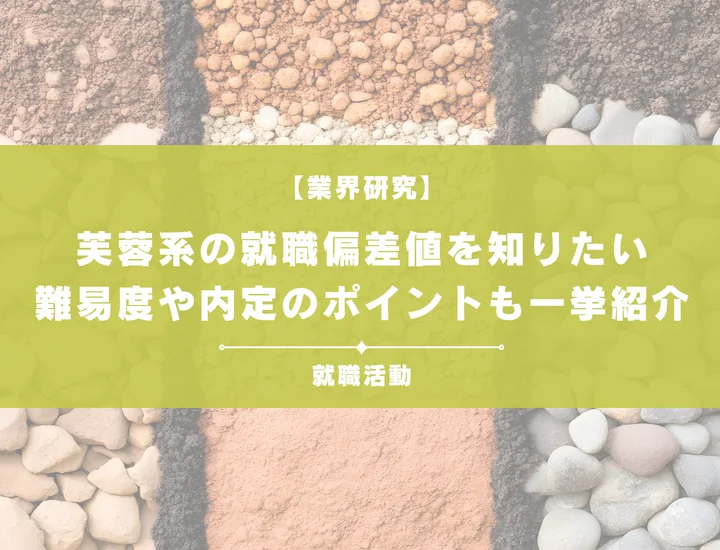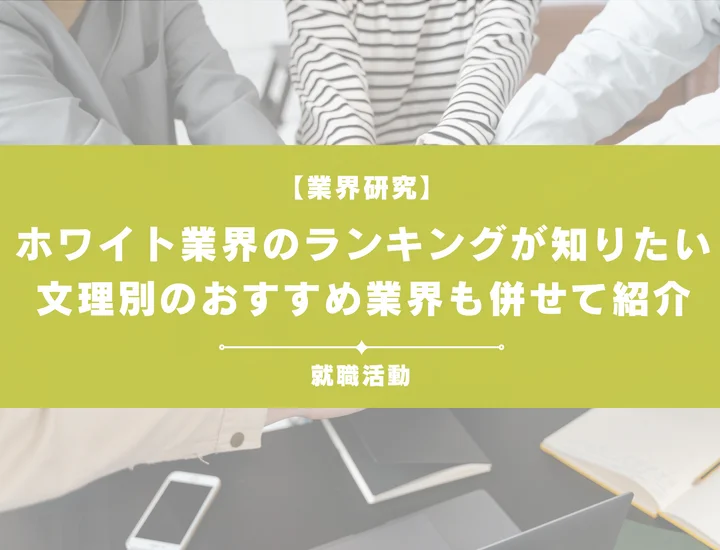HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
開発職で働くことを考えている方のために、開発職の基本的な役割、仕事内容、求められるスキル、そして、開発職として成功するために必要な要素について紹介します。
開発職を将来の職業の第一志望に据えている方はもちろんのこと、なんとなく興味がある方もぜひ、本記事を参考にしてみてください。
【開発職 向いている人】開発職とは
まずは、開発職の業務内容について簡単に知っておきましょう。
すでに理解がある人は飛ばしても構いません。
開発職は、新技術の研究から製品の設計、開発、さらには市場への導入までを一手に担う重要な職種であり、経済の成長や技術の進歩の推進力として非常に重要な役割を果たしています。
その活動範囲の広さから、制約やテクノロジー、製造業といった多様な産業にまたがり、それぞれの分野で専門知識と技術を発揮しています。
開発職の担当者は新たな技術の研究を行い、実用化に向けた技術開発も行います。
例えば、製薬業界では新薬の開発には科学や生物学の知識が不可欠であり、長年にわたる研究も重要です。
テクノロジー業界ならば、新しいソフトウェア、ハードウェアの開発がこれに当たり、急速に進化する市場要求に大きな製品を生み出すために最新の技術トレンドを追いかける必要があります。
このように、開発職はただ単に新しい製品を作るだけでなく、技術的な挑戦に取り組み、製品を市場に導入するまでの全過程を総合的に管理する職種であり、その重要性は今後もさらに高まると考えられています。
将来性
技術の進化、特に情報技術や再生可能エネルギーなどの分野の進化は顕著です。
新しい発見やイノベーションが連続しており、新たな製品やサービスが市場に導入されています。
例えば、AIやビッグデータの進歩により多くの業界での作業プロセスに変革が起きています。
また、消費者のニーズも常に変化し続けており、新しい製品やサービスを開発して答えなければなりません。
例えば、環境への意識が高まっているため、よりエコフレンドリーな製品や持続可能な生産プロセスの需要も高まっています。
平均年収
開発職の平均年収は約548万円とされています。
この数値は、他の職種と比較して高い水準にあります。
その理由として、開発職には専門的なスキルや高度な技術が求められる点が挙げられます。
特に、プログラミングやシステム設計、製品開発に関する知識が不可欠であり、習得には時間と努力を要します。
また、IT業界や製造業など、技術革新の進展が著しい分野では、開発職の需要が高まっています。
さらに、開発職は経験やスキルによって給与が大きく変動する特徴があり、専門性が高まるほど収入の増加が見込めます。
【開発職 向いている人】主な仕事内容
続いて、開発職の主な仕事内容についても理解を深めておきましょう。
大きく分けて3つの業務があるため、それぞれ紹介します。
製品開発
製品開発は、新製品のアイデアから市場導入に至るまでの一連のプロセスを指し、アイデアの具現化や設計、テスト、そして最終的な市場への導入という段階に分かれます。
革新的な製品を生み出すために重要な業務であり、開発職の中でも特に重要な役割を果たします。
最初のステップは企画部門から新しい商品を企画することです。
ニーズを的確に捉え、それに応じて製品を思い描きます。
そして、アイデアを具体的な製品設計に落とし込みます。
技術者やデザイナーが協力して製品の詳細な設計図を作成するのです。
そして設計が完了すると、プロトタイプの制作とテストを行い、最終段階でテストを通過した製品が市場に導入されます。
このように、製品開発はアイデアの発想から市場導入にまで多岐にわたる工程を経て、新たな製品を送り出す業務です。
技術開発
技術開発は、開発職における重要な役割の1つです。
既存の技術の改善や新技術の開発を通じて、より効率的な製品を創出することを目的としています。
製品の性能の向上やコストの削減、環境への影響の軽減やユーザー体験の改善など多方面にわたるメリットを生み出すために、日々業務に取り組む仕事です。
市場調査や技術的な調査を行い、既存の製品やプロセスの限界点や改善の余地を特定します。
そして具体的な技術開発の計画を行い、研究開発チームが組織され共同でエンジニアや技術者が開発を進めていきます。
そして、性能試験や耐久性の試験、安全試験などの継続的なテストを行い、必要に応じて調整を行います。
このようなプロセスを経て開発された新技術や改良技術が製品化され、製造プロセスに統合される、または新しいサービスとして市場に導入されます
このように、技術開発は新しいアイデアを生み出すだけでなく、それを実用化し市場で競争力を持たせるために重要な役割を担います。
研究開発
研究開発は新しい知識の探求や技術の革新を目的とする仕事です。
科学的方法を用いて未知の領域を解明し、長期的な視点で業界や社会の進歩に寄与することを目的としています。
研究開発においては、まず現在の技術や科学的な進展を把握した上で、研究の出発点を定めます。
その後、具体的な研究課題を特定し、実験を行い、新しい材料や化合物、ソフトウェアのアルゴリズムなどを開発し、様々な条件下でテストを行います。
そして得られたデータを解析し、フィードバックに基づいて研究報告の調整を行います。
最終的に研究開発は新しい知識や技術を生み出すことを目指しますが、単に学問的な貢献を目指すだけでなく、実際に製品の開発や産業への応用を目指すことが大切です。
【開発職 向いている人】研究職との違い
開発職と研究職は、どちらも専門知識を活かす仕事ですが、その目的は大きく異なります。
研究職が未知の真理や技術を探求する「0から1を生み出す」仕事であるのに対し、開発職は研究成果などを基に製品やサービスを形にする「1を100にする」仕事です。
ここでは、その具体的な違いを3つの観点から解説します。
働く目的
研究職の主な目的は、新しい知識や技術を発見し、学術的な進歩に貢献することです。
論文の発表や学会での報告が、重要な成果となります。
一方、開発職の目的は、顧客のニーズや市場の課題を解決する製品・サービスを創り出し、事業に貢献することです。
製品の売上やユーザー満足度といった、ビジネス上の成果がゴールになります。
知的好奇心を満たすことか、世の中の課題解決か、どちらに重きを置くかが大きな違いです。
求められるスキル
研究職では、仮説を立てて検証を繰り返すための論理的思考力や、特定の分野を深く掘り下げる探究心が不可欠です。
前例のないことに挑戦する粘り強さも求められます。
対して開発職では、既存の技術を応用して製品化するための課題解決能力が重要です。
また、プロジェクトを円滑に進めるための、チームメンバーとのコミュニケーション能力やマネジメントスキルも必須となります。
納期やコストといった制約の中で、最適な解を見つけ出す能力が求められます。
評価基準
研究職の評価は、論文の引用数や学会での評価、特許の取得など、学術的なインパクトによって測られることが多いです。
成果が認められるまでには、長い年月がかかることもあります。
一方、開発職は、開発した製品の売上や利益、市場シェアといったビジネスへの貢献度が主な評価基準となります。
また、プロジェクトの納期遵守やコスト削減、品質なども評価の対象です。
比較的短期間で成果が問われる傾向にあります。
【開発職 向いている人】求められるスキル
続いて、開発職で求められるスキルについて考えてみましょう。
後ほど紹介する開発職に向いている人の5つの特徴と併せて、自分に備わっているかを確認してみてください。
当てはまる部分はより伸ばせるように、そして当てはまっていない部分は就活本番、もしくは就職までに改善できるように取り組みましょう。
問題解決能力
近年以前にも増して、多くの企業で求められるようになっている問題解決能力は、開発職にも求められています。
複雑な問題に直面した際に解決策を導き出すことは、開発職において重要です。
開発を行うにあたっては、未知の要素も多いため、まず問題の特定ができないことが多いです。
よって、問題解決能力を活用し、問題の本質を理解した上で、それがどのように発生したのか、何が原因であるのかを明確にできる人物が求められています。
問題が何であるのか、正確に特定ができないと、効果的に解決策を見つけることが難しいからです。
このようにして問題を特定した後に解決を行うというプロセスを繰り返すことで、開発職は仕事を進めていきます。
プロジェクト管理能力
開発職は基本的に1人で仕事をこなすことはありません。
新しい製品やソリューションを市場に投入するためには、様々な専門知識が必要であり、多くの専門家が参加します。
一人ひとり、得意なことは異なり、全員がプロジェクト管理能力を備えているわけではありません。
つまり、プロジェクトが円滑に進むように進行や状況、進捗の確認などを行えるプロジェクト管理能力が高い人物が求められています。
例えば、製薬業界なら、厳格な規制に基づいて臨床試験の設計から実施承認申請まで多くの段階を一貫して進捗を保たなければなりません。
テクノロジー分野なら、迅速に市場に投入し、技術の進化に対応するため効率的なプロジェクトの実行が求められます。
製造業においては、新製品の設計から生産、供給チェーンの管理までプロジェクト管理が製品の品質と生産の効率を左右します。
このように、開発職においては単純な技術だけでなく、プロジェクト全体を見渡し計画し、調整する能力が求められています。
ストレス耐性
開発職では、厳しい納期の中で作業を進めることが多く、プレッシャーに耐えながら業務を遂行する力が求められます。
特に、大規模なシステム開発や顧客の要求が頻繁に変わるプロジェクトでは、想定外のトラブルに直面することも珍しくありません。
問題が発生した際には、冷静に状況を分析し、適切な解決策を見出す能力が重要です。
また、長時間の作業や急な仕様変更など、柔軟に対応しながら開発を進めるためには、精神的なタフさも必要となります。
常に学び続ける姿勢
技術の進歩が速い開発職では、新しい技術やツールが次々と登場し、それらを活用することで開発効率が大きく向上します。
そのため、一度習得したスキルに満足せず、常に最新の知識を学び続ける姿勢が求められます。
特に、プログラミング言語やフレームワーク、クラウド技術、AIやデータ解析の分野では、新しい技術の登場が目まぐるしく、競争力を維持するためには継続的な学習が欠かせません。
また、企業によっては、新技術をいち早く導入し、競争優位性を確保することが求められるため、スピーディーなキャッチアップ能力も重要です。
コミュニケーション能力
開発はチームで進めることが一般的であり、他のエンジニアや関係者との円滑な連携が欠かせません。
プログラムの設計や仕様変更、トラブル発生時には、適切な情報共有ができるかどうかがプロジェクトの成功に直結します。
特に、プロジェクトマネージャーやデザイナー、営業担当者など、技術的な知識が異なるメンバーと協力する場面も多いため、専門用語を噛み砕いて説明するスキルも求められます。
また、単に会話ができるだけでなく、相手の意図を正しく理解し、適切なフィードバックを行うことが大切です。
【開発職 向いている人】向いている人の7つの特徴
続いて、開発職に向いている人の5つの特徴について一緒に確認してみましょう。
先ほど紹介した2つの開発職において求められるスキルと併せて、自分が開発職に向いているかの判断材料にしてください。
・技術的洞察力
・創造性
・詳細への注意
・チームでの協働性
・持続的な学習意欲
・発想力がある
・分析が得意
技術的洞察力
開発職においては、新しい技術の可能性を見極め、実用化する能力が求められています。
単に技術的に詳細な分析を行うだけでなく、それがどのようにして市場や社会に影響を与え、価値をもたらすかについて深く洞察する必要があるからです。
新技術が提供するソリューションが現在および将来の問題にどのように対応できるかについて分析し、技術が持つ革新的な側面を見出すことが求められます。
既存の市場ニーズだけでなく、新たな需要を創出するビジョンを持つことが大切です。
創造性
開発職は新しい価値を社会に提供する仕事であるため、創造性がある人物は大いに歓迎されます。
新しい製品やプロセスの開発において、革新的なソリューションを提供できれば、企業や業界全体の変革を促進可能です。
創造性のある人は、問題解決に対立する新しいアプローチをとれるだけでなく、難しい課題に対しても新たな視点から解決策を提供できます。
既存の技術や方法に依存することなく、新しい解決策を導き出すことで、より効率的またはコストパフォーマンスの高い手法を企業にもたらすことができます。
また、創造的な人物は、実験的であり、リスクを恐れない姿勢を持ち合わせていることが多く、むしろ失敗から学ぶ姿勢を持っているため、失敗しても挫けることなく、最終的に業界よりリードする革新を生み出せる可能性が高いです。
詳細への注意
開発職で働くにあたっては、注意力が非常に重要です。
なぜならば、開発職の人々が取り組む業務は小さなエラーや改善点を見落とすと、最終的に重要な問題に発展する可能性が高いからです。
例えば何かしらの新しいシステムの開発を行っている場合、設計やテストのフェーズにおいて細かな不具合や潜在的なリスクを発見することが重要です。
プログラムが完成間近になってバグが見つかった場合、どこが問題であるのか見つけるのに膨大な時間がかかります。
また、注意力があるということは、メンバー間でのコミュニケーションを強化することにもつながります。
同僚からのフィードバックに注意深く耳を傾けることができ、その情報を活用して自らの作業に反映させることができる人物は、色々な物事から良いことを吸収する考えを持っており、常に自分を成長させる、そしてプロジェクトをより良い方向に導くためにアンテナを張り巡らせています。
チームでの協働性
開発職においてはチームで共同できる人物が求められています。
先ほども話したように、開発職は基本的にプロジェクトで仕事を進めていくため、一人ひとりが役割をこなしつつ100%以上の力を発揮する必要があります。
特に複雑なプロジェクトや多くの職種が関与する作業において重要な役割を果たせる能力です。
協調性がある人物は、チーム内でのコミュニケーションと協力を促進し、目標達成に必要な調和を生み出すことも可能です。
協調性のある人物はまず、他のメンバーの意見やアイデアを注意深く聞き、それを理解し尊重することで、プロジェクトに対する共通の理解を促します。
また、協調性がある人物は、柔軟性も持ち合わせていることが多いため、必要に応じて自分の役割やアプローチを調整できます。
プロジェクトには予期せぬ問題が発生することが日常茶飯事であり、こうした状況においても効率的に対応し、チームが一致団結して前進できるように導く能力が求められています。
持続的な学習意欲
開発職においては、持続的な学習意欲も欠かせません。
常に最新の技術や知識を学び続ける姿勢がある人物は、技術が急速に進化し続ける現代において特に重要です。
変化し続ける市場のニーズに応じて自らのスキルをアップデートし、新しいチャレンジに適用する能力が高い人物は、開発職において高く評価されます。
新しい技術や知識が導入されるたびに対応しようと努力を続け、それらを活用しながら新しい価値を生み出そうと努力できる人物こそ開発職に適しています。
学習意欲がある人物は、チーム内での知識の共有にも積極的であり、自分が学んだ新しい技術や知識を周りに提供するだけでなく、周囲からの提案などにも柔軟に対応し、耳を傾けます。
学習意欲が高い人物が揃うことで、それぞれが学んだ内容を共有し、チーム全体の学びとすることで、プロジェクトは想定よりも素晴らしいものになる可能性があります。
発想力がある
開発職では、新しい技術やアイデアを生み出す力が求められます。
発想力とは、単に新しいことを思いつくことだけでなく、既存の技術や知識を組み合わせ、より効果的な解決策を見出す力も含まれます。
特に、製品開発やシステム設計の分野では、従来の手法では対応できない課題を解決するために、新たなアプローチを考えることが重要です。
また、技術の進化が速い業界では、時代に合った新しいアイデアを柔軟に取り入れることができる人材が求められます。
分析が得意
開発職では、実験結果やデータを基に、製品やシステムの改善を行うことが求められます。
分析力が高い人は、得られたデータから有益なアプローチを導き出し、開発の精度を向上させることができます。
例えば、新しい製品を開発する際には、テストデータを収集し、問題点を特定した上で最適な修正を加える必要があります。
また、エラーやバグの原因を特定し、迅速に修正するためにも、データを的確に読み取り、問題の本質を見極める力が重要です。
【開発職 向いている人】向いていない人の特徴
続いて、開発職に向いていない人に多く当てはまっている特徴について紹介します。
以下の2つの特徴が両方当てはまってしまう場合は、就活本番までに克服を目指すか、別の業界も就活の選択肢に入れることをおすすめします。
・低いストレス耐性
・変化への適応が苦手
低いストレス耐性
ここまで紹介してきたように、開発職はストレス耐性が求められる職業です。
つまり、ストレス耐性があまりない人、プレッシャーに弱い人は向いていないかもしれません。
プレッシャーが高い環境で100%のパフォーマンスを発揮することができない場合、克服する必要があります。
ストレス耐性が低い人は、納期などのプレッシャーに対して非常に弱く不安を感じる傾向があります。
ストレスを感じている時に仕事に取り組むと、注意力や判断力が低下し、モチベーションなども下がる可能性が高いです。
当然、仕事の質や効率が低下してしまいます。
また、常に高いストレスを感じていると、最終的に健康にまで影響が及ぶ可能性があるため、私生活にまで何かしら影響が出るかもしれません。
よって、ストレス耐性に自信がない人は克服を目指しましょう。
変化への適応が苦手
開発職は先ほど紹介したように変化が激しい環境で働くことが多いです。
新しい技術や方法への移行に対応できない人物は、開発職として成長を遂げることが難しいです。
技術は絶えず進化しており、開発職の人が働く業界は、特に新しい手法やアプローチを迅速に取り入れるため、柔軟性と適応性が必要なのです。
変化への適用が苦手な人は、既存のスキルや知識に強く依存してしまい、新しい技術へアプローチを採用することに不安や抵抗を感じてしまいます。
そのため、新しいシステムやツールの学習が遅れがちで、プロジェクトの進行に悪影響を与えることすらあります。
特に技術の意向に関しては、場合によっては短期間での習得が求められるため、学ぶ意欲が薄いとプロジェクトどころか、会社全体にも影響が及ぶことがあります。
【開発職 向いている人】向いていない人が克服するには
開発職に向いていない人の特徴について2つ紹介しましたが、では当てはまっていない人は開発職を目指してはいけないのでしょうか。
結論として、そんなことはありません。
ただし、何も対策をせずにそのまま就活をしてしまうと落とされる可能性が高いですし、もし内定を得られたとしても働き始めてから苦労します。
よって、以下の2つの対策に取り組み、克服してから就活に臨んだ方が良いでしょう。
ストレス管理の方法を学ぶ
人はそれぞれ特性があるため、根本的な性格を変えることは難しいです。
ストレスに弱い人が短期間で一気にストレスに強くなることは、可能性として低いと言わざるを得ません。
しかし、ストレスを管理する方法を学ぶことでうまく対処できるようにはなります。
例えば、納期に対して強いプレッシャーを感じ、それがストレスに発展してしまうならば、時間をうまく管理し、効率的に業務に取り組む術を身につけましょう。
また、自分なりのリラックス方法を編み出すのもおすすめです。
お気に入りの曲を聴く、お香を焚く、瞑想をするなど、人それぞれリラックス方法を様々ですが、自分に合っているものを見つけられれば、ストレスの管理をうまくできるようになるかもしれません。
柔軟性を養う
柔軟性が足りないと自覚のある人は、異なる視点から物事を見る能力を身につけられるようトレーニングを積んでみましょう。
例えば、何かしらの事象に対して自分の考えだけでなく、別の人ならばどのように考えるのか想像してみることで柔軟性を養えます。
柔軟な思考やしなやかな変化に対応できるようになりましょう。
また、フィードバックを積極的に求めることも、柔軟性を養う上で重要です。
就活を進める上では、自己PRや志望動機などを誰かに読んでもらい、客観的な視点を導入することも大切であるため、柔軟性を養うのに最適なトレーニングにもなります。
開発職への適正を高めるため、そして就活を成功させるためにも是非、自分の書いたエントリーシートを誰かに読んでもらい、フィードバックしてもらいましょう。
まとめ
今回は開発職に向いている人の特徴から求められるスキル、仕事内容や向いていない人の特徴、そして適正が低い人の対処法について紹介しました。
開発職はプレッシャーと向き合いながら仕事を進める必要があり、常に知識のアップデートや新しい価値観を受け入れることが求められます。
よって簡単な仕事ではありませんが、自分たちが生み出した新しい価値や製品が市場に受け入れられた時のやりがいは他のどの職業でも得ることができないものです。
ぜひ、本記事を読んで自分が開発職に向いていると感じた人、もしくは開発職に魅力を感じた人は就活の選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
Digmediaでは、志望動機や自己PR、面接の対策など就活における基本的な対策からニッチな対策方法まで詳しく紹介しているため、就活の情報をもっと知りたい方はぜひ他の記事も参考にしてみてください。