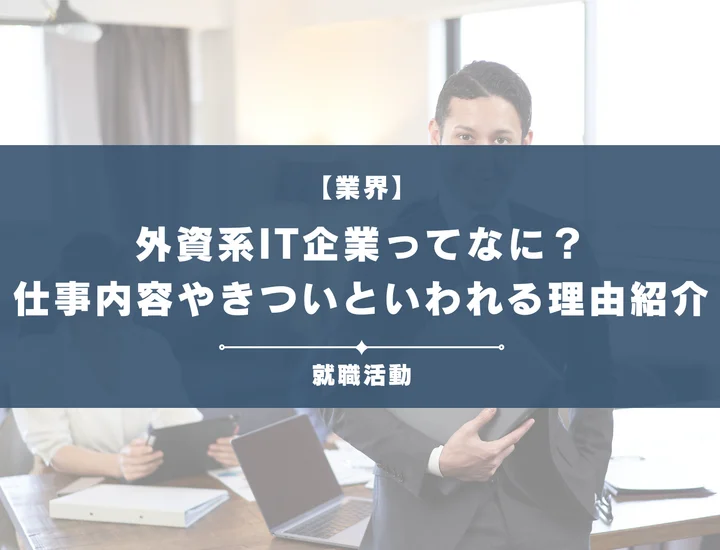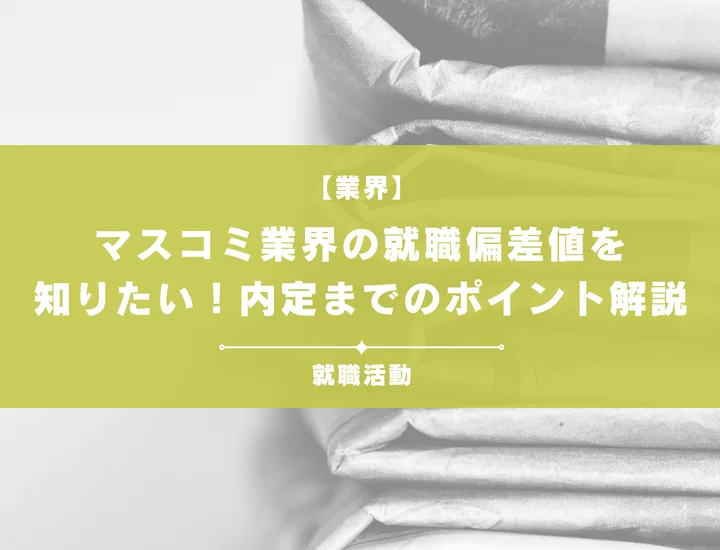HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業の入社難易度を測る目安として、主に就職活動生の間で使われる指標です。
模試の偏差値とは異なり、公的な機関が算出しているわけではなく、内定者の学歴や選考の倍率、人気度などから総合的に判断され、インターネットの掲示板やまとめサイトなどでランキング化されます。
インフラ業界を目指す上でも、この就職偏差値は志望企業を選ぶための一つの参考情報として活用されています。
人気と難易度を測るバロメーターと言えるでしょう。
インフラ業界の就職偏差値ランキング
インフラ業界の就職偏差値ランキングは、就活生にとって志望企業群を把握する上で非常に人気のある情報源です。
ただし、これらのランキングは作成者や評価基準によって順位が変動する点に注意が必要です。
一般的に、電力、ガス、大手私鉄、通信キャリアといった、各分野のトップ企業が上位を占める傾向にあります。
インフラ業界全体の就職偏差値は、その安定性から比較的高い水準で推移することが多いですが、具体的な順位だけを鵜呑みにせず、なぜその企業が評価されているのかを分析することが重要です。
【インフラ業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】ENEOS
国内最大級のエネルギー企業であり、総合職の人気が非常に高いです。
石油・ガス・再生可能エネルギーなど幅広い事業を展開しており、グローバルな視点と技術力が求められます。
入社を目指すには、エネルギー政策や脱炭素分野への理解を深め、社会課題に対する意欲を具体的に伝えることが重要です。
【インフラ業界】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】東京ガス 出光興産
【68】大阪ガス
【67】関西電力 中部電力 伊藤忠エネクス
【66】東京電力 東北電力 JERA レノバ パシフィコ・エナジー
大手電力・ガス会社や新エネルギー関連企業が多く、安定性と社会貢献性の高さが特徴です。
地域インフラを支える使命感や技術革新への関心が求められます。
エントリー時には、エネルギーの将来像や再生可能エネルギーへの理解を自分の言葉で語れるようにしておくとよいでしょう。
【インフラ業界】Cランク(就職偏差値61以上)
Cランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Cランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐインフラ業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【65】九州電力 電源開発 首都高速道路 ユーラスエナジー
【64】ソフトバンク 中国電力 阪神高速道路 NEXCO中日本
【63】北海道電力 NEXCO東日本 NEXCO西日本
【62】北陸電力 東邦ガス 四国電力 沖縄電力 沖縄セルラー電話 日本原子力発電
【61】北陸電気工事 九電みらいエナジー 自然電力 イーレックス SBパワー リニューアブル・ジャパン ユアテック
全国の地域インフラを支える電力会社や道路・通信系の企業が中心です。
公共性の高い事業に携わるため、地域貢献への思いと安全意識が重視されます。
インターンや技術職の経験を通じて、現場理解を深めておくことが選考突破の鍵になります。
【インフラ業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】静岡ガス 京葉ガス 日本瓦斯 東邦液化ガス 横浜高速鉄道 福岡北九州高速道路 カナディアン・ソーラー・ジャパン
【59】NTTアノードエナジー 楽天エナジー オプテージ 西部ガス 北海道瓦斯 ミツウロコ Looop 首都圏新都市鉄道 エフオン
【58】サーラコーポレーション レモンガス 広島ガスプロパン りゅうせき 北陸瓦斯 広島ガス 東邦アセチレン
【57】エネアーク関西 鈴与商事 ツバメガスフロンティア 東急パワーサプライ 大丸エナウィン アースインフィニティ トーエル 愛知道路コンセッション
【56】日本海ガス 西日本液化ガス 関東コスモガス 九州石油ガス TGオクトパスエナジー
地域密着型のガス・電力会社や再生可能エネルギー関連企業が中心です。
地元との関係性を重視し、安定した環境で長く働きたい人に向いています。
地元愛や地域活性化への貢献意欲を志望動機として具体的に伝えることが評価につながります。
【インフラ業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】芦ノ湖スカイライン 高山石油ガス 八戸液化ガス 長野プロパンガス マルエイ 箱根ターンパイク
地域特化型の小規模インフラ・エネルギー企業が多く、地域社会を支える役割を担っています。
社員同士の距離が近く、地域に根ざした仕事をしたい人に向いています。
面接では、地域への愛着や長期的なキャリアビジョンを具体的に話すことが大切です。
【インフラ業界】とは
インフラ業界とは、私たちの日常生活や社会経済活動の基盤を支える不可欠なサービスを提供する産業群を指します。
具体的には、電力、ガス、水道といったエネルギー分野、鉄道、道路、航空といった交通分野、そしてインターネットや電話網を担う通信分野などが含まれます。
これらのサービスが停止すると社会機能が麻痺してしまうため、極めて公共性が高く、景気変動の影響を受けにくい安定性が魅力です。
就職活動においても、インフラ業界はその社会貢献度の高さと雇用の安定性から、文系・理系問わず多くの学生から根強い人気を集めています。
社会の基盤となるサービスを提供する産業
インフラ業界の最も重要な役割は、社会の基盤、つまりライフラインを維持・提供することです。
例えば、電力会社は家庭の照明や電化製品だけでなく、工場や病院、交通機関など、あらゆる産業活動に必要なエネルギーを供給しています。
ガスや水道が止まれば、私たちの日常生活は立ち行かなくなります。
また、鉄道や道路は人やモノの移動を支え、経済活動の動脈としての役割を担っています。
通信業界が提供するインターネットや電話網は、現代社会における情報伝達の根幹です。
このように、インフラ業界は社会全体を下支えする、まさに縁の下の力持ちと言える存在であり、その仕事は人々の当たり前の生活を守るという大きな使命を帯びています。
景気に関わらず常に需要があり続けるサービスであるため、産業としての安定性も抜群に高いのが特徴です。
公共性と安定性が高い分野
インフラ業界のサービスは、特定の人々だけでなく、国民生活全体にとって不可欠なものであるため、非常に高い公共性を有しています。
そのため、多くのインフラ企業は法律による規制を受けたり、公的な側面を持っていたりすることが多く、利益追求だけでなく、サービスの安定供給という社会的使命を最優先に求められます。
この公共性の高さは、そのまま事業の安定性につながります。
電気や水、交通手段といったサービスは、景気が良かろうと悪かろうと、人々が生活する上で必ず必要とされるため、需要が急激になくなることがありません。
流行り廃りに左右されにくいビジネスモデルであり、企業経営が非常に安定しているのが大きな特徴です。
就職先として見た場合、この安定性は長期的なキャリアを築く上で大きな安心材料となり、インフラ業界が就職偏差値で高く評価される理由の一つとなっています。
技術革新と設備投資が重要な業界
インフラ業界は安定している一方で、非常に大規模な設備投資を必要とする装置産業であるという側面も持っています。
発電所やダム、鉄道網、通信基地局などを建設・維持するためには莫大な初期費用と継続的なメンテナンス費用がかかります。
このため、新規参入が難しく、既存の大手企業による寡占状態となりやすい傾向があります。
また、安定供給を続けるためには、老朽化した設備の更新だけでなく、時代の変化に対応するための技術革新が不可欠です。
例えば、電力業界では脱炭素化に向けた再生可能エネルギーの導入やスマートグリッドの構築、通信業界では5Gや6Gといった次世代通信規格の開発、交通業界では自動運転技術やMaaSの推進など、最先端の技術開発が活発に行われています。
安定した基盤の上で、未来の社会を創るダイナミックな挑戦が行われている点も、インフラ業界の大きな魅力です。
【インフラ業界】特徴
インフラ業界で働くことには、他の業界とは異なるいくつかの特徴があります。
最大の魅力は、社会基盤を支えるという強い使命感と、景気に左右されにくい経営基盤がもたらす雇用の安定性です。
一方で、人々の生活に直結するため、ミスが許されないという重い責任も伴います。
また、専門的な技術や知識、関連する法律・規制の理解が求められる場面も多く、継続的な学習が不可欠です。
ここでは、インフラ業界で働く上での主な特徴を具体的に見ていきましょう。
長期的・安定的なキャリア形成がしやすい
インフラ業界の企業は、その事業の安定性を背景に、従業員の雇用も長期的に守られる傾向が強いのが特徴です。
景気後退期でも大規模なリストラが起こりにくく、安心して長く働き続けることができます。
また、多くの企業では年功序列的な給与体系や人事制度が残っている場合もあり、着実に経験を積むことでキャリアアップや昇給が期待できます。
さらに、インフラの運用・保守には高度な専門知識が必要とされるため、社内での教育・研修制度が非常に充実しています。
ジョブローテーションを通じて複数の部門を経験させ、ゼネラリストを育成する企業もあれば、一つの分野のスペシャリストとして技術を極めていくキャリアパスが用意されている場合もあります。
福利厚生も手厚い企業が多く、ライフイベントを経ても働き続けやすい環境が整っている点は、長期的なキャリア形成を目指す上で大きな魅力と言えるでしょう。
専門知識と法規対応が求められる
インフラ業界の業務は、社会の安全と安定供給に直結するため、非常に高度な専門知識が求められます。
理系であれば、電気、機械、土木、情報通信など、それぞれの分野における深い技術的知見が不可欠です。
設備の設計、建設、保守、運用管理など、あらゆる場面で専門性が問われます。
文系であっても、用地取得のための交渉、エネルギーの調達、料金制度の設計、あるいは総務や経理といった管理部門においても、業界特有の知識が必要となります。
特に重要なのが法規への対応です。
インフラ事業は、電気事業法、ガス事業法、鉄道事業法など、各分野の業法によって厳しく規制されています。
許認可の取得や安全基準の遵守、国や自治体への報告など、法令に基づいた正確な業務遂行が常に求められます。
入社後も資格取得や新しい規制の学習など、継続的な自己研鑽が欠かせません。
チームでの運用と緊急対応力が必要
インフラ設備は24時間365日、休むことなく稼働し続ける必要があります。
そのため、多くの現場では交代制のシフト勤務(夜勤や当直)が導入されており、安定供給をチーム全体で支えています。
日々の運用管理においては、メンバー間の正確な情報共有と連携が欠かせません。
一つのミスや連絡漏れが、大規模な供給停止や事故につながる可能性があるため、強い協調性と責任感が求められます。
さらに、インフラ業界で働く上で避けられないのが緊急時の対応です。
台風や地震といった自然災害、あるいは突発的な設備トラブルが発生した際は、昼夜を問わず迅速な復旧作業にあたる必要があります。
想定外の事態にも冷静に対処し、安全を確保しながら最適な手順でサービスを復旧させる判断力と、プレッシャーの中で確実に業務を遂行するタフな精神力が求められる仕事です。
【インフラ業界】向いている人
インフラ業界は、その安定性や社会貢献性の高さから多くの就活生に人気ですが、特有の業務内容や企業文化があるため、向き不向きが分かれる側面もあります。
社会基盤を支えるという重い責任を負いながら、地道な業務を確実に遂行することが求められます。
また、大規模な組織でチームとして動く場面も多いです。
ここでは、インフラ業界の仕事に特に向いている人の特徴を3つの観点から解説します。
自身がインフラ業界で活躍できる人材かどうか、自己分析と照らし合わせてみてください。
安定志向で責任感が強い人
インフラ業界は、短期的な成果よりも長期的な安定供給を最優先します。
そのため、目まぐるしく変化する環境で刺激を求める人よりも、一つの会社で腰を据え、堅実にキャリアを築きたいという安定志向の人に向いています。
また、インフラ業界の仕事は、人々の生活に直結するがゆえに、絶対に止めてはならないというプレッシャーが常にかかります。
華やかな成果が見えにくい保守・点検といった地道な作業も多くありますが、それこそが社会の当たり前を守っているという強い責任感と誇りを持てる人が求められます。
自分の仕事が社会基盤を支えているという事実にやりがいを感じ、任された業務を最後まで確実にやり遂げる誠実さや使命感の強さが、この業界で活躍するための最も重要な資質です。
流行に左右されず、社会貢献性の高い仕事にじっくり取り組みたい人にとって、最適な環境です。
技術的な理解力やものづくりが好きな人
インフラ業界は、巨大な設備や複雑なシステムによって成り立っています。
理系の学生であれば、発電所や変電所、鉄道車両、通信ネットワークといった大規模な構造物や、それらを制御する仕組みに興味を持てることは大きな強みです。
設備の保守・運用や新しい技術の開発において、技術的な探究心やものづくりへの情熱が活かされます。
文系の学生であっても、こうした社会基盤がどのような技術で動いているのか、その仕組みに対して知的好奇心を持てるかどうかが重要です。
直接的に技術を扱うことはなくても、技術部門と連携してプロジェクトを進めたり、技術的な制約を理解した上で企画を立案したりする場面は多々あります。
社会を動かす仕組みそのものに興味があり、大規模なプロジェクトに関わりたいと考える人にとって、非常にやりがいのある分野と言えるでしょう。
状況判断と冷静な対応ができる人
インフラ業界の使命は安定供給ですが、自然災害や予期せぬトラブルによって、その安定が脅かされる事態は必ず発生します。
そうした非常時において、パニックにならず冷静に状況を分析し、最善の対応策を判断・実行できる能力が極めて重要です。
現場では、安全の確保を最優先しながら、どのエリアから復旧させるか、どのような手順で作業を進めるかなど、限られた情報の中で迅速な意思決定を迫られます。
平時においても、日々のオペレーションの中で小さな異常のサインを見逃さず、大きなトラブルに発展する前に対処する慎重さが求められます。
決められたルールやマニュアルを遵守する規律正しさと、想定外の事態にも臨機応変に対応できる柔軟性を併せ持ち、プレッシャーのかかる場面でも冷静さを保てる人は、インフラ業界で高く評価されます。
【インフラ業界】向いていない人の特徴
インフラ業界は社会の基盤を支える重要な仕事であり、責任の重さや専門性の高さを理解して働く姿勢が求められます。
そのため他業界と比べて向き不向きがはっきり出やすい特徴があります。
特に安定性が高い一方で、緊急対応やシフト勤務など仕事特有の厳しさも存在します。
この章ではインフラ業界を目指す際に知っておくべき、向いていない人のポイントを整理して解説します。
突発対応や不規則勤務が苦手な人
インフラ業界では設備トラブルや災害時の対応など、突発的な状況に対処する場面が少なくありません。
そのため夜間や休日でも緊急出動が発生することがあり、不規則な勤務体系にストレスを感じやすい人は負担になりやすいです。
また設備は24時間稼働しているため、交代勤務やシフト制が組まれるケースも多く、生活リズムが乱れがちになります。
責任感と冷静な判断が求められる環境のため、突発対応が極端に苦手だと業務遂行が難しくなることがあります。
結果として継続勤務に影響することもあるため、不規則な働き方に過度なストレスを感じる人は注意が必要です。
専門知識の習得に消極的な人
インフラ業界は安全性や法規遵守が重要であり、常に新しい知識の習得が求められます。
例えば電気や機械の基礎知識に加えて、設備の管理方法や法令の変更を継続的に学ぶ必要があります。
さらに資格取得がキャリアに直結するため、学習意欲が低いと昇進や業務の幅が広がりにくくなります。
また技術革新が進む今は、デジタル化やDXの理解も欠かせません。
そのため知識の更新に消極的な人は業務への適応が遅れ、評価が下がりやすい傾向があります。
地道な作業や安全確認を軽視する人
インフラ業界の仕事は派手さとは対照的に、地道で正確な作業の積み重ねが中心です。
設備点検や記録作成、安全確認など、一見すると単調に感じる作業が日常的に発生します。
しかしこれらは事故を防ぐための重要なプロセスであり、慎重に取り組む姿勢が求められます。
もし確認作業を軽視したり、効率を優先しすぎたりすると大きなトラブルにつながる可能性があります。
そのため細かい作業が苦手で注意力が続かない人は現場で評価されにくく、ストレスを感じやすい傾向があります。
【インフラ業界】今後伸びる理由と将来性の展望
インフラ業界は社会全体を支える重要な分野であり、技術革新や国の政策によって今後も大きな成長が期待されています。
特に再生可能エネルギーの普及やデジタル化の加速は、インフラ企業の事業領域を拡大させる大きな要因となっています。
さらに設備の老朽化が進む日本では、更新工事や保全業務への投資が継続する見込みがあります。
こうした背景から、インフラ業界は安定性と将来性を兼ね備えた就職先として注目されています。
再生可能エネルギーと脱炭素化で需要が拡大する分野
インフラ業界の中でも、再生可能エネルギーへの転換は大きな成長ドライバーの一つです。
世界的に脱炭素化の流れが強まる中で、太陽光や風力といった再エネ発電所の建設や運用が急速に増えています。
電力会社や設備メーカーは再エネ設備の導入を拡大しており、新規プロジェクトが全国で次々に立ち上がっています。
また送電設備の強化や蓄電池の導入など、新たな技術への投資が不可欠になっています。
そのためエネルギーインフラに関わる技術職や保全職の需要は今後も堅調に推移すると考えられています。
特にカーボンニュートラルに向けた取り組みが加速している点が、インフラ業界の将来性を高める大きな要因です。
デジタル化・DXによるインフラ設備の高度化
インフラ業界ではデジタル化が急速に進んでおり、AIやIoTを活用したスマートインフラの導入が続いています。
これまで人手で行っていた設備点検は、ドローンやセンサーによって自動化が進み、作業の安全性と効率が大きく向上しています。
例えば電力会社では、AIを用いた需要予測や設備故障の予兆検知が始まっており、現場の負担軽減と安定供給を両立できる環境が整いつつあります。
また水道や通信といったライフラインでも、遠隔監視システムが導入され、トラブル発生時の迅速な対応が可能になっています。
これにより技術者の役割も変化し、データ分析やシステム運用に関わる新しいタイプの人材が求められるようになっています。
DXが進展することでインフラ企業の業務は高度化し、専門性を高めながらキャリアの幅も広がる点が大きな魅力です。
老朽化設備の更新需要とインフラ投資の継続
日本では高度経済成長期に整備された多くの設備が老朽化しており、更新工事や保全業務が長期的に必要とされています。
特に電力設備や上下水道、橋梁、鉄道インフラは老朽化が進んでおり、安全性の確保が大きな課題となっています。
このため国や自治体は設備更新のための投資を拡大しており、インフラ企業への需要は今後も安定して続く見込みがあります。
また自然災害が増えている影響から、防災対策や耐震補強の重要性が高まり、インフラ整備に関する新たなプロジェクトも増加しています。
こうした背景により施工管理や保全技術者などの採用は継続的に行われ、若手の活躍機会も広がっています。
設備更新の需要が長期的に続く点がインフラ業界の安定性と将来性の高さを裏付けています。
【インフラ業界】内定をもらうためのポイント
インフラ業界は、その安定性から就職偏差値が総じて高く、多くの優秀な学生が応募する人気の業界です。
そのため、内定を獲得するには、他の就活生と差別化できる明確な志望動機と、業界への深い理解が不可欠です。
単に安定しているからという理由だけでは、採用担当者の心には響きません。
なぜ他の業界ではなくインフラなのか、そしてなぜその企業でなければならないのかを論理的に説明する必要があります。
ここでは、インフラ業界の内定を掴むための重要なポイントを解説します。
業界理解と志望動機を具体化すること
インフラ業界の選考で最も重視されるのが志望動機です。
社会貢献性や安定性といった業界共通の魅力だけを語るのではなく、なぜその企業を選んだのかを明確にする必要があります。
インフラ業界と一口に言っても、電力、ガス、鉄道、通信など分野は多岐にわたり、同じ分野でも企業によって事業エリアや強み、今後の事業戦略は異なります。
例えば、同じ電力会社でも、再生可能エネルギーに注力している企業、原子力発電を主軸とする企業など様々です。
企業研究を徹底的に行い、その企業が現在抱えている課題や、今後どのような社会を実現しようとしているのかを深く理解しましょう。
その上で、自分の過去の経験や価値観が、その企業のどのような点に共鳴し、どのように貢献できるのかを具体的に結びつけて説明することが、説得力のある志望動機につながります。
関連資格や技術経験をアピールすること
インフラ業界は専門性が高いため、学生時代に関連する知識や経験を積んでいることは大きなアピールポイントになります。
理系学生であれば、自身の研究内容が志望企業のどの技術分野(例:材料工学、制御システム、データ分析など)に関連しているかを具体的に示しましょう。
電気主任技術者や情報処理技術者試験など、難易度の高い資格に挑戦している場合は、その学習意欲も評価されます。
文系学生であっても、例えば鉄道会社の不動産開発に興味があるなら宅地建物取引士、海外プロジェクトに関わりたいなら高いTOEICスコアや留学経験などが有効です。
必須ではありませんが、インターンシップに参加して実際の業務に触れた経験は、志望度の高さと業界理解の深さを示す強力な材料となります。
業界で働く上で求められる専門性に対し、自ら学ぼうとする姿勢をアピールすることが重要です。
安全意識や現場対応力を示すこと
インフラ業界の根幹は安全・安定供給です。
選考過程では、候補者がいかに高い安全意識を持っているか、そして予期せぬ事態にどう対処できるかが見られています。
これをアピールするには、学生時代の具体的なエピソードを用いるのが効果的です。
例えば、アルバイト先で安全マニュアルの遵守を徹底した経験、サークル活動でリスクを予見して対策を講じた経験、研究室で安全手順を守り地道な実験を続けた経験などが挙げられます。
重要なのは、大きな成功体験よりも、決められたルールを愚直に守る誠実さや、問題が発生した時に他者と協力して冷静に対処したプロセスを具体的に語ることです。
インフラを支える人材として、最も信頼できる人物であると評価してもらうことが、内定への近道となります。
【インフラ業界】必要資格一覧と持っていると有利なスキル
インフラ業界では安全性と専門性が重視されるため、資格の有無が選考に大きく影響します。
特に電気や機械、通信などの分野では基礎資格を持っているかが評価されやすく、業務理解の深さを示す材料になります。
また資格を保有していることで配属の幅が広がり、若手のうちから活躍しやすくなるケースも多いです。
この章では、インフラ業界で有利になる代表的な資格とスキルを具体的に解説します。
電気・機械分野で評価される資格
インフラ業界の中でも電力や設備保守の領域は電気系の資格が特に重視されます。
なぜなら多くの業務が電気設備の点検や運転管理と直結しており、基礎的な知識が求められるためです。
代表的な資格としては電気工事士、電気主任技術者、エネルギー管理士などが挙げられ、取得していると選考で理解度の高さを示すことができます。
さらに第二種冷凍機械責任者やボイラー技士など、設備の運用に関連する資格も評価の対象になります。
これらの資格は実務で直接活かせるため、若手でも専門性を持った人材として扱われやすい点が大きな強みです。
通信・インフラIT領域で有利になる資格
近年のインフラ業界ではデジタル化が進み、通信インフラやIT系の資格を持つ学生の評価が高まっています。
特に通信キャリアや設備保守企業ではネットワークの基礎を理解できるCCNA、工事担任者などが有利です。
またインフラDXが進む中で、データ分析やシステム運用のスキルも強く求められています。
基礎的なITパスポートや情報セキュリティ関連の学習を進めておくと、業界の変革に対応できる人材として見られます。
加えてインフラ企業では設備管理システムや監視システムを扱うため、情報系の知識があると文系でも専門職に近い領域で活躍できる点が魅力です。
施工管理や安全管理で強みになる資格
インフラ業界の根幹には建設や保守の現場があり、施工管理や安全管理の資格は非常に評価されます。
土木施工管理技士や管工事施工管理技士は工事の品質と安全を守る重要な役割を担うため、採用段階から企業が注目する資格です。
また施工管理技士は文系でも取得を目指しやすく、現場系のキャリアを志望する学生にとって強力なアピール材料になります。
安全管理に関しては危険物取扱者や安全衛生管理者なども評価され、設備の運用に必要な知識を証明できます。
現場では資格者が常駐しなければならないケースもあるため、取得しておくと任される業務の幅を大きく広げられる点が魅力です。
【インフラ業界】よくある質問
就職偏差値が高く、安定しているイメージのインフラ業界ですが、その特殊性からか就職活動生からは多くの質問が寄せられます。
特に、技術職のイメージが強いため文系学生の不安や、24時間稼働ならではの勤務形態、そして長期的な将来性については、誰もが気になるところでしょう。
インフラ業界への就職を目指す上で、多くの人が抱く疑問点について、ここで分かりやすく回答していきます。
文系出身でも入れますか?
結論から言うと、文系出身者もインフラ業界で大いに活躍できます。
インフラ業界には、技術職(理系)と事務系・営業系(文系)の採用枠が両方存在します。
もちろん、設備の設計・保守・運用といった中核業務は理系出身者が担うことが多いです。
しかし、会社を運営していくためには、経営企画、人事、経理、法務といった管理部門が不可欠です。
また、電力・ガス自由化に伴う法人営業(セールス)やマーケティング、用地取得のための交渉、海外からの燃料調達、鉄道会社が行う駅ナカ開発や不動産事業など、文系出身者の知識や交渉力、企画力が求められるフィールドは非常に多岐にわたります。
技術的な知識は入社後の研修で学べる機会も多いため、文系だからと臆することなく、自分の強みがどの部門で活かせるかを考えて挑戦することが大切です。
夜勤や当直は多いですか?
これは、職種や配属先によって大きく異なります。
インフラは24時間365日稼働しているため、その安定供給を支える現場では夜勤や当直(宿直)が必須となります。
具体的には、発電所や工場の運転・監視オペレーター、鉄道の運行管理者、通信網の監視センター、設備の保守・メンテナンス担当者などが該当します。
これらの職種では、シフト制勤務が基本となり、土日祝日の出勤や深夜勤務も発生します。
一方で、本社の企画部門、人事、経理、法務、あるいは日中をメインとする営業部門などでは、他の業界の事務職と同様に、カレンダー通りの日勤(例:9時〜17時)が基本となる場合がほとんどです。
入社後すぐに全員が夜勤を経験するわけではなく、技術系で現場配属となった場合にシフト勤務になる可能性が高い、と理解しておくとよいでしょう。
将来性はありますか?
インフラ業界の将来性を不安視する声もありますが、社会基盤である以上、需要がなくなることはありません。
ただし、業界は今、大きな変革期を迎えています。
電力・ガス業界では、脱炭素化(カーボンニュートラル)に向けた再生可能エネルギーへのシフトや、エネルギーの効率的な利用を促すスマートグリッドの構築が急務です。
通信業界では5Gの普及、さらに6Gの開発競争が進んでいます。
交通業界では自動運転やMaaS(Mobility as a Service)といった新しい移動サービスの概念が生まれています。
また、国内の多くのインフラ設備が高度経済成長期に作られており、それらの老朽化対策(維持・更新)も待ったなしの課題です。
AIやIoTを活用した効率的なメンテナンス手法の開発も進んでいます。
安定した基盤の上で、こうした社会課題の解決や次世代インフラの構築に挑戦できるため、将来性は非常に高いと言えます。
まとめ
インフラ業界の就職偏差値は、その安定性と社会貢献性の高さから、依然として高い水準を維持しています。
人々の当たり前の生活を支えるという重い責任を伴いますが、それだけに大きなやりがいと長期的なキャリアを得られる魅力的な業界です。
安定しているだけでなく、脱炭素化やデジタル化といった技術革新のフロンティアでもあります。
本記事で解説した業界の特徴や求められる人物像を深く理解し、自分と企業との接点を明確にすることが、人気のインフラ業界で内定を勝ち取るための鍵となります。

_720x550.webp)

_720x550.webp)