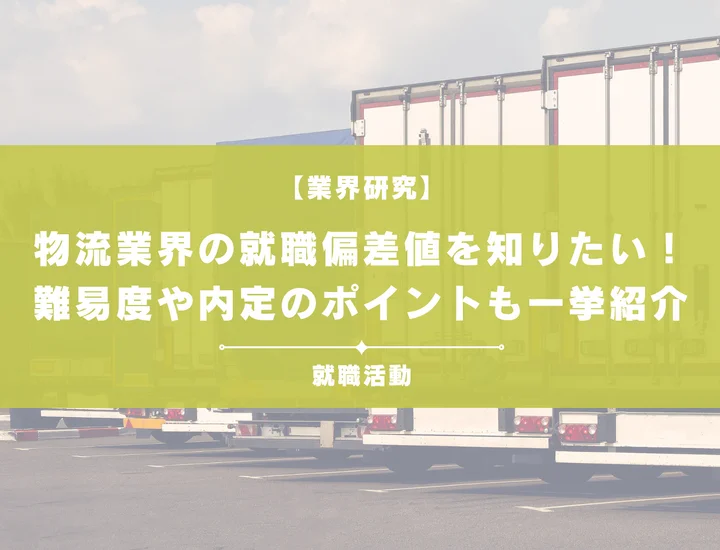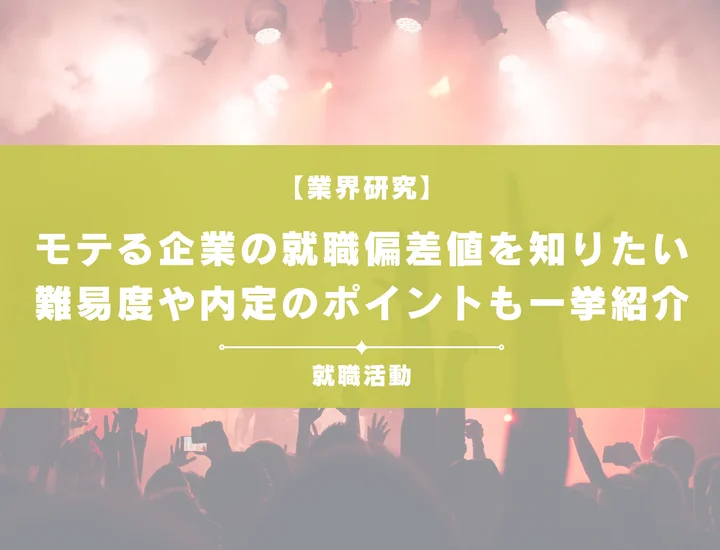HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、主に就職活動を行う学生が、企業の入社難易度を客観的に測るために使う指標のことです。
予備校などが算出する大学の偏差値と同様に、企業の人気度、選考の倍率、求められる学歴や専門性、内定者の実績などを基に、相対的な難しさが数値化されています。
ただし、これは公的なデータではなく、就職活動関連の掲示板や情報サイトなどで独自に集計された、あくまで目安の一つです。
数値が高いほど入社が難しいとされ、業界研究や企業選びの参考として広く利用されています。
物流業界の就職偏差値ランキング
物流業界の就職偏差値ランキングは、業界内に数多く存在する企業の入社難易度を相対的に比較できるようにしたものです。
物流業界はBtoB企業が中心で学生には馴染みが薄い面もありますが、日本郵船や商船三井といった海運大手は総合商社と並ぶ最難関レベルとされています。
この記事で紹介するランキングは、物流業界全体の就職偏差値の傾向を把握するための一つの参考資料としてご活用ください。
自分が目指す企業がどの位置にあるのかを知ることは、対策を立てる上で重要です。
【物流業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】日本郵船 商船三井
Aランクは、日本の海運業界の2大巨頭である「海運メガキャリア」が独占しています。
世界を舞台にしたダイナミックな仕事内容と圧倒的な高給与で、就活生から絶大な人気を誇ります。
総合商社や外資系コンサルと並ぶ最難関レベルであり、高い学歴と卓越した語学力、論理的思考力が求められます。
OB訪問などを通じた徹底的な企業研究と、グローバルな視野を持った自己PRが不可欠です。
【物流業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ物流業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】川崎汽船
【68】三菱倉庫 飯野海運 NSユナイテッド海運 共栄タンカーONE
【67】日本郵政(総合職) JAL(総合職) ANA(総合職) 住友倉庫 成田国際空港
【66】ロジスティード 三井倉庫 郵船ロジスティクス 日本貨物航空 明治海運 東京汽船 川崎近海汽船 乾汽船 A.P.モラー・マースク アメリカン・プレジデント・ラインズ 新関西国際空港 日本自動車ターミナル
Bランクは、海運大手の川崎汽船に加え、「財閥系」と呼ばれる大手倉庫会社が中心です。
また、JAL・ANAの総合職や大手フォワーダー、主要空港運営会社など、各分野のトップ企業が並びます。
倉庫会社は単なる保管業ではなく、不動産事業や3PLが収益の柱であることを理解する必要があります。
Aランク同様に高いレベルの競争となり、物流の仕組み全体を理解した上で、なぜその事業領域(海・陸・空・倉庫)を選ぶのかを明確にする必要があります。
【物流業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】澁澤倉庫 安田倉庫 明治海運 日新 玉井商船 東洋埠頭 三井物産グローバルロジスティクス 伊藤忠ロジスティクス 住商グローバルロジスティクス 丸紅ロジスティクス
【64】NX日本通運 ヤマト運輸(総合職) 佐川急便(総合職) 上組 近鉄エクスプレス 日鉄物流 三菱ケミカル物流 コマツ物流 ホンダロジスティクス UPSジャパン DHLジャパン キューネ・アンド・ナーゲル
【63】西濃運輸 西濃シェンカー 鈴与 山九 センコー 日本石油輸送 栗林商船 ブリヂストン物流 三菱電機ロジスティクス キリングループロジスティクス サントリーロジスティクス マツダロジスティクス 日野グローバルロジスティクス いすゞロジスティクス
【62】JR貨物 福山通運 SBS 日本梱包運輸倉庫 キユーソー流通システム 明治ロジテック 花王ロジスティクス 東ソー物流 レンゴーロジスティクス DNPロジスティクス 宇部物流サービス 楽天スーパーロジスティクス
【61】トヨタ輸送 バンテック 名鉄運輸 トランコム 東陽倉庫 川西倉庫 杉村倉庫 LIXIL物流 王子物流 日立建機ロジテック ケイラインロジスティックス
Cランクは、NX(日本通運)やヤマト、佐川といった陸運の最大手企業が中心となります。
また、総合商社や大手メーカーの物流機能を担う子会社(商社系物流・メーカー系物流)や、独立系の倉庫・フォワーダーも多く含まれます。
メーカー系物流を志望する場合は、親会社の事業や製品特性と物流の関連性を深く研究することが対策の鍵です。
Bランク以上に、物流の「現場」に近いオペレーションへの理解や、国内の物流課題(2024年問題など)に対する自分なりの考えを求められる傾向があります。
【物流業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】トナミ運輸 アルプス物流 丸和運輸機関 日本トランスシティ ゼロ ハマキョウレックス フジトランスコーポレーション ダイトーコーポレーション
【59】新潟運輸 名糖運輸 ロジネットジャパン 日本ロジテム ケイヒン 日本トランスネット 日発運輸 マルハニチロ物流
【58】キムラユニティー 愛知陸運 エスラインギフ 丸運 遠州トラック 岡山県貨物運送 南総通運 サンリツ センコン物流 日本コンセプト 濃飛倉庫運輸 ジェイアール東日本物流
【57】アクシアロジ キャリテック ホンダロジコム サンワネッツ 姫路合同貨物自動車 ユーネットランス 双葉運輸 両備トランスポート 滋賀近交運輸倉庫 サカイ引越センター ベルメゾンロジスコ
【56】佐渡汽船 西部運輸 山口県貨物倉庫 ムロオ シモハナ物流 ギオン サーラ物流 太平洋陸送 トクヤマ海陸運送 ワコール流通 オーティーティーロジスティクス
Dランクは、特定の地域や分野で強みを持つ優良な中堅企業が集まります。
全国的な知名度はCランク以上に劣るものの、地域経済を支える重要な陸運会社や、特定の業界(自動車、食品、引っ越しなど)に特化した企業が目立ちます。
安定した経営基盤を持つBtoB企業が多いため、派手さよりも堅実な社風を好む学生に向いています。
選考では、なぜその地域や特定分野の物流に興味を持ったのかを明確に伝える必要があります。
【物流業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】ベストロジ三重 玉村運輸 北海道フーズ輸送 トーエイ物流 駿和物流 ハート引越センター 東上通運 ホリウチ・トータルサービス 大洋荷役 ロジクエスト 丸共シーランド ニッカコーポレーション やよい運送 ロジスティクスウェーブジャパン
Eランクは、より地域密着型、あるいは特定の荷主との取引を主軸とする物流企業が中心です。
物流のオペレーションを「現場」で支える、社会に不可欠な企業群と言えます。
選考の難易度(学歴フィルターなど)は比較的緩やかになりますが、入社後のミスマッチを防ぐことが重要です。
業務内容や勤務体系(シフト勤務や体力的な側面)、キャリアパスをしっかり確認することが対策となります。
【物流業界】とは
物流業界は、モノの生産地から消費地までの流れ、すなわち輸送、保管、管理を担う産業です。
私たちが日々手にする商品や、企業の生産活動に必要な原材料は、すべて物流業界の働きによって届けられています。
単にモノを運ぶだけでなく、サプライチェーン全体の効率化を設計する重要な役割も担っています。
経済活動の根幹を支える、まさに社会インフラと呼べる産業分野であり、その裾野は非常に広いのが特徴です。
モノの「流れ」を管理し、生産者から消費者へ届ける社会インフラ産業
物流業界の最も基本的な役割は、モノを生産者から消費者へと届けることです。
しかし、それは単にA地点からB地点へ運ぶだけではありません。
モノの生産、在庫、流通、消費という一連の流れ全体を管理し、最適化することが求められます。
例えば、メーカーが製品を作っても、それを適切なタイミングで、適切な量だけ、適切な場所に届けられなければ、ビジネスは成立しません。
物流業界は、このモノの流れ、すなわちサプライチェーンの血液として機能しています。
スーパーに商品が並ぶのも、ネット通販で注文した商品が翌日届くのも、全て物流業界が社会インフラとして機能しているからです。
もし物流が一日でも止まれば、社会活動や経済活動は深刻な打撃を受けます。
このように、物流業界は目立たなくとも、私たちの生活基盤そのものを支える極めて公共性の高い産業です。
近年では、このモノの流れをいかに効率化し、コストを下げ、環境負荷を低減するかが経営戦略上の重要課題となっており、物流業界はその課題解決のプロフェッショナルとして、企業の競争力を左右する存在にもなっています。
陸運、海運、空運、倉庫管理など多様な分野で構成
物流業界と一口に言っても、その内訳は非常に多様です。
まず、最も身近なのがトラックや鉄道で国内の輸送を担う陸運です。
ヤマト運輸や佐川急便、NX(日本通運)などが代表的です。
次に、国際間の大量輸送を担うのが海運です。
日本郵船、商船三井、川崎汽船の3大キャリアが有名で、資源やコンテナを巨大な船で運びます。
就職偏差値ランキングでも最上位を占めることが多い分野です。
そして、スピードが求められる貨物(電子部品や医薬品など)を運ぶのが空運です。
JALやANAの貨物部門、あるいはDHLやFedExといった国際宅配便(クーリエ)がこれにあたります。
さらに、これら輸送の結節点となるのが倉庫管理(倉庫業)です。
三菱倉庫や三井倉庫などの財閥系企業は、単にモノを保管するだけでなく、不動産事業や高度な在庫管理サービスも提供しています。
これら陸・海・空・倉庫が複雑に連携し合い、グローバルなモノの流れが形成されています。
運ぶだけでなく、保管・荷役・包装・情報管理までを一貫して担う役割
物流の機能は、単にモノを運ぶ輸送だけではありません。
物流は一般的に、輸送、保管、荷役(にやく)、包装、流通加工、情報管理の6つの機能で構成されていると言われます。
輸送はトラックや船で運ぶこと、保管は倉庫で在庫を管理することです。
荷役とは、倉庫への入出庫、トラックへの積み下ろし、あるいは仕分け作業などを指します。
包装は、輸送中の破損を防ぐための梱包や、商品価値を高めるためのラッピングです。
流通加工は、倉庫内で値札をつけたり、組み立てたりする作業を指します。
そして最も重要なのが、これら全てのプロセスを管理する情報管理です。
今、荷物がどこにあり、在庫がいくつで、いつまでに届ける必要があるのか。
これらの情報をITシステムで一元管理し、サプライチェーン全体を最適化することが現代の物流業界の中心的な役割です。
特に、荷主企業の物流業務を一括で請け負う3PL(サードパーティ・ロジスティクス)と呼ばれるビジネスモデルでは、これら全ての機能を組み合わせて最適な物流ソリューションを提供します。
【物流業界】特徴
物流業界は、経済の血液とも呼ばれるように、社会になくてはならない存在です。
それゆえに公共性が高く、安定した需要があるのが特徴です。
一方で、景気や国際情勢、あるいは燃料価格の変動といった外部要因の影響を受けやすい側面も持っています。
最近では、ドライバー不足や2024年問題への対応として、AIやロボティクスによる自動化・効率化(物流DX)が急速に進んでいる、変革期の業界でもあります。
社会活動や経済に不可欠で、公共性が非常に高いビジネスモデル
物流業界の最大の特徴は、その圧倒的な公共性です。
私たちの生活は、物流が正常に機能していることを前提に成り立っています。
例えば、コンビニやスーパーに毎日商品が届くこと、企業の工場が部品を受け取って生産活動ができること。
これら全てが物流によって支えられています。
パンデミックの際にも、医療物資や生活必需品の輸送を担う物流業界は、社会機能を維持するためのエッセンシャルワークとして再評価されました。
このように、物流は利益を追求する民間企業でありながら、同時に社会インフラを担うという強い使命を帯びています。
そのため、景気の波によって需要がゼロになることはありません。
人々の生活や経済活動が続く限り、モノの流れは決して止まらないため、非常に安定したビジネスモデルであると言えます。
この安定性と社会貢献性の高さが、物流業界の大きな魅力です。
天候、交通状況、国際情勢に業績が左右されやすい
社会インフラとして安定している一方で、物流業界は自社でコントロールできない外部要因の影響を非常に受けやすいという特徴も持っています。
例えば、大雨や台風、大雪などの悪天候が発生すると、トラックは速度制限や通行止めに、船や飛行機は欠航になる可能性があります。
これにより、配送の大幅な遅延やコストの増加が発生します。
また、陸運は高速道路の事故渋滞、海運はスエズ運河の座礁事故のような国際的な隘路(チョークポイント)の問題、空運は火山の噴火による航空網の麻痺など、予期せぬトラブルの影響を直接受けます。
さらに、国際物流は世界経済の動向と直結しています。
好景気でモノの動きが活発になれば業績は上がりますが、不況になれば輸送量は減少します。
燃料である原油の価格高騰や、為替変動も収益に大きな影響を与えます。
このように、常に外的リスクにさらされながらも、いかに安定してモノを届け続けるかが問われる産業です。
テクノロジーによる効率化・変革が急速に進んでいる
物流業界は今、大きな変革期を迎えています。
その最大の要因は、深刻化する人手不足、特にトラックドライバーの不足です。
これに加えて、EC(電子商取引)の拡大による小口多頻度配送の増加、そして2024年問題と呼ばれるドライバーの労働時間規制の強化が、業界全体の大きな課題となっています。
こうした課題を解決するため、テクノロジーによる効率化、いわゆる物流DX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいます。
具体的には、AIによる最適な配送ルートの自動算出、倉庫内でのピッキング作業を行うロボットの導入、ドローンや自動運転トラックによる無人配送の実証実験などです。
また、伝票のデジタル化や、ブロックチェーン技術によるトレーサビリティ(輸送追跡)の高度化も進んでいます。
物流業界は、かつての労働集約的なイメージから、最新テクノロジーを駆使するスマートな産業へと変貌を遂げようとしているのです。
【物流業界】向いている人
物流業界は、社会インフラを支えたいという強い使命感を持つ人に向いています。
また、世界中のモノの流れを裏側でコントロールすることに興味がある人にも最適です。
一見地味に見えるかもしれませんが、グローバルなサプライチェーンの最適化を考えるダイナミックな仕事も多くあります。
日々の業務を確実にこなし、チームと連携できる堅実さも求められる業界です。
グローバルなモノの流れや、サプライチェーンの「効率化」に関心がある人
物流業界は、モノが国境を越えて動くグローバルなビジネスの最前線です。
特に海運会社や国際フォワーダー(国際物流業者)の仕事は、世界経済のダイナミズムを肌で感じることができます。
例えば、どの航路にどれだけの船を配置すれば最も効率的か、A国の工場からB国の倉庫を経由してC国の消費者に届ける最適なルートは何か、といったグローバルなパズルを解くような仕事です。
このような、世界地図を俯瞰してモノの流れ、すなわちサプライチェーン全体を設計し、その効率化や最適化を考えることにワクワクする人は、物流業界に非常に向いています。
物流の効率化は、単にコストを削減するだけでなく、環境負荷の低減(CO2削減)にも直結します。
社会貢献とビジネスの効率性を両立させることに知的な面白さを感じられる人にとって、物流業界は非常にやりがいのある舞台となるでしょう。
地道な調整や作業を遂行できる人
物流の仕事は、華やかな企画立案ばかりではありません。
むしろ、その多くは日々の地道な調整業務や、ミスが許されない確実なオペレーションの遂行によって成り立っています。
例えば、お客様(荷主)からの急な配送依頼への対応、ドライバーや倉庫作業員との連携、税関手続きのための膨大な書類作成、天候や交通状況による遅延発生時のリカバリープランの策定など、泥臭い調整業務が日常的に発生します。
また、倉庫管理や運航管理の仕事では、安全ルールや作業手順を100%守り抜き、ミスや事故を絶対に起こさないという堅実さが求められます。
派手な成果を求めるよりも、関係者と粘り強く交渉し、決められたことを確実にやり遂げることに満足感を覚える人。
あるいは、複雑に絡み合った現場の課題を一つ一つ丁寧に解きほぐしていくような仕事が苦にならない人。
そうした堅実さと忍耐強さを持った人が、物流の現場を支え、信頼を勝ち取ることができます。
社会インフラを「止めない」という強い使命感や責任感を持てる人
物流は、止まることが許されない社会インフラです。
もし物流が止まれば、人々の生活は混乱し、経済活動は麻痺してしまいます。
この社会基盤を絶対に止めない、という強い使命感と責任感こそが、物流業界で働く上で最も重要な資質です。
台風や大雪の日でも、人々が寝静まった深夜でも、物流の現場は動き続けています。
それは、自分が休むと誰かの生活が困る、社会が回らなくなるという自覚があるからです。
パンデミックや災害時といった有事の際にこそ、その真価が問われます。
このような状況下で、困難を乗り越えてでもモノを届けようとする責任感。
自分の仕事が社会を支えているという誇り。
これらを持てる人は、物流業界から強く求められます。
誰かの役に立っていることを実感したい、社会貢献性の高い仕事がしたいと考える人にとって、物流業界は最適な選択肢の一つと言えるでしょう。
【物流業界】内定をもらうためのポイント
物流業界の内定を得るためには、なぜ数ある業界の中で物流を選ぶのか、その理由を明確にすることが最も重要です。
社会インフラとしての重要性への共感や、サプライチェーンの効率化への興味など、自分なりの切り口を見つけましょう。
また、物流はチームワークで成り立つため、規律性や協調性をアピールすることも効果的です。
物流業界の課題であるDX(デジタルトランスフォーメーション)にどう貢献したいかを語れると、さらに評価が高まります。
「なぜ物流か」を社会を支える重要性や、効率化への興味と絡めて語る
就職偏差値が高い物流企業、特に海運や大手倉庫の選考では、志望動機の深さが厳しく問われます。
単に安定していそう、グローバルに働けそう、といった理由だけでは不十分です。
なぜメーカーでも商社でもなく、物流業界なのか。
その答えを、業界の特性と結びつけて語る必要があります。
最も王道なのは、社会インフラとしての重要性に焦点を当てることです。
パンデミックや災害時に物流が社会を支えた事実に触れ、自分も社会基盤を止めないという使命感を持って働きたい、という熱意を伝えるアプローチです。
もう一つは、効率化への興味です。
物流は、AIやデータを活用して最適化を図る、いわば理系的な側面も持っています。
パズルのように複雑なサプライチェーンを、テクノロジーやアイデアでいかに効率化し、コストや環境負荷を下げるか。
そうした知的な面白さに魅力を感じた、という志望動機も説得力があります。
いずれにせよ、物流業界の社会的な役割を深く理解した上での志望動機が不可欠です。
チームで連携し、時間やルールを守ってタスクを完遂した経験をアピール
物流の仕事は、一人のスーパースターが活躍するのではなく、多くの部門や協力会社が連携するチームプレーで成り立っています。
そして、安全と時間を守ることが絶対的なルールです。
そのため、学生時代の経験として、個人の能力の高さよりも、チームの一員として規律を守り、仲間と協力して目標を達成したエピソードが高く評価されます。
例えば、体育会の部活動で、安全ルールを徹底しながら練習メニューを管理した経験。
あるいは、文化祭の実行委員として、多くの関係者と地道な調整を重ね、スケジュール通りにイベントを成功させた経験。
飲食店のアルバイトで、スタッフと連携して時間内に正確なデリバリーを行った経験なども良いでしょう。
重要なのは、その中で自分がどのような役割を果たし、時間を守るため、あるいはルールを守るためにどのような工夫や努力をしたかを具体的に語ることです。
誠実さや責任感、協調性といった資質が、物流業界で働く上で不可欠であることをアピールしましょう。
国内外のモノの流れ(サプライチェーン)への理解や、DXにどう貢献したいか
選考を突破するためには、物流業界が直面している課題への理解も欠かせません。
その代表が、サプライチェーンの複雑化と、人手不足に対応するためのDX(デジタルトランスフォーメーション)です。
単に物流に興味があると言うだけでなく、現代のモノの流れがどのような課題を抱えているかを自分なりに勉強しておくことが重要です。
例えば、ECの拡大が物流現場にどのような影響を与えているか、2024年問題とは具体的に何か、といった点です。
その上で、こうした課題に対して、自分が入社後にどう貢献したいかを語れると、他の就活生と大きな差をつけることができます。
例えば、データ分析のスキルを学んでおり、AIによる配送ルート最適化に貢献したい。
あるいは、異文化コミュニケーション能力を活かして、海外のパートナー企業との情報連携をスムーズにし、サプライチェーンの透明性を高めたい、などです。
未来の物流を創る一員としてのポテンシャルを示すことが、内定への近道となります。
【物流業界】よくある質問
物流業界は、就職偏差値や企業規模に関わらず、学生の皆さんから多くの質問をいただきます。
特に、現場仕事のイメージから来る体力面の不安や、AIによる自動化で仕事がなくなるのではないか、といった将来性に関する疑問が多いようです。
また、勤務体系に関する質問もよく寄せられます。
ここでは、そうした物流業界特有のよくある質問について、実情を解説していきます。
体力がないと(または女性は)不利ですか?
結論から言うと、総合職や一般職の採用において、体力がないことや女性であることが不利になることはありません。
確かに、トラックドライバーや倉庫内の荷役作業員など、現場の第一線では体力が必要な仕事もあります。
しかし、物流業界の仕事はそれだけではありません。
むしろ、大手企業や就職偏差値ランキング上位の企業の総合職は、その多くがデスクワーク中心です。
例えば、お客様の物流ニーズをヒアリングして最適なプランを設計する営業企画、船や飛行機のスペースを管理するブッキング業務、データ分析によってサプライチェーンの課題を洗い出すコンサルティング業務、あるいは人事や経理といった管理部門など、体力を必要としない仕事の方が圧倒的に多いのです。
近年は、倉庫作業もロボット化や自動化が進んでおり、女性やシニア層でも働きやすい環境が整備されてきています。
体力よりも、むしろ細やかな気配りや、粘り強い調整能力、データ分析能力などが求められる場面が増えています。
AIや自動化で仕事はなくなりますか?
AIや自動化によって、物流業界の仕事が将来なくなるのではないか、という不安を持つ人も多いでしょう。
確かに、倉庫内の単純なピッキング作業や、伝票の入力作業、あるいはトラックの自動運転が実現すればドライバーなど、一部の定型的な仕事はAIやロボットに置き換えられていく可能性が高いです。
しかし、物流業界の仕事が全てなくなるわけでは決してありません。
むしろ、AIや自動化が進むことで、人間にしかできない、より付加価値の高い仕事の重要性が増していきます。
例えば、AIが算出したデータを基に、お客様に新たな物流戦略を提案するコンサルティング業務。
自動化設備を導入・管理するためのシステム設計。
あるいは、予期せぬトラブル(天候不順や事故)が発生した際の、複雑なリカバリープランの策定や関係各所との調整。
これらは、高度な判断力やコミュニケーション能力、創造性を必要とするため、AIには代替できません。
物流業界は、仕事がなくなるのではなく、仕事の質が大きく変わっていく業界だと理解するのが正しいでしょう。
現場仕事は休みがないですか?
物流は24時間365日動いているインフラ産業であるため、職種によっては不規則な勤務やカレンダー通りの休みが取りにくい場合があります。
特に、空港の貨物部門や、24時間稼働の物流センター(倉庫)、あるいは長距離トラックドライバーや船乗り(海運)といった職種は、シフト制勤務や長期休暇がまとまって取れる(代わりに航海中は休みなし)といった特殊な勤務体系になることが多いです。
しかし、これは物流業界のすべての仕事に当てはまるわけではありません。
例えば、本社の総合職(営業、企画、人事、経理など)は、他の業界の一般的な企業と同様に、土日祝日休みのカレンダー通りの勤務が基本です。
また、現場仕事であっても、労働基準法に基づいた休日が必ず設定されており、休みなく働き続けるということはありません。
近年は、2024年問題への対応として、むしろ業界全体で労働時間の管理や休日の確保が厳しく義務付けられており、働き方改革が急速に進んでいる分野でもあります。
まとめ
物流業界は、社会インフラを支える使命感と、グローバルなモノの流れを動かすダイナミズムを持つ魅力的な業界です。
就職偏差値のランキングで見ると、海運大手や財閥系倉庫は最難関ですが、それ以外にも優良なBtoB企業が数多く存在します。
物流業界が直面する課題であるDXやサプライチェーンの効率化に、自分がどう貢献できるかを具体的にアピールすることが、内定を勝ち取る鍵となります。
この記事を参考に、業界研究を深めて選考に臨んでください。