
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
【薬学部の就職先】はじめに
薬学部の進路は六年制と四年制で大きく変わります。
本記事では二つの違いと共通点を整理しながら、薬剤師の仕事について詳しく解説します。
【薬学部の就職先】進路選択のリアル:6年制と4年制の違いと共通点
薬学部には、薬剤師国家試験の受験資格を得られる6年制と、研究者や開発者を目指す4年制の2つのコースがあります。
どちらのコースを選ぶかによって、就職先やキャリアパスは大きく変わります。
6年制は臨床現場や医療機関での薬剤師職が中心である一方、4年制は研究・開発職を目指して大学院に進む学生が多数を占めます。
一見すると進路が限定的に見えますが、薬学の専門性は幅広い業界で求められており、近年は薬剤師資格を取得せず別の道を選ぶ学生も増えています。
薬学部6年制(薬学科)卒業生の主な進路と特徴
6年制薬学科の学生は、卒業と同時に薬剤師国家試験の受験資格を得られます。
そのため、卒業後は薬剤師として医療現場で活躍するケースが圧倒的に多いです。
病院や調剤薬局、ドラッグストアといった医療の最前線で働くことが主な進路であり、約8割の学生が薬剤師として就職しています。
勤務先によって業務内容は異なりますが、患者とのコミュニケーションや処方箋調剤、医療チームとの連携といった役割が中心です。
一方で、残りの約2割の学生は、薬剤師資格を活かしながら一般企業や公的機関へ進む道を選びます。
製薬メーカーでのMR職、治験関連企業での開発職、公務員としての薬事監視など、活躍の場は広がっています。
薬剤師資格は医療分野で強い武器になるため、安定性のある進路を選びやすいことが大きな特徴です。
薬学部4年制(薬科学科)卒業生の主な進路と特徴
4年制薬科学科の学生は薬剤師免許を取得できません。
そのため、より研究開発に特化した進路を選ぶ人が多いのが特徴です。
約8〜9割の学生が大学院に進学し、修士課程でさらに専門性を高めた上で、製薬会社や化学メーカー、バイオ関連企業などで研究職・開発職に就職します。
研究室での実験経験や専門知識をもとに、創薬、医薬品開発、品質管理、分析業務などに携わるケースが一般的です。
一方で、学部卒で就職する人も1〜2割存在します。
この場合、研究補助職や営業職、開発支援業務(CROなど)が主な進路となりますが、修士卒に比べると選択肢は限られやすい傾向があります。
そのため、4年制の学生にとって大学院進学はほぼ必須のキャリアパスといえます。
薬剤師免許はなくても、研究分野での専門性を活かすことで、多様な産業分野で活躍できる可能性があります。
就職活動を始めるべきタイミングと準備
薬学部の就職活動は、他学部と比べて早めの準備が必要です。
6年制の場合は、国家試験対策と就活を並行して行う必要があるため、5年次の後期から動き始める学生が多く見られます。
病院や薬局での実習経験を整理し、自分の得意分野や将来像を早い段階で明確にすることが重要です。
一方、4年制の学生や大学院生は、M1の早い段階からインターンシップや企業研究を始めることが成功の鍵になります。
製薬会社やバイオ関連の研究職は競争率が高いため、志望企業の情報収集や業界理解を深めることが欠かせません。
また、研究内容と志望職種の関連性を自分の言葉で説明できるように準備しておくと、選考を有利に進められます。
薬学の専門性を活かしたキャリアを描くためには、就活の早期スタートが非常に有効です。
薬剤師になりたくないと感じる学生が増えている
近年、薬剤師を目指さずに別の進路を考える学生が増えています。
その背景には、調剤業務の単調さへの不安や、キャリアの停滞感、将来性への懸念といった意識があります。
調剤や服薬指導が中心となる現場では、スキルの幅を広げにくいと感じる学生も少なくありません。
さらに、AIやロボット技術の発展により、将来的に一部の業務が自動化されることへの不安もあります。
しかし、これは決して悲観的なことではなく、薬学の専門性を医療以外の分野で生かしたいという前向きな意思表示ともいえます。
実際に、製薬業界、化粧品、食品、バイオテクノロジー、データサイエンスといった分野で活躍する薬学部出身者も増えています。
薬剤師になることだけが進路ではなく、自分の関心と強みを生かした多様なキャリアパスがあるという視点を持つことが大切です。
【薬学部の就職先】薬学部出身のメイン選択肢:薬剤師とは
薬剤師は、人々の健康と命を守るうえで欠かせない重要な職業です。
医師の処方箋に基づいて薬を調剤するだけでなく、患者の状態や薬の飲み合わせを確認し、安全に治療を受けられるよう支える役割を担っています。
また、医療現場では医師や看護師と連携し、治療の質を高めるチーム医療の一員としても活躍します。
薬剤師の主な就職先とその仕事内容
薬剤師の活躍の場は非常に幅広く、大きく分けると三つの就職先に分類されます。
それぞれの職場には異なる役割や求められるスキルがあり、自分の将来像や働き方に合わせた選択が必要です。
ここでは、それぞれの就職先での具体的な仕事内容や特徴を詳しく解説します。
調剤薬局
調剤薬局は、薬剤師の就職先として最も多い選択肢です。
医師の処方箋をもとに薬を調剤し、患者に対して服薬指導を行い、薬の飲み方や注意点を丁寧に説明します。
また、薬の使用履歴を記録し、重複投与や飲み合わせの確認を行う薬歴管理も重要な業務の一つです。
さらに近年では、高齢化社会の進展により、在宅医療にも対応する薬局が増えています。
在宅医療では、薬剤師が患者の自宅を訪問し、薬の管理や服薬のサポートを行います。
このように調剤薬局は、地域の人々と直接関わりながら医療を支える場であり、患者との距離が近い仕事です。
一人ひとりとじっくり向き合える環境であるため、人と話すことが好きな人や地域医療に貢献したい人に向いている職場です。
病院
病院薬剤師は、医療チームの一員として高い専門性が求められる職種です。
調剤業務はもちろん、入院患者や外来患者に対する薬の説明や管理、治療内容の確認を行います。
さらに、医師や看護師と密に連携しながら行う病棟業務も重要な役割です。
病棟業務では、処方内容の確認や副作用のチェック、点滴や注射薬の調製など、より専門的な知識と判断力が必要となります。
また、医薬品情報の管理や新薬の導入に関わるDI業務も担います。
これらの業務を通じて、患者の治療効果を高め、安全な医療の提供に貢献します。
病院で働く薬剤師は、日々医療の最前線に立ち、多職種と連携しながら専門性を磨くことができます。
高度な知識やスキルを身につけたい人にとって、大きなやりがいがある職場といえます。
ドラッグストア
ドラッグストアは、調剤と販売の両方を担う薬剤師の活躍の場です。
調剤室で処方箋に基づく調剤を行うだけでなく、一般用医薬品の販売や健康相談にも対応します。
生活習慣病やセルフメディケーションに関するアドバイスを行う場面も多く、地域住民とのコミュニケーションが非常に重要です。
また、店舗運営にも関わるため、在庫管理やスタッフの教育、売り場の改善といったマネジメント業務を経験することも可能です。
調剤業務と小売業務の両方に携わることで、幅広いスキルを身につけられる点が大きな特徴です。
さらに、店舗運営の経験を積むことで、将来的には管理薬剤師や店長といったキャリアアップの道も開かれます。
医療の知識だけでなく、経営や接客にも興味がある人にとって魅力的な職場です。
薬剤師の仕事の将来性は
薬剤師の将来性について不安を感じる人は少なくありません。
調剤の自動化やAIの進歩によって、仕事が減るのではないかと考える学生も増えています。
しかし、結論から言えば、専門性を高めた薬剤師の将来は明るいといえます。
今後の医療現場では、薬を渡すだけの仕事ではなく、対人業務がより重要になっていきます。
患者の生活背景を踏まえた服薬指導や、副作用のチェック、医師への処方提案などは、機械には代替できない役割です。
さらに、高齢化社会の進行に伴い、在宅医療の需要も増えています。
薬剤師が患者の自宅を訪問して薬の管理や健康相談を行うケースも多くなり、地域医療の担い手としての存在感が強まっています。
このように、薬剤師の仕事は単なる調剤から、より人と関わる方向へと変化しています。
薬剤師として就職活動を成功させるための対策
薬剤師の就職活動で大切なのは、専門知識だけではなく、人柄や実践的な経験です。
病院や薬局での実習経験は、もっとも重要なアピールポイントになります。
単に経験した事実を述べるのではなく、何を学び、どのような工夫をしたのかを具体的に説明できるように整理しておく必要があります。
また、医療現場では患者や医師、看護師など多くの人と関わるため、コミュニケーション能力も評価されます。
アルバイトや部活動、ボランティアなどで培った協調性や傾聴力を伝えるエピソードが有効です。
さらに、志望先に対する明確な理由を持つことも重要です。
病院、薬局、ドラッグストアは、それぞれ業務内容や求められるスキルが異なります。
自分のキャリア像を踏まえて、なぜその職場を選んだのかをしっかり言葉にできれば、面接官に強い印象を与えることができます。
薬剤師の平均年収とキャリアパス
薬剤師は、医療職の中でも安定した収入が期待できる職種です。
初任給は一般的に年収400万から500万円程度と高水準で、就職先によってはさらに高い場合もあります。
その後のキャリアパスは多岐にわたります。
薬局やドラッグストアでは、経験を重ねることで管理薬剤師となり、経営や在庫、人事といった店舗運営にも携わります。
また、専門知識を深め、感染制御やがん薬物療法などの認定資格を取得すれば、高度な医療に関わるスペシャリストとしての道も開けます。
独立して薬局を経営することも可能で、経営手腕によって大きな収入を得る人も少なくありません。
さらに、臨床での経験を活かして製薬メーカーや公務員に転職するケースもあります。
薬剤師のキャリアは一つの道に限られず、経験とスキルの積み重ねによって大きく広がっていきます。
【薬学部の就職先】薬剤師以外のキャリア:メーカー
薬学部出身者の進路というと、まず薬剤師を思い浮かべる人が多いです。
しかし、薬学の専門知識は医療現場だけでなく、メーカーなどの民間企業でも高く評価されています。
特に製薬メーカーをはじめ、化粧品や食品といったヘルスケア関連の業界は、薬学部生にとって人気の高い選択肢です。
ここでは、薬剤師以外の進路として代表的なメーカーの職種と、その仕事内容を詳しく解説します。
製薬メーカー:MR(医薬情報担当者)の仕事内容
MRは、自社の医薬品について医療従事者に正確な情報を提供する役割を担います。
医師や薬剤師に対し、薬の効果や安全性、副作用の情報を伝えることで、適切な使用を促すことが主な仕事です。
同時に、医療現場で得られた副作用や使用状況の情報を開発部門にフィードバックし、今後の改良や新薬開発に役立てます。
営業的な側面と、専門知識を活かした学術的な側面の両方を持つため、幅広いスキルが求められます。
特に重要なのは、医療従事者と信頼関係を築くコミュニケーション力です。
担当エリアを広く回る必要があるため体力も必要であり、数字を意識した営業姿勢と誠実な対応力の両立が求められます。
薬学部で学んだ知識を活かしながら、ビジネスの現場で活躍できる人気の高い職種です。
製薬メーカー:研究職・開発職の仕事内容
研究職は、新しい薬を生み出すための基礎研究を担当します。
高度な知識と実験技術が必要なため、修士以上の学歴が必要となるケースが多く見られます。
一方、開発職は研究段階で見つかった候補物質を、人に使える医薬品として実用化する役割を担います。
治験の計画や実施、データ解析、薬事対応などが中心であり、綿密な計画力と論理的な思考が求められます。
新薬が世の中に出るまでには長い年月と多くの人の協力が必要です。
その中で研究職と開発職は、医療の進歩を支える重要な役割を担っています。
薬学の知識を深め、社会に大きな影響を与える仕事を目指す人に向いている分野です。
製薬メーカー:品質管理・品質保証の仕事内容
医薬品は人の健康に直接関わるものであるため、品質の確保が非常に重要です。
品質管理(QC)は、製造された医薬品が国の基準や社内の規格を満たしているかを試験・分析する仕事です。
異物混入や成分のばらつきがないかを厳しくチェックし、安全性を保証します。
一方、品質保証(QA)は、製造過程全体が適切に管理されているかを監査し、法令や規則の遵守状況を確認する仕事です。
いずれも医薬品の信頼性を守るための重要な役割であり、責任感と正確な判断力が求められます。
営業職や研究職と比べると比較的安定した勤務環境であることが多く、ワークライフバランスを重視する学生にも人気があります。
薬学部で培った基礎知識を活かしながら、裏方として社会に貢献できる職種です。
製薬メーカー:化粧品・食品メーカーの仕事内容
薬学の知識は、製薬業界以外でも活かすことができます。
化粧品メーカーでは、皮膚科学や薬理学の知識を活かし、製品の処方設計や有効成分の選定、品質管理などを行います。
スキンケア製品や医薬部外品などの開発に関わるケースも多く、消費者の生活に近い領域で活躍できます。
食品メーカーでは、生化学や栄養学の知識を基盤に、健康志向の高まりに対応した機能性食品の開発に携わります。
特定保健用食品や機能性表示食品といった製品の研究・開発・品質保証に関わる仕事が中心です。
医療現場とは異なるフィールドでありながら、人々の健康を支える役割を担う点は薬剤師と共通しています。
幅広い業界で薬学の知識を応用できることは、大きな強みといえます。
メーカーへの就職は4年制・6年制どちらが有利?
メーカーへの就職は、目指す職種によって有利な学歴が異なります。
研究職や開発職を目指す場合は、4年制の大学院修了者がもっとも有利な立場となります。
6年制卒の場合は大学院進学がほぼ必須であり、院に進めば十分に競争力を持てます。
一方、MR職は4年制・6年制どちらの学生にも広く門戸が開かれており、薬剤師資格を持つ6年制卒は特に有利になる傾向があります。
品質管理や品質保証は、学部卒でも比較的就職しやすい分野ですが、院卒になるとより高い評価を受けやすくなります。
このように、薬学部の知識は多様な職種に活かすことができ、進路の幅は広いです。
薬剤師として臨床に進むだけでなく、企業の一員として社会を支えるキャリアを描く道も十分に現実的です。
【薬学部の就職先】4年制向け:大学院進学は必須?学部卒で目指せる業界・業種
薬学部4年制は、薬剤師免許を取得できる6年制と異なり、研究や開発を重視した学びが特徴です。
そのため、卒業後の進路では、大学院に進学するか、学部卒で就職するかという大きな分かれ道があります。
研究職を目指す学生の多くは大学院に進学しますが、学部卒でも活躍できる職種は存在します。
どの道を選ぶかによって、将来のキャリアの幅や待遇、仕事の内容は大きく変わります。
薬学部4年制卒業生の学部卒と修士卒の就職先の違い
薬学部4年制の卒業生にとって、学部卒と修士卒ではキャリアの選択肢に大きな差が出ます。
まず、専門性という点で、修士卒は学部卒よりも深い研究経験と知識を持つため、企業から高く評価されやすくなります。
製薬メーカーを例にすると、学部卒は営業職やCRO(臨床開発支援)、一般職への就職が中心となり、研究職への採用は非常に難しいのが現状です。
一方、修士卒は研究職・開発職の主要な採用対象となり、就職の幅が大きく広がります。
さらに、給与面でも初任給に2万〜4万円程度の差が出ることがあります。
また、修士卒は専門職採用枠に応募できるため、学部卒よりも競争相手が限定され、有利に進められるケースもあります。
学部卒の場合は、他学部の学生との競争が激しくなる傾向があります。
大学院進学のメリット・デメリット
大学院進学は、研究職や開発職を目指すうえで非常に有利な選択です。
メリットとして、まず製薬メーカーなどの研究職への応募資格を得られます。
専門性が深まるため、就職先の幅が広がるのも大きな利点です。
また、修士卒は初任給が優遇されやすく、キャリアの初期段階から待遇面でも差がつく傾向があります。
一方で、学費や時間の負担が増えるというデメリットもあります。
さらに、研究テーマの進行次第では成果が出ず、就職活動で思うようにアピールできないリスクもあります。
進学を考える際は、将来のキャリアパスと費用対効果を冷静に考えることが重要です。
学部卒で就職する際の強みとなるスキルとは
学部卒で就職活動を行う場合、薬学の専門知識に加えて、汎用性の高いスキルを強調することが重要です。
まず、卒業研究の経験は強いアピールポイントとなります。
研究が途中であっても、課題に対してどのように仮説を立て、実験を進め、問題を解決しようとしたのかというプロセスを伝えることで、分析力や粘り強さを示せます。
また、営業職や企画職などではコミュニケーション力が重視されます。
アルバイトやサークル活動でのチーム経験も有効な材料になります。
さらに、薬学で培った論理的思考力は、多くの業界で評価されやすいスキルです。
自分の強みを専門性と一般的なスキルの両面から整理することが成功への鍵になります。
学部卒からでも目指せる専門性の高い職種
修士卒が多い中でも、学部卒で専門性を活かせる職種は存在します。
まず、CRO(開発支援)の分野では、CRA(臨床開発モニター)の補助やデータ管理業務などのアシスタント職があります。
これらは薬学の基礎知識を活かしながら、医薬品開発に携わることができる職種です。
また、医療機器メーカーでは、薬剤ではなく機器を扱う技術営業職やサポート職があります。
医療現場とのやりとりが多いため、薬学の背景が強みになります。
さらに、公務員として行政系や技術系の職に就く道もあります。
薬学の知識は公衆衛生や医療行政など、幅広い分野で活用できるため、安定した進路として人気があります。
このように、学部卒でも努力次第で専門性を活かしたキャリアを築くことは十分可能です。
【薬学部の就職先】薬剤以外の道を選ぶ際に後悔しないキャリア戦略
薬学部に進学したものの、将来的に薬剤師になりたくないと考える学生は近年少なくありません。
調剤業務の単調さや将来性への不安、より広い分野で活躍したいという気持ちなど、その理由はさまざまです。
しかし、ただ漠然と「薬剤師にならない」という選択をするだけでは、後悔するリスクも高くなります。
大切なのは、自分自身をよく理解し、戦略的にキャリアを組み立てることです。
自分の適正を見極める自己分析の重要性
まず、薬剤師以外の道を選ぶ際に最も重要なのは、自分がなぜその道を選びたいのかを明確にすることです。
薬剤師になりたくない理由を深掘りすることで、自分が何を求めているのかが見えてきます。
単調な業務が嫌だと感じているなら、人との関わりが多い仕事や、ものづくりに携わる仕事に興味がある可能性があります。
また、価値観を整理することも大切です。
給与、ワークライフバランス、社会貢献、成長環境といった要素の中で、何を重視するのかを明確にしましょう。
さらに、過去の経験を棚卸しすることで、自分の強みや興味の方向性が見えてきます。
研究、アルバイト、サークルなどの活動の中で楽しかったことや達成感を感じた場面を振り返ると、進むべき方向がよりはっきりします。
薬学以外のスキルの磨き方
製薬メーカーの研究職や外資系企業を目指すなら、英語力は必須のスキルです。
特にTOEICなどの資格は、採用や配属先に直接影響するケースもあります。
さらに、PCスキルも重要です。
Excelによるデータ処理や統計解析の経験は、品質管理や開発職でも強いアピールになります。
営業職やコンサルタント職を視野に入れるなら、傾聴力や提案力、プレゼンテーション能力といった対人スキルが欠かせません。
こうしたスキルは、アルバイトや学生団体などの日常的な活動の中でも磨くことができます。
薬学の専門性と社会人基礎力を両立させることで、進路の幅は大きく広がります。
志望業界・職種別のインターンシップ活用法
薬剤師以外の進路を考えるうえで、インターンシップは非常に重要なステップです。
短期インターンでは、製薬メーカーの研究職やCRO、MRなどの職種の業務内容を実際に体験できます。
夏から秋にかけて募集が始まることが多いため、早めの情報収集と応募が必要です。
一方、一般企業の長期インターンでは、IT企業やコンサル業界などでビジネススキルを磨くことができます。
業界研究と自己分析を兼ねて複数のインターンに参加することで、自分に合った職種を見極められます。
インターンシップは単なる職場体験ではなく、志望動機を強化する重要な材料にもなります。
就活本番で説得力を持って語るためにも、積極的に活用することが効果的です。
薬剤師資格を取得することのメリット・デメリット
6年制の学生にとって、薬剤師資格を取得するかどうかは大きな分岐点です。
資格取得には国家試験対策という大きな負担が伴いますが、その価値は小さくありません。
メリットとしてまず挙げられるのは、キャリアの保険となることです。
もし他の業界でのキャリアが合わなかった場合、薬剤師としての道に戻ることができます。
また、薬剤師資格は専門性の証明にもなり、企業によっては資格手当の対象となる場合もあります。
一方で、国家試験対策と就活が重なるため、時間的な負担は大きくなります。
さらに、非薬剤師職を目指す場合は、面接で必ず「なぜ資格を使わないのか」という質問を受けるため、明確な回答を準備する必要があります。
資格を取るか取らないかは、将来のキャリア戦略と照らし合わせ、慎重に判断することが大切です。
【薬学部の就職先】就職活動を成功させるための実績的なアドバイス
薬学部生は、専門性の高い知識と実習経験を持つため、他の学部の学生とは異なる強みを活かした就職活動が必要です。
薬剤師としての道を選ぶ人もいれば、製薬メーカーや一般企業を目指す人もいます。
どちらの道に進む場合でも、自分の強みを整理し、それを企業に伝える戦略を立てることが重要です。
薬学部生がアピールするべき強みの具体例
薬学部の学びを通じて身につけた能力は、企業にとって大きな魅力となります。
まず一つ目は、論理的思考力と正確性です。
調剤や実験では細かな手順を正確にこなす力が求められ、課題解決を論理的に進める力も自然と身につきます。
二つ目は、忍耐力と粘り強さです。
6年間にわたる学習、実験の積み重ね、実習の経験は、困難な課題に立ち向かう力の証明になります。
三つ目は、専門知識です。
薬理学や分析化学などの専門分野の知識を、志望職種にどう活かせるかを明確に説明できれば、強力なアピール材料になります。
企業は、知識だけでなくそれを実践にどうつなげるかを見るため、強みは具体的なエピソードとセットで伝えることが大切です。
ESで差をつけるための書き方
エントリーシートで重要なのは、読みやすさと説得力です。
まず研究テーマについては、専門外の人にも伝わるように説明することを意識します。
背景、目的、手法、結果、学びの流れで整理し、専門用語をできるだけ避けることで、内容が伝わりやすくなります。
志望動機では、薬学の知識を活かしたいという漠然とした内容ではなく、その企業でなければならない理由を明確にします。
企業の研究分野や事業内容、理念などを事前に調べ、自分の経験や興味と結びつけることが重要です。
また、文章は長くなりすぎないように簡潔にまとめることも大切です。
エントリーシートの完成度は、面接への第一関門となるため、丁寧な準備が欠かせません。
OB・OG訪問を効果的に行うための質問リスト
OB・OG訪問は、インターネットでは得られない情報を得る絶好の機会です。
まず、仕事の実情について尋ねる質問を用意しましょう。
たとえば、一日のスケジュールや大変な業務内容、入社前とのギャップなどを聞くことで、実際の働き方をイメージできます。
次に、キャリアパスに関する質問も重要です。
5年後、10年後にどのようなキャリアを築けるのか、薬学の知識をどのように活かしているのかを聞くことで、長期的な視点を持てます。
さらに、職場の雰囲気や社風を知るための質問も効果的です。
チーム内の連携や社員同士の関係性を聞くことで、自分に合った職場かどうかを判断できます。
訪問の目的を明確にし、質問を準備して臨むことで、得られる情報の質は格段に上がります。
面接で必ず聞かれる質問と模範解答
薬学部生は、面接で聞かれる質問の傾向が明確です。
まず、薬剤師以外の職種を志望する場合、必ず「なぜ薬剤師にならなかったのか」と聞かれます。
このときは、薬剤師という職業を否定するのではなく、自分の志向との違いを冷静に説明することがポイントです。
たとえば、「より多くの人に影響を与える仕事に挑戦したい」「研究や開発の現場で新しい価値を生み出したい」といった前向きな理由を伝えると効果的です。
薬剤師職を志望する場合は、実習経験から学んだことを具体的に話すことが重要です。
困難な状況をどう乗り越えたのかをストーリーとして語ることで、課題解決力や対人スキルをアピールできます。
【薬学部の就職先】まとめ
薬学部の学生にはかなり多くのキャリア選択肢があります。
この記事を手がかりに価値観と強みを言語化し、納得できる進路選択へつなげていきましょう。

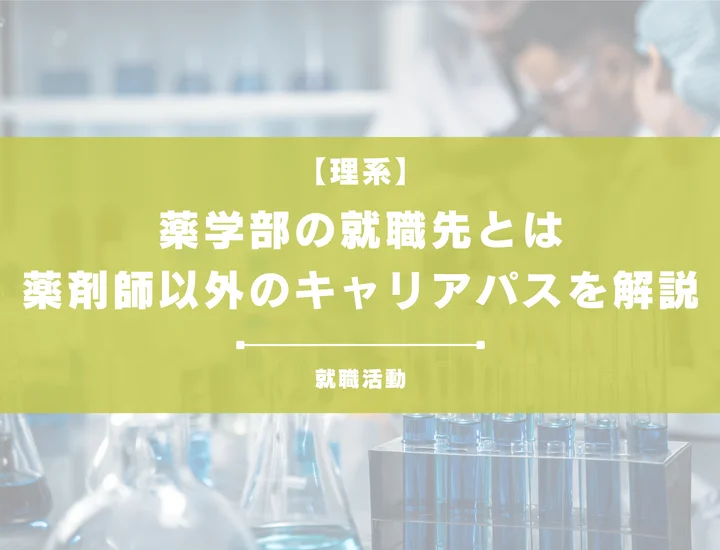


_720x550.webp)





