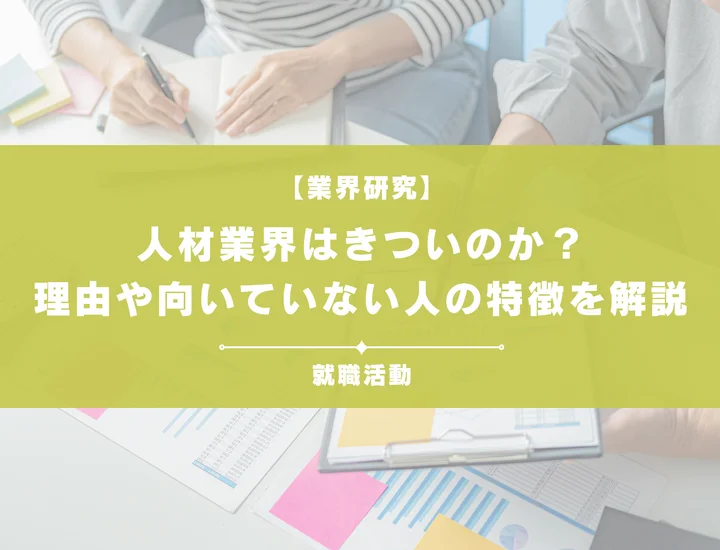HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
今回は、就活生の皆さんから「実際どうなの?」「きついって本当?」とよく聞かれる「人材業界」について、その実態を徹底解説していきます。
人のキャリアに関わるやりがいのある仕事ですが、同時に厳しいイメージもありますよね。
この記事では、人材業界の仕事内容から「きつい」と言われる理由、向いている人の特徴まで、皆さんの疑問に答えていきます。
ぜひ業界研究の参考にしてくださいね。
【人材業界はきついのか】人材業界はきつい?
就職活動を進める中で、「人材業界はきつい」という噂を耳にしたことがある人も多いかもしれません。
確かに、営業目標(ノルマ)へのプレッシャーや、企業と求職者という「人」を扱う難しさから、精神的・体力的にハードな側面があるのは事実です。
しかし、すべての仕事がそうだとは限りませんし、その「きつさ」を上回る大きなやりがいを感じられるのも、この業界の特徴です。
この記事では、なぜ「きつい」と言われるのか、その理由とリアルな実態を、客観的な視点で深掘りしていきます。
【人材業界はきついのか】人材業界の仕事内容
「人材業界」と一口に言っても、そのビジネスモデルは多岐にわたります。
共通しているのは、企業における「人」に関する課題、例えば「優秀な人材を採用したい」「人材育成に困っている」といった悩みや、個人の「働きたい」「キャリアアップしたい」という想いを繋ぎ、解決に導くことです。
皆さんがイメージする「人を紹介する」仕事以外にも、様々な形で「働く」を支援するサービスが存在します。
具体的にどのようなビジネスがあるのかを知ることは、業界理解の第一歩です。
ここでは、人材業界の主な事業内容を4つのカテゴリーに分けて、それぞれの仕事内容を詳しく見ていきましょう。
自分の興味がどの分野に近いか考えながら読んでみてください。
人材紹介
人材紹介は、正社員や契約社員として働きたい求職者と、人材を募集している企業とを仲介(マッチング)するサービスです。
エージェントと呼ばれることもありますね。
企業が求める人物像と、求職者が希望するキャリアや条件を詳細にヒアリングし、双方にとって最適な出会いを創出することがミッションです。
このサービスの多くは「成功報酬型」で、紹介した人材の入社が決定した時点で企業からフィー(紹介料)を受け取ります。
そのため、単に人を紹介するだけでなく、いかにミスマッチなく、長く活躍してもらえるかが重要になります。
求職者にとっては、非公開求人の紹介を受けられたり、キャリア相談に乗ってもらえたりするメリットがあります。
企業にとっては、採用活動の効率化や、自社だけでは出会えない層へのアプローチが可能になるという価値を提供しています。
企業の採用課題と個人のキャリアプランの両方に深く関わる、責任とやりがいの大きな仕事です。
人材派遣
人材派遣は、人材派遣会社(派遣元)が雇用するスタッフ(派遣社員)を、別の企業(派遣先)に派遣し、派遣先の指揮命令のもとで働いてもらうサービス形態です。
大きな特徴は、雇用契約を結ぶ会社(派遣元)と、実際に仕事をする場所(派遣先)が異なる点にあります。
企業側にとっては、繁忙期やプロジェクト単位など、必要な時に必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できるというメリットがあります。
働く側にとっては、勤務地や時間、業務内容など、自分のライフスタイルや希望に合わせた働き方を選びやすいのが特徴です。
派遣会社の役割は、スタッフの希望に合う仕事を紹介するだけでなく、派遣先企業との契約管理、そして派遣スタッフが安心して就業できるよう、定期的な面談やキャリア相談などのフォローアップを行うことも非常に重要です。
企業とスタッフの橋渡し役として、きめ細やかなサポートが求められます。
求人広告
求人広告は、企業の採用情報を自社で運営するWebサイトや雑誌などのメディアに掲載し、求職者を集めるサービスです。
皆さんが就職活動で利用しているナビサイトも、この求人広告の一種です。
このビジネスの役割は、単に広告枠を販売することではありません。
企業が「どんな人材を」「なぜ採用したいのか」という本質的な課題をヒアリングし、その企業の魅力がターゲットとなる求職者に最も響く形で伝わるような広告企画や原稿内容を提案します。
場合によっては、採用戦略全体の見直しや、採用ブランディングの支援から関わることもあります。
企業の採用成功が、メディアの価値向上に直結するため、どうすれば応募が集まり、良い採用に繋がるかをクライアントと二人三脚で考え抜く、コンサルティング的な側面も強い仕事です。
営業職が広告枠を提案し、制作職(ライター)が取材・執筆を担うなど、社内での連携も活発です。
その他(人材コンサルティング、研修サービスなど)
上記3つ以外にも、人材業界には「人」に関する多様なサービスが存在します。
例えば、企業の経営課題や組織課題を「人」の側面から解決する「人材コンサルティング」があります。
これには、人事評価制度の構築支援、組織風土の改革、採用戦略の立案などが含まれます。
また、「人材育成・研修サービス」も大きな柱です。
新入社員研修や管理職研修、特定のスキル(例:プログラミング、語学)を向上させるための研修プログラムを提供し、企業で働く人々の成長を直接的にサポートします。
最近では、適性検査や組織診断ツールの開発・販売(アセスメント事業)や、AIを活用した採用管理システム(ATS)を提供する「HRテック」と呼ばれる分野も急速に拡大しています。
採用だけでなく、入社後の活躍や組織全体の活性化まで、企業の「人」に関するあらゆる課題を支援する領域へと広がっているのが、現代の人材業界の姿です。
【人材業界はきついのか】人材業界の主な職種
人材業界のビジネスモデルを支えるのは、そこで働く「人」です。
業界のイメージから「営業職」が多いと思われがちですが、実際には様々な専門性を持った職種が連携してサービスを提供しています。
例えば、求職者に寄り添う役割、企業の課題を解決する役割、両者の間を調整する役割、そしてサービスを裏から支える役割など、多岐にわたります。
自分がどのポジションで強みを発揮できそうかをイメージすることは、業界研究において非常に重要です。
ここでは、人材業界で活躍する代表的な職種を5つピックアップし、それぞれの具体的な仕事内容や求められるスキルについて解説していきます。
自分の性格や得意なことと照らし合わせながら、どの職種に魅力を感じるか考えてみましょう。
キャリアアドバイザー(CA)/キャリアコンサルタント
キャリアアドバイザー(CA)は、主に人材紹介会社や派遣会社に所属し、仕事を探している求職者(個人)のサポートを専門に行う職種です。
キャリアコンサルタントと呼ばれることもあります。
最初のキャリアカウンセリング(面談)を通じて、求職者のこれまでの経験やスキル、今後のキャリアプラン、希望条件、さらには価値観や潜在的な強みまで深くヒアリングします。
その上で、その人に最適な求人を提案し、応募書類の添削や面接対策、企業との面接日程調整などを一貫してサポートします。
単に仕事を紹介するだけでなく、求職者自身が気づいていない可能性を引き出し、納得のいくキャリア選択ができるよう導く、まさに「キャリアの伴走者」です。
人の話に深く耳を傾ける傾聴力と、その人の将来を真剣に考えて提案できる力が求められる、非常にやりがいのある仕事です。
リクルーティングアドバイザー(RA)/法人営業
リクルーティングアドバイザー(RA)は、キャリアアドバイザー(CA)と対になる存在で、主に人材紹介会社で企業(法人)側のサポートを担当します。
一般的には「法人営業」と呼ばれる役割です。
RAのミッションは、企業の経営者や人事担当者から、事業戦略や組織課題、そして具体的な採用ニーズ(どんな人材が、なぜ、いつまでに必要なのか)を詳細にヒアリングすることです。
その上で、自社に登録している求職者の中から最適な人材を推薦したり、採用成功に向けた戦略的な提案(例:採用要件の見直し、面接プロセスの改善提案など)を行ったりします。
新規の取引先を開拓するための営業活動も重要な業務の一つです。
企業の事業成長を採用という側面からダイレクトに支援できる点が大きなやりがいです。
経営層と対話する機会も多く、課題解決能力や高度な交渉力が鍛えられます。
コーディネーター(人材派遣)
コーディネーターは、主に人材派遣会社において、派遣登録スタッフ(派遣社員)と派遣先企業のマッチングを担う職種です。
CAとRAの役割を一部併せ持つようなイメージに近いかもしれません。
まず、派遣登録を希望する方と面談し、スキルや希望条件をヒアリングします。
同時に、企業から寄せられる求人(どのようなスキルを持つ人が何時間、どの部署で必要か)を管理します。
そして、双方の希望条件が合致する最適な組み合わせを見つけ出し、仕事を紹介します。
仕事がスタートした後も、派遣スタッフが安心して働けているか定期的に連絡を取り、悩みやトラブルがあれば派遣先企業との間に入って調整する「フォローアップ」も非常に重要な業務です。
きめ細やかな気配りとスピーディーな対応力が求められ、多くの人の「働く」を支えている実感を得やすい仕事です。
求人広告の営業
求人広告の営業は、求人メディアを運営する会社で、企業に広告掲載を提案する職種です。
RA(リクルーティングアドバイザー)と似ていますが、商材が「人材」そのものではなく、「広告枠」や「採用支援サービス」である点が異なります。
主な業務は、企業の採用課題をヒアリングし、自社メディアのどのプランに、どのような内容の広告を掲載すればターゲット層に響き、応募に繋がるかを企画・提案することです。
企業の採用成功がゴールであるため、掲載して終わりではありません。
応募状況を分析し、「もっと魅力が伝わるように原稿を修正しましょう」といった改善提案も行います。
企業の隠れた魅力を引き出し、採用ブランディングを支援するクリエイティブな側面もあります。
成果が応募数や採用数といった目に見える形で返ってくるため、達成感を味わいやすい仕事です。
制作/ライター
制作(ライター)は、主に求人広告メディアにおいて、求人原稿の取材・執筆を担当する職種です。
営業担当者と協力し、時には同行して広告を掲載する企業へ訪問し、人事担当者や現場で働く社員の方々に直接インタビューを行います。
仕事のやりがい、職場の雰囲気、求める人物像、あるいは仕事の厳しさといったリアルな情報を引き出し、それを求職者の心に響く言葉で文章化していきます。
同じ仕事内容でも、ターゲット(例:未経験者、経験者、学生)によって訴求するポイントを変える工夫も必要です。
作成した原稿一つで、応募数や採用の質が大きく変わることもあり、企業の採用成功を左右する非常に重要な役割を担っています。
文章力はもちろん、相手の本音を引き出す取材力や、物事の本質を掴む理解力が求められる専門職です。
【人材業界はきついのか】人材業界がきついとされる理由
さて、この記事の核心ともいえる「人材業界がきつい」と言われる理由について、具体的に見ていきましょう。
多くの就活生が不安に感じるこのイメージは、どこから来ているのでしょうか。
もちろん、やりがいが大きい仕事であることは間違いありませんが、その裏で一定の「きつさ」を感じやすい業界特有の構造や業務特性が存在するのも事実です。
ただし、ここで挙げる理由がすべての企業、すべての職種に当てはまるわけではありません。
あくまで「そうした傾向がある」という視点で理解し、自分にとってそれは乗り越えられそうか、あるいは魅力が上回るかを判断する材料にしてください。
ノルマや目標達成へのプレッシャー
人材業界、特に営業職(RAや求人広告営業)や、成果が数字に直結しやすいCAなどの職種では、月間や四半期ごとの売上、成約件数、マッチング数といった目標(ノルマ)が設定されていることが一般的です。
特に人材紹介は成功報酬型ビジネスが主流であるため、成果(=入社決定)が出なければ売上がゼロというプレッシャーが常につきまといます。
目標達成への意識が低いと、周囲との差を感じたり、上司からの指導を受けたりすることもあるでしょう。
この「数字を追う」という環境を楽しめるか、それとも重圧に感じるかで、きつさの度合いは大きく変わってきます。
一方で、成果を出せばインセンティブ(報奨金)や昇進・昇給に直結しやすく、正当に評価されやすいという側面もあります。
業務量が多く、労働時間が長くなりがち
人材業界の仕事は、マルチタスクが基本です。
例えばCAであれば、複数の求職者の面談、書類添削、面接対策、企業への推薦、日程調整などを同時並行で進めます。
RAであれば、既存顧客のフォロー、新規開拓、求人票の作成、CAとの連携など、業務は多岐にわたります。
企業と求職者の間に立つため、双方のスケジュール調整や突発的なトラブル対応も発生しやすいです。
また、求職者との面談は、相手の仕事終わりの夜間や、土日に行われることも少なくありません。
結果として、業務量が多くなり、労働時間が長くなる傾向にあるのは事実です。
効率的なタスク管理能力と、オン・オフの切り替えが求められます。
扱うのが「人」であることの難しさ
この仕事のやりがいの源泉である「人」を扱うことは、同時に最大の難しさでもあります。
「人」の感情や状況は、機械やモノのように予測・コントロールすることができません。
例えば、内定が出て喜んでいた求職者が、突然「やはり辞退します」と連絡してきたり、入社直後に「イメージと違った」と早期退職してしまったりすることもあります。
企業と求職者の板挟みになり、理不尽な要求やクレームに対応しなければならない場面もゼロではありません。
自分の努力や誠意だけではどうにもならない事態に直面した時、精神的なタフさが求められます。
人の人生や企業の経営に深く関わるからこその、責任の重さを感じる瞬間です。
景気変動の影響を受けやすい
人材業界の市場動向は、社会全体の景気と密接に連動しています。
一般的に、景気が良い(好景気)と、企業は「もっと人手が必要だ」「事業を拡大したい」と採用活動を活発化させるため、求人数が増え、業界全体が活況を呈します。
逆に、景気が悪い(不景気)と、企業は採用を手控え、コスト削減のために人材関連の予算を真っ先にカットする傾向があります。
企業の採用意欲に業績が左右されやすいビジネスモデルであるため、個人の努力とは関係ない外部要因で、急に目標達成が難しくなるといった「きつさ」を感じることがあります。
安定性を最重要視する人にとっては、この変動の大きさが不安要素になるかもしれません。
新規開拓営業(テレアポなど)の精神的負担
特にRA(法人営業)や求人広告営業のキャリア序盤では、新規の取引先企業を開拓するための営業活動が求められることが多いです。
その代表的な手法が、いわゆる「テレアポ」(テレフォンアポインター)です。
企業のリストをもとに片っ端から電話をかけ、自社サービスを紹介し、商談のアポイントメント獲得を目指します。
当然ながら、話も聞いてもらえずに断られることが大半です。
1日に何十件、何百件と電話をかけ続ける中で、「自分は必要とされていないのでは」と精神的に疲弊してしまう人もいます。
この「断られること前提」の活動を、営業としての基礎体力をつけるための必要なプロセスと捉えられるかどうかが、一つの分岐点になります。
業界の競争激化
人材業界は、他の業界に比べて比較的参入障壁が低いとされており、大手企業から中小・ベンチャー企業まで、非常に多くのプレイヤーが存在します。
特に近年は、特定の業界(例:IT、医療・介護)や職種(例:エンジニア、ハイクラス層)に特化した専門型エージェントや、AIを活用したHRテック企業など、新しいサービスも次々と生まれています。
常に競合他社との差別化を図らなければ、企業や求職者に選ばれ続けることはできません。
サービスの質やスピード、価格などを巡る激しい競争の中で、常に新しい知識をインプットし、高い価値を提供し続けなければならないというプレッシャーも、「きつさ」の一因と言えるでしょう。
人材業界の現状・課題
「きつい」とされる理由と同時に、人材業界が今どのような状況に置かれているのか、その「現状」と「課題」を理解しておくことも非常に重要です。
社会の変化の波を真っ先に受けるのが、この業界の特徴でもあります。
特に「少子高齢化」や「働き方の多様化」といったキーワードは、人材業界のビジネスに直結する大きなテーマです。
こうしたマクロな視点を持つことで、業界の将来性や、その中で自分がどのような役割を果たせるかを考えるヒントになります。
ここでは、現代の人材業界が直面している主要な3つのポイントについて解説します。
労働力人口の減少と採用難
日本は今、少子高齢化の進展により、生産年齢人口(15歳~64歳)が減少し続ける「労働力人口の減少」という大きな課題に直面しています。
これは、多くの企業にとって「人手不足」、特に専門的なスキルを持つ人材の「採用難」を意味します。
人材業界にとっては、企業の採用ニーズが高まるため、一見するとビジネスチャンスが拡大しているように思えます。
しかし実際には、求職者(働き手)自体が減っているため、企業が求める人材を確保することが以前よりも難しくなっています。
いかにして限られた人材と企業を効果的にマッチングさせるか、あるいは、これまで光が当たらなかった層(例:シニア、主婦・主夫、外国人材など)の活躍をどう支援するかが、業界全体の大きな課題となっています。
働き方の多様化への対応
テレワークやフレックスタイム制の普及、副業・兼業の解禁、フリーランスやギグワーカー(単発の仕事請負)といった新しい働き方の広がりなど、個人の「働き方」に対する価値観は劇的に多様化しています。
従来の「正社員として一つの会社で定年まで働く」というモデルが当たり前ではなくなりました。
人材業界は、こうした個人の多様なニーズと、企業の多様な人材活用ニーズの両方に応えていく必要があります。
例えば、フリーランス専門のマッチングプラットフォーム、副業人材の紹介サービス、あるいはテレワーク前提の求人特集など、新しい働き方に即したサービスを迅速に開発・提供できるかが、企業の競争力を左右するようになっています。
HRテックの台頭と差別化
HRテック(Human Resources Technology)とは、AI(人工知能)、ビッグデータ、クラウドなどのテクノロジーを活用して、採用、労務管理、人材育成といった人事領域の業務を効率化・高度化する技術やサービスのことです。
例えば、AIが膨大な履歴書データから最適な候補者を選び出したり、オンライン面接ツールが普及したりしています。
これにより、従来は人が時間をかけて行っていた業務が自動化されつつあります。
人材業界にとっても、HRテックの活用は業務効率化のために不可欠です。
しかし同時に、テクノロジーだけでは代替できない「人の介在価値」、つまりキャリアアドバイザーによる深いカウンセリングや、RAによる企業の潜在課題の掘り起こしといった、人間ならではの付加価値をいかに提供し、他社と差別化していくかが大きな課題となっています。
人材業界の今後の動向
現状と課題を踏まえた上で、人材業界は今後どのように変化していくのでしょうか。
労働力人口の減少やテクノロジーの進化といった大きな流れは、今後も続くと予想されます。
こうした変化は、業界にとって「脅威」であると同時に、新しいサービスを生み出す「機会」でもあります。
就活生の皆さんが入社し、中核を担うことになる5年後、10年後を見据え、この業界が向かう先を理解しておくことは非常に有意義です。
ここでは、人材業界の「これから」を読み解く上で重要な、3つの動向について解説します。
マッチングの「質」の追求
これまでは、いかに多くの求人と求職者を集め、その「量」をマッチングさせるかという点が重視されがちでした。
しかし今後は、テクノロジーの進化で単純なマッチングはAIに代替されていく可能性があります。
だからこそ、人間が介在するからこその「質」の高いマッチングがより一層求められます。
単にスキルや条件が合うかどうかだけでなく、その人の価値観、潜在能力、キャリアプランと、企業の組織風土、事業の将来性、求める人物像といった、表面化しにくい部分まで深く理解した上でのマッチングです。
また、入社させて終わりではなく、入社後にその人が定着し、活躍できるよう支援する「オンボーディング」サービスの重要性も増していくでしょう。
採用以外の「人事課題」への領域拡大
企業の「人」に関する課題は、「採用」だけにとどまりません。
むしろ、採用した人材をいかに「育成」し、やりがいを持って働いてもらい(エンゲージメント向上)、公正に「評価」し、適切な「配置」を行うかといった、採用後の課題の方が複雑で根深い場合も多いです。
人材業界の今後の動向として、こうした「採用」以外の領域、つまり人材育成、組織開発、人事制度コンサルティングといった分野への事業拡大が加速すると予想されます。
採用を入り口として企業との関係性を築き、そこから派生するあらゆる人事課題をワンストップで解決できる「企業の戦略的パートナー」としての役割が、ますます重要になっていきます。
M&Aや事業提携の活発化
多様化・複雑化する企業のニーズや、急速に進化するHRテックに対応するため、自社だけですべてのサービスを提供し続けるのは難しくなっています。
そのため、異なる強みを持つ企業同士が連携する動きが活発化しています。
例えば、従来型の人材紹介会社が、AI技術に強みを持つHRテックベンチャーを買収(M&A)したり、人材育成(研修)に強みを持つ企業と業務提携したりするケースです。
これにより、「人材紹介+AIマッチング」「採用支援+入社後研修」といった、より付加価値の高いサービスをワンストップで提供できるようになります。
就活生の皆さんにとっては、入社する企業がどのような戦略を描き、他社とどう連携しているかという視点も、企業選びの軸の一つになるかもしれません。
【人材業界はきついのか】人材業界に向いている人
ここまで人材業界のリアルな「きつさ」や「課題」、そして「将来性」について見てきました。
これらを踏まえて、一体どのような人がこの業界で活躍できるのでしょうか。
もちろん、現時点で完璧に当てはまる必要はありませんし、入社後に身につけられるスキルもたくさんあります。
しかし、業界の特性上、求められやすい「素養」や「マインドセット」があるのも事実です。
自分の性格やこれまでの経験と照らし合わせながら、「これは自分に合っているかも」と感じるポイントがあるか、ぜひチェックしてみてください。
人の成長やキャリアに関心がある人
これが最も根本的かつ重要な素養です。
「人」そのものに強い興味・関心があり、他者の成長や成功を自分のことのように喜べる人。
人のキャリアという、人生においても非常に重要なターニングポイントに立ち会い、その人の可能性を信じて真剣にサポートすることにやりがいを感じられる人は、この仕事の適性が高いと言えます。
逆に、他人の事情に深入りすることに抵抗があったり、面倒だと感じてしまったりする人には難しいかもしれません。
誰かの「ありがとう」のために全力を尽くせる、おせっかいなぐらいが丁度良い場合もあります。
高い目標達成意欲とタフさがある人
「きついとされる理由」でも触れた通り、多くの職種で目標(数字)が設定され、その達成が求められます。
このプレッシャーを単なる「きつさ」と捉えるのではなく、「どうすれば達成できるか」をゲーム感覚で考え、工夫し、乗り越えるプロセスに面白さや成長実感を見いだせる人が向いています。
思うように成果が出ない時や、理不尽な事態に直面した時でも、すぐに諦めずに粘り強く取り組める精神的なタフさ。
失敗から学び、次に行動を切り替えられるポジティブな思考も非常に重要です。
コミュニケーション能力が高い人
人材業界の仕事は、コミュニケーションの連続です。
ただし、ここで言うコミュニケーション能力とは、単に「話が上手い」ことではありません。
むしろ、相手が本当に言いたいこと、言葉の裏にある本音や課題を正確に引き出す「傾聴力」が何より重要です。
その上で、企業の人事担当者、経営者、求職者など、立場や価値観の異なる様々な相手に対し、こちらの意図を分かりやすく伝え、納得してもらう「説明力」、そして時には利害関係を調整する「交渉力」が求められます。
人と人との間に立ち、信頼関係を築けることが、成果に直結します。
学習意欲が高く、情報感度が高い人
人材業界で扱う「人」と「企業」を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しています。
担当する業界(例:IT、医療、金融など)の最新動向、新しいビジネストレンド、労働関連の法律改正、競合他社の新しいサービス、最新のHRテック情報など、常に新しい知識をインプットし続ける必要があります。
知らないと、企業や求職者から信頼を得ることはできません。
好奇心が旺盛で、自ら進んで情報をキャッチアップし、学んだことをすぐに仕事に活かそうとする姿勢は、この業界で長く活躍するための強力な武器になります。
課題解決思考がある人
人材業界の仕事は、突き詰めると「課題解決業」です。
企業が抱える「採用がうまくいかない」という課題、求職者が抱える「自分に合う仕事がわからない」という課題。
これらの表面的な言葉の裏にある「本質的な原因は何か」を突き止め、「どうすればそれを解決できるか」という具体的な打ち手(解決策)を考え、提案し、実行することが求められます。
単なる「御用聞き」ではなく、相手の期待を超える付加価値を提供しようとする思考(=課題解決思考)が、プロフェッショナルとして信頼される鍵となります。
【人材業界はきついのか】人材業界に向いていない人
「向いている人」がいる一方で、残念ながら「この業界の特性とは合わないかもしれない」という人もいます。
これは決して、その人の能力が劣っているという意味ではありません。
あくまで「特性のマッチング」の問題です。
自分の価値観や、仕事に求めるものと、業界が求めるものが大きく異なると、入社後に「こんなはずじゃなかった」と苦しむことになってしまいます。
自分の弱点と向き合うのは勇気がいるかもしれませんが、ミスマッチを防ぐためにも、率直に自分自身を振り返ってみましょう。
精神的なプレッシャーに弱い人
「きつい理由」でも挙げた通り、ノルマや目標達成へのプレッシャー、そして「人の人生を左右するかもしれない」という仕事の責任の重さは、この業界で働く上で常について回ります。
これらのプレッシャーを「やりがい」や「成長の糧」と捉えられず、過度なストレスとして感じてしまう人は、精神的に消耗してしまう可能性が高いです。
自分のペースで、じっくりと一つの物事に取り組みたいと考えている人にとっては、スピードと成果を求められる環境が息苦しく感じられるかもしれません。
感情移入しすぎてしまう人
求職者に親身に寄り添うことは非常に大切ですが、それと「感情移入」は異なります。
求職者の不採用や突然の辞退、あるいは企業の採用中止といった出来事に、必要以上に落ち込んだり、相手の感情に引きずられすぎたりすると、冷静な判断ができなくなってしまいます。
時には、求職者にとって厳しい現実を伝えたり、企業の意向を代弁したりしなければならない場面もあります。
他者と自分との間に適切な境界線を引き、プロフェッショナルとして客観的な視点を保つバランス感覚が苦手な人は、苦労するかもしれません。
ルーティンワークを好む人
人材業界の仕事は、日々状況が変化します。
昨日まで順調だった案件が急にストップしたり、予期せぬトラブルが発生したりすることも日常茶飯事です。
マニュアル通り、決められた手順通りにコツコツと作業を進める「ルーティンワーク」は比較的少なく、常に状況を判断し、柔軟に対応を変えていくことが求められます。
「変化」をストレスと感じる人や、イレギュラーな対応が苦手で、安定した業務プロセスの中で働きたいという志向が強い人には、この業界のスピード感や変動性は合わない可能性があります。
数字や成果を追うのが苦手な人
多くの職種で、自分の仕事の成果が「売上」「成約件数」といった「数字」で明確に評価されます。
プロセス(どれだけ頑張ったか)ももちろん大事ですが、それ以上に「結果(成果)が出たか」が問われる世界です。
「数字に追われるのは嫌だ」「結果よりもプロセスを評価してほしい」という気持ちが強い人にとっては、この環境は非常に「きつい」と感じられるでしょう。
自分の行動が成果に結びついているかを常に分析し、改善していくことに楽しさを見いだせないと、モチベーションを維持するのが難しいかもしれません。
人と深く関わるのが億劫な人
この仕事は、良くも悪くも「人」と深く関わります。
企業の経営課題や、求職者のキャリアプラン、時にはプライベートな側面にまで踏み込んでヒアリングすることもあります。
表面的な関係性ではなく、信頼関係を築くために相手の内面にまで関わっていく必要があります。
人と話すこと自体は嫌いではないけれど、他者の人生や組織の深い部分にまで関わるのは精神的に疲れる、あるいはビジネスライクなドライな関係性を好む人にとっては、この仕事の本質的な部分が負担になってしまう可能性があります。
人材業界に行くためにすべきこと
人材業界の「きつさ」も「やりがい」も理解した上で、「それでもこの業界に挑戦したい」と決意した皆さん。
その熱意は非常に素晴らしいものです。
では、具体的に就職活動では何を準備すればよいのでしょうか。
人気業界の一つでもあるため、ライバルに差をつけるためには、「なぜ人材業界なのか」を深く突き詰めることが不可欠です。
ここでは、人材業界を目指す上で特に重要となる準備やアピールすべきポイントについて、3つのステップに分けて解説します。
今からできることもたくさんありますよ。
徹底した業界・企業研究
まず基本となるのが、業界・企業研究です。
この記事でも紹介した通り、人材業界には「紹介」「派遣」「広告」「コンサル」など多様なビジネスモデルがあります。
それぞれのビジネスモデルの違い、収益構造、強み・弱みを自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深めましょう。
その上で、興味のある企業をいくつかピックアップし、「なぜA社はB社よりも○○に強いのか」「この会社は今後どの領域に力を入れていこうとしているのか」といった、「比較」と「将来性」の視点で研究を進めてください。
IR情報(株主向け情報)や最新のニュースリリースをチェックするのも、企業の「今」を知る上で非常に有効です。
なぜ「人材」なのかを突き詰める(志望動機)
これは面接で必ず聞かれる、最重要ポイントです。
「人の役に立ちたい」「成長したい」といった動機は、他の業界にも当てはまりますよね。
そうではなく、「なぜ、金融でもメーカーでもなく、人材という領域でそれを実現したいのか」を明確に言語化する必要があります。
そのためには、自己分析を徹底的に行い、自分の過去の経験と結びつけることが不可決です。
例えば、「部活動で後輩の育成にやりがいを感じた」「アルバイト先で新人教育を任され、仕組みを改善した」といった原体験から、「人の可能性を引き出すこと」や「組織の課題を解決すること」に興味を持った、というように、具体的なエピソードに基づいた説得力のある志望動機を構築しましょう。
人材業界でのインターンシップ経験
もし可能であれば、人材業界でのインターンシップに参加することを強くお勧めします。
百聞は一見に如かず。
実際の職場で、社員の方々がどのように働いているのかを肌で感じることは、何物にも代えがたい経験となります。
テレアポや架電業務、データ入力、あるいは求職者対応の補助など、リアルな業務の一部を体験させてもらえる機会があれば、記事で読んだ「きつさ」と「やりがい」の両方を実感できるはずです。
そこで「自分には合っている」と確信できれば、それがそのまま志望動機にもなりますし、「合わない」と分かれば、早い段階で軌道修正ができます。
社員の方との繋がりができることも、大きな財産になるでしょう。
適職診断ツールを用いる
ここまで記事を読み進めて、「人材業界、面白そうだけど、本当に自分に向いているのかな…」と、まだ確信が持てない人もいるかもしれませんね。
そんな時は、客観的な視点で自分自身を分析する手助けとして、「適職診断ツール」を活用してみるのも一つの方法です。
就活市場にも、手軽に利用できる診断ツールが用意されています。
これらのツールは、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格的な傾向や、強み・弱み、どのような仕事環境や職種に向いている可能性が高いかを統計的に示してくれます。
もちろん、診断結果がすべてではありませんし、それに縛られる必要は全くありません。
しかし、「自分では気づかなかった強み」や、「確かにそういう側面もあるな」といった、自己理解を深めるための「材料」や「きっかけ」として非常に役立ちます。
【人材業界はきついのか】適性がわからないときは
適職診断ツールを使っても、自己分析を重ねても、この記事を読んでも、「結局、自分に人材業界が合っているのか、適性がどこにあるのかサッパリわからない…」と悩んでしまう人もいるでしょう。
でも、安心してください。
就活生の段階で、自分の適性を完璧に理解している人など、ほとんどいません。
不安に思うのは当然のことです。
適性というものは、最初からカチッと決まっているものではなく、色々な情報に触れ、多くの人と出会い、実際に行動(インターンや選考)してみる中で、徐々に見えてくるものです。
もし一人で悩んで行き詰まってしまったら、大学のキャリアセンターの職員、OB・OG訪問で出会った社会人、あるいは「就活市場」のような就活エージェントのアドバイザーなど、信頼できる第三者に壁打ち相手になってもらうことをお勧めします。
客観的な視点からのフィードバックが、思わぬ気づきを与えてくれるはずです。
おわりに
今回は、「人材業界はきついのか」というテーマで、業界のリアルな仕事内容から、きついと言われる理由、そして将来性や適性まで、幅広く解説してきました。
確かに、プレッシャーやハードな側面もありますが、それ以上に「人の人生」や「企業の成長」という、非常にダイナミックで社会貢献性の高いテーマに、当事者として深く関われる、計り知れないやりがいのある仕事だということも伝わったなら幸いです。
この記事が、皆さんの業界研究の一助となり、自分自身のキャリアを真剣に考えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
皆さんの就職活動を、心から応援しています!