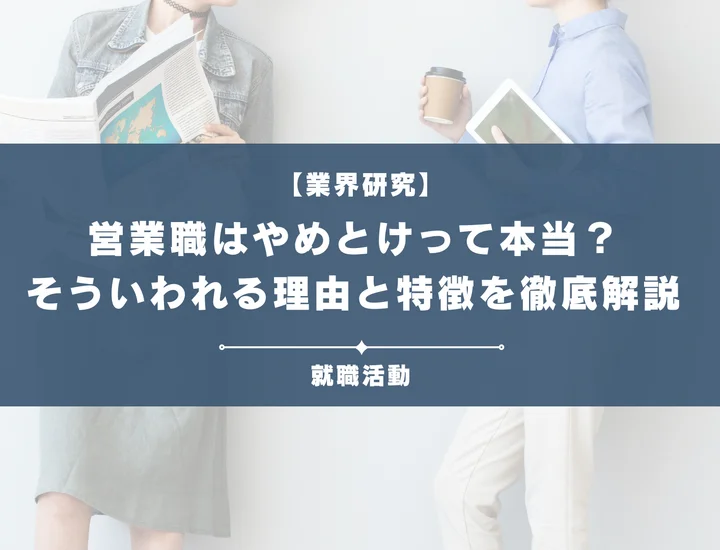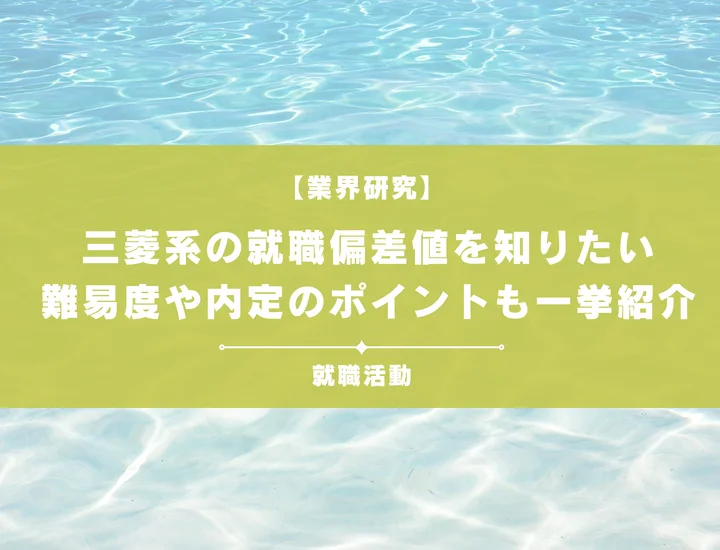HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
27卒として就活を意識し始めたばかりなのに、先輩やインターネットから聞こえてくる、営業はやめとけ、という言葉に不安を感じていませんか。
自分はコミュニケーションが得意な方ではないし、営業なんて絶対に無理そうだ。
大手企業に入っても、結局きつい営業に配属されたらどうしよう。
その不安、よくわかります。
しかし、その営業はやめとけという一言を鵜呑みにして、あなたの可能性を狭めてしまうのは、あまりにも勿体無いことです。
この記事では、なぜ営業はやめとけと言われるのか、あなたが本当に避けるべき営業を具体的に見抜く方法を徹底解説します。
【営業やめとけ】そう言われる理由とは
営業はやめとけという言葉が、なぜこれほどまでに広まっているのでしょうか。
多くの学生が不安に思う背景には、営業職に対して定着した、いくつかの具体的なネガティブイメージがあります。
もちろん、これらは全ての営業職に当てはまるわけではありませんが、多くの人が共通して抱く懸念点であることは事実です。
ここでは、そう言われる主な理由を3つの側面に分解して、その実態を詳しく見ていきましょう。
漠然とした不安の正体を知ることが、適切な企業研究の第一歩となります。
ノルマが厳しく精神的に消耗しやすい
営業はやめとけと言われる最大の理由の一つが、ノルマの存在です。
営業職の多くは、売上や契約件数などの数値目標、すなわちノルマが設定されています。
この数字を達成することが絶対的な使命とされ、毎月、あるいは毎週のように達成状況を厳しく管理されるケースも少なくありません。
目標が未達の場合、上司からの厳しい叱責、いわゆる詰めの文化が残っている企業も存在します。
なぜ達成できなかったのか、どうやって挽回するのかを、プレッシャーの中で説明し続けなければなりません。
このような環境下では、常に数字に追われる感覚に陥り、精神的に大きく消耗してしまいます。
特に責任感が強い人ほど、成果が出ない自分を責めてしまい、心身のバランスを崩すきっかけにもなりかねません。
こうした過度なプレッシャーが、営業はきつい、やめとけというイメージを強固にしているのです。
顧客対応のストレスが大きい
営業職は、会社の顔として顧客と直接向き合う仕事です。
そのため、顧客からの期待に応えるやりがいがある一方で、それに伴うストレスも非常に大きいと言えます。
例えば、自社の製品やサービスに不具合があった場合、直接の担当者である営業が謝罪の矢面に立たされます。
時には、自分に非がないことでも理不尽なクレームを受けたり、無理な要求をされたりすることもあるでしょう。
また、顧客の要望に応えたいという思いと、会社のルールや利益との板挟みになり、苦悩するケースも少なくありません。
顧客との約束を守るために、他部署に頭を下げて調整に奔走したり、納期のプレッシャーに追われたりすることも日常茶飯事です。
このような人間関係のストレスや、常に他者の要求に応え続けなければならない緊張感が、営業はやめとけと感じさせる一因となっています。
成果主義で評価が不安定になりやすい
営業職の評価は、売上や契約件数といった数値、つまり成果で決まることが一般的です。
これは、成果を出せば若手でも早くから昇進できたり、高いインセンティブ(報奨金)を得られたりするメリットの裏返しでもあります。
しかし、見方を変えれば、成果が出なければ評価されないという不安定さも内包しています。
例えば、景気の動向や市場の変化、あるいは担当エリアの特性によって、個人の努力だけではどうにもならない要因で成果が出にくくなる時期もあります。
そんな時でも、成果主義の環境下では、プロセスがいかに丁寧であっても、結果が出なければ評価は下がりがちです。
同期が大きな契約を決めて評価されている横で、自分だけが成果を出せずにいると、焦りや劣等感を感じやすくなります。
給与がインセンティブの割合が高い場合、成果次第で月々の収入が大きく変動し、生活が不安定になるリスクも考えられます。
【営業やめとけ】向いていない人の特徴
営業はやめとけという言葉が気になるのは、もしかしたら自分には向いていないかもしれない、という不安があるからではないでしょうか。
もちろん、営業にも多様なスタイルがあり、一概に決めつけることはできません。
しかし、一般的にきついとされる営業のスタイルにおいて、特にストレスを感じやすい人の特徴は確かに存在します。
ここでは、どのようなタイプの人が営業職、特に成果を厳しく問われる環境で苦労しやすいのか、3つの特徴を挙げて解説します。
自分自身に当てはまるか、少し立ち止まって考えてみましょう。
プレッシャーに弱い人は継続が難しい
営業職は、良くも悪くも数字という明確な結果を求められる仕事です。
前述の通り、ノルマや目標達成へのプレッシャーは常につきまといます。
プレッシャーに弱い、あるいはストレスを感じやすい人にとって、この環境は非常に厳しいものになるでしょう。
例えば、目標達成が近づくと夜も眠れなくなったり、上司の顔色を過度にうかがってしまったりする人は注意が必要です。
営業活動は、常に順調とは限りません。
むしろ、断られることの方が多いのが現実です。
断られるたびに深く落ち込んでしまい、自分の人間性まで否定されたように感じてしまうと、次のアポイントを取る一歩が踏み出せなくなってしまいます。
成果が出ない時期に、それを乗り越えるための精神的なタフネスや、プレッシャーをエネルギーに変えるような思考の転換が苦手な場合、営業職を継続することは難しいかもしれません。
初対面の相手とのコミュニケーションが苦手
営業活動、特に新規開拓が中心となる営業では、日常的に初対面の相手と関係を築くことが求められます。
テレアポで顔も見えない相手に自社の商品を説明したり、飛び込み訪問で全く接点のない企業に足を運んだりすることもあります。
人見知りであったり、初対面の相手との会話に強い緊張を感じたりする人にとって、これは大きな精神的負担となります。
また、コミュニケーションが苦手といっても、単に話すのが不得意というだけではありません。
相手の懐に飛び込むような積極性や、時には断られてもめげない精神的な強さが求められる場面も多くあります。
もちろん、全ての営業がこうした強引なスタイルではありませんが、いわゆる営業と聞いてイメージされるような、外向的で積極的なコミュニケーションが苦手だと自覚している場合、日々の業務が苦痛になってしまう可能性は高いでしょう。
自分のペースで働きたい人は合わないことが多い
営業職は、基本的に顧客の都合に合わせて動く仕事です。
自分のスケジュール管理も重要ですが、それ以上に顧客からの急な依頼や問い合わせ、トラブル対応などで、予定通りに仕事が進まないことが頻繁に起こります。
例えば、定時退社しようと思っていた矢先に顧客から緊急の電話がかかってきたり、休日に対応を求められたりするケースもゼロではありません。
また、営業は個人プレーのように見えて、実際はチームで目標を追いかける側面も強いです。
チーム全体の目標達成のために、個人の行動が管理されたり、日々の進捗報告が細かく求められたりすることもあります。
自分のタスクを自分の裁量で、静かな環境でコツコツと進めたい、あるいは仕事とプライベートの時間はきっちり分けたいという、マイペースを重視する働き方を望む人にとって、営業職の突発的で他者中心のタイムスケジュールは、大きなストレス源となるでしょう。
【営業やめとけ】後悔しやすい瞬間はあるの?
営業はやめとけ、という言葉を振り切って入社したとしても、実際に働いてみて想像とのギャップに苦しみ、後悔する瞬間が訪れる可能性はあります。
就職活動中に抱いていたイメージと、入社後のリアルな業務との間に大きな乖離があると、こんなはずではなかった、と感じてしまうのです。
特に27卒の皆さんは、初めての社会人生活に期待と不安が入り混じっていることでしょう。
ここでは、先輩社員たちが実際に営業職に就いて後悔しやすいと感じた、具体的な瞬間を3つご紹介します。
これらを知っておくことで、企業選びのミスマッチを防ぐヒントになるかもしれません。
想像以上の労働時間にギャップを感じたとき
就職活動中は、キラキラとしたオフィスや、やりがいに満ちた先輩社員の話に魅力を感じていたかもしれません。
しかし、実際に入社してみると、想像以上に労働時間が長い現実に直面することがあります。
営業職は、日中は顧客先を訪問し、夕方に帰社してから見積書の作成や報告書、翌日の準備などの事務作業に追われる、というケースが少なくありません。
結果として、定時で帰れる日はほとんどなく、慢性的な長時間労働に陥ってしまうのです。
また、顧客との関係構築の名目で、業務時間外の接待や飲み会、休日のゴルフなどが半ば強制的に行われる企業も、残念ながらまだ存在します。
ワークライフバランスを重視して会社を選んだはずなのに、実態は全く異なっていた。
こうしたギャップに気づいたとき、営業はやめとけという言葉が現実味を帯びて、強く後悔する瞬間となるでしょう。
成果が出ない時期に詰められたとき
営業活動は、常に成果が出続けるわけではありません。
どれだけ真面目に努力していても、市場の動向や競合の存在、あるいは単に運悪く、成果が出ないスランプの時期は誰にでも訪れます。
問題は、その成果が出ない時期の周囲の反応です。
特に、個人の努力やプロセスを評価せず、結果(数字)だけで判断する風土の会社の場合、成果が出ていないと上司から厳しく詰められることになります。
会議の場で、なぜできないのか、どうするつもりなのかと大勢の前で叱責されたり、毎日のように進捗確認の連絡が来たりすると、精神的に追い詰められてしまいます。
自分なりに試行錯誤し、もがいている最中にプレッシャーだけをかけられると、次第に仕事へのモチベーションは失われていきます。
あんなに頑張っているのに誰も認めてくれない、と感じたとき、営業職を選んだことを後悔するかもしれません。
自分の成長が数値化されずモチベが保てないとき
営業職の評価は、売上や契約件数といった明確な数字で測られることがほとんどです。
しかし、この評価方法が、逆にモチベーションの低下につながる瞬間があります。
それは、数字には表れない自分の成長や努力が、全く評価されないと感じたときです。
例えば、すぐに契約には結びつかなくても、顧客との深い信頼関係を築けていたり、難しい要望に応えるために新しい知識を必死で勉強したりしていても、それが売上数字に直結していなければ、評価はゼロ、というケースです。
営業の仕事は、数字を作ることだけではありません。
顧客の課題に寄り添うこと、市場の情報を社内にフィードバックすること、後輩を指導することなど、多岐にわたります。
しかし、評価制度が売上数字に偏りすぎていると、それらの重要な業務への意欲が湧かなくなります。
自分は数字を達成するための駒でしかないのか、と感じたとき、仕事のやりがいを見失い、後悔につながるのです。
【営業やめとけ】そうではないケースも存在する
ここまで、営業はやめとけと言われる理由や、後悔しやすい瞬間について解説してきました。
読んでいるうちに、やはり営業は自分には無理かもしれない、と不安が大きくなった方もいるかもしれません。
しかし、重要なのは、これらが全ての営業職に当てはまるわけではない、ということです。
世の中には、過度な精神論や長時間労働とは無縁の、むしろ知的に、そして効率的に働ける営業職も数多く存在します。
漠然としたイメージだけで判断するのではなく、どのような営業であれば自分でも活躍できる可能性があるのか、その違いを見極めることが重要です。
商材が強く提案しやすい企業で働く場合
営業の難易度を大きく左右する要因の一つに、取り扱う商材(商品やサービス)の強さがあります。
もし、その商材が市場で圧倒的なシェアを持っていたり、他社にはない独自の強みを持っていたりする場合、営業活動は格段に進めやすくなります。
いわゆるプロダクトが強いという状態です。
このような企業では、営業が無理に売り込まなくても、顧客側から問い合わせが来る反響営業(インバウンドセールス)が中心となることもあります。
営業の役割は、ゼロから信頼関係を築くことよりも、既にあるブランド力や製品力を背景に、顧客のニーズを正確にヒアリングし、最適な提案をすることにシフトします。
もちろん、専門知識の習得は必要ですが、理不尽な飛び込み営業やテレアポを強制されることは少ないでしょう。
企業のブランド力や商材の競争力を企業研究でしっかり見極めることは、きつい営業を避ける上で非常に有効です。
ノルマよりもサポート重視の法人営業の場合
営業と一言で言っても、誰に何を売るかで、その働き方は全く異なります。
特に、個人(BtoC)ではなく、法人(BtoB)を相手にする営業の場合、働き方が大きく異なるケースがあります。
もちろんBtoB営業にも厳しいノルマを課す企業はありますが、中には新規開拓よりも既存顧客との関係維持やサポートを重視する、ルート営業と呼ばれるスタイルもあります。
この場合、求められるのは新規契約を次々に取ってくる瞬発力よりも、顧客と長期的な信頼関係を築き、継続的に取引をしてもらうためのサポート力や調整力です。
ノルマが全くないわけではありませんが、そのプレッシャーは比較的緩やかで、顧客の課題解決にじっくり取り組むことができます。
また、法人相手であるため、土日の対応や理不尽なクレームは個人向け営業に比べて少ない傾向にあります。
安定した環境で、顧客と深く長く付き合いたいと考える人には、こうした法人営業が向いている可能性があります。
自分の強みが営業とマッチしている場合
営業はやめとけという言葉を気にする人の中には、営業に必要なスキルを誤解しているケースが少なくありません。
営業=外向的で、誰とでもすぐに打ち解けられるコミュニケーションお化け、というイメージを持っているなら、それは古い考え方かもしれません。
現代の営業、特にBtoBのソリューション営業などでは、むしろ別の強みが求められます。
例えば、自分が話すことよりも、相手の話をじっくりと聞く傾聴力。
顧客が本当に困っていること、言葉にできていないニーズを引き出す力です。
あるいは、複雑な課題を整理し、論理的に解決策を組み立てる分析力や思考力。
こうした力は、決して外向的な性格でなくても発揮できます。
もし、あなたがプレッシャーには弱くても、人の話を聞くのが得意だったり、物事を分析して整理するのが得意だったりするならば、その強みは現代の営業現場で高く評価される可能性があります。
自分の強みを正しく理解し、それが活きる営業スタイルを見つけることが重要です。
【営業やめとけ】営業以外のおすすめ職種
営業はやめとけという意見に共感し、自分にはやはり営業職は向いていない、と感じた27卒の学生も多いでしょう。
しかし、多くの企業が新卒採用では総合職として一括採用し、その多くが営業部門に配属されるのが現実です。
では、営業職を避けたい場合、どのようなキャリアの選択肢があるのでしょうか。
幸いなことに、近年は働き方が多様化し、新卒でも専門性を追求できる職種が増えています。
ここでは、営業職以外のキャリアとして、特に注目されている3つの職種を紹介します。
それぞれの仕事内容や求められるスキルを理解し、自分の適性と照らし合わせてみてください。
企画・マーケティング系の職種
企画・マーケティング職は、就活生からも非常に人気が高い職種です。
市場のトレンドを分析し、新しい商品やサービスを企画したり、既存の商品をどうすればもっと売れるか、その戦略や仕組みを考えたりする仕事です。
営業が最前線で顧客にアプローチするのに対し、マーケティングはその後方支援、あるいは戦略の司令塔として機能します。
データ分析やロジカルシンキング、消費者の心理を読み解く洞察力が求められます。
ただし、この職種は新卒でいきなり配属されるケースが非常に稀である、という現実も知っておく必要があります。
多くの企業では、まず営業職として現場を経験し、顧客や市場を理解した上で、数年後にマーケティング部門へ異動するというキャリアパスが一般的です。
もし新卒からこの職種を目指すのであれば、専門のインターンに参加したり、学生時代から関連する実績を積んだりするなど、相応の準備と狭き門をくぐる覚悟が必要です。
カスタマーサクセス(営業よりも関係構築が中心)
カスタマーサクセスは、ここ数年で、特にSaaS(Software as a Service)業界を中心に急速に広まった比較的新しい職種です。
その名の通り、顧客の成功を支援することがミッションです。
営業職が契約を取る(売る)までをゴールとするのに対し、カスタマーサクセスは契約後の顧客に対し、そのサービスを最大限に活用してもらい、継続的に利用してもらう(解約を防ぐ)ことを目指します。
具体的な業務は、導入時のオンボーディング支援、定期的な活用状況のヒアリング、課題解決のための提案などです。
営業のように新規のノルマに追われるプレッシャーは少ない一方で、顧客と長期的な信頼関係を築く力や、サービスへの深い理解、課題解決能力が求められます。
売ることよりも、サポートすること、関係性を築くことにやりがいを感じる人にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
事務・総務などバックオフィス職
事務職や総務、人事、経理といったバックオフィス系の職種も、営業を避けたい学生にとって有力な選択肢です。
これらの職種は、営業のように直接売上を生み出すことはありませんが、会社組織が円滑に機能するために不可欠なサポート役を担います。
例えば、経理であれば会社のお金の流れを管理し、人事であれば採用や労務管理を担当します。
業務の多くは定型化されているため、自分のペースでコツコツと正確に仕事を進めることが求められます。
顧客対応のストレスは少なく、比較的ワークライフバランスも取りやすい傾向にあります。
ただし、営業職に比べて募集枠が少ないのが一般的です。
また、ルーティンワークが中心となるため、刺激や大きな変化を求める人には物足りなく感じるかもしれません。
安定した環境で、専門性を身につけながら会社を支えたいと考える人に向いている職種と言えるでしょう。
【営業やめとけ】営業を避けたい就活生がすべきこと
営業はやめとけ、という言葉に強く共感し、自分は営業以外の道に進みたいと決意した27卒のあなたへ。
その決意を現実のものにするためには、ただ不安がって避けるだけではなく、具体的な行動を起こす必要があります。
就職活動において、営業職の募集は圧倒的に多いのが実情です。
その中で、自分の希望するキャリアを掴み取るためには、戦略的な準備が不可欠です。
ここでは、営業職を本気で避けたい就活生が、今すぐ取り組むべき3つのことを解説します。
これらを実行することで、あなたの就活の軸はより明確になり、ミスマッチのない企業選びが可能になります。
自己分析で自分の適性を整理する
まず最初に取り組むべきは、徹底した自己分析です。
なぜ自分は営業を避けたいのでしょうか。
それは、単にノルマがきついからでしょうか、それとも初対面の人と話すのが苦手だからでしょうか。
あるいは、自分のペースで仕事ができないのが嫌なのでしょうか。
この営業が嫌な理由を深掘りすることで、逆に自分が仕事に何を求めているのか、自分の強みや弱みが何であるかが見えてきます。
例えば、プレッシャーには弱いが、データを分析してコツコツ作業するのは得意だ、ということがわかれば、マーケティングのアナリストやバックオフィス職が向いているかもしれません。
あるいは、人と話すのは好きだが、売ることに罪悪感がある、というならカスタマーサクセスが適しているかもしれません。
営業をやめとけ、という他人の言葉ではなく、自分の内面と向き合い、自分だけの働く軸を明確にすることが、全てのスタートラインです。
働き方の優先順位を明確にする
自己分析で自分の適性が見えてきたら、次に働き方における優先順位を明確にしましょう。
あなたは仕事において何を最も重視しますか。
例えば、とにかく高い給与を得て若いうちから稼ぎたいのか、それとも給与は平均的でもいいからプライベートの時間をしっかり確保したい(ワークライフバランス)のか。
あるいは、安定した環境で長く働きたいのか、常に新しいことに挑戦できる刺激的な環境がいいのか。
これら全ての条件を満たす完璧な職場は、残念ながら存在しません。
何かを得るためには、何かを妥協する必要があります。
営業職を避けるということは、もしかしたら高いインセンティブを得るチャンスや、一部の企業への入社の門戸を狭めることかもしれません。
それを理解した上で、自分にとって譲れない条件は何か、その優先順位をはっきりと定めることが、後悔しない選択をするために非常に重要です。
営業以外のインターンで業務を体験してみる
自己分析と優先順位付けが完了したら、最後は行動です。
営業職を避けたいのであれば、営業以外の職種、特に興味を持った職種のインターンシップに積極的に参加しましょう。
企画・マーケティング職、カスタマーサクセス職、あるいはバックオフィス職など、近年は多様な職種でインターンが募集されています。
営業はやめとけ、という言葉がそうであるように、他の職種についても、外から見ているだけではわからないリアルな業務や厳しさが必ずあります。
例えば、企画職は華やかに見えますが、実際は地味なデータ分析や泥臭い調整業務がほとんどかもしれません。
インターンを通じて実際の業務を体験することで、その仕事が本当に自分に向いているのか、自分のイメージとギャップはないかを確認できます。
百聞は一見に如かず。
机上の企業研究では得られない、生きた情報を手に入れることが、営業を回避した先にある、自分に最適なキャリアを見つける最短距離となります。
【営業やめとけ】自分は営業に向いている?チェックリスト!
ここまで、営業はやめとけと言われる理由や、営業以外の選択肢について見てきました。
しかし、中には営業が嫌だと決めつけていたけれど、もしかしたら自分にもできる営業があるかもしれない、と考え始めた人もいるかもしれません。
前述の通り、営業のスタイルは多様化しており、従来のイメージとは異なる働き方が増えています。
そこで、あなたが営業職、特に現代型の営業職への適性があるかどうかを判断するため、簡単なチェックリストを用意しました。
自分が当てはまるかどうか、自己分析の一環として考えてみてください。
会話よりも質問をする方が得意か
あなたは、自分が一方的に話すよりも、相手の話を聞き、その内容に沿って質問を投げかける方が得意ではありませんか。
もしそうであれば、あなたは営業の重要な素質を持っています。
古い営業スタイルでは、流暢に自社製品の魅力を語る話術が重要視されたかもしれません。
しかし、現代のソリューション営業やコンサルティング営業において最も重要なのは、傾聴力です。
顧客が本当に困っていることは何か、その背景にはどんな課題があるのか。
それを正確に引き出すためには、相手に気持ちよく話してもらう質問力が不可欠です。
自分が主役になって話したい人よりも、相手を主役にして課題を発見することに興味を持てる人の方が、現代の営業には向いていると言えます。
おしゃべり上手である必要は全くないのです。
数字で成果を見られることに抵抗がないか
あなたは、自分の努力や成果が、テストの点数やスポーツのスコアのように、明確な数字で示されることに抵抗がない、むしろやりがいを感じるタイプではありませんか。
営業職は、良くも悪くも成果が数字で可視化されます。
この数字を、自分へのプレッシャーや他者との比較材料としてネガティブに捉えるのではなく、自分の成長の指標としてポジティブに捉えられるかが重要です。
目標というゴールがあるからこそ、そこに至るプロセスを工夫しようと努力できる。
達成すれば純粋に嬉しいし、未達であればどこに改善点があったのかを客観的に分析できる。
このように、数字を自分の行動を改善するためのフィードバックとして冷静に受け止められる人は、営業職で成長しやすい特性を持っています。
過度なプレッシャーは問題ですが、成果の可視化自体は受け入れられるか、考えてみましょう。
継続して関係構築することにストレスがないか
あなたは、一度きりの関係性よりも、同じ相手と継続的にコミュニケーションを取り、徐々に信頼関係を深めていくことにやりがいを感じるタイプではありませんか。
全ての営業が新規開拓で、初対面の人とばかり会うわけではありません。
特にBtoBのルート営業やカスタマーサクセスに近い営業では、既存の顧客とどれだけ長く、良い関係を築けるかが成果に直結します。
派手な成果を追いかけるよりも、顧客からの小さなありがとうや、頼りにされているという実感に喜びを感じる。
細やかな連絡や、相手の状況を想像した先回りのサポートを苦としない。
こうした地道な関係構築を大切にできる人は、売り切り型の営業ではなく、長期的なパートナーシップが求められる営業分野で大きな力を発揮するでしょう。
一過性の成果よりも、積み重ねを重視する人に向いています。
よくある質問
ここまで営業はやめとけ、というテーマで多角的に解説してきましたが、27卒の皆さんの中には、まだ解消しきれない疑問や不安が残っているかもしれません。
就職活動は、皆さんにとって初めての大きな選択であり、情報が多すぎるゆえに混乱してしまうことも多いでしょう。
ここでは、就活生から特によく寄せられる、営業職に関する3つの素朴な疑問について、簡潔にお答えしていきます。
漠然とした不安を解消し、自信を持って次のステップに進むための参考にしてください。
営業は本当にやめといた方がいいの?
結論から言うと、全ての人が営業をやめといた方がいい、ということは決してありません。
ただし、この記事で解説してきたような、過度な精神論や長時間労働が常態化している古い体質の営業、いわゆるやめとけと言われる営業は、避けた方が賢明です。
重要なのは、営業という職種を一括りにして判断しないことです。
あなたの強み、例えば傾聴力や分析力が活かせる現代型の営業(ソリューション営業やインサイドセールスなど)もあれば、あなたの価値観(安定志向やワークライフバランス)に合致する法人向けのルート営業などもあります。
営業はやめとけという言葉に思考停止せず、なぜそう言われるのかを理解した上で、自分に合うスタイルの営業があるか、フラットな目線で企業研究をすることが大切です。
営業を避けると内定は取りにくくなる?
これは多くの就活生が抱く不安ですが、答えはイエスでもあり、ノーでもあります。
まずイエスである理由は、新卒採用市場において、営業職の募集人数が他の職種に比べて圧倒的に多いという事実があるからです。
単純に門戸が広いため、営業職も選択肢に入れる方が、内定を獲得できる企業の数は増える可能性が高いです。
一方で、ノーである理由もあります。
近年は、ジョブ型雇用(職種別採用)を導入する企業も増えており、新卒から専門職(エンジニア、マーケター、デザイナー、バックオフィスなど)として採用されるケースも珍しくありません。
もしあなたが営業以外の分野で明確な適性やスキル、熱意を示せるのであれば、営業職を避けたからといって内定が取れなくなるわけではありません。
大切なのは、募集人数の多さに流されるのではなく、自分の軸に合った職種で、なぜ自分がその仕事に適しているのかを語れる準備をすることです。
営業と他の職種の働き方はどれくらい違う?
営業職と他の職種、例えばバックオフィス職や企画職との働き方は、いくつかの点で大きく異なります。
最も大きな違いは、やはり評価基準と時間の使い方でしょう。
営業職は、成果(数字)が評価に直結しやすい一方で、顧客対応などで時間の使い方が他律的(他者の都合に左右される)になりがちです。
一方、バックオフィス職は、成果が数字で表れにくい反面、業務プロセスや正確性が評価されます。
また、比較的スケジュールが読みやすく、自分のペースで仕事を進めやすい傾向があります。
企画職は、クリエイティブな側面が注目されがちですが、実際は多くの関係者を巻き込む調整業務や、成果が出るまでの期間が長いという特徴があります。
どの職種にも一長一短があり、求められるスキルやストレスの種類も異なります。
どの働き方が自分に合っているかを、自己分析と照らし合わせて考えることが重要です。
まとめ
この記事で紹介したチェックリストや、ヤバい企業の見抜き方を参考に、インターンやOB訪問を通じて、あなた自身の目で確かめてください。
世の中の神話に惑わされず、あなたが心から納得できるキャリアを選び抜くことを応援しています。