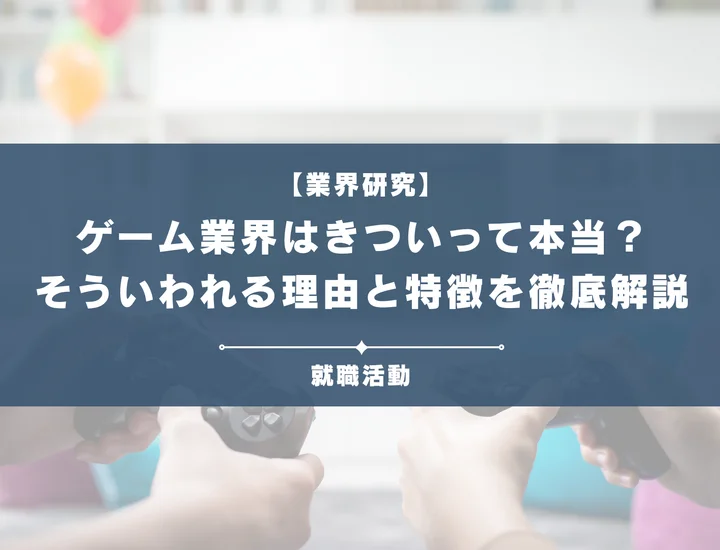HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
子どもの頃からゲームに熱中し、「将来はゲームクリエイターになりたい」「大好きなゲームに関わる仕事がしたい」と考えている就活生は多いのではないでしょうか。
しかし、いざ就職活動を始めると「ゲーム業界は激務」「離職率が高い」といったネガティブな情報も耳に入り、不安を感じる人もいるかもしれません。
この記事では、就活アドバイザーの視点から、ゲーム業界のリアルな実態に迫ります。
仕事内容、職種、きついと言われる理由、現状の課題、そしてどんな人が向いているのかを具体的に解説しますので、あなたの不安を解消し、入念な業界研究の一助となることを目指します。
ゲーム業界への就職を目指すあなたが、後悔のない選択をするための道しるべとして、ぜひ最後まで読んでください。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界はきつい?
ゲーム業界に対する「きつい」というイメージは、一部の事実に基づいているものの、業界全体を一律に判断するのは早計です。
実際、ゲーム開発の現場では、リリースの直前や大型アップデート前など、一時的に作業量が大幅に増え、残業や休日出勤が多くなる「デスマ―チ」と呼ばれる状況が発生することがあります。
これは、ユーザーの期待に応えるべく、開発の最終段階で品質を徹底的に高めるため、あるいは予期せぬバグへの対応に追われるためです。
しかし、全ての企業、全ての部署が常に激務というわけではありません。
企業の規模、開発しているゲームの種類、働き方改革への取り組み、そして配属される部署によって、労働環境は大きく異なります。
大切なのは、ネガティブな側面だけを見て諦めるのではなく、なぜそう言われるのか、具体的な仕事内容と照らし合わせて深く理解することです。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界の仕事内容
ゲーム業界の仕事内容は、私たちが普段遊んでいる「ゲーム」という形になるまでに、非常に多岐にわたります。
単にゲームを企画して作るだけでなく、それをユーザーに届けるためのマーケティングや運営など、多くのプロフェッショナルが関わっています。
主な仕事内容を理解することは、あなたがこの業界でどのような役割を果たしたいのかを考える上で不可欠です。
企画・プロデュース
ゲームのコンセプトを考え、具体的な仕様を決定するのが企画・プロデュースの仕事です。
企画職の代表的なポジションは「ゲームプランナー」と呼ばれ、市場調査を行い、どんなゲームがユーザーに求められているのか、どうすればヒットするのかを深く考えます。
また、プロデューサーやディレクターは、プロジェクト全体の予算管理やスケジュール調整、意思決定を行い、ゲーム開発を統括する非常に重要な役割を担います。
ゲームが完成するまでの全ての工程において、企画書や仕様書を作成し、開発チーム間の連携をスムーズにするためのコミュニケーションを取ることも、彼らの重要なミッションの一つです。
チームメンバーの能力を最大限に引き出しながら、プロジェクトを成功に導くためのリーダーシップも求められます。
開発・制作
企画されたゲームを実際に作り上げるのが、開発・制作の仕事です。
この工程には、プログラマー、デザイナー、サウンドクリエイターなど、専門的なスキルを持つ多くの職種が関わります。
プログラマーはゲームの動きやシステムをコードで実装し、デザイナーはキャラクターや背景などのグラフィックを作成、サウンドクリエイターはBGMや効果音を作り出します。
それぞれの専門分野で高いスキルが求められるのはもちろんのこと、企画意図を正確に理解し、それを技術的に実現するための協調性も欠かせません。
この開発プロセスは、時に技術的な課題や仕様変更に直面し、試行錯誤を繰り返すことになりますが、アイデアが形になっていく過程は大きなやりがいとなります。
運営・マーケティング
ゲームがリリースされてからも、ユーザーに継続して楽しんでもらうための運営・マーケティングの仕事があります。
運営職は、ゲーム内のイベント企画やデータ分析を行い、ユーザーの満足度や定着率を高める施策を打ち出し、ゲームの寿命を延ばす役割を担います。
また、カスタマーサポートとしてユーザーからの問い合わせに対応し、ゲームの改善に役立てるのも大切な業務です。
マーケティング職は、テレビCMやSNS、Web広告などを活用し、新規ユーザーを獲得するためのプロモーション戦略を実行します。
ゲームの面白さを最大限に引き出し、市場に適切にアピールするための戦略的な視点が求められます。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界の主な職種
ゲーム業界には非常に多様な職種があり、それぞれが専門性を活かしてゲーム開発に貢献しています。
あなたが持つスキルや興味が、どの職種にフィットするのかを考えてみましょう。
ゲームプランナー(企画職)
ゲームプランナーは、ゲームのアイデアを生み出し、仕様書として具体化する、いわば「設計図」を描く役割です。
具体的な業務内容は、レベルデザインの考案、ユーザーインターフェース(UI)の設計、シナリオの作成など多岐にわたります。
ユーザーが「面白い」と感じる体験とは何かを常に考え続け、それを実現するための論理的な思考力と発想力が求められます。
開発チーム全体の中で、企画の意図を明確に伝え、方向性を定めるためのコミュニケーション能力も非常に重要となります。
プログラマー
プログラマーは、プランナーが作成した仕様書に基づき、ゲームが動作するためのシステムを構築します。
キャラクターの動きや、ゲームのルール、サーバーとの通信処理など、ゲームの「骨格」を作る非常に重要な役割です。
使用するプログラミング言語や開発環境は多岐にわたるため、最新の技術トレンドを常に学び続ける向上心が求められます。
また、バグ(プログラムの不具合)を徹底的に修正する根気強さや論理的な問題解決能力も不可欠です。
デザイナー(アーティスト)
デザイナーは、ゲームのビジュアル要素全てを担当します。
キャラクターデザイン、背景、アイテム、エフェクト、ユーザーインターフェースなど、多岐にわたる専門分野があります。
例えば、キャラクターデザイナーは魅力的な見た目だけでなく、設定や世界観を表現するデザインを求められ、3Dモデルを作成することもあります。
高いデッサン力や色彩感覚に加え、開発チームの一員として、アートディレクターやプランナーの意図を理解し、ビジュアルに落とし込む協調性も重要です。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界がきついとされる理由
ゲーム業界が「きつい」と言われる背景には、その仕事の特性や業界の構造に起因するいくつかの要因があります。
これらの理由を理解しておくことで、入社後のギャップを減らすことができます。
納期前の開発スケジュールが過酷になりやすい
ゲーム開発では、特にリリース直前や大規模なアップデート前になると、開発スケジュールがタイトになる傾向があります。
ユーザーへの期待値が高い人気タイトルほど、わずかなバグや不具合も許されないため、徹底的なデバッグ(バグ修正)作業が必要になります。
この時期は、徹夜や休日出勤が続く、いわゆる「デスマ―チ」が発生しやすく、これが「ゲーム業界は激務」というイメージの最大の要因となっています。
ただし、これは一部のプロジェクトや企業に限定されるものであり、近年は働き方改革が進んでいる企業も増えています。
ユーザーからのフィードバックが厳しい
ゲームは、開発者が数年かけて心血を注いだ作品である一方、リリース後はすぐに世界中のユーザーからの評価に晒されます。
SNSやレビューサイトでのフィードバックは、時には厳しく、開発者の努力を否定するかのような意見が寄せられることも少なくありません。
自分が手掛けた作品が酷評される精神的なプレッシャーは、この業界特有の「きつさ」の一つです。
しかし、ポジティブなフィードバックは大きなやりがいにつながり、ユーザーの声を元にゲームを改善していくことに喜びを見いだせるかが鍵となります。
移り変わりが激しい技術・トレンドへの対応
ゲーム業界の技術進化のスピードは非常に速く、新しい開発ツールやプログラミング言語、そしてユーザーが求めるゲームのトレンドは常に変化しています。
VRやメタバースといった新技術への対応も求められており、常に新しい知識やスキルを学び続けなければ、時代の変化に取り残されてしまうというプレッシャーがあります。
技術職だけでなく、企画職やデザイナーも、新しいゲームデザインや表現方法を常に探求し続ける必要があり、自己学習を怠れない点が「きつい」と感じる原因の一つです。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界の現状・課題
ゲーム業界は大きな成長を続けている一方で、いくつかの課題も抱えています。
現状と課題を正しく把握することで、将来性を見極める視点を養うことができます。
開発費の高騰と開発サイクルの長期化
スマートフォンの普及により、ゲームのグラフィックやシステムは年々高度化しています。
それに伴い、ゲーム一本の開発にかかる費用が巨額になり、開発期間も長期化する傾向にあります。
特に大規模なコンソールゲームやPCゲームでは、数年単位のプロジェクトになることも珍しくありません。
開発費の高騰は、一度失敗した時のリスクが非常に高くなることを意味し、企画段階から市場のニーズを的確に捉えることがより重要になっています。
このリスクを分散するため、複数の小規模プロジェクトを同時進行させる企業も増えています。
人材の流動性と技術者の確保
ゲーム業界全体で、特に高い技術力を持つプログラマーやデザイナーの需要が高まっており、優秀な人材の獲得競争が激化しています。
一方で、先述した激務のイメージなどから、離職率が高い企業や職種も存在し、人材の流動性が高いという側面もあります。
企業側は、福利厚生の充実やリモートワークの導入など、働きやすい環境づくりを進めていますが、プロジェクトの成功と人材の定着を両立させることが、業界全体の大きな課題となっています。
グローバル市場での競争激化
日本のゲームは世界的に高い評価を受けていますが、近年は中国や韓国、欧米の企業が開発するゲームが台頭し、グローバル市場での競争が非常に激しくなっています。
単に面白いゲームを作るだけでなく、世界中の異なる文化や嗜好を持つユーザーに受け入れられるかを考慮した企画やマーケティングが求められています。
また、eスポーツの普及など、ゲームを「競技」として捉える新しいトレンドへの対応も重要です。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界に向いている人
ゲーム業界での仕事は、単にゲームが好きという情熱だけでなく、特定の資質や考え方を持っている人に向いています。
自分がこれらの特徴に当てはまるか考えてみましょう。
困難な状況でも最後までやり抜く粘り強さがある人
ゲーム開発は、予期せぬバグの発生、仕様変更、タイトな納期など、多くの困難に直面します。
特にリリース前のデバッグ作業や、技術的な課題を解決する際には、途中で諦めずに徹底的に問題と向き合う粘り強さが非常に重要です。
何百回とテストを繰り返したり、何時間もかけてコードの不具合を探し出したりする作業は地味ですが、この「やり抜く力」こそがゲームの完成度を高めます。
完成したときの達成感と、ユーザーの笑顔を想像できる人はこの業界に向いています。
新しい技術やトレンドへの強い探求心がある人
ゲーム業界は技術の進化が速いため、常に新しい知識やスキルをアップデートし続ける姿勢が求められます。
プログラマーであれば新しい言語や開発ツールの習得、デザイナーであれば最新の表現技術の研究、プランナーであれば市場の新しいトレンド分析など、職種に関わらず、自己学習を厭わない強い探求心を持つことが成功の鍵となります。
現状に満足せず、より良いゲーム体験を提供するために常に学び続けられる人は、この業界で長く活躍できるでしょう。
チームでの協調性と高いコミュニケーション能力を持つ人
ゲーム開発は、企画、プログラミング、デザイン、サウンドなど、異なる専門分野を持つ多くのメンバーが関わるチーム作業です。
自分のアイデアや考えを正確に伝え、他者の意見にも耳を傾ける高いコミュニケーション能力が不可欠です。
特に、企画職は開発チーム全体のハブとなるため、異なる職種のメンバー間の意見を調整し、円滑なプロジェクト進行をサポートする協調性が求められます。
自分の専門性を活かしつつ、チームとしての目標達成を最優先できる人が向いています。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界に向いていない人
一方で、ゲーム業界の特性や働き方が合わないと感じる人もいます。
自分が以下の特徴に当てはまる場合は、入社後のミスマッチを防ぐためにも、別の業界も検討してみることをおすすめします。
「ゲームで遊ぶのが好き」だけで仕事の厳しさを乗り越えられない人
「ゲームが好きだから」という理由だけで入社することは、最初のモチベーションとしては重要ですが、それだけでは仕事の厳しさを乗り越えることは難しいでしょう。
ゲームを「作る」ことは、「遊ぶ」こととは全く異なります。
開発の現場では、自分の好きなゲームジャンルとは関係のない作業を長時間こなしたり、自分のこだわりを泣く泣く諦めなければならない状況に直面したりすることがあります。
仕事としてのゲーム開発にプロフェッショナルな意識を持てない人は、モチベーションを維持することが難しくなる可能性があります。
曖昧な指示や急な仕様変更に対応できない人
特に開発の初期段階では、企画が固まりきっておらず、指示が抽象的であったり、開発途中でユーザーの反応や市場の変化に応じて急な仕様変更が入ることが頻繁にあります。
これらの変化は、時にそれまでの作業が無駄になることを意味するため、柔軟に対応できない人や、常に明確な指示を求める人は大きなストレスを感じるでしょう。
不確実な状況下でも、常に最善を尽くし、前向きに取り組む姿勢が求められます。
個人主義でチームでの協調性が低い人
ゲーム開発は、基本的にチームで行うものであり、自分の担当以外の工程にも気を配る必要があります。
自分の仕事だけを完璧にこなせば良いという考え方では、プロジェクト全体の進行を遅らせてしまう可能性があります。
特に、締め切りが迫っている時などは、自分の専門外の作業を手伝うなど、チームへの貢献意識を持てない人は、業界の働き方と合わないかもしれません。
チームメンバーと連携し、一つの目標に向かって協力し合える協調性が不可欠です。
【ゲーム業界はきついのか】ゲーム業界に行くためにすべきこと
ゲーム業界への就職を成功させるためには、単にエントリーシートを提出するだけでなく、計画的かつ具体的な準備が必要です。
以下のステップを実践して、他の就活生と差をつけましょう。
志望職種に必要なスキルを習得する
ゲーム業界は専門性の高い職種が多いため、志望する職種に必要なスキルを学生のうちに徹底的に習得しておくことが最も重要です。
例えば、プログラマー志望であればプログラミング言語の学習とポートフォリオの作成、デザイナー志望であればデッサン力やデザインツールの習熟、プランナー志望であればオリジナルのゲーム企画書を作成してみるなど、職種に直結する具体的な成果物を用意しましょう。
企業側は、即戦力となり得るポテンシャルを重視しますので、具体的なスキル証明ができるように努めてください。
業界・企業研究を徹底的に行い「なぜその会社か」を明確にする
ゲーム業界は、コンソールゲーム、PCゲーム、スマートフォンゲーム、アーケードなど、細かくセグメントが分かれています。
また、企業によって開発体制や企業文化、働き方も大きく異なります。
単に「ゲームが好き」というだけでなく、なぜその企業の、そのジャンルのゲーム開発に携わりたいのかを具体的に言語化できるように、企業研究を徹底的に行いましょう。
企業のIR情報や採用サイト、開発者のインタビュー記事などを読み込み、具体的な事業内容や開発実績と自分のやりたいことを結びつけることが内定への近道です。
ポートフォリオを作成し、実務レベルのスキルをアピールする
特にクリエイティブ職や技術職では、履歴書や面接での言葉だけでなく、あなたのスキルを証明するポートフォリオが選考の最重要項目となります。
あなたが実際に制作したゲーム、プログラミング作品、デザイン作品などを、分かりやすく、魅力的にまとめましょう。
企業側は、単なる作品の完成度だけでなく、あなたがどのような意図で、どのような技術を用いてその作品を作ったのかというプロセスや思考力を見ています。
作品の説明文には、工夫した点や問題解決のプロセスを必ず盛り込むようにしてください。
まとめ
ゲーム業界は、確かに激務や厳しいフィードバックといった「きつい」側面を持つことがありますが、それは同時に、世界中の人々に喜びや感動を与えることができる、非常にやりがいのある業界であることの裏返しでもあります。
この記事で解説した仕事内容や職種、そして向いている人の特徴を参考に、あなたが本当にこの業界で活躍したいのか、どのような形で貢献したいのかを今一度深く考えてみてください。
技術的なスキルや探求心、そして何よりも困難を乗り越える粘り強さを持つ人にとって、ゲーム業界は夢を追いかけられる素晴らしい場所です。
不安を自信に変えるための具体的な行動を今すぐ起こし、あなたの情熱を形にできる道を進んでください。
Digmediaは、あなたの挑戦を心から応援しています。