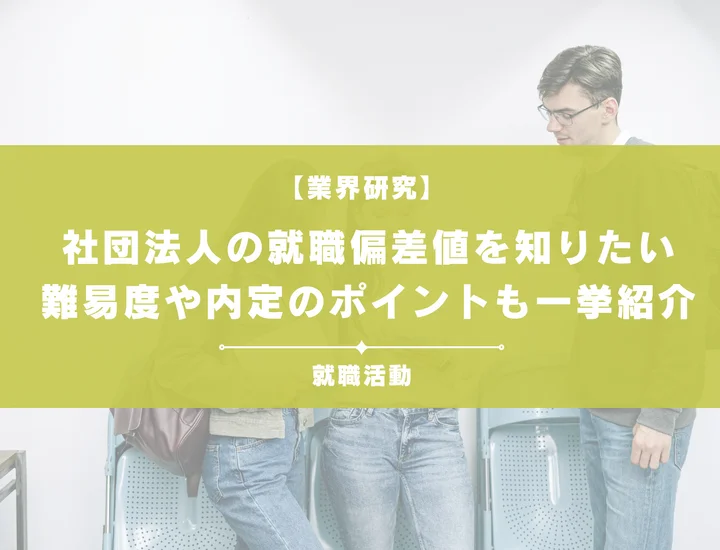HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職活動を進める中で、「就職偏差値」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
これは、正式な指標ではありませんが、主にインターネット上の掲示板などで、企業の人気度や入社の難易度を相対的に評価するために使われる指標です。
企業が公表している情報ではなく、就活生間での感覚的な評価や過去の採用実績、選考の倍率などに基づいて設定されているため、あくまで一つの参考情報として捉えるのが賢明でしょう。
この数値が高いほど、一般的に競争率が高く、内定を得るのが難しい企業群であると認識されています。
ただし、就職偏差値は企業の優劣を示すものではなく、あなたにとって本当に働きがいのある企業かどうかは、個々の企業理念や事業内容を深く理解した上で判断することが重要です。
今回は、就職偏差値という視点から、特定の業界に焦点を当てて詳しく解説していきます。
社団法人の就職偏差値ランキング
社団法人と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。
一般企業とは異なり、非営利の活動が中心であるため、一見すると就職偏差値とは無縁に思えるかもしれません。
しかし、実は社会的な影響力の大きさや安定性、そして活動の公共性から、特定の社団法人は新卒就活生の間で非常に高い人気を誇っています。
特に、国の政策に関わるような団体や、業界全体を統括するような組織は、競争率が非常に高く、難関企業として認識されることが多いです。
このランキングは、あくまで就活生間の評判や難易度に基づいた目安であり、実際の採用基準や組織の価値を決定づけるものではありませんが、業界研究の一環として、人気度合いを把握するのに役立つでしょう。
【社団法人】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】日本経済団体連合会
このランクは、日本の経済界全体を代表し、政府の政策決定に絶大な影響力を持つ組織です。
具体的な業務は政策提言、国際連携、産業界の意見集約であり、入職には極めて高い知性と、日本の未来に対する強い使命感が求められます。
【社団法人】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ社団法人の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】経済同友会 日本商工会議所 全国銀行協会 日本証券業協会
【68】関西経済連合会 中部経済連合会 新経済連盟 預金保険機構 生命保険協会 日本損害保険協会 投資信託協会 損害保険料率算出機構 証券保管振替機構 日本商品先物取引協会
【67】日本自動車工業会 日本鉄鋼連盟 日本鉱業協会 日本電機工業会 日本機械工業連合会 日本製薬団体連合会 石油化学工業協会 日本民営鉄道協会 石油鉱業連盟 日本船主協会 電気事業連合会 日本化学工業協会 全国地方銀行協会 全国信用金庫協会
【66】日本ガス協会 不動産協会 全日本航空事業連合会 日本航空宇宙工業会 全国清涼飲料連合会 ビール酒造組合 出版倫理協議会 日本医療機器工業会 日本貸金業協会 全国宅地建物取引業協会連合会
この層は、特定の巨大産業全体を統括する団体や、金融・保険といった基幹産業の自主規制・政策提言を担う団体が中心です。
対策としては、業界の構造や課題に関する深い理解を示すことが必須です。政策分析能力、高い論理的思考力、そして会員企業との調整能力が評価されます。
【社団法人】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】全国農業協同組合連合会 日本クレジット協会 日本たばこ協会 日本パン工業会 製粉協会 日本乳業協会 日本化学繊維協会 日本製紙連合会 日本造船工業会 日本衛生材料工業連合会 全日本不動産協会
【64】日本音楽著作権協会 日本物流団体連合会 日本鉄道車輌工業会 日本蒸留酒酒造組合 日本電線工業会 日本自動車タイヤ協会 日本ゴム協会 全国軽自動車協会連合会 日本鉄道技術協会
【63】全国漁業協同組合連合会 全国森林組合連合会 日本水道協会 日本工業用水協会 日本下水道協会 日本LPガス協会 電池工業会 日本記録メディア工業会 第二地方銀行協会
【62】日本書籍出版協会 日本通信販売協会 日本プラントメンテナンス協会 日本紡績協会 セメント協会 日本アルミニウム協会 日本チタン協会 日本ファインセラミックス協会
【61】日本自動車販売協会連合会 日本エレベータ協会 日本ねじ工業会 日本産業機械工業会 日本電気制御機器工業会 カメラ映像機器工業会 日本マーケティング協会 日本暗号資産取引業協会
このランクは、生活に不可欠な産業(食品、農業、インフラ)や、特定の技術分野を担う中堅の業界団体が中心となります。
対策としては、その業界特有の法規制や技術動向に対する専門知識をアピールすることが重要です。多様な会員の利害を調整するための高いコミュニケーション能力も求められます。
【社団法人】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】日本百貨店協会 日本電気大型店協会 日本ショッピングセンター協会 日本スーパーマーケット協会 全国電機商業組合連合会 日本チェーンドラッグストア協会 日本測量機器工業会
【59】日本冷凍食品協会 全国警備業協会 全日本トラック協会 日本バス協会 日本自動車リース協会連合会 日本フランチャイズチェーン協会 日本時計協会 日本筆記具工業会 日本ガスメーター工業会
【58】日本出版取次協会 日本自動車輸入組合 全国レンタカー協会 全国個人タクシー協会 日本工作機械販売協会 ドラム缶工業会 日本琺瑯工業会 日本肥料アンモニア協会 日本缶詰協会 日本食肉格付協会
【57】日本健康・栄養食品協会 全国オートバイ協同組合連合会 日本書店商業組合連合会 外国自動車輸入協同組合 日本中古自動車販売協会連合会 日本児童図書出版協会 全日本コーヒー協会 日本紅茶協会 日本パスタ協会 日本ソース工業会 日本マーガリン工業会 日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 日本食品添加物協会
【56】中古二輪自動車流通協会 日本伝統工芸士会 日本人形協会 日本楽譜出版協会 日本マタニティフード協会 日本アイスクリーム協会 日本ソフトクリーム協議会 日本ジェラート協会 全国ローヤルゼリー公正取引協議会 日本地ビール協会 全国和菓子協会 日本チョコレート・ココア協会 日本フラワーデザイナー協会
この層は、小売業、流通業、特定の嗜好品・専門品を取り扱う、よりニッチな分野の業界団体が多くを占めます。
対策としては、その業界の市場動向や消費者ニーズに対する具体的な分析を示すことです。広報・イベント企画能力や、業界の標準化・品質管理への貢献意欲も重要視されます。
【社団法人】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】パチンコ・チェーンストア協会 日本訪問販売協会 日本カヌー工業会 日本遊戯銃協同組合 日本エアースポーツガン協会 全国手すき和紙連合会 全日本宗教用具協同組合 日本金属洋食器工業組合 全国せんべい協会 日本チューインガム協会
このランクは、特定の趣味や地域文化、非常にニッチな製品を扱う小規模な団体が中心です。
対策としては、その団体が扱う分野への強い愛着と専門知識を伝えることが求められます。少人数体制での運営能力や、企画・実行力といった即戦力となる能力が評価されます。
【社団法人】とは
社団法人とは、特定の目的を持った人々の集まり(社団)に法人格が与えられた組織のことです。
一般企業が利益の追求を主な目的とするのに対し、社団法人は公益的な活動や特定の共通利益の実現を目的として活動する非営利法人です。
これは、組織の活動によって得られた収益を、構成員へ分配することを目的としないという点が、営利企業との大きな違いと言えるでしょう。
活動分野は非常に幅広く、業界団体の運営、資格試験の実施、学術研究の推進、地域社会の振興、環境保全など多岐にわたります。
社会全体の利益や特定の分野の発展に貢献するという使命感を持って働くことができる点が、就活生にとって大きな魅力となっています。
基本的な仕組み
社団法人の基本的な仕組みは、構成員である社員によって運営されるという点に特徴があります。
ここでいう「社員」は、一般企業の従業員ではなく、法人の意思決定に参加する権利を持つ人や団体のことを指します。
最高意思決定機関として「社員総会」があり、事業計画や予算、役員の選任といった重要事項がここで決定されます。
日常的な業務執行は、社員総会で選任された理事や監事などからなる「理事会」が行います。
活動の公共性や透明性が重視されるため、事業報告や財務状況の公開が義務付けられていることが多く、ガバナンスの確保が非常に重要となります。
収益事業を行うことも可能ですが、その収益はあくまで法人の活動目的に沿った事業に充てられる必要があり、利益の分配を目的としないという原則が徹底されています。
主な役割と業務内容
社団法人の主な役割は、その設立目的に基づいて、社会的な課題解決や特定の分野の発展に貢献することです。
業務内容は法人によって大きく異なりますが、一般的なものとしては、業界標準の策定やルールの整備、資格制度の運営と試験の実施、会員への情報提供や研修の実施などが挙げられます。
また、国や地方公共団体からの委託事業を受け、公益性の高いプロジェクトを推進することもあります。
たとえば、環境保全を目的とする社団法人であれば、啓発活動や調査研究が主な業務となり、業界団体であれば、政策提言や会員企業の支援が中心となります。
いずれにしても、社会全体への貢献度が高く、自身の仕事が持つ意義を実感しやすいという特徴があります。
業界の発展を支える専門性の高さ
社団法人は、特定の分野における専門知識やノウハウが集積された組織であることが多く、その業界全体の発展や、より良い社会の実現に不可欠な役割を担っています。
例えば、医療分野の社団法人であれば最新の研究動向をまとめ、質の高い医療提供のためのガイドラインを策定するなど、高度な専門性が要求されます。
また、国や地方自治体といった公的機関との連携も深く、政策決定の過程で重要な役割を果たすことも少なくありません。
そのため、職員には単なる事務処理能力だけでなく、所属する分野に関する深い理解と、関係各所との調整を行うコミュニケーション能力が求められます。
この専門性の高さと社会への影響力が、社団法人で働くことの大きな魅力の一つと言えるでしょう。
【社団法人】特徴
社団法人業界の特徴を解説していきます。
また、単に目の前の業務をこなすだけでなく、社会的な課題解決に貢献する使命感や、組織の公益性を理解し、ルールを遵守できる誠実さが必要です。
安定した経営基盤を持つ法人が多い
多くの社団法人は、その活動の公共性や公益性から、国や自治体からの補助金や委託事業、あるいは会員からの会費収入を主な財源としています。
一般企業のような市場競争に直接晒されることが少なく、収益源が比較的安定しているため、経営基盤が安定している法人が多いことが特徴です。
もちろん、個々の団体の財政状況によって差はありますが、長期的な視点での事業計画を立てやすく、腰を据えて社会貢献性の高い業務に取り組める環境があると言えます。
ただし、その安定性は事業の公共性が基盤となっているため、常に社会的なニーズに応じた活動内容の見直しや、透明性の高い組織運営が求められます。
社会貢献度の高い業務が中心となる
社団法人の最大の魅力の一つは、携わる業務が直接的に社会貢献に繋がる点です。
利益追求を第一の目的とする企業とは異なり、団体の設立目的である公益の実現や特定の分野の発展のために働くことになります。
例えば、病気の研究支援、文化財の保護、中小企業の経営支援など、自身の仕事が社会全体や特定の人々の生活向上に役立っていることを実感できる機会が多いです。
この社会貢献性の高さに強く惹かれ、入職を志望する就活生は少なくありません。
営利を目的としないため、短期的な成果よりも、長期的な視点での社会への影響や価値を重視した働き方ができるでしょう。
専門性が求められスキルアップしやすい環境
社団法人は、特定の専門分野に特化した活動を行っているため、職員にはその分野に関する深い知識やスキルが求められます。
入職後も、業務を通じて専門性を高めるための研修制度や、資格取得支援などが充実している団体が多いです。
また、学術団体や研究機関と連携することも多く、常に最先端の情報に触れながら働くことができる環境にあります。
例えば、法律系の社団法人であれば法改正に関する知識、IT系の団体であれば最新技術の動向など、自身の専門性を磨き続けることができるのは大きなメリットです。
専門性を高めることが、そのまま社会への貢献に繋がるため、自己成長意欲の高い人にとって理想的な職場環境と言えます。
【社団法人】向いている人
社団法人に向いてる人の特徴を解説していきます。
利用者だけでなく、地域住民や行政とも連携するため、高いコミュニケーション能力と協調性、そして変化に対応できる柔軟な姿勢を持つ人が活躍できます。
社会的な意義を重視して働きたい人
社団法人は、利益追求ではなく、公共の利益や特定のコミュニティへの貢献を使命として活動しています。
そのため、自分の仕事を通じて社会にどのような価値を提供できるかという「社会的な意義」を強く重視する人に向いています。
短期的な業績よりも、長期的な視点で社会を良くしていくことにやりがいを感じる人、人々の生活や特定の分野の発展に役立ちたいという熱い思いを持つ人は、社団法人での仕事に大きな充実感を得られるでしょう。
営利企業では得られない、使命感に基づいた働き方を実現したい人にとって、最適な職場環境と言えます。
特定の分野に対する強い興味や専門性を持つ人
多くの社団法人は、医療、環境、教育、産業振興など、特定の分野に特化して活動しています。
そのため、特定の分野に対する強い関心や、学生時代に培った専門知識を活かしたいと考えている人に非常に向いています。
入職後もその分野のプロフェッショナルとして、深く掘り下げた業務に携わることになるため、飽きることなく探求し続けられる意欲が求められます。
例えば、「日本の伝統文化を次世代に伝えたい」や「再生可能エネルギーの普及に貢献したい」といった具体的な目標や専門性を持っている人は、その知識や情熱を存分に発揮できるでしょう。
公平性や正確性を重視し真面目に取り組める人
社団法人の活動は、公共性が高く、その決定や行動が社会全体に影響を与えることがあります。
そのため、業務遂行においては、常に公平性、透明性、そして正確性が求められます。
例えば、資格試験の運営やルールの策定など、多くの人に関わる業務では、わずかなミスや偏りが大きな問題に繋がりかねません。
地道な作業にも手を抜かず、細部にまで気を配りながら真面目に正確に取り組むことができる人は、社団法人の職員として非常に重宝されます。
組織としての信頼を維持するために、規律を重んじ、責任感を持って職務を全うできる姿勢が重要です。
【社団法人】向いていない人
向いていない人の特徴を解説していきます。
しかし、以下に当てはまるからといって内定がもらえないというわけではないので参考程度にみていきましょう。
短期間で大きな金銭的報酬を求める人
社団法人は非営利組織であり、その活動目的は利益の最大化ではありません。
そのため、一般の営利企業と比較して、給与水準が控えめな場合が多いです。
もちろん、高い専門性を持つ一部の団体や公的色の強い団体では例外もありますが、基本的な給与体系は、社会貢献を重視する組織の性質を反映していると言えます。
したがって、入社数年で高い役職や多額の報酬を得ることを最優先に考えている人は、社団法人でのキャリアパスに物足りなさを感じるかもしれません。
仕事の価値を金銭的な報酬よりも、社会的な貢献度に見出せるかどうかが適性の分かれ目になります。
頻繁な異動やダイナミックな事業展開を望む人
多くの社団法人は、設立目的に沿った安定的な活動を継続することを重視しており、一般の企業のような頻繁な事業転換や、数年ごとの大幅な組織改編は少ない傾向にあります。
また、職員の異動も、特定の専門分野に長く携わることが求められるため、営利企業ほど頻繁ではないことが多いです。
そのため、新しい環境や分野での挑戦を短いスパンで繰り返したい、あるいは、市場の最前線でダイナミックに事業を拡大していくことに魅力を感じる人には、社団法人の落ち着いた環境は刺激が足りないと感じられるかもしれません。
一つの分野でじっくりと専門性を高めていきたい人とは対照的です。
成果が目に見える形で出ることにこだわる人
社団法人の活動は、政策提言、ルールの整備、啓発活動など、その成果がすぐに数字や業績として表れにくいものが多くあります。
社会的な影響は大きいものの、「売上」や「利益」といった明確な指標で個人の貢献度が測りにくいという特徴があります。
短期間で目に見える成果を出し、それによって評価されたいという志向が強い人にとっては、自分の仕事が本当に社会に役立っているのかという実感が持ちにくい場面があるかもしれません。
長期的な視点で、社会全体が少しずつ良くなることに喜びを感じられる、粘り強さを持つ人が向いています。
【社団法人】内定をもらうためのポイント
社会福祉法人での内定獲得には、単なる資格やスキルだけでなく、あなたの人間性と法人への理解度が鍵となります。
志望する分野に関する専門知識を深める
社団法人は特定の専門分野に特化した活動を行っているため、内定を得るためには、まずその団体が関わる分野に関する深い専門知識を身につけることが極めて重要です。
大学での専攻や研究テーマを、志望する法人の活動とどのように結びつけられるかを具体的に説明できるように準備しましょう。
例えば、環境系の社団法人であれば環境問題に関する法規制や最新技術、経済系の団体であればマクロ経済の動向や統計分析の知識などが求められます。
単に知識があるだけでなく、その知識を活かして入社後にどのように貢献したいのかというビジョンを示すことが、採用担当者の心に響くでしょう。
社会貢献への強い意欲を具体的に示す
社団法人の採用において、社会貢献に対する強い意欲と、なぜその団体でなければならないのかという熱意は非常に重視されます。
単に「社会の役に立ちたい」という抽象的な表現ではなく、その団体の具体的な活動内容やミッションに触れ、自分が共感した点や、自身が持ちうるスキル・経験をどう活かせるのかを具体的に語る必要があります。
例えば、特定のボランティア活動の経験や、NPO活動への参加経験などを通じて培った、社会課題への意識の高さや解決への意欲をアピールすると効果的です。
面接では、具体的なエピソードを交えながら、自身の情熱を伝えることが大切になります。
組織への適応力をアピールする経験を積む
社団法人は、行政、企業、他の非営利団体など、多様な関係者と連携しながら事業を進めることが多く、高いコミュニケーション能力や、組織の一員として協調性を持って行動できる能力が求められます。
学生時代に、チームで何かを成し遂げた経験や、多様な価値観を持つ人々と協力して活動した経験などを具体的に語れるように準備しましょう。
サークル活動の運営や、アルバイトでの顧客対応、グループワークでの役割遂行など、組織内での自分の立ち位置を理解し、円滑な人間関係を築ける適応力を示すことが、内定獲得に繋がる重要な要素となります。
【社団法人】よくある質問
社団法人業界を志望する学生からよくある質問をまとめました。
確認して、自分の悩みも解決していきましょう。
一般企業と比べて給与水準は低いですか
一概には言えませんが、一般的に利益追求を目的とする営利企業と比較すると、社団法人の給与水準は控えめな傾向があります。
これは、社団法人が非営利組織であり、収益を事業活動に再投資することを原則としているためです。
しかし、国の特殊法人など、公共性の極めて高い一部の団体では、公務員に準じた給与体系が適用されるなど、例外もあります。
重要なのは、金銭的な報酬だけでなく、仕事の社会的意義や安定性、専門性の高さなど、社団法人が提供する非金銭的な価値をどう評価するかです。
就職活動を進める際には、志望する法人の給与水準や昇給制度を事前に確認しておくことをおすすめします。
どのような資格やスキルが有利になりますか
社団法人が活動する分野によって求められる資格やスキルは大きく異なりますが、一般的には、その法人の活動に直結する専門資格や語学力は有利に働くことが多いです。
例えば、法律系の団体であれば弁護士や司法書士、医療系であれば医師や看護師の資格、国際的な活動を行う団体であれば高い英語力などが挙げられます。
また、特定の専門知識を裏付ける学術的な学位や、データ分析能力、広報活動に必要なデジタルスキルなども求められることがあります。
資格やスキルはあくまで手段であり、それらを活用して入社後にどう貢献できるのかを具体的に説明できることが最も重要です。
転勤はありますか
転勤の有無は、法人の規模や活動範囲によって大きく異なります。
全国規模で支部や支局を持つ社団法人であれば、総合職として採用された場合、数年ごとの転勤がある可能性は十分あります。
例えば、業界全体を統括するような大規模な団体や、国策に関わるような特殊法人は、広範囲に活動拠点を持ち、職員の異動も計画的に行われることがあります。
一方で、特定の地域や限定的な分野に特化した小規模な社団法人であれば、基本的に転勤がない場合も多いです。
採用選考を受ける前に、希望する法人の組織体制や勤務地に関する情報をしっかりと確認し、自身のキャリアプランと照らし合わせることが大切です。
まとめ
本記事では、就職偏差値という切り口から、社団法人という組織について詳しく解説しました。
社団法人は、営利を目的としないという特性から、一般企業とは異なる魅力とキャリアパスを提供してくれます。
特に、社会貢献性の高い業務に携わりたいという強い思いや、特定の専門分野を深く探求したいという意欲を持つ方にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
就職偏差値はあくまで一つの指標に過ぎませんが、人気度の高さを知ることは、準備の目安になります。
あなたが本当に大切にしたい価値観と、団体のミッションが一致しているかどうかを深く見極め、熱意を持って選考に臨んでください。