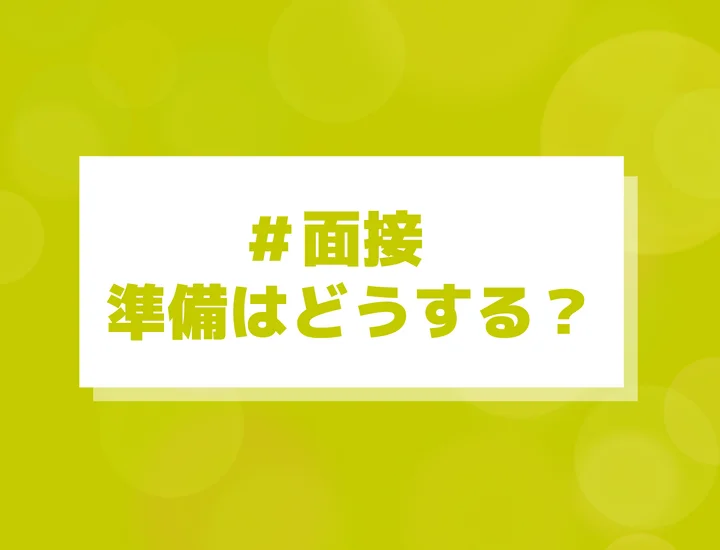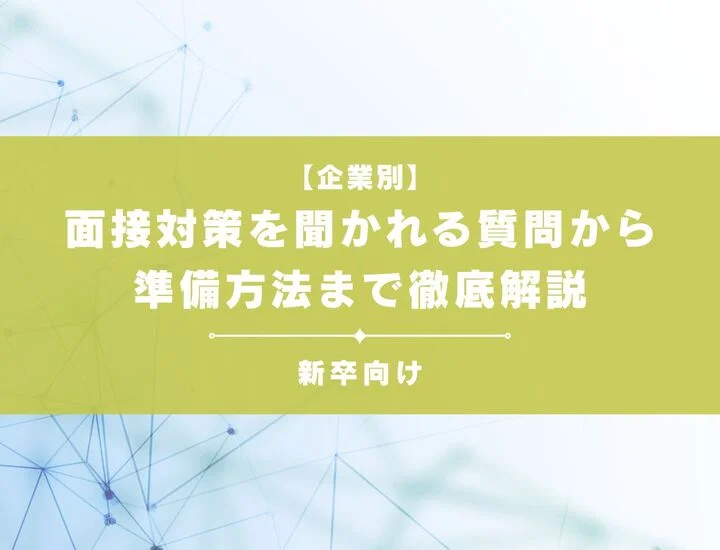HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
「集団面接の逆質問で何を聞けば良いのかわからない」
「そもそもどういう理由で面接官は聞くのか?」
「どんな逆質問をすると企業に評価されるのか?」
集団面接の逆質問に関して、このような悩みをお持ちの就活生は多いでしょう。
今回は集団面接の「逆質問」について重要性とポイントをご紹介します。
目次[目次を全て表示する]
【集団面接で逆質問】企業側の意図を捉える
集団面接では、最後に「何か質問はありますか」と逆質問の時間が設けられることがあります。
この時間は、ただ疑問を解消するためだけではなく、あなたの姿勢や人柄を評価する大切な機会でもあります。
企業側の意図を理解したうえで、戦略的に質問することが重要です。
学生の入社意欲を知るため
企業が集団面接で逆質問を促す理由の一つに、学生の入社意欲を確かめる目的があります。
「特にありません」と答えてしまうと、関心が薄い、準備不足、志望度が低いといった印象を与えてしまう可能性があります。
一方で、事前に企業研究を行い、仕事内容や社風などに関連する質問ができれば、「この企業で働きたい」という前向きな姿勢が伝わります。
質問の内容から、企業が何に力を入れているかを読み取る力や、自分のキャリアへの意識の高さも評価対象となるため、準備しておくことが大切です。
企業への興味関心を図るため
逆質問の場面では、学生が企業のどこに注目しているかを確認する意図もあります。
たとえば、「貴社の研修制度について詳しく知りたい」といった質問からは、成長意欲や企業文化への関心が伝わります。
一方で、待遇や休日だけに関する質問が続くと、目先の条件ばかりに目が向いている印象を与えることもあります。
企業は、質問の内容を通じて学生の価値観や興味の方向性を把握しようとしています。
どんな質問をするかで、あなたがどんな考えを持ち、どのように働こうとしているのかが伝わるのです。
集団でのコミュニケーション能力を図るため
集団面接での逆質問では、自分の発言だけでなく、全体の場を意識した行動も評価対象になります。
他の学生がすでに聞いた内容を繰り返すと、準備不足や空気を読めない印象につながるため注意が必要です。
また、質問が長すぎたり、自分ばかりが話す姿勢も好ましくありません。
逆に、他の人の質問をよく聞き、それに関連した質問を簡潔に投げかけることができれば、柔軟な思考力や協調性を示すことができます。
企業は、このような場面での立ち居振る舞いから、入社後にチームで働く際の適応力や配慮のある行動ができるかどうかも見ています。
【集団面接で逆質問】逆質問で好印象を与えよう
逆質問は面接のオマケのように捉えてる人も多い印象ですが、集団面接は逆質問で企業へ好印象を与えられるチャンスです。
逆質問をすることでなぜ企業へ好印象を与えられるのか、その理由を解説します。
意欲をアピールできる
集団面接における逆質問で好印象を与えられる理由は、企業へ入社したい意欲をアピールできるからです。
集団面接は志願者の人数を一気にふるい落とす目的で行われ、一次面接で多く見られます。
しかし、企業側からは学生時代に力を入れたことや自己PRなど、基本的なことしか聞かれません。
ですので、そのような場面で自分が積極的に逆質問をすると、企業に好印象を与えて、周囲と差をつけられるのです。
中には質問された志望動機を上手く答えれば十分なのではと思う方もいるかもしれません。
集団面接に参加して黙っているだけでは、採用担当者がネガティブなイメージを持つこともあるので、逆質問で意欲を伝えることが大切です。
何に興味関心があるのか知ってもらえる
集団面接における逆質問で好印象を与えられるもう一つの理由は、興味関心を抱いている対象を採用担当者に知ってもらえるからです。
そもそも逆質問は、自分なりに色々考えているから出てくるもので、企業の取り組みや業界に対して興味関心を持っていることに他なりません。
企業は学生の興味関心や価値観を深掘り、学生の志向を把握するために面接を行うので、興味の対象を明確に伝えることが大切です。
とりあえず内定が欲しい気持ちはわかりますが、内定を貰うことは社会生活の始まりに過ぎません。
入社した後の働き方やキャリアについても計画的に考えていることをアピールでき、人事に好印象を与えられます。
人柄を知ってもらえる
面接において逆質問を活用することは、企業や職務内容に関する興味や好奇心を見せるだけでなく、自分の性格や価値観を伝える絶好の機会になります。
例えば、逆質問を通じて、自主的に情報を求め、深い理解を目指す姿勢や、学習と成長に対する意欲を示すことができるというわけです。
さらに、質問の仕方から、論理的に物事を考え、コミュニケーションスキルの高さを強調することができる場合もあるでしょう。
また、どういう質問をするかということや表現の仕方によっては、自身の仕事への見方や将来に対する考え方を、自然な形で面接官に伝えることが可能です。
【集団面接で逆質問】グループ面接の特徴
集団面接は複数人で行われる選考方法です。
就活生4人〜5人に対し、面接官は2人〜3人という場合が一般的です。
質問に関しても、定番な内容が多いです。
一つの質問内容に対して順番に回答していき、面接官へアピールする流れになっています。
集団面接は複数人で行うので、どうしても一人当たりの持ち時間が短くなってしまいがちです。
そのため、 周りと一味違う印象を与えることが大切です。
また、周りの就活生の答えも同時に聞くことになります。
他の就活生が、より正しい答えを回答していれば、その時点ではっきりと差をつけられてしまいます。
これまで一対一の面接では緊張しなかった人でも、周りの就活生の中で自分の回答を発言することが「恥ずかしい」と思う人もいるでしょう。
しかし、集団面接に臨むのであれば、それらは克服しなければいけません。
特に、就活生から人気の大手企業などでは、グループ面接で選考を行うことが多いです。
質問の意図を捉えて、自分の主張をしっかりと述べましょう。
グループ面接で聞かれることに関して詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
差がつきにくい
集団面接では余程のインパクトがない限り、差がつきにくいのが現実です。
その理由として、 一人当たりに対する時間が短いというのも大きな要因でしょう。
さらには、すらすらと答えられる場合は良いですが、言葉に詰まり、その場で回答に答えられないと次の質問者へと発言が移ってしまいます。
つまり、一人の面接と比べると伝えられる情報量に大きな限りが出てしまうのです。
そのため、与えられた質問に対して面接官の意図を瞬時に判断し、「何を伝えるのが適切か」を割り出す必要があります。
しかし、選考結果は、同じように合否が出てしまいます。
そのため、一つ一つの答弁が重要になることを理解した上で、 逆質問が特に重要なポイントとなってきます。
逆質問で、何を聞くかによって、その人の質問の力量が試されてきます。
逆質問で、 入社後を意識した質問などをすることで、相手の面接官により好印象を残すことができます。
それらのポイントを、実際に下記の例を見て説明していきます。
【集団面接で逆質問】グループ面接のポイント
なぜ集団面接で逆質問をすると企業へ好印象を与えられるのか理由についてご紹介しました。
次に集団面接の逆質問では、どのようなポイントに気を付ければいいのか具体例と合わせて解説します。
簡潔に話す
集団面接で逆質問をするときは、簡潔にわかりやすく話すことがポイントです。
できるだけ自分が他の人よりもアピールしたい気持ちはわかります。
しかし、集団面接の時間は長くても60分で、一人ひとりに与えられる時間は決して多くはありません。
採用担当者は、志願者の必要な情報を限られた時間内に聞き出すことを念頭に置いています。
ダラダラとまとまり無く質問をすると、周囲への気遣いができない学生だと思われるリスクがあるので、「結論から話す」ことを意識しましょう。
社会人にとって時間は1分1秒たりとも惜しいものです。
相手に簡潔に伝えるスキルは入社してからも必ず活きるので、簡潔に話すよう心掛けましょう。
基本的に笑顔で
集団面接に限ったことではありませんが、基本的に笑顔で相手の顔を見て質問や受け答えをするようにしましょう。
相手に好印象を与えるため、面接での表情は特に大切です。
採用担当者も1人の人間ですので、面接だけでなく入社後もできるだけ明るい人とコミュニケーションを取りたいと思っています。
人が相手に与える視覚情報の大切さを訴えたもので、アルバート・メラビアンという心理学者が提唱した「メラビアンの法則」があります。
メラビアンの法則は、コミュニケーションにおいて視覚情報が55%の割合で影響を与えるという法則です。
「的を得た質問をする優秀な学生だけど愛想が無い」と思われないよう、笑顔で逆質問をするよう心掛けましょう。
他の就活生の話も聞いておく
他の就活生が逆質問する時は、丁寧に話を聞いておくことも重要です。
集団面接では他の就活生の話も聞く機会があり、面接官によっては「今のAさんの話に対してどう思いましたか?」と話を振られることがあります。
とはいえ、優れた解決策や優秀な回答をしようと背伸びする必要はなく、自分なりの意見を一つでも持つことが大切です。
他の就活生の長い話を聞いて眠くなる気持ちにもなりますが、それでも他の就活生の話を聞きましょう。
社会人として、人の話を聞く態度を見られている可能性もあるからです。
採用担当者が「ちゃんと話を聞いているのかな?」と心配にならないくらいに、ボーっとしないで耳を傾ける姿勢を取りましょう。
周りに流されない
集団面接では、他の受験者の意見を聞く中で、自分の意見を見失うことがあります。
しかし、周りに合わせすぎると、自分の考えや価値観が伝わりにくくなってしまいます。
他者の意見を受け入れる柔軟性を持ちながらも、自分の意見をしっかりと持ち、それを的確に伝えることが重要です。
例えば、「他の方の意見に共感する部分もありますが、私はこのように考えます」と、自分らしい視点を加えることで、個性を際立たせることができます。
はきはきと話す
面接において、はきはきと話すことは非常に重要です。
自信を持っているように見えるだけでなく、相手に話の内容がしっかり伝わるという点でも大きなメリットがあります。
声の大きさやトーンにメリハリをつけることで、聞き手は話に集中しやすくなり、内容の印象も強く残ります。
逆に、声が小さく曖昧な話し方をしてしまうと、内容が良くても説得力に欠けてしまう可能性があります。
とくに集団面接では他の就活生との比較もあるため、第一声から聞き取りやすく明るい印象を意識することが大切です。
【集団面接で逆質問】逆質問の種類
それでは、具体的にどのような質問をすれば良いのでしょうか。
具体例やポイント、逆にやってはいけないことについても説明していきます。
「企業理解するための質問」「働いている社員を理解するための質問」「仕事内容を理解するための質問」、これらのポイントを押さえて周りと差をつけましょう。
集団面接は個人の持ち時間が限られているため焦ってしまうことやほかの就活生と比べてしまい本来の力を発揮できないことが多いです。
しかし、対策をして挑めば、自分をアピールする最大のチャンスにもなります。
自信を持ってグループ面接に挑みましょう。
企業理解するための質問
企業の方向性や強み、これからのビジョンを知るうえで重要な質問です。
自分と企業、双方の考えに相違がない確認することができます。
下記の具体例をもとにしっかりと対策し、企業の新たな一面を知るチャンスにしましょう。
「5年後、10年後のビジョンを教えてください」という質問は、入社したい気持ちが一過性のものではないことを伝えられます。
やる気や向上心をアピールするには、自分が働いていることを前提にした質問が有効的です。
「御社の最大のアピールポイントはなんですか」という質問は、企業を正しく理解できているかの確認にもなります。
また、自分と企業の相性を判断する基準にもなり、ミスマッチを防ぐこともできるのです。
「これだけは他社に負けないと思う強みはなんですか」という質問は、現場の実情を知ることができます。
他社に関する質問は印象に残りやすく、高い入社意欲を感じることができます。
働いている社員を知るための質問
実際に働いている社員についての質問は、入社した自分のイメージを掴みやすいです。
また、面接官に自分が働いているところを想像してもらえます。
「日々の業務で意識していることを教えてください」という質問は、自分がどういう意識で業務をこなしていくか、具体的に想像できるのです。
また、すでに入社後の業務プロセスを意識していることを示せます。
「入社3年程度の方はどのような業務に携わっていますか」という質問も、入社3年目の自分をすでにイメージしているというアピールにもなります。
3年先を見据えた質問をすることにより、さらに熱意を伝えられるでしょう。
「達成感を感じたエピソードを教えてください」という質問は、仕事にやりがいを見出し、自ら向上したいという強い意思を感じさせます。
また、会社というチームを意識し、協調性を持って業務に臨みたいという気持ちも伝わります。
仕事内容を知るための質問
具体的な仕事の内容は、入社前に知っておきたいことの一つです。
面接官が答えやすい質問を意識すると、より詳しい情報を入手することができるでしょう。
「実務に入るまでの時間と経緯を教えてください」という質問は、仕事に対する関心の高さと責任感をアピールできます。
単に内容を聞くだけでなく、詳細に知りたいという気持ちが表れているので、好印象にもつながる可能性でしょう。
「仕事で求められることはなんですか」という質問は、仕事に必要な柔軟性や協調性を意識しているというアピールになります。
より仕事内容をイメージしやすい質問であり、仕事での目標も設定しやすいです。
「今後、事業をどのように展開させる予定ですか」という質問は、真剣に入社を望んでいる姿勢を示せます。
企業そのものへの関心と、入社意欲を強く面接官にアピールすることができます。
【集団面接で逆質問】面接官から好印象を得られる5つの逆質問
それでは、実際に面接官に好印象を残す逆質問とは一体なんでしょうか?
面接官から好印象を得るためには、下記の3つのポイントが重要視されます。
・志望する理由が確固たるもの
・非常に優秀(希有)であること
・想いが強いこと
・自分の成長意欲を自分の成長意欲をアピールできる質問
・自分の将来を描くための質問
面接官から評価される傾向のあるものを3つに分類した上で、それぞれに合致する3つの逆質問のパターンを解説していきましょう。
逆質問は「自分をアピールする」非常に大切な時間ですが、あくまで「質問」なので関係ない話をしても逆に悪い印象を与えてしまうかもしれないので注意してください。
これら3つのポイントを意識した逆質問をおこなうことで、 面接官から「優秀な学生」という評価を獲得することができます。
一つ一つのポイントをしっかり押さえていきましょう。
志望する理由が確固たるもの
「どうしてもその企業で働きたい」と、逆質問の中でアピールする質問としては下記のような逆質問が効果的です。
・私が志望している職種に対しての仕事スケジュールなどを詳しく知りたいです。
・入社までに、どんなことを勉強しておけば良いか教えてください。
・私が配属を希望している部署の人数や、規模感はどんな感じでしょうか?
・配属先、または志望職種の方とお会いすることは可能ですか?
上記のような逆質問をすると面接官からも 「うちへの志望度が高い学生かもしれない」という評価につながることもあります。
企業側も、 できれば「第一志望」で応募をしてきている学生を採用したいのが本音です。
そのため、入社後の動きや、それまでに何を勉強しておけば良いのかを聞くことで好印象を与えることができるかもしれません。
非常に優秀(希有)であること
「私は他の学生よりも優秀です」と逆質問の中でアピールすることは誰しも知っておきたいポイントでしょう。
下記のような逆質問が特に効果的です。
・学生時代に〇〇でインターンをしていたのですが、同じ領域の新規事業を立ち上げたいと思っているのですが可能でしょうか?
・〇〇の資格を持っているのですが、それを御社で活用することは可能でしょうか?
なるべく、抽象的なものは避けて、 より具体的に「自分は何ができる」というのをアピールすることが大事です。
企業側も優秀な学生の基準として「1年目から戦力として働いてくれるか」を見ていることが多いです。
学生時代に何かビジネスでの経験があれば、それを踏まえた上での逆質問が適切でしょう。
想いが強いこと
上記で説明した「志望する理由が確固たるもの」と似ていますが、「想いを伝えたい」のであれば、以下の質問を聞いてみると効果的です。
・御社の〇〇さんと話をさせていただく機会があったのですが、他の社員さんも熱い気持ちで仕事をしている人が多いですか?
・私はとにかく若い時から「成長したい」と考えているのですが、入社1年目2年目の社員さんは、どのような成長曲線を描いていますか?
自分の成長意欲をアピールできる質問
自分が成長に積極的であることを示す質問は、面接官に良い印象を与えます。
例えば、「御社で活躍するためにはどのようなスキルや知識が特に重要だとお考えですか?」という質問は、自分の努力すべき方向性を知りたいという意欲を示すものです。
また、「新人の育成において、どのような研修プログラムやサポート体制があるのでしょうか?」と尋ねることで、学ぶ姿勢や成長意欲を強調できます。
このような質問を通じて、入社後に自ら努力を重ねていく姿勢をアピールしましょう。
自分の将来像を描くための質問
入社後のキャリアを真剣に考えていることを示す質問も、好印象を与える効果的な方法です。
例えば、「御社でキャリアを積んでいく中で、どのようなポジションや役割に挑戦する機会がありますか?」という質問は、将来の成長や活躍を見据えていることを伝えられます。
さらに、「活躍されている社員の共通点や特徴を教えていただけますか?」と質問すれば、理想のロールモデルを探し、自分もそのように成長したいという意欲が伝わります。
【集団面接で逆質問】NG質問の特徴
質問だからといって、なんでも聞いて良いわけではありません。
意図・目的が明確でない質問はしないようにしましょう。
特に、グループ面接ではほかの就活生と比較されやすくなってしまいます。
社会人としてのモラルを問われたり、自信のなさが表れていたりするような質問は控えたほうが効果的です。
マイナスな印象を与えてしまうような以下の質問は避けましょう。
「企業のホームページに掲載されている内容を質問」「ネガティブな質問」「プライバシーを侵害する質問」「「はい」か「いいえ」で答えられてしまう質問」、これらがNG質問の特徴です。
回避するためのポイントや工夫をしっかり理解しておきましょう。
調べればわかる情報
調べればすぐにわかるようなことを質問してしまうのは、明らかな準備不足です。
従業員・企業理念・主力製品などに関する質問は、必ずホームページなどに記載されています。
このような質問をしてしまうと、企業への理解や意欲が不足していると判断されかねません。
ホームページ、求人情報などは暗記するつもりで精読し、面接に臨みましょう。
事前調査を入念に行ったことが伝われば、面接官への印象も良くなります。
読み込んだうえで自分が興味を持ったことや詳しく知りたいと思ったことを質問すれば、入社したい気持ちは自然に伝わるでしょう。
また、同時に競合企業をリサーチしておくと用意周到さをアピールできます。
事前準備の大切さを理解し、ほかの就活生と差をつけましょう。
ネガティブな質問
面接では、自分が採用に値する人物だと、ポジティブな面をアピールする必要があります。
自信のなさが窺える質問や仕事に対するやる気を感じられない質問は、当然採用から遠ざかるでしょう。
たとえば、「仕事を教えてもらえる環境ですか」という質問は、自分の仕事に自信がないという印象を受けます。
受け身ではなく、自ら進んで行動できるということを質問を通してアピールしましょう。
「新たなスキルを学べますか」という質問も、自主性がないと受け取られてしまいます。
会社に頼りきるのではなく、学びたいスキルは自発的に学ぶことを意識しましょう。
「残業時間はどのくらいでしょうか」という質問も、仕事への興味が薄いと捉えられてしまいます。
福利厚生については誰しもが気になるところです。
しかし、残業や休日出勤についての質問が質問が集中してしまうと、仕事への熱意は伝わりにくくなります。
プライバシーを侵害する質問
プライバシーに関する質問は、面接においてのコミュニケーション方法としては避けたほうベストです。
個人情報を探ろうとする行為は、人間性が顕著に表れてしまい信用問題にも関わります。
面接官の人柄を知ろうと興味を持つことは良いことですが、過度にプライベートな質問をしてしまうとモラルそのものが問われてしまいます。
下記の具体例を参考にし、絶対にしないようにしましょう。
「年齢を教えてください」「付き合っている人はいますか」「給料はどれくらいですか」などの質問は、面接にまったく関係ありません。
ただし、臨機応変に応じて良い場合もあります。
面接官の方から個人的な話題を切り出してきたのであれば、コミュニケーションの一環として答えましょう。
個人的な趣味や週末の予定の話題は、節度を守れば親交を深められる良いきっかけとなります。
「はい」か「いいえ」で答えられてしまう質問
面接では、社会人として必要な能力を見ているのはもちろんですが、その中には当然コミュニケーション能力も含まれています。
面接官の回答が一言で終わってしまう質問は、会話が続かず詳しい情報も得ることができません。
思わぬ角度から情報が得られることもあるので、面接官とのコミュニケーションは常に意識しておくことが大切です。
また、コミュニケーション能力の有無を判断するためだけに質問している場合もありますが、常に相手を思いやることを意識していれば大丈夫です。
この質問に限らずですが、自分が得たい情報を意識して質問をすることを心がけましょう。
以上のポイントを踏まえると、スムーズに面接が進み、さらには自分のアピールにもつながります。
【集団面接で逆質問】逆質問に関してよくある質問
ここからは、逆質問でよくある質問について、出来るだけ具体的に解説していきます。
そもそも逆質問については苦手意識をもつ方も多く、なかなか自分で正解を探しづらいものでもあるでしょう。
是非、下記で解説するよくある質問への回答を通じ、具体的なイメージを掴んでいって下さい。
逆質問をするタイミングはいつ?
まず、面接で逆質問をするタイミングについて解説していきます。
大体の面接では、最後に「何か質問はありますか?」と聞かれることが多いです。
この質問の意図としては、応募者の熱意や意欲、企業に対する理解などを把握するための質問なので、ここで逆質問をすることはごく自然な流れです。
また、面接官の話に関連するして質問が思いついた場合も逆質問して問題ないでしょう。
そうすることで、積極性と面接官の話に対する理解力をアピールすることが可能です。
ただし、その際に面接官の話を遮らないようにタイミングには注意が必要です。
そして、面接官から特に逆質問を促されない場合もあるでしょう。
そういった場合、面接の終盤に自分から切り出してまとめて質問することも有効です。
しかし、長々と質問するのは避け、簡潔にまとめる意識をしましょう。
逆質問の質問回数は何回まで?
結論、面接で逆質問をする適切な回数について、特に明確な決まりは存在しません。
しかし、面接のフェーズによって仮定することはできるので是非参考にしてみてください。
・一次面接:企業や仕事に対する基本的な理解度を確認するため、1〜2個程度に留めましょう。
長々と質問すると、時間内に面接官が答えられない可能性もあります。
・二次面接以降:より具体的な質問をすることで、入社意欲や熱意をアピールすることができます。
複数の質問をしても良いでしょう。
・最終面接:入社後のキャリアプランなどを具体的な質問することで、企業とのマッチ度を確認することができます。
多少多めに質問しても良いでしょう。
他の学生と質問内容が被った場合は?
また、逆質問が他の学生と質問内容が被ってしまうことは珍しくありません。
そのような場合でも、自分ならではの質問は可能です。
下記、3つほど手法を紹介するので参考にしてみてください。
1. 補足質問をする
他の学生と同じ質問をする場合は、さらに深掘りする質問をすることで、差別化を図ることができます。
例:「すでに質問もありましたが、もう少し具体的に必要なスキルを教えていただきたいです。」
2. 自分の経験と関連付ける
質問内容に自分の経験を関連付けることで、熱意や意欲を伝えることができます。
例:御社の社風について、チームワークを大切にされていると伺いました。
御社に入社したら、チームの一員として貢献したいと考えておりますが、その力を発揮できる場所はありますでしょうか?
3. 質問の意図を説明する
意図を説明することで、背景にある考えや価値観を伝えることができます。
例:御社の研修制度について気になっております。
理由としては、入社後にすぐに戦力になれるよう、事前に自分でも学んでおきたいと考えております。
【集団面接で逆質問】例文
以下では、集団面接での逆質問の具体例と、それぞれの質問に対する意図や解説を紹介します。
逆質問は、自分の関心や意欲を示す絶好の機会です。
それぞれのポイントを理解し、適切に活用しましょう。
①御社が今後注力される分野やプロジェクトについて、具体的にお伺いできますか?
会社の成長や方向性に強い関心があることを示す質問です。
この質問により、企業の未来を見据えた考え方を知るだけでなく、面接官に「長期的に貢献したい」という意欲をアピールできます。
事前に調査した内容に基づいて、例えば「最近の○○プロジェクトについて伺いたいのですが」など具体的な切り口を加えると、より説得力が高まります。
この姿勢は、企業に「積極的な候補者」という印象を与えることができます。
②業界全体で競争が激化している中、御社が特に重視している差別化ポイントは何ですか?
業界動向を理解していることを示しつつ、企業の強みを知りたいという姿勢を伝える質問です。
この質問をする際、具体的な競争状況や他社との差異に触れることで、業界分析ができていることを示せます。
「御社の○○製品が市場で高評価を得ている理由についても教えていただけますか?」などの具体例を加えることで、さらに深い関心をアピールできます。
面接官に「自社の価値を理解してくれる候補者」として印象付けることが可能です。
③入社までに身につけておいた方が良いスキルや知識があれば教えてください。
成長意欲や学習意欲があることをアピールできる質問です。
また、具体的なスキルや知識を尋ねることで、入社後に即戦力として活躍したいという積極性を示せます。
さらに、「スキルの習得にあたって具体的に取り組めることがあれば教えてください」など追加の質問を加えると、より意欲的な印象を与えることができます。
事前準備をしておけば、面接官から具体的なアドバイスを得ることも可能です。
④新入社員が早期に成果を出すために、特に意識すべきことは何ですか?
入社後に成果を出すことに強い意欲があることを伝える質問です。
この質問は、面接官に「挑戦意欲がある候補者」という印象を与え、評価を高める可能性があります。
さらに、「新入社員がよく直面する課題や乗り越えるためのポイントも伺えれば嬉しいです」と補足することで、具体的なアドバイスを引き出しやすくなります。
面接後にも活かせる情報を得るチャンスとして活用しましょう。
⑤御社でのキャリア形成において、若手社員が直面する主な課題にはどのようなものがありますか?
自分のキャリアに真剣に向き合っている姿勢を示す質問です。
この質問を通じて、企業が期待する成長プロセスやサポート体制について具体的に知ることができます。
「課題を乗り越えた先にどのような成長が期待されるか」などの視点を加えることで、将来の成長ビジョンを共有する形にもなり、好印象を与えることが可能です。
⑥新入社員が職場に早くなじむために、どのようなサポートがありますか?
新しい環境への適応力と、チームワークを大切にしたいという意欲を示せる質問です。
さらに、「具体的な研修制度や先輩社員からのサポートについてもお聞きしたいです」と追加すると、企業の体制への理解を深める助けになります。
この質問は、「柔軟性があり、協調性の高い人材」として評価される可能性が高まります。
⑦御社での仕事で、特に印象に残っているプロジェクトについて教えていただけますか?
面接官の経験に関心を示すことで、対話を通じて関係を築きやすくなる質問です。
また、自分がそのようなプロジェクトでどのように貢献できるかを考える材料にもなり、入社後のビジョンを明確にできます。
この質問は、自分がその企業で働く姿をイメージしやすくすると同時に、面接官にも好印象を与える非常に有効な質問です。
⑧御社で働く中で、面接官ご自身が特に感じられるやりがいはどのようなものですか?
面接官の価値観や仕事への取り組み方を知るための質問です。
「そのやりがいを得るために、特に重要だと感じるスキルや姿勢についても教えていただけますか?」と付け加えることで、より具体的なアドバイスを得られます。
さらに、面接官のエピソードから会社の文化や価値観に触れることで、自分との相性を確認できます。
この質問を通じて、面接官との会話が活発になるだけでなく、自分がその企業でどのように成長できるかのヒントを得ることも可能です。
⑨今後、御社が挑戦したいと考えている新しい事業分野があれば教えてください。
企業の未来や成長戦略に興味を持っていることをアピールできる質問です。
「その分野の取り組みにおいて、社員がどのように関与するのか、求められる役割についてもお伺いしたいです」と加えることで、具体的な人材像やプロジェクトの詳細を引き出すことができます。
この質問は、自分がどのように企業の未来に貢献できるかを考えるきっかけになるとともに、長期的に企業と共に成長したいという意欲を伝えるのに非常に有効です。
⑩業界の変化が激しい中で、御社が持つ強みをどう活かしていくお考えですか?
業界全体の動向を理解し、企業の競争力や方向性に関心を持っていることを伝える質問です。
「その強みをどのように維持・発展させていくか、またそれに関連して今後注力したい分野があれば教えていただきたいです」と掘り下げれば、より詳細な情報を得られます。
この質問を通じて、自分が企業の戦略にどう貢献できるかを具体的に考える材料を得ることができ、企業分析力や入社後の展望を持っていることを示せます。
【集団面接で逆質問】逆質問一覧
ここまで記事を読んでみてどうしても逆質問が見つからない場合いこの一覧を参考にしてみてください。
向上心に関する逆質問
成長意欲を伝えたい場合は、評価制度やスキルアップ支援などに関する質問がおすすめです。
「どのような姿勢が評価されやすいか」や「新人がどのように成長しているか」などを尋ねると、前向きな姿勢がより伝わり、努力を重ねる人材だと印象づけることができます。
例文
社内で成長するために必要なスキルは何ですか?
このポジションで成功するためにはどんな能力が必要ですか?
入社後、最初の1年で求められる成果は何ですか?
社員の成長を支援するプログラムはありますか?
どのような社員が長期的に成功する傾向がありますか?
自己成長を促進するための社内の文化や環境について教えてください。
御社では、キャリアアップのためにどのようなサポートがありますか?
どのような評価基準で社員の成長が測られますか?
上司や同僚からのフィードバックはどのように行われますか?
自己啓発や研修制度について詳しく教えていただけますか?
資格に関する逆質問
資格取得やインターン経験に関連づけた質問は、主体的に学んできた姿勢を伝える効果があります。
「業務で役立つ資格は何か」「入社後に推奨されるスキルアップ方法はあるか」などの質問を通じて、学びに対する姿勢を具体的にアピールできます。
例文
このポジションに必要な資格は何ですか?
業務を効率化するために、取得すべき資格はありますか?
資格取得をサポートする制度はありますか?
業界特有の資格について、入社後に取得が推奨されるものはありますか?
この仕事を通じて、新たに資格を取得することは可能でしょうか?
会社は資格取得のためのサポートをどのように行っていますか?
資格やスキルの向上をサポートするために、社内で提供されている研修はありますか?
資格を活かしたキャリアパスの例を教えてください。
資格取得を目指している社員に対して、どのような支援が行われますか?
資格を持っている社員が活躍できる場はありますか?
将来性に関する逆質問
キャリアの方向性がある程度明確な場合は、自身の将来像と照らし合わせた質問が効果的です。
「○年後にどのようなキャリアステップを描けるか」などを聞くことで、企業で長く働く意志や成長志向を自然に伝えることができます。
例文
御社の今後の成長戦略について教えてください。
企業の未来に向けたビジョンや目標について詳しく教えてください。
今後5年間で会社がどのように変わると考えていますか?
新規事業や新しい市場に進出する計画はありますか?
業界全体の将来性について、どのように感じていますか?
御社が目指す長期的なビジョンに対して、どのような役割を果たすことが期待されていますか?
新しいテクノロジーやイノベーションにどのように取り組んでいますか?
会社の成長に向けて、どのような変革が行われていますか?
近い将来に新しい市場への進出を計画していますか?
御社が目指す未来のビジョンに共感できる点は何ですか?
企業の過去に関する逆質問
企業の歴史や過去の取り組みに触れた質問は、丁寧に企業研究をしている印象を与えられます。
たとえば「○○年に始められた○○の取り組みにはどんな意図があったのか」と聞くと、表面的でない理解が伝わり好印象を持たれやすいです。
例文
御社の創業の背景について教えてください。
会社の成り立ちや初期の挑戦について、どのような経験がありますか?
会社が過去に直面した主な課題と、その解決方法について教えてください。
会社の成功事例として特に印象的なものはありますか?
これまでの成長の中で、最も大きな転機は何でしたか?
御社が現在のような形になるまでの過程で学んだことは何ですか?
これまでの企業文化の変遷について教えてください。
初期の頃から変わった社内の価値観や文化について、どのように感じていますか?
会社の歴史の中で、特に重要な出来事は何ですか?
会社の過去から学んだ重要な教訓を教えてください。
企業の現在に関する逆質問
企業の現状や直近のプロジェクトなどに関する質問は、タイムリーな関心を示すことができます。
たとえば「現在力を入れている商品や事業は何か」など、ニュースやIR資料を踏まえて質問すると、情報収集力と理解度の高さを評価されやすくなります。
例文
現在、御社の最も注力している事業やプロジェクトは何ですか?
会社が現在抱えている最大の課題は何ですか?
今の組織体制について、どのように感じていますか?
競合他社と比べて、御社の強みはどのような点ですか?
現在の業績や市場でのポジションについて、どのように捉えていますか?
御社が現在進めているイノベーションや改善点について教えてください。
社内の文化や価値観は現在どのようなものですか?
現在、どのような新しいテクノロジーやツールを導入していますか?
チームの構成や雰囲気について、どのような特徴がありますか?
現在の業界の競争環境について、どのように感じていますか?
企業の未来に関する逆質問
今後の事業展開やビジョンに関する質問は、長期的な視点を持っている印象を与えられます。
「中期経営計画で掲げている○○は、現場レベルではどのように進んでいるのか」など、具体的な内容に踏み込むと好印象です。
例文
これからの5年間で、どのような目標を掲げていますか?
未来の市場における御社の位置づけをどのように見ていらっしゃいますか?
新しい事業展開を考えている分野はありますか?
未来のテクノロジーや業界動向にどのように対応していくつもりですか?
御社の未来に向けたビジョンや目標について、どのように考えていますか?
今後、どのような成長戦略を採用していく予定ですか?
御社の業務の進化に合わせて、社員にもどのような変化が期待されていますか?
未来の事業展開において、どのような役割を担うことができると考えていますか?
未来の市場における競争優位性をどのように確保しようとしていますか?
長期的に見た時、御社の最も大きな強みは何だと思いますか?
チームや働き方に関する逆質問
チームの雰囲気や働き方に関する質問をすることで、協調性を重視している人柄をアピールできます。
たとえば「新人が馴染みやすい環境か」「チームで大切にしている価値観」などを尋ねると、周囲と協調して働ける印象を与えられます。
例文
チームでのコラボレーションはどのように行われていますか?
部署間でのコミュニケーションはどのように取られていますか?
社内で最も大切にされている価値観や文化は何ですか?
リモートワークやフレックス勤務について、どのような方針がありますか?
チームメンバーの多様性について、どのように考えていますか?
チームのパフォーマンスを最大化するための取り組みは何ですか?
御社で働く上で、最も大切にしている働き方は何ですか?
部署内の雰囲気やチームワークについて教えてください。
御社でのワークライフバランスの取り方について、どのような方針がありますか?
新しいメンバーのチームへの適応をサポートする方法はありますか?
仕事の内容に関する逆質問
配属先での業務内容や一日の流れなどを尋ねると、具体的な関心があると伝えることができます。
「入社後すぐに任される仕事は何か」「未経験からでも取り組みやすい業務はあるか」など、現場への理解を深める姿勢が伝わります。
例文
1日の典型的な業務内容はどのようなものですか?
このポジションで最も重要な業務は何ですか?
チーム内でのコミュニケーションはどのように取られていますか?
この役職で最もやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?
業務において一番チャレンジングな部分は何ですか?
新たに提案される業務改善策について、どのような流れで決定されますか?
仕事の優先順位はどのように決定されますか?
部門内での業務分担や役割分担はどのようになっていますか?
特に重要な業務に対して、どのようなサポートがありますか?
業務の進捗管理はどのように行われていますか?
会社の価値観や文化に関する逆質問
企業理念や文化に関心を持った質問は、企業研究を丁寧に行っている証として高評価に繋がります。
「企業文化の中で大切にしている考え方」「社員間で共有されている価値観」などを質問すると、共感を示すことができます。
例文
御社の企業文化で最も大切にしている価値観は何ですか?
社内の価値観や文化が形成された背景について教えてください。
社内で一番重視されている行動規範は何ですか?
御社のリーダーシップスタイルについて、どのように考えていますか?
社員間での意見交換やフィードバックの文化について教えてください。
御社が大切にしている「働きがい」とはどのようなものですか?
チーム内でのサポートや協力の文化はどのように確立されていますか?
社内イベントやチームビルディング活動はどのようなものがありますか?
御社の社風において、最も誇りに思う部分は何ですか?
会社の文化が社員に与える影響について、どのように感じていますか?
成果や評価に関する逆質問
成果がどう評価されるかを尋ねることで、仕事に対して意欲的に取り組む姿勢を伝えることができます。
「個人の努力はどのように評価されるのか」「定量的な評価と定性的な評価の割合」などを聞くと、結果にこだわる姿勢が伝わります。
例文
目標設定と成果の評価基準について教えてください。
社員の成果をどのように評価し、反映させていますか?
成果主義とチームワークのバランスはどのように保たれていますか?
評価は定期的に行われるのでしょうか?
過去の社員の成功事例を教えてください。
パフォーマンスに応じた報酬やインセンティブ制度について教えてください。
評価プロセスにおけるフィードバックの頻度や内容はどのようになっていますか?
社員のキャリアアップに向けたサポート体制はどうなっていますか?
評価の透明性はどのように確保されていますか?
社員がモチベーションを維持するための取り組みはどのようなものがありますか?
【集団面接で逆質問】逆質問は複数用意しておこう!
いかがでしょうか?
グループ面接において、 周りとの差をつけるためには「逆質問」がいかに重要であるかが理解できたかと思います。
これまで逆質問を上手くできなかった人も上記のポイントを理解して質問をすれば、相手に好印象を残すことができるようになります。
グループ面接を突破するためには、他の就活生との差をアピールすることが大切です。
その点においても、 逆質問をいくつか用意しておくことで、どんな場面でも緊張せずに行うことができるようになります。
逆質問を複数用意しておけば、他の就活生と質問が被らないだけでなく、面接官の人柄や面接での話の流れに応じて対応することができます。
ぜひこれからグループ面接を受ける方は、参考にしてみてください。