
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
食品関係の仕事に就きたいと考えている学生の中には、食品商社を本命の就職先と考えている人も多いでしょう。
すでに気になっている企業がある、という学生もいるかもしれません。
そんな学生のために、
食品商社とは?
商社とは生産者やメーカー、小売店との間の取り引きを仲介し、その手数料を得て商売をしている企業のことです。
商社には特定の分野にこだわらずに様々な商品の仲介をする総合商社と、ある特定の分野の商品だけを取り扱う専門商社の2つがありますが、食品商社は食品だけを扱う専門商社になります。
海外や国内で生産された原料を生産者から買い取ってメーカーに販売し、メーカーが製造した商品を小売店に販売するのが主な仕事です。
これをトレーディング業務と言います。
ただし、近年ではインターネットの普及などによりメーカーや小売店が商社を介さずに、直接取り引きを行うケースが目立つようになってきました。
そのため、食品商社の中には自ら仕入れた原材料を使って、自社商品を開発し、製造・販売ルートに乗せるところまでを生業とする企業も増えてきています。
食品商社の役割は?
食品商社は、食品の流通を支える重要な存在です。
原材料の調達から加工・物流、販売まで、食品が消費者のもとに届くまでの一連のプロセスに関わっています。
ここでは役割を詳細化して解説していきます。
食品商社の最も基本的な役割は、食品の原材料を調達することです。
国内外の生産者やメーカーと取引を行い、安定的に食材を供給できるようにしています。
食品は天候や季節に左右されやすいため、一つの供給元に依存するのではなく、複数の仕入れ先と取引を行い、供給のリスクを分散させています。
また、消費者のニーズに応じた高品質な原材料を確保するために、生産地の選定や品質管理にも力を入れています。
食品商社は、調達した原材料を適切に管理し、加工・配送を行う役割も担っています。
食品の種類によっては長距離輸送が必要になるため、鮮度を維持するための冷蔵・冷凍技術を活用した物流システムが不可欠です。
例えば、大手食品商社は全国に倉庫を配置し、小売店や飲食店へ迅速に供給できる体制を整えています。
また、単に原材料を輸送するだけでなく、食品メーカーや小売店のニーズに応じて、原材料の一次加工やパッケージングを行うこともあります。
食品商社は、仕入れた食品や加工食品を小売店や外食産業へ販売する役割も担っています。
単に商品を卸すだけでなく、市場のトレンドを分析し、消費者のニーズに合った食品を提案することが求められます。
例えば、健康志向の高まりに伴い、低カロリー食品やオーガニック食品の需要が増えている場合、食品商社はそうした商品をいち早く取り入れ、小売店に提供します。
また、食品メーカーや飲食チェーンと協力し、新商品の開発やマーケティング戦略の立案にも関与することがあります。
食品商社のビジネスモデルは?
これからは食品商社のビジネスモデルについて解説します。
商社のビジネスモデルとしては主に、トレーディングと事業投資があります。
食品商社のビジネスモデルとして、まず一つ目はトレーディングがあります。
商社は商品を売りたい企業と商品を買いたい企業の間に入る仲介役のような役割を担います。
具体的には海外や国内で生産された原料を生産者から買い取ってメーカーに販売し、メーカーが製造した商品を小売店に販売するのが主な仕事です。
これをトレーディング業務と言います。
ただ1990年以降、商社のトレーディング業務は減少傾向にあります。
事業投資とは他社に投資を行い、その企業の価値向上とともに利益を得る仕組みです。
商社が伸びそうだと考えた企業の株式を買収することで事業投資を行います。
有名な事業投資としては、コンビニエンスストアなどがあります。伊藤忠商事はファミリーマート、三菱商事はローソンなどそれぞれの商社が事業投資を行っています。
またコンビニ以外にもエネルギー事業や金属資源事業もあります。
具体的な仕事内容
食品商社への就職を希望しているならば、業種への知識だけでなく、職種に関しての知識も深めるようにしましょう。
同じ企業であっても職種によって働き方ややりがいがまったくと言っていいほど異なるからです。
また、仕事のミスマッチを減らして早期離職を予防するという意味でも、職種を詳しく知ることは非常に役に立ちます。
食品商社での仕事内容は主に「営業」と「事務」「事業企画」の3つに分けられるので、ここでは両者について詳しく見ていくことにします。
食品商社の職種として中心になるのは営業職になるでしょう。
より価格が安くて品質が高く、安全な原料を手に入れるために国内・国外を飛び回って新しい仕入先を開拓したり、自社の取り扱う商品を少しでも多く販売してもらえるように、小売店に売り込みを行ったりすることで、業績に貢献するのが仕事の目的になります。
効率的にクライアントを回るために最短のルートでの移動を心がけ、クライアントの心を打つ訴求力の高いプレゼン資料を準備するなど、結果を出すためには大きな努力も必要となります。
その結果としてコンビニやスーパーなどに自社の商品がズラッと陳列されたところを目の当たりにすれば、大きなやりがいを感じるでしょう。
事業企画とは事業を新しく立ち上げる際に、企画の立案を行う職種です。具体的な仕事内容は様々です。
主な仕事内容は、そのような企業と取引するのか具体的な計画を考えます。また自社の事業計画について考えることがあり、企業戦略も考えることがあります。さらに他社の事業計画を考えるといった、コンサルティングの業務まであります。
そのため。この職種は最新の市場のトレンドを把握する能力や、企業の将来性を見抜く力などが求められるでしょう。
食品商社の事務職には一般事務と営業事務の2つがあります。
・一般事務一般事務は総務部や人事部などで働く社員のことで、会社経営に関する帳簿の管理や決算資料の作成や補助、社員の管理や福利厚生制度の促進、社内衛生管理や備品管理などに従事する人たちのことです。
外部の取引先相手の仕事というよりは、社内向けの業務が主となります。
・営業事務営業事務は営業職の社員のサポートを行うのが主な仕事内容です。
営業職の社員が効率的にクライアントと打ち合わせできるようにスケジュール管理を行ったり、クライアントの情報を管理・分析して効果的なプレゼンができるように戦略を定めたり、営業職社員に代わって資料を作成したりします。
クライアントのデータを入力して顧客管理を行ったり、電話やメールの対応に当たったり、郵便物等の発送を行ったりすることもあります。
一般事務よりも業績に貢献しているという実感が強く、やりがいも大きなものとなります。
総合商社と食品商社の違い
総合商社と食品商社の違いとして、扱う分野の幅が違うということが挙げられます。
総合商社は様々な分野を扱う一方、食品商社は食品関連の分野に特化している点が特徴で、エネルギー、金属、化学品、機械、インフラ、生活産業など、多岐にわたる事業を展開しています。
一方、食品商社は、食品の原料調達、加工、流通を中心に事業を展開しています。
農産物、水産物、畜産物、飲料、加工食品など、消費者の需要に応じた商品を国内外から調達し、メーカーや小売業者に供給する役割を担います。
食品メーカーとの違い
食品商社と食品メーカーについて、その違いがわからない人も少なくないでしょう。
どちらも製品を販売するという意味では同じですが、厳密にいえば大きく異なる企業です。
例えば食品メーカーの場合、自社で商品を企画して生産、そして販売までおこなっています。
一方で食品商社の場合は、あくまでも既存の商品を調達してから販売しているのがポイントです。
ちなみに、食品商社によっては、プライベートブランドとしての商品を製造しているケースもあります。
しかし、一般的な食品メーカーほどの製造量には満たないため、商品の企画や開発に大きく関わりたい人の場合は、食品メーカーを志望した方が良いでしょう。
そのため、食品商社の役割は、あくまでもメーカーと小売業者を結ぶ立場だと思っておいてください。
【食品商社】商社にはどんな種類がある?
食品を扱う商社にも様々な種類があるということを知らない人もいるのではないでしょうか。
実は専門商社だけではなく他の商社も食品を扱っているので、それぞれの種類について一緒に確認していきましょう。
総合商社
総合商社は世界中から様々な食料品を調達し、グローバルな供給網を通じて、流通させています。
代表的な総合商社には三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、双日、豊田通商などがあります。
いずれも、生活産業グループや食料本部など、食品関連事業専門に扱う部門を設けています。
農産物や水産物、肉類、加工食品など幅広いカテゴリーの商品を取り扱い、生産者から消費者までのサプライチェーンを構築し、効率的な流通システムを提供しています。
国際貿易の促進、新たな食品の開発と市場への導入、食品安全性の確保や、持続可能な食品供給の支援なども含まれています。
グローバルな視点を持ち、多様なリソースとネットワークを活用して世界中の人々に高品質で安全な商品を提供するために取り組んでいるのが特徴であると言えるでしょう。
総合商社系専門商社
総合商社系専門商社は、総合商社の食料品部門を母体として設立された食品の専門商社です。
総合商社が構築したバリューチェーンの特定の過程を担当する商社です。
代表的な総合商社系専門商社には、丸紅食品、住商フーズ、物産フードサービス、三菱ケミカルフーズ、伊藤忠食品などがあります。
総合商社の広大なネットワークと資源をバックとして持ちながら、特定の食品カテゴリーやニッチな市場にアプローチすることができるので、より専門的なサービスを提供していることが特徴です。
食品産業の効率性を高め、消費者の多様なニーズに応えるために、グローバルな視野を持ちつつ、地域や特定市場のニーズに対応しているのが特徴です。
独立系専門商社
独立系専門商社は、総合商社などと異なり、独自の形態として特定の食品市場に特化し、その分野で深い専門知識とネットワークを構築しているのが大きな特徴です。
代表的な独立系専門商社には、国分グループや加藤産業などが挙げられます。
特定の食品カテゴリーや流通に焦点を当てて、メーカーから小売業者、消費者までを結ぶ独自の供給網を持っているのが特徴です。
柔軟性と市場への深い理解が強みであり、独自のリサーチや市場分析を行い、消費者のニーズやトレンドに迅速に対応する能力も有しています。
また、地域密着型のサービスを提供していることもあり、地域社会との強固な関係を持っており、地域経済の活性化に寄与しているのも大きな特徴であると言えるでしょう。
【食品商社】向いている人・向いていない人
食品系の商社には個人の性格によって、向いている人・向いていない人がわかることがあります。そのため食品商社の就職を考えている人は、これから紹介する向いている人と向いていない人の特徴から自身の適正を考えてみてください。
向いている人
ここでは食品商社に向いている人の特徴を紹介します。自身に適正があれば、仕事で活躍することができるでしょう。食品商社を受けようか迷っている人は参考にしてください。
まず食品商社に向いている人の特徴として、「食」に対しての興味が強い人が挙げられます。
ほとんどの業務で「食」に携わるため、食に興味がない場合は苦痛に感じる可能性が高いです。例えば外食をする際はいろいろ吟味して決める人、食品を選ぶ際に原材料などにこだわりがあるという人は向いていると言えるでしょう。
また「食」に対しての興味が強い人は自身の職に対する知識を深めることができます。
食品商社はビジネス構造的に生産者と販売者の仲介役として仕事をします。
そのため食品商社で働く場合、生産者や販売者など様々な属性の人とコミュニケーションを取らなければなりません。生産者と販売者の間に入って仕事を行うため、両者に不利益が生まれないようにコミュニケーションを取る必要があります。
向いていない人
ここでは食品商社に向いていない人の特徴を紹介します。食品商社を受けようか迷っている人は参考にしてください。
まず食品商社に向いていない人の特徴として、「食」にあまり興味がない人が挙げられます。
食に興味がない人には向いていません。仕事中は食品のことについて考える時間が長いため、興味がない場合、おもしろくないと感じる可能性があります。
給料が高いから、という理由で志望する人もいると思いますが、仕事内容もしっかり調べるようにしましょう。
次に食品商社に向いていない人の特徴として、コミュニケーションに自信がない人が挙げられます。
前述の通り、食品商社は生産者や販売者など様々な人とコミュニケーションを取ります。そのためコミュニケーションが少ない仕事をしたい、黙々と作業したいなどと考えている人は向いていないといえます。
ただコミュニケーション能力は後天的に鍛えることができるので、コミュニケーション能力を向上させたいという人は問題ないでしょう。
【食品商社】求められるスキル
食品商社で活躍するためには、専門知識だけでなく、変化の激しい市場に対応できる多様なスキルが求められます。
海外との取引も多いため、語学力はもちろんのこと、国内外の食文化やトレンドを深く理解する探求心も不可欠です。
また、多くの関係者と円滑にビジネスを進めるための、高度なコミュニケーション能力も重要視されます。
さらに、予期せぬトラブルにも冷静に対処し、最善の策を導き出す課題解決能力も、日々の業務で常に試されるスキルと言えるでしょう。
語学力
食品商社における語学力は、単に言葉を話せるだけでなく、ビジネスを円滑に進めるための重要なツールです。
特に、海外のサプライヤーとの交渉や、現地の食文化・市場をリサーチする際には、英語や中国語などの語学力が不可欠となります。
現地の担当者と直接コミュニケーションをとることで、より良い条件での仕入れや、新たな商品の発掘につながる可能性が広がります。
また、海外の展示会に参加したり、現地の工場を視察したりする機会も多く、語学力は情報収集の質を大きく左右します。
文化や習慣の違いを乗り越え、信頼関係を築くためにも、相手の言葉で対話できる能力は大きな強みとなるのです。
将来的に海外駐在などを視野に入れる場合、その重要性はさらに増すでしょう。
コミュニケーション能力
食品商社では、社内外の多様な人々と関わるため、コミュニケーション能力が極めて重要です。
生産者やメーカー、国内外のサプライヤー、そして商品を届ける小売店や飲食店など、多くのステークホルダーとの連携が欠かせません。
それぞれの立場や要望を正確に理解し、Win-Winの関係を築くための交渉力や調整力が求められます。
例えば、生産者には品質へのこだわりを伝え、小売店には商品の魅力を的確にプレゼンテーションする必要があります。
また、社内の営業、物流、品質管理といった他部署とのスムーズな連携も、ビジネスを成功させる上で不可欠です。
相手の意図を汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝えることで、信頼関係を構築し、円滑な取引を実現します。
課題解決能力
食品商社の仕事は、常に予期せぬ課題と隣り合わせです。
天候不順による原料の不作、輸送中のトラブル、為替の変動、食の安全に関わる問題など、様々なリスクが潜んでいます。
こうした問題が発生した際に、冷静に状況を分析し、原因を特定する能力が求められます。
そして、代替案の提案や関係各所との迅速な調整など、被害を最小限に抑えるための具体的な解決策を立案し、実行に移さなければなりません。
例えば、ある食材の輸入が滞った場合、代替となる供給元を迅速に探し出し、品質やコストの交渉をまとめるといった対応が必要です。
過去の事例やデータに学びつつも、前例のない問題に対して柔軟な発想で立ち向かう力が、ビジネスの継続性を支えるのです。
【食品商社】具体的な企業11選
ここでは食品商社の中でも事業規模が大きく、学生からの人気も高いトップ3の企業について詳しく見ていきます。
食品商社への就職を目指すならば企業研究を徹底し、企業ごとの特徴や強み・弱み、将来的な事業展開の見通しなどの違いをしっかりと理解しておきましょう。
「なぜ食品商社の中でこの会社でなければならないのか」を説明できるようになれば、面接で志望動機を尋ねられた際に魅力的な回答ができ、採用担当者からの評価も高くなります。
・三菱食品株式会社
・加藤産業株式会社
・伊藤忠食品株式会社
・株式会社日本アクセス
・国分グループ本社株式会社
・三井食品株式会社
・ヤマエ久野株式会社
・スターゼン株式会社
・西本Wismettacホールディングス株式会社
・株式会社トーホー
・株式会社ラクト・ジャパン
三菱食品株式会社
食品商社の中でもっとも事業規模が大きいのが三菱食品株式会社です。
景気の影響を受けやすい食品会社ですが、長年安定した業績を残しています。
2011年に菱食、明治屋商事、サンエス、フードサービスネットワークの4社が経営統合して誕生した三菱グループの連結子会社で、売上高はおよそ2兆5,000億円となっています。
業界2位の加藤産業株式会社の売上高が1兆円ほどですから業界ダントツのトップ企業と言えるでしょう。
社員数は4,400人と多く、採用は総合職のみで職種による区別はありません。
入社後に事務や営業、マーケティングなどの職種に配置されますが、給料などに差はありません。
社員の平均年齢は43.6歳、平均年収は663万円となっています。
・社員数は4,400人
・社員の平均年齢は43.6歳
・平均年収は663万円
加藤産業株式会社
加藤産業株式会社は兵庫県西宮市に本社を置く、独立系の食品商社です。
業界では第2位の事業規模を誇り、売上高は1兆円となっています。
トップの三菱食品株式会社があらゆるジャンルの食品を、バランス良く取り扱っているのと比べると、加藤産業株式会社はインスタント食品や冷凍食品の売上高が、他のジャンルに比べて高くなっているのが特徴です。
社員数はおよそ1,000人、社員の平均年齢は40.2歳で、平均年収は647万円と三菱食品株式会社と比べても遜色ありません。
食品商社は原価率が高いためどうしても利益率が1%以下と低くなりがちですが、加藤産業株式会社は売上経常利益率が1.5%と業界内でも高くなっていることが平均給与が高い理由でしょう。
・社員数はおよそ1,000人
・社員の平均年齢は40.2歳
・平均年収は647万円
伊藤忠食品株式会社
伊藤忠食品株式会社は大阪市中央区と東京都港区に本社を置く食品商社です。
企業名を見ても分かるように、総合商社である伊藤忠商事の子会社です。
伊藤忠商事との関係からコンビニエンスストアのセブン-イレブンや、スーパーのイトーヨーカドーとの取り引きが多く、食品商社としては3番目の規模の売上高6,600億円を誇ります。
同業他社と比べると健康食品の取扱高が多く、また、食品ロスの解消に積極的に取り組むなど、新しい価値の創造に力を注いでいるのが特徴です。
伊藤忠食品株式会社の社員数はおよそ1,000人で、社員の平均年齢は41.8歳となっており、社員の平均勤続年数は上位2社を上回る18年です。
平均年収は635万円で、従業員1人あたりの営業利益は業界トップとなっています。
・社員数はおよそ1,000人
・社員の平均年齢は41.8歳
・平均年収は635万円
株式会社日本アクセス
株式会社日本アクセスは、これまで数々の統合や合併を繰り返して事業を拡大させてきた、日本の食を支える食品総合卸業者です。
また、株式会社日本アクセスは厳密にいうと、こちらも伊藤忠商事のグループ企業として活躍しており、売上高は2兆1976円になっています。
基本は卸売業をやっているのがポイントですが、最近では家庭での食品ロスを少しでも減らすために、新製品開発を進めているのが大きな特徴です。
日本アクセスではSDGsを意識した活動をしているため、製品開発に加えてECを活用しながら過剰になった商品を極力無駄にしないように、さまざまな消費者に向けて直接販売しているところも見逃せません。
なお、従業員の平均年齢は41.7歳で、平均年収は717万円になっています。
人によっては900万円以上稼ぐこともあるため、十分な高収入を狙うこともできるでしょう。
・従業員の平均年齢は41.7歳
・平均年収は717万円
国分グループ本社株式会社
国分グループ本社株式会社は、酒類食品卸売業として長年事業を展開する企業です。
常に「食のマーケティングカンパニー」であり続けることを意識し、さまざまなパートナーと連携してきました。
貿易事業に関しては輸出専門部署で、多くのメーカーが取り扱う食品や酒類を、海外へと輸出しています。
ちなみに、食品総合商社としては前述した伊藤忠商事系の株式会社日本アクセスに続いて、売上高は1兆9330億円で全国3位になっているのが大きな特徴です。
従業員の平均年齢は43.3歳、平均年収はおよそ823万円になっています。
・平均年齢は43.3歳
・平均年収はおよそ823万円
三井食品株式会社
三井食品株式会社は、東京に本社を置く総合食品卸売業です。
国内外問わず、すでに2500社以上のメーカーから商品を仕入れ、全国各地の外食産業や小売店などに、商品を販売しています。
売上高は6643億円となっており、三井物産グループの食品事業における中核機能を果たしているのがポイントです。
三井食品では何よりも「人」を大切にすることを考え、社内のスタッフ同士はもちろん社外のクライアントとも、常に円滑なコミュニケーションを心がけています。
そのため、協調性がありかつ積極的に何でも行動できる人ほど、相性の良い企業だといえるでしょう。
ヤマエ久野株式会社
ヤマエ久野株式会社は、福岡県に位置する九州でナンバー1といわれる食品商社です。
主に小麦粉や酒類、加工食品などを仕入れたり、農産物の加工や弁当惣菜の製造までおこない、さまざまな小売店に販売しています。
一般的な商社のように販売ルートがあるだけではなく、九州ならではの特性を理解した上で、独自の戦略を練られるようになっているのが大きな特徴です。
そのため、どこでどんな商品が売れるのかもすべて把握できているのが、ヤマエ久野株式会社における最大の強みといって良いでしょう。
なお売上高は4380億円で、従業員の平均年齢は39.9歳、平均年収は618万円となっています。
もし九州地方で食品商社を探している場合は、こちらの企業を検討してみるのも良いでしょう。
・平均年齢は39.9歳
・平均年収は618万円
スターゼン株式会社
スターゼン株式会社は、東京に位置する食品商社です。
主に食肉に関する強みを持っているのが特徴で、外食産業や小売店に販売するだけではなく、自社内でも食肉を製造したり加工したりしています。
そのため、食肉について興味関心がある人ほど、相性の良い食品商社になるでしょう。
売上高は4251億円で、すでに3000社以上もの取引先を開拓している有名な商社といっても過言ではありません。
なお従業員の平均年齢は39歳で、平均年収は648万円です。
国内だけではなくアメリカやシンガポールなど、さまざまな国にも輸出実績があるため、グローバルに活動したい人にとっても、ベストな食品商社だといえるでしょう。
・平均年齢は39歳
・平均年収は648万円
西本Wismettacホールディングス株式会社
西本Wismettacホールディングス株式会社は、アジア食品を世界に展開している食品商社です。
創業から100年以上の歴史があり、欧州や豪州などに存在する日本食レストランを中心に、さまざまな食品を輸出しています。
海外では日本食のニーズが高くなってきているため、これからもますます成長する可能性のある食品商社といえるでしょう。
なお売上高は2752億円で、従業員の平均年齢は41.4歳、平均年収は1074万円となっています。
こちらも世界規模で仕事がしたい人にとって理想的な環境が整っているため、検討する価値ありです。
・平均年齢は41.4歳
・平均年収は1074万円
株式会社トーホー
株式会社トーホーは、兵庫県に位置する食品商社です。
ここ12年の間に36社ものM&Aをおこなっているのが特徴で、順調に売上が伸びています。
従業員もM&Aによって1500人以上増え、今後も将来性のある大きな企業だといえるでしょう。
なお直近の売上は2155億円で、従業員の平均年齢は42.5歳、平均年収が520万円となっています。
業務用食品専業卸売事業においては国内売上ナンバー1を誇るため、実績のあるところで頑張りたい人にとっても最適な食品商社でしょう。
・平均年齢は42.5歳
・平均年収が520万円
株式会社ラクト・ジャパン
株式会社ラクト・ジャパンは、主に乳製品に強みを持つ食品商社です。
同じ業界の中でも専門的分野において活動しており、さらに少数精鋭であるところも大きな特徴だといえるでしょう。
とはいえ、国内で輸入されている乳製品の35%を株式会社ラクト・ジャパンの商品が占めているため、業界内でもトップクラスのシェア率を誇ります。
売上も直近で1474億円まで上るため、今後の成長にも大きく期待できる食品商社です。
また、国内で働いている従業員だけではなく、海外でも駐在員として活動している人もいるのがポイントです。
そのため、総合職として入社した人は、すぐ海外での仕事経験ができる可能性もあるのが魅力的だといえるでしょう。
平均年収は819万円になります。
・平均年収は819万円
年収・売上ランキング
ここからは大手食品商社の年収や売上をランキング形式で紹介します。
食品商社を受けようとしているが、具体的な企業を知りたい人にはおすすめです。
年収・売上ランキング
ここでは食品商社の有名企業の平均年収ランキングを紹介します。先ほど企業ごとに平均年収を紹介しましたが、ここではランキング形式で一目でわかるようにまとめています。
年収ランキング
1位 西本Wismettacホールディングス株式会社 平均年収1074万
2位 国分グループ本社株式会社 平均年収823万円
3位 ラクト・ジャパン 平均年収819万円
4位 株式会社日本アクセス 平均年収717万円
5位 三菱食品株式会社 平均年収663万円
売上ランキング
1位 三菱食品株式会社 売上高:2兆5,000億円
2位 株式会社日本アクセス 売上高:2兆3300億円
3位 国分グループ本社株式会社 売上高:1兆9330億円
4位 加藤産業株式会社 売上高:1兆1170億円
5位 三井食品株式会社 売上高:6643億円
【食品商社】働く魅力や大変な点
具体的な企業名や年収はわかったけど、実際食品商社で働く魅力は何だろうと疑問に思っている人もいると思います。
ここからは食品商社で働く魅力について紹介します。具体的な魅力は、「調達から販売までプロセスに関われる」と「調達から販売までプロセスに関われる」です。これから詳しく解説します。
調達から販売までプロセスに関われる
まず食品商社で働くことの魅力の一つとして、製品の原料調達から販売まで一貫してプロセスに関われるということです。
食品商社は主に生産者と販売者の仲介役を行います。そのため原料の調達から販売までの一連の流れのすべてに関わることができます。
そもそも食品業界では、最初から最後まですべてに関われる会社は少ないです。もし食品業界を志望していて、生産におけるすべてのプロセスに関わりたいと考えている人は食品商社がおすすめです。
身近な食品に関われる
食品商社で働くことのもう一つの魅力として、身近な商品に関われるという点があります。
食品商社で扱うことになる商品は日常生活で使われている場合があります。例えばコンビニエンスストアやスーパーマーケットで買い物をする際などには、自身が食品商社の仕事で関わったことのある商品を目にする機会が多くなるでしょう。
自身が仕事で関わった商品が実際に日常生活で一般の人に役立っていると感じることができるので、それが大きなやりがいに感じることが多いでしょう。
肉体労働がある
食品商社の仕事には、華やかなイメージとは裏腹に、意外と体力勝負な一面もあります。
特に、物流倉庫での検品や在庫管理、展示会でのブース設営や商品陳列などは、体を動かす作業が多くなります。
重い商品を運んだり、長時間立ちっぱなしで作業したりすることもあるため、基礎的な体力は必要不可欠です。
また、営業職であっても、顧客への商品提案のためにサンプルを運んだり、スーパーの売り場作りを手伝ったりすることもあります。
デスクワークだけでなく、現場での作業も厭わないフットワークの軽さが求められる仕事です。
特に若手のうちは、こうした現場での経験を通して、商品知識や物流の仕組みを肌で学んでいくことが重要になります。
仕入れ先と小売店の板挟みとなる
食品商社の営業は、商品の仕入れ先であるメーカーや生産者と、販売先である小売店の間に立つ、重要な架け橋です。
しかし、両者の要望が相反する場合、その調整役として難しい立場に立たされることも少なくありません。
例えば、メーカーは「できるだけ高く売りたい」、小売店は「できるだけ安く仕入れたい」という思いを持っています。
また、品質に対する考え方や、納品ロット、納期など、様々な条件で意見が対立することもあります。
こうした状況で、双方の言い分に耳を傾け、粘り強く交渉し、お互いが納得できる着地点を見つけ出す必要があります。
時には厳しい言葉を投げかけられることもあり、精神的なタフさが求められる、まさに「板挟み」となる大変さがあります。
【食品商社】最新の動向と将来性
食品商社に就職することを考える際に、この業界は本当に大丈夫なのか?安心して働き続けられるのか?など、色々不安になってしまう人もいるかもしれません。
では食品商社業界について、その後の動向を見ていきましょう。
コロナの影響
2020年に入ってから、日本ではコロナによってさまざまな影響が出ました。
外食産業においても大きく需要が落ち込み、しばらくの間は自宅で食事をする人も多々いたのが現実です。
そのため、外食産業とも付き合いのある食品商社の売上にも、大きく影響しました。
とはいえ、食品商社の場合は外食産業だけではなく、家庭向けの商品を作っているメーカーとも付き合いがあるため、コロナによって大打撃を受けにくかった企業だといえるでしょう。
DX化が進んでいる
近年のAIの発達により、食品商社でもDX化が進んでいます。
具体的にはAIを活用した需要予測や、受注先の事務作業を自動化して生産効率を上げるなどの取り組みが行われています。
人手不足であった生産者側が自動化によって生産効率を上げたなどという例があります。
今後もこの流れは進んでいくと考えられます。
円安による影響
近年の円安傾向により、海外から輸入するコストが高くなっています。
そのため国産原料への回帰が進んでいます。
食品商社は安定供給するための海外調達戦略を見直し始めており、今後どのような戦略を取るのか注目されています。
将来性
食品商社は、文字通り食品を取り扱う企業です。
食は生きていく上で必要不可欠な存在ですので、将来的に衰退するようなことはまずないでしょう。
だからこそ、安心して働ける業界であることは間違いありません。
ただし、需要が永久的にあるからこそ、競合他社も増えがちになるのがポイントです。
そのため、企業によってはネットワークを拡大するために、M&A戦略をとっているところも少なくありません。
また海外展開もしやすい業界ですので、将来性に関しての心配は特にしなくても良いでしょう。
中小企業の将来性
大手の場合は経営統合によって売上を作る傾向がありますが、中小企業の場合は地域密着型を意識して売上を安定させたり、新規事業を立ち上げて新しい売上を発掘させたりする傾向があります。
そのため、大手企業じゃなくても十分に活躍していけるといえるでしょう。
さまざまな企業を分析して、自分にもっとも相性の良い食品商社を選んでみてください。
【食品商社】Q&A
食品商社は、食品の流通を支える重要な業界です。
しかし、商社という業種自体に激務のイメージを持つ人も多く、労働環境や待遇について気になる方も多いでしょう。
ここでは、食品商社の労働環境や年収に関する疑問について詳しく解説します。
激務って本当?
食品商社は、現地営業や物流管理などの業務が多いため、体力を要する仕事が少なくありません。
特に、営業職では顧客対応のために全国各地を移動することがあり、勤務時間が長くなるケースもあります。
また、荷物の配達や物流業務に関わる場合、早朝や深夜の業務が発生することもあり、体力的に厳しいと感じる人もいるでしょう。
一方で、近年は働き方改革が進み、企業によっては労働時間の短縮やフレックスタイム制の導入が行われています。
企業ごとに働き方に違いがあるため、自分に合った環境を選ぶことが大切です。
平均年収は?
食品商社の平均年収は約500万円とされています。
総合商社と比較すると高いとは言えませんが、日本全体の平均年収と比較すると高い水準にあります。
また、企業規模や職種によっても年収には差があり、大手企業では年収600万円以上を得られる場合もあります。
営業職では、インセンティブ制度を導入している企業もあり、成績次第で年収を上げることが可能です。
一方、事務職や物流管理職では固定給の割合が大きく、年収の伸び幅は営業職ほど大きくはありません。
【食品商社】対策方法や志望動機の例文
ここでは食品商社の選考を受ける人の対策方法を紹介します。
食品商社を受けたいと考えている人はしっかり対策して選考にのぞみましょう。
業界分析を行う
まず面接ではなぜ食品業界を志望するのか、またなぜ商社なのかを聞かれます。
そのため食品業界に対する理解を深めてから選考に臨めば、説得力のある志望動機を言うことができるでしょう。
業界分析を行う際にはインターネットやAIで情報収集するのもよいですが、就活エージェントを利用するのがおすすめです。
プロのエージェントに業界について聞けば、有益な情報を得ることができるでしょう。
企業研究を行う
次に企業研究を行いましょう。
食品業界の中でもなぜ弊社を志望するのか聞かれる可能性が高いです。
食品商社をたくさん受ける予定の方でも、受ける企業一つ一つに対してそれぞれの志望理由を用意しましょう。
企業のHPを見るなどして、それぞれの企業の情報を集めるのが良いでしょう。
就活エージェントを利用する
食品商社への就職を目指すなら、就活エージェントの活用が非常に有効な手段となります。
エージェントは、一般には公開されていない非公開求人を多数保有している場合があります。
そのため、自分一人では見つけられなかった優良企業や、希望に合ったポジションに出会える可能性が高まります。
また、キャリアアドバイザーが、食品商社業界の動向や、各企業が求める人物像について詳しい情報を提供してくれます。
エントリーシートの添削や面接対策など、選考を突破するための具体的なサポートを受けられるのも大きなメリットです。
客観的な視点から自分の強みや適性を見つけてもらうことで、より説得力のある自己PRや志望動機を作成できるでしょう。
複数のエージェントに登録し、自分に合ったアドバイザーを見つけることをお勧めします。
おすすめの志望動機
ここからは食品商社の志望動機をいくつか紹介します。
それぞれ異なる就活生の例文ですが、文章構成や動機のアピールの仕方などが非常に上手いので、是非参考にしてみてください。
また食品商社の志望動機について詳しく知りたい人は下記の記事を参考にしてみてください。
私が食品商社を志望する理由は、人々の生活を支える食の流通に魅力を感じたからです。
幼少期から食に興味があり、大学でも食品科学を専攻し、食材の品質や安全性について学びました。
その中で、食品流通の重要性を理解し、世界中から良質な食材を安定的に供給する仕組みづくりに関わりたいと考えるようになりました。
特に、御社が取り組むフェアトレードやサステナビリティへの意識の高さに共感しています。
私が大学時代に参加したゼミでは、食品廃棄の削減をテーマにした研究に取り組みました。
そこで、サプライチェーンの効率化が食品ロス削減に繋がることを学びました。
また、インターンでは、輸入食品を扱う業務に携わり、国際的な食材調達の難しさと可能性を実感しました。
これらの経験を通じて培った分析力や調整力を活かし、御社で人々に価値ある食品を届けるサポートをしたいです。
私は食品商社を志望する理由として、食文化を世界中に広げる可能性に魅了された点があります。
海外留学中、地元の食材や料理が持つ力を実感し、それを他国に伝える役割を果たしたいと思うようになりました。
特に、御社が手掛けるアジア市場向けの輸出事業に興味を抱いております。
私は大学で経済学を学び、国際貿易の仕組みを研究しました。
ゼミ活動では、農産物の輸出に関するデータを分析し、国際競争力を高める施策について発表しました。
また、アルバイト経験として海外の食品店で働いた際には、多国籍な顧客に向けて商品説明を行い、文化の違いを超えた接客の大切さを学びました。
この経験から、言語や文化の壁を越えて、多様な価値観を結びつける食品ビジネスに挑戦したいという思いが強まりました。
御社の取り扱う幅広い商品ラインナップと、世界中の人々に喜ばれる食品流通に関わる環境で、自分の経験を活かしたいと考えています。
食品商社に興味を持ったきっかけは、大学でのサークル活動を通じて得た、食材の多様性への関心です。
私はフードイベントを運営するサークルに所属し、地域の特産品をテーマにした企画を担当しました。
そこで、地元農家との交流や、輸入食品を活用したメニュー提案に携わり、食の価値を伝える仕事に強く惹かれるようになりました。
御社の展開する輸入食材の事業は、私の関心と一致しており、食材の魅力を広める活動に携わりたいと考えています。
大学で学んだマーケティングの知識を活かし、商品プロモーションのアイデアを実現する力を磨いてきました。
また、地方創生をテーマにしたプロジェクトでは、地域特産品の販路拡大を目的とした施策を提案し、実行しました。
その際に得た企画力と調整力を、御社のグローバルな食品流通事業で役立てたいと考えています。
まとめ
ここまで食品商社の特徴を紹介してきました。
同じ商社でも総合商社と食品商社では仕事の内容や取り扱う商品が全く異なることが分かっていただけたかと思います。
最近は海外から安くて品質の良い食品が大量に輸入されるようになり、市場を取り巻く環境も刻々と変化しており、常に激しい競争にさらされています。
食品商社への就職を目指す学生はそれぞれの企業の特徴をしっかりと把握して、自分に合った就職先を見つけるように心がけましょう。
また実際に応募しようと思った方は下記の記事を参考にしてください。








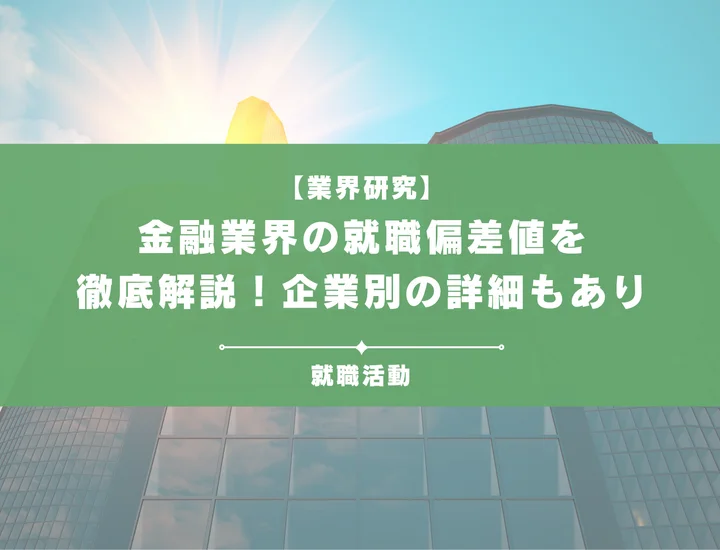






就活コンサルタント木下より
ここでは「食品商社とはどのような会社なのか?」 「社員はどんな仕事をしているのか?」 「食品商社にはどのような企業があるのか?」
など、就職活動を行う上でぜひとも知っておきたい情報を紹介していきます。