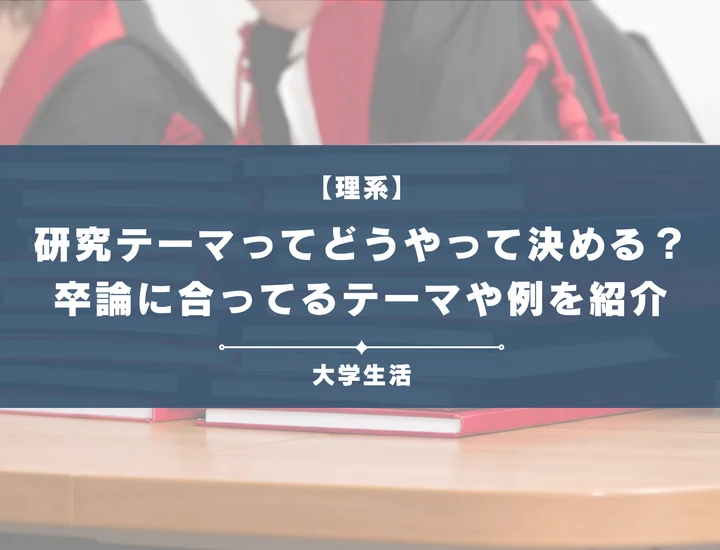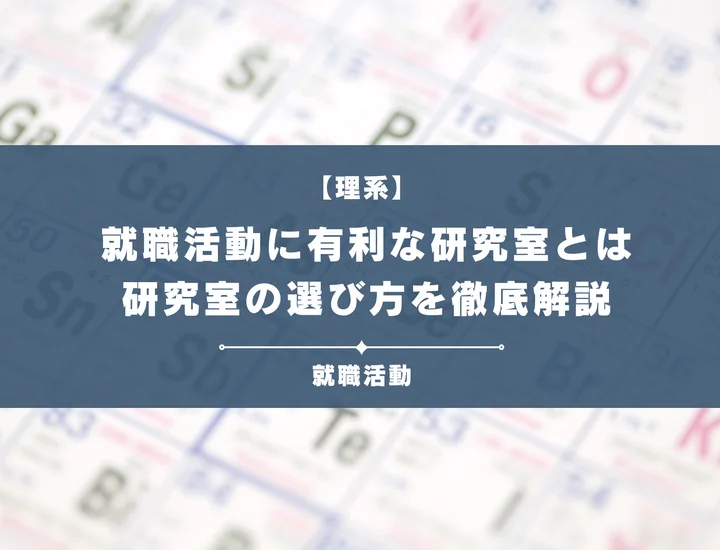HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
大学3年生に上がると、否が応でも進路のことが頭をよぎることになるでしょう。
特に理系の学生は一般企業や専門分野の企業に就職をするのか、それとも大学院へと進むのかの2択を迫られることが多いです。
そんな悩みを抱えている人向けに、今回は大学院に進むメリットやデメリットなどについて解説していきましょう。
【理系は院に行くべき?】大学院はどんなところ?
大学院とは、大学で学んだことをさらに深く学んで、研究を行う場所です。
大学とは違い、大学院は2年間だけ学び、そこで修士という学位を貰うことができます。
ほかにも3年、もしくは4年間学んで博士を得ることができる院もありますが、そういった分野は専門性が高い人は研究者としての道を歩むことが多いです。
文科省が発表している「令和元年度学校基本調査」によると、理学や工学系の生徒の大学院進学率は、ここ数年40%前後を推移しており、進学率は比較的高いことがわかります。
しかし、これは全大学を対象にしているため、実際の進学率は大学によって大きく変わってくるでしょう。
学部と大学院の違い
大学院は学部で身につけた知識をさらに深め、自ら研究を進める場所です。
学部では幅広い教養と専門分野の基礎を学び、講義や実習を通して知識を身につけます。
これに対して大学院では特定の研究テーマを中心に、自分で課題を見つけ、解決策を考えながら研究を進めます。
授業を受けるだけではなく、自分の手で実験や解析を行い、新しい成果を生み出す姿勢が求められます。
学生は研究室に所属し、指導教員のもとでテーマを設定して論文や学会発表を目指します。
日々の活動は講義中心から研究中心へと大きく変わり、時間の使い方も自分の裁量が大きくなります。
自ら計画を立てて実験や調査を進めるため、主体性と責任感が必要です。
学部で学んだ知識を基盤に、未知の課題に挑む力が育つことが大学院の最大の特徴です。
修士課程と博士課程の違い
大学院には主に修士課程と博士課程があります。
修士課程はおよそ二年間で、専門分野の知識を深めつつ研究を行い、その成果を修士論文としてまとめます。
理系では多くの学生が修士課程に進学し、企業への就職を目指します。
企業は修士修了者を高度な専門知識を持つ人材として評価するため、研究職だけでなく開発や技術職など幅広い職種で有利に働きます。
一方、博士課程は修士課程を修了した後さらに三年間研究を続け、自立した研究者として新しい知見を発表することが求められます。
学会での発表や国際的な論文執筆を通じて、世界に向けて成果を示す力が必要です。
博士課程を修了すると大学教員や国公立研究機関の研究職、企業の高度専門職などに進む道が開けますが、修士課程に比べて求められる責任と研究成果のレベルは一段と高くなります。
理系学生にとっての大学院の位置づけ
理系分野では大学院進学が専門性を磨く重要なステップと考えられています。
化学や生物、物理、情報科学、材料工学など多くの分野では、学部卒だけでは研究や開発に必要な知識が不十分とされることが多く、修士課程まで進むのが一般的です。
研究活動を通じて問題を発見し、解決する経験を積むことで、論理的な思考力や実験計画力、データ解析力など社会で役立つ力が身につきます。
また、企業は大学院での研究経験を評価し、採用時に修士修了を条件とする場合もあります。
博士課程に進めば国際的な研究者として活躍する道が開けますが、研究職に限らず企業の先端開発や高度な技術職など挑戦できる領域も広がります。
大学院は単に学問を深める場にとどまらず、専門性と実践力を兼ね備えた人材へ成長するための大切な舞台となっています。
【理系は院に行くべき?】院に進むメリット
大学の4年間に加えて、さらに2年間を学びや研究に費やす大学院ですが、院に進むメリットは何でしょうか。
ここでは理系の学生が大学院へと進むメリットについて紹介していきましょう。
大手企業に就職できる
「令和元年度科学技術要覧」によると、「日本の企業の産業別研究者数割合」は下記の通りになっております。
ほかにも電気機械器具製造業や化学工業なども、それぞれ7%超えの割合を閉めており、研究者の割合が高い分野というのはその分、就職しやすい業界と言えます。
さらに「日本の企業の専門別研究者数割合」は、以下の通りです。
このように2つの分野が全体の半分を占めており、機械系及び電気通信系の企業は研究者の需要が高いようです。
大学院生の就活については、こちらの記事でご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
学校から推薦を受けやすい
大学院に進むと学校側から企業推薦を受けやすいというメリットがあります。
学校側から貰える推薦には教授推薦と学内推薦の主に2種類がありますが、共に研究をした教授が研究内容に合わせた企業を推薦してくれる場合もあるのです。
また、企業の研究職以外にも国営などの公的機関の研究所でも新卒採用というのは、毎年行われています。
たとえば、自衛隊の防衛装備の研究と開発を行っている防衛装備庁、医薬品や化学の研究を行う国立医薬品食品衛生研究所です。
こういった公的機関への就職は推薦があるほうが圧倒的に有利になります。
ほかにも独立行政法人や非営利団体などの、企業ではない団体もあるなど、選択肢は意外に多いのです。
給料が高い
厚生労働省が発表している「令和元年賃金構造基本統計調整結果(初任給)」によると、学歴別に見た初任給は下記の通りです。
初任給でも、大学を卒業した人と比較しても月に3万円近くの差があります。
また、「令和2年度賃金構造基本統計調査結果」によると、学歴別平均月収は大卒が約39万円、大学院卒が約46万円。
さらに平均月収のピークを比較すると、学部卒で約53万円、大学院卒で約74万円と単純計算で年収に252万円もの差がついています。
年収がピークの年齢に差があるため、一概には言えないですが、それでも大学院卒とそれ以外では賃金に大きな差があることがわかります。
特に30代後半から大学院生と学部卒とで賃金に差が出始めてくるので、2年の学びの差が賃金の差に大きく響いてくるのです。
専門性が高い
大学院に進むことで、大学で学んでいたことよりも、さらに専門性の高い内容を学べます。
そのため、学部卒の人よりも深い知識と高いスキルを得た状態で社会に出ることができるでしょう。
特に専門性の高い企業の研究職となると、即戦力となる人材を求めているケースが多く、大学院で学んだ内容や研究内容を重視する傾向にあります。
その際に、自分が研究してきた内容を説明することで、就職活動を有利に進めることができます。
研究スキルと専門知識が身につく
大学院では、特定の分野を深く掘り下げることで、学部では得られない高度な知識を習得できます。
講義だけでなく、研究室での日常的な実験や調査を通して、最新の研究に触れながら学ぶため、実践力が磨かれます。
論文を読み解き、自分の研究に役立てる力や、実験計画を立ててデータを解析する技術も身につきます。
学部時代に学んだ基礎を土台に、自分で課題を設定して結果をまとめる経験は、どの分野に進んでも役立つ財産になります。
また、指導教員や先輩の指導を受けながら研究を進めることで、専門分野の知識だけでなく、研究を進めるための考え方も身につきます。
こうした経験は、社会に出てからも問題解決や新しい技術の開発に直結する力となります。
論理的思考力・課題解決能力が向上する
研究活動では、未解決の課題に対して仮説を立て、実験や調査を行い、結果を考察するという一連の流れを繰り返します。
この過程は、計画を立てて実行し、評価し、改善するという循環を何度も体験することを意味します。
自分の考えを論理的に整理し、結果をもとに次の手を導き出す力が自然と身につきます。
学部の授業のように答えが用意された課題ではなく、自ら問いを立てる環境に身を置くことで、問題を多角的に捉える習慣が育ちます。
このようにして培われた論理的思考力や課題解決力は、研究者としてだけでなく、企業での開発業務や企画職など、幅広い職場でも求められる重要な能力です。
プレゼンテーション能力が磨かれる
大学院では、研究発表や学会での質疑応答など、自分の研究を他人に伝える場が数多くあります。
専門的な内容を分かりやすく説明するためには、相手の知識レベルを考えた言葉選びや資料作成が必要です。
研究室内での進捗報告や仲間との議論を通じて、自分の考えを簡潔にまとめ、説得力を持って話す力が鍛えられます。
これらの経験は、就職活動における面接や、社会人になってからの会議やプレゼンにも、そのまま活かすことができます。
自分の研究成果を正確かつ魅力的に伝える練習を積むことで、どの職業においても役立つ表現力と対応力が身につきます。
人脈が広がる
大学院では、研究室の仲間や教授に加えて、学会や共同研究を通じて他大学の研究者や企業の技術者など、多くの人と出会います。
同じ分野に興味を持つ人々と交流することで、情報交換や共同研究の機会が生まれ、将来のキャリアに大きな影響を与える人脈が築かれます。
研究室での日々の活動を通じて得られる信頼関係は、学位取得後の就職や転職の際にも心強い支えとなります。
また、指導教員から企業や研究機関を紹介してもらえることもあり、自分では得られない貴重な情報や機会につながります。
このように大学院で築いたネットワークは、研究者だけでなく、一般企業で働く場合にも、大きな財産として生涯にわたって役立ちます。
【理系は院に行くべき?】院に進むデメリット
専門性の高い職業に就けることや生涯的な賃金の面などから大学院に進むことは大きなメリットがあることは明白です。
しかし、メリットだけではなく、大学院に進むことにはデメリットも存在するのです。
そこで、大学院に進む際のデメリットについて紹介していきましょう。
社会に出るのが2年遅れる
大学を卒業してから、さらに2年間学ぶため、当たり前ではありますが就職するが2年遅れることになります。
社会経験における2年の差は大きく、社会におけるマナーやスキルなど同い年の学部卒の人間とは差ができてしまうのです。
もちろん、大学院生時代を研究や勉学に励むことでカバーできる面もあります。
しかし、もし大学院生時代を有意義に過ごすことができなかったら、その差は覆すのが難しい差になる可能性もあるのです。
それを避けるためにも、大学院に進むと決めたのなら将来のために努力し続ける必要があるでしょう。
学費
こちらも当たり前のことですが、大学院に進むということは学費がかかるということです。
学費というのは国立や私立によって異なってきますが国立の場合、法科大学院以外は学費の総額が2年間で約138万円となっています。
これは国立の大学院には「標準額」が定められているため、例外である法科大学院以外の大学院の学費は一律になっているのです。
反面、私立は大学によって大きく変わっていきます。
理系の場合は文系よりも学費が高くなる傾向にあるため、安いところでも2年間で約150万円、高いところでは250万円を超える大学もあるのです。
そのため、私立の大学で大学院に進む場合は、目安として180万円〜200万円くらいは学費でかかると考えておきましょう。
就職につながりにくいテーマの研究もある
理系の研究というのは、何もすべての研究テーマが就職に有利になるわけではありません。
そういった伸び悩んでいる業界の研究やすでに研究し尽くされていると見なされているものを研究したとしても、就職活動につながりにくいのです。
また、研究にも流行りと廃りがあります。
最新の注目を浴びている研究をすれば、その研究内容に興味を抱き手を伸ばしてくる企業も多くあるでしょう。
しかし、あまり注目されていないテーマを研究してしまうと、研究内容に企業も注目しません。
そのため、研究テーマについては教授と共に、よく吟味をする必要があるでしょう。
研究と就活の両立が忙しい
これは大学生にも言えることなのですが、自分の研究と就活の両立というのは想像以上に難しく、就職活動になかなか手が回らないという人もいます。
大学生とは違い、大学院では研究や実験を今まで以上に行って結果を出す必要があるのです。
そのため、朝から晩まで研究室に引きこもっての生活も珍しくなく、それに加えてレポートや論文の作成、教授の仕事を手伝うなどの作業もあります。
学費を稼ぐためにバイトやTAなどをしていると、さらに多忙になることでしょう。
分野によっては分野外の勉強も必要になってくるため、そういった多忙な生活を送りながら就職活動を行う覚悟をしましょう。
大学院生のスケジュールについては、こちらの記事でご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
希望の職種に就けない可能性がある
大学院で研究を重ねても、自分が希望する職種に就けない場合があります。
研究テーマが特定の分野に偏っている場合、その分野を活かせる企業が限られていると求人が少なくなることがあります。
自分の研究内容が専門的すぎると、一般企業の採用条件に合わず選考で不利になる場合もあります。
また、大学院での研究が長期化すると社会に出る時期が遅れ、同年代の学部卒の就職者よりも実務経験で差がつく可能性があります。
このような状況では、研究で得た知識を十分に活かせない職種に就く選択を迫られることもあり、結果として希望していた進路を諦めることになる場合があります。
進学前に自分が目指す職種や業界が大学院での学びをどの程度評価するのかを調べておくことが重要です。
研究テーマと就職先のミスマッチ
大学院で深く取り組んだ研究テーマと、実際に就職する企業で担当する業務が大きく異なることがあります。
例えば、材料工学で新素材の研究をしていても、就職先が営業や管理部門であれば専門知識を活かす機会は限られます。
せっかく時間をかけて専門性を高めたのに、その知識を仕事に直接使えない状況が続くと、努力が無駄になったと感じてしまう人も少なくありません。
さらに、研究を重ねることで自分の興味や得意分野が変わり、就職活動の時期に志望業界が定まらなくなるケースもあります。
このようなミスマッチを避けるためには、研究を始める段階から自分がどのような業界や職種に興味があるのかを意識し、研究テーマを選ぶ際に就職先との関連性を考えることが必要です。
大学院での学びを将来の仕事に結びつけるためには、早い段階から情報収集と自己分析を進める姿勢が欠かせません。
【理系は院に行くべき?】院卒で就活に失敗しないため
大学院に進んだとしても、就職活動に失敗してしまうと元も子もありません。
そこで、就職に失敗しないためのポイントを3つ解説していきましょう。
研究と就活のバランス
研究の没頭しすぎてしまうと、就職活動に取り組む時間がなくなってしまいます。
そのため研究と就職活動のバランスを考えた綿密なスケジュールを組む必要があるでしょう。
就職活動というのは毎年3月1日から広報活動が開始されますので、まずはその前に応募する企業をある程度決めておく必要があります。
人気のある企業というのは広報活動の開始と同時に、応募が殺到することが多く、スタートダッシュに遅れてしまうと後から、致命的な遅れになることも。
それを防ぐためにも、あらかじめ3月1日に向けて研究の進捗状況及び日程の調整を行って、就職活動に対して準備を進めておきましょう。
業界・職種にこだわりすぎない
大学院で研究をしているのなら、自分の研究分野や研究テーマに沿った業界や仕事に就きたいと思うことでしょう。
しかし研究分野や業界によっては、あまりにニッチな業界や職種になることもあり、募集している企業が少ないということもあり得ます。
そうなると、就職活動をしても希望する企業がない、募集している企業が少なくて倍率が非常に高いなど、いろいろと不利な状況になってしまいます。
しかし、自分が研究している分野と業界が異なったとしても、勉強や研究を続けた経験は無駄になりません。
研究によって身についた論理的思考は、どの職場においても役に立ちますし、専門外だからこそ新しい発見もできます。
業界や職種にこだわるあまりに視野を狭くするのではなく、広い視野を持って就職活動に臨みましょう。
院卒の強みを理解する
学部生と大学院生には大きな違いがあります。
学部生というのは高等学校などと同じく、教員から授業を受けるという形で勉学に励みますが、大学院生は自ら進んで研究をします。
いわば、学部生を含めた学生というのは知識を教え込まれるインプット型であり、大学院生は研究して新たな知識を得るアウトプット型であると言えるでしょう。
そのため、学部生よりも院生のほうが論理的思考が身につけやすく、就職後の社会生活において大いに役立つでしょう。
就活のスケジュール管理術
大学院生は研究に多くの時間を割くため、就職活動の準備を後回しにすると計画が崩れやすくなります。
研究発表や実験の予定が入りやすい時期を把握したうえで、いつまでにエントリーや面接準備を終わらせるかを逆算して計画を立てることが大切です。
学会や論文提出の締め切りと就職活動の日程が重なることもあるため、月単位や週単位でやるべきことを整理しておくと余裕を持って動けます。
カレンダーやアプリなどを活用し、研究と就活の両方の予定を一つにまとめて管理すると、抜け漏れを防ぎながら効率的に時間を使えます。
研究室の指導教員や先輩に早めに相談して、面接や説明会の日程を確保するための協力を得ることも重要です。
計画を立てておけば、研究が忙しくても自分のペースで就職活動を進めることができ、精神的な負担も軽減されます。
情報収集の重要性
院卒として強みを生かした就職活動を行うには、多角的な情報収集が欠かせません。
企業の公式サイトや採用ページだけでなく、研究室の先輩や教授からの情報、大学のキャリアセンターが提供する資料などを幅広く活用しましょう。
特に、院卒の採用に積極的な企業や研究内容を活かせる職種は、学部卒向けの一般的な情報だけでは見つけにくい場合があります。
学会や研究会で企業の担当者と直接話す機会を持つことで、最新の採用動向や業界のニーズを知ることができます。
また、研究テーマと関連する分野に強い企業を把握することで、自分の専門をアピールしやすい応募先を絞り込むことが可能になります。
こうした情報を早めに集めることで、志望理由や自己PRを具体的に作成でき、選考で説得力を持たせることができます。
OB・OG訪問の活用法
実際にその企業で働く院卒の先輩に話を聞くことで、仕事の実態や研究内容がどのように活かされているかを具体的に知ることができます。
採用ページだけでは分からない職場の雰囲気やキャリアパスを知ることができ、自分がその環境で活躍できるかを判断する参考になります。
訪問の際は、仕事内容や研究との関連、働きがいなど具体的な質問を準備しておくことが大切です。
質問内容を事前に整理しておくことで、短時間でも有益な情報を得ることができ、相手にも誠実さが伝わります。
また、訪問後はお礼の連絡を忘れずに行い、丁寧な対応を心がけることで、今後の人脈としてつながりが生まれる場合もあります。
OB・OG訪問を積極的に活用することで、志望企業への理解が深まり、自分に合ったキャリアプランをより具体的に描くことが可能になります。
【理系は院に行くべき?】学部卒との違いを理解しよう
大学院に進学するか学部卒で就職するかを考える際には、それぞれの立場に求められる役割や選考方法の違いを理解することが欠かせません。
学部卒と院卒では企業が期待する能力や選考で重視するポイントが大きく異なります。
ここでは学部卒と院卒の違いを四つの観点から詳しく解説します。
求められる役割の違い
学部卒は新卒のポテンシャル採用として、入社後に育成していく前提で採用されます。
一方、大学院を修了した学生は高度な専門性と即戦力を期待される傾向が強くなります。
特に研究開発職では、大学院で培った専門知識や研究スキルを生かして企業の研究活動に貢献することが求められます。
そのため、学部卒よりも入社時点で一定の技術力や論理的思考力を持っていることが前提とされる場合があります。
また、業務に早く適応し成果を出すことが期待されるため、自分の研究内容がどのように企業の事業に役立つのかを説明できる準備が必要です。
このように学部卒と院卒では、入社後の成長を前提とするか、すぐに成果を求められるかという点で大きな違いがあります。
選考フローの違い
学部卒の選考では一般的な面接や適性検査が中心ですが、院卒向けの選考では研究内容を詳しく確認するための独自のフローが設けられることがあります。
専門知識を測るための筆記試験や、研究内容を深く掘り下げる口頭試問が実施される場合もあります。
企業は大学院で得た知識や研究成果が実務にどの程度活かせるかを重視するため、研究背景や成果を分かりやすく伝える力が必要です。
また、面接では研究の進め方や課題解決の過程を具体的に説明できることが評価につながります。
事前に自分の研究を第三者に説明する練習を重ね、専門的な内容を誰にでも理解してもらえるように整理しておくことが重要です。
このように院卒の選考では、学部卒以上に研究に関する深い質問に対応できる準備が求められます。
面接で聞かれることの違い
学部卒の面接では、学生時代に頑張ったことやアルバイト経験など、人柄や潜在能力を確認する質問が中心になります。
一方、大学院生の場合は研究内容が面接の中心となり、研究テーマを選んだ理由や研究の面白さ、苦労した点、成果を企業でどのように活かしたいかを論理的に説明する必要があります。
研究の目的や意義を短時間で分かりやすくまとめるためには、専門用語を避けて日常的な言葉に置き換える工夫が重要です。
また、研究で得た知識やスキルを企業でどのように応用できるかを具体的に話すことで、採用担当者に自分の即戦力としての価値を伝えることができます。
面接準備の段階で、研究の概要や成果を一枚の資料にまとめて説明する練習をしておくと、当日の質疑にも落ち着いて対応できます。
ESの書き方の違い
学部卒のエントリーシートでは、学生時代に力を入れた活動や学外の経験を中心にアピールすることが多くなります。
これに対して院卒の場合は、研究内容をどれだけ分かりやすく、かつ論理的に説明できるかが評価の鍵となります。
専門用語を多用すると採用担当者に内容が伝わりにくくなるため、誰でも理解できる言葉に置き換えて説明することが大切です。
研究の目的、実験方法、成果、そして企業での活かし方を簡潔に整理し、文章の流れが自然になるよう心がけましょう。
また、研究以外の活動についても簡単に触れることで、人柄やコミュニケーション能力を伝えることができます。
研究を中心に据えながらも、社会で必要とされる幅広い力を持っていることを示すことで、院卒としての強みを最大限にアピールできます。
【理系は院に行くべき?】どんな企業が院卒を求めているのか
大学院で研究を重ねた学生は、学部卒にはない専門知識と論理的思考力を持つ人材として多くの企業から注目されています。
近年はメーカーやIT業界だけでなく、コンサルティングファームなど幅広い分野で院卒を積極的に採用する動きが広がっています。
ここでは院卒を求めている主な業界と職種、そして企業が期待するスキルや採用情報の探し方を詳しく解説します。
メーカー(研究開発職)
自動車、化学、電気機器などのメーカーは、研究開発職で院卒を積極的に採用しています。
これらの業界では新製品の開発や既存製品の改良に高度な知識が必要であり、大学院で培った専門性が直接役立ちます。
たとえば材料特性を理解した上で新しい素材を設計したり、電気機器の性能を向上させるための実験を行ったりする場面では、研究で得たデータ解析力や実験計画力が求められます。
学部卒が入社後に基礎を学びながら力をつけていくのに対し、院卒には入社初期からテーマを与えられ、自分の知識を生かして成果を出すことが期待されます。
また、大学院で論文作成や学会発表を経験していることで、結果を論理的に整理し分かりやすく伝える力も評価されます。
これらの力は製品開発だけでなく、他部署との連携や顧客への技術説明など多様な業務にも役立ちます。
IT企業(データサイエンティストなど)
ビッグデータの活用が進むIT業界では、高度な数学や統計学、プログラミングスキルを持つ院卒が求められています。
データサイエンティストやAIエンジニアなどの職種は、膨大なデータを解析し新しい価値を生み出す役割を担うため、大学院で培った研究能力が大きな武器となります。
データを集め、仮説を立て、検証して結論を導く一連の流れは研究活動と共通しており、大学院での経験がそのまま業務に活かせます。
また、プログラミングや数理解析を通じて問題を発見し、解決する力を示すことで、入社後も新しい技術に柔軟に対応できる人材として評価されます。
IT企業は変化のスピードが速いため、自ら学び続ける姿勢を持つ院卒は特に重宝されます。
コンサルティングファーム
コンサルティング業界は、論理的思考力や課題解決能力を重視するため、理系院卒を高く評価します。
クライアント企業の抱える複雑な問題を分析し、解決策を提示する仕事では、研究で培ったデータ分析力や仮説検証の経験が直接役立ちます。
研究テーマを進める過程で身につく問題設定力や計画的に実験を進める力は、コンサルタントとして顧客の課題を整理し解決する際に不可欠です。
また、研究発表や論文作成を通じて鍛えた説明力や説得力は、プレゼンテーションや提案書作成の場面でも強みとなります。
理系院卒は専門分野にとどまらず、数値に基づいた分析や論理的な議論を得意とするため、多様な業界の案件に柔軟に対応できる点も評価されます。
院卒採用を接居的に行っている企業の探し方
院卒を積極的に採用している企業を見つけるには、早い段階で情報を集めることが大切です。
企業の採用サイトや就職情報サイトで、院卒、修士卒、博士卒などの募集要項を細かく確認しましょう。
大学のキャリアセンターでは、過去に院卒を採用した企業のデータや先輩の内定実績を知ることができます。
理系専門の就職エージェントに相談することで、非公開求人や業界別の採用動向を得ることも可能です。
また、学会や研究発表会では企業の採用担当者が参加している場合もあるため、直接話を聞いて採用意欲を確認するチャンスになります。
複数の情報源を活用し、研究内容を評価してくれる企業を早めに見つけることで、就職活動を有利に進めることができます。
企業が院卒に期待するスキルとは
企業は院卒に対して、専門知識や論理的思考力、課題解決能力に加え、自ら学び続ける探求心を強く期待しています。
大学院での研究は、未解決の問題に挑み、仮説を立て、実験や分析を繰り返しながら結論を導く過程の連続です。
この経験によって得られる計画力、粘り強さ、独創的な発想力は、学部卒にはない院卒ならではの強みです。
さらに、研究成果を論文や発表としてまとめる中で培った表現力や説明力も、企業が重視する重要なスキルです。
入社後も新しい課題に自ら取り組み、学び続ける姿勢を持つ人材は、技術革新が激しい業界において長期的に活躍できる可能性が高いと評価されます。
このように大学院で得た経験は、研究職だけでなく幅広い職種で活かせる普遍的な力として企業から期待されています。
【理系は院に行くべき?】まとめ
理系の大学院についてメリットやデメリットを交えて解説していきましたが、いかがだったでしょうか。
企業や国の中枢を担う研究者になることを目標をしているのであれば、院に進むことは避けられないことです。
大学院に進むことについては、学費の問題や研究と就職活動などクリアしなければいけない問題がいくつもあります。
しかし得られるメリットが大きいことも事実であり、自分の経済状況などを踏まえてから考えるようにしましょう。