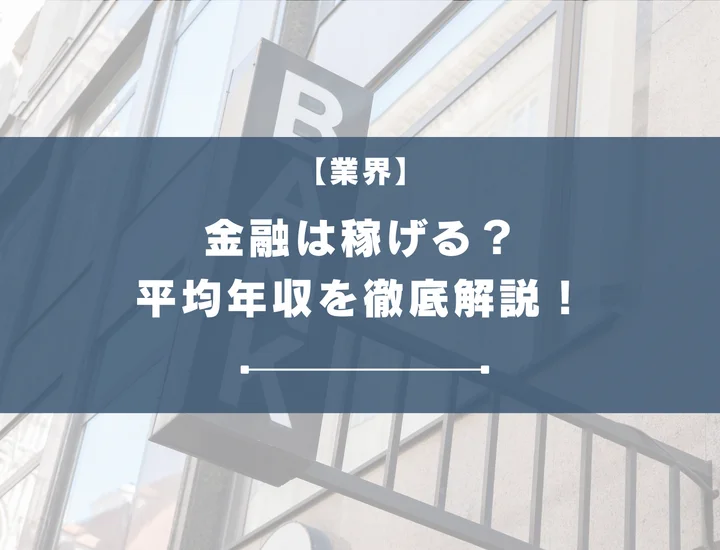HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
「設計」は、英語にすると「design デザイン」です。
日本でデザインと聞くと絵を描く仕事のイメージが強いようですが、実際にはデザイナーは市場にあるあらゆるものの設計者であり、人の作る製品には必ず存在します。
就活で設計職を目指す場合、何をデザインしたいのかによって進むべき道は変わります。
果たしてどのような将来のビジョンが描けるのか、詳しく見ていきましょう。
【設計職ってどんな仕事?】そもそも設計職とは?
冒頭で述べたように、設計職はあらゆる分野で設計・製図を行うのが仕事です。
最もイメージされやすいのが建築系や機械系ですが、そのほかの業界にも設計職は存在し、ありとあらゆるものをデザインしています。
理系学部生が就職しやすい現場であり、CADなどのソフトウェアスキルを持つ学生を優先的に採用する企業も多いです。
特に社会インフラに関係する製品の設計職には高い専門性が求められ、就職は狭き門と言えます。
ちなみに、開発職と設計職とが混同されがちですが、双方は異なる職種です。
企業によって細かな線引きが違う場合もありますが、ざっくり言えば設計職が作成した設計図をもとに、実物を製作するのが開発職だと理解すれば良いでしょう。
製品の企画段階から量産までを担う
設計職は、製品の構想から市場投入までのすべての段階に関わります。
単に図面を作成するだけではなく、製品のアイデアを形にし、実際に量産できる状態へ導くまでが設計者の仕事です。
業務の流れとしては、まず製品の企画や仕様の検討を行い、その後、必要な部品の選定や構造の設計を進めます。
次に、試作品を作り、性能や安全性を評価します。
問題点を洗い出し、改良を重ねたうえで、最終的に製造部門へ引き継ぎます。
この一連の過程を通じて、設計者は製品の技術的な責任を負う存在となります。
つまり、設計職は製品の完成度を左右する「技術の要」として、モノづくりの中核を担っているのです。
上流と下流の違いを理解しよう
設計の仕事は、大きく「上流工程」と「下流工程」に分かれます。
上流工程は、開発の初期段階であり、どのような製品を作るのかを決めるフェーズです。
市場のニーズを分析し、製品の目的や仕様を定める要件定義や基本設計を行います。
この段階では、技術力だけでなく、発想力や他部署との調整力も求められます。
一方、下流工程では、上流で決まった設計方針をもとに、実際に製造可能な形へと落とし込んでいきます。
具体的には、詳細設計や部品図の作成、試作品の評価や改良などが中心です。
上流が「全体像を描く仕事」、下流が「形にする仕事」と言えます。
どちらの工程も設計職にとって欠かせず、経験を積むことで製品の構造全体を理解できるようになります。
産業分野ごとの設計職の役割とは
設計職の仕事内容は、扱う製品や産業分野によって大きく異なります。
自動車や重工業の分野では、安全性や耐久性が最も重視されます。
設計者は厳しい規格や安全基準を守りながら、膨大な部品を組み合わせ、安定して動作する構造を考えます。
ITや家電の分野では、製品の開発スピードが早く、小型化や省エネ性能の向上、使いやすさを重視した設計が求められます。
また、プラントやインフラ分野の設計では、発電所や工場など大規模な設備全体を最適に動かすための設計が中心です。
この分野では、システム全体の効率や安全性を見据えた設計力が重要になります。
自分の専攻や興味に合わせて、どの産業分野の設計に携わるかを考えることが、今後のキャリア形成につながります。
【設計職ってどんな仕事?】設計職の仕事内容
設計職の仕事内容は、もちろん何を設計するかによって詳細は大きく異なります。
ただ、総じて言えば、アイディアを具現化し、最終的に販売できる製品にするための設計図を作成するのが仕事内容です。
たとえば、自動車メーカーの設計職はイメージしやすいですが、まったく新しい自動車の企画アイディアが出された場合、それを実際に製作できるよう図面に落とし込むのが設計職の仕事となっています。
アイディアは、たとえ、いかに素晴らしく思えてもそのままでは単なる空論です。
製品にするためには具現化するための詳細な情報が必要となり、設計者がそれらの情報をすべて正しく設定することで、初めて実現への道が拓けます。
優秀な開発者が揃っていても、設計者がいなければモノづくりはできません。
それだけ重要な職種であり、具体性も緻密性も求められる職種と言えます。
仕事内容は多岐にわたる
設計職と一言でまとめても、仕事内容は多岐にわたります。
ざっと身の回りを見渡してみても、社会インフラを想像してみても、人の作った製品は数多くあり、そのひとつひとつにすべて設計者が存在します。
また、たった一つの家電であっても、実にたくさんの設計者が関わらなければ製品が成り立ちません。
たとえば、電子レンジ一つ取ってみても、マシンの本体機構部品を担当する機械設計もいれば、内部構造の電気電子部分を担う電子設計もいます。
また、組み上がった電子レンジを動かすためには、ソフトウェアを設計する制御設計がいなければなりません。
これらの設計職が協働し、作られた設計図に基づいて実際に開発部隊が開発し、ようやく一つの電子レンジの試作が完成するのです。
いかなる製品であっても設計の仕事内容は実に幅広く、なくてはならない存在です。
機械設計職
機械設計職は、製品の外形や内部構造、動く仕組みを設計する仕事です。
主に三次元CADを使って部品の形を設計し、組み立てたときに正しく動作するかを確認します。
また、製品が壊れにくく、長期間使えるようにするためには、強度や変形の解析も欠かせません。
材料の性質を考慮し、必要に応じて厚みや材質を調整します。
さらに、実際の製造工程を意識して、加工しやすく、コストのかからない設計を行うことも重要です。
このように、機械設計職は理論だけでなく、実際のモノづくりに直結する判断力が求められます。
試作品の評価や改良を繰り返しながら、より良い製品を形にしていくことが大きなやりがいとなります。
電気・電子設計職
電気・電子設計職は、製品を動かすための電気的な仕組みを作る仕事です。
電流や電圧を制御する回路の設計、基板上の部品配置、電源設計などが主な業務となります。
製品が正確に動作するように、抵抗やコンデンサ、トランジスタなどの部品を最適に組み合わせます。
また、電磁気学や半導体の基礎知識が必要であり、設計後はシミュレーションを行って動作の確認をします。
さらに、電気ノイズや発熱などのトラブルを防ぐ工夫も欠かせません。
電気設計は目に見えないエネルギーを扱うため、理論的な思考と慎重さが求められます。
安全性や効率性を両立させることが、この職種の大きな使命です。
ソフトウェア設計職
ソフトウェア設計職は、機械や電子部品を制御するためのプログラムを作る仕事です。
家電や自動車、産業機械などの内部で動くプログラムを設計し、製品を正確に制御します。
使用する言語はCやC++などが中心で、限られたメモリや処理速度の中で効率的に動作させる工夫が求められます。
ハードウェアと密接に関わるため、電子回路やセンサーの仕組みを理解しておく必要があります。
また、実際にプログラムを動かして動作を確認し、不具合を修正するテスト工程も重要です。
ソフトウェア設計は、機械や電気の仕組みを「頭脳」として支える仕事であり、論理的思考と粘り強さが大切です。
設計検証も重要な仕事
設計職の仕事は、設計して終わりではありません。
むしろ、作ったものが正しく動くか、安全で長持ちするかを確認する「検証・評価」が大きな役割を占めます。
試作品を実際に動かし、温度、振動、圧力などの条件で耐久性を確かめます。
テストで得られたデータを分析し、問題があれば設計を見直して改良します。
この過程では、原因を探し出す観察力や論理的な思考力が欠かせません。
また、他部署と協力しながら課題を解決していくため、チームでの連携も重要です。
地道な作業の積み重ねが高品質な製品づくりにつながるため、検証工程は設計者としての信頼を築くうえで非常に大切な仕事です。
【設計職ってどんな仕事?】専攻別:設計職へのキャリアパス
設計職は、自分の専攻分野によって進む道や活かせる知識が大きく変わります。
大学で学んだ専門分野は、就職後の設計業務に直結することが多く、自分の強みをどのように活かすかを意識することが大切です。
ここでは、代表的な理系専攻ごとに、どのような設計分野で活躍できるのかを具体的に紹介します。
機械系学科:自動車・産業機械設計
機械系出身者は、設計職の中でも特に幅広い分野で活躍できます。
機械設計では、材料力学、熱力学、流体力学、機構学といった基礎知識が直接的に活かされます。
自動車のボディ設計、ロボットのアーム機構、エアコンの熱交換器設計など、物理的な構造を持つ製品を扱うのが主な領域です。
また、CAE解析やシミュレーションの経験は、実務でも高く評価されます。
自ら設計した構造が実際に動き、性能を発揮する瞬間に大きな達成感を得られる仕事です。
生産技術や品質保証と連携しながら、強度や安全性、コストのバランスを取る力も求められます。
モノづくりの根幹を支える技術職として、最も王道といえるキャリアパスです。
電気電子系学科:家電・半導体・通信設計
電気電子系の学生は、製品の頭脳や心臓部分にあたる設計を担います。
電流の流れや電力供給の仕組みを理解し、電子回路や基板を設計して製品を動かすのが主な役割です。
家電製品やスマートフォン、パソコンの内部回路から、通信機器や発電システムなどの大型設備まで活躍の場は広いです。
また、半導体技術や電磁気学の知識を活かして、より省エネで高性能な製品を作ることが求められます。
ノイズ対策や安全性の確保など、目に見えない課題を解決するのも電気設計の重要な仕事です。
製品の信頼性を支える責任の大きな仕事であり、社会のインフラを支える使命感を持てる分野でもあります。
情報系学科:組み込みシステム・制御系ソフトウェア設計
情報系の学生は、製品の中で動くソフトウェア設計を中心に活躍します。
家電、自動車、産業機械など、あらゆる製品に組み込まれている制御プログラムを設計します。
C言語などのプログラミングスキルや、リアルタイムで動作するシステムに関する知識が求められます。
例えば、自動車の電子制御ユニットや、工場で稼働する自動化装置、IoT家電などが代表的な対象です。
ハードウェアと連携して動くため、電気や機械の仕組みを理解する力も必要です。
実際に自分のプログラムで機械が動く瞬間の達成感は大きく、開発の中心で活躍できる分野です。
ソフトとハードの橋渡し役として、今後ますます需要が高まるキャリアパスです。
物理・化学系学科:素材開発と製品設計の接点
物理・化学系の学生は、設計職の中でも素材や品質を支える重要なポジションで力を発揮します。
直接的に機械や回路を設計しなくても、材料や構造の基礎を理解する力が大きな武器になります。
新しい素材の開発や、表面処理の改良、耐久性の向上など、製品性能を根本から支える役割を担います。
たとえば、スマートフォンの軽量素材、車の耐熱部品、光学機器のレンズ素材など、活躍の場は多岐にわたります。
また、製品の品質評価や材料試験など、科学的な視点で設計を支える業務も多いです。
基礎研究と応用設計をつなぐ立場として、理論と実践の両面からモノづくりに貢献できる魅力的なキャリアです。
【設計職ってどんな仕事?】設計職に就職するためには?
設計職を目指すのは理系学生がほとんどですが、設計職に就職するためにどうしても必要な資格は特に存在するわけではありません。
ただし、最低限の専門知識がなければどんな企業でも採用されるのは厳しいでしょう。
もちろん目指す部門によって必要とされる専門知識は異なり、機械設計や電気設計なら工学系の知識、制御するソフトウェア設計では情報処理系の知識が求められます。
それらのスキルを持つことをアピールしやすいのは、やはりその専門の資格を持つことです。
たとえば、機械設計に関する資格には「機械設計技術者」(1~3級)がありますが、2級以上は実務経験が必要になるため、3級の取得を学生時代に目指すのは一つの方法です。
設計職につくのは基本理系学生
理系生の機械学科や電気電子学科、情報学科の生徒がそれらの分野におけるメーカーの設計職につくことはとても多いです。
もともとそうした分野に興味があって進学していることでしょうし、適正があればそれを活かして設計職に就くのは自然な流れと言えます。
特に、自身が設計したものをたくさんの人に使ってもらいたい、社会に役立てたいという夢を抱く理系学生はとても多いです。
メーカーにとっては中枢にあたりますし、やりがいのある仕事を求めて応募する就活生も例年たくさんいます。
実際に同じ学校から就職した先輩も多いでしょうから、いざ就活となってもOB訪問などがしやすい環境で情報が入りやすいことも利点でしょう。
院に行くと就職の選択肢が広がる
実は理系学生が悩むポイントが、大学卒業後の進路です。
設計職には就きたいけれど、だからこそ院に進んでもっと深く研究を重ねてからのほうが良いのではないかと考える学生が多いからです。
事実、大手メーカーの設計職や開発部門には理系大学の院生が多く、院生が中心で事業を回していると言っても過言ではありません。
世界に名の通るような大手メーカーへの就職を目指すなら、院へ進学し、専門性を磨いてからのほうがより望む設計職に就くのに有利であることは確かです。
ただし、設計のため院に行くことを選択する場合は、どのような仕事に携わりたいのか、きちんと分野や領域、具体的な製品をイメージしたうえで行くことが重要となります。
やみくもに院に行ってもただ単に人生の時間を費やすだけになってしまいますので、しっかりキャリアビジョンを定め、かつ綿密に企業のリサーチをすることが大切です。
選考で評価される研究テーマの伝え方
設計職の面接で評価されるのは、研究内容の専門性そのものではなく、研究を通じてどのように課題を見つけ、解決してきたかというプロセスです。
面接官が注目するのは、あなたの思考の流れと行動の根拠です。
まず、課題設定力を示すために「なぜそのテーマを選んだのか」「どんな問題意識を持って取り組んだのか」を明確に伝えましょう。
次に、実行力や工夫を表すために「どんな困難に直面し、どんな仮説や工夫で乗り越えたのか」を具体的に話します。
このとき、専門用語を避けて一般的な言葉に置き換えることが大切です。
図や数値を交えながら、論理的に説明することで説得力が高まります。
また、結果よりも試行錯誤の過程や学んだことを重視して伝えると、研究姿勢や粘り強さがより伝わります。
必須スキル:CAD/CAEなどの設計ツール習得
設計職では、専門知識だけでなく、設計ツールを扱えるかどうかも大きな評価基準になります。
まず、機械系では三次元CAD(SolidWorks、CATIAなど)を使い、部品の形状を設計したり、組み立て後の干渉や動作を確認したりする力が求められます。
さらに、CAE解析によって強度や振動、熱伝導などを数値的に評価できることが理想です。
電気・電子系では、回路シミュレーターやPCB設計ツールを使い、正確な回路設計や基板レイアウトを行います。
情報系では、CやC++、Python、MATLABといったプログラミング言語を使い、制御アルゴリズムやシミュレーションの開発を行います。
こうしたツールは、設計者としての実務力を示す客観的な証拠となります。
面接やエントリーシートでは、具体的に使用したソフト名や活用した場面を挙げると、即戦力としての印象を与えやすくなります。
【設計職ってどんな仕事?】設計職のやりがいと大変な点
設計職は、製品を生み出す中心的な役割を担う仕事です。
自分の発想や工夫が実際の形となり、社会で使われる瞬間には大きな達成感があります。
一方で、納期やコスト、品質といった厳しい制約の中で仕事を進めなければならず、苦労も多い現場です。
ここでは、設計職のやりがいと大変な点をそれぞれの側面から解説します。
メリット:自分のアイデアが形になる達成感
設計職の最大の魅力は、自分の頭の中にあるアイデアが実際の製品として形になることです。
設計者は、企画の初期段階から構造や機能を考え、図面を作り、試作品を作って改良を重ねます。
長い時間をかけて完成した製品が初めて動いた瞬間には、何物にも代えがたい喜びがあります。
さらに、自分が関わった製品が店頭に並んだり、街で使われているのを見かけたときには、社会の役に立っている実感を得られます。
この達成感は、単に数字や資料で成果を確認する仕事では味わえません。
努力の結果が「目に見える形」で世の中に残ることこそ、設計職ならではの醍醐味です。
デメリット:納期・コスト・品質との戦い
設計職は理想を追い求める仕事である一方で、常に現実的な制約との戦いが伴います。
企業や顧客から求められるのは、高品質で低コスト、そして短納期という厳しい条件です。
どれか一つを優先すれば、他の要素が犠牲になることもあります。
そのため、設計者は常に最適なバランスを探りながら調整を重ねます。
また、途中で仕様変更が発生したり、試作品の不具合が見つかって設計をやり直すことも少なくありません。
納期が迫る中で修正を繰り返すプレッシャーは大きく、精神的にも根気が求められます。
それでも、困難を乗り越えて最終製品が完成したときの達成感が、次の挑戦への原動力になります。
残業や休日出勤の実態
設計職の働き方は、業界や担当するプロジェクトによって大きく異なります。
特に繁忙期は、納期前のトラブル対応や最終調整のために残業が増える傾向があります。
新製品の立ち上げ時期はスケジュールが厳しく、休日出勤が発生することもあります。
一方で、落ち着いた時期には有給休暇を取りやすく、比較的自由に時間を使える職場もあります。
大手メーカーでは労務管理が整備されており、残業時間の上限が明確に定められている場合が多いです。
しかし、開発スピードを重視するベンチャー企業やIT関連の設計職では、仕事量の波が激しくなる傾向があります。
設計職は時間に追われることもありますが、その分、自分が手掛けた仕事の成果が明確に見えるため、努力が報われる職種でもあります。
設計職のキャリアパス
設計職で経験を積むと、将来のキャリアパスは複数の方向に広がります。
一つは、特定の技術分野を極める専門職の道です。
熱設計、光学設計、流体解析など、自分の得意分野を深め、社内外で技術の中心となる人材を目指します。
もう一つは、プロジェクトマネージャーとしてチーム全体をまとめる道です。
設計スキルに加えて、進捗管理やコスト管理、人員配置など、組織運営の力が求められます。
また、現場の知識を活かして製品企画やマーケティングに転じる人もいます。
どの道に進むにしても、設計職で培った問題解決力と論理的思考は、大きな武器となります。
自分の適性や興味に応じて、専門性を深めるか、マネジメントへ進むかを選ぶことができます。
【設計職ってどんな仕事?】まとめ
設計職はあらゆる製品開発に存在し、実に多岐にわたる業務で人の生活を支えています。
自身が設計したものが市場で販売される光景を目にすれば、大きな喜びと達成感を感じられることでしょう。
ただ、そのやりがいと同時に大きな責任も生まれ、間違いのない仕事を収めるための努力が必要とされる職種でもあります。
設計職に就くのは理系学生がほとんどですが、大手メーカーでは院生が中心となる場合もあります。
必須の資格は原則ありませんが、狭き門を制するためには自身の専門知識のアピールが必要です。
専攻に関係する資格の取得を狙うのも一つの手段でしょう。