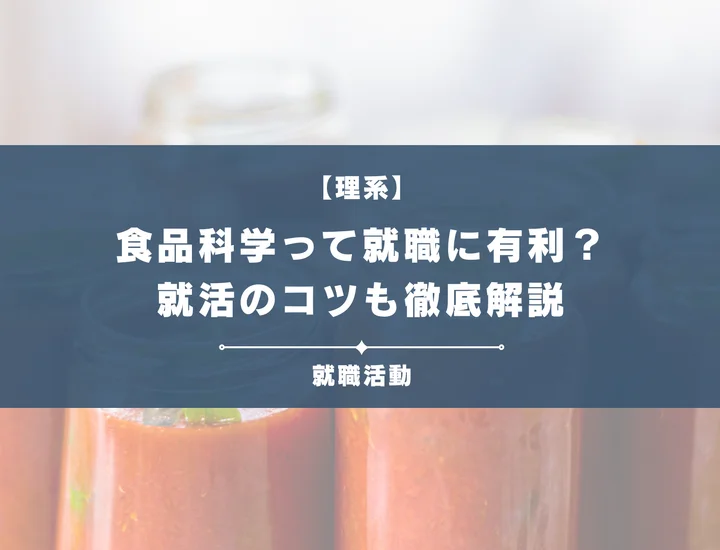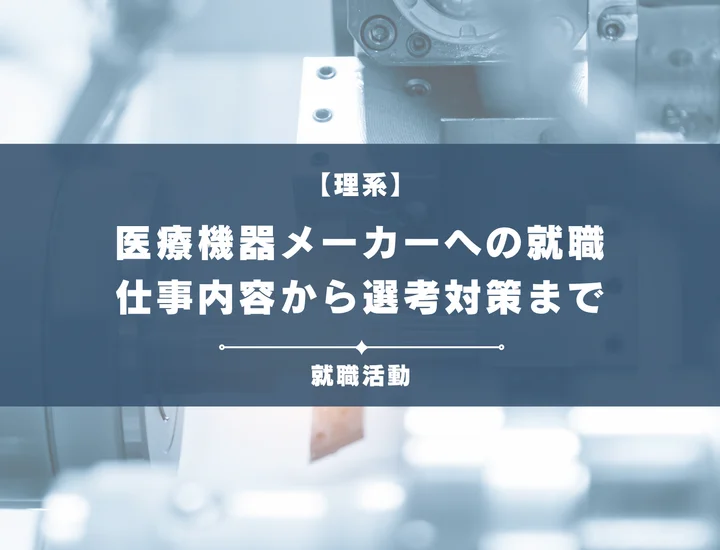HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに

秋を目前に、ひとまず就活が落ち着き、卒論にそろそろ取り組み始めようかと考えている大学4年生も多いでしょう。
卒業論文、いわゆる「卒論」は理系の場合、ほぼ100%に近い割合で必要です。
ちなみに、文系の一部では卒論が必要ないケースもあります。
しかし、理系の場合は自分で実験したデータをもとに卒論を制作・発表し、合格しなければ卒業できません。
いつまでに卒論を完成させればよいのか、またいつからスタートさせれば間に合うのか、といった大まかな流れを事前に把握することが大切です。
本記事では、主に理系の卒論に取り組む方々を応援すべく、期限内に終えられる計画の立て方などをご紹介いたします。
【理系の卒論はいつまでに終わらせる?】卒論完成とは?
理系の卒論提出期日は、学部や研究室にもよりますが、学部4年生の2月中旬〜3月上旬と考えるとよいでしょう。
また卒業認定を受けるには、単に卒業研究を論文にまとめて終了ではなく、卒論提出と審査員前でのプレゼンという2段階が待ち構えています。
これらを3月の決められた期日までに終わらせ、審査に合格してはじめて卒業できるのです。
それでは、具体的にはどのような工程を踏むのでしょうか。
大まかには、「テーマを決める」→「目的や背景、目標などを明確化する」→「実験の準備、実践」を進めながら、並行して論文を書き始めるのが一般的でしょう。
具体的な計画の立て方は、同じ研究室の先輩のアドバイスを受けるのが1番です。
なお、論文は先生の添削を受けて修正しながら完成させるため、その手間を考慮する必要もあります。
そして、プレゼンに向けてスライド作成や製本化をして、プレゼン本番・論文提出をむかえるのです。
卒論を完成させるまでの流れは以下の記事で詳しく解説しているので確認してみてください!
卒業研究を製本化する
卒論は論文を書いて終わりではありません。
仕上げにA4用紙、20ページ程度にまとめ、製本して提出することが多くの大学で必要とされます。
卒論は研究結果として大学に長年所蔵されるため、レポート用紙へ簡単にまとめたようなものでは受け取ってもらえません。
しかし、製本に時間を取られてはもったいないので、予算があれば業者に依頼するのがクオリティも高く、間違いないでしょう。
また、ハードカバーでの提出を指定する大学も多く、自前の製本では不可となる可能性もあります。
製本のルールが提示されるので事前に必ずチェックして、製本に関することで再提出にならないように注意する必要があります。
修士の先輩などに質問できる場合は、どのように製本したか、どの業者がおすすめか、といったアドバイスをもらうとよいでしょう。
審査員の前でプレゼンする
合格認定をもらうための必要なステップとしてもう1つ、審査員前でのプレゼン(発表)があります。
その際、資料として必須になるのがスライドです。
プレゼンはストーリー性を意識することで伝わりやすくなり、どんなスライドが必要かも想像しやすくなります。
スライドは、「1枚に対して内容は1つ」と決め、文字数もできるだけ減らし、簡素な見た目を意識しましょう。
また、俯瞰して見たときに、「目的と結論が一致しているか」「プレゼンに対して視覚的な補助となるようなスライドであるか」などを考えながら作成することが重要です。
社会に出てからもプレゼンの機会はたびたび訪れます。
卒論発表は、「どうすれば相手により伝わるか」「どうすれば相手に納得してもらえるか」といったプレゼン力を養う絶好のチャンスです。
苦手意識のある方もいるかもしれませんが、この機会を成長のために有効活用しましょう。
【理系の卒論はいつまでに終わらせる?】卒論はいつまでに終わらせるの?
前述の通り、理系の卒論提出期日は早くて2月下旬〜3月上旬、ゼミによって異なりますが、一般的には3月下旬までとされています。
理系の場合、自分で実験したデータをもとに論文を制作するため、実験が失敗するなどして遅れると、最後は期日に追われて大変な状況になる可能性も否めません。
研究は、事前研究や本研究・分析を合わせても3〜4ヶ月かかると見て、遅くとも夏休み明けに始めるのが理想です。
そして、冬休みに入るころから執筆を始めて、2ヶ月ほどで完成を目指していきます。
終盤にはスライド作成の時間も必要になります。
場合によっては計画にそって見切りをつけ、そのときまでに得た成果を綺麗にまとめることも必要です。
人によって違いはあると思いますが、4年生のスタート時点で大まかな計画を立てることと、冬休み期間にできるだけ執筆を進めておくことがポイントになるでしょう。
卒論の発表会は2月下旬!
一般的には2月下旬に、「卒論発表会」というプレゼンの場が開かれます。
自分が研究した内容を、指導教官の先生方やゼミの同級生などの前でプレゼンし、質疑応答をするものです。
もしかしたら、別の研究室の方々が参加する場合もあるかもしれません。
このとき、資料としてスクリーンに映すスライドが必要なため、2月下旬前までにそれらも完成させます。
スライドの内容はプレゼンの伝わりやすさに直結するため、手を抜けません。
直前にバタバタと急いで作ることにならないよう、十分な時間が確保できる見通しを立てておきたいものです。
また、発表会の前には必ずプレゼンの練習をしましょう。
原稿を用意し、スライドごとに伝えたいことが明確であるか、確認しながら練習するのがおすすめです。
発表本番では原稿を見ずに話せるよう、とにかく繰り返し練習して、自然な発表を目指しましょう。
卒論完成までの流れは?
卒論完成までの一連の流れは、ここまでも大まかにご説明してきましたが、より具体的に確認していきましょう。
今回は、余裕をもった理想のスケジュールをご紹介いたします。
早い方だと、学部4年生の春から研究テーマを考え始め、夏休み前から研究準備に取りかかります。
ちなみに、院試を受ける場合は7〜8月が試験本番のため、試験勉強とテーマ決めを並行しながら、試験終了後すぐに研究準備へ取りかかるのが理想でしょう。
そして、夏休み明けから論文の執筆と本研究を開始します。
研究室などによって異なりますが、中間発表が10月〜12月ころにあるかもしれません。
ここで進捗状況を客観的に確認できます。
その後は実験と執筆、スライド作成をできるだけ並行して進めていきます。
前述の通り、冬休み期間に作業を止めないことが、最後まで余裕をもったスケジュールで進めるためのポイントです。
後半には「先生の添削を受けて修正をする」という自分以外の都合を考慮した作業も発生します。
なお、実験データが消えてしまったり、機材トラブルで実験が遅れたりするといったアクシデントが起きる可能性もゼロではありません。
したがって、執筆開始は早ければ早いほうが安心でしょう。
理系の卒論提出時期はいつ?
理系学生の多くが気になるのは、卒論の正式な提出時期です。
一般的に、理系の卒論は卒業年度の1月下旬から2月上旬に提出日が設定される大学が多いです。
文系に比べて早めのスケジュールになるのは、提出後に卒論発表会や審査を行うためであり、研究成果を発表し合う場が確保されているからです。
この期間に合わせて研究や執筆を進めなければならないため、年末年始を含む時期は特に集中力が求められます。
また、研究室ごとに内部的な締め切りが設けられている場合もあり、大学公式の提出日より前に完成している必要があります。
そのため、学生は大学の公式なスケジュールだけでなく、研究室単位での予定も把握することが欠かせません。
特に理系は実験やデータ解析に時間を要するため、余裕を持って準備を進めていくことが大切です。
提出時期の注意点
卒論提出を控える学生にとって、いくつかの注意点を意識しておくことは非常に重要です。
まず、大学公式の締め切りとは別に、研究室独自の提出期限が設定されている場合があります。
これは指導教員が内容を事前に確認し、修正点を伝えるためであり、公式締め切りに間に合わせるための必須ステップとなります。
また、卒論は印刷や製本をして提出するのが一般的です。
学内の印刷所や外部業者を利用する場合、提出直前は多くの学生で混み合うため、想定以上に時間がかかることがあります。
そのため、余裕を持ってデータを完成させ、早めに印刷や製本の準備を進めることが不可欠です。
さらに、データのバックアップも忘れてはなりません。
パソコンの故障やデータ消失は、毎年のように起きるトラブルです。
USBやクラウドサービスを利用し、複数の場所に保存しておくことで、万一の事態にも備えることができます。
【理系の卒論はいつまでに終わらせる?】卒論完成にはどのくらいの時間がかかるの?
一口に卒論の完成と言っても、論文の執筆だけでなく、スライドの作成や発表に向けての原稿作成、練習も必要だとわかりました。
それでは、実際に多くの学部4年生は、完成までにどのくらいの時間がかかっているのでしょうか。
もちろん、1年間を卒論のためだけに当てることはできません。
就職活動や院試、アルバイトなどと並行しながら忙しく取り組むのが実情です。
執筆だけでいえば、平均で2〜3ヶ月というケースが多いようです。
一見短く感じますが、どのような工夫をすればこの見込み通りに進められるのでしょうか。
卒論完成には2ヶ月ほどかかる!
研究室などによって違いはあると思いますが、先生や先輩が計画を立てる際に親身にサポートしてくれたことで、短期間で完成できたケースが多いようです。
また、実験のデータを早いうちから集めていたことが、短期間での完成につながったという声もあります。
理系の卒論は、文系と比べても作業量が多く、時間がかかることは歴然でしょう。
提出期限が2月中旬として、本提出前の添削指導を見越して、遅くとも12月下旬までには執筆を開始するのがおすすめです。
約2万字を書くことになるので、データがそろっていなくても、序論など書けるところから早めに着手しておくに越したことはありません。
実験に失敗するなどのアクシデントによって、1ヶ月以上計画が後ろ倒しになる可能性があるのも理系の特徴です。
執筆開始前にさまざまな論文を読んでおく、指定の書式を頭に入れておくだけでも、そのあとの作業スピードに差が出るでしょう。
日頃の考察で効率的に書ける!
研究のタイプは大きく分けて2種類あり、論証型と報告型があります。
論証型は、予想の結果を先に立てて仮説の検証や立証をします。
それに対し報告型は、調査が進んでいない未知の部分を研究し、結果を報告するスタイルです。
論証型で実験をする場合は、手法を正確に使って完成度の高い結果をコツコツと集めておけば、執筆はスムーズに進みます。
報告型の場合、論証型よりも手法やデータ解釈の自由度は高くなります。
しかし、研究準備の段階からコツコツと多くのデータを集め、納得度の高い考察をしなければ説得力がない論文となってしまうのです。
当然、執筆も進めにくくなるでしょう。
どちらにせよ、こまめに研究や実験の結果をまとめておくことが、効率的な執筆につながるといえます。
そして、些細に感じるデータも取りこぼさず記録しておけば、予想外の展開となった場合も執筆が止まってしまうリスクを減らせるでしょう。
【理系の卒論はいつまでに終わらせる?】理系の卒論は大変!
理系の卒論は大変です。
提出期日までに計画通り余裕をもって終えるのは、それなりにハードルの高い話でしょう。
たとえば、仮説を立てて実験をしても、思ったような結果が出ない場合もあります。
また、必要なデータを得るためには実験の厳密な事前準備や、質疑応答に対応するための準備もしなければなりません。
これらは想像以上に大変で、予定通りにいかない場合も多いでしょう。
臨機応変に、仮説と違う結果が出てもその新規性に価値を見出せれば問題ありませんが、戸惑って行き詰まる可能性もあります。
順調に執筆が進んだとしても、先生の添削によって何度も修正が必要となり、後れを取ることも考えられます。
このように理系の卒論は文系よりもハードなので、提出期日直前に徹夜が続くという体験談も多くあるのです。
理系の卒論の書き方のコツを知ろう!
ここまで聞くと大変なことばかりの理系の卒論ですが、少しでもコツをつかんでスムーズに進めていただきたいものです。
まず、基本事項として、「壮大すぎるテーマは避け、実験を含めてできる範囲の内容にする」ことが重要です。
既存の資料をもとに実験、執筆するのが一般的でしょう。
その先行研究を参考にしつつ、自分なりの新規性のある結論にまとめます。
書式も指定のルールがある場合も多いですが、卒論は大まかに「はじめに」「序論」「本論」「事例」「結論」という5つの構成から成ることを頭に入れておきましょう。
この構成を意識して、自分の意図と実験で得たデータをもとに、導きたい結論へ向かって論じていけばよいのです。
この2点を押さえておくだけでも、見通しが立てやすくなります。
スケジュール管理が鍵となる理由
理系の卒論を無事に完成させるためには、徹底したスケジュール管理が何よりも大切です。
研究には実験の失敗や予期せぬトラブルがつきものであり、その都度やり直しが必要になる場合もあります。
余裕を持った計画を立てておくことで、こうした問題が発生しても慌てずに対応でき、結果として完成度の高い卒論に仕上げることが可能です。
また、明確なスケジュールを持って取り組むことは、精神的な安定にもつながります。
締め切りが近づいて焦りや不安を感じる場面でも、やるべき作業が明確であれば落ち着いて取り組むことができます。
さらに、計画的に進めることで論文の内容を何度も見直す時間が確保でき、考察を深めたり表現を洗練させたりする余裕も生まれます。
【理系の卒論はいつまでにおらわせる?】いつから始めるべき?
理系の卒論は、研究室に配属されたその瞬間から準備が始まっていると言っても過言ではありません。
実験や調査に多くの時間が必要となるため、のんびり構えているとすぐに時間が足りなくなってしまいます。
文系のように短期間でまとめることができるケースは少なく、日々の積み重ねが卒論完成に直結します。
ここでは、理系の卒論を無事に仕上げるために必要なスタート時期と、その具体的な流れについて詳しく解説します。
卒論のテーマ設定はいつから?
理系の卒論で最初に直面するのが、研究テーマを決める段階です。
多くの研究室では4月から5月にかけてテーマを選定しますが、この作業は単なる選択ではなく、その後1年間の方向性を決める大切な作業です。
自分の興味や将来の進路に関わる分野を意識しながら、指導教員と密に相談することが欠かせません。
テーマが曖昧なまま研究を進めると、計画の立案が困難になり、時間の無駄が発生してしまいます。
また、自分のやりたい内容と研究室の方針をしっかりすり合わせることも重要です。
研究室ごとに得意とする分野や進め方が異なるため、無理のないテーマを選ぶことで最後までやり切る力につながります。
さらに、テーマを早期に固めることで、夏以降の実験や調査に十分な時間を割けるという大きな利点もあります。
実験はいつからスタートする?
研究テーマが決まったら、次は実験や調査の開始です。
理系の卒論において、この段階が最も時間を要する部分であり、卒業論文の中核をなすものでもあります。
多くの研究室では春学期から予備実験を始め、本格的なデータ収集は夏休み以降に集中します。
特に夏休みは長期間研究に打ち込める貴重な機会であり、この時期にどれだけデータを集められるかが、その後の執筆に大きく影響します。
夏の努力が不足すると秋以降の進捗が遅れ、最終的に追い込まれる可能性が高まります。
逆に、この時期に集中的に取り組んでデータを確保すれば、執筆作業を余裕を持って進められます。
また、実験は失敗ややり直しがつきものであるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
卒論の本格的な執筆はいつから始める
卒論の執筆に本格的に取り組むのは、秋以降が一般的です。
夏休みで集めたデータがある程度揃う段階から、徐々に文章を書き始めるのが理想的です。
特に秋学期には先行研究の調査や文献整理を進めつつ、実験結果のまとめや考察を少しずつ書き進めていきます。
執筆を後回しにすると、データ整理と文章作成が重なり、大きな負担となってしまいます。
早めに書き始めておくことで、指導教員からのフィードバックを受ける時間も確保でき、修正や改善の余裕が生まれます。
理想的には年末までに骨組みを完成させ、年明け以降は仕上げや推敲に時間を割くことです。
執筆作業は一度に仕上げるものではなく、何度も見直しながら質を高めていくものなので、計画的な取り組みが不可欠です。
【理系の卒論はいつまでにおらわせる?】卒論発表会はいつ?成功のポイント
理系の学生にとって卒論発表会は、大学生活の集大成ともいえる大切な場面です。
長期間取り組んできた研究をまとめ、他者にわかりやすく伝えることで、研究者としての成長を示す機会となります。
卒論の提出がゴールではなく、その内容を発表することで理解の深さや表現力も問われます。
ここでは、卒論発表会の時期や流れ、スライド作成の工夫、質疑応答への準備について具体的に解説します。
発表会の時期と具体的な流れ
理系の卒論発表会は、卒業を控えた2月下旬から3月上旬に行われるのが一般的です。
大学や学科によって多少の差はありますが、ほとんどの場合は卒論提出後に日程が設定されます。
発表形式はパワーポイントを用いた口頭発表が中心で、持ち時間は一人あたり10分から15分程度が標準です。
限られた時間の中で研究の目的、方法、結果、考察を簡潔に伝えることが求められるため、要点を整理する力が必要になります。
また、発表会は単なる報告の場ではなく、学内の研究成果を共有し合う大切な機会でもあります。
学生同士が互いの研究に触れることで視野が広がり、学問的な刺激を受ける貴重な場となるのです。
発表会は緊張感が伴いますが、準備をしっかり行えば自信を持って臨むことができます。
発表スライド作成のポイント
発表スライドは、聴衆に研究をわかりやすく伝えるための重要な道具です。
まず意識すべきは、一枚のスライドに盛り込む情報は一つだけという考え方です。
複数の情報を詰め込みすぎると聞き手が混乱し、伝えたい本質がぼやけてしまいます。
また、数字や文章で説明するよりも、図やグラフを活用して視覚的に理解させる工夫が有効です。
複雑な結果でも、グラフで示せば一目で伝わることが多く、聴衆の集中を保ちやすくなります。
さらに、文字の大きさや色使いも重要です。
遠くからでも見やすいフォントサイズを使用し、背景と文字のコントラストをはっきりさせることで伝わりやすさが増します。
スライドは美しく整えることよりも、研究の核心を的確に示すためにあるという意識を持ちましょう。
質疑応答に備えるには
卒論発表会の最後には必ず質疑応答の時間が設けられます。
この場では、指導教員や審査員、場合によっては同級生から質問を受けることになります。
答えに詰まってしまうと、自分の研究を十分に理解していない印象を与えてしまうため、準備が欠かせません。
まずは、自分の発表内容を振り返り、想定される質問をリスト化して回答を用意しておきましょう。
また、指導教員や先輩に模擬発表を聞いてもらい、実際に質問を受ける練習をすると効果的です。
その過程で自分では気づけなかった弱点や説明不足の点を補うことができます。
質疑応答は緊張する時間ではありますが、しっかり準備しておけば自分の理解の深さを示す良い機会になります。
【理系の卒論はいつまでに終わらせる?】まとめ
理系の卒論完成までの流れや、必要な作業、制作のコツについて一通り把握できたと思います。
これらをふまえつつ、身近な先輩や先生にアドバイスを受けながら1人で抱えこまず、完成へ向けて頑張りましょう。
また、体調管理は何よりも大切です。
せっかく立てた計画も、体調を崩してしまえば否応無しに後ろ倒しとなってしまいます。
睡眠不足で風邪を引くなど、もってのほかです。
しっかり休息を取りながら、期日より余裕をもって卒論提出ができるよう気をつけていきましょう。