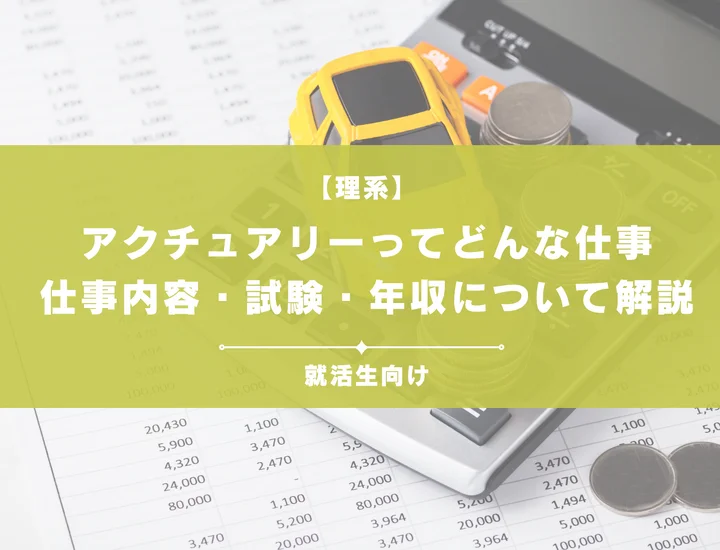HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
「農学部では何を学ぶことができるのだろう?」
「農学部を卒業すると、どのような会社に入れるのだろうか?」
農学部志望の人や在学中の人は、このような疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では、農学部で学ぶことができる学系の内容や関係の深い業界、卒業後に就くことができる職種などについて解説しています。
この記事を読むことで、農学部を目指す際にどのような学系を選べば良いのか、卒業後にどのような仕事に就くことができるのかがわかるため、農学部の受験を考えていたり、就職先に迷っている人の参考になるでしょう。
農学部受験を考えている人や農学部に在籍中で就職に不安のある人は、是非この記事を一読してください。
農学部とは

農学部は、食料の生産や環境の保全、生物資源の活用など、人類と自然の共存に関する幅広い分野を科学的に探求する学部です。
作物や家畜の生産を扱う生物生産科学、生物の機能を応用する応用生物科学、食品やバイオ技術に関わる農芸化学、農村や農業の経済を分析する農業経済学など多彩な領域を学びます。
さらに森林科学、水産学、環境科学、農業工学など、自然と社会をつなぐ専門知識や技術を体系的に学ぶことができます。
生物生産科学:作物や家畜の生産・育種・病害虫対策など
応用生物科学:生物の機能や特性を応用して、食料・医薬品・エネルギーなどの生産に役立てる
農芸化学:生物が持つ様々な機能を化学的に解明し、食品やバイオテクノロジーに応用する学問
農業経済学:農業や農村に関わる経済現象を分析して、経営について学ぶ
農業工学:農作業の効率化や省力化のための機械や施設、土地改良などを研究する
森林科学:森林の育成・管理・利用・保全について学ぶ
水産学:水産生物の養殖、資源管理、水産食品などについて学ぶ
環境科学:農業や食料生産が環境に与える影響を評価し、持続可能な社会の実現を目指す
大学によっては食品科学、栄養学、獣医学、地域開発などの分野も設置されており、進路の幅も広がっています。
こうした学びを通じて、持続可能な社会の実現や世界的な食料問題の解決に貢献できる力を養うことができます。
他の学部学科との違い

農学部は「食」「環境」「生命」に関わる応用的な研究を通じて、人と自然の共生を目指す学問領域です。
しかし、似た内容を扱うように見える理学部や工学部、生活科学部、獣医学部、環境学部などとは、それぞれ研究の目的や対象、アプローチが異なります。
ここでは、就活生が自分の専門性を正確に伝えるために理解しておきたい、他学部との違いについて詳しく解説します。
理学部化学科
理学部化学科は、物質の構造や性質、反応などを原子・分子レベルで解明する基礎科学の研究を主な目的としています。
学問としての「化学」を深く掘り下げ、現象の背後にある理論や法則を明らかにすることを重視しており、有機・無機・物理・分析化学などを中心に体系的に学びます。
研究対象は金属や高分子、溶液など多岐にわたり、自然界や産業界で起こる化学変化を幅広く扱います。
一方、農学部はこのような化学的知見を基盤としつつ、作物、家畜、農薬、肥料、食品、環境汚染物質など、人間の生活や生産活動と密接に関わるものに焦点を当てています。
化学を「手段」として活用し、環境保全や食の安全・安定供給など社会的課題の解決をめざす応用的な視点が特徴です。
理学部生物学科
理学部生物学科は、生命現象の普遍的なメカニズムを探る基礎研究を目的とし、分子生物学、細胞生物学、進化学、生態学などを中心に学びます。
自然界に存在するあらゆる生物を研究対象とし、特定の目的や応用を前提としない純粋な探究心に基づくアプローチが基本です。
例えば、遺伝子の発現機構や生物の進化過程の理解など、学術的な問いに対する答えを探すことが中心です。
一方で農学部では、こうした基礎的な知識を土台としつつ、人間の生活と直結する生物資源の持続的な利用や、食料生産の効率化、安全性の確保、環境との調和など、実社会への応用を重視しています。
研究対象も、作物、家畜、水産生物、森林、土壌、微生物など人の暮らしに密接に関係するものが中心であり、地域社会や経済との関係性も含めた幅広い視点で学びを進めます。
工学部応用生物学科
工学部応用生物学科は、生物の機能を工学的に応用することで、新しい技術や産業の創出を目指す学科です。
バイオテクノロジーや遺伝子工学、タンパク質工学、細胞工学などを駆使し、医療やエネルギー、環境浄化などの分野で革新をもたらすことを目的としています。
研究対象は微生物、酵素、遺伝子、細胞などであり、その機能を利用した生物反応プロセスや生産技術の開発が主軸となります。
一方、農学部では、作物や家畜、水産生物、森林、土壌といった自然環境に根差した生物資源を対象とし、それらをいかに持続可能な形で活用・生産していくかに重点を置いています。
また、農村社会との関わりや地域振興、食料の安定供給など、「人間の生活の基盤を支える」ことを目的としており、理工系の視点だけではなく、経済・環境・社会全体を視野に入れた総合科学の性質を持ちます。
生活科学部(食物栄養学科・食品科学科など)
生活科学部の食物栄養学科や食品科学科では、人間の健康維持や生活の質の向上を目的に、栄養学、調理学、食品衛生学などを学びます。
食品の栄養成分や調理科学、食習慣の影響、健康との関連性といった、「人が食べる段階」での食品や栄養の研究が中心です。
管理栄養士や食品衛生の専門家を目指す学生も多く、消費者の視点から食を科学的に捉えることが特徴です。
一方、農学部では、作物や家畜、水産物などの「生産現場」に焦点を当て、栽培・飼育から加工、流通、安全性評価に至るまで、食の全工程を総合的に扱います。
食品の機能性や保存性、品質管理などにも取り組みますが、それは生産や供給の一環としての研究であり、視点がよりマクロで供給者側にあります。
「食べる」ことに焦点を当てる生活科学部に対して、「作る」「届ける」「支える」ことまで含めるのが農学部の視点です。
獣医学部
獣医学部は、動物の病気やケガを予防・診断・治療すること、動物福祉や公衆衛生を守ることを目的とする専門学部です。
学びの中心は解剖学、生理学、病理学、臨床獣医学などで、実験動物から産業動物、ペット、野生動物まで幅広い動物を研究対象とします。
国家資格である獣医師免許取得を前提とした実践的な教育が行われ、人と動物の健康を守る医療従事者としての側面が強い学部です。
一方で農学部は、家畜(牛・豚・鶏など)に限定し、その繁殖、育種、飼養管理、衛生管理、畜産物の品質向上などを通じて、安全な食料生産を目指します。
目的は医療ではなく「安定供給と効率的な生産」であり、経済性や生産システム全体を見据えた研究が求められます。
さらに、農業経済学や地域振興とも結びつき、農業全体の発展を見据えた幅広い学びができる点も特徴です。
環境学部・地球環境学科など
環境学部や地球環境学科は、地球規模の環境問題に対する科学的理解と社会的解決を目指す学問領域です。
気候変動、大気汚染、生態系の保全、再生可能エネルギー、環境政策などを対象に、理系と文系の知見を融合させながら研究を進めます。
その目的は、自然と人間活動の調和をはかり、持続可能な社会システムを構築することにあります。
一方で農学部も、持続可能性や環境保全に強い関心を持ちますが、焦点は農業・林業・水産業といった生物資源の利用と環境との関係にあります。
農地、森林、水域、生態系などを舞台に、資源の活用と環境保全を両立させるための具体的な技術や制度を研究します。
たとえば、農薬や肥料の使用が環境に与える影響の分析、持続可能な農法の開発、環境負荷の少ない畜産管理などがその一例です。
の違いを正しく理解し、自分の価値観や興味と照らし合わせて判断することが大切です。進路選択のポイント
理系の進路選択では、単に得意・不得意だけでなく、自分がどのような問いに興味を持ち、どのような形で社会に関わりたいかを考えることが重要です。
数学・化学・生物といった主要科目は、それぞれが異なるアプローチで世界を捉えています。
進路を選ぶ際は、そ
以下に、進路選びにおいて意識したい観点を紹介します。
興味関心の深堀り
進路を考えるうえで最も基本となるのは、自分が心から「面白い」と思える対象を見つけることです。
数学なら論理構造の美しさ、化学なら物質の仕組みを解明する楽しさ、生物なら生命の神秘や複雑さに惹かれるかもしれません。
どの分野に最も好奇心が刺激されるかを突き詰めて考えることで、進むべき道が見えてきます。
授業中に感じた疑問や面白さを思い出し、教員に質問をぶつけてみるのも良いでしょう。
分野ごとの魅力や難しさを具体的に体感することが、進路選択の重要なヒントになります。
何を探求したいのか考える
将来、どのような課題に対して自分の知識を活かしたいのかを考えることも進路選びの軸になります。
たとえば、数学を用いてAIや暗号理論を探究したい、化学の力で新素材や医薬品の開発に貢献したい、あるいは生物学を通じて病気や食料問題の解決に関わりたい、など多様なテーマがあります。
明確な課題意識がない場合でも、各学科の研究テーマを調べることで、自分の興味とつながる分野が見つかるかもしれません。
研究室や卒論テーマの事例から、「自分なら何を掘り下げたいか」をイメージしてみると、選択の手がかりになります。
各分野の学びの特性を理解する
理系の各学科には、学ぶ内容やアプローチに違いがあります。
数学科は抽象的な構造や論理の体系を扱い、理論に強く関心がある人に向いています。
化学科は物質の構造や反応の仕組みを追究し、実験と観察を通じて知識を深めます。
応用化学科はそれを実社会に応用する視点が加わり、材料や製品開発とのつながりが強いです。
薬学科は医療と薬の関係に特化し、国家資格取得を目指す専門職志向の学びです。
農芸化学や農学科は、生命・環境・食といった社会課題と向き合いながら応用力を育てます。
それぞれの特性を理解し、自分に合った学びの形を見極めることが大切です。
得意科目と適正を考慮する
進路選択では、興味に加えて自分の得意分野や適性を冷静に見つめることも重要です。
数学が得意で論理的な思考力に自信がある人は、数学科や情報系の分野で力を発揮できるかもしれません。
化学が得意で実験が好きな人は、化学科や応用化学科が向いている可能性があります。
生物に興味があり、観察や探究心を持って取り組める人は、生物学科や農学系が適しています。
各学科で求められる能力や学習スタイルを調べ、自分の強みが活かせる環境かどうかを見極めましょう。
将来のキャリアパスを考える
進路を選ぶ際は、将来どのような職業に就きたいかを具体的にイメージすることも重要です。
数学系は教員や研究者に加え、金融、データサイエンス、IT分野など分析力を活かす職種に広がりがあります。
化学系は製薬、化粧品、素材、食品などの研究開発職が多く、企業での需要も高いです。
生物系は医療、環境、農業、バイオ産業などで応用の場が広く、近年では再生医療や遺伝子工学といった最先端分野でも活躍できます。
各学科の卒業生がどのような進路を歩んでいるのか、大学の進路データやOB・OG訪問などを活用して情報収集しましょう。
以下では、農学部で学べることを一覧化して紹介します。
自身が学んだことと照らし合わせ、参考にしてみてください。
農学部で学ぶこと一覧

前述の通り、農業・林業・水産業など第一次産業に関する内容、微生物や遺伝子工学、有機化学などの基礎的な学問など、農学部では、広い範囲の学問を学ぶことができます。
以下では、農学部で学べることを一覧化して紹介します。
自身が学んだことと照らし合わせ、参考にしてみてください。
- 食品系
- 農学系
- 微生物系
- 畜産系
- 海洋・水産系
- 遺伝子工学系
- 農芸化学系
- 林業系
- 土壌系
- 有機化学系
- 地球環境系
- 獣医学系
- 農業工業学系
- 農業経済系
食品系
農業や水産業、畜産などで生産されるものは食品の原材料になります。そのため、農学部では食品系の学問について学ぶことができます。食品の加工や保存、あるいは腐敗防止など、原材料から消費者の口に届くまでの一連の流れに関することを学べるでしょう。
食品の栄養素に着目したり、食感について研究したり等、食品に関する多種多様な研究が行われている分野とされています。
農学系
農学部では、農学系の学問を学ぶことができます。農作物の生産性向上や品種改良など、農業に関する広い範囲が対象です。専門課程に進めば、研究室での実験だけでなく大学付属の農場で実習も経験できる場合があります。
微生物系
醸造や発酵などのような、微生物を応用して農産物を人間に有用な食品に加工する研究を行っている大学が多くあります。
工学部にも発酵はありますが、農学部発祥の学問であるとされています。また、生産性の観点から土中の微生物関連の内容を研究しているところもあります。
畜産系
牛・豚・鶏などの家畜の飼育や改良などが畜産系になります。家畜の健康維持、品種改良や品質向上、肉・乳の加工・保存や安全性確保など、畜産に関する一連の内容を学ぶことができます。牧場経営など経営に関する内容も畜産系の学問の対象範囲です。
家畜の健康維持や病気予防など、獣医系と学ぶ内容が重なる部分も多いのも、畜産系の特徴です。
家畜だけでなく、その家畜を育てるための草地に注目して研究している大学もあります。
海洋・水産系
海洋・水産系の学科も農学部です。魚介類や海藻などの捕獲・採集・養殖のような漁業関連の知識を学ぶことができます。資源保護や収穫量の向上など、水産資源に関連した経済的な観点の内容もあります。
マグロの完全養殖や、謎が多いウナギの生態の解明など、時代の先端を行く研究を行っている大学もあります。また、最近よく話題に取り上げられる漂流ゴミやマイクロプラスチックなどの海洋環境保護に関する研究を行っているところもあり、注目される学系でしょう。
遺伝子工学系
農作物の品種改良に関連して、遺伝子工学系の学問を学ぶこともできます。遺伝子組み換えで病気に強い品種や、害虫を避けることができる品種を作るなどが、この分野に当たります。
理学や工学にも遺伝子を扱う学科はありますが、農学では農作物の品種改良のように農業に直接関連している内容を扱っているところが多いのが特徴です。具体的には、カイコや稲、テンサイ、ホウレンソウなど産業上重要な生物の遺伝子研究を行ったりするところもあります。
農芸化学系
農芸化学とは、農業が対象としている植物や動物、微生物の働きなどを、化学の切り口から研究する学問です。発酵などを酵素という化学物質として捉えたり、害虫駆除の農薬を研究したりするなど、基礎から応用まで多様な研究が行われています。
理学や工学の化学系学科との違いは、上記の遺伝子工学系と同じく、農業に直接関連する内容を化学の切り口で取り扱っているところでしょう。
林業系
高性能木質材料の開発、木材パルプやバイオエタノールのような木材利用はもちろん、森林育成、森林環境改善など、林業に関する広い分野が対象です。
地球温暖化を防ぐための温室効果ガスの排出抑制など、世界的に注目されている研究を行っているところも、林業系の特徴といえます。
変わったところでは、森林に関連するものとして野生動物や昆虫、きのこなどの菌類を研究しているところもあります。
土壌系
農産物の安定生産と収穫量向上のために、土壌そのものを研究する分野が土壌系です。土の構成成分や含まれる栄養素、土壌中の昆虫やミミズなどの生き物、土中の微生物、土の保水性など研究対象は広範囲にわたります。
土を通して、地球温暖化などの気候変動に関する研究を行っているところもあります。
有機化学系
農芸化学よりもさらに突っ込んだ、天然に存在する化合物そのものを研究する有機化学系の学科も、農学部にはあります。生理活性のある有機化合物の医薬への応用などが対象です。生物有機化学あるいは天然物化学という表現がされている場合もあります。
理学や工学にも、有機化学を研究している学科・研究室はありますが、上述の遺伝子や農芸化学と同様、農学での有機化学系の特徴は、農業に直接関連する内容を有機化学の切り口から研究するところでしょう。
地球環境系
農業や水産業、林業などを個別に対象とするのではなく、生態系全体を包括的に捉えて、地球環境全般を対象とした学問を行っているところもあります。
地球環境保全の観点から、砂漠の緑化や国土保全のための水管理なども研究テーマとして取り上げられています。
獣医学系
家畜やペットなどの病気予防やケガの治療など、動物全般を対象にした医学を学ぶ学科です。動物の生態を個体レベルだけでなく、分子レベルや遺伝子レベルで研究しているところもあります。
農学部のほかの学系と異なり、獣医師の資格を取得するためには6年の修業年限の後に、獣医師国家試験に合格することが必要です。
出典:獣医師国家試験:農林水産省
参照:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/shiken/shiken.html
農業工業学系
農業工業とは、高齢化などでの就農人口減少に対して、工学的な観点から解決策を考える学問です。農業農村工学と表現している場合もあります。
水や土地の有効利用や環境保全、自然エネルギーの利用などに対して、工学的なアプローチで取り組んでいるところもあり、農学と工学の学際の学系といえるでしょう。農業法人等による集約化や機械化による農作業の効率化や生産性の向上などに取り組んでいるところもあります。
農業経済系
農業経済系は、農産物の生産や流通などを、経済学の切り口から捉えて考える学問です。農場での生産から流通、消費まで、経済的な観点で農業を捉えて、自然科学と社会科学の学際的な領域に当たる分野といえます。
農場経営のような地域ローカルな内容はもちろん、国家間の食物移動である食糧自給率や世界的な飢餓など、国内の課題から世界的な問題まで、広く取り組むことができる学科です。
農学部と関係が深い業界

農学部は上記の通り、幅広く多種多様な内容を学ぶことができる学部です。そのため、卒業後の就職先として考えることができる業界も幅広くあります。以下では、その中から代表的ないくつかを取り上げます。
食品
農産物は食品の原材料となるため、食品業界とは深い関係にあります。一口に食品業界と言っても、乳製品や製菓などの加工食品系から、食肉や水産品などの食材系の企業、ジュースやアルコールのような飲料系企業など、さまざまな企業があります。
加工食品系業界では、乳製品や製菓以外でもハムやベーコンなどの肉製品、ケチャップや調味料、製パン業なども加工系の業種です。
近年では健康志向から、特定保健用食品や機能性表示食品が注目されており、そのようなものを製造している企業にも、農学部出身者が多く進んでいるとされています。
農林・水産
農学部の実習などで学んだことを直接活かせる、農業や林業、水産業などの第一次産業の業界も、農学部と関係が深い業界です。現場系の仕事が多いことがこの業界の特徴と言えます。
農業法人などの大規模農業企業や牧場・養豚場や養鶏場などの畜産系企業、森林組合や木材を作る製材加工会社、水産加工会社などが、農林・水産系業界への就職の代表例でしょう。
高い生産性が得られる改良された種や苗、新種の花卉などの開発を行っている種苗メーカーなども、農業系の企業と言えます。
公社・団体・官公庁
農研機構や森林研究・整備機構、水産研究・教育機構のような国立研究開発機構や独立行政法人、都道府県の農業試験場、地方公共団体の農政課など、公社・団体・官公庁には多くの就職先候補があります。
また、JICA海外協力隊で野菜栽培指導を行うことなども、公社・団体・官公庁への就職といえるでしょう。
農学部の進路

上記では、農学部を卒業した人の就職先として関係の深い業界を取り上げました。以下ではそれらの業界に卒業生が進んだ場合に、就くことが多い職種・仕事内容について解説します。
研究・技術者としての道が多い傾向ですが、それだけではなく実業系の仕事もあるため、気になっている人は参考にしてみてください。
- 農業
- 農業系研究・技術者
- バイオ技術者
- 食品系研究・技術者
農業
農学部出身者で農業に就く人は多いでしょう。家業の農家を継ぐために農学部に入ったという人もいますが、実家が農家ではない人も、農業に就くことはできます。
近年、少子高齢化の影響で、農業を継続できなくなり辞める農家が増え、耕作放棄地が増えていることが問題になっており、このような農地を再生・集約化し、大規模農場を経営するという農業法人が増えています。このような農業法人も農学部出身者の就職先となるでしょう。
農業系研究・技術者
農学部の卒業生の進路として多いのが、農業系研究・技術者の道です。都道府県の農業試験場や畜産試験場のような地方独立行政法人が主な就職先となります。また、国立研究開発法人や独立行政法人も進路としては考えられ、前述の農研機構などはその代表格と言えるでしょう。
上記は国や地方公共団体の職員としての研究者の道ですが、企業に就職して研究・技術者として進むという道もあります。種苗メーカーなどは、品種改良された種や苗の開発を継続的に行っており、そのような会社に入って研究職に就くということもできるでしょう。
農学部を卒業した後、大学院に進んで修士号や博士号を取得して、そのまま大学に残って助教や准教授、教授などの教育者としての道を歩む人もいます。
バイオ技術者
農学部では微生物系や遺伝子工学系の学問を学ぶことができます。そのため、バイオ技術者になる人も多いと言われています。製薬会社や化粧品会社などが主な就職先になると言われていますが、遺伝子組み換え技術を活かした、種苗メーカーという進路もあるでしょう。
上述の通り、理学や工学のバイオテクノロジーと比較して、農学部で学ぶバイオテクノロジーは品種改良や遺伝子操作による新種開発など、農業に直接関わる内容が多いため、種苗メーカーなどの技術には活かされやすいと言えます。
食品系研究・技術者
農作物は食品の原材料であるため、農学部卒業生の就職先で食品系企業は多いと言えるでしょう。特に農学部では、食品加工や保存、発酵など食品に関連する多くの学問を学ぶことができるため、その知識を活かして食品系の会社に進み、研究・技術者になる人は多いとされています。
新製品開発や既存製品の改良などはもちろんですが、生産技術の改良・向上、保存・流通技術の改良・開発、賞味期限や消費期限を延長する新技術の開発など、農学部出身者が活躍できる食品系研究・技術の仕事は多いと言えるでしょう。
農学部の学系や卒業後の進路を理解しよう

本記事では、農学部で学ぶことができる学問・学系や、卒業後にどのような就職先があるのか、どのような職種に就くことができるのか進路についても紹介してきました。
農学部への受験を考えている人、農学部を目指して勉強を開始している人、既に農学部に在籍していて今後の進路について迷っている人などは、この記事を参考に、農学部に対する理解を深めて、今後の進路を検討してみてください。