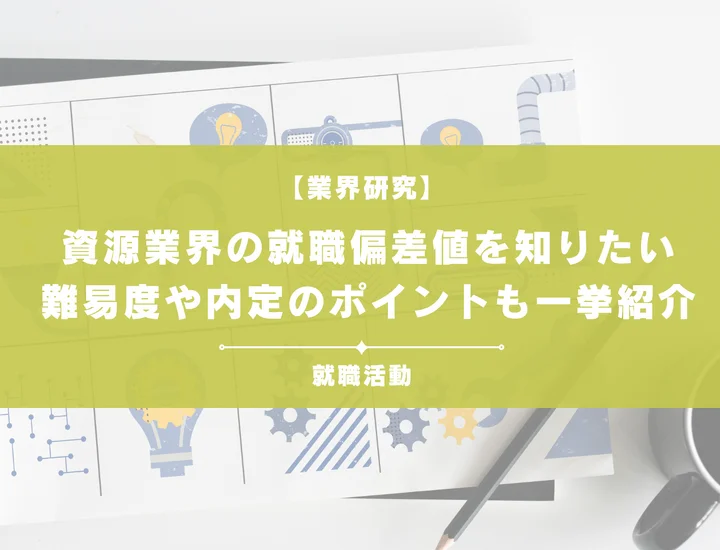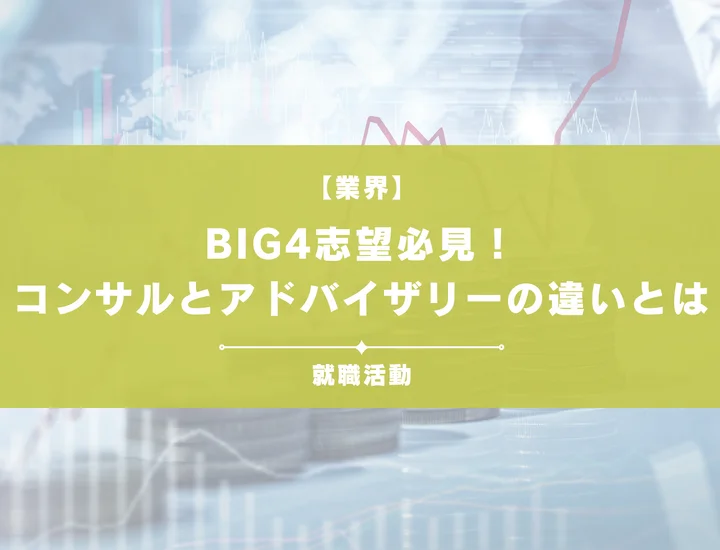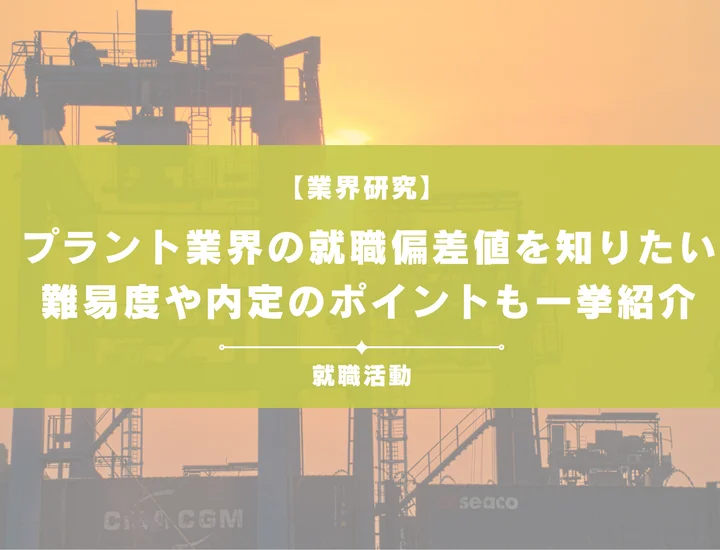HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
「製薬会社で働きたいけど、どんな仕事があるの?」 「製薬会社って人気が高くて就職が難しそう」 「製薬業界の現状や動向は?」 現在就職活動や転職活動をしている人の中には、製薬会社に勤めたいと思っている人もいるでしょう。また、それに向けて修士課程や博士課程に在籍している学生さんもいるかもしれません。
この記事では、製薬会社で働く主な職種やその業務内容、製薬業界で求められる人材などを紹介します。また、製薬業界全体の動向なども併せて解説するため、業界研究の一助となるでしょう。
この記事を参考にして製薬業界の業界研究を進め、自分の足りないスキルを身につけるなど自分の強みを増やしてください。
【業界研究 製薬】そもそも製薬業界とは

就職活動において業界研究は欠かせません。業界研究をすることで、志望動機に説得力を持たせるだけでなく、志望業界を絞ったり視野を広げたりすることができます。
業界研究に着手する前に、そもそも製薬業界とはどんな業界なのかを解説します。
製薬業界のビジネスモデル
製薬会社は医薬品を製造し、病院や薬局・薬店で患者に販売して利益を出します。医薬品の大半は製薬会社から卸売会社を経由して最終的に患者に提供され、各段階において収益が発生するというのが、製薬業界のビジネスモデルです。
また、製薬会社は新薬の研究開発も担っています。新薬の承認を得るまでに多くの年月と何百億円という費用をかけます。新薬の発売後は独占販売が認められますが、特許期間終了後にジェネリック医薬品(後発医薬品)が登場すれば、急激に売上が落ち込むでしょう。
医薬品の種類
医薬品には医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、新薬、ジェネリック医薬品の5種類があります。
医療用医薬品は医師の処方箋に基づいて薬剤師が調剤する薬です。要指導医薬品は医療用医薬品から一般用医薬品に転用されたばかりの薬で、薬局などで薬剤師から対面で購入する必要があります。
一般用医薬品は有効成分の含有量が少なく、薬局やインターネットで購入が可能です。新薬は国からの承認を受けて発売された医薬品で、発売後一定期間独占販売が認められています。
ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間満了後に新薬と同等の効果があると国の承認を得た医薬品のことです。
出典:くすりの種類|日本製薬工業協会 参照:https://www.jpma.or.jp/about_medicine/guide/type/index.html
出典:医薬品の種類・分類|東京都健康安全研究センター 参照:https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/kj_shoku/qqbox/shurui/
【業界研究 製薬】製薬業界の動向

かつて、日本の薬剤研究のレベルは欧米に比べて低く、日本は輸入薬に頼っていました。しかし、1883年に日本初の製薬会社である大日本製薬会社が設立されて以降、日本の製薬技術も急速に前進しました。
製薬業界の最近の動向を見て、業界研究に活かしましょう。
出典:大日本製薬(株)『大日本製薬六十年史』(1957.05)|渋沢社史データベース 参照:https://shashi.shibusawa.or.jp/details_basic.php?sid=3840
市場規模
厚生労働省の「令和2年 薬事工業生産動態統計年報の概要」によると、令和2年の医薬品生産金額は前年比1.9%減の9兆3,053億円でした。
また、令和2年度の国民医療費(電算処理分)31.3兆円において調剤医療費(電算処理分)は7.5兆円を占めています。
出典:令和2年 薬事工業生産動態統計年報の概要|厚生労働省 参照:https://www.mhlw.go.jp/topics/yakuji/2020/nenpo/
出典:医科医療費(電算処理分)の動向|厚生労働省 参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000823975.pdf
出典:調剤医療費(電算処理分)の動向の概要|厚生労働省 参照:https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/20/dl/gaiyo_data.pdf
薬価改定による価格引き下げの影響
近年少子高齢化などによって医療費が増加しているうえ、医療費における調剤医療費はおよそ4分の1までに達しています。このような事態を鑑みて国は薬価の引き下げを強化し、膨れ上がった薬剤費用を抑制する政策を打ち出しています。
厚生労働省の発表によると令和4年度の薬価基準改定による改定率は、医療費ベースで1.35%減、薬剤費ベースで6.69%減です。このように、製薬市場は近年の薬価改定による価格引き下げの影響を受けて縮小傾向にあります。
出典:令和4年度 薬価基準改定の概要|厚生労働省 参照:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000942947.pdf
コロナによる影響
新型コロナウイルス感染症が世界で拡大したため、海外の大手製薬会社だけでなく国内の各製薬会社もワクチンや治療薬の開発に取り組んでいます。
一方で、新型コロナウイルスへの感染リスクを警戒した患者の受診抑制によって、医薬品の需要は減少、または停滞しています。新型コロナウイルス感染症が製薬業界に与える影響は一時的である可能性もありますが、各社厳しい状況が続くでしょう。
海外でのシェア拡大がポイント
日本では、前述した薬価改定による薬価引き下げ政策は継続されると予想されます。さらに、ジェネリック医薬品の普及拡大などによって、製薬会社はますます厳しい状況が到来するでしょう。
そのため、より大きな市場規模が期待できる国外でのシェア拡大がポイントとなります。特に、経済成長が著しい新興国における需要の増大が重要です。
AI技術の活用
膨大な費用と時間を要する新薬の開発が世界レベルに追いつくために、ICT技術との融合が1つの打開策として大いに期待されています。
特に、注目されているのがディープラーニングなどのAI技術の活用です。これにより、新薬の候補となる物質をより迅速に検索でき、新薬の開発に投じる時間を大幅に短縮できるため、現在積極的に検討されています。
【業界研究 製薬】製薬業界の職種は?

就職活動における業界研究に伴って、職種の研究も大切になります。製薬会社は新薬の研究・開発から製造、販売まで事業展開しており、それらの業務を担う職種があります。
理系の学生は主に研究職や開発職、生産職、MR(医薬情報担当者)、文系の学生はMR(医薬情報担当者)や事務職を志望する場合が多いでしょう。
ここでは製薬会社ならではの職種とその業務内容を紹介します。
研究
製薬会社の研究職は理系の就職先として人気のある職種で、薬剤の実験やその結果分析が主な業務です。
創薬研究職は部門ごとに班で研究を進め、医薬品の基礎研究から新薬候補物質の有効性・安全性を動物を用いて確認する前臨床研究まで幅広く携わります。
製薬会社の研究職に就くには、ほとんどの場合理系の修士もしくは博士の取得が必要です。また、実験・分析を進める論理的思考能力や最新技術を得るための探究心、英語力なども必要になります。
開発
開発職は臨床試験を行って新薬の開発をする職種です。製薬会社の開発職も研究職と同様、理系の修士もしくは博士の取得が必要であり、人気の職種なので採用を勝ち取るのは狭き門と言えるでしょう。
臨床試験は治験とも呼ばれ、動物実験で効果が確認された発売前の医薬品を、医療施設や被験者の協力のもと人体に投与し、その薬剤の安全性・有効性・安定性をチェックします。この臨床試験計画を立案するのも開発職です。
開発職は責任のある仕事であり、医療関係者などとのコミュニケーション能力も求められます。
MR(医薬情報担当者)
医療施設などで医薬品の有効性や安全性などの情報提供や情報収集を行うのがMR(Medical Representatives:医薬情報担当者)です。
製薬会社の営業部門に属し、自社の医薬品を医療機関に販売・流通させることが主なミッションです。文系の学生も応募することができますが、製薬会社によってMRの育成手法やビジネスモデルは異なるため、MRの専門的知識の習得レベルには差があるでしょう。
MRは自社製品の売上に直結する職種であり、コミュニケーション能力だけでなく、医薬品に対する幅広い知識や対応力なども必要になります。
薬事職
薬事職は、製薬業界の中でも特に専門性の高い仕事の一つです。
医薬品や医療機器は、開発が完了すればすぐに販売できるわけではなく、厚生労働省などの公的機関から製造販売の承認を得る必要があります。
この承認申請に関わる業務を一手に担うのが薬事職です。
具体的には、治験や臨床試験で得られたデータを整理し、法的に求められる形式に沿って申請書類を作成します。
さらに、行政とのやり取りを通じて審査を進め、必要に応じて追加の資料を提出したり、説明を行ったりします。
こうした手続きを適切に進めなければ、せっかく開発した薬が患者に届くことはありません。
専門知識だけでなく、法規制の正確な理解や書類作成の正確性が求められる仕事です。
広報・マーケティング
広報・マーケティング職は、製薬業界の中で企業の顔ともいえる役割を担っています。
単に製品を宣伝するだけでなく、市場のニーズを分析し、医療従事者や患者にとって本当に必要とされる情報を届けるのが使命です。
業務内容としては、市場調査を行い、どのような薬が求められているのかを把握することから始まります。
その結果を踏まえ、製品の強みを活かした戦略を立案し、実際のプロモーション活動につなげます。
また、企業や製品の信頼性を高めるために、学会発表やメディア対応を行うのも広報の大切な仕事です。
マーケティングでは、単に売上を追うのではなく、医療現場の課題解決に貢献する視点が求められます。
製薬業界における広報・マーケティングは、企業の成長と社会的信頼の両方を支える役割を持つため、非常にやりがいのある仕事です。
【業界研究 製薬】製薬業界大手5社
製薬業界は人々の健康を支える極めて重要な産業であり、日本には世界的にも存在感を放つ大手企業が複数存在しています。
以下では、日本の製薬業界を代表する大手5社について、それぞれの特徴や強みを詳しく見ていきます。
武田薬品
大塚製薬
アステラス製薬
第一三共
中外製薬
武田薬品
武田薬品は国内シェア1位を誇る日本最大の製薬会社であり、グローバル展開でも大きな存在感を持っています。
特に2019年のアイルランドの製薬会社シャイアー買収によって、世界中に幅広い研究拠点と販売網を確立しました。
消化器系疾患やがん、中枢神経系疾患、希少疾病などを重点領域に掲げ、先端的な創薬を進めています。
武田薬品の企業文化としてよく語られるのがタケダイズムと呼ばれる価値観です。
これは誠実さ、公正さ、正直さ、不屈の精神を重んじ、患者や社会の信頼に応える姿勢を示しています。
また、環境や社会貢献にも積極的で、持続可能な医療を提供することに注力しています。
こうした姿勢から、国内外で高い評価を受けるとともに、日本を代表するグローバル製薬企業としての地位を確立しています。
大塚製薬
大塚製薬は医薬品事業とニュートラシューティカル事業の二本柱で成長を続けている企業です。
医薬品事業では、中枢神経系疾患やがん領域を中心に研究開発を進めており、抗精神病薬や抗がん剤の分野で世界的に高い評価を得ています。
一方、ニュートラシューティカル事業では栄養補助食品や飲料を展開し、ポカリスエットやカロリーメイトといったヒット商品を生み出しました。
研究技術職や生産職は、基礎研究から製造に至るまで幅広い分野に携わることができるのが特徴です。
また、病気予防から治療までを一貫して支える製品開発を進めており、ヘルスケア全体を見据えた活動を行っています。
大塚製薬は独創的な発想を大切にし、他社にないユニークな製品を世に送り出す姿勢を貫いている点が強みです。
アステラス製薬
アステラス製薬は山之内製薬と藤沢薬品工業の合併によって誕生した企業で、グローバルに事業を展開しています。
前立腺がん治療剤エンザルタミドや、過活動膀胱治療薬ミラベグロンなどを主力製品とし、これらは世界各国で高い販売実績を誇ります。
重点領域をオンコロジー(がん)、免疫、神経疾患などに定め、革新的な医薬品の研究開発に力を入れています。
また、グローバル販売を積極的に行い、海外売上比率が高いのも特徴です。
研究開発では、再生医療や細胞医療といった次世代医療技術にも挑戦しており、将来的な成長分野に注力しています。
アステラス製薬は「先端と信頼の医薬を創造し、人々の健康に貢献する」という理念を掲げ、世界中でその存在感を高め続けています。
第一三共
第一三共は抗がん剤の分野で特に強みを持ち、グローバル創薬企業を目指して活動しています。
近年は抗体薬物複合体(ADC)と呼ばれる新しい治療法に注力し、その技術は世界的にも注目を集めています。
幅広い製品ラインナップを持ち、高血圧症治療薬や糖尿病治療薬など生活習慣病領域でも実績があります。
研究開発の国際化も進めており、欧米の大手企業とも提携しながら新薬を開発しています。
また、社会貢献性を重視し、がんや希少疾患といった未充足の医療ニーズに応える活動を進めているのも特徴です。
国内外で研究拠点を持ち、グローバル企業としての成長を加速させており、日本の製薬業界を代表する存在となっています。
中外製薬
中外製薬は独自のバイオ技術を強みとし、がんや免疫疾患などの分野で革新的な医薬品を開発しています。
特にスイスの製薬大手ロシュとの戦略的アライアンスを背景に、世界規模での研究開発体制を構築しています。
この提携により、ロシュの研究成果を国内市場に展開できる一方、中外製薬の技術を海外に広げることも可能になっています。
主力製品には抗がん剤アバスチンや免疫治療薬アクテムラなどがあり、いずれも世界的に高い評価を受けています。
また、バイオ医薬品の分野では日本を代表する企業であり、最先端の技術開発をリードしています。
独自の研究力とグローバルネットワークを兼ね備え、世界の医療に大きく貢献しているのが中外製薬の大きな特徴です。
【業界研究 製薬】働く魅力ややりがい
製薬業界は人々の健康や命に直結する分野であり、その社会的な意義は非常に大きいです。
病気の治療や予防に欠かせない薬を扱うため、需要が途切れることはなく、安定性や将来性の高さが魅力の一つです。
ここでは、製薬業界で働く際に得られる大きな魅力について詳しく解説していきます。
安定している
製薬業界の大きな魅力は、社会における需要が安定していることです。
薬は人が生きていくうえで必要不可欠なものであり、病気にかかる人がゼロになることはありません。
生活習慣病や感染症、さらには高齢化に伴う疾患など、薬が必要とされる場面は年齢や世代を問わず常に存在しています。
また、大手企業を中心に研究開発や製造体制が整備されており、社会全体に薬を安定的に供給する仕組みが構築されています。
医療は国の制度によっても支えられているため、他業界に比べて急激な需要減少や大規模な人員削減のリスクが少ない点も特徴です。
このように、製薬業界は安心して長期的に働ける環境が整っていると言えます。
高収入
製薬業界のもう一つの大きな特徴は、給与水準が非常に高いことです。
製薬会社の平均年収をランキングで見ると、上位の企業はすべて1000万円を超えており、他の業界と比べても高い水準にあります。
これは研究開発に莫大な投資が必要である一方、その成果が新薬として市場に出た際に大きな収益を生み出すビジネスモデルが背景にあります。
また、世界的に競争力を持つ日本の大手製薬企業は、海外市場での売上も高く、グローバルに活躍できる点も収入面の安定につながっています。
営業職や研究開発職など職種によって給与の差はありますが、どの分野でも専門性が求められるため、他業界より高い待遇が設定されやすいのです。
高収入という点は、生活の安定だけでなく自己成長や家族を支える基盤としても大きな魅力になります。
社会課題を解決に貢献できる
製薬業界で働く最大のやりがいは、人々の健康や社会課題の解決に直接貢献できることです。
新薬の開発や既存薬の改良は、これまで治療が困難だった病気に光を当てることにつながります。
がんや難病、感染症など多くの疾患に対し、新たな治療薬を提供することは患者本人だけでなく家族や社会全体に大きな影響を与えます。
また、高齢化社会では認知症や生活習慣病への対応が求められており、製薬業界はその最前線で解決策を生み出しています。
感染症対策では、パンデミックに対するワクチンや治療薬の供給が社会全体を守る手段となり、国際的な責任も果たしています。
こうした取り組みを通じて、自分の仕事が社会の課題を解決しているという実感を持てるのは、製薬業界ならではの魅力といえるでしょう。
【業界研究 製薬】求められる人物像
製薬業界は、人の命や健康に直結する仕事を担っているため、他の業界以上に求められる人物像がはっきりしています。
薬の研究・開発・販売のすべてにおいて厳格な規則があり、常に高い倫理観と責任感が必要です。
ここでは、製薬業界で特に求められる代表的な人物像について詳しく解説していきます。
責任感がある人
製薬業界では、薬の成分や投与量によっては思いがけない副作用が発生し、患者に深刻な健康被害をもたらすリスクがあります。
そのため、仕事に関わるすべての人に高い責任感が求められます。
研究開発の現場では一つのデータの誤りが大きな損失や事故につながる可能性があり、品質管理や薬事業務でも規則を正しく理解し遵守する姿勢が不可欠です。
また、営業やマーケティングにおいても、誇張や誤解を招く説明は重大なトラブルを生み出すため、常に正確さと誠実さが必要とされます。
製薬業界は利益を追求する一方で、人の命を守る使命を持つ業界です。
そのため倫理観や正義感を持ち、自らの行動に責任を持てる人材が求められます。
短期的な成果だけを重視するのではなく、長期的に社会に役立つ医薬品を提供するという意識が欠かせません。
コミュニケーション能力が高い人
製薬業界では、研究者や医師、規制当局、さらには患者まで幅広い人々と関わります。
そのため、物事を論理的に整理し、相手にわかりやすく説明できる能力が重要です。
新薬の効果や安全性を伝える際には、専門用語を多用するのではなく、相手の立場に合わせた言葉を使うことが信頼につながります。
営業職では医師や薬剤師と信頼関係を築くために丁寧な対話が欠かせず、研究職でもチームで成果を出すためには情報を正確に共有する力が必要です。
また、グローバル展開している製薬会社では海外の研究者や現地法人とのやり取りも多く、異文化理解や語学力を伴ったコミュニケーション力が求められます。
単に話すだけでなく、相手の意見を受け止め共感しながら調整できる姿勢は、プロジェクトを円滑に進めるうえで欠かせません。
まとめ
製薬業界は人々の健康と命に直結する重要な分野であり、薬事や研究開発、営業やマーケティングなど多様な職種が連携して支えています。
また、安定した需要と高収入の魅力があり、社会課題の解決にも貢献できる業界として大きな可能性を広げています。
この記事を参考に、是非製薬業界への就職を成功させてください。