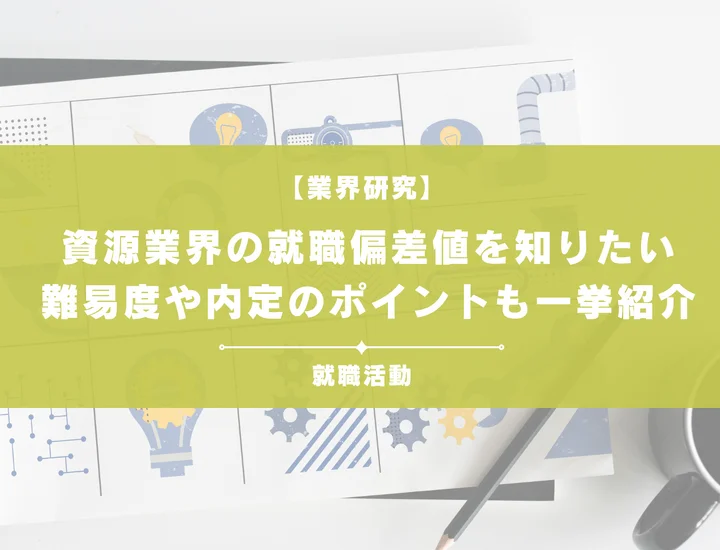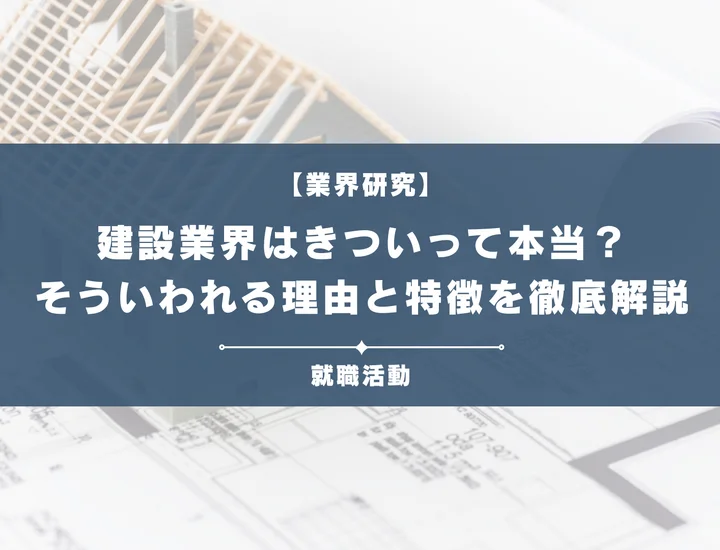HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
この記事を読めば、資源業界のリアルな姿と、あなたが活躍できる可能性が見えてくるはずです。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
「就職偏差値」という言葉、就活を始めるとよく耳にしますよね。
これは、特定の企業や業界の「入社難易度」を、予備校の偏差値のように分かりやすく数値で表したものです。
これは選考の倍率、内定者の学歴、企業の人気度、年収や待遇など、さまざまな要素を総合的に考慮して算出されることが多く、就活生が企業選びをする上での一つの目安として利用されています。
ただし、この偏差値はあくまで「目安」であるこを忘れないでください。
偏差値が高いからといって自分に合っているとは限りませんし、逆に低いからといって魅力がないわけでもありません。
大切なのは、その数字の背景にある理由(なぜ人気なのか、どんな人が求められているのか)を理解し、自分の価値観やキャリアプランと照らし合わせて考えることです。
この記事では、資源業界の偏差値ランキングを紹介しますが、それを鵜呑みにせず、自分なりの企業研究を深めるための「きっかけ」として活用してくださいね。
資源業界の就職偏差値ランキング
それでは、さっそく資源業界の就職偏差値ランキングを見ていきましょう。
この業界は、石油、天然ガス、石炭、金属鉱物など、国の経済活動を根幹から支える重要な役割を担っています。
そのため、事業規模が非常に大きく、高い安定性や将来性を持つ企業が多いのが特徴です。
一方で、事業の性質上、高度な専門知識や技術力が求められることや、事業所が国内外の特定の地域に集中しがちな面もあります。
こうした業界特性が、就職偏差値にも反映されています。
一般的に、資源の探査・開発(上流)を手がける企業や、国内外に強力な販売網を持つ大手企業は、その影響力の大きさや待遇の良さから就活生の人気が集中し、結果として偏差値が高くなる傾向にあります。
ここでは、ランクごとによく名前が挙がる企業や、そのランク帯の企業群の傾向について解説していきます。
【資源業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】INPEX
日本の石油・天然ガス開発(E&P)業界の頂点に君臨する企業です。
石油・ガスという国のエネルギー安全保障の根幹を担うため、その重要性と待遇、安定性から人気が集中します。
最高水準の学歴や専門性に加え、海外プロジェクトを遂行する卓越した語学力とタフネスが求められる最難関企業です。
【資源業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ資源業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】ENEOS JX石油開発
【68】出光興産 エクソンモービルジャパン
【67】石油資源開発 住友金属鉱山 三井石油開発
【66】コスモエネルギー JX金属 シェブロンジャパン BPジャパン
石油元売り大手(ENEOS、出光)、非鉄金属メジャー(住金、JX金属)、有力E&P企業、そして外資系石油メジャー(スーパーメジャー)が並びます。
いずれも巨大な資本力と安定性を誇る、業界のリーディングカンパニー群です。
エネルギー・資源市場への深い理解と、グローバルな視点が不可欠です。
外資系企業は、Aランクに準ずる極めて高い英語力と専門性が求められます。
【資源業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】古河機械金属 三井金属鉱業 三菱マテリアル JX金属探開 アラムコ・アジア・ジャパン
【64】日鉄鉱業 富士石油 エネルギー・金属鉱物資源機構
【63】石原産業 日本海洋石油資源開発 サハリン石油ガス開発
【62】JFEミネラル 古河メタルリソース パンパシフィック・カッパー
【61】日本冶金工業
財閥系を含む大手非鉄金属メーカーや、政府系機関(JOGMEC)、特定のプロジェクト(サハリン)に従事する企業が中心です。
日本の産業基盤を支える重要なBtoB企業群です。
理系であれば材料・化学・地質などの高い専門性が、事務系であれば資源ビジネスへの深い理解が求められます。
JOGMECのような機関は、民間企業とは異なる公共的な視点も必要です。
【資源業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】中外鉱業
【59】東邦亜鉛 大平洋金属
【58】神岡鉱業 日比共同製錬 小名浜製錬 八戸製錬
【57】小坂製錬 彦島製錬 四阪製錬所
【56】秋田製錬
特定の金属の製錬(精製)を専門に行う企業や、ニッチな鉱物資源を扱うBtoB企業が中心です。
一般知名度は低いものの、産業サプライチェーンにおいて不可欠な役割を担っています。
就職活動の基本的な対策に加え、その企業が扱う特定の金属や技術への関心、そして製錬所などが立地する地域で働く意欲が問われます。
【資源業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】ゴールデン佐渡
佐渡金山のように、特定の鉱山(現在は観光施設)の運営など、非常にニッチな分野や特定の地域に根差した事業を行う企業です。
資源業界というよりは、観光や地域振興といった側面が強い場合もあります。
その企業が現在行っている具体的な事業内容(観光、地域貢献など)を深く理解し、そこで働きたいという明確な動機を伝えることが重要です。
【資源業界】とは
「資源業界」と一口に言っても、その範囲は非常に広く、奥深いものです。
この業界は、私たちの生活やあらゆる産業活動の源となる「資源」を社会に供給するという、極めて重要な使命を担っています。
具体的には、石油や天然ガスといった「エネルギー資源」から、鉄や銅、アルミニウム、さらにはスマートフォンなどに使われるレアメタルといった「鉱物資源」まで、地球が持つさまざまな恵みを取り扱い、社会が必要とする形に変えて届ける役割を担っています。
日本の産業を根底から支える、まさに「基幹産業」の一つと言えるでしょう。
このセクションでは、そんな資源業界の全体像を理解するために、基本的な仕組みや、そこで働く人々の主な役割について詳しく解説していきます。
基本的な仕組み
資源業界のビジネスは、その流れから大きく「上流(Upstream)」「中流(Midstream)」「下流(Downstream)」の3つに分けて理解するのが一般的です。
まず「上流」は、石油や天然ガス、鉱物資源が眠っている場所を探し出す「探査」と、それらを地中から掘り出す「開発・生産」の領域です。
資源の権益(採掘する権利)を確保するための国際的な交渉もここに含まれ、最もリスクが大きく、同時に大きなリターンを生む可能性があるビジネスの源泉です。
次に「中流」は、採掘された原油や天然ガス、鉱石を、パイプラインやタンカーなどで「輸送」し、精製所や製錬所に運ぶプロセスを指します。
また、運ばれてきた資源を「貯蔵」し、安定供給に備える役割も担います。
最後に「下流」は、中流から運ばれてきた原油をガソリンやプラスチック原料などに「精製」したり、鉱石から金属を取り出す「製錬・加工」を行ったり、さらにはそれらの製品を「販売」する領域です。
ガソリンスタンドや素材メーカーへの販売など、消費者に最も近いところでビジネスが展開されます。
企業によって、この上流から下流まで全てを一貫して行う「総合エネルギー企業」もあれば、特定の領域に特化した「専門企業」もあります。
主な役割と業務内容
資源業界での仕事は、前述した「上流・中流・下流」の各プロセスにおいて、非常に多岐にわたります。
「上流」では、地質学や物理学の知識を駆使して資源の埋蔵量を探査する「技術系」の仕事(地質学者、エンジニア)や、資源国政府や他企業と交渉して権益を獲得する「事務系」の仕事(渉外、法務、財務)があります。
「中流」では、巨大なタンカーやパイプラインのオペレーションを管理する「輸送・物流管理」や、原油やLNG(液化天然ガス)の売買を行う「トレーディング」といった仕事が中心です。
「下流」では、製油所や製錬所でプラントの安全・安定稼働を支える「生産管理」や「設備保全」のエンジニア、そして精製された製品を国内外の顧客に販売する「営業」や「マーケティング」の役割があります。
これら以外にも、全社的な戦略を立てる「経営企画」、脱炭素社会に向けた新技術を研究する「R&D(研究開発)」、そしてこれら全ての活動を支える「人事」や「経理」など、文系・理系問わず多様な専門性を持った人々が活躍しています。
自分の専門性や興味が、この壮大なバリューチェーンのどこで活かせるかを考えることが、業界理解の第一歩となるでしょう。
業界の将来性と課題
資源業界は、社会に不可欠なエネルギーや素材を供給するという重要な役割を担う一方で、現在「脱炭素」という世界的な大きな変革の波に直面しています。
地球温暖化対策として、石油や石炭といった化石燃料から、太陽光や風力などの再生可能エネルギーへの転換が求められているのです。
これは資源業界にとって大きな「課題」であると同時に、新たな「ビジネスチャンス」でもあります。
多くの資源企業は、従来の石油・ガス事業で培った技術や資本力を活かし、再生可能エネルギー(洋上風力、地熱、バイオマスなど)の開発に積極的に投資しています。
また、二酸化炭素を回収して地中に貯留する「CCS(Carbon Capture and Storage)」技術や、次世代エネルギーとして期待される「水素」や「アンモニア」のサプライチェーン構築にも力を入れています。
さらに、鉱物資源の分野では、使わなくなった製品から金属を回収する「リサイクル(都市鉱山)」の重要性が高まっています。
既存の資源ビジネスの安定供給責任を果たしつつ、いかにして新しい時代のエネルギー・素材産業へと変革していくか。
資源業界は今、非常にダイナミックな変革期を迎えており、これからの未来を創るという大きなやりがいがある業界とも言えるでしょう。
【資源業界】特徴
資源業界には、他の業界とは異なるいくつかの際立った特徴があります。
これらは、就職先としてこの業界を考える上で、非常に重要なポイントとなります。
例えば、プロジェクトの「期間」や「規模」が非常に大きかったり、ビジネスの舞台が「国内」に留まらなかったり、といった点です。
また、取り扱う商材が「コモディティ(商品)」であることも、ビジネスの難しさや面白さに直結しています。
これらの特徴を理解することは、自分がこの業界で働くことを具体的にイメージする上で大いに役立ちます。
「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぐためにも、資源業界ならではの「当たり前」を知っておきましょう。
ここでは、特に就活生の皆さんに知っておいてほしい3つの特徴をピックアップして解説します。
グローバルな事業展開と異文化理解
資源業界の最大の特徴の一つは、その事業が本質的にグローバルであることです。
日本は石油や天然ガス、金属鉱物といった資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。
そのため、資源を「開発」する上流部門の仕事は、必然的に中東、アフリカ、南米、オーストラリアといった資源国が舞台となります。
現地政府や地域住民、多様な国籍のパートナー企業と交渉し、協力しながらプロジェクトを進めていく必要があり、単なる語学力を超えた「異文化理解力」や「タフな交渉力」が求められます。
また、開発した資源を日本に運ぶ「中流」や、国内外の市場で売買する「下流」においても、国際的な市況や地政学リスクを常に把握しながらビジネスを展開する必要があります。
若いうちから海外駐在や出張のチャンスが豊富にあることは、グローバルに活躍したいと考える学生にとって大きな魅力と言えるでしょう。
逆に言えば、国内だけで完結する仕事をしたいという人には、あまり向かない業界かもしれません。
スケールが大きく長期的な視点
資源業界で動く「モノ」と「カネ」のスケールは、他の業界と比べても桁違いに大きいのが特徴です。
例えば、一つの油田やガス田を開発するプロジェクトには、数千億円から数兆円といった巨額の投資が必要となり、その準備から生産開始までには10年以上の歳月がかかることも珍しくありません。
また、非鉄金属の製錬所や石油の精製プラントなども、建設には莫大な費用と時間がかかります。
このように、一つのプロジェクトが非常に「大規模」かつ「長期的」であるため、そこで働く社員には、目先の利益にとらわれない長期的な視点と、粘り強さが求められます。
自分が関わったプロジェクトが形になるまでには時間がかかりますが、それが実現した時には、国家や社会のインフラを支えているという非常に大きなやりがいを感じることができます。
「地図に残る仕事」や「国の未来を創る仕事」といった言葉に惹かれる人にとっては、これ以上ないほど魅力的な環境と言えるでしょう。
高い安定性と社会貢献性
資源業界が取り扱うエネルギーや素材は、電気、ガス、水道と同じように、現代社会のあらゆる活動にとって「なくてはならないもの」です。
景気の変動によって需要が多少増減することはあっても、その需要がゼロになることはありません。
この「社会インフラ」としての側面が、資源業界の経営の「安定性」に繋がっています。
実際に、先に紹介した就職偏差値ランキングの上位企業は、その多くが長い歴史を持ち、安定した経営基盤を誇っています。
また、資源の安定供給を維持することは、国民の生活や日本経済を守ることに直結しており、非常に「社会貢献性」の高い仕事であると言えます。
特に、地震や台風といった災害時にもエネルギー供給を止めないように奮闘する姿は、この業界の使命感の表れです。
「誰かの役に立ちたい」「社会を根底から支えたい」という強い想いを持っている人にとって、資源業界は日々その使命感を実感しながら働ける場所です。
【資源業界】向いている人
ここまで資源業界の仕事内容や特徴を見てきて、「自分はこの業界でやっていけるだろうか?」と考え始めた人もいるかもしれませんね。
資源業界は、確かにスケールが大きく、グローバルな舞台で活躍できる魅力的な業界です。
しかし、その一方で、困難な交渉やタフな環境での業務、長期的な視点など、この業界ならではの厳しさも併せ持っています。
つまり、誰もが活躍できるわけではなく、特定の「素養」や「価値観」を持つ人がより輝ける場所であるとも言えます。
ここでは、就活アドバイザーの視点から、これまでの内定者や現役社員の方々の特徴を踏まえ、資源業界に「向いている人」の共通点を3つにまとめてみました。
自分自身に当てはまるかどうか、チェックしながら読み進めてみてください。
スケールの大きな仕事に挑戦したい人
資源業界の仕事は、前述の通り、動く金額やプロジェクトの期間、社会に与える影響のどれをとっても「スケールが大きい」のが特徴です。
数千億円規模の投資判断や、10年先、20年先のエネルギー需要を見据えたプロジェクトに関わることも日常茶飯事です。
こうした環境では、細かな作業を正確にこなす能力以上に、物事を俯瞰的に捉え、大きなビジョンを描けることが重要になります。
「自分の仕事が、社会や国の未来にどう繋がっているのか」を常に意識し、そこにやりがいを感じられる人が求められています。
学生時代の経験で言えば、例えば「大規模なイベントの企画・運営をゼロから立ち上げた」経験や、「長期的な目標を立てて、仲間を巻き込みながら達成した」経験などがある人は、その素養があるかもしれません。
目先の成果だけでなく、長期的な視点で大きなことを成し遂げたいという情熱を持つ人にとって、資源業界は最高の舞台となるでしょう。
グローバルな環境でタフに働ける人
資源業界とグローバルな環境は、切っても切れない関係にあります。
資源の多くを海外に依存する日本では、資源の探査・開発から調達、輸送、トレーディングに至るまで、あらゆる場面で海外との関わりが発生します。
そのため、英語をはじめとする語学力はもちろんのこと、異なる文化、価値観、商習慣を持つ人々と臆せずにコミュニケーションをとり、信頼関係を築ける能力が不可欠です。
また、赴任先は必ずしも先進的な都市部とは限らず、時にはインフラが未整備な僻地や、政治的に不安定な地域である可能性もゼロではありません。
そうした予期せぬ困難やストレスがかかる状況でも、心身ともに健康を保ち、冷静に課題を解決していける「タフさ」が求められます。
「海外留学で言葉も通じない環境に飛び込んだ」「厳しい環境下での部活動や研究を最後までやり抜いた」といった経験を持つ人は、この業界で必要とされるタフさを備えている可能性が高いです。
強い使命感と責任感を持てる人
資源業界の仕事は、社会のインフラを支えるという「使命感」と、安定供給を維持するという「責任感」に支えられています。
エネルギーや素材の供給が止まれば、工場は生産を停止し、病院の機能は麻痺し、私たちの日常生活は成り立たなくなってしまいます。
だからこそ、この業界で働く人々は、「自分たちが日本のエネルギー(あるいは産業)を守っている」という強い誇りと責任感を持って日々の業務に取り組んでいます。
たとえ地味な仕事であっても、それが社会の基盤を支えていることを理解し、最後まで手を抜かずにやり遂げる姿勢が重要です。
また、脱炭素という業界の大きな変革期においては、既存のビジネスを守る責任感と、未来の社会のために新しいことに挑戦する使命感の両方が必要とされます。
「誰かのために全力を尽くした経験」や「ルールや約束事を誠実に守り続けてきた経験」がある人は、この業界が求める「使命感」や「責任感」と強く共鳴できるはずです。
【資源業界】向いていない人
一方で、資源業界の特徴が、あるタイプの人にとっては「働きにくさ」につながってしまう可能性も否定できません。
例えば、非常に「安定」している業界ですが、働く環境そのものが「安定」しているかというと、必ずしもそうとは言えません。
グローバルな事業展開は、裏を返せば「転勤」や「海外赴任」の可能性が常にあるということでもあります。
また、プロジェクトの期間が非常に長いため、「すぐに成果を出したい」「短期間で結果が目に見える仕事がしたい」という人にとっては、もどかしさを感じるかもしれません。
ここでは、先ほどの「向いている人」とは対照的に、「資源業界にはあまり向いていないかもしれない人」の特徴を3つ挙げてみます。
もし当てはまる項目があっても落ち込む必要はありません。
これはあくまで傾向であり、大切なのは「自分は何を優先したいのか」を明確にすることです。
変化を好まず、安定志向が強すぎる人
資源業界の企業は経営基盤が「安定」していると述べましたが、働く個人のキャリアが「安定」しているとは限りません。
特に大手企業の場合、数年ごとに関わりの薄い部署へ異動するジョブローテーションが一般的です。
また、海外赴任や国内の事業所(製油所や製錬所は臨海部や地方にあることが多い)への転勤も、キャリアの中で織り込んでおく必要があります。
そのため、「一つの勤務地で長く働きたい」「住む場所や仕事内容を自分でコントロールしたい」といった安定志向が強すぎる人にとっては、ストレスを感じる環境かもしれません。
さらに現在は、脱炭素という業界全体の大きな「変化」の時期でもあります。
これまでの常識が通用しなくなり、新しい事業や働き方が求められています。
環境の変化や新しいことへの挑戦を「リスク」として捉え、できるだけ避けたいと考える人にとっては、業界の変革期についていくのが難しいと感じる可能性があります。
チームより個人で完結する仕事をしたい人
資源業界が手がけるプロジェクトは、そのスケールの大きさから、決して一人で完結することはありません。
探査、開発、生産、輸送、販売といった各分野の専門家が、国籍や文化の垣根を越えてチームを組み、協力し合って初めて成立します。
そこでは、自分の専門性を発揮することと同じくらい、他のメンバーの意見を尊重し、全体の目標達成のために協調することが求められます。
例えば、「自分の研究やプログラミングに没頭したい」「他人に干渉されず、自分のペースで仕事を進めたい」といった志向が強い人は、常にチームワークを求められる資源業界の働き方に違和感を覚えるかもしれません。
もちろん、個人の高い専門性は必要不可決ですが、その専門性を「チームの成果」のためにどう活かすかという視点を持てない人には、活躍の場が限られてしまう可能性があります。
個人の成果が明確に評価される環境を望む人にとっては、少し物足りなさを感じるかもしれません。
すぐに成果を実感したい人
資源業界のプロジェクトは、10年、20年単位の非常に長期的なものが中心です。
今日植えた種が明日芽を出す、といった短期的な成果はほとんど期待できません。
例えば、若手社員が担当する仕事は、巨大なプロジェクト全体から見ればごく一部であり、自分の仕事が最終的にどのような形で社会の役に立っているのかを実感しにくい側面があります。
「自分が作ったサービスがすぐに世に出て、ユーザーの反応を見たい」「半年や1年の短期的な目標を次々とクリアしていきたい」といった、スピード感や短期的な成果を重視する人にとっては、資源業界の時間の流れは遅すぎると感じるでしょう。
「成果が出るまで時間がかかってもいいから、歴史に残るような大きな仕事をしたい」という長期的な視点を持てない人には、日々の地道な業務を続けるモチベーションを維持するのが難しいかもしれません。
成果が形になるまでの長い道のりを楽しめるかどうかが、一つの分かれ目になります。
【資源業界】内定をもらうためのポイント
さて、資源業界がどんな場所で、どんな人が求められているか、だいぶイメージが掴めてきたのではないでしょうか。
その上で「やっぱり資源業界に挑戦したい!」と思ったあなたに、ここからは内定をぐっと引き寄せるための具体的なポイントを解説していきます。
資源業界は、その専門性やグローバル性から、他の業界とは少し異なる視点での準備が求められます。
ただ「安定しているから」「スケールが大きいから」といった漠然とした理由だけでは、数多くのライバルの中で埋もれてしまいます。
「なぜ、数ある業界の中で資源業界なのか」「なぜ、その企業でなければならないのか」を、あなた自身の言葉で明確に語れるようになることが何よりも重要です。
ここでは、志望動機の作り方から、学生時代にやっておくべきことまで、3つのステップに分けてアドバイスを送ります。
資源業界への理解と熱意を示す志望動機
内定を勝ち取る上で最も重要なのが「志望動機」の質です。
資源業界の選考では、特に「なぜ商社やメーカーではなく、資源業界なのか?」という点を深く問われます。
例えば、グローバルに働きたい、スケールの大きな仕事がしたい、という動機は総合商社やプラントエンジニアリング業界にも当てはまりますよね。
そこで重要になるのが、資源業界の「本質」を理解することです。
それは、「資源の安定供給に対する責任」と「地球環境問題への挑戦」という、社会インフラを根底で支える使命感です。
この使命感に共感し、「自分は日本のエネルギーの未来にこう貢献したい」「脱炭素という課題に、この会社の技術(あるいは事業)を通じて取り組みたい」という具体的なビジョンを示す必要があります。
そのためには、各社のIR情報(投資家向け情報)や中期経営計画を読み込み、その企業が今、何に力を入れ、どこへ向かおうとしているのかを徹底的に研究しましょう。
その上で、自分の経験(例えば、留学経験や理系の専門知識)が、その企業の未来にどう貢献できるのかを論理的に結びつけることができれば、説得力のある志望動機が完成します。
インターンシップやOB・OG訪問での情報収集
資源業界のビジネスは、BtoB(企業間取引)が中心で、日常生活で触れる機会が少ないため、具体的な仕事内容をイメージしにくいという側面があります。
そこで非常に有効なのが、インターンシップやOB・OG訪問です。
インターンシップでは、グループワークを通じて業界の課題(例:再生可能エネルギー事業の立案など)に取り組むことで、座学では得られない「リアルな仕事の難しさや面白さ」を体感できます。
また、現場で働く社員の方々と接することで、その企業の「社風」や「働き方」が自分に合っているかを見極める絶好の機会にもなります。
OB・OG訪問は、さらに一歩踏み込んで、「実際の海外駐在はどんな感じか」「仕事のやりがいは何か、逆に大変なことは何か」といった生々しい情報を引き出すチャンスです。
特に、自分が興味のある職種や部門で働く先輩に話を聞ければ、志望動機を深める上でこれ以上ないヒントが得られるでしょう。
こうした「足で稼いだ情報」は、エントリーシートや面接での受け答えに深みと熱意を与えてくれます。
求められるスキル(語学力・専門性)のアピール
資源業界で活躍するためには、特定のスキルが求められることが多いのも事実です。
まず、文系・理系問わず重要になるのが「語学力」、特に英語力です。
事業の多くが海外と関わるため、TOEICのスコアはもちろんのこと、「英語を使って何を成し遂げたか」という具体的な経験(例:留学先での交渉経験、外国人との協働プロジェクトなど)をアピールできると非常に強力です。
次に、理系の学生であれば「専門性」が大きな武器になります。
地質、物理、化学、機械、土木といった専門知識は、探査、開発、プラントの操業など、業界のあらゆる場面で直接活かすことができます。
自分の研究内容が、志望企業のどの事業分野や技術開発に貢献できるのかを具体的に説明できるように準備しておきましょう。
文系の学生であっても、例えば法学部なら国際契約、経済学部なら資源のトレーディングや市場分析といった形で、自分の専門性を活かせる分野は必ずあります。
「自分にはスキルがない」と諦めず、学生時代の経験を「資源業界で求められる力」に変換してアピールする工夫をしてみてください。
【資源業界】よくある質問
資源業界について深く知れば知るほど、新たな疑問や不安も出てくるかもしれませんね。
ここでは、就活生の皆さんからよく寄せられる質問をピックアップし、就活アドバイザーとして率直にお答えしていきます。
「文系だから不利なのでは?」「海外勤務って実際どれくらいあるの?」といった、多くの人が気になるポイントだと思います。
これらの疑問を解消することで、あなたが資源業界で働くイメージをよりクリアにするお手伝いができれば嬉しいです。
もちろん、ここで回答することはあくまで一般的な傾向であり、最終的には企業ごとの違いが大きいということも念頭に置いて読んでみてください。
文系でも活躍できるフィールドはありますか?
結論から言えば、文系学生が活躍できるフィールドは非常にたくさんあります。
資源業界と聞くと、理系のエンジニアがプラントや鉱山で働いているイメージが強いかもしれませんが、それは業界の一側面に過ぎません。
例えば、海外の資源国政府やパートナー企業と交渉して権益を獲得する「渉外・法務」、巨額のプロジェクト資金を調達する「財務・経理」、国際市況を読んで原油やLNGを売買する「トレーダー」、国内外の顧客に製品を販売する「営業」など、ビジネスの根幹を動かしているのは文系出身者が多いことも珍しくありません。
また、全社的な戦略を練る「経営企画」や、グローバルな人材を採用・育成する「人事」も、文系が中心となって活躍する重要な部門です。
理系の専門知識は入社後に学ぶ意欲さえあればカバーできます。
それ以上に、文系学生に期待されるのは、多様なステークホルダー(利害関係者)を巻き込むコミュニケーション能力や、複雑な物事を整理・分析して最適解を導き出す論理的思考力です。
自分の強みがどの職種で活かせるか、ぜひ広い視野で探してみてください。
海外勤務(駐在)の可能性はどれくらいですか?
これは企業や職種によって大きく異なりますが、一般的なメーカーや金融機関などと比べれば、海外勤務(駐在)や長期の海外出張を経験する可能性は「非常に高い」と言えます。
特に、石油・天然ガスの「上流(探査・開発)」部門や、海外での権益獲得を目指す「渉外」部門、資源を売買する「トレーディング」部門などを志望する場合は、キャリアの中で一度は海外勤務を経験すると考えておいた方が良いでしょう。
赴任先も、ニューヨークやロンドンといった先進的な都市から、中東、アフリカ、東南アジアの事業所(時には僻地)まで多岐にわたります。
一方で、国内の製油所や製錬所での「生産管理」や「設備保全」といった職種や、国内の顧客を担当する「営業」部門などは、海外との関わりが比較的少ない場合もあります。
もし海外勤務を強く希望する(あるいは、逆に避けたい)場合は、各社の事業内容(海外比率など)や、職種ごとのキャリアパスを、OB・OG訪問や説明会で具体的に確認しておくことを強くお勧めします。
「脱炭素」の流れで、将来性は大丈夫ですか?
「脱炭素」は、資源業界にとって間違いなく最大の経営課題であり、避けては通れない道です。
「石油業界=斜陽産業」といったイメージを持つ人もいるかもしれませんが、それは少し短絡的かもしれません。
まず、再生可能エネルギーが普及したとしても、石油や天然ガスが社会から一切不要になるわけではない、という現実があります。
例えば、プラスチックの原料(ナフサ)や、航空機の燃料(ジェット燃料)などは、今のところ石油に代わる有効な代替手段が確立されていません。
また、再生可能エネルギーは天候に左右されるため、それを補完する火力発電(天然ガスなど)の役割も当面は重要です。
その上で、多くの資源企業は「脱炭素」を脅威ではなく、新しいビジネスチャンスとして捉え、積極的に変革しようとしています。
具体的には、洋上風力や地熱といった再生可能エネルギー事業への巨額の投資、水素やアンモニアといった次世代エネルギーの開発、CCS(CO2回収・貯留)技術の確立などです。
従来の資源ビジネスで得た収益と技術力を、未来のエネルギー社会の構築にどう振り向けていくか。
まさに今、そのダイナミックな変革の最前線に立ち会えるのが、現在の資源業界とも言えるのです。
将来性は「既存事業のまま」では危ういですが、「変革に成功すれば」非常に大きい、というのが答えになるでしょう。
まとめ
今回は、資源業界の就職偏差値から、そのビジネスの仕組み、働く人の特徴、そして内定獲得のポイントまで、幅広く解説してきました。
資源業界は、私たちの生活と社会を文字通り根底から支える、非常に「スケールが大きく」かつ「責任の重い」仕事が集まる場所です。
グローバルな舞台でのタフな挑戦、国家規模のプロジェクトを動かすダイナミズム、そして「脱炭素」という人類規模の課題解決への貢献。
これらは、他の業界ではなかなか味わうことのできない、資源業界ならではの「やりがい」と言えるでしょう。
もしあなたが、「困難であっても、大きなことに挑戦したい」「自分の仕事で社会の未来を支えたい」と本気で考えているなら、資源業界はあなたのその情熱を真正面から受け止めてくれるはずです。
資源業界について、さらに詳しく知りたいことや、個別の企業研究で悩んでいることがあれば、この記事を振り返ってみてください。