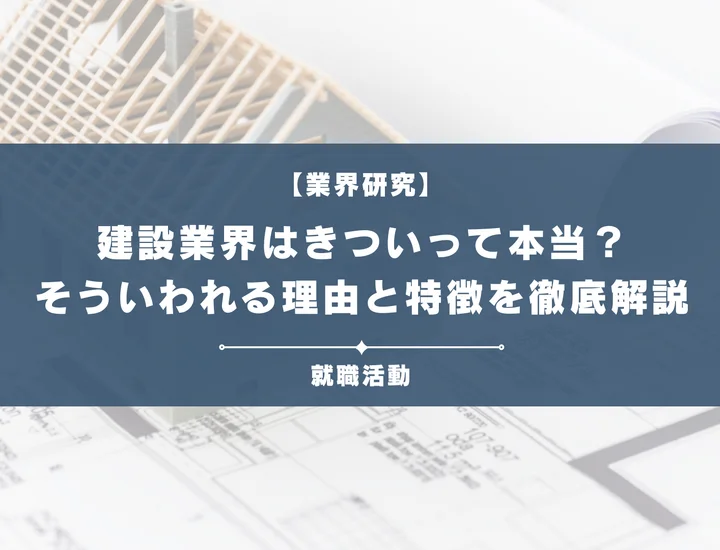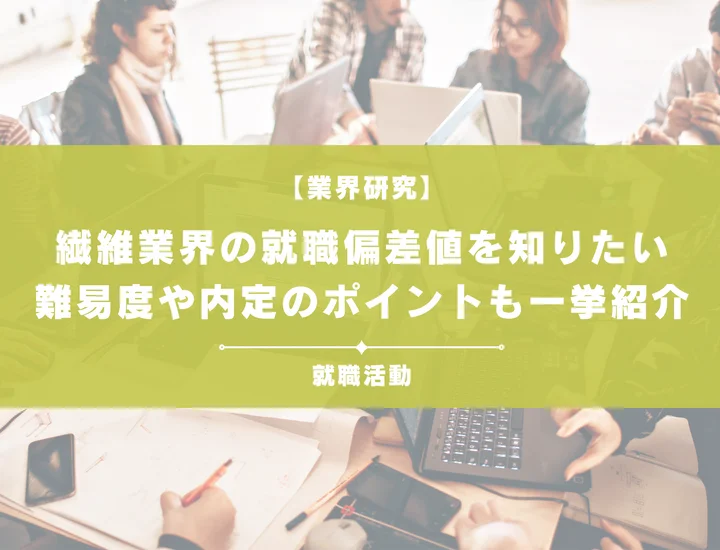HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
この記事では、建設業界の仕事内容や実態、きついと言われる理由、そしてこの業界に向いている人の特徴まで、新卒就活生の皆さんが知っておくべき情報をWebライターとして活躍する就活アドバイザーの視点から詳しく解説します。
【建設業界はきついのか】建設業界はきつい?
建設業界ときいて、皆さんはどのようなイメージを抱きますか。
高度経済成長期から日本のインフラを支えてきた重要な産業である一方で、「きつい」「大変」といったネガティブな側面がフォーカスされることも少なくありません。
体力勝負で残業が多い、現場の人間関係が厳しそうなど、不安を煽るような情報に触れる機会も多いでしょう。
しかし、これらのイメージは、業界全体の一面を切り取ったものである可能性もあります。
現在の建設業界は、技術革新や働き方改革が進められており、以前とは状況が大きく変わってきている部分も多くあります。
この記事を通して、建設業界の多面的な実態を理解し、皆さんが自身の適性を冷静に見極めるための判断材料を提供します。
【建設業界はきついのか】建設業界の仕事内容
建設業界は、その名の通り「もの」を作り上げる仕事ですが、そのプロセスには多岐にわたる役割が存在します。
建物やインフラを計画し、設計し、実際に建設し、そして維持管理していくまで、それぞれの段階で専門的な仕事が求められます。
新卒で入社する場合、主にプロジェクトを動かす管理側の仕事に就くことが多いです。
建設業界の仕事は、地図に残るようなスケールの大きなものづくりに携われる点が最大の魅力と言えるでしょう。
企画・開発
企画・開発の仕事は、プロジェクトの最も初期段階を担います。
例えば、新しい商業施設やマンションを建設する際、どのような建物が必要とされているのかを調査し、具体的な計画を立案することが主な役割です。
市場調査を行い、土地の選定、予算設定、建設後の収益性などを多角的に検討します。
デベロッパーなどが中心となって行う業務であり、街づくり全体のビジョンを描く、創造的で戦略的な側面を持つ仕事です。
設計・積算
設計の仕事は、企画された建物を具体的な形にするための設計図を作成します。
意匠設計、構造設計、設備設計など専門分野に分かれており、建物の安全性、機能性、デザイン性を追求します。
積算の仕事は、その設計図に基づいて、建設に必要な材料費や人件費などの総工費を算出することです。
プロジェクトのコスト管理において非常に重要な役割を担い、高い専門性と正確性が求められます。
施工管理
施工管理は、設計図通りに建築物が完成するように、現場全体を指揮・監督する仕事です。
品質、工程、安全、原価の4大管理が主な業務となり、協力会社や職人さんと連携を取りながら、プロジェクトを納期通りに進行させます。
現場の最前線で働くため、コミュニケーション能力や問題解決能力が非常に重要となります。
新卒で多くの方が携わることになる、建設業界の核となる仕事の一つです。
【建設業界はきついのか】建設業界の主な職種
建設業界には、プロジェクトを推進するために様々な専門性を持った職種が存在します。
特に新卒が活躍する可能性が高い、代表的な職種をいくつかご紹介します。
それぞれの職種が持つ役割を理解することで、皆さんの興味や適性に合ったキャリアパスを見つける手助けになるはずです。
総合職(施工管理)
総合職としての採用で最も多いのが施工管理です。
先に述べた通り、建設現場における工事全体のマネジメントを担います。
具体的には、日々の作業進捗の確認や、品質基準が守られているかのチェック、作業員の安全管理、コストの計算などを行います。
現場の状況に応じて臨機応変な対応力が求められ、完成した時の達成感は非常に大きい職種です。
建築設計職
建築設計職は、主に意匠設計、構造設計、設備設計に分かれます。
意匠設計は建物の外観や間取りといったデザイン面を担当し、構造設計は地震や風に耐えうる安全性を確保するための構造を設計します。
設備設計は、電気・空調・給排水などの設備を設計します。
専門知識と創造性を活かし、人々の生活や活動の基盤となる空間を創造する非常にやりがいのある仕事です。
営業職
建設業界の営業職は、ハウスメーカーやゼネコンなどによって役割が異なります。
ハウスメーカーの場合、個人のお客様に対して住宅の提案・販売を行うことが中心です。
ゼネコンやサブコンの場合、企業や官公庁に対し、建設プロジェクトの受注に向けた提案活動を行うことが主な業務となります。
顧客のニーズを的確に把握し、技術部門と連携しながら最適なソリューションを提供する能力が求められます。
【建設業界はきついのか】建設業界がきついとされる理由
建設業界がきついと言われる背景には、いくつかの共通した要因があります。
これらの要因を事前に理解しておくことは、入社後のギャップを減らし、長く活躍するための準備に繋がります。
ただ単に「きつい」と捉えるのではなく、なぜそのような状況になるのか、その構造的な理由を掘り下げて考えてみましょう。
労働時間の長さ
建設業界は、プロジェクトの納期が厳格に定められていることが多く、特に工期の終盤や予期せぬトラブルが発生した際には、労働時間が長くなりがちです。
施工管理職の場合、現場の作業開始前や終了後に事務作業を行う必要があり、朝早くから夜遅くまで働くといった状況も発生しやすい傾向にあります。
近年は働き方改革が進められていますが、現場の状況によっては依然として長時間労働が課題とされています。
天候に左右される
屋外での作業が多い建設現場では、天候の影響を大きく受けます。
雨や強風、極端な暑さや寒さなど、悪天候時には作業が中断されたり、計画通りに進まないことが頻繁にあります。
これによって、工期の調整やスケジュールの見直しが頻繁に発生し、現場を管理する施工管理職には柔軟な対応と精神的なタフさが求められます。
自然との闘いの中で、安全と品質を両立させる難しさがあります。
責任の重さ
建設業界の仕事は、人々の命や財産に関わる重大な責任を伴います。
一つとして同じものがない「ものづくり」であり、ミスが大きな事故や手戻りにつながる可能性があります。
特に施工管理職は、現場の安全、品質、コスト、スケジュールのすべてに責任を持つため、常に緊張感を持って仕事に取り組む必要があります。
この責任感の重さが、精神的な負担となり、「きつい」と感じる一つの要因となっています。
【建設業界はきついのか】建設業界の現状・課題
建設業界は今、大きな転換期を迎えています。
人手不足、高齢化、技術革新など、様々な要素が絡み合い、業界全体で課題解決に向けた取り組みが進められています。
これらの課題と現状を把握しておくことは、皆さんが将来働く上での変化やチャンスを知ることに繋がります。
深刻な人手不足と高齢化
建設業界では、若年層の入職者が減少する一方で、団塊の世代が大量に定年を迎える「2025年問題」を筆頭に、深刻な人手不足と技術者の高齢化が進んでいます。
これにより、現場のノウハウ継承が難しくなり、一人当たりの業務負担が増加する傾向にあります。
この課題を解決するため、業界全体で若手育成や女性の活躍推進、外国人材の受け入れなどが積極的に進められています。
働き方改革の推進
長時間労働の是正や週休二日の確保など、労働環境の改善は業界の喫緊の課題です。
2024年4月からは時間外労働の上限規制が適用されるなど、法律による縛りも加わり、各企業は生産性向上と業務効率化を強く求められています。
具体的には、IT技術の活用による現場管理の効率化や、休暇取得の促進といった取り組みが進められており、以前よりも働きやすい環境への変革が期待されています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入
建設業界では、ドローンによる測量、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用した設計・施工、IoTセンサーによる現場管理など、デジタル技術の導入が加速しています。
これらの技術は、人手不足の解消や生産性の劇的な向上、さらには品質・安全性の向上に寄与すると期待されています。
デジタル技術を活用できる人材、つまり新しい技術に柔軟に対応できる新卒の皆さんの活躍の場が広がっています。
【建設業界はきついのか】建設業界に向いている人
建設業界で活躍し、やりがいを感じられる人には、いくつかの共通した特徴が見られます。
皆さんがこれらの特徴に当てはまるか、自己分析の一環として参考にしてみてください。
ものづくりへの熱意がある人
建設業界は、建物やインフラといった、人々の生活基盤を支える「もの」を形にする仕事です。
完成した時に大きな達成感を得られるのは、ものづくりに対する強い熱意があるからこそです。
自らが関わった成果が長く社会に残ることに、大きな喜びを感じる人は、この業界で長く活躍できるでしょう。
チームで働くことが好きな人
一つの建設プロジェクトは、設計者、施工管理者、職人さん、協力会社など、多くの人が関わるチーム戦です。
それぞれの専門性を尊重し、連携を取りながら共通の目標に向かって進める協調性が非常に重要です。
一人で完結する仕事ではなく、多様な人々と協力し、コミュニケーションを取りながら仕事を進めることが好きな人に向いています。
粘り強さと忍耐力がある人
建設プロジェクトは、計画通りに進むことばかりではありません。
天候不順や予期せぬトラブル、厳しい納期など、様々な困難に直面することがあります。
そのような状況でも、諦めずに解決策を探り、最後まで責任を持ってやり遂げる粘り強さと忍耐力は、この業界で成功するための必須条件と言えるでしょう。
コミュニケーション能力が高い人
施工管理の仕事は、現場で働く様々な年代、背景を持つ人々との円滑なコミュニケーションが不可欠です。
指示を的確に伝え、意見をまとめ、時には交渉を行う必要があります。
相手の立場を理解し、信頼関係を築ける高いコミュニケーション能力は、プロジェクトをスムーズに進行させるための鍵となります。
【建設業界はきついのか】建設業界に向いていない人
建設業界が持つ特性上、特定の考え方や志向を持つ人にとっては、仕事が困難に感じられる可能性があります。
もちろん、すべての人が以下に当てはまるわけではありませんが、自身のキャリア選択におけるリスクとして知っておくことが重要です。
現場作業に抵抗がある人
施工管理職など現場に近い職種では、事務所内でのデスクワークだけでなく、実際に建設現場に出向き、時には屋外で作業を監督する必要があります。
泥や埃に抵抗がある、あるいは体力的な負担を極度に避けたいと考える人は、現場での仕事にストレスを感じやすいかもしれません。
細かい計画変更に柔軟に対応できない人
建設現場は生き物であり、天候や資材の納期遅れなど、予期せぬ要因によって計画が変更されることが日常的に起こります。
決まったスケジュール通りにすべてが進むことを強く求める人や、予期せぬ変更に対してストレスを感じやすい人は、この業界のダイナミズムについていくのが難しいかもしれません。
人とのコミュニケーションを極力避けたい人
前述の通り、建設業界の仕事は多くの人々との連携が不可欠です。
特に施工管理職は、職人さんや協力会社の安全・進捗を管理し、意見調整を行う必要があります。
一人で黙々と作業に集中したいと考え、人とのコミュニケーションを苦手とする人は、プロジェクトマネジメントの職務に困難を感じる可能性があります。
【建設業界はきついのか】建設業界に行くためにすべきこと
建設業界を志望する皆さんが、内定を獲得し、入社後にスムーズに活躍できるよう、今から取り組むべき具体的なアクションをご紹介します。
漠然とした不安を解消し、自信を持って就職活動に臨むための準備を始めましょう。
業界と職種への深い理解
まずは、この記事で触れた内容をさらに深掘りし、建設業界が抱える課題、今後の展望、そして志望する企業がどのような事業を展開しているのかを徹底的に調べましょう。
特に、施工管理、設計、営業といった職種の具体的な仕事内容や一日の流れを理解することが重要です。
企業説明会やインターンシップを通じて、リアルな情報を得る努力をしましょう。
企業ごとの働き方改革への取り組み調査
建設業界がきついとされる理由の一つに長時間労働がありますが、各企業は働き方改革に積極的に取り組んでいます。
志望する企業が、具体的にどのような労働時間短縮や休暇取得促進の施策を行っているのかを、採用情報やニュースリリースから調査しましょう。
これは、入社後のギャップを防ぐだけでなく、面接での志望動機や企業選びの軸として語る際の強力な材料になります。
チームで目標を達成した経験の棚卸し
建設業界はチームワークが非常に重要です。
学生時代に、サークル活動、アルバイト、ゼミなどで、多様なメンバーと協力し、困難を乗り越えて一つの目標を達成した経験を具体的に振り返りましょう。
その際、自分がどのような役割を果たし、どのようにチームに貢献したのかを言語化しておくことで、面接で説得力のある自己PRを展開できるようになります。
まとめ
建設業界は、きついと言われる側面がある一方で、人々の生活や社会の基盤を支える、非常に社会的意義の大きな仕事です。
労働環境の改善やDXの推進など、業界全体で大きな変革期を迎えており、皆さんのような新しい視点とエネルギーを持った人材が求められています。
不安を煽る情報に惑わされるのではなく、業界の現状と課題を正しく理解し、ご自身の適性と照らし合わせて、建設業界が本当に皆さんにとって魅力的なフィールドであるかを判断してください。
もし、地図に残るようなスケールの大きなものづくりに情熱を感じるなら、ぜひ一歩踏み出し、この業界への扉を開いてみましょう。
Digmediaは、皆さんの挑戦を全力で応援しています。