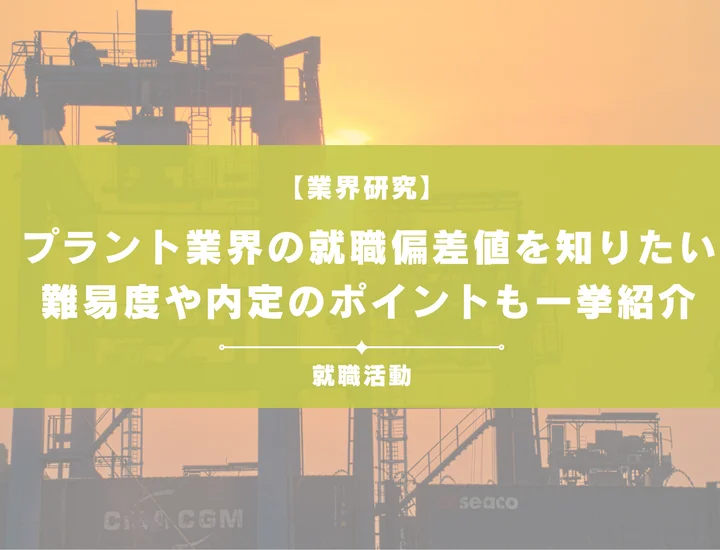HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
この記事では、この「就職偏差値」というモノサシを使って、ある特定の業界を深掘りしていきます。
自分に合った企業選びのヒントとして、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業の入社難易度を予備校の偏差値になぞらえて格付けした、インターネット発祥の俗語です。
企業の人気度や選考の難しさなどを基に、主に就活生やネット利用者が独自に作成します。
公的な機関による客観的なデータではないため、あくまで主観も含まれる「目安」の一つとして捉えられています。
プラント業界の就職偏差値ランキング
それでは早速、今回のテーマである「プラント業界」の就職偏差値ランキングを見ていきましょう。
プラント業界は、石油精製所や発電所といった巨大な生産設備を世界中に建設する、非常にスケールの大きな仕事です。
そのため、入社難易度は総じて高く、特にトップ企業は最難関と言われています。
ここでは、一般的な就職偏差値の指標に基づき、Aランク(最難関)からEランク(標準)まで分類して紹介します。
ただし、これはあくまで一つの目安です。
偏差値の高い企業が必ずしも自分に合うとは限らないので、自分の価値観やキャリアプランと照らし合わせながら、参考程度に捉えてくださいね。
【プラント業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】日揮
日本のプラントエンジニアリング(EPC)業界の頂点に立つ企業です。
世界中でLNGプラントなどの巨大プロジェクトを手掛ける、国内随一の企業として圧倒的な人気を誇ります。
高い学歴、卓越した語学力(特に英語)、そしてグローバルな大規模プロジェクトをやり遂げる強靭な精神力と調整能力が求められます。
【プラント業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐプラント業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】千代田化工建設
【68】栗田工業 日鉄エンジニアリング
【67】JFEエンジニアリング
【66】東洋エンジ二アリング オルガノ
日揮と並ぶ大手総合エンジニアリング企業(千代田、東洋)や、鉄鋼系(日鉄、JFE)、水処理専業(栗田、オルガノ)のトップ企業が並びます。
いずれも各分野のリーディングカンパニーであり、就職難易度は極めて高いです。
Aランク同様の高いスペックに加え、エネルギー、環境、インフラといった社会課題への深い理解と、それを技術で解決する意欲が問われます。
【プラント業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】タクマ 東芝プラントシステム ヴェオリア・ジャパン
【64】富士古河E&C 三菱ケミカルエンジニアリング 三菱電機プラントエンジニアリング 丸紅パワー&インフラシステムズ
【63】日立プラントコンストラクション 日立プラントサービス かんでんエンジニアリング
【62】月島機械 川崎エンジニアリング クボタ環境エンジニアリング MHIパワーエンジニアリング 千代田エクスワンエンジニアリング 日鉄環境エネルギーソリューション
【61】水道機工 荏原環境プラント タクマ・エンジニアリング 東レエンジニアリング カナデビアエンジニアリング コベルコプロフェッショナルサービス
環境プラント(タクマ)や水インフラ(ヴェオリア)などの専門分野で高い技術力を持つ企業や、大手メーカー系のプラント子会社が中心です。
親会社の安定性と専門性を兼ね備えた優良企業群です。
高い専門知識や研究実績に加え、特定のプラント・技術分野への明確な志望動機と、プロジェクトを遂行する協調性や責任感が求められます。
【プラント業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】山九 高田工業所 三井E&Sエンジニアリング DOWAテクノエンジ 中部プラントサービス
【59】タクマテクノス 日立プラントメカニクス 山九プラントテクノ
【58】月島アクアJFEソリューション ヴェオリア・ジェネッツ日本
【57】月島ジェイテクノメンテサービス 芝田化工設計 高田プラント建設 ニッコーテクノ ヤスナ設計工房
【56】大同プラント工業 北陸プラントサービス 東海プラントエンジニアリング 三共エンジニアリング 綜研テクニックス
プラントの建設やメンテナンス(保全)を主力とする企業や、大手エンジニアリング会社の子会社・関連会社が主です。
プラントを「現場で支える」重要な役割を担う企業群です。
就職活動の基本対策を徹底することが前提です。
現場での安全管理やオペレーションへの関心、そして技術を地道に習得していく姿勢が評価されます。
【プラント業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】協立設備 関西化学機械製作 関東エルエンジニアリング 岡本エンジニアリング 富士エンジニアリングサービス ジャパンエンジニアリング 翼エンジニアリングサービス
地域密着型、あるいは特定の設備・工程に特化したエンジニアリング・メンテナンス企業が中心です。
全国的な知名度は高くなくても、特定の技術や地域で確固たる基盤を持つ企業が多いです。
企業研究をしっかり行い、その企業ならではの強みを理解した上で、技術者として貢献したいという熱意を伝えることが重要です。
【プラント業界】とは
そもそも「プラント業界」と聞いても、具体的に何をしているのかピンとこない人も多いかもしれませんね。
簡単に言えば、プラント業界とは、石油、ガス、化学、発電、製鉄、食品、医薬品など、様々なモノを生産するための「工場設備一式」を設計し、建設する業界のことです。
私たちが日常で使うエネルギーや製品の多くは、このプラント業界が建設した巨大な設備によって生み出されています。
まさに、現代社会の産業基盤を根底から支える、非常に重要な役割を担っている業界なのです。
基本的な仕組み
プラント業界のビジネスモデルは、多くの場合「EPC」という言葉で説明されます。
これは、Engineering(設計)、Procurement(調達)、Construction(建設)の頭文字を取ったものです。
プラント建設のプロジェクトを受注すると、まず顧客(主にエネルギー会社や化学メーカーなど)の要求に基づき、膨大な量の図面を作成し、プラントの仕様を決定します(設計)。
次に、その設計に基づき、世界中から必要な機器や資材(例えば、巨大なタンク、複雑な配管、精密な制御装置など)を最適なコストと品質、納期で購入・手配します(調達)。
そして最後に、建設現場でそれらの機器や資材を組み立て、プラントを実際に建設していきます(建設)。
これらEPCを一括して請け負うのが、プラントエンジニアリング会社の基本的な仕組みです。
プロジェクトは数千億円規模、工期は数年に及ぶことも珍しくありません。
主な役割と業務内容
プラント業界には、非常に多岐にわたる役割と業務内容が存在します。
まず、プロジェクト全体を統括するのが「プロジェクトマネージャー」です。
予算、スケジュール、品質、安全など、プロジェクトの全責任を負い、巨大なチームを率いる指揮官の役割を担います。
次に、具体的な設計を行う「エンジニア(設計者)」です。
プロセス設計、機械設計、電気設計、計装設計、土木建築設計など、非常に高度な専門分野に分かれています。
そして、世界中から最適な資材を買い付ける「調達(バイヤー)」、建設現場で施工を管理する「建設管理(コンストラクションマネージャー)」、完成したプラントが仕様通りに動くかを確認する「試運転(コミッショニング)」などがあります。
これら以外にも、プロジェクトを受注するための「営業」や、契約・法務、経理・財務など、多くの専門家が連携して一つのプラントを創り上げていきます。
理系・文系問わず、多様な活躍の場があるのが特徴です。
プラント業界の将来性と動向
プラント業界と聞くと、石油やガスといった従来のエネルギー分野のイメージが強いかもしれませんが、現在、業界は大きな変革期を迎えています。
最も大きなトレンドは「脱炭素化」です。
世界的にカーボンニュートラルへの移行が急務とされる中、プラント業界はその技術力で中心的な役割を担おうとしています。
具体的には、LNG(液化天然ガス)プラントへのシフトに加え、CO2を回収・貯留する「CCS」技術、水素やアンモニアといった次世代エネルギーの製造・利用プラント、さらには洋上風力や地熱といった再生可能エネルギー関連の設備建設への需要が急速に高まっています。
また、AIやIoTを活用したプラントの「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」も進んでおり、設計の自動化や効率的な運転・保守に技術が活用されています。
今後は、従来のエネルギー分野で培った高度なエンジニアリング技術を、いかにして環境・エネルギー分野に応用していくかが、各社の将来性を左右する鍵となっています。
【プラント業界】特徴
プラント業界は、他の業界とは一線を画す、非常にユニークでダイナミックな特徴を持っています。
就職活動でこの業界を志望するなら、まずはその「スケールの大きさ」と「グローバル性」を理解することが欠かせません。
数千億円が動き、数千人が関わり、完成までに数年を要するプロジェクトは、まさに「地球規模の仕事」と言えます。
しかし、その壮大さゆえに、求められる責任やスキルも非常に高度なものになります。
一つのミスがプロジェクト全体に大きな影響を与えかねない緊張感の中で、世界中のプロフェッショナルたちと協働していくことになります。
ここでは、プラント業界を理解する上で欠かせない、代表的な3つの特徴について深掘りしていきます。
自分の性格や価値観が、この業界の持つ独特のカルチャーと合っているか、ぜひ確かめながら読み進めてください。
特徴1:プロジェクト規模が非常に大きい
プラント業界の最大の特徴は、何と言ってもそのプロジェクト規模の壮大さです。
一つのプラント建設プロジェクトにかかる費用は、数千億円から、時には1兆円を超えることもあります。
そして、その建設には数年単位の時間がかかります。
これは、単に一つの「建物」を建てるのではなく、エネルギーを生み出したり、化学製品を作ったりするための「巨大な生産システム」そのものをゼロから創り出す作業だからです。
関わる人の数も桁違いで、設計、調達、建設、試運転の各フェーズで、国籍も専門も異なる何千人もの人々が協力します。
自分が関わったプラントが、一つの国のエネルギー供給を支えたり、人々の生活に欠かせない製品を生み出したりする。
その社会インフラを支えるという圧倒的なやりがいと達成感は、他の業界ではなかなか味わえない、プラント業界ならではの醍醐味と言えるでしょう。
特徴2:グローバルに活躍できる
二つ目の特徴は、活躍の舞台が全世界に広がっていることです。
プラントが建設される場所は、石油や天然ガスなどの資源が豊富な中東、アフリカ、東南アジア、あるいは経済成長が著しい新興国など、その多くが海外です。
そのため、プロジェクトに関わるエンジニアやスタッフは、必然的に海外出張や海外駐在の機会が非常に多くなります。
数ヶ月単位の出張は日常茶飯事ですし、プロジェクトのピーク時には数年間、現地の建設現場に赴任することも珍しくありません。
また、顧客、協力会社、同僚など、一緒に働く人々も多国籍です。
異なる文化、言語、価値観を持つ人々と議論を交わし、一つの目標に向かってチームをまとめ上げていく必要があります。
語学力はもちろんのこと、多様性を受け入れる柔軟性や、異なる環境でもパフォーマンスを発揮できるタフネスが不可欠です。
世界を舞台に自分の力を試したい人にとっては、これ以上ない環境と言えます。
特徴3:高度な専門知識と技術力が求められる
三つ目の特徴は、非常に高度かつ広範な専門知識と技術力が求められる点です。
プラントは、機械、電気、電子、化学、土木、建築、ITなど、あらゆる工学分野の技術が集結した「技術の結晶」です。
例えば、超高温・高圧に耐える特殊な素材の選定、ミクロン単位の精度が求められる機器の設計、プラント全体を最適に自動制御するシステムの構築など、どれ一つとっても簡単なものはありません。
また、プロジェクトを成功させるためには、これらの多様な技術をまとめ上げ、予算内・納期内に安全に建設を完了させる「プロジェクトマネジメント」の能力が極めて重要になります。
技術は日々進歩しており、脱炭素化のような新しい社会の要請にも応えていかなければなりません。
そのため、入社後も常に最新の知識を学び続ける姿勢と、複雑な課題を解決しようとする知的な探究心が強く求められる業界です。
【プラント業界】向いている人
プラント業界の壮大なスケールとグローバルな環境は、多くの人にとって魅力的に映る一方で、非常にタフな側面も持ち合わせています。
この業界でいきいきと活躍し、成長し続けられる人には、いくつかの共通した素養があります。
それは単なる学歴や専門知識だけではありません。
むしろ、困難な状況でも前向きに物事を捉え、周囲を巻き込みながら粘り強くやり遂げる力が問われます。
自分がこの業界の独特な環境で輝けるかどうか、自己分析と照らし合わせながら考えてみてください。
ここでは、プラント業界で特に求められる3つの人物像について解説します。
一つでも強く当てはまると感じるものがあれば、あなたはプラント業界への適性があるかもしれません。
向いている人1:リーダーシップと調整力がある人
プラント建設は、決して一人では成し遂げられません。
設計、調達、建設の各部門、さらには顧客、世界中の協力会社(ベンダーやサブコン)、現地の作業員まで、関わるステークホルダーは膨大な数にのぼります。
それぞれの立場や利害が異なる中で、全員を一つの目標(=プラントの完成)に向かわせるためには、強力なリーダーシップと卓越した調整力が不可欠です。
これは、サークルやアルバイト、研究室などで、意見の異なるメンバーをまとめ、困難な目標を達成した経験と通じるものがあります。
自分の意見を主張するだけでなく、相手の意見に耳を傾け、利害を調整し、チーム全体の士気を高められる人。
そうした「巻き込み力」を持つ人は、プラント業界のプロジェクトマネージャーとして大きく成長できる素質を持っています。
向いている人2:タフで異文化コミュニケーションを楽しめる人
プラント業界の仕事は、華やかな側面ばかりではありません。
建設現場は、砂漠の真ん中や、インフラが未整備な新興国であることも多く、気候的にも文化的にも厳しい環境での業務を覚悟する必要があります。
また、プロジェクトは常に予期せぬトラブルとの戦いです。
納期や予算のプレッシャーの中で、冷静さを失わず、粘り強く問題解決にあたる精神的なタフさが求められます。
さらに、前述の通り、関わる人々は多国籍です。
言語の壁はもちろん、仕事に対する価値観や商習慣の違いに直面することも日常茶飯事です。
こうした環境の変化や文化の違いを「困難」と捉えるのではなく、「面白い」と捉えられる好奇心や柔軟性、ポジティブさを持っている人は、グローバルな現場でこそ力を発揮できるでしょう。
向いている人3:知的好奇心が旺盛で学び続けられる人
プラントは技術の集合体であり、その技術は常に進化しています。
より効率的に、より安全に、そして近年ではより環境に優しく、といった社会の要請に応えるため、新しい技術や工法が次々と導入されています。
また、プロジェクトごとに扱う製品(石油、化学、医薬など)や適用される法律・規格も異なります。
そのため、一度覚えた知識だけで通用する世界ではありません。
自分の専門分野はもちろん、関連する分野の知識も貪欲に吸収し、常に自分をアップデートし続ける姿勢が不可欠です。
「なぜそうなるのか?」を突き詰めて考える探究心や、複雑な物事を論理的に理解しようとする知的好奇心が旺盛な人は、プラントエンジニアとして、あるいはプロジェクトを動かす一員として、長期的に活躍し続けることができます。
【プラント業界】向いていない人
一方で、プラント業界の持つ特性が、どうしても自分の価値観や働き方の希望と合わない、という人もいるはずです。
それは決して優劣の問題ではなく、単に「向き・不向き」の問題です。
ミスマッチな就職は、自分にとっても企業にとっても不幸な結果を招きかねません。
自分の「やりたくないこと」や「避けたい環境」を明確にすることも、就職活動における重要な自己分析の一つです。
プラント業界のダイナミックさは、裏を返せば「変化の激しさ」や「安定性の欠如」と感じられるかもしれません。
ここでは、プラント業界への就職を考え直した方がよいかもしれない人の特徴を3つ挙げます。
もし強く共感する項目があるなら、一度立ち止まって、本当にこの業界が自分に合っているのかを再検討してみることをお勧めします。
向いていない人1:安定志向でルーティンワークを好む人
プラント業界の仕事は、「プロジェクトベース」で動いています。
一つのプロジェクトが終われば、また次の新しいプロジェクトに移ります。
それはつまり、勤務地、業務内容、一緒に働くチームメンバーが数年単位でガラッと変わることを意味します。
「総合職」として採用された場合、国内のオフィスで設計業務をしていたかと思えば、次のプロジェクトではアフリカの建設現場に数年間赴任する、といったキャリアパスも全く珍しくありません。
毎日同じ場所に出勤し、決められた手順でコツコツと業務をこなすような、安定したルーティンワークを好む人にとっては、こうした環境の変化は大きなストレスになる可能性が高いです。
転勤や海外赴任を避けたい、予測可能なキャリアプランを歩みたいという志向が強い人には、ミスマッチが起こりやすい業界と言えます。
向いていない人2:チームワークより個人プレーを重視する人
プラント建設は、究極のチームスポーツです。
どれだけ優秀なエンジニアが一人いても、プラントは完成しません。
設計、調達、建設、試運転など、異なる専門性を持つ多くの人々が緊密に連携し、情報を共有し、互いに協力し合って初めてプロジェクトは前に進みます。
もちろん、個々の専門性を高めることは重要ですが、それ以上に「チーム全体としてどう成果を出すか」という視点が常に求められます。
自分の担当業務だけを黙々とこなし、他人とのコミュニケーションや調整作業を煩わしいと感じるタイプの人、あるいは「自分の力だけで成果を出したい」という個人プレーを重視する志向が強すぎる人は、この業界の働き方に馴染むのが難しいかもしれません。
常に「報・連・相」を徹底し、周囲と協働することを楽しめない人には厳しい環境です。
向いていない人3:プレッシャーに弱い人
プラント業界の仕事は、非常に大きな責任を伴います。
動く金額が数千億円単位であるため、一つの判断ミスが会社に莫大な損失を与えかねません。
また、巨大な設備を扱うため、安全管理は最優先事項であり、常に緊張感が伴います。
定められた納期と予算の中で、世界中から集まった人々と、時には厳しい自然環境の中でプロジェクトを遂行しなければならないプレッシャーは相当なものです。
予期せぬトラブルが発生した際には、冷静に原因を分析し、迅速かつ的確な対応を迫られます。
こうした極度のプレッシャーの中で冷静さを保ち、むしろそれを「やりがい」として楽しめるタフさが必要です。
責任の重い仕事は避けたい、プレッシャーがかかるとパフォーマンスが著しく落ちてしまうという自覚がある人は、この業界の厳しさに圧倒されてしまうかもしれません。
【プラント業界】内定をもらうためのポイント
ここまで読んで、プラント業界の魅力と厳しさの両面を理解した上で、「やはり挑戦したい」と強く感じた人もいるでしょう。
プラント業界、特にAランクやBランクの人気企業は、最難関レベルの就職先の一つです。
内定を勝ち取るためには、他の業界以上に綿密な戦略と徹底した準備が不可欠になります。
単に「スケールの大きな仕事がしたい」といった漠然とした志望動機だけでは、数多くの優秀なライバルたちに埋もれてしまいます。
なぜプラント業界なのか、その中でもなぜその企業なのか、そして自分がいかにしてその過酷な環境で貢献できるのかを、具体的なエピソードと言葉で証明する必要があります。
ここでは、プラント業界の内定を掴むために、特に意識すべき3つのポイントを解説します。
ポイント1:業界・企業研究の徹底と「なぜ」の深掘り
プラント業界を目指すなら、まずは徹底的な業界・企業研究から始めましょう。
同じ「プラント業界」でも、日揮グローバル、千代田化工建設、東洋エンジニアリングといった総合エンジニアリング(EPC)会社と、メーカー系のエンジニアリング会社、あるいは水処理や環境分野に特化した会社では、得意とする分野や技術、主な市場(国・地域)、企業のカルチャーが全く異なります。
例えば、LNGプラントに圧倒的な強みを持つ企業もあれば、製鉄や都市インフラに強みを持つ企業もあります。
各社のIR情報(決算資料)や中期経営計画を読み込み、「どの分野で」「どの地域で」収益を上げているのか、そして「今度どこに」注力しようとしているのかを正確に把握してください。
その上で、「なぜゼネコンやメーカーではなく、プラントエンジニアリングなのか」「なぜA社ではなく、B社なのか」という問いに対して、自分の経験や価値観に基づいた明確な答えを用意することが、選考突破の第一歩となります。
ポイント2:学生時代の経験を「プロジェクト遂行能力」に紐づける
面接官が知りたいのは、あなたが「プラント業界の過酷なプロジェクトをやり遂げる素養があるか」です。
学生には当然、プラント建設の経験はありません。
そこで重要になるのが、学生時代の様々な経験(サークル活動、アルバイト、留学、研究、インターンなど)を、いかにしてプラント業界で求められる「プロジェクト遂行能力」に紐づけて語れるかです。
重要なのは「何を成し遂げたか」という結果そのものよりも、「どのような困難な目標に対し」「多様なメンバーをどう巻き込み」「予期せぬ課題をどう乗り越え」「最終的に目標を達成したか」というプロセスです。
あなたの経験を「ミニ・プロジェクト」として捉え直し、そこで発揮したリーダーシップ、調整力、課題解決能力を具体的にアピールしてください。
小さな経験でも構いません。
そこであなたがどう考え、どう行動したのかを論理的に説明することが、あなたのポテンシャルを証明する鍵となります。
ポイント3:語学力と異文化適応力のアピール
プラント業界において、グローバル対応力は「あれば尚良い」スキルではなく、「必須」の素養です。
TOEICのスコアは、もちろん高いに越したことはありませんが、それだけで十分ではありません。
企業側が見ているのは、スコアそのものよりも、「実際に英語を使ってタフな交渉や調整ができるか」そして「異なる文化背景を持つ人々と臆せずコミュニケーションを取り、信頼関係を築けるか」という点です。
留学経験があるなら、単に行ったという事実だけでなく、現地でどのような困難に直面し、それをどう乗り越えて成果を出したのかを具体的に語りましょう。
留学経験がなくても、例えば、多様な国籍の人が集まる環境でのアルバイト経験や、語学学習に対する主体的な取り組みをアピールすることも可能です。
自分が未知の環境や厳しい状況に放り込まれても、物怖じせずに周囲と協力して結果を出せる「タフさ」と「柔軟性」を持っていることを、説得力を持って伝えてください。
【プラント業界】よくある質問
プラント業界という、少し特殊でスケールの大きな世界を目指すにあたって、就活生の皆さんからは多くの質問が寄せられます。
その多くは、業務の専門性や、海外勤務の実態、働き方の厳しさといった、リアルな部分に関するものです。
確かに、業界のイメージが先行してしまい、実態が見えにくい部分もあるかもしれません。
ここでは、多くの就活生が共通して抱く疑問について、就活アドバイザーの視点から正直にお答えしていきます。
企業説明会などではなかなか聞きづらいと感じることもあるかもしれませんが、ミスマッチを防ぐためにも、ぜひここで疑問を解消しておきましょう。
Q1:理系でないと厳しいですか?
この質問は非常によく受けます。
結論から言うと、文系出身者でも活躍の場は十分にあります。
プラント業界は理系のイメージが強いですが、プロジェクトを動かすためには、設計(エンジニア)以外にも多くの機能が必要です。
例えば、世界中から資材を買い付ける「調達(バイヤー)」、顧客と交渉しプロジェクトを受注する「営業」、複雑な契約を管理する「法務」、プロジェクトの採算を管理する「経理・財務」、現地でのロジスティクスや労務管理を担う「アドミ(管理部門)」など、文系学生が専門性を発揮できる職種は多岐にわたります。
ただし、文系職であっても、技術や製品に対する一定の理解や関心は求められます。
理系学生と対等に議論し、技術的な内容を理解しようと努力する姿勢は不可欠です。
選考では、なぜ技術系の会社で文系として働きたいのか、その理由を明確にすることが重要です。
Q2:海外勤務の頻度や期間はどれくらいですか?
これも非常に多い質問ですが、答えは「企業、職種、担当するプロジェクトによって全く異なる」というのが実情です。
まず、海外に行くチャンスが比較的多いのは、建設現場での施工管理を担う「建設部門」や、プラントの最終調整を行う「試運転部門」です。
これらの職種では、プロジェクトのピーク時に数ヶ月から数年単位で現地に駐在することが一般的です。
設計部門は国内のオフィス勤務が基本ですが、設計の詳細を詰めるために顧客先(海外)へ短期出張したり、建設が始まった現場へ応援で数ヶ月赴任したりすることもあります。
調達部門も、機器の検査や価格交渉で海外の製造工場へ出張する機会があります。
若手のうちから海外経験を積ませる方針の企業も多いため、キャリアプランとして海外勤務をどの程度受け入れられるかは、事前によく考えておく必要があります。
Q3:激務というイメージがありますが、実際はどうですか?
プラント業界の仕事には、残念ながら「波」があります。
プロジェクトが順調に進んでいる定常期は比較的落ち着いていますが、プロジェクトの終盤、つまりプラントの納期が迫っている時期や、予期せぬトラブルが発生した際は、どうしても業務が集中し、残業や休日出勤が増える傾向があります。
これは、数千億円規模のプロジェクトの納期を絶対に守らなければならないという、強い責任感の表れでもあります。
ただし、業界全体として働き方改革は進んでおり、昔のような「無茶な働き方」は減ってきています。
また、プロジェクトベースで働くことのメリットとして、一つの大きなプロジェクトが無事に完了した後には、比較的まとまった長期休暇(リフレッシュ休暇)を取得しやすいという文化がある企業も多いです。
常に忙しいわけではなく、メリハリをつけて働くスタイルが基本だと理解しておくと良いでしょう。
まとめ
プラント業界について、その偏差値ランキングから、仕事の仕組み、特徴、向き不向き、そして内定獲得のポイントまで詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?この業界は、数千億円規模のプロジェクトを、世界中を舞台に動かすという、他では決して味わえない壮大なスケールとやりがいに満ちています。
その一方で、求められる責任は重く、環境もタフであることは間違いありません。
しかし、困難な課題に立ち向かい、多様な仲間と協力して巨大な「ものづくり」を成し遂げたいと本気で願う人にとって、これほど魅力的なフィールドはないでしょう。
この記事が、あなたの業界研究の一助となり、挑戦への一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。