
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就職活動において、エントリーシート(ES)は必ずと言っていいほど提出を求められます。
しかし、多くの就活生が最初に直面するのが、「いつからESの準備をすればいいのか?」という問題です。
大学1、2年生の人たちは特に、ESとは何なのか、具体的に何を聞かれるのか、などわからないことは多いはずです。
というわけで今回はそんな方たちに向けて就活のESの準備はいつから始めればいいのかということを解説していきたいと思います。
目次[目次を全て表示する]
【エントリーシート いつから】ESとは?
ESとは、エントリーシートの略称で、就職活動で企業に提出する書類の1つで、志望動機や自己PR、長所や短所などの自己分析やアピールポイントを記入します。
ESは、採用担当者が学生の人柄や適性を見極める重要な資料であり、選考の通過や面接の内容に影響します。
そのため、企業が求める人物像に合わせて内容を変える必要があります。
したがって、ESは、就職活動において非常に重要な書類であると言えます。
ESと履歴書は何が違うの?
就職活動で必要な書類には、ESと履歴書がありますが、これらの違いがわからない方も多いと思います。
ESと履歴書の1番大きな違いは、ESは自分の志望動機や自己PR、将来のビジョンなどを自由に記入する書類であるのに対して、履歴書は自分の氏名や学歴などの基本情報をフォーマットに沿って記入する書類であるという点です。
バイトの面接前などで履歴書の提出を求められたことがある人は履歴書については想像しやすいと思いますが、あれに志望動機や自己分析などを加えたものがESです。
また、文章量も違い、一般的にESの方が文章量は多いです。
【エントリーシート いつから】ES作成はいつから始めるべき?
就活生にとって、ESは最も重要な選考書類の1つです。
しかし、ESの作成にかかる時間はそれなりに長く、適切な表現や内容を考えることが求められます。
そこで、ESをいつから書き始めるべきか、という疑問を持つ人も多いと思います。
そこで以下では、ESの作成に必要な時間やポイントを踏まえて、いつからESを書き始めるのが最適かについて解説します。
サマーインターンに参加する場合
大学3年の春ごろ募集が始まるサマーインターンに参加しようと考えている場合、いつごろESの準備を始めたらいいのでしょうか。
大学2年生冬~大学3年生春ごろ
サマーインターンのES締め切りは、インターンの種類や企業によって異なりますが、一般的には インターンの開始日の2ヶ月前 が目安とされています。
例えば、7月から9月にかけて開催される短期サマーインターンの場合は、 5月から6月 に募集締め切りが多いです。
ESの作成に時間がかかりそうだなと思う方は大学2年生冬~大学3年生春ごろを目安に準備に取り掛かるのがいいでしょう。
大学4年から就職活動を始める場合
早期内定や内々定をもらわずに大学4年の春から就活を本格的に取り組もうと考えている人はいつごろESの準備を始めたらいいのでしょうか。
4~5月ごろ
大学4年から就職活動を始める場合は、ESの作成についても注意が必要です。
一般的には4月から5月が目安とされていますが、業界や企業によって異なる場合があります。
例えば、マスコミや広告などの業界は、大学3年の11月から12月にかけて選考を開始する場合が多く、ESの提出期限もそれに合わせて早まります。
また、外資系やベンチャー系企業は、サマーインターンシップやオータムインターンシップから内定につながることが多いため、大学3年の4月から5月にかけてESを提出する必要があります。
そのため、参加したい企業の募集締切や選考スケジュールを事前に調べ、早めにESを作成する必要があります。ESの作成には自己分析や就活情報の収集が欠かせません。自分の強みや志望動機を明確に伝えることで、書類選考を通過する可能性が高まります。
【エントリーシート いつから】企業がESで見ていること
ESは自由形式だからといって、なんでも書いていいのかと言ったらそれは違って、採用担当者がみている重要なポイントがあります。
下記にて、ESでみられる重要なポイントを説明します。
自己分析の深さ
自己分析の深さがESで評価される理由は、自己分析が自己PRの土台となる要素だからです。
自己PRは就活生が自分をアピールする重要な項目なので、採用担当者は必ず見ています。自己分析が浅いと自己PRも弱くなってしまい、内定を得ることも難しくなってしまいます。
また、自己分析が深いということは、自分自身を客観的に見ることができることを示しています。
自己分析を深めることで、自分自身の強みや弱み、価値観や興味を明確にし、自分自身の将来像を描くことができ、自身にとってのメリットもあります。
さらに深い自己分析を書くことで自分自身の強みを生かせる職場や仕事に出会いやすいというメリットもあります。
自己分析を行い、自分自身の価値観や興味を明確化することで、自分に合った職場や仕事に出会いやすくなります。
入社後のキャリアプラン
ESでは、自分の将来の目標や希望する職種や業務などを記入することがあります。
これは、単に志望動機を伝えるだけでなく、入社後のキャリアプランを明確にすることが目的です。
採用担当者は、ESで応募者がどのようなキャリアを描いているかを見て、その企業で実現できるかどうかを判断します。
また、応募者が自分のキャリアに対して真剣に考えているかどうかも見ています。
ESで入社後のキャリアプランを書く際には、具体的で現実的な内容にすることが大切で、自分の強みや適性、興味や関心を踏まえて、その企業でどのような仕事がしたいか、どのような成果が出したいか、どのようなスキルや知識が必要かなどを考えて書きましょう。
自社とのマッチ度の確認
企業はエントリーシート(ES)を通じて、応募者のキャリアプランや適性を判断するだけでなく、自社との相性が合っているかどうかも確認しています。
特に、応募者の価値観や目標が企業の社風や業務内容と一致しているかを見極めることは、長期的な雇用の観点から非常に重要なポイントとなります。
自社とマッチしていない人材を採用すると、入社後のミスマッチによる早期退職につながるリスクがあるため、慎重に選考を行います。
そのため、企業が求める人材像を把握し、それに沿った自己PRや志望動機を記述することが重要です。
例えば、チームワークを重視する企業であれば、協調性を強調するエピソードを盛り込むことで好印象を与えることができます。
【エントリーシート いつから】就活の流れ
ESは就活の初期段階で提出することが多い書類ですが、それだけでは内定には至りません。
就活にはさまざまな選考ステップがあり、それぞれに合格しなければなりません。
就活の全体の流れを知っておくことで、ESを書く際にも自分の目標や志望動機を明確にすることができやすくなると思います。
一般的な就活の流れは以下の通りです。
自己分析・企業研究
ESを書く前には自己分析・企業研究が欠かせません。
面接では、志望動機や自己PRなどを言えるようにする必要がありますが、事前に自己分析をしておくことで、根拠のある回答ができるようになります。
自己分析をする方法はいろいろありますが、一つの方法として、自己分析ツールを使うことがあります。
自己分析ツールとは、インターネット上で質問に答えるだけで、自分のタイプや特徴を診断してくれるツールのことで、無料で就職支援会社や就活サイトなどが提供しているものもあります。
また、企業研究をすることで、その企業の特徴や魅力、事業内容やビジョン、社風や制度などを理解することができ、なぜその業界、企業を志望しているのかを採用担当者にアピールすることができます。
企業分析には志望する企業や競合他社のIRやSNSをチェックしたり、OB訪問などをすることが有効です。
自分に合った方法を見つけて自己分析と企業分析を早めに終わらせておきましょう。
履歴書・ESの作成
自己分析と企業分析を終えたら、次は履歴書やESの作成に取り掛かりましょう。
履歴書やESは、自分の経歴やスキル、志望動機や適性などを採用担当者に伝える重要な書類です。
履歴書やESの作成には、以下のポイントに注意してください。
一つの履歴書やESで何社も応募すること
履歴書やESは、自分が志望する企業や職種に対する熱意や適性を伝えるために、内容を変えることが必要です。
一つの履歴書やESで何社も応募すると、ありきたりで抽象的な内容になってしまい、採用担当者への印象が薄くなります。
誤字脱字・字が汚いこと
採用担当者は、履歴書やESを見て、自分の会社や仕事に対する真剣さや態度を判断しています。
そのため、履歴書やESには、誤字脱字や表記揺れなどのミスがないように注意深くチェックしなければいけません。
また、手書きの場合は、字が汚くならないように気をつけましょう。
誤字脱字や字が汚いと、採用担当者に不快感や不信感を与え、不採用になりやすいです。
そのため、履歴書やESは、綺麗に印刷して提出しましょう。
会社説明会・面接
会社説明会とは、企業が自社情報を提供する場であり、選考に必要な情報を詳しく説明しています。
多くの企業は3月に説明会を設けていますが、説明会前に ESの提出を求める企業も多くあるので事前にESを書いておくことをお勧めします。
一方、面接は企業が就活生の適性や人物を判断する場であり、自己PRや魅力を伝えることが大切です。
そのため、参加前には自己分析と企業分析を行い、服装や適切なマナーに気を配ることが重要です。
以下で、就活に役立つツールを解説しますので、ぜひ使ってみてください。
就活エージェント
就活エージェントとは、就活生の就職活動をサポートしてくれる無料のサービスです。
専任のアドバイザーが自分に合った企業を紹介してくれたり、面接対策や履歴書添削などを行ってくれたりします。
就活エージェントに登録すると、非公開求人にも応募できるチャンスがあります。
興味のある方は、こちらから登録してみてください。
内定
面接やグループディスカッションに合格したら内定がもらえます。
就活において、内定がもらえるのは一般的に大学4年(大学院2年)の10月が正式な内定日とされています。
ただし、業界や企業によっては、それよりも早く内定を出すところもあります。
例えば、外資系企業やベンチャー企業、マスコミ企業などは、大学3年(大学院1年)の秋〜冬に選考を開始し、早ければ大学3年(大学院1年)の冬に内定を出す場合もあります。
また、内定の前段階として内々定というものがあります。内々定とは、内定がもらえると決まっている状態で、契約なしの口約束のみのものです。
経団連に加盟している企業は、採用選考活動が開始する6月1日以降に内々定を出し始めます。
つまり、就活で内定をもらうためには、6月以降に選考に進むことが重要です。
【エントリーシート いつから】就活スケジュール
就職活動を円滑に進めるためには、スケジュールを正しく把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
特に、インターンシップやエントリーのタイミングを逃さないように、各時期ごとのポイントを押さえておく必要があります。
就活の流れを理解することで、自己分析や企業研究を効果的に行い、適切な時期に必要な対策を講じることができます。
ここでは、大学3年生の夏から大学4年生の内定獲得までのスケジュールについて詳しく解説します。
大学3年夏
大学3年生の夏は、多くの企業がインターンシップを実施する時期であり、就活準備の第一歩となる重要な期間です。
特に、大手企業や外資系企業では、夏のインターンシップを経て早期選考に進むケースが多く、早い段階で就活のスタートを切ることが求められます。
この時期に業界や企業の特徴を把握し、自分に合ったキャリアの方向性を見極めることが重要です。
また、インターンシップに参加することで、業務内容を体験しながら、実際の仕事の流れや社風を理解する機会を得ることができます。
選考過程ではエントリーシートや面接が必要な場合もあるため、早めに準備を進めることが大切です。
特に、志望動機や自己PRを明確にし、書類作成や面接対策に取り組むことで、今後の本選考にも活かすことができます。
大学3年秋冬
大学3年生の秋から冬にかけては、多くの企業がプレエントリーや会社説明会を開催し、本選考へ向けた準備が本格化する時期です。
企業の採用活動が活発になるため、情報収集を徹底し、自分が興味のある業界や企業の選考スケジュールを把握することが重要になります。
また、この時期には冬のインターンシップが開催される企業も多く、参加することで実務経験を積みながら企業理解を深めることができます。
一部の企業では、冬のインターン参加者を対象に早期選考を実施するケースもあるため、積極的にエントリーすることが推奨されます。
夏のインターンに参加できなかった場合でも、この時期に経験を積むことで、就活本番に向けた準備を進めることが可能です。
大学4年春
大学4年生の春になると、多くの企業で本選考が始まり、エントリーシートの提出や筆記試験、面接が実施される時期になります。
この時期は、多くの企業が採用活動を本格化させるため、エントリーシートの作成や面接準備に追われることが予想されます。
計画的に時間を確保し、質の高い応募書類を作成することが重要です。
特に、企業ごとに求める人材像や選考プロセスが異なるため、志望する企業ごとにカスタマイズしたエントリーシートを作成することが求められます。
また、筆記試験の対策も重要であり、SPIや玉手箱など、企業が採用する試験形式を把握し、事前に対策を講じる必要があります。
この時期は、エントリー数が多くなり、スケジュール管理が難しくなるため、締め切りをしっかり確認し、計画的に進めることが重要です。
大学4年生6月〜
一般的に、多くの企業が6月頃に内定を出し始め、本選考が終盤に差し掛かる時期です。
エントリーシートの提出から内定までには、約2か月かかることが多いため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。
この時期には、周囲の学生が内定を獲得し始め、焦りを感じることもあるかもしれませんが、自分のペースを大切にすることが重要です。
6月以降も選考を行う企業は多く、特に中小企業やベンチャー企業では、秋採用を実施するケースもあります。
また、一度選考に落ちてしまった場合でも、視野を広げて別の企業を探すことで、新たなチャンスを得ることができます。
内定を得た後は、入社までの期間を有効に活用し、社会人としての準備を進めることが大切です。
【エントリーシート いつから】ESは早く提出するメリット
一般的に、エントリーシートの提出期限は長めに設定されていますが、早めに提出することにはさまざまなメリットがあります。
特に、企業側の評価基準として志望度や熱意が重要視される場合、提出時期が合否に影響を与えることもあります。
ここでは、エントリーシートを早めに提出することの利点について詳しく解説していきます。
好印象を持たれやすい
エントリーシートの選考は、多くの企業で提出順に行われることが一般的です。
そのため、締め切り間際に提出するよりも、早い段階で提出することで、企業側に熱意や志望度の高さを伝えることができます。
また、企業の採用担当者は、応募者の行動から姿勢や仕事への取り組み方を見ているため、素早く提出することで前向きな印象を与えられる可能性があります。
特に、人気企業や応募者数の多い企業では、選考の序盤で優秀な学生が評価されるケースが少なくありません。
そのため、できるだけ早いタイミングでエントリーシートを提出することで、じっくりと評価してもらいやすくなります。
しっかりとしたクオリティのエントリーシートを、可能な限り早く提出することが、選考を有利に進めるためのポイントとなります。
合否で迷ったときに採用させることも
企業がエントリーシートを評価する際、応募者の能力や経験が似ている場合、どちらを採用するか迷うことがあります。
そのような状況では、より熱意が伝わる応募者が選ばれることが多いため、エントリーシートの提出時期が合否に影響を与えることもあります。
特に、企業は志望度の高い人材を求めているため、早めに提出することで「この会社に入りたい」という強い意思をアピールできます。
一方で、締め切り直前に提出した場合、企業側に「本当にこの企業を第一志望として考えているのか」と疑念を持たれる可能性があります。
また、企業の採用枠には限りがあり、早期に評価の高い応募者が確保されると、後半の応募者は相対的に選考が厳しくなることもあります。
そのため、できるだけ早い段階で提出することで、採用される可能性を高めることができます。
【エントリーシート いつから】ES提出が遅いことで起きるデメリット
前述では、エントリーシートを早く提出することのメリットを紹介しましたが、逆に提出が遅れることで生じるデメリットもあります。
特に、応募者数の多い企業では、提出のタイミングが選考の結果に影響を及ぼすことも少なくありません。
ここでは、エントリーシートの提出が遅れた場合に起こる可能性のあるリスクについて解説します。
これらの点に注意し、スムーズな就職活動を進められるようにしましょう。
提出が遅いとしっかり読んでくれない
大企業や人気のある企業では、エントリーシートの提出数が数百から数千に及ぶことも珍しくありません。
そのため、企業の採用担当者がすべての応募書類を細かく確認することは、現実的に難しい場合があります。
特に、締め切り間近に大量のエントリーシートが一斉に提出されると、1つ1つを丁寧に読む余裕がなくなってしまうことがあります。
また、企業側は限られた時間の中で優秀な人材を選抜しなければならないため、早い段階で提出されたエントリーシートの方が、じっくりと評価される可能性が高まります。
一方で、締め切り直前に提出されたエントリーシートは、他の応募者と比較する余裕がなく、選考の優先度が低くなることもあり得ます。
選考が始まる順番はES提出順
多くの企業では、エントリーシートの提出締切を一度だけではなく、一次締切・二次締切など複数回に分けて設定することがあります。
こうした企業では、エントリーシートの提出順に応じて選考が進められるため、遅く提出すると、その分だけ選考の機会が減る可能性があります。
特に、応募者の多い企業では、早い段階で優秀な人材が見つかると、それ以降の選考枠が少なくなることがあります。
そのため、後半の締め切りで提出した場合、同じレベルのエントリーシートでも、企業側の採用枠の状況によって合否が変わることもあり得ます。
また、定員に達した時点で募集が終了する場合もあるため、希望する企業の選考を受けられないリスクを避けるためにも、早めの提出が重要です。
【エントリーシート いつから】ESを早めに提出するためのポイント
エントリーシートは、就職活動において最も重要な書類の一つであり、早めに準備し、提出することが選考をスムーズに進めるための鍵となります。
しかし、締め切り間近になって慌てて作成すると、内容が十分に練られず、クオリティが下がってしまう可能性があります。
そこで、エントリーシートを早めに提出するためのポイントを押さえ、計画的に進めることが大切です。
ここでは、スケジュール管理、事前準備、頻出項目の対策について解説します。
スケジュール管理が大切
エントリーシートを早めに提出するためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。
締め切りを把握していないと、提出期限が迫ったときに焦ることになり、質の低いエントリーシートを出してしまうリスクが高まります。
そのため、企業ごとの提出期限を一覧で管理し、余裕を持って準備することが重要です。
スマートフォンのカレンダーアプリやリマインダー機能を活用すれば、事前にアラートを設定し、提出期限を忘れることを防ぐことができます。
また、エントリーシートの作成には時間がかかるため、1社ごとに締め切り直前に取り組むのではなく、早めにドラフトを作成し、修正を加えながら完成度を高めることが理想的です。
特に、複数の企業に応募する場合は、提出時期が重なることが多いため、計画的に進めないと負担が大きくなります。
事前に必要な情報を集める
エントリーシートをスムーズに作成するためには、事前に必要な情報を収集しておくことが重要です。
特に、自己分析や業界研究を進め、自分の強みや適性、興味のある業界や企業の特徴を把握しておくことで、内容の質を高めることができます。
企業ごとに求める人物像や社風、事業内容が異なるため、それぞれに適したアピールポイントを考えることが求められます。
そのため、企業の採用ページや説明会の情報、社員のインタビュー記事などを活用し、企業の特徴を把握しておくことが有効です。
また、エントリーシートの設問は、企業ごとに異なる部分もありますが、共通してよく聞かれる質問も多いため、あらかじめ回答の方向性を考えておくと、作成の効率が向上します。
よく聞かれる項目は回答を考えておく
エントリーシートには、多くの企業で共通して問われる項目があります。
例えば、「自身の強み(長所・短所)」「志望動機」「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」といった質問は、ほとんどの企業で求められる内容です。
これらの項目は、事前にしっかりと考えておくことで、エントリーシートの作成をスムーズに進めることができます。
特に、自己PRやガクチカは、自分の経験を具体的に述べる必要があるため、エピソードを整理し、どのように伝えるかを練っておくことが大切です。
また、志望動機に関しては、企業ごとにカスタマイズする必要がありますが、基本的な軸は決めておくことで、効率的に作成できます。
事前に回答を準備しておくことで、締め切りが迫った際にも焦らず対応でき、内容のクオリティも維持しやすくなります。
まとめ
今回は就職活動においてとても大切であるエントリシート(ES)について見てきました。
エントリシートについての情報から企業がエントリシートで見ていること、就活スケジュール、早期提出のメリットやそのポイントなど詳しく解説してきました。
エントリシート作成の上で大切なことは事前準備です。
志望する業界や企業の内定を確実につかめるようにESの準備はなるべく早く済ませておきましょう。

_720x550.webp)
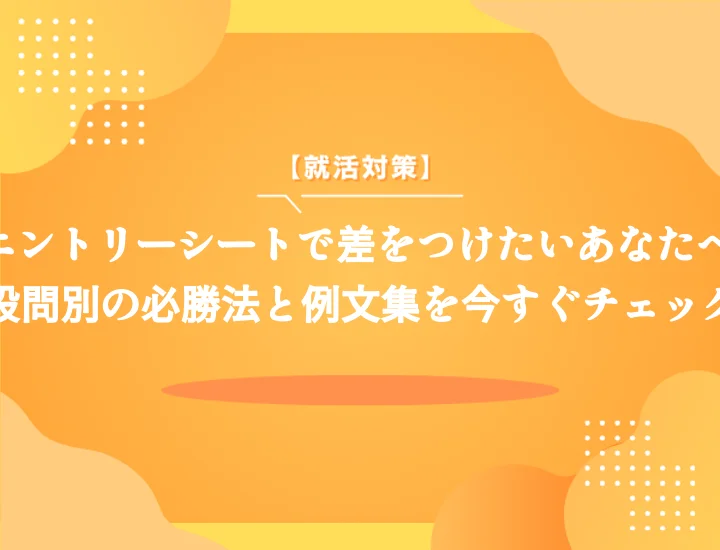

_720x550.webp)





