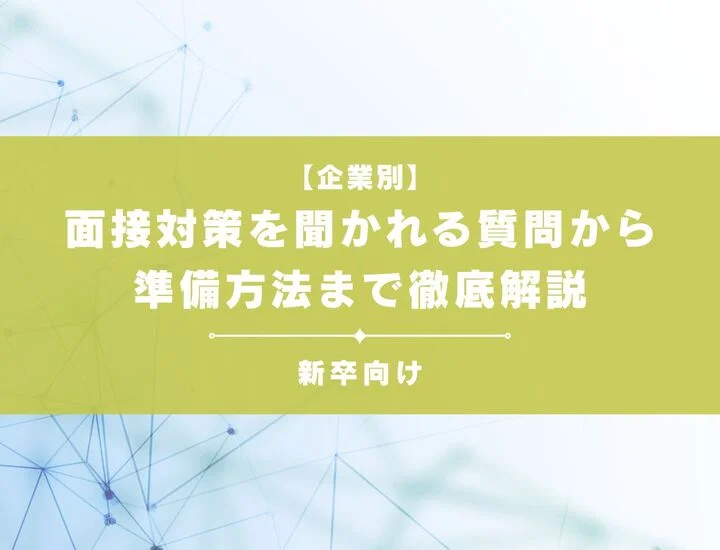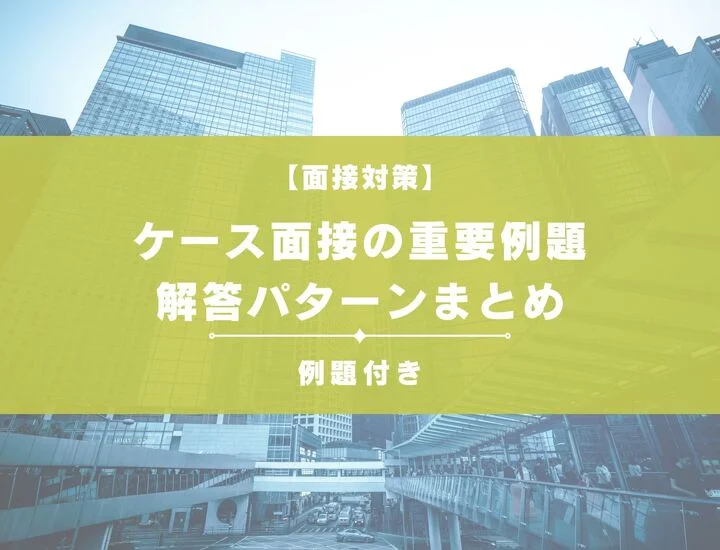HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
面接では、応募者のスキルや経験だけでなく、社会人としての基本的なマナーや受け答えの内容も評価されます。
マナーがなっていない、話し方が悪い、事前準備が足りていないといった理由で不採用になってしまうことも少なくありません。
しかし、面接での失敗を次につなげることで、より良い結果を得ることができます。
本記事では、面接で落ちる原因を解説し、それを防ぐための対策や、次の面接に向けた準備方法について詳しく説明していきます。
【面接落ちた】フェーズごとの主な理由
面接は大きく「一次面接」「二次面接」「最終面接」に分かれ、それぞれで求められるポイントが異なります。
そのため、一次面接では問題なく通過できても、二次面接や最終面接で落ちてしまうことがあります。
各面接ごとに評価基準が異なるため、それぞれのポイントを理解し、対策を立てることが重要です。
ここでは、各段階でチェックされる内容や落ちる理由について解説します。
一次面接
一次面接は、主に人事担当者が面接官を務めることが多く、基本的なビジネスマナーやコミュニケーション能力が評価されます。
この段階では、学生の第一印象が大きく影響し、話し方や態度、礼儀が重要視されます。
また、自己紹介や自己PR、志望動機などの基本的な質問が中心となるため、分かりやすく簡潔に伝えられるかが鍵となります。
一次面接で落ちる主な理由としては、「話がまとまっていない」「ハキハキ話せていない」「志望動機が曖昧」などが挙げられます。
事前に話す内容を整理し、明確に伝えられるよう練習することが大切です。
二次面接
二次面接では、現場の責任者や配属予定の上司が面接官を務めることが多く、実務能力や企業とのマッチ度が評価されます。
一次面接よりも深掘りされるため、志望動機や自己PR、ガクチカに関する質問が多くなります。
また、「入社後にどのように活躍したいか」など、具体的なキャリアビジョンが問われることもあります。
二次面接では、自分の強みを業務と結びつけて話せるようにし、企業の求める人材像を理解した上で回答することが重要です。
最終面接
最終面接では、役員や社長などの経営層が面接官を務めるため、企業理解や会社との相性が重視されます。
これまでの面接とは異なり、「なぜこの会社なのか」「将来的にどう成長していきたいのか」といった長期的な視点での質問が増えます。
また、経営層は会社の理念や価値観を大切にしているため、企業との相性を慎重に見極める傾向があります。
最終面接では、企業のビジョンと自分のキャリアプランを一致させ、長期的に貢献できる人材であることを伝えることが重要です。
【面接落ちた】マナーがなっていない
面接では、応募者のスキルや経験だけでなく、社会人としての基本的なマナーも評価されます。
身だしなみや態度、話し方といった要素は、相手に与える印象を大きく左右するため、注意が必要です。
特に、社会人として基本的なルールを守れない場合、「この人と一緒に働きたいか」と疑問を持たれてしまうことがあります。
ここでは、面接に落ちやすい人のマナーについて、具体的なポイントごとに解説していきます。
身だしなみが悪い
面接では、清潔感のある服装が求められます。
寝癖やシワだらけのスーツ、靴の汚れなどは、相手にだらしない印象を与えてしまいます。
特に、第一印象は数秒で決まると言われており、最初の見た目が悪ければ、その後のやり取りにも影響を与える可能性があります。
また、身だしなみが整っていないと「準備ができていない」「仕事でも細かい部分をおろそかにする」と思われることがあります。
面接前には、鏡で全身を確認し、髪型や服装を整えることが重要です。
声が小さい
面接では、はっきりとした声で話すことが求められます。
声が小さいと、自信がないように見えるだけでなく、話している内容が伝わりにくくなります。
また、面接官に対する熱意が感じられず、志望度が低いと誤解される可能性があります。
緊張してしまうことは仕方ありませんが、普段よりも意識して声を大きくすることで、相手にしっかりと自分の考えを伝えることができます。
面接前に深呼吸をして気持ちを落ち着け、ゆっくりとした口調で話すことを意識しましょう。
態度や姿勢が悪い
面接では、話す内容だけでなく、話していないときの態度や姿勢も重要です。
猫背になっていたり、足を組んで座っていたりすると、相手にだらしない印象を与えてしまいます。
また、相手の目を見ずに視線をそらしたり、腕を組んでしまったりすると、消極的または反抗的な態度に見られることがあります。
面接では、背筋を伸ばし、適度に相手の目を見ながら話すことを意識しましょう。
また、話を聞く際には、うなずいたり表情を動かしたりすることで、積極的な姿勢をアピールすることができます。
無断遅刻をする
面接に遅刻することは、面接官に対して非常に悪い印象を与えます。
特に、無断で遅刻をしてしまうと、時間を守る意識が低いと判断され、選考を通過するのは難しくなります。
どうしても遅れてしまう場合は、できるだけ早く企業に連絡し、到着予定時間を伝えることが必要です。
また、余裕をもって面接会場に到着できるように、事前にアクセス方法を確認し、早めに出発することを心がけましょう。
遅刻のリスクを減らすためには、公共交通機関の遅延情報をチェックし、面接の30分前には到着するように計画するのが理想的です。
社会人の基本的マナーが守れていない
面接は、社会人としての常識や基本的なマナーを確認する場でもあります。
挨拶をしない、敬語が正しく使えない、相手の話を遮るといった行動は、マイナスの印象を与えてしまいます。
また、スマートフォンの電源を切らずに着信音が鳴ってしまうと、集中力やマナーに欠けると判断される可能性があります。
社会人としての基本的な礼儀を身につけるためには、事前に面接のマナーを確認し、練習することが大切です。
「この人と一緒に働きたい」と思われるような言動を意識し、礼儀正しく対応することが求められます。
【面接落ちた】受け答えが悪い
面接では、受け答えの内容が評価に大きな影響を与えます。
話し方ひとつで、相手に与える印象が大きく変わるため、適切なコミュニケーションを意識することが重要です。
ここでは、面接で落ちやすい受け答えの特徴を具体的に解説し、改善のポイントについて説明していきます。
結論から話せていない
面接では、結論から話すことが重要です。
面接官は短時間で応募者の考えを理解しようとするため、話の順序がわかりにくいと、内容をつかみにくくなります。
例えば、「なぜこの会社を志望したのか」という質問に対して、背景や経緯から話し始めると、聞き手は何が言いたいのかを推測しながら聞くことになります。
これでは面接官の負担が大きくなり、印象が悪くなってしまう可能性があります。
「御社の〇〇という点に魅力を感じ、志望しました」と最初に伝え、その後に理由やエピソードを補足することで、伝わりやすい回答になります。
簡潔に話せていない
面接では、要点を押さえて簡潔に話すことが求められます。
話が長すぎると、面接官は途中で集中力を失い、内容を聞き取るのが難しくなってしまいます。
また、余計な情報が多いと、肝心のポイントがぼやけてしまい、応募者の強みや適性が伝わりにくくなります。
特に、自分の経験やスキルをアピールする際は、「結論」「根拠」「具体例」の順で話すことを意識すると、簡潔でわかりやすい回答になります。
事前に模擬面接を行い、話の長さを調整することも効果的です。
質問と回答がかみ合っていない
面接では、質問の意図を正しく理解し、それに沿った回答をすることが重要です。
質問と回答がかみ合っていないと、「この人は人の話をきちんと聞けるのか?」と面接官に疑問を持たれてしまう可能性があります。
例えば、「この仕事で活かせる強みは何ですか?」と聞かれた際に、自分の強みの説明だけをして、業務との関連性に触れないと、回答の方向性がずれてしまいます。
相手の質問の意図をしっかり理解し、ポイントを押さえた返答をすることで、的確なコミュニケーションができるようになります。
【面接落ちた】対策ができていない
面接では、事前の準備が合否を左右します。
しっかりとした対策ができていないと、面接官に「本気度が低い」「自社で活躍するイメージが湧かない」と判断され、選考を通過するのが難しくなります。
ここでは、面接対策が不十分なことで落ちやすい例を具体的に説明し、対策方法を解説していきます。
企業研究ができていない
企業研究が不十分だと、面接で適切な受け答えができず、企業への理解や志望度の低さを疑われてしまいます。
例えば、「当社の事業内容をご存じですか?」という質問に対して、表面的な情報しか答えられないと、「本当に当社に興味があるのか?」と面接官に不信感を持たれる可能性があります。
また、企業の特徴やビジョンを理解していないと、「なぜこの会社を志望したのか」という質問にも説得力のある回答ができません。
事前に企業の公式サイトやIR資料、ニュース記事などをチェックし、業界の動向や競合企業との違いを把握しておくことが大切です。
逆質問ができない
面接の終盤に設けられる「逆質問」は、応募者の志望度や思考力を測る重要な場面です。
何も質問しないと、「特に関心がない」「どの企業でもいいと考えている」と受け取られる可能性があります。
逆に、的確な質問をすることで、企業への理解を深めるだけでなく、「入社後のビジョンをしっかり持っている」という印象を与えることができます。
例えば、「御社の○○のプロジェクトに興味がありますが、新入社員が関われる機会はありますか?」といった具体的な質問をすることで、積極的な姿勢を示すことができます。
スキル・経験が伝えられていない
自分の強みや経験を適切に伝えられないと、面接官に「この人を採用するメリットがわからない」と思われてしまいます。
たとえ優れたスキルや経験を持っていても、話し方が曖昧だったり、具体性に欠けたりすると、魅力が十分に伝わりません。
例えば、「チームワークが得意です」と言うだけでは説得力がなく、「大学のゼミで○○のプロジェクトを担当し、○○の役割を果たしたことで、チーム全体の成果が向上した」というように、具体的なエピソードを交えることが大切です。
【面接落ちた】次に活かす方法
面接で不採用になってしまうと、誰でも落ち込んでしまうものです。
しかし、大切なのはその経験を次に活かすことです。
ここでは、不採用を前向きに捉え、次につながる行動について説明していきます。
落ちた理由をメールで聞く
不採用になった際、企業に理由を尋ねることで、具体的な改善点を把握できます。
企業によっては回答してくれない場合もありますが、丁寧な姿勢で尋ねることで、フィードバックを得られることがあります。
例えば、「面接の際に改善すべき点がございましたら、今後の成長のためにご教示いただけますと幸いです」といった形で尋ねると、企業側も対応しやすくなります。
フィードバックを受けることで、自分の弱点を客観的に理解し、次の面接でより良い受け答えができるようになります。
面接の内容を振り返る
面接を振り返ることは、次の選考に向けた重要なステップです。
面接でどのような質問をされたか、どのように答えたかを思い出し、良かった点と悪かった点を整理しましょう。
特に、答えに詰まった質問や、話がまとまらなかった部分を振り返ることで、次回の面接に向けてより良い準備ができます。
また、面接官の反応も重要なポイントです。
話している最中に相手の表情が曇ったり、深掘りされる質問が多かったりした場合は、伝え方や内容に問題があった可能性があります。
【面接落ちた】次の面接への準備
面接で落ちないためには、事前の準備が重要です。
面接の流れを理解し、基本的なマナーを再確認することはもちろん、緊張を和らげる方法や、質問に対する効果的な回答を準備することが大切です。
ここでは、面接に向けた具体的な準備方法について詳しく説明していきます。
面接のマナーを再確認
面接では、第一印象が大きな影響を与えます。
挨拶の仕方、服装、時間厳守などの基本的なマナーを改めて確認し、自然に実践できるようにしておきましょう。
例えば、入室時のノックの回数や、椅子に座るタイミング、退室時の一礼など、細かな動作も評価の対象となります。
また、清潔感のある服装を心がけ、シワや汚れのないスーツを着用することも大切です。
社会人としての基本的なマナーを守ることで、面接官に好印象を与えることができます。
緊張を解消する方法
面接で緊張しすぎると、普段通りのパフォーマンスが発揮できなくなります。
緊張を和らげるためには、「面接は一つの経験」と捉え、過度なプレッシャーを感じないようにすることが大切です。
また、面接前に深呼吸をしたり、リラックスできる音楽を聴いたりするのも効果的です。
「落ちても次がある」と考え、完璧を求めすぎずに臨むことで、自然体で受け答えができるようになります。
緊張をコントロールすることで、落ち着いた態度で面接に臨めるようになります。
各質問に対する効果的な回答方法
面接では、よくある質問に対して事前に答えを用意しておくことが重要です。
特に、「自己紹介」「志望動機」「強みと弱み」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」といった質問は、ほぼ必ず聞かれるため、ポイントを押さえた回答を準備しましょう。
具体的には、「結論→理由→具体例→再び結論」の流れで話すことで、簡潔かつ分かりやすい回答になります。
また、企業ごとに求める人物像が異なるため、それに合わせた回答を考えることも大切です。
数字を使う
面接で話す内容に数字を取り入れることで、説得力を高めることができます。
たとえば、「アルバイトで売上向上に貢献しました」と言うよりも、「新しい接客方法を導入し、月間売上を15%増加させました」と伝えるほうが、具体的な成果がイメージしやすくなります。
また、「サークルのリーダーとして活動しました」と言うよりも、「50人のメンバーをまとめ、3カ月間のプロジェクトを成功させました」と数字を加えることで、話の規模感が伝わります。
より具体的に話す
面接では、話の内容が曖昧だと伝わりにくく、面接官に良い印象を与えにくくなります。
そのため、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識して話すことが重要です。
たとえば、「私はチームワークを大切にしています」とだけ伝えても、具体的なイメージが湧きません。
しかし、「ゼミのグループ研究で、リーダーとしてメンバー5人の意見を調整し、3週間で発表資料を完成させました」と言えば、どのような状況でチームワークを発揮したのかが伝わります。
コミュニケーション能力の強化
面接では、単に正しい答えを述べるだけでなく、面接官と円滑なコミュニケーションを取ることも重要です。
聞かれた質問に対して的確に答えるだけでなく、相手の反応を見ながら会話を進める力が求められます。
このスキルを向上させるためには、日常的に会話の練習を行い、意識的に相手の話を聞くことが効果的です。
また、プレゼンテーションの練習を通じて、自分の考えをわかりやすく伝える力を養うことも、面接対策として有効です。
企業研究と自己分析の徹底
面接官は、「なぜこの企業を志望したのか」「どのように貢献できるのか」を重視しています。
そのため、企業の理念や事業内容、競合他社との違いを理解し、それに基づいた回答を準備することが重要です。
また、自分の長所や短所を整理し、過去の経験を振り返ることで、説得力のあるエピソードを準備できます。
自己分析を通じて、自分がどのような価値を提供できるのかを明確にすることで、面接官に好印象を与えることができます。
模擬面接を通じての事前準備
本番に向けて、模擬面接を行うことは非常に有効です。
友人やキャリアセンターの担当者と一緒に実践的な練習を行い、フィードバックをもらうことで、改善点を見つけることができます。
また、録音や録画をして自分の話し方や表情を客観的に確認することもおすすめです。
模擬面接を重ねることで、本番でも自信を持って受け答えができるようになり、より良いパフォーマンスを発揮できるようになります。
【面接落ちた】お悩みQ&A
面接を受けた後、多くの就活生は結果が気になり、不安になることがあります。
特に、面接に落ちた場合、その理由が気になることもあるでしょう。
しかし、面接の結果に一喜一憂するのではなく、次に向けた対策を考えることが大切です。
ここでは、面接後のよくある質問について回答し、次につなげるためのポイントを解説します。
面接の落ちた理由を聞くのは非常識ですか?
面接に落ちた理由を企業に尋ねることは、決して非常識ではありません。
むしろ、次回の面接に向けた改善点を知るために有効な手段といえます。
ただし、聞き方には注意が必要です。
「なぜ落ちたのですか?」と直接的に聞くのではなく、「今後の選考に活かしたいため、改善点を教えていただけますか?」といった前向きな姿勢で問い合わせることが大切です。
すべての企業が回答してくれるわけではありませんが、フィードバックをもらえれば、次の面接対策に役立ちます。
面接で落ちた理由おきくのは電話でもいいですか?
電話で問い合わせることも可能ですが、企業側の負担を考えると、メールでの問い合わせが望ましいです。
企業の担当者は忙しいため、電話では対応しにくい場合があります。
一方、メールであれば、企業側が都合の良いタイミングで返信できるため、相手に配慮した方法といえます。
問い合わせる際は、「お忙しいところ恐縮ですが、今後の選考に活かしたいため、フィードバックをいただけますと幸いです」と、丁寧な文面を心がけることが重要です。
面接に落ち続けて自信がなくなってきた…どうすればいい?
面接に落ちると、自分に問題があるのではないかと落ち込んでしまうこともあります。
しかし、面接は「自分がダメ」なのではなく、「企業との相性が合わなかった」だけのことも多いです。
大切なのは、落ちた理由を分析し、次の面接で改善することです。
例えば、面接での回答が曖昧だった場合は、自己分析を深める、話し方を見直すなどの対策が考えられます。
また、第三者にフィードバックをもらうのも有効な方法です。
焦らず、自分に合う企業を見つけることを意識しながら、前向きに就活を続けていきましょう。
まとめ
面接で不採用になる原因は、マナーの欠如、受け答えの不適切さ、事前対策の不足にあります。
身だしなみや態度、話し方に気を配り、企業研究を徹底することで、面接官に好印象を与えることができます。
また、質問には結論から簡潔に答え、相手の意図を正しく理解することが重要です。
不採用となった場合でも、振り返りやフィードバックを活用し、次につなげる努力をすることで成長できます。
しっかりと準備をし、自信を持って面接に臨みましょう。