
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
就職活動の一次面接は、企業との最初の接点となる重要な選考ステップです。
「一次面接だからまだ大丈夫」と油断してしまうと、準備不足が原因で思わぬ不合格に繋がることもあります。
この記事では、一次面接の特徴や面接官が見ているポイント、通過するための対策を詳しく紹介していきます。
今後の面接を乗り越えるための準備に、ぜひ活用してください。
【一次面接は落ちるとやばい】一次面接の特徴
就職活動における一次面接は、選考の最初の関門となる場です。
ここでは企業が学生の基本的な印象や適性を見極めるため、短時間で効率的に情報を得ようとします。
面接の雰囲気や面接官の特徴は、最終面接とは大きく異なるため、事前に傾向をつかんでおくことが対策のカギとなります。
面接官は若手の現場社員が多い
一次面接では、若手の現場社員が面接官を務めるケースが多く見られます。
これは、実際に現場で働く社員の目線で学生の雰囲気や人柄を見たいという企業側の意図があるためです。
一方で、こうした面接官は採用担当の専門職ではないため、質問内容もオーソドックスなものが中心になる傾向があります。
たとえば、「学生時代に力を入れたこと」や「自己PR」などが主な質問です。
形式ばった受け答えよりも、自分の言葉で率直に話すことが求められます。
志望者数が多いため面接時間が短い
一次面接では、多くの応募者と限られた時間内で面接を行う必要があるため、一人あたりの面接時間が短くなる傾向にあります。
そのため、面接官が学生の本質を深く掘り下げて見極めるのは難しく、主に第一印象や話し方、受け答えの姿勢など、基本的な部分が重視されます。
質問も「なぜ当社を志望したのか」「どんな仕事がしたいか」など、簡潔な答えが求められるものが多くなります。
このような面接では、話の構成や伝え方をあらかじめ整理しておくことが大切です。
【一次面接は落ちるとやばい】誰でも受かることはできるのか?
就活の一次面接は「まだ本番ではない」と軽く考える人もいますが、実際には大きな選考の壁となる場面です。
「一次面接なんて誰でも受かる」と思って油断してしまうと、思わぬところで落選してしまうことも少なくありません。
ここでは、一次面接で落ちる人の割合とその背景について詳しく解説します。
一次面接の落ちる割合
一次面接に落ちる割合は、企業や業界によって大きく異なります。
特に大企業では応募者数が非常に多いため、限られた面接枠の中で多くの人を選抜する必要があり、一次面接の通過率は比較的低くなる傾向があります。
一般的には、30%〜50%程度が一次面接で落ちるともいわれていますが、人気企業ではそれ以上に絞り込まれることもあります。
一方、中小企業や採用人数の多い企業では、ある程度広く学生の話を聞く目的で、一次面接の合格率が高めに設定されているケースもあります。
【一次面接は落ちるとやばい】面接官がチェックするポイント
就活の最初の関門である一次面接では、「基本的なことしか聞かれない」と考えて油断してしまう学生も少なくありません。
ここでは、一次面接で面接官が重視しているチェックポイントを詳しく紹介していきます。
第一印象
一次面接では、最初の数分で応募者の印象が大きく左右されると言われています。
第一印象は、話し方だけでなく、姿勢や表情、服装の清潔感、挨拶の仕方など複数の要素から構成されています。
どれだけ話の内容が良くても、だらしない服装や無表情な態度では、評価を下げてしまう可能性があります。
面接官は多くの応募者と短時間で接するため、最初の印象がその後の評価に影響を与えることも珍しくありません。
身だしなみや立ち居振る舞いに注意を払うことが、一次面接を突破する第一歩といえます。
基本的な社会人としてのマナーが身についているか
一次面接では、ビジネスマナーの基本ができているかを面接官はチェックしています。
たとえば、ノックの回数、入室時の挨拶、椅子に座るタイミングなど、学生の対応ひとつひとつが見られています。
マナーは一朝一夕で身につくものではありませんが、最低限の所作ができていないと、入社後の教育コストが高いと判断されることもあります。
社会人としてふさわしい振る舞いができるかどうかは、面接突破だけでなく、働くうえでの信頼獲得にも直結します。
普段から意識してマナーを身につけておくことが重要です。
コミュニケーション能力があるか
一次面接では、話の内容以上に、相手とスムーズに会話を成立させる力があるかを確認されます。
たとえば、質問の意図をしっかり理解し、それに対して適切な内容を簡潔に返答する姿勢が求められます。
また、表情やうなずきなどの非言語的な反応も、良いコミュニケーションには欠かせません。
緊張しても誠実に受け答えできるかどうかが評価のポイントになるため、練習を通して伝え方の工夫を身につけることが大切です。
「話し上手」である必要はありませんが、「伝わる話し方」ができるかどうかが重要とされています。
入社意欲や熱意があるか
どの企業も「本気で入社したい」と考えている学生に来てほしいと考えています。
そのため一次面接では、志望動機がしっかりしているか、自社への理解があるか、仕事への熱意が感じられるかといった点が重視されます。
また、質問に対する姿勢や表情などからも、入社への意欲は自然と伝わります。
表面的な言葉ではなく、「なぜその企業を選んだのか」「どんなことをやりたいのか」といった深掘りされた理由を自分の言葉で伝えることが大切です。
一緒に働きたいと思える人材であるか
企業は、新卒採用においてスキルよりもポテンシャルを重視しています。
そのため、面接官は「この人と一緒に働きたいか」「チームに合いそうか」といった感覚的なポイントも見ています。
協調性や素直さ、向上心といった要素が会話や態度から感じられると、好印象を与えることができます。
特に一次面接では、話の中身よりも人柄や雰囲気といった要素の評価が重視される傾向にあります。
「信頼できそう」「育てやすそう」と感じてもらえることが通過のカギとなります。
明るくハキハキと話せているか
面接の場で緊張するのは当然ですが、明るくはきはきと話すことは非常に重要です。
聞き取りやすさは内容の伝わりやすさに直結し、元気さや自信の有無も印象として大きく残ります。
仮に内容が完璧でなくても、前向きな姿勢や笑顔で話せていれば、それだけで印象は良くなります。
逆に、声が小さく、目線を合わせずに話してしまうと、やる気がないと思われてしまうリスクもあります。
練習を通じて発声や話し方を改善し、自分らしい明るさを表現できるようにしておくことが大切です。
【一次面接は落ちるとやばい】落ちてしまう人の特徴
一次面接は選考の初期段階ですが、油断は禁物です。
ここで落ちてしまう原因は、面接の基本が身についていないことや、企業研究・自己分析の甘さなど、準備不足によるものが多く見られます。
ここでは、一次面接で落ちてしまいやすい人に共通する特徴を紹介し、面接通過に向けた改善のヒントをお伝えします。
ビジネスマナー不足や身だしなみ
一次面接では、第一印象がその後の評価に大きく影響します。
そのため、身だしなみやマナーが整っていないと、それだけでマイナス評価につながります。
たとえば、服装がだらしなかったり、挨拶やお辞儀が適切でなかったりすることで、「社会人としての基本ができていない」と判断されるおそれがあります。
面接ではスーツの着こなしや髪型、姿勢や表情など、見た目に関する点を細かく見られていることを意識しましょう。
事前に鏡の前でチェックし、緊張していても基本の礼儀が自然にできるように準備することが大切です。
自己分析ができていない
自己分析が不十分なまま面接に臨むと、自分の強みや志望動機をうまく伝えられません。
たとえば、「長所は協調性です」と述べても、それを裏づける経験や考え方を語れなければ、説得力は生まれません。
面接官は「この人は何をしたいのか」「何を大事にしているのか」を見ようとしているため、自己理解が浅いと評価は下がります。
自己分析が進んでいないと、話に一貫性がなくなったり、志望動機が浅くなったりすることがあります。
自分の過去の経験を振り返り、そこから得た学びや価値観を整理することが、面接対策の第一歩となります。
仕事や会社の理解度が低い
企業に対する理解が浅いまま面接に臨むと、志望動機が曖昧になり、印象が薄れてしまいます。
面接官は「なぜうちの会社を選んだのか」「どの仕事に関心があるのか」といった点を重視しているため、具体的に答えられないと準備不足と判断されかねません。
特に一次面接では、基本的な業務内容や企業理念などについての知識があるかがチェックされます。
企業研究を行う際は、ホームページやIR資料、社員インタビューなどを参考に、業界や競合との差別化も意識して整理しておくことが重要です。
エントリーシートと発言に一貫性がない
エントリーシートと面接で話す内容に矛盾があると、信頼性に欠けると判断されてしまいます。
たとえば、ESで「企画職を志望している」と書いておきながら、面接で「営業職にも興味がある」と話してしまうと、「本当に志望しているのか」と疑念を持たれることがあります。
発言の一貫性がないと、面接官はその場しのぎで答えている印象を受け、熱意や誠実さが伝わりません。
ESを提出したあとは、必ず自分の記述内容を見直し、面接でも同じ軸で話ができるよう準備しておきましょう。
コミュニケーション能力が低い
一次面接では、スムーズに会話が成り立つかどうかが重要な評価ポイントです。
面接は、業務に必要な最低限のコミュニケーション能力が備わっているかを見極める場でもあります。
たとえば、質問の意図を正確にくみ取れず的外れな回答をしてしまったり、話が長くまとまりのない印象を与えたりすると、「相手の立場で考えられない」「仕事での会話も噛み合わないのでは」と不安を持たれてしまいます。
また、緊張のあまり表情が硬くなりすぎていたり、声が小さすぎたりするのもマイナス要因になり得ます。
入社意欲が低い
入社意欲が低いように見える学生は、一次面接で不合格となる可能性が高くなります。
志望動機が曖昧であったり、「なぜこの会社なのか」「どんな仕事がしたいのか」といった質問に対し、自信のない口調で答えてしまうと、熱意が伝わりにくくなります。
面接官は、「この人は本当にうちの会社で働きたいと思っているのだろうか」と感じた時点で、評価を下げる傾向があります。
入社意欲は、発言だけでなく表情や態度からも判断されます。
企業研究や自己分析を徹底し、自分の言葉で志望理由を語れるように準備しておくことが重要です。
結論ファーストで回答していない
一次面接で落ちる人の中には、話の構成がわかりづらいという共通点があります。
特に「結論が最後に来る」「何を言いたいのか見えにくい」話し方は、面接官にとって大きなストレスとなります。
面接は限られた時間内での対話であり、短時間で印象を残すためには、最初に結論を伝えることが求められます。
そのうえで、理由や具体的なエピソードを補足することで、論理的でわかりやすい話し方になります。
たとえば、「私の強みは責任感です。
その理由は~」という形で伝えると、聞き手も理解しやすくなります。
逆質問の質が低い
面接の最後によくある「何か質問はありますか?」という逆質問も、評価に影響する要素の一つです。
逆質問があまりに漠然としていたり、調べればすぐにわかるようなことを聞いてしまうと、「この学生は事前に企業研究をしていないのでは」と思われてしまいます。
また、質問の意図が不明確だったり、面接官を困らせるような聞き方をすると、コミュニケーション能力の面でもマイナスに捉えられます。
良い逆質問とは、自分の志望動機や関心とつながりのある内容で、かつ面接官の話を踏まえて展開されるものです。
【一次面接は落ちるとやばい】今からできる通過するための対策
一次面接に落ちないため、今からでもできる対策にはどんなものがあるか解説します。
しっかりとした準備をしておくことが面接通過するために重要です。
再度正しいマナーと身だしなみのチェックをする
面接で第一印象が与える影響は非常に大きく、どれだけ優れた受け答えができたとしても、マナーや身だしなみが整っていないと印象を大きく損ねてしまいます。
自分では気づきにくい部分も多いため、一度家族や友人に身だしなみや立ち居振る舞いをチェックしてもらうのも効果的です。
入室の際のお辞儀や挨拶、椅子の座り方、話す時の姿勢など、社会人としての基本動作を丁寧に見直しましょう。
清潔感のある服装や髪型を心がけることが、第一印象を良くする大きな鍵になります。
自己分析と企業、業界研究の見直し
一次面接で落ちてしまう場合、自己理解や企業理解が浅い可能性があります。
自己分析では、自分の価値観や強み、弱みを明確にし、なぜその企業で働きたいのかを筋道立てて語れるようにしましょう。
また、企業研究は公式サイトだけでなく、IR情報、業界ニュース、社員インタビューなども確認し、独自の視点を持つことが大切です。
業界研究も並行して行うことで、他社との差別化が図れるようになり、志望動機に説得力が増します。
一度原点に立ち返り、自分の言葉で語れる準備を整えましょう。
模擬面接繰り返し行い面接に慣れる
面接の通過率を高めるためには、場数を踏んで「慣れる」ことが欠かせません。
特に一次面接では緊張から本来の力を発揮できない学生も多いため、繰り返しの練習が効果的です。
大学のキャリアセンター、就活エージェント、AI面接練習ツールなどを活用し、客観的なフィードバックを得ながら改善を重ねましょう。
模擬面接では、話し方、声のトーン、表情、回答の構成など幅広くチェックしておくことが重要です。
実践の場を想定した練習を重ねることで、本番でも落ち着いて受け答えができるようになります。
一次面接の特徴をよく知る
選考の段階によって、面接で見られるポイントは異なります。
一次面接では、基本的なマナー、受け答えの姿勢、志望意欲など、学生の基礎的な資質を中心に評価されます。
ここで評価されるのはスキルよりも「社会人としての土台があるかどうか」や「最低限のコミュニケーション力があるか」といった部分です。
逆に言えば、この段階でつまずいてしまうのは基本的な準備不足が原因であることも多いです。
まずは一次面接で何が見られているのかを理解し、そのうえで対策を立てていきましょう。
会話のキャッチボールを意識する
面接では、ただ一方的に話すのではなく、面接官との対話として会話のキャッチボールができているかが重要です。
相手の質問の意図を正しく理解し、それに沿った回答ができるかどうかで評価が分かれます。
「聞かれたことに答える」ことは当たり前ですが、結論から述べ、その理由やエピソードを補足する形を意識すると伝わりやすくなります。
また、話し終わった後の間や相手の表情を読み取りながら話すと、自然なやり取りになり印象も良くなります。
コミュニケーション力は訓練で伸ばせる要素です。
志望動機を明確にする
企業側が特に重視するのが志望動機です。
数ある企業の中でなぜその企業を選んだのか、自分のキャリアビジョンとどのように結びつくのかを明確に伝えることが必要です。
企業のビジョンや取り組みに共感していること、職種に対する熱意、自分の強みを活かせる根拠などを盛り込むことで、説得力が増します。
また、他の企業にも同じようなことを言っていないかという視点でチェックされるため、使い回しではなく、その企業だからこその志望理由を作るようにしましょう。
大きな声でハキハキと話す
話す内容が良くても、声が小さく聞き取りづらいと、それだけで印象が下がることもあります。
一次面接では明るく、ハキハキと話すことで自信や意欲を伝えることができます。
特に面接の序盤で印象が固まりやすいため、最初の挨拶や自己紹介は特に意識して話しましょう。
口の開き方、声の通りやすさ、話すスピードなどを録音や動画で確認して練習するのも効果的です。
表情やアイコンタクトにも気を配ることで、さらに良い印象を与えることができます。
質問の回答を用意する
一次面接でよくある質問に対しては、事前に自分の答えを整理しておくことが重要です。
たとえば、「自己紹介」「学生時代に力を入れたこと」「志望動機」「短所とその克服」などは定番質問です。
想定問答を用意しておくことで、いざ質問されたときも焦らず、自分の伝えたいことを的確に表現できます。
ただし、丸暗記ではなく、ポイントを押さえた自然な言葉で話すことを心がけましょう。
準備することは安心感にもつながり、本番での自信にもつながります。
【一次面接は落ちるとやばい】よく聞かれる質問
一次面接は選考の初期段階であるものの、企業が就活生の基本的な適性を見極める重要な場でもあります。
ここからはよくある質問とその意図について解説していきます。
特に頻出する質問には、面接官が注目している評価ポイントが詰まっています。
自己紹介
一次面接での自己紹介は、面接官が応募者の第一印象をつかむ重要なタイミングです。
この質問の意図は、本人確認の意味合いに加えて、面接に向けた準備ができているかを確認することにあります。
自己紹介では、大学名や学部、簡単な経歴を話したうえで、自分の性格や強みを簡潔に伝えると効果的です。
ダラダラと話すのではなく、1分程度にまとめると印象が良くなります。
また、面接官がその後の質問を考える材料として自己紹介を活用することもあるため、話す内容には一貫性と流れを持たせておくと良いでしょう。
長所・短所
一次面接で長所や短所が聞かれる理由は、入社後にどのような形で組織に貢献できるのか、またどのような点でサポートが必要なのかを判断するためです。
この質問では、自分の性格や行動特性を正しく理解しているかが問われます。
長所は単に「明るい」「真面目」などの一言で終わらせず、具体的なエピソードを添えて伝えることが大切です。
短所についても、課題にどう向き合い、どんな改善を試みたのかまでを説明することで、成長意欲や誠実さをアピールできます。
ガクチカ
ガクチカは、学生時代にどのような目標を持ち、どんな工夫や努力を重ねて成果を出したのかを示す質問です。
企業はこの質問を通じて、課題解決能力や粘り強さ、リーダーシップなどのポテンシャルを見極めています。
「アルバイトで売上を伸ばした」「部活動で大会を運営した」などの経験を具体的に語りつつ、行動や考え方に焦点を当てると効果的です。
また、その経験から得た学びを今後の仕事にどう活かしたいかまで述べることで、より深い自己PRにつながります。
自己PR
自己PRは、自分の強みを企業に向けて明確に伝える場です。
一次面接では、自分の持つ資質や能力をどのように企業で活かせるかという観点での説明が求められます。
ただ強みを述べるだけでなく、実際にその強みを発揮した場面を具体的に示すことで説得力が増します。
さらに、志望企業の業務内容と結びつけて、「この強みは御社の〇〇の場面で活かせると考えています」と伝えると、入社後のイメージが面接官にも伝わりやすくなります。
再現性のある強みをエピソードとともに語ることが、自己PR成功のカギです。
志望動機
志望動機では、「なぜこの企業なのか」「この業界の中でもなぜここを選んだのか」といった視点が重視されます。
特に一次面接では、応募者の志望度や企業理解が浅いとすぐに見抜かれてしまいます。
企業の理念や事業内容、働き方の特徴などをきちんと調べたうえで、自分の経験や将来像とどのように重なるのかを丁寧に伝えましょう。
たとえば、「学生時代の〇〇の経験から、御社の〇〇の取り組みに共感しました」といった形で、自分の経験と企業の特長をリンクさせると説得力が高まります。
他社との違いを意識した志望動機が評価されやすくなります。
逆質問
逆質問は、面接官に対して応募者から質問をすることで、企業への関心や準備の度合いをアピールできる重要な時間です。
「入社後のキャリアパスについて教えていただけますか」や「新人が担当する業務の特徴を教えていただきたいです」といった質問は、具体性があり意欲が伝わります。
一方で、「福利厚生は何ですか」など、事前に調べればわかる質問ばかりだと、志望度の低さや準備不足と受け取られることもあります。
逆質問では、事前に企業研究を行ったうえで、自分なりの疑問や興味を持って質問する姿勢が重要です。
対話型のやりとりを意識して、入社後を見据えた前向きな質問をするよう心がけましょう。
【一次面接は落ちるとやばい】受かる可能性が高いサイン
面接を受けたあと、「手応えがあった」「これは落ちたかもしれない」といった感覚を持つ就活生は多いものです。
しかし、感触だけでは判断が難しい場合もあるため、面接官の対応や面接中のやりとりを冷静に振り返ることが大切です。
ここでは、合格の可能性があるとされる代表的なサインを具体的に解説していきます。
面接時間が想定よりも長い
予定されていた面接時間よりも長くなることは、面接官がその応募者に強い関心を持っているサインといえます。
通常、面接時間はあらかじめ決められており、基本的にはその範囲で進行します。
しかし、応募者の話が興味深かったり、より深く知りたいと感じた場合、自然と会話が長引く傾向があります。
とくに追加で質問されたり、雑談が多くなる場合は、面接官が前向きな印象を持っている可能性が高いです。
ただし、時間が長い=必ず合格とは限らないため、話の内容や相手のリアクションも含めて総合的に判断しましょう。
面接中に頻繁にメモを取っている
面接中に面接官がこまめにメモを取っている場面に遭遇すると、不安に感じるかもしれません。
しかし、これは合否判断を慎重に進めている、あるいは次の選考に情報を引き継ぐための準備である可能性が高いです。
一次面接では、現場社員や若手社員が担当することも多く、最終的な合否を人事部に委ねるケースも少なくありません。
そのため、面接の記録を詳細に残しておく必要があり、特に好印象を受けたポイントを残すために熱心にメモを取ることがあります。
メモを取られているからといって気にしすぎず、落ち着いて対応を続けることが大切です。
企業について積極的にアピールされる
面接官が自社の魅力や働きやすさについて熱心に語ってくる場合は、合格の可能性が高まっているサインと考えられます。
これは、応募者に対して「ぜひうちで働いてほしい」という気持ちが生まれた結果として見られる行動です。
たとえば、福利厚生の具体的な内容や、職場の雰囲気、社風などを詳しく説明してくれるケースは多くあります。
面接官自身の体験談を交えて説明する場合は、特に好意的な印象を抱いている証拠ともいえます。
このような対応があった場合には、自身の志望度も率直に伝えると、より良い関係性を築くきっかけになります。
他社の応募状況を確認される
「他にどのような企業を受けていますか」といった質問は、多くの面接で行われるものですが、一次面接でこの質問が出た場合は注目すべきポイントです。
企業側がこの質問をする意図には、就活の軸を見極めたいという目的のほか、競合他社への流出リスクを考慮しているケースもあります。
つまり、「この人を確保したい」と思っている場合に、他社の進捗状況を探ることがあるのです。
そのため、具体的な企業名や選考段階を答える際には、軸の一貫性を意識しながら話すとよいでしょう。
ただし、他社の状況を尋ねられたからといって必ずしも合格とは限らないため、あくまで目安として捉えてください。
次回以降の選考の話を持ち掛けられる
一次面接の最後に「次の面接は〇日頃になりそうです」「このあと課題の案内があります」など、次のステップに関する説明があった場合は、高確率で通過していると考えられます。
企業は応募者に対して興味を持っているとき、他社に先を越されないよう、あえて早めに次のステップの情報を提示することがあります。
これは内定につなげたいという意思表示とも捉えられ、特に競争率の高い企業では、次の面接日を仮押さえしておくケースも珍しくありません。
こうした対応を受けた場合は、感謝を伝えつつ前向きな姿勢を見せると、より好印象につながります。
まとめ
一次面接を突破するには、特別なスキルよりも基本的な準備や態度が重要になります。
面接官の立場や評価ポイントを理解し、自分自身を丁寧に伝えることがカギです。
本記事で紹介した対策やポイントをもとに、冷静に準備を進めていけば、確実に通過率を上げられます。
自分の魅力を信じて、面接に自信を持って臨んでください。



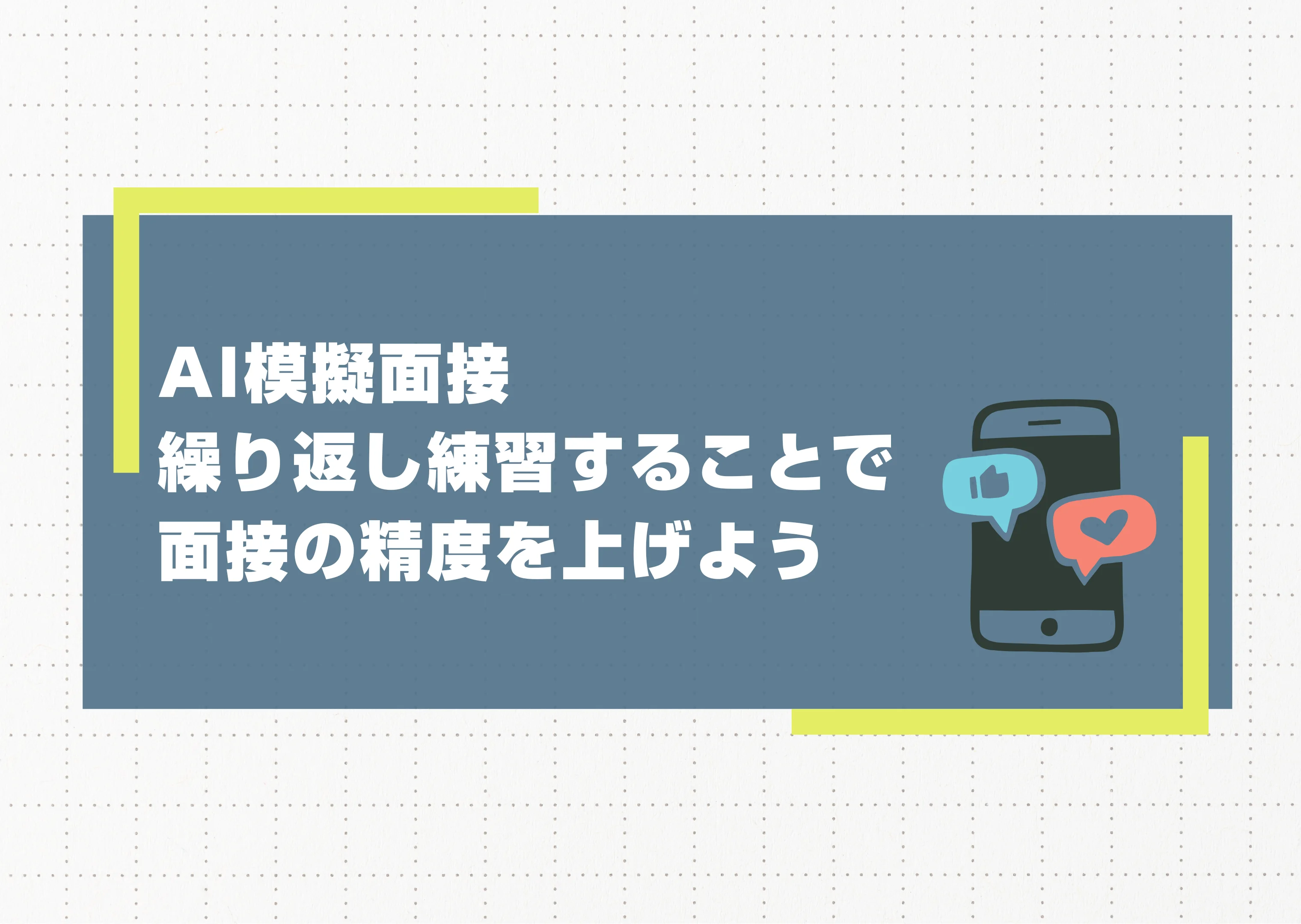



と相性が良い性格とは?仕事・恋愛の相性やおすすめの職業も紹介 (1)_720x550.webp)






