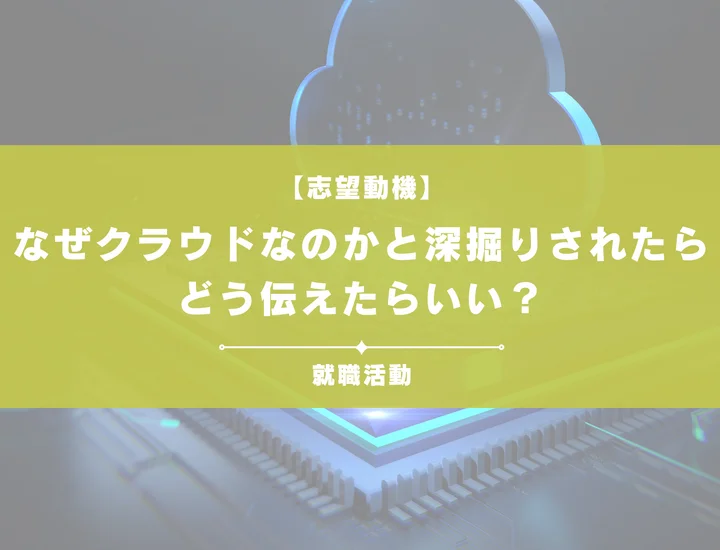HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
-
設備管理の仕事内容
-
設備管理として働くメリット
-
設備管理の志望動機の構成と例文
目次[目次を全て表示する]
はじめに
質の高い志望動機を提出するためには、まずはその職種や業界について理解を深めておく必要があります。
この記事では設備管理の業務内容や就職するメリットについて説明した後に、志望動機の作り方や就職先別の例文を紹介します。
「設備管理職になんとなく興味がある」という方はもちろん「設備管理職を目指しており,
志望動機を書いているものの、クオリティに納得がいっていない」という方もぜひ参考にしてみてください。
設備管理は安定・キャリア志向の学生に人気!
設備管理は安定を重視するキャリア志向の学生に人気の職種です。
建物や工場、商業施設などの設備を点検、補修し、トラブルを未然に防ぐ役割を担うため、業務内容がはっきりしており、仕事の見通しを立てやすいことが特徴です。
また、インフラや大手企業の設備に関わるケースも多く、景気の変動に左右されにくいという安心感があります。
そして、資格の取得や実務経験がキャリアの積み上げに直結するため、長期的に働きたい方にとっては、将来設計がしやすい点も魅力と言えるでしょう。
【設備管理の志望動機】そもそも設備管理とは?
まず、設備管理とはどのような仕事なのかについて理解を深めておきましょう。
自分が将来どのような業務を担当することになるのか分かっていなければ、質の高い志望動機は出来上がりません。
また、業務内容を理解しておくことで、志望動機の核となるテーマを見つけやすくなるはずです。
ぜひ目を通してみてください。
設備管理の仕事内容(ビル・工場・病院など)
設備管理の仕事は建物や施設の安全、快適な環境を維持するために欠かせない役割です。
対象となる施設はオフィスビルや商業施設、病院、工場など多岐にわたります。
空調や電気、給排水といった各種設備の点検や整備的なメンテナンス、そしてトラブルが起きた時の緊急対応などが求められます。
また、法令で定められた点検の実施や、その結果に基づく修繕計画の立案、実行なども重要な仕事です。
省エネの観点から設備の運転状況を分析し、効率的な運営を考える場面もあります。
設備の異常を未然に防ぐため、機器の状態を常に監視し、細かな変化にも気づけるような観察力と知識が求められます。
施設を裏側から支える仕事の魅力
設備管理の魅力は目立たないながらも人々の生活や業務を支える確かな役割にあります。
ビルや病院、工場といった施設が安全かつ効率的に機能するには設備が正常に稼働し続けることが不可欠です。
また、トラブルを未然に防ぎ快適な空間を維持することは利用者の満足度や業務の生産性にも直結します。
自分の手で点検や修繕を行うことで、建物が正常に動き続けるのを実感でき、達成感と責任感が得られるでしょう。
また、社会インフラの一端を担う仕事であるため、災害時や停電などの非常時にも対応が求められ、そこでの判断や技術が多くの人を助けることにつながります。
人前には出にくい分、直接感謝の言葉をもらう機会は少ないかもしれませんが、建物全体の安心を静かに支える存在として、やりがいのある仕事だと言えるでしょう。
【設備管理の志望動機】新卒で設備管理を志望するメリット
続いて、新卒で設備管理職を志望するメリットについて紹介します。
もちろん別の職種から転職して設備管理職として働く人もいますが、新卒として設備管理職に就職すると、以下のようなメリットを享受できます。
志望動機に書ける項目も多いですから、ぜひ参考にしてみてください。
若いうちから専門性を積み上げられる
設備管理は現場での実務を通じて早期に技術を習得しやすい環境が整っているのが魅力です。
若いうちから多様な設備に触れることで、実践的なスキルを身につけられます。
点検やメンテナンスを繰り返す中で、機器の構造や故障の原因、適切な対応方法を現場で学ぶことができ、座学だけでは得られない知識が蓄積されていくでしょう。
また、経験を積むことで状況判断力や機械の理解が深まり、現場を任される場面も増えてきます。
早い段階から専門的な分野で力を伸ばしたい人にとって、やりがいの大きい職種だと言えるでしょう。
資格取得と実務経験を同時に積める
設備管理の現場では電気工事士やボイラー技士、危険物取扱者など業務に関連する国家資格を取得することが推奨されています。
新卒で入ることで、こうした資格の勉強を実務と並行して進められるのも大きな魅力です。
現場に出て設備に触れながら学ぶことで、テキストだけでは理解しにくい部分も具体的なイメージを捉えやすくなり、効率よく知識を身につけられるでしょう。
また、多くの企業は資格取得支援制度を整えており、試験費用の補助や勉強会の開催など、成長を後押しする体制が整っています。
こうした環境の中で実務経験と資格の両方を積み重ねていくことができ、より高度な設備や責任あるポジションを任される可能性も広がるでしょう。
社会インフラを支えるやりがいを感じられる
設備管理の仕事は先ほども触れたように、建物や施設が安全に機能し続けるための土台を支えるものであり、その意義が非常に大きいです。
病院、工場、商業施設など、社会のあらゆる場面で必要とされる設備の維持を担うことから、自分の仕事が多くの人々の日常生活や業務に直結していると実感できます。
医療現場では空調や電源の安定供給が命に関わる要素となり、工場では設備の不具合が生産ライン全体に影響を及ぼすこともあります。
こうした状況に迅速に対応し、設備の安定化を守ることは非常に責任のある行動であり、大きなやりがいにつながるものです。
【設備管理の志望動機】向いている人・求められる力
続いて、設備管理職に向いている人の特徴や求められる力について紹介します。
以下の4つの項目が当てはまる人は、設備管理職にまさに最適な人物と言えるでしょう。
以下の項目は志望動機に書いても良いですし、自己PRの主題ともなり得る要素です。
自分に当てはまる項目はいくつあるか、考えながら読んでみてください。
コツコツ取り組める慎重な人
設備管理の仕事では日々、点検やメンテナンスを継続して行うことが求められます。
変化が少なく見える作業ではありますが、少しの異常を見逃さず、丁寧に確認を重ねることが施設の安全や利用者の快適性につながります。
したがって、目立つことよりも地道な作業に価値を見出せる人や、ルールや手順を正確に守ることに抵抗がない人に向いているでしょう。
また、記録を丁寧に残して定期点検のスケジュールを守ることも重要であり、継続的な作業を面倒に感じず、コツコツと積み重ねていける慎重な性格の人ほど活躍しやすいです。
機器の異常を察知するにはわずかな音や振動、温度の変化にも敏感である必要があり、細かな変化を見逃さない観察力も活かされます。
探究心
設備管理の分野では常に新しい技術や機器が導入されており、変化に対する柔軟性と学び続ける姿勢が欠かせません。
設備の仕組みや構造を理解し、不具合の原因を突き止めるにはただ決まった作業をこなすだけでは不十分です。
なぜそのトラブルが起きたのか、どのような構造になっているのか掘り下げる探究心がある人ほど現場で重宝されるでしょう。
また、メーカーごとに仕様が異なる機器に対応するためには進んでマニュアルを読み込んだり、現地で得た知識を次の対応に活かしたりすることが必要不可欠です。
電気、空調、ボイラーなど設備の分野は幅広く、一度覚えて終わりではありません。
したがって、わからないことを放置せず納得いくまで追求できる人ほど、スキルの幅を広げていけるでしょう。
コミュニケーション力
設備管理の現場では1人で黙々と作業するだけでなく、周囲との連携も非常に重要です。
作業前の申し送りや、点検中に異常があった場合の迅速な報告、修繕に関する関係者への説明など、様々な人々とやりとりを行います。
また、複数人で作業を行う現場が多く、協力して進めるためにお互いの役割や作業状況を明確に伝え合う必要があります。
専門的な内容を相手に分かりやすく説明する力や、状況に応じた報・連・相ができる力も必須です。
言葉にしないと伝わらない情報も多いため、伝えるべきことはタイミングよく伝えられることが、信頼関係の構築につながるでしょう。
責任感・使命感
設備管理の業務は社会の基盤となるインフラを支える重大な役割を担っています。
ビルや病院、工場といった施設が日々正常に稼働しているのは、設備が滞りなく機能しているからこそです。
この状態を維持するために、設備管理の担当者は点検整備を繰り返し、少しでも異常があればすぐに対応します。
このような仕事は目立たない場所で人々の安全な生活を支える役割を担っており、強い責任感が必要とされます。
【設備管理の志望動機】志望動機を作るポイント
続いて、志望動機を作るにあたって意識しておきたいポイントを5つ紹介します。
以下のポイントを理解している就活生とそうでない就活生とでは志望動機のクオリティが大きく異なります。
また、設備管理職以外を目指す場合でも応用できる要素もありますから、複数の職種を併願している方もぜひ確認しておいてください。
なぜ設備管理なのかを明確にする
志望動機を書く際には、なぜ設備管理という職種を選んだのかをはっきりと伝えることが重要です。
選んだ理由が曖昧なままだと、他の技術職でも良いのではないかと思われてしまう可能性があります。
したがって、自分なりの仕事選びの軸を明確にして、設備管理で異なる点を丁寧に説明することが大切です。
自分がなぜ設備管理を目指しているのかを明確にした後、それをきっかけや体験と結びつけて具体的に書きましょう。
研究、アルバイト、日常生活の中で建物や設備に関心を持った経験があるならば、そのエピソードを交えて書くと説得力が増します。
なぜこの会社なのかを深掘りする
設備管理がしたいというだけでは多くの企業に当てはまる内容になってしまい、志望動機としては非常に弱いです。
企業が本当に知りたいのは「なぜ、数ある企業の中で自社を選んだのか」という視点です。
そこで、企業ごとの特徴や事業内容を入念に調べて、自分の価値観や経験とどう結びつくかを言葉にすることを心がけましょう。
ビル、工場、病院など様々な職場がありますが「なぜその施設を選んだのか」「その施設で成し遂げたいことは何か」などを深掘りすると志望動機の深さが伝わります。
企業理念、研修制度、社風など数字に現れにくい部分を調べて志望動機に盛り込み、自分の言葉で、なぜその会社で働きたいのかを分かりやすく説明することが大切です。
将来像・取得したい資格を具体的に語る
採用担当者はあなたが入社後どのように成長していくかという視点でも志望動機を見ています。
したがって、将来的にどのような設備管理技術者を目指しているのか、どのような資格を取得したいのかを具体的に語ることで、キャリアに対する意識の高さをアピールできます。
将来像を語ることで、入社後の成長や長期的なキャリアを見据えていることが伝わるでしょう。
自分の理想とする姿を描くことで、設備管理という仕事に対して真剣に向き合っていることを伝えることが大切です。
専門知識より姿勢や意欲をアピール
新卒採用においては実務経験や専門知識よりも、仕事に対する成長意欲が重視されます。
よって、設備管理に関する知識が浅いことを不安に感じる必要はありません。
むしろ、知らないことに対して積極的に学び、周囲から吸収しようとする姿勢があるかどうかの方が重視されるでしょう。
これまでの学生生活の中で、コツコツ継続したことや問題に真摯に取り組み解決したことがあれば、それを根拠として添えて問題解決に取り組む姿勢をアピールしましょう。
ポテンシャル採用であることを理解した上で、自分がどのように貢献できるかを考え、表現することを心がけましょう。
適切な構成に沿って志望動機を組み立てる
説得力のある志望動機を作るためには、内容だけでなく構成にも注意を払わなければなりません。
まず、設備管理を選んだ理由を最初に述べ、その上でなぜその会社なのか、入社後にどうなりたいのかという流れで話を展開することで、論理的に整理された文章になります。
順序が曖昧だと伝わりにくく、印象に残りにくい原因となってしまいます。
「結論→理由→エピソード→入社後の貢献」という流れで説明することを心がけましょう。
【設備管理の志望動機】例文まとめ
ここまで紹介してきた内容を踏まえた上で、就職先別に設備管理職を目指す人の志望動機の例文を作成しました。
ポイントや構成などを踏まえた上で作成しているため、あなたが目指している就職先以外に関する例文も参考になるはずです。
時間に余裕がある方は、参考になる部分を箇条書きでメモなどしつつ、読んでみてください。
例文①オフィスビル
貴社を志望する理由は都市機能の中枢を支えるオフィスビルの設備を安全かつ快適に保ち、多くの働く人々の活動を裏から支えたいと感じるからです。
大学在学中にアルバイトでオフィス清掃の仕事をしていた際、空調が止まってしまい現場が混乱していた際、設備管理の方がすぐに駆けつけ状況を確認して対応される姿を目の当たりにしました。
多くの人の働きやすさを守っている存在に強く心を動かされ、自分も支える仕事に就きたいと考えるようになりました。
貴社は首都圏を中心に数多くの大型オフィスビルを管理し、エネルギー管理や省エネの分野にも注力されている点に共感しています。
現場の知識と資格取得を重ねながら、設備の効率的な運用に貢献し、快適な職場環境の維持に尽力する所存です。
例文②マンション
貴社を志望する理由は居住空間としての安全と快適さを守るマンション管理業務に強く関心があるからです。
大学時代、築年数の古い集合住宅に住んでおり、水回りの不調や照明の不具合が発生した際、すぐに設備管理の方が訪問してくださり、原因を説明しながら修理してくださったことが印象に残っています。
その対応によって安心感を得られた体験が、設備管理という仕事の価値を実感するきっかけとなりました。
貴社は住宅設備のトラブル対応だけでなく、リニューアルや長期修繕計画の提案なども含めて、総合的なマンション管理を行っている点に惹かれました。
入社後、電気工事士などの資格を取得しながら、入居者の立場に立った迅速かつ丁寧な対応を徹底し、安全な住環境づくりに貢献する所存です。
例文③工場・倉庫
貴社を志望する理由は生産活動の根幹を支える工場設備の安定稼働に魅力を感じたからです。
大学の実習で製造業の現場を訪問した際、生産ラインが設備トラブルで一時停止してしまいました。
その時、設備担当の方が素早く点検し、的確な処置でラインを復旧させていた姿を目にして、設備管理の現場全体に与える影響の大きさを痛感しました。
貴社は多種多様な工場や物流施設を管理しており、日常点検だけでなく、効率的な運用提案や省エネ支援にも力を入れている点に惹かれました。
入社後は現場で経験を積みながら、トラブル予防と設備の最適化を両立し、安定した生産活動の実現に貢献する所存です。
例文④商業施設・ホテル
貴社を志望する理由は、多くの人が集まる商業施設やホテルにおいて安全性と快適性を同時に実現する設備管理に魅力を感じたからです。
私は旅行が趣味ですが、ある宿泊先で給湯設備のトラブルが発生し、フロントへ連絡したところ、設備管理の方がすぐに対応してくださいました。
おかげで不便を感じることなく過ごすことができ、その後の丁寧な説明と笑顔の対応も非常に印象的でした。
この体験を通じて、自分も安心感を届ける一員になりたいと強く思うようになりました。
貴社は全国の大型商業施設や宿泊施設を幅広く管理し、利用者視点を重視した運営を行っている点に共感しております。
入社後は現場の状況を正確に把握し、素早く対応できる判断力と技術を磨き、施設全体の安心感を支える存在として活躍する所存です。
例文⑤駅・空港
貴社を志望する理由は人の流れが絶えない駅や空港で、インフラの安定を支える設備管理に強い関心があるからです。
以前、空港で停電によるトラブルに遭遇したことがあります。
案内板が消え、利用者が混乱していた中、設備管理の方々が非常用電源を作動させ、空調や表示板の復旧に尽力していた場面を目にしました。
目立たない場所であっても人々の安心と移動を守る存在に心を打たれ、この仕事に対する憧れを持つようになりました。
貴社は公共性の高い駅舎や空港施設の設備管理を多数手がけており、高度な安全管理体制と緊急時の対応力に定評がある点に魅力を感じております。
入社後は突発的な事態にも冷静に対応できる判断力を養い、利用者の安全と円滑な運営を支える設備管理者として成長する所存です。
例文⑥病院・学校施設
貴社を志望する理由は命や教育に関わる現場を設備面から支える意義の大きさに惹かれたからです。
学生時代、実家近くの病院に祖父を送迎した際、院内のエレベーターが故障して使えなくなった際に、設備担当の方が迅速に対応してくださいました。
患者や家族が不安そうな様子だった中、点検の状況を丁寧に説明しながら作業していたその姿に感動し、設備管理という職種が人の安心や命に関わる仕事であることを実感しました。
特に貴社は医療機関や学校施設に特化した設備管理のノウハウを持ち、利用者視点での維持管理を徹底されている点に共感しています。
入社後は緊急対応力と日常の点検精度を高め、患者や児童生徒、その家族が安心して過ごせる環境を守る技術者として貢献する所存です。
【設備管理の志望動機】キャリアパス・将来像
設備管理職のキャリアパスや将来像にはどのようなものがあるのかについても紹介します。
設備管理職は様々なキャリアパスが広がっており、担いたい役割によって取り組むべきことも異なります。
技術力を高めるか、管理職のような形でリーダーとして働くかなど、様々な選択肢があるため、キャリアプランを立てるためにも参考にしてみてください。
資格を取得してできる業務を広げる
設備管理のキャリアにおいて、資格の取得は大きな意味を持ちます。
実務を通じて技術を身につけながら、電気工事士、ボイラー技士、冷凍機械責任者などの資格を取得しておくことで、任される業務の幅が着実に広がっていくでしょう。
電気工事士の資格を取れば高圧機器の取り扱いが可能になり、緊急時の対応範囲が増えるほか、法的な制限をクリアして現場の安全性を高めることにもつながります。
設備管理の現場では「できること」がそのまま信頼と評価に直結するため、資格は自分のスキルを客観的に証明する手段となります。
チームをまとめるリーダー職を目指す
現場での経験を積み、専門知識や判断力が身についてくると、いずれは複数の設備管理スタッフをまとめる立場に進むことが期待されます。
リーダー職になると自分の作業に加えて作業スケジュールの管理、スタッフへの技術指導、トラブル対応の方針決定なども担当するようになります。
この段階になると現場の運営に関与する場面が増え、設備全体の管理体制をどう維持改善していくかを考える視点も必要となります。
現場経験を活かして指導する立場に立ちたいと考えている人には、リーダー職はまさに最適と言えるでしょう。
大規模施設の管理責任者や技術コンサルへ進む
設備管理のキャリアをさらに発展させると、大規模施設の管理責任者や技術コンサルタントといった専門性の高いポジションを目指すことも可能です。
病院、空港、大型商業施設内には複雑で高機能な設備が多い現場もあり、全体の管理を担う責任者が必要です。
また、豊富な現場経験や知識をもとに、第三者の立場から設備管理の課題解決を提案する技術コンサルタントとして進む選択肢もあります。
省エネ対策や老朽設備の更新提案、効率的なメンテナンス体制の構築など、より高い視点から施設全体の品質向上に寄与することが求められます。
現場で得た知見を広く応用し、より大きな視点で施設運営に携われるため、設備管理の仕事を長く続けたい人にとって理想的な将来像の1つです。
【設備管理の志望動機】設備管理に活かせる資格
設備管理として働くにあたって活かせる資格についても紹介します。
いずれも難易度は比較的高いですが、取得することで業務の幅が広がりますし、企業によっては資格手当を支給してくれるところも多いです。
時間に余裕がある方は就活と並行しながら今から勉強を始めても良いでしょう。
第二種電気工事士
第二種電気工事士は設備管理の現場で最も活用される代表的な資格の1つです。
この資格を持っていれば、600V以下の電圧で使用する電気設備の工事や配線作業が可能になります。
ビルや工場などで使われる照明やコンセント、ブレーカーなどの交換、修理、点検を行えるようになるのです。
有資格者でなければ取り扱えない作業が多く存在するため、この資格を持っているだけで業務の幅が大きく広がります。
新人のうちに取得する人も多く、実務経験と並行して取得を目指すことで、早い段階から信頼される技術者として現場に貢献することが可能になります。
筆記と実技の両方が必要ですが、設備にかかる知識を深める第一歩として、多くの方が挑戦する資格です。
危険物取扱者乙種4類
危険物取扱者乙種4類はガソリン、灯油、アルコールなどの可燃性液体を安全に取り扱うために必要な国家資格です。
設備管理の現場ではこうした危険物を使用する設備が設置されていることが多く、安全に扱い、管理するためにこの資格が役立ちます。
非常用発電機の燃料タンクや暖房設備の燃料補充作業など、日常業務でも危険物を扱うことも多いです。
この資格を持っておけば、危険物を保管、点検、補充する業務が可能となり、施設の安全管理にも貢献できます。
また、法的な監督者としての役割を果たすこともできるため、責任あるポジションを早い段階で任せてもらえるようになるでしょう。
二級ボイラー技士
二級ボイラー技士は蒸気や温水を利用するボイラー設備を安全に運転管理するための国家資格です。
設備管理の現場では病院や工場、ホテルなどで大型ボイラーが使われていることが多く、その操作や点検にはこの資格が必須です。
正しい知識と手順に基づいて取り扱わなければ事故につながる可能性があるため、現場での安全性を確保する上で非常に重要な資格と言えます。
この資格を持っておけば、運転記録の作成や異常発生時の初期対応など、専門性の高い業務にも関われるようになります。
また、ボイラーを扱う施設では有資格者の常駐が法律で定められている場合もあるため、就職・転職市場でも高く評価されるでしょう。
第三種冷凍機械責任者
第三種冷凍機械責任者は冷凍機や冷却設備の運転、補修を行うために必要な資格で、冷凍能力が一定以下の装置に対してはこの資格で管理が可能です。
冷蔵倉庫や食品工場、データセンター、病院などでは温度管理が業務の根幹を支えることも多く、冷凍機械の安定稼働が求められます。
この資格を持っておけば、冷媒の性質や冷凍サイクルに関する専門的な知識が身についているという証明ができ、日々の設備点検やトラブル対応の質も向上します。
また、法令上、有資格者による管理が求められる現場も多いため、キャリアの幅を広げるために取得しておきたい資格の1つです。
実務に密接に関わる内容が多いため、現場経験と並行して学ぶことでより理解が深まり、応用力も高まるでしょう。
消防設備士(乙6種)
消防設備士乙種6類は消火器の点検、整備、設置に関わる業務を行うために必要な資格です。
設備管理の仕事では火災時の初期消火を担う消火器の定期点検や法令に基づく維持管理を任される場面が多くあります。
この資格を持っていれば、目視確認をするだけでなく、消火器の内部構造や設置基準に関する深い知識をもとにした点検作業が可能になります。
また、消防法に基づく点検報告書の作成なども任されるようになり、企業では非常に重宝されることでしょう。
近年は防災意識の高まりから消防設備の管理の重要性も増しており、有資格者の需要が高まっているため、ぜひ取得しておきたい資格です。
【設備管理の志望動機】よくある質問(Q&A)
続いて、設備管理職を目指している就活生の方々からよくいただく質問についても紹介します。
以下の質問は就活エージェントを運営する中で多くの就活生の方々から実際にいただいた質問です。
この記事を読んでくれているあなたも気になっているものが多いでしょうから、ぜひ疑問を解消して、すっきりした気持ちで就活を進めるためにも、参考にしてください。
文系だけど設備管理に応募はできる?
設備管理は技術職というイメージから「理系でないと難しいのでは?」と不安に感じる文系の方も多いでしょう。
結論として、文系出身であっても、設備管理の現場で活躍している人は少なくありません。
新卒の方は未経験が前提であるため、入社後に基礎から丁寧に教える研修体制を整えている企業も多く、学部や専攻に関係なくスタートラインに立てる環境が用意されています。
また、設備の仕組みや取り扱いに関する知識は現場での経験や社内教育、資格取得を通して徐々に習得していくものであり、入社時点での専門知識が不足していても問題ありません。
むしろ、コツコツと学ぶ責任感、コミュニケーションを大切にする力などをアピールできれば、理系のライバルがいたとしても、内定を獲得することは十分に可能でしょう。
設備管理になるためにどんな資格をいつまでに取ればいい?
設備管理の仕事では業務に関連した資格を取得していくことが求められます。
特に、入社前から取得しておくと評価されやすいのは第二種電気工事士です。
筆記と実技の両方があるため、時間に余裕のある学生時代に取り組むと、他の就活生に差をつけられます。
一方、実務経験が受験資格になっている資格は、入社後に業務と並行して勉強を進めることが一般的です。
資格取得支援制度を設けている企業も多く、受験料の補助や学習時間の確保など、成長を後押しする仕組みが整っています。
したがって、余裕があれば第二種電気工事士を取得しておきましょう。
それ以外の資格は、無理に目指すよりは、志望動機や自己PR、ガクチカなど、よく聞かれる質問の対策をしっかりしておくことをおすすめします。
設備管理の配属先って選べるの?
設備管理の配属先は企業ごとの事業規模や業態によって異なりますが、勤務地や担当施設があらかじめ決められているケースが多いです。
新卒の場合、研修後に適性や人員配置などの都合を踏まえて配属が決まることが多く、希望が必ず通るとは限りません。
ただし、事前の面談やエントリーシートなどで「病院施設に関心がある」など希望を伝えておけば、考慮される可能性はあります。
とはいえ、配属後も定期的に異動や転勤がある企業に就職する場合は、ライフスタイルの変化に対応しなければなりません。
異動を希望しない方は、あらかじめ企業研究の際に異動の可能性があるか確認しておきましょう。
設備管理って残業や夜勤はある?
設備管理の仕事は施設の稼働時間や管理体制によって勤務実態が大きく変わるため「受ける企業によって変わるのが実情」というのが、この質問への答えになります。
24時間稼働している病院や工場では夜間対応や休日勤務が必要な場合があるため、夜勤や休日出勤が発生することもあるでしょう。
一方、オフィスビルであれば、夜勤は無く、残業も比較的少ない傾向にあります。
ただし、トラブルが発生した場合には予定外の対応が必要になることもあるため、繁忙期や修繕工事の時期には残業が増えることも少なくありません。
ただし、多くの企業では勤務時間の管理やシフト制度を整備しており、過度な長時間労働を避ける取り組みも進んでいるため、そこまで心配する必要はないでしょう。
まとめ
今回は設備管理を目指している方のために、業務内容や向いている人の特徴、キャリアパスや志望動機を作るポイントなどについて紹介しつつ、具体的な志望動機の例文も紹介しました。
設備管理は専門性が高く安定した職業であるため、非常に人気があります。
しかし、一つひとつ丁寧に対策を行えば内定獲得は十分に獲得可能ですから、この記事を参考にまずは質の高い志望動機を作成してください。