
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
【6月に内定なし】6月に内定がないのは手遅れ?今から巻き返せる?
6月に入ってもまだ内定がないと、焦りや不安を感じる就活生の方も多いのではないでしょうか。
周囲の友人が次々と内定を獲得していく中で、「自分はこのままで大丈夫なのだろうか」「もう手遅れなのではないか」と心配になる気持ちはよくわかります。
しかし、結論からお伝えすると、6月にまだ内定がなくても手遅れではありません。
もちろん、現状に危機感を持つことは非常に重要ですが、今からでも戦略的に行動すれば、十分に巻き返すことは可能です。
大切なのは、やみくもに焦るのではなく、現状を冷静に分析し、具体的な対策を講じることです。
これまでの就職活動を振り返り、何が足りなかったのか、どこを改善すべきかを明確にすることで、これからの活動をより効果的に進めることができるでしょう。
通常はどれくらいに内定獲得できる?
「6月に入ったのに、まだ内定がない…」と不安を感じている就活生の方もいるかもしれません。
就職活動における内定獲得時期は、業界や企業、個人の進捗によって様々ですが、一般的に多くの学生がいつ頃内定を獲得しているのか、最新の調査結果を踏まえて解説します。
就活市場の調査によると、多くの学生が3月から6月にかけて内定を獲得しています。
しかし、これはあくまで平均的なデータであり、内定獲得時期が遅れることが必ずしも不利になるわけではありません。
大切なのは、焦らず、自身のペースで就職活動を継続することです。
【6月に内定なし】最新の26卒の内定率と今すべきこと
就職活動も本格化し、6月に入ると周りの友人から内定の報告を聞く機会が増え、焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。
特に、26卒の皆さんは、インターンシップからの早期選考が活発だったこともあり、すでに内定を獲得している人も少なくありません。
しかし、だからといって内定がない状況で悲観的になる必要は全くありません。

株式会社キャリタスの調査によると、2025年6月1日時点での26卒の内定率は83.7%と高水準ではあるものの、就職活動を継続している学生も全体の38%いることが示されています。
内定を保持しながら本命企業の選考を進めている学生もいれば、まだ内定がない状態で活動を続けている学生もいるため、焦りを感じる必要はありません。
大切なのは、現状を把握し、これからどのように行動していくかです。
このセクションでは、最新の26卒の内定状況と、先輩である25卒の同時期の内定状況を比較し、内定がない場合に焦る必要がない理由について詳しく解説していきます。
25卒はどうだった?4年6月時点の内定率
26卒の皆さんが現在の内定状況を把握する上で、ひとつ前の世代である25卒の同時期の状況を知ることは、今後の対策を考える上で非常に参考になります。
株式会社キャリタスの調査によると、2025年6月1日時点での26卒の内定率は83.7%であり、これは前年同時期(2024年6月1日時点)の25卒の内定率85.2%と比較すると、わずかながら下回っています。
このことから、26卒の就職活動は、昨年と比較してわずかに内定獲得のペースが緩やかであるとも考えられます。
もちろん、これはあくまで全体的な傾向であり、個々の学生の状況は様々ですが、昨年の同時期に内定がなかった学生も、その後しっかりと内定を獲得しているという事実を忘れないでください。
6月以降も多くの企業が選考を継続していますし、夏採用や秋採用を行う企業も少なくありません。焦らず、自分のペースで着実に就職活動を進めることが重要です。
4年の3月までに内定が取れれば大丈夫!焦る必要はない
現時点で内定がないからといって、悲観的になったり、焦ってやみくもに選考を受けたりする必要はありません。
就職活動は長期戦であり、内定獲得のタイミングは人それぞれです。
重要なのは、大学卒業までに自身が納得できる企業から内定を得られることです。
キャリタスの調査でも、6月1日時点で内定を保持しながらも就職活動を継続している学生が一定数存在し、その理由として「本命企業がまだ選考中」という回答が最も多いことが示されています。
これは、多くの学生が複数の企業の選考を受け、より良い選択肢を求めて活動している証拠でもあります。
また、大手企業や人気企業の中には、選考スケジュールが遅いところも多く、これから本格的に選考が始まるケースも珍しくありません。
焦りから視野が狭くなり、本来の希望とは異なる企業に決めてしまうことのないよう、冷静に自己分析や企業研究を深め、自身の強みや企業への貢献可能性を具体的に伝える準備を進めましょう。
アルバイト経験など、これまでの経験を活かして、自分の価値を最大限にアピールする構成をしっかりと練り上げることが、今後の内定獲得に繋がるはずです。例えば、PREP法やSTAR法を活用して、結論から具体的なエピソード、そしてそこから何を学び、企業でどう活かせるのかを明確に伝える練習を重ねましょう 。
【6月に内定なし】まずは内定がない原因を把握しよう
6月になっても内定がない場合、まずはその原因を特定することが重要です。
就活の軸が決まっていないと、内定獲得は難しい
エントリー数が少ない
選考対策が不十分
企業の難易度が高すぎる
原因が分からなければ、効果的な対策を立てることができません。
就職活動の進捗は人それぞれですが、共通して見られる原因がいくつか存在します。
例えば、就活の軸が定まっていなかったり、エントリー数が少なかったり、あるいは選考対策が不十分であったりするケースが考えられます。
これらの原因を一つずつ丁寧に分析し、自分に当てはまるものを見つけることで、今後の就職活動の方向性が明確になります。
漠然とした不安を抱えるのではなく、具体的な課題を洗い出し、それに対する解決策を講じることで、内定獲得に近づくことができるでしょう。
就活の軸が決まっていないと、内定獲得は難しい
就活の軸とは、企業選びや自己PRをする際の基準となる、自分なりの価値観や目指す方向性のことです 。
この軸が明確でないと、企業に「なぜこの企業を選んだのか」「入社後に何をしたいのか」を効果的に伝えることが難しくなります。
採用担当者は、学生が自社で働くことへの熱意や、入社後にどのような貢献ができるかを判断したいと考えています。就活の軸が曖昧なままだと、一貫性のない企業選びをしてしまったり、面接での受け答えが抽象的になったりするため、企業側にあなたの熱意や強みが伝わりにくくなってしまうのです。
就活の軸が定まらなければミスマッチの可能性が高まる
就活の軸が定まっていないと、自分にとって何を大切にしたいかが明確でないまま企業選びをしてしまい、結果として企業とのミスマッチが生じやすくなります 。
たとえば、「なんとなく有名だから」「給料が高そうだから」といった理由だけで企業を選ぶと、入社後に「思っていた仕事内容と違った」「社風が合わない」といった問題に直面する可能性があります。
企業側も、早期離職は避けたいと考えています。
そのため、学生が自身の価値観を理解し、それに合致する企業を選んでいるかを重視しています。
ミスマッチを防ぎ、入社後の満足度を高めるためにも、就活の軸を明確にすることは非常に重要です。
正確な業界研究・企業研究ができない
就活の軸が曖昧な状態では、業界や企業を調べる際にも目的意識が持ちづらく、表面的な情報収集にとどまりがちです 。
例えば、「自分は何を重視して働きたいのか」が不明確だと、どの業界や企業が自分に合っているのか判断できず、手当たり次第に情報を集めてしまうことになります。
これでは効率的な情報収集ができないだけでなく、企業の魅力を深く理解することも困難です。
結果として、エントリーシートや面接で具体的な志望動機を語ることができず、他の就活生との差別化も図りにくくなります。
エントリー数が少ない
6月になっても内定がない原因として、エントリー数が少ないというシンプルな理由が挙げられることがあります。
これは案外見落としがちなポイントでもあります。
たとえ万全の選考対策をしていても、応募する企業数が少なければ、それだけ内定を獲得するチャンスも少なくなります。
特に、人気の高い企業ばかりに集中してエントリーし、結果として選考を通過できない場合、全体のエントリー数が伸び悩む傾向にあります。
内定を獲得するためには、ある程度の母数が必要です。自分の興味や適性に合う企業を幅広く探し、積極的にエントリーしていくことで、選考を通過する機会を増やし、内定獲得の確率を高めることができるでしょう。
選考対策が不十分
自己PRや志望動機を書いているのに書類選考に通らない、面接でうまく話せないと感じている場合、それは選考対策が不十分であることが原因かもしれません 。
多くの就活生は、基本的な対策は行っているものの、企業の求める人物像や、自分の強みを効果的にアピールする方法を深く理解できていないことがあります。
例えば、自己PRでは具体的なエピソードを盛り込み、成果を数字で示すことで説得力が増します 。
志望動機では、企業理念や事業内容を深く理解し、それと自身の経験や将来の目標を結びつけて語ることで、企業への熱意が伝わります。
面接では、質問の意図を正確に捉え、論理的かつ簡潔に回答する練習が必要です。
これらの対策を徹底することで、選考通過の可能性を高めることができるでしょう。
企業の難易度が高すぎる
人気企業や大手企業、有名ブランド企業は倍率が非常に高く、どんなに準備をしても簡単に内定をもらえるわけではありません。
多くの就活生がこれらの企業を志望するため、競争は必然的に激しくなります。
もし、これまで応募した企業がすべて大手や人気企業だった場合、それが内定がない原因の一つになっている可能性があります。
もちろん、希望する企業に挑戦することは素晴らしいことですが、現実的に内定獲得の確率を高めるためには、選択肢を広げることも重要です。
漠然と大手を志望するのはNG
「漠然と大手企業が良い」という理由だけで企業選びをしていると、本当に自分に合った企業を見つけるのが難しくなります。
大手企業は確かに安定性やブランド力がありますが、社風や仕事内容が必ずしも自分に合うとは限りません。
中小企業やベンチャー企業にも、魅力的な仕事や成長できる機会が豊富に存在します。
漠然としたイメージだけで企業を絞ってしまうと、思わぬ優良企業を見逃してしまう可能性もあります。
まずは自分の就活の軸を明確にし、その軸に合致する企業を業界や規模にとらわれずに探すことが、納得のいく就職活動につながります。
【6月に内定なし】6月に内定なしから挽回するための方法5選
6月になっても内定がない状況は、多くの就活生にとって不安を感じるものです。
しかし、この段階で内定がなくても、決して挽回できないわけではありません。
焦らず、現状を冷静に分析し、効果的な対策を講じることで、内定獲得の可能性は十分にあります。
大切なのは、これまでの就職活動をただ漠然と続けるのではなく、戦略的にアプローチを見直すことです。
このセクションでは、6月からの挽回に向けた具体的な5つの方法を解説します。
現状把握と就活スケジュールの整理
自己分析をして就活の軸を見つめ直す
業界を絞ってエントリー数を増やす
選考を振り返って原因別に対策をする
秋採用や二次募集の選考情報を調べる
現状把握と就活スケジュールの整理
現状把握と就活スケジュールの整理は、今後の就職活動を効果的に進める上で非常に重要です。
なぜなら、漠然と活動を続けるだけでは、何が課題で、何に時間を割くべきかが見えにくくなってしまうからです。
まずは、これまでにエントリーした企業数、書類選考の通過率、面接の進捗状況などを具体的に数値化してみましょう。
これにより、自身の活動量や、どの選考段階で躓いているのかを客観的に把握できます。
次に、今後の就活スケジュールを整理し、残りどれくらいの期間で、どのくらいの企業にアプローチできそうかを具体的に計画します。
例えば、気になる企業のエントリー締め切りや選考フローをリストアップし、それに合わせて自己分析や企業研究、ES作成、面接練習などの準備期間を設けるといった方法です。
このように現状を把握し、具体的なスケジュールを立てることで、無駄なく効率的に就職活動を進めることができ、焦りや不安の軽減にもつながります。
自己分析をして就活の軸を見つめ直す
6月になっても内定がない場合、自己分析を深め、就活の軸を見つめ直すことは非常に大切です。
なぜなら、就活の軸が明確でないと、企業選びが曖昧になり、結果的にミスマッチな企業に応募してしまったり、面接で説得力のあるアピールができなかったりする可能性があるからです。
具体的な方法としては、まず、これまでのアルバイト経験や学業、サークル活動などで「何を頑張ってきたのか」「どんな時に喜びを感じたのか」「どのような課題に直面し、どう乗り越えたのか」を深掘りしてみましょう。
特にアルバイト経験をガクチカでアピールする際は、「結論を先に書く」「アルバイトを始めたきっかけを書く」「アルバイトのエピソードを書く」「成果を書く」「アルバイトから学んだことを書く」という構成を意識すると、自身の経験から得た学びや強みが明確になります。
業界を絞ってエントリー数を増やす
業界を絞ってエントリー数を増やすことは、効率的に内定獲得を目指す上で有効な戦略です。
なぜなら、興味のある業界を絞り込むことで、企業研究の質を高められると同時に、その業界内の様々な企業にアプローチできるため、内定獲得のチャンスを広げられるからです。
闇雲に多くの業界にエントリーするよりも、特定の業界に特化することで、その業界の動向や企業文化、求める人物像について深く理解することができ、ESや面接でのアピールに説得力を持たせることができます。
具体的な方法としては、まず、自己分析で見つめ直した就活の軸と照らし合わせながら、自分が本当に興味を持てる業界や、自身の強みを活かせそうな業界をいくつかピックアップします。
次に、それらの業界内で、これまで知らなかった中小企業やベンチャー企業にも目を向けてみましょう。
大手企業だけでなく、中堅・中小企業にも魅力的な仕事や成長機会は多く存在します。さらに、選考プロセスが比較的短い企業や、通年採用を行っている企業なども視野に入れることで、内定獲得までのスピードを早めることも可能です。
選考を振り返って原因別に対策をする
これまでの選考結果を振り返り、原因別に対策を講じることは、今後の内定獲得に直結する重要なステップです。
なぜなら、失敗から学び、改善することで、次回の選考に活かせるからです。
具体的には、書類選考で落ちてしまう場合は、ESの書き方、特にガクチカや自己PRの内容に問題がないかを見直しましょう。
例えば、ガクチカにおいては、「結論を先に書く」「アルバイトを始めたきっかけを書く」「アルバイトのエピソードを書く」「成果を書く」「アルバイトから学んだことを書く」という構成が効果的です。
アルバイトのエピソードではSTAR法(状況→課題→行動→結果)を用いて、具体的な行動と成果を数字で示すことを意識してください。
また、面接で不採用になる場合は、質問への受け答えの内容、話し方、表情、身だしなみなどを客観的に評価し、改善点を見つけましょう。
自己分析が不足している可能性も考えられるため、自身の強みや弱み、企業への志望動機が明確に伝えられているかを確認することも大切です。
秋採用や二次募集の選考情報を調べる
6月に内定がない場合でも、秋採用や二次募集の選考情報を積極的に調べることは非常に有効な挽回策です。
なぜなら、多くの企業が通年採用を行っていたり、夏季インターンシップからの早期選考、あるいは欠員補充のために秋以降も採用活動を継続したりするからです。
特に、大手企業や人気企業では、春採用で内定が出揃わなかった場合や、内定辞退者が出た場合に二次募集を行うことがあります。
中小企業やベンチャー企業では、計画的な採用というよりは、事業の拡大や人材のニーズに合わせて随時採用を行うケースも多いため、秋以降もチャンスは豊富にあります。
具体的な方法としては、就職情報サイトの情報をこまめにチェックするだけでなく、企業の採用ホームページを直接確認したり、大学のキャリアセンターに相談したりするのも良いでしょう。
【6月に内定なし】6月に内定なしの就活生がすべき対策を選考フロー別に解説
6月になっても内定がない場合、選考のどの段階でつまづいているのかを把握し、そこを重点的に対策することが重要です。
選考フローは、一般的にES・履歴書、Webテスト、グループディスカッション、面接の4段階に分かれています。
それぞれの段階で求められる能力や対策が異なるため、自分の課題に合わせて効率的に準備を進めましょう。
ES・履歴書で落ちてしまう場合
選考対策を十分に行ったうえでエントリーしても、ESや履歴書で落ちてしまう人は、志望動機・ガクチカ・自己PR(強み)のいずれかに問題があると考えられます。
自己分析からアピールポイントを見直す
求められている人物像を理解する
文章の構成を見直す
企業はESや履歴書を通じて、あなたの基本的な能力や意欲、企業とのマッチ度を判断しています。
抽象的な表現や、他の学生と差別化できていない内容では、採用担当者の目に留まることは難しいでしょう。
自己分析からアピールポイントを見直す
企業から高い評価を受けるESを作成するには、前もって自己分析をしっかり行っておく必要があります。
自分の強みや弱み、価値観、興味などを深く掘り下げ、企業が求める人物像と結びつくアピールポイントを見つけ出すことが重要です。
具体的なエピソードを交えながら、自身の経験や学びをどのように企業で活かせるのかを具体的に示すことで、説得力のあるESを作成できます。
求められている人物像を理解する
魅力のあるES・履歴書を作成するには、業界・企業分析をしっかりと行うことも重要です。
応募する企業がどのような人材を求めているのかを理解し、それに合わせて自分の強みや経験をアピールすることで、企業とのマッチ度が高いことを効果的に伝えられます。
企業の採用ページやインターンシップ、OB・OG訪問などを通じて、具体的な情報を集め、ESに反映させましょう。
文章の構成を見直す
ESを書くときにはPREP法(結論→理由→具体例→結論)を使って書くことをおすすめします。
まず結論を先に述べ、次にその理由を説明し、具体的なエピソードを挙げて説得力を持たせ、最後にその経験を通じて何を学んだのかを伝える構成です。
この構成を用いることで、論理的で分かりやすい文章になり、採用担当者もスムーズに内容を理解できます。
ビジネスにおいても基本的に結論から先に述べるのが重要とされています。
Webテストで落ちてしまう場合
選考を受ける中で、Webテストで落ちてしまう場合は、やはりWebテスト対策が足りていない可能性が高いです。
事前にテストの種類を調べておく
何度も繰り返し解いて練習する
時間を測って模擬試験を解く
Webテストは、能力や性格を測るためのもので、基本的な学力や思考力を問われます。
対策なしで臨むと、思わぬ結果になることもあります。
事前にテストの種類を調べておく
Webテストで落ちてしまう人は、具体的な対策を行うためにも、事前にテストの種類を調べる必要があります。
SPI、玉手箱、TG-WEBなど、Webテストにはいくつかの種類があり、それぞれ出題傾向や対策方法が異なります。
志望する企業がどの種類のWebテストを採用しているのかを事前に把握し、そのテストに特化した対策を行うことで、効率的にスコアアップを目指せます。
何度も繰り返し解いて練習する
Webテスト対策の基本は、過去問や問題集を何度も繰り返し解いて練習することです。
最初はミスが多くても、解き直しを通じて理解が深まり、問題のパターンが読めるようになります。
特に、苦手な分野や頻出問題は重点的に繰り返し練習することで、本番での得点力向上につながります。
数をこなすことで、問題に慣れ、解答スピードも向上するでしょう。
時間を測って模擬試験を解く
Webテストは時間内に解き終えるスピードも重要です(要出典)。
いくら正答率が高くても、時間内にすべての問題を解ききれなければ意味がありません。
実際に時間を測って模擬試験を解くことで、本番の緊張感に慣れるとともに、時間配分の感覚を養うことができます。
苦手な問題に時間をかけすぎないよう、解き進めるスピードを意識して練習しましょう。
グループディスカッションで落ちてしまう場合
グループディスカッションでは、周りより抜きん出て目立つことより、決められた役割をしっかりとこなすことが大切です。
志望企業の事業内容に関する知識を持っておく
フレームワークを覚える
友人や知人と一緒に対策する
チームの一員として、議論に貢献し、円滑なコミュニケーションを取ることが評価されます。
志望企業の事業内容に関する知識を持っておく
グループディスカッションで高評価を得るには、企業の事業内容について、さまざまな知識・情報を持っておくことが大切です。
議論のテーマが企業の事業や業界に関するものであることが多いため、事前に知識を蓄えておくことで、より建設的な意見を述べたり、的確な質問をしたりできるようになります。
フレームワークを覚える
フレームワークとは、思考の軸や視点を整理する「型」のことです。
グループディスカッションでは、論理的に議論を進めることが求められます。
MECE(モレなくダブりなく)、ロジックツリー、SWOT分析など、いくつかのフレームワークを覚えておくことで、議論の構造を整理し、効率的に結論を導き出すことができます。
これらのフレームワークを活用することで、思考力や論理性をアピールできるでしょう。
友人や知人と一緒に対策する
グループディスカッションで落ちてしまう場合は、友人と事前にディスカッションをシミュレーションすることで、練習を重ねることも重要です。
実際に複数人で議論することで、自分の発言の仕方や、他のメンバーとの連携の取り方などを客観的に確認できます。
フィードバックをもらいながら改善を繰り返すことで、本番でのパフォーマンスを向上させることができます。
面接で落ちてしまう場合
就活の面接で落ちてしまう人は、用意する回答を改めて見直したり、ひたすら面接練習・模擬面接を重ねたりすることが大切です。
面接で落ちてしまう場合の対策方法
自己分析・企業分析をする
必須質問に対する答えを作っておく
一次・二次・最終面接ごとの対策をする
面接は、あなたの個性や人間性を企業に伝える重要な場です。
自信を持って臨めるよう、徹底した準備を行いましょう。
自己分析・企業分析をする
面接対策を強化する際は、あらかじめ自己分析や企業分析をしっかりと行っておくことも大事です。
自己分析で自分の強みや経験を明確にし、企業分析でその企業が求める人物像や事業内容を深く理解することで、面接で説得力のある回答をすることができます。
自分の経験と企業の求めるものを結びつけて話すことで、企業への熱意と貢献意欲を効果的にアピールできます。
必須質問に対する答えを作っておく
就活の面接で落ちないためには、必須質問に対する答えをまとめておくことが大切です。
自己紹介、志望動機、学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)、自己PR、入社後に何をしたいか、短所と長所、逆質問など、頻繁に聞かれる質問に対する回答は、事前に準備し、何度も練習しておきましょう。
丸暗記ではなく、自分の言葉で自然に話せるように練習を重ねることが重要です。
一次・二次・最終面接ごとの対策をする
一次・二次・最終面接には、それぞれ特徴があり、対策方法も異なります。
一次面接では、基本的なコミュニケーション能力や人柄が重視される傾向があります。
二次面接では、より具体的な経験やスキル、入社意欲が問われることが多いです。
そして最終面接では、入社への熱意や企業とのマッチ度、将来のビジョンなどが重点的に見られます。
【6月に内定なし】6月以降もエントリーできる企業
6月に入っても内定がない場合、多くの就活生は焦りを感じるかもしれません。
しかし、6月以降も積極的に採用活動を行っている企業は数多く存在します。
特に、通年採用を行っている企業や、事業拡大に伴い追加募集を行う企業、または内定辞退者が出たために二次募集を行う企業などが挙げられます。
大切なのは、諦めずに情報収集を続け、自身の状況に合った企業を見つけることです。
このセクションでは、6月以降もエントリー可能な企業の傾向と、具体的な企業例について詳しく解説します。
上場企業・大手グループ企業
6月以降もエントリーが可能な上場企業や大手グループ企業は存在します。
一般的に大手企業は春に採用活動のピークを迎えますが、通年採用を取り入れている企業や、内定辞退による欠員補充のために追加募集を行うケースも少なくありません。
例えば、近年ではIT業界を中心に、ソフトバンクのような大手企業が通年採用を行っています。
また、事業の多角化を進める楽天グループや、特定の職種で専門性の高い人材を継続的に募集している富士通なども、時期を問わず採用活動を行っていることがあります。
これらの企業は、新卒採用だけでなく、キャリア採用と並行して若手層の確保に力を入れているため、6月以降もチャンスがあります。
さらに、大手グループ企業の中には、事業会社ごとに採用スケジュールが異なる場合があり、親会社が採用を終えていても、子会社がまだ募集しているといったケースもあります。
例えば、NTTグループの各事業会社や、三井物産の子会社など、幅広い選択肢が考えられます。
これらの企業を狙う場合は、各企業の採用ホームページや採用情報サイトをこまめにチェックし、最新の募集状況を確認することが重要です。
中小企業・ベンチャー企業
中小企業やベンチャー企業は、6月以降も積極的に採用活動を行っているケースが非常に多いです。
大手企業のような大規模な新卒一括採用とは異なり、通年採用や欠員が出た際、事業拡大のタイミングなどで随時募集を行う傾向があるため、6月以降も多くのチャンスがあります。
Webサービス開発、AI、SaaS(Software as a Service)などを手掛ける企業では、スピード感を持って事業を展開しているため、年間を通して採用を行っています。
また、地方の中小企業も、年間を通して採用活動を行っていることがあります。
企業の規模にこだわらず、自身の興味や強みと合致する企業を探すことで、思わぬ出会いがあるかもしれません。
二次募集をしている企業
6月以降も、多くの企業が二次募集を行っています。
二次募集は、主に春採用で内定辞退者が出た場合や、当初の採用計画人数に達しなかった場合、あるいは新たな事業計画に伴って追加で人材が必要になった場合などに実施されます。
特に、BtoB(企業間取引)の企業や、専門性の高い職種を持つ企業、あるいは知名度は高くなくとも安定した経営基盤を持つ優良企業などが、ひっそりと二次募集を行っているケースは少なくありません。
二次募集の情報は、大手就職情報サイトに掲載されることもありますが、企業の採用ホームページで直接告知されることも多いです。
大学のキャリアセンターや就職エージェントが、二次募集を行っている企業の情報を非公開で持っている場合もあります。気になる企業がある場合は、過去の採用実績や、例年の採用動向を調べてみるのも良いでしょう。
まとめ
6月に内定がない状況でも、決して手遅れではありません。
まずは現状を冷静に分析し、内定がない原因を特定することから始めましょう。
自己分析や企業研究の徹底、選考対策の見直し、そして就活の軸を明確にすることが重要です。
また、選考フロー別の具体的な対策を講じ、ベンチャーや中小企業も視野に入れるなど、効率的な戦略も有効です。
焦らず、しかし危機感を持って行動すれば、納得のいく内定獲得は十分に可能です。
諦めずに、前向きに就職活動を続けていきましょう。



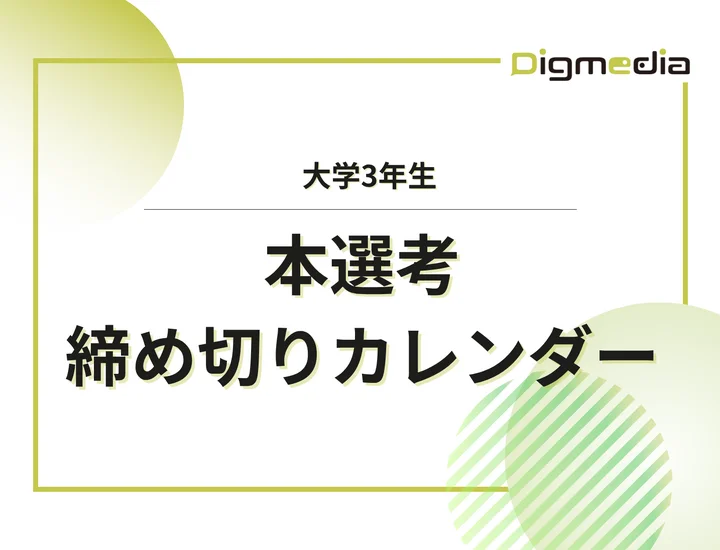







伊東美奈
(Digmedia監修者/キャリアアドバイザー)
伊東美奈
(Digmedia監修者)
この時期だからこそできる対策に焦点を当て、諦めずに就職活動を続けることで、納得のいく結果を手にすることができます。