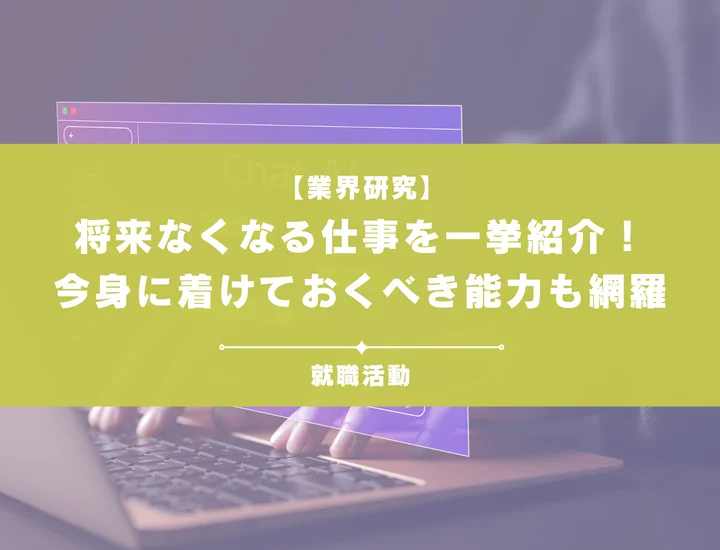HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
10年後、今ある仕事の多くがAIに代替される。
就職活動を控える中で、このような言葉に不安を感じていませんか。
特に、自分が目指す業界や職種が、将来なくなる仕事のリストに含まれていたら、どんな企業を選べばよいのか、どんなスキルを身につければよいのか、道に迷ってしまうのも無理はありません。
この記事では、なぜ仕事がなくなるといわれるのか、その根本原因から、AIに代替されやすい仕事の特徴までを分かりやすく解説します。
【将来なくなる仕事】なぜ仕事がなくなるといわれるのか
将来、一部の仕事がなくなると予測される背景には、単にAIがすごいというだけでなく、より大きな社会の変化が関係しています。
技術の進化と、私たちの社会が抱える課題。
この両面から、仕事のあり方が変わろうとしているのです。
ここでは、その根本原因となっている3つの大きな変化について見ていきましょう。
この構造を理解することが、未来を生き抜くためのキャリア戦略を立てる第一歩となります。
AIの急速な進化
まず最大の要因として、AI、つまり人工知知能の急速な進化が挙げられます。
少し前までのAIは、決められたルールに従って動く、いわば高性能な計算機のような存在でした。
しかし、近年のAIはディープラーニングという技術によって、自らデータの中からパターンを学習し、判断する能力を持つに至っています。
これにより、文章の作成や要約、プログラミングコードの生成、さらにはイラストや音楽の創作といった、これまで人間にしかできないと考えられていた創造的な領域にまで、その活躍の場を広げています。
2025年現在、多くの学生がレポート作成などでこれらのAI技術に触れていることでしょう。
このように、AIは特定の作業を自動化するだけでなく、知的生産活動そのものをサポートし、一部を代替できるレベルにまで進化しています。
このAIの進化が、人間の仕事内容を根底から変えようとしているのです。
RPAによる「定型業務」の自動化
AIと並んで仕事の自動化を推し進めているのが、RPA(Robotic Process Automation)です。
これは、PCの中で動くソフトウェアのロボットが、人間が行っていた事務作業を代行してくれる技術を指します。
例えば、請求書データを会計システムに入力する、複数のサイトから情報を収集してExcelにまとめる、決まった内容のメールを定期的に送信するといった、手順が決まっている繰り返し作業はRPAの最も得意とするところです。
多くの企業では、これまで人間の従業員が多くの時間を費やしてきたこれらの定型業務をRPAに任せることで、業務の効率化と人手不足の解消を進めています。
特に、事務職や経理職、人事職などのバックオフィス業務において、この流れは顕著です。
RPAの導入は、仕事がなくなるというより、仕事の中の単純作業の部分がなくなることを意味します。
そして、人間はより付加価値の高い、創造的な業務に集中することが求められるようになるのです。
人口減少といった社会構造の変化
技術的な進化に加え、日本の社会が直面する人口減少と少子高齢化も、仕事のあり方を変える大きな要因です。
労働力人口が年々減少していく中で、これまでと同じやり方を続けていては、社会や経済を維持することが困難になります。
そのため、企業は少ない人数でも高い生産性を上げることが死活問題となっており、AIやRPAの導入による業務の自動化・効率化は、もはや避けては通れない経営課題なのです。
多くの企業が推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)も、この課題解決の一環です。
つまり、仕事の自動化は、単にコストを削減するためだけでなく、人手不足という社会全体の課題を乗り越え、企業が存続していくための必然的な選択といえます。
この大きな社会構造の変化を理解すると、私たちが今、なぜスキルを磨き、変化に対応できる人材になる必要があるのかが見えてくるはずです。
【将来なくなる仕事】AIに代替されやすい仕事の特徴3選
将来なくなるといわれる仕事には、いくつかの共通した特徴があります。
ただし、ここで挙げる特徴を持つ職業が、明日すぐに消えてなくなるわけではありません。
仕事の中に含まれる一部の業務が、AIやロボットに置き換わりやすい、と捉えるのが正確です。
自分の興味がある仕事にこれらの特徴が含まれていないかを確認し、これから求められる役割の変化について考えるきっかけにしてみてください。
データの整理や入力
AIやRPAに代替されやすい業務の筆頭として挙げられるのが、データの整理や入力といった作業です。
例えば、紙のアンケート結果をExcelに入力する、会議の議事録を書き起こす、顧客リストを更新するといった業務がこれに該当します。
これらの業務は、作業手順やルールが明確であり、誰が担当しても成果物の品質がほぼ変わらないという特徴があります。
このような再現性の高い定型業務は、人間よりもAIやRPAの方が、はるかに高速かつ正確に処理することが可能です。
音声認識AIを使えば議事録は自動でテキスト化され、AI-OCRという技術を使えば紙の書類も瞬時にデータ化できます。
一般事務やデータ入力の仕事は、まさにこの領域の業務が中心となるため、仕事内容が大きく変化していくと考えられます。
今後は、単に入力するだけでなく、整理されたデータをどう解釈し、ビジネスに活かすかという分析力や企画力が人間に求められるようになります。
ルールが明確な情報処理・分析業務
ルールやマニュアルが明確に定められており、その基準に基づいて情報を処理・分析する業務も、AIへの代替が進むと考えられています。
例えば、銀行における住宅ローンの審査業務を考えてみましょう。
年収、勤務先、勤続年数、過去の信用情報といった膨大なデータに基づき、融資の可否や融資額を判断するプロセスは、AIが最も得意とするところです。
AIは過去の何万件もの事例を学習し、人間が見落とすような微細なパターンも見つけ出し、客観的な判断を下すことができます。
これは、保険金支払いの査定業務や、工場の製品検査における異常検知など、さまざまな分野に共通していえることです。
ただし、全ての判断がAIに委ねられるわけではありません。
AIの分析結果が本当に妥当であるかを最終的に評価したり、前例のないイレギュラーな事態に対応したり、顧客の個別の事情を汲んで柔軟な判断を下したりするのは、依然として人間の重要な役割であり続けます。
単純な窓口・受付業務
企業のコールセンターや商業施設のインフォメーション、ホテルのチェックインカウンターなどで行われる、単純な窓口・受付業務も、AIによる自動化が進みやすい領域です。
よくある質問への回答であれば、AIチャットボットが24時間365日対応する方が、利用者にとっても企業にとっても効率的です。
実際に、ウェブサイトの問い合わせ窓口がチャットボットになっているケースは、皆さんも頻繁に目にするでしょう。
また、ホテルの無人チェックインや、レストランのセルフオーダーシステムも普及が進んでいます。
これらの例からも分かるように、マニュアルに沿った基本的な情報提供や案内業務は、AIやロボットに置き換わっていく可能性が高いといえます。
その一方で、お客様からの複雑な相談に対応したり、予期せぬトラブルを解決したり、あるいは丁寧な接客で顧客満足度を高めたりといった、高度なコミュニケーション能力やホスピタリティが求められる役割の価値は、むしろ相対的に高まっていくと考えられます。
承知いたしました。
前回に引き続き、ご指定の条件と構成で記事の続きを執筆します。
【将来なくなる仕事】具体的な仕事一覧
ここでは、AIの進化や社会構造の変化によって、仕事内容が大きく変わっていく、あるいは一部がなくなるといわれる仕事を具体的に見ていきましょう。
大切なことなので繰り返しますが、これらの職業が完全になくなるわけではありません。
仕事の中に含まれる定型的な業務が自動化され、人間に求められる役割がより高度で専門的なものへと変化していく、と理解してください。
あなたのキャリアを考える上で、どの部分に未来の価値があるのか、思考を深める材料として活用していただければ幸いです。
事務職
事務職は、将来なくなる仕事の代表例として頻繁に挙げられる職種の一つです。
その主な理由は、業務内容にデータ入力、書類の作成・整理、伝票処理、経費精算といった、RPA(Robotic Process Automation)が得意とする定型業務が多く含まれるためです。
これらの作業は、手順さえ決めればAIやロボットが24時間、ミスなく高速に実行できます。
そのため、ただ言われた通りに作業をこなすだけの事務職の役割は、今後減少していく可能性が高いでしょう。
しかし、事務職の仕事が全てなくなるわけではありません。
むしろ、定型業務から解放された人間には、より付加価値の高い役割が期待されます。
例えば、部署間の業務が円滑に進むよう調整するコミュニケーション能力、既存の業務プロセスを分析して非効率な点を見つけ出し改善を提案する能力、さらには集計されたデータを分析して事業に役立つ洞察を見つけ出す力などです。
単なる作業者ではなく、組織の潤滑油となり、主体的に課題を発見・解決できる事務職の価値は、今後ますます高まっていくはずです。
レジ打ち・接客業
スーパーやコンビニにおけるレジ打ち業務は、セルフレジや無人店舗の普及により、代替が進む代表的な仕事です。
バーコードを読み取り金銭の授受を行うという単純作業は、機械化が容易な領域といえます。
また、アパレル店などでの簡単な商品説明や在庫確認といった業務も、店内に設置されたタブレットやAIアシスタントで対応できるようになるでしょう。
しかし、接客業の本質的な価値は、商品を売ることだけではありません。
お客様との何気ない会話から隠れたニーズを引き出し、最適な商品を提案するコンサルティング能力。
専門知識に基づいた的確なアドバイス。
また来たいと思わせるような心のこもったおもてなしや、リピーターを育てるための関係構築。
こうした人の感情や状況を深く理解し、柔軟に対応する能力は、AIには決して真似のできない人間ならではの強みです。
レジ打ちという作業は減っても、顧客に特別な購買体験を提供するという、接客業の専門性はより一層重要になります。
製造業
日本の基幹産業である製造業も、自動化の波と無縁ではありません。
工場の生産ラインにおける部品の組み立て、製品の検査、溶接といった物理的な作業は、産業用ロボットの導入によって急速に自動化が進んでいます。
特に、決められた手順を正確に繰り返す作業は、人間よりもロボットの方が効率的であり、品質も安定させやすいからです。
そのため、ラインで単純作業に従事する工員の需要は減少していくと予測されます。
その一方で、人間に求められる役割は、より高度で知的なものへとシフトしています。
例えば、工場全体の生産性を最大化するために生産ラインを設計・管理する能力。
導入されたロボットが正常に稼働するようメンテナンスを行ったり、新たなロボットを導入する企画を立てたりする能力。
AIやセンサーを活用して品質管理プロセスそのものを改善する能力などです。
これからの製造業では、自ら手を動かすだけでなく、ロボットやAIをパートナーとして使いこなし、工場全体のパフォーマンスを向上させる人材が中心的な役割を担っていくでしょう。
運転手
自動車の自動運転技術の進化は、運転手の仕事に大きな影響を与えると予測されています。
特に、高速道路など、比較的単純な環境を長時間走行する長距離トラックや、決まったルートを往復する路線バス、特定のエリアを巡回する配送車などは、自動運転技術が適用されやすい分野です。
レベル5と呼ばれる完全自動運転が社会に全面的に実装されるまでにはまだ時間を要しますが、特定の条件下での自動運転はすでに実用化が始まっています。
そのため、ただ車を運転するだけの仕事は、将来的には減少する可能性が高いでしょう。
しかし、全ての運転業務がなくなるわけではありません。
例えば、複雑な交通状況や予期せぬ障害物に対応する能力、荷物の積み下ろしといった付帯作業、乗客とのコミュニケーションが求められるタクシーや、介助が必要な利用者を送迎する介護タクシーなど、運転以外の付加価値が求められる仕事の重要性は依然として高いままです。
移動という機能に、どのようなサービスを上乗せできるかが、今後の運転手の価値を左右します。
警備員
商業施設やオフィスビルなどでの警備員の仕事も、テクノロジーによって大きく変化する職種の一つです。
施設内の定点監視や決まったルートの巡回といった業務は、高性能な監視カメラとAIの画像認識技術を組み合わせることで、人間よりも高い精度で24時間実行可能になります。
不審な動きをする人物をAIが自動で検知したり、ドローンが広範囲を巡回したりすることで、省人化が進むでしょう。
これにより、警備員の役割は、監視という受け身の業務から、有事の際に能動的に対応する役割へと重点が移っていきます。
例えば、AIが異常を検知した際に現場へ急行し、状況を判断して的確な対応をとる能力。
不審者と対峙したり、災害時に人々を安全に避難誘導したりといった、人間の冷静な判断と行動力が不可欠な業務です。
また、要人警護のように、常に変化する状況の中で微細な危険を察知し、臨機応変に動くスキルもAIには代替できません。
テクノロジーを監視の目として活用し、人間は最後の砦として安全を守る、という関係性がより明確になっていくでしょう。
ライター・翻訳
文章を生成するAIの登場により、ライターや翻訳家の仕事も変革の時を迎えています。
例えば、製品のスペックをまとめた紹介文や、決まった形式のプレスリリース、ウェブサイトのアクセスデータに基づいた簡単なレポート記事などは、AIが瞬時に生成できるようになりました。
また、日常的なビジネスメールや定型的な文章の翻訳も、AI翻訳ツールの精度は飛躍的に向上しています。
このような情報整理や要約が中心のライティング・翻訳業務は、今後AIに代替されていく可能性が高いです。
しかし、人間のライターや翻訳家の価値が失われるわけではありません。
むしろ、AIには生み出せない独自の価値がより強く求められます。
例えば、自身の体験や深い洞察に基づいたコラム、専門家への綿密な取材を通じて本質に迫る記事、読者の感情を揺さぶり行動を促すようなコピーライティング。
翻訳においても、作品の文化的背景や行間のニュアンスを汲み取って訳出する文芸翻訳など、高い創造性と深い思考力が求められる領域では、人間の専門性が不可欠です。
ホテルのフロントスタッフ
ホテルの顔ともいえるフロントスタッフの仕事も、自動化が進む領域です。
特に、宿泊客のチェックイン・チェックアウト手続きは、自動チェックイン機やスマートフォンアプリの活用により、無人化・省人化が進んでいます。
予約内容の確認やルームキーの発行、精算といった定型的な手続きは、機械に任せる方が効率的であり、宿泊客にとっても待ち時間が短縮されるという利点があります。
そのため、手続き業務を主としていたフロントスタッフの役割は縮小していくでしょう。
その代わりに人間には、AIや機械にはできない、心のこもったおもてなしの提供が求められます。
例えば、お客様一人ひとりの要望を丁寧にヒアリングし、その人に合った観光プランやレストランを提案するコンシェルジュのような役割。
予期せぬトラブルやクレームに対して、誠意をもって柔軟に対応する問題解決能力。
こうした血の通ったコミュニケーションを通じて、ホテルのファンを増やし、特別な滞在体験を演出することが、これからのフロントスタッフの最も重要なミッションになります。
清掃員
商業施設やオフィス、ホテルなどにおける清掃業務も、ロボット技術の導入によって変化しています。
すでに多くの施設で、床の掃き掃除や拭き掃除を行う自律走行型の清掃ロボットが活躍しており、人間が広いフロアを清掃する必要は減りつつあります。
今後、ロボットの性能がさらに向上すれば、窓ガラスやトイレなど、より複雑な場所の清掃も自動化されていくでしょう。
このように、決められた範囲を清掃するという単純作業は、徐々にロボットに置き換わっていくと考えられます。
一方で、人間にしかできない業務の価値は残ります。
例えば、ロボットが入れないような狭い場所や、複雑な構造を持つ箇所の細やかな清掃。
清掃全体の品質を管理し、ロボットが正しく稼働しているかをチェックするマネジメント業務。
また、清掃ロボット自体のメンテナンスや、より効率的な清掃計画の立案なども人間の重要な役割です。
ただ清掃をするだけでなく、クリーンな環境を維持するための管理者としての視点が、今後の清掃員には求められます。
配達員
Eコマース市場の拡大に伴い需要が増している配達員の仕事も、将来的には自動化技術の影響を大きく受けると考えられています。
特に、ラストワンマイルと呼ばれる、配送拠点から個人の自宅までの最後の区間の配達において、ドローンや自動運転ロボットの活用が期待されています。
すでに一部の地域では実証実験が進んでおり、これらの技術が社会に本格的に実装されれば、人間が一件一件家を回って荷物を届ける必要性は減少するでしょう。
しかし、全ての配達が自動化されるわけではありません。
例えば、オートロックのマンションや、入り組んだ路地の奥にある住宅など、ロボットでは対応が難しい場所への配達。
配達先での顧客とのコミュニケーションや、代引きのような付帯サービス。
そして、ドローンやロボットを含む配送網全体を効率的に管理・運営する管制業務などは、人間の役割として重要であり続けます。
物理的に荷物を運ぶという作業から、配送システム全体を最適化する仕事へと、求められるスキルが変化していく可能性があります。
調理スタッフ
飲食店の厨房における調理の仕事も、ロボット技術の導入が進んでいる分野の一つです。
特に、レシピや手順が標準化されている作業は、ロボット化に適しています。
例えば、ファミリーレストランや牛丼チェーンにおける揚げ物や焼き物、ファストフード店でのポテトを揚げる作業、あるいはラーメン店で麺を茹でる作業などは、すでにロボットが担っているケースも増えています。
これらの定型的な調理作業は、品質を安定させ、人手不足を解消する上で有効なため、今後さらに普及していくでしょう。
その一方で、人間にしかできない調理の領域の価値は高まります。
旬の食材を見極め、その日の最高の状態で提供するための目利き。
新しい味や食感を追求し、人々を驚かせる新メニューを開発する創造性。
お客様の好みやアレルギーに合わせてメニューを調整する柔軟性。
そして、カウンター越しにお客様との会話を楽しみながら料理を提供するパフォーマンスなどです。
調理という作業だけでなく、食を通じて人々を楽しませるエンターテイナーとしての役割が、調理スタッフにはより強く求められるようになります。
銀行業務
銀行の仕事は、AIやフィンテックの進化によって最も大きく変化する業種の一つといわれています。
特に、銀行の支店の窓口で行われる入出金や振込、税金の支払いといった定型的な手続きは、そのほとんどがATMやインターネットバンキングで完結できるようになりました。
これにより、窓口担当者である銀行員の役割は大幅に縮小しています。
また、これまで行員の経験や勘に頼る部分もあった住宅ローンなどの融資審査も、AIが過去の膨大なデータを分析して判断するようになり、自動化が進んでいます。
このように、手続きや単純な判断業務が減少する一方で、人間にしかできない高度な専門性が求められる業務の重要性が増しています。
例えば、顧客のライフプランに寄り添い、資産運用や相続について総合的な提案を行うコンサルティング業務。
企業の経営課題を深く理解し、事業承継やM&Aを支援するソリューション提案などです。
金融に関する深い知識と高いコミュニケーション能力を駆史して、顧客の複雑な課題を解決するパートナーとしての役割が、これからの銀行員には不可欠となります。
倉庫作業・ピッキング業務
倉庫での商品整理や仕分け、ピッキングの作業は、AIやロボットの導入によって大きく変わりつつあります。
機械は人のように疲れず、正確な動作を長時間続けることができます。
近年では、自動で倉庫内を移動して商品を運ぶロボットや、カメラとセンサーで在庫を管理するシステムが普及しています。
これにより、人が行っていた単純な仕分けや運搬の多くが自動化されています。
特に大手物流企業では、AIが最短ルートを計算して作業を指示する仕組みが取り入れられています。
その結果、作業スピードが上がり、人手を大幅に減らすことができています。
ただし、人の判断や臨機応変な対応が必要な工程も残るため、完全に置き換わるわけではありません。
経理・会計業務
経理や会計の仕事は、AIによって大きな変化を迎えています。
もともと数字を扱う正確さが求められる仕事であり、ルールが明確な分野ほどAIが得意とする領域です。
すでに多くの企業では、請求書の処理や経費の確認、決算の集計などを自動で行うシステムが導入されています。
これにより、人が入力や確認にかけていた時間が短縮され、ミスも減少しています。
また、AIは膨大な取引データから不正や異常を検出することもできるため、内部監査の効率化にも役立っています。
一方で、経理担当者がまったく不要になるわけではありません。
数字の意味を読み取り、経営判断につなげる分析や提案の部分は人の役割として残ります。
今後は単なる事務作業ではなく、経営の視点を持った経理人材がより求められていくでしょう。
コールセンター・カスタマーサポート
問い合わせ対応を行うコールセンターやサポート業務も、AIの導入が進んでいます。
チャットや音声を理解する技術が向上したことで、自動応答が人に近い形でできるようになりました。
よくある質問への対応や予約の確認など、定型的な内容はすでにAIが代行しています。
これにより、企業は人件費を抑えながら、24時間対応が可能になりました。
ただし、複雑な相談や感情のこもった対応が必要な場面では、依然として人の力が必要です。
AIが得意なのはスピードと正確さであり、人が得意なのは共感や気づかいです。
今後は、AIが基本的な対応を行い、人は難しい問題解決や顧客との関係構築に専念する形へと移行していくでしょう。
建設作業員・現場作業スタッフ
建設の現場でも、自動化の波は確実に広がっています。
重機の操作や測量、資材の運搬など、危険を伴う作業は機械による代替が進んでいます。
ドローンを使って上空から現場を撮影したり、AIが図面をもとに作業手順を指示したりする仕組みも実用化されています。
これにより、作業の効率化だけでなく、安全性の向上にもつながっています。
また、3Dデータを使った設計や管理システムの普及により、現場での手作業が減少しています。
しかし、天候や地形などの不確定要素が多い現場では、今も人の判断が欠かせません。
機械が得意なのは正確さと再現性であり、現場での柔軟な対応は人の役割として残ります。
今後は、AIや機械の力を活用しながら、現場を統括する管理者や安全面を支える技術者が中心的な役割を担うようになるでしょう。
AIによってなくならない仕事の特徴
AIの進化によって多くの仕事が変化していますが、その一方で、人にしかできない仕事も確かに存在します。
機械がどれほど正確に動けるようになっても、人の感性や思いやり、判断力を完全に再現することはできません。
ここでは、AI時代でも価値が高いといわれる仕事の特徴を5つの観点から解説します。
創造性やセンスを求められる職業
AIは与えられた情報をもとに最適な答えを導き出すことは得意ですが、まったく新しい発想を生み出すことは苦手です。
そのため、デザイン、音楽、映像、文章など、感性が問われる仕事は今後も人の力が求められます。
これらの仕事では、技術よりも感じる力や伝える力が大切です。
同じテーマでも、人によって表現の仕方や受け取り方が異なるため、唯一の正解がありません。
その自由さが、AIには真似できない価値を生み出しています。
また、AIが制作を補助する場面も増えていますが、最終的な方向を決めるのは人です。
発想の種を見つけ、形にしていく過程こそが人の仕事として残ります。
新しい価値をつくる力を持つ人ほど、これからの時代に強く求められていくでしょう。
人と信頼関係を築く仕事
人の気持ちや状況に寄り添い、信頼を築く仕事はAIには難しい分野です。
営業やカウンセラー、保育士などの職種では、相手の表情や声のトーンを感じ取り、その場に合わせて対応する力が必要です。
AIは情報を分析できますが、人の感情の細やかな変化までは理解できません。
また、信頼関係は時間をかけて築かれるものです。
人との約束を守り、誠実に対応し続けることで初めて生まれる信頼は、数字やデータでは表せません。
人との関係を大切にできる人は、どんな時代でも必要とされます。
仕事の成果は目に見える数字だけでなく、誰とどう関わるかにも左右されます。
AIがサポートする時代だからこそ、人にしかできない心の通った関係づくりが価値になります。
命や感情を扱う仕事(医療・教育・介護など)
医療や教育、介護の分野は、AIが最も入りにくい領域の一つです。
これらの仕事では、相手の命や気持ちを扱うため、単なる知識や作業ではなく、人の思いやりや判断力が必要です。
AIが検査や記録を助けることはできても、患者や利用者の心に寄り添うことはできません。
たとえば、看護師が患者の不安を感じ取って声をかける、教師が生徒の悩みに気づく、介護士が相手の立場に立って動く。
こうした行動は、数値では表せない人の感情から生まれます。
今後もAIはサポートの役割を担う一方で、人の温かさが求められる仕事は残ります。
この分野で大切なのは、相手を理解しようとする姿勢です。
どんなに技術が進んでも、人を思う心が職業の根本にあることは変わりません。
IT技術を動かす・管理する職種
AIやSaaSのような仕組みを支える仕事も、今後の時代に必要とされ続けます。
システムエンジニアやプロジェクトマネージャーなど、技術を活用して仕組みを動かす人が欠かせません。
AIは自らを設計することができないため、それを操作し、改善し、正しい方向に導く人が必要です。
また、データを安全に扱うための管理や、トラブルが起きたときの判断も人の責任で行われます。
これらの職種では、技術知識だけでなく、問題が起きたときに冷静に対応する力が求められます。
AIに指示を出す立場として働く人ほど、その重要性が高まっています。
今後も、技術を使う人ではなく、動かす人としての役割が価値を持ち続けるでしょう。
現場判断が求められる専門職
現場での判断が欠かせない仕事も、AIに置き換えることは難しい領域です。
消防士や警察官、整備士、建築現場の監督などは、その場の状況を見て瞬時に判断する力が必要です。
現場では常に予測できない事態が起きるため、あらかじめ決められたルールだけでは対応できません。
AIはデータに基づく判断は得意ですが、想定外の状況に柔軟に対応することは苦手です。
また、人命や安全に関わる仕事では、わずかな判断の違いが大きな結果を生むことがあります。
経験からくる勘や現場感覚は、人だからこそ身につけられる力です。
今後は、AIが補助を行いつつ、人が最終判断を下す体制が主流になると考えられます。
現場での責任を持ち、状況に応じた判断ができる人ほど、社会で必要とされ続けます。
【将来なくなる仕事】AI時代に価値が高まる仕事とは
これまでAIに代替されやすい仕事の特徴を見てきましたが、悲観的になる必要は全くありません。
ここからは視点を変えて、AIが進化するからこそ、逆に人間の価値が高まる仕事は何かを探っていきましょう。
AIを仕事を奪うライバルではなく、面倒な作業を肩代わりしてくれる優秀なパートナーと捉えれば、私たち人間は、より本質的で創造的な仕事に集中できます。
そこにこそ、未来のキャリアを築く大きなチャンスが隠されています。
0→1を生み出す「創造性」が求められる仕事
AIは、過去に学習した膨大なデータから最適なパターンを見つけ出し、組み合わせることは得意です。
しかし、データが存在しない、全く新しい何かをゼロから生み出すことはできません。
この0→1を生み出す創造性こそ、AI時代における人間の最も重要な価値の一つです。
例えば、世の中の誰も見たことがないような新しいサービスを企画する仕事、まだ解明されていない真理を探究する研究開発の仕事、人の心を惹きつける斬新なデザインや物語を生み出すクリエイターの仕事などがこれにあたります。
これからの時代に求められるのは、常識を疑い、既存の枠組みを超えて新しいアイデアを発想し、それを形にしていく力です。
あなたの自由な発想やユニークな視点そのものが、これからの社会では強力な武器になります。
AIにできない領域で、あなただけの価値を創造していくことが重要です。
人の心を動かす高度なコミュニケーションが必要な仕事
論理的な回答を返すことはできても、AIが人の心の機微を深く理解し、信頼関係を築くことは困難です。
相手の言葉の裏にある本当の悩みや願いを汲み取り、対話を通じて共に課題を解決していくプロセスは、人間にしかできない高度なコミュニケーションの領域です。
例えば、企業の経営者が抱える複雑な悩みに寄り添い、最適な戦略を提案するコンサルタント。
顧客との深い関係性の中から、潜在的なニーズを引き出し、期待を超える提案をする営業職。
悩める人の心に寄り添い、その人らしい生き方を支援するカウンセラーやキャリアコンサルタント。
こうした仕事の本質は、論理だけでは解決できない人の感情を扱い、心を動かすことにあります。
また、多様な個性を持つメンバーを一つのチームとしてまとめ、目標達成に導くマネジメント能力も、AIには代替できない重要なスキルです。
複雑な課題を解決する「非定型な思考」が問われる仕事
私たちの社会やビジネスの世界は、前例のない、一つの正解がない複雑な問題に満ちあふれています。
AIは過去のデータに基づいて最適解を提示することはできますが、未来がどうなるか分からない状況で、断片的な情報から本質を見抜き、戦略的な意思決定を下すことはできません。
このような答えのない問いに立ち向かう、非定型な思考力こそが人間の価値となります。
例えば、変化する市場環境の中で会社の進むべき道を決める経営戦略の立案。
社会の課題を解決するための新しい事業開発。
法律や倫理といった、単純な計算では割り切れない要素を考慮しながら、最適な判断を下す専門職などが挙げられます。
AIが出した分析結果を鵜呑みにするのではなく、そのデータが持つ意味を多角的に解釈し、自らの責任で未来を切り拓く意思決定を行う。
その役割は、ますます重要になっていくでしょう。
【将来なくなる仕事】今から身に着けておくべきスキル
AI時代に価値が高まる仕事の共通点が見えてきたところで、次に考えるべきは、そのために今からどんなスキルを身につけるべきか、です。
特定の業界でしか通用しない専門知識も大切ですが、それ以上に、どんな業界や職種に就いても役立つ、持ち運び可能なポータブルスキルの習得が重要になります。
ここでは、特に27卒の皆さんに意識してほしい3つのスキルを紹介します。
これらのスキルは、変化の激しい未来を生き抜くための土台となります。
課題発見・解決能力
これからの時代、与えられた問題を正確に解く能力以上に、そもそも何が本当の課題なのかを見つけ出す能力が重要になります。
目の前にある事象に対して、なぜそうなっているのだろうと深く掘り下げ、本質的な原因を探り当てる力です。
例えば、サークル活動で新入生がなかなか定着しないという問題があったとします。
その時、ただ歓迎会を増やすという安易な解決策に飛びつくのではなく、なぜ定着しないのか、新入生は何に不安を感じているのか、既存メンバーとの間にコミュニケーションの壁はないか、といった問いを立てて深掘りしていく。
この思考プロセスそのものが、課題発見・解決能力のトレーニングになります。
アルバイト先での業務改善提案や、ゼミでの研究活動など、あなたの身の回りにはこのスキルを磨く機会があふれています。
当たり前を疑い、常により良い状態を目指す姿勢を大切にしてください。
ロジカルシンキング
ロジカルシンキング、つまり論理的思考力は、複雑な物事を整理し、筋道を立てて考え、相手に分かりやすく伝えるための基本的なスキルです。
どんなに素晴らしいアイデアを持っていても、それを相手に納得してもらえなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。
このスキルは、就職活動のあらゆる場面で役立ちます。
例えば、グループディスカッションで議論が紛糾した際に、論点を整理して議論を前に進める。
面接で、自分が学生時代に力を入れたことについて、PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識して、説得力を持って話す。
エントリーシートで、志望動機を矛盾なく構成する。
これらは全てロジカルシンキングが土台となります。
日頃からニュースや本の内容を要約したり、自分の考えを構造的に書き出してみたりする習慣をつけることで、このスキルは着実に鍛えられます。
学び続ける力
変化のスピードが速い現代において、大学で学んだ知識だけで社会人生活を乗り切ることは不可能です。
昨日までの常識が、今日にはもう通用しなくなるかもしれません。
そこで不可欠になるのが、生涯を通じて学び続ける力、つまり学習意欲です。
これには、新しい知識やスキルを学ぶリスキリングだけでなく、過去の成功体験や凝り固まった価値観を一度捨て去るアンラーニングも含まれます。
大切なのは、知らないことがあることを素直に認め、常に自分をアップデートし続けようとする謙虚な姿勢と好奇心です。
この学び続ける力こそが、AIの進化や市場の変化といった、あらゆる変化に対応するための最強の武器となります。
特定のスキルを一つ身につけて安心するのではなく、学び方そのものを学び、変化を楽しめる人材になることを目指しましょう。
デジタルリテラシー
デジタルリテラシーとは、パソコンやスマートフォンを使いこなす力だけではなく、デジタル技術を理解し正しく活用する力のことです。
AIやクラウドサービス、データ分析など、新しい仕組みを理解し、自分の仕事にどう生かすかを考えられる人が求められています。
たとえば、文書作成や表計算だけでなく、オンライン会議の運営や情報の整理、効率的な共有なども含まれます。
また、情報の正しさを見極める力や、セキュリティへの意識も欠かせません。
今後の仕事では、どんな職種でもデジタル技術に触れる機会が増えるため、基本的な操作に慣れておくことが大切です。
新しいツールを恐れず試してみる姿勢が、自分の成長につながります。
デジタルを使う力は、あらゆる仕事の土台となるスキルです。
分析力
分析力とは、情報やデータから意味を読み取り、正しい判断を下す力です。
AIが膨大な情報を整理する時代だからこそ、人はその結果をどう活かすかを考える役割を担います。
数値をただ見るだけではなく、そこから原因や傾向を導き出し、改善の方向を考える力が求められています。
この力があれば、感覚ではなく根拠に基づいた行動ができます。
また、分析は数字に限らず、人や社会の動きを理解する上でも役立ちます。
仕事の中で「なぜそうなったのか」を意識して考えることで、自然と分析力は鍛えられます。
正確に情報を整理し、次の行動につなげる力を持つ人は、どんな職場でも重宝されます。
分析は難しい作業ではなく、日常の中で考える習慣から始まります。
感情理解・対人対応力
AIが発達しても、人の気持ちを理解し、相手に寄り添う力は人にしか持てません。
この力は、どんな仕事にも共通して必要とされます。
相手の表情や言葉の裏にある思いを読み取り、安心感を与えられる人は、職場でも信頼されます。
対人対応力とは、ただ話すだけでなく、相手の立場を考えながら適切に行動する力のことです。
感情理解がある人は、チームでの協力やお客様との関係づくりにおいて大きな強みを発揮します。
また、困っている人を支えたり、トラブルを穏やかに解決したりする力にもつながります。
AIが効率を上げる時代だからこそ、人の心に寄り添える力がより価値を持つようになります。
相手を思いやる姿勢こそが、これからの働き方の中で最も大切な力です。
【将来なくなる仕事】将来性のある企業を見極めるコツ
個人のスキルアップと同時に、自分が成長できる環境、つまり将来性のある企業を選ぶことも非常に重要です。
ただし、ここでいう将来性とは、単に今儲かっているという意味ではありません。
変化の時代を乗りこなし、持続的に成長していける力を持っているか、ということです。
企業のウェブサイトの美しさや知名度だけでなく、その内側に目を向けて、変化に対応できる企業かどうかを見極める3つのコツを紹介します。
DXやAI活用に本気で取り組んでいるか
多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)やAI活用を掲げていますが、その本気度には大きな差があります。
企業のウェブサイトにスローガンが書いてあるだけで満足せず、その企業のIR情報、特に投資家向けに発行している中期経営計画や年次報告書を読んでみましょう。
そこに、DXやAI活用に対して、具体的な目標や投資額、どのような体制で進めているかが書かれていれば、その企業は本気である可能性が高いです。
また、社長や役員が、自らの言葉でテクノロジー活用の重要性やビジョンについて語っているかどうかも重要な判断材料です。
変化を他人事ではなく、経営の中心課題として捉えている企業は、将来も成長し続ける体力を持っているといえます。
社員の学びなおしを支援しているか
変化に対応できる企業は、社員が成長し続けることを重要だと考えています。
そのため、社員の学び直し、つまりリスキリングを積極的に支援する制度が整っていることが多いです。
企業の採用サイトで、研修制度や資格取得支援、自己啓発支援といった福利厚生をチェックしてみましょう。
ただし、制度があることだけでなく、それが実際にどれだけ利用されているかも重要です。
可能であれば、OB/OG訪問やインターンシップの機会を活用して、若手の社員に、最近どんな研修を受けたか、会社は自分の成長をどう支援してくれるか、といったリアルな話を聞いてみることをお勧めします。
社員への投資を惜しまない企業は、人と共に未来を創っていこうという意思の表れであり、将来性が高い企業といえるでしょう。
会社ならではの独自の強みがあるか
価格競争や技術の模倣が激しい現代において、企業が安定して成長し続けるためには、他社が簡単に真似できない独自の強み、つまり競争優位性を持っていることが不可欠です。
それは、特許で守られた圧倒的な技術力かもしれませんし、長年かけて築き上げてきた強力なブランドイメージかもしれません。
あるいは、全国に張り巡らされた独自の物流網や、特定の顧客層との深い信頼関係といった場合もあります。
企業研究をする際には、この会社の利益はどこから生まれているのか、競合他社と比べて何が決定的に違うのか、という視点で深く分析してみてください。
独自の強みを持つ企業は、外部環境の変化にも揺らぎにくく、長期的に見て安定したキャリアを築きやすいといえます。
AI時代にキャリアを築くための考え方
AIが社会の仕組みを大きく変えている今、これからの働き方は変わらないものにしがみつくよりも、変化を受け入れ、進化していくことが大切になります。
新しい技術や考え方を柔軟に取り入れ、自分の力で学び直しながら時代に合わせて成長できる人が、AI時代の主役になります。
ここでは、AI時代にキャリアを築くために欠かせない4つの考え方を紹介します。
変化を恐れず学び直す姿勢
これからの社会では、いまの知識が一生通用するとは限りません。
新しい技術や働き方が次々と生まれる中で、自分の考えを更新し続けることが求められます。
学び直しとは、ただ資格を取ることではなく、新しい考え方や視点を取り入れることです。
変化を恐れずに、新しい知識を吸収する人ほど次のチャンスをつかめます。
一方で、過去のやり方に固執してしまうと成長の機会を逃してしまいます。
学び直しを習慣にすることで、仕事への不安を減らし、自信を持って行動できるようになります。
時代が変わっても、自ら学ぶ姿勢を持ち続けることが、長く活躍するための土台になります。
テクノロジーを味方にする視点
AIの発展を脅威としてではなく、自分の仕事を支えてくれる存在として考えることが重要です。
技術を遠ざけるのではなく、どう使えば自分の仕事をより良くできるかを考えることが求められます。
AIは繰り返しの作業を得意としますが、創造的な発想や人とのつながりは人にしかできません。
つまり、AIに任せられる部分は任せ、人が得意な部分に力を注ぐことで、より大きな成果を生み出せます。
また、AIを理解し使いこなす力は、どんな職種でも必要になります。
日常の中で少しずつ技術に触れ、便利に活用する習慣を持つことが、自分の強みを広げる第一歩です。
テクノロジーをうまく取り入れられる人は、時代の変化を楽しみながら働くことができます。
自分の価値を数値化・言語化する
AI時代では、ただ頑張っているだけでは評価されにくくなります。
自分がどんな成果を出したのかを、数字や言葉で説明できる力が大切になります。
これは、自分を客観的に理解する力ともいえます。
たとえば、どのような課題を解決したのか、どんな工夫で成果を上げたのかを整理しておくことで、自分の強みを明確にできます。
また、転職や昇進の際にも、自分の実績を具体的に伝えることが評価につながります。
AIがデータで判断する時代だからこそ、自分の働きをデータとして示す意識が必要です。
数値化と同時に、言葉で自分の価値を伝えられる人は、どんな環境でも信頼を得やすくなります。
職業よりもスキルで考えるキャリア設計
AIの発展により、今ある職業が変化していく中で、何の仕事をするか、よりも、どんな力を持っているか、が重要になります。
一つの職業にとらわれるより、どんな状況でも通用するスキルを育てることが大切です。
たとえば、課題を見つける力、人と協力して進める力、新しい知識を取り入れる力などは、どんな業界でも役立ちます。
職業は変わっても、スキルがあれば新しい仕事にも対応できます。
AI時代では、職種の境界があいまいになり、一人が複数の役割を担うことも増えていきます。
その中で、自分の得意分野を広げ、柔軟に働ける人が強くなります。
職業名にとらわれず、自分の力を軸にキャリアを考えることが、長く活躍するための鍵になります。
【将来なくなる仕事】今日からできる3つのアクション
ここまで、AI時代の仕事やスキル、企業選びについて考えてきました。
最後のセクションでは、これらの知識を具体的な行動に移すための、今日からすぐに始められる3つのアクションを紹介します。
頭で理解するだけでなく、実際に行動を起こすことで、あなたの就職活動はより深く、意味のあるものになるはずです。
漠然とした不安を行動力に変え、未来の自分への投資を始めましょう。
自己分析:なくならない自分の軸を見つける
将来性があるから、安定しているから、といった他人軸だけでキャリアを選ぶと、変化の時代ではすぐに道に迷ってしまいます。
まず取り組むべきは、どんな環境でも揺らぐことのない、あなた自身の価値観や強み、つまり自分軸を明確にすることです。
自分はどんな時にやりがいを感じるのか、何をしている時に時間を忘れるほど夢中になれるのか。
逆に、どうしても譲れない価値観は何か。
これまでの経験を丁寧に振り返り、自分の心の声に耳を傾けることで、あなただけのキャリアの羅針盤が見えてきます。
このなくならない自分の軸さえしっかりしていれば、たとえAIがどれだけ進化しても、時代の変化に翻弄されることなく、自分らしいキャリアを歩み続けることができるでしょう。
長期インターンシップで「課題解決力」を養う
数時間や1日で終わる仕事体験も有意義ですが、より実践的なスキルを身につけたいなら、長期インターンシップに挑戦することをお勧めします。
社員と同じように、責任ある仕事を任され、数ヶ月単位でリアルなビジネスの課題に取り組む経験は、何物にも代えがたい財産になります。
そこでは、前述した課題発見・解決能力や、チームで働くためのコミュニケーション能力を、机上の空論ではなく実践として学ぶことができます。
うまくいかないことや、理不尽に感じることもあるかもしれません。
しかし、そうした困難を乗り越えようと試行錯誤する経験そのものが、あなたを大きく成長させてくれます。
学生という立場でビジネスの最前線に立てるこの貴重な機会を、ぜひ活用してみてください。
仕事の"不"を聞く
OB/OG訪問や社会人との座談会は、仕事のリアルを知る絶好の機会です。
その際に、仕事のやりがいや成功体験といったキラキラした話を聞くだけでなく、あえて仕事のネガティブな側面、つまり不便、不満、不安といった"不"の部分について質問してみてください。
例えば、業界が抱える課題は何か、仕事の中で一番非効率だと感じることは何か、といった質問です。
社会人が感じる"不"の中には、AIやテクノロジーではまだ解決できていない、人間が価値を発揮すべき領域が隠されています。
それは、新しいビジネスの種かもしれませんし、あなたがその会社で貢献できることのヒントかもしれません。
仕事の光と影の両面を知ることで、あなたの企業選びやキャリアプランは、より解像度の高いものになるはずです。
まとめ
将来なくなる仕事という言葉は、私たちに不安を感じさせますが、それは同時に、これからの働き方や自分のキャリアについて真剣に考える絶好の機会を与えてくれているともいえます。
AIやロボットは、私たちの仕事を奪う冷たい敵ではありません。
面倒で退屈な作業を肩代わりしてくれる、優秀で頼もしい相棒です。
その相棒をいかに使いこなし、人間にしかできない創造性の発揮や、高度なコミュニケーション、複雑な課題解決に集中できるか。
それが、これからの時代を豊かに生き抜くための鍵となります。
変化の激しい時代だからこそ、特定の企業や業界に安住を求めるのではなく、どんな環境でも価値を発揮できる自分自身になることを目指しましょう。